レガシーシステム統合で実現する医療DXのメリットとは?
医療

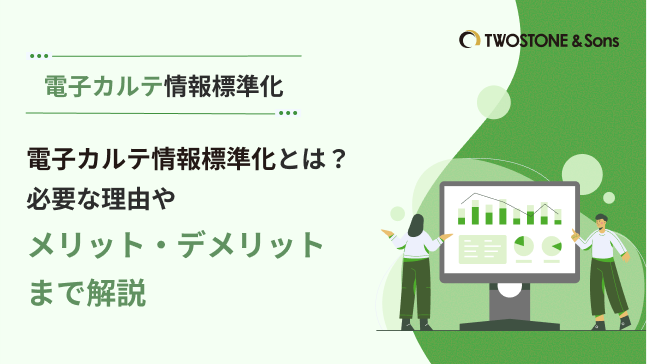
電子カルテの情報標準化によって、患者さんの転院や救急搬送時に過去の正確な診療情報が即座に共有され、重複検査や投薬ミスの防止につながります。この記事では、電子カルテ情報標準化が必要な理由やメリット・デメリットまでを紹介します。
電子カルテ情報標準化を促進するうえで、まず電子カルテ標準規格の統一が求められます。電子カルテの情報標準化が実現すると、患者さんの転院や救急搬送時に過去の正確な診療情報が即座に共有できるようになります。
本記事では、電子カルテ情報標準化が必要な理由やメリット・デメリットまでを解説していきます。電子カルテの標準化を準備する際のポイントまで紹介しているため、ぜひ最後までご覧ください。

電子カルテ情報標準化について、以下のとおり紹介していきます。
それぞれ解説します。
電子カルテの標準規格には、目的別に複数種類が存在します。
各規格は役割が異なり、HL7 FHIRは柔軟なデータ交換を、SS-MIX2は診療情報の保管・交換を目的としています。政府は、スマートフォンで扱いやすい最新国際標準規格「HL7 FHIR」を、データ連携の中核として普及させる方針です。目的に応じた複数規格の適切な組み合わせが、円滑な情報連携を実現します。
厚生労働省が中心となり、電子カルテ標準規格の統一が強力に推進中です。医療現場で頻繁にやり取りされる重要情報から優先的に標準化が進みます。主に、「3文書6情報」と呼ばれる項目が対象です。
3文書は
6情報は以下のとおりです。
2025年1月までの標準形式での情報交換実現に向け、国はシステム改修の補助金で医療機関を支援します。最重要項目から足並みをそろえ、全国的な医療情報連携の基盤を確実に構築します。
出典参照:【資料1】標準規格準拠の電子カルテ導入の推進策 第3回健康・医療・介護情報利活用検討会 医療情報ネットワークの基盤に関するワーキンググループ資料|厚生労働省

電子カルテ情報標準化が必要な理由は、以下の4つです。
ひとつずつ解説します。
電子カルテ情報標準化は、切れ目のない質の高い医療提供を可能にします。患者さんの転院や救急搬送時に過去の正確な診療情報が即座に共有され、重複検査や投薬ミスを防げるため、迅速で適切な処置につながりやすいです。
たとえば、意識不明で搬送された患者のアレルギー情報や服用薬が瞬時に分かると、救命判断の安全性も向上できます。医療情報がスムーズに連携する仕組みが、いかなる状況でも患者さんが最善の医療を受けられる体制を支えます。
患者さんは、自身の正確な医療・健康情報を一元的に確認・管理できるようになるため、主体的な健康管理への意識も高まりやすいです。標準化はマイナポータルなどのプラットフォーム(PHR)を通じ、自分の検査結果や薬剤情報への常時アクセスを可能にできます。
また、自身の健康状態の正しい把握は、生活習慣改善や病気の早期発見への意欲を高めやすいです。情報標準化は、医療をおまかせにせず、患者さんが自らの健康の主役となることを後押ししてくれます。
医療現場の業務効率化の実現は、標準化が必要な大きな理由です。主に、紹介状作成や他院からのデータ手入力といった事務作業が大幅に削減され、医療従事者は本来の専門業務に集中する時間が増えます。
転院患者の診療情報をシステム間で直接取り込むことで、看護師や事務員による紙書類からの再入力も不要です。業務の変革は医療従事者の負担を軽くし、患者と向き合う時間を確保できるようになるため、医療の質向上につながります。
電子カルテ情報標準化は、質の高い医療ビッグデータの二次利用を推進しています。匿名化された膨大な診療データの集約・分析は、新たな治療法や医薬品の開発、効果的な予防医療政策の立案等、医学研究の発展につながりやすいです。
従来は、各機関にデータが散在し形式もバラバラで、大規模なデータ解析は困難でした。しかし、標準化されたデータ基盤が整うと、日本の医療全体の発展が加速し、未来の医療をより良く変える力になります。

電子カルテ情報標準化の課題は、以下の3つです。
それぞれ解説します。
電子カルテ情報標準化推進における最大の課題は、経済的な負担です。通常、標準規格対応の電子カルテシステム導入や既存システム改修には、多額の費用がかかります。
経営基盤の弱い中小規模の医療機関には、大きな障壁です。そのため、国は導入を後押しする補助金制度を設けています。しかし、自己負担額は大きいため、コスト問題は標準化の普及速度を左右する重要な要素です。
システム導入・運用を管理できる、専門的なIT人材の不足も深刻な課題です。経済産業省の調査によると、2030年までに、IT人材の供給が「16〜79万人」程度不足すると推計されています。新システムの導入計画、運用開始後のトラブル対応、日々のセキュリティ管理を担える人材は多くの医療機関で不足しています。
情報システム部門を設置する余裕のない診療所や地方病院では、外部業者への依存が実情です。人材不足はシステムの安定稼働や情報セキュリティへの不安を生み、導入のためらいを招いています。
出典参照:第2-(1)-7図 IT人材需給の推計|厚生労働省
新システムが現場の業務フローに合わず、一時的に効率が低下する懸念があります。各医療機関は長年の経験で独自の工夫を重ね、業務を最適化している場合があります。
標準化された画一的なシステムを導入すると、作業手順の複雑化や二度手間の発生リスクも生じやすいです。既存業務とのギャップを埋め、現場の混乱を最小限に抑える点が、スムーズな移行実現に不可欠です。

電子カルテ情報標準化のメリットを、以下にそれぞれ紹介します。
ひとつずつ解説します。
電子カルテ情報標準化による患者側のメリットは、以下の4つです。
それぞれ解説します。
電子カルテ情報標準化が進むと、医療の安全性が飛躍的に向上します。たとえば、薬剤アレルギーや禁忌薬といった命に関わる重要情報が、どの医療機関でも正確に共有され、医療過誤のリスクが大幅に低減しやすいです。
もし旅先で急に倒れても、搬送先の病院が持病やアレルギーを瞬時に把握できます。情報を守る「命のセーフティネット」が全国に張り巡らされる状態になります。
電子カルテ情報標準化によって、生涯を通じて一貫性のある治療が可能です。出生から生涯を終えるまでの医療情報が一元管理され、引っ越しや転院をしても治療歴を踏まえた継続的なケアを受けられます。
その結果、慢性疾患の管理や長期的な健康増進計画が立てやすいです。個人個人の「生涯カルテ」が、切れ目のない健康サポートを実現してくれます。
電子カルテ情報標準化は、通院の時間的・身体的負担を軽減してくれます。たとえば、オンライン診療の普及や、医療機関変更ごとの重複検査・投薬が削減されるため、患者さんの貴重な時間と体力が守られやすいです。
また、紹介状受取のための再来院も不要になります。医療へのアクセスが手軽になり、治療の継続しやすさも向上できます。
電子カルテ情報標準化によって、自身の正確な医療・健康情報を、いつでも手元のスマートフォンなどで確認できます。マイナポータルなどを通じて、過去の検査結果や処方薬の情報を正確に把握でき、自己管理に役立ちます。
また、健康診断結果の経年比較や、薬の飲み合わせ確認が容易です。自分の健康情報の主導権を自身が持つと、より主体的な健康管理が実現できます。
電子カルテ情報標準化による医療機関側のメリットは、以下の4つです。
ひとつずつ解説します
電子カルテ情報標準化は、医療従事者が患者と向き合う本来の専門業務により多くの時間を割けるようになります。他院との情報連携にかかる紹介状作成やデータ入力の事務作業が自動化・効率化され、医師や看護師の負担が軽減されやすいです。
結果的に、患者との対話時間を十分に確保し、より丁寧な診察やケアを提供できます。医療の質と患者満足度の向上に直結する、価値のある変化です。
電子カルテ情報標準化によって、院内のさまざまな医療機器や部門システムとの連携がスムーズになります。標準規格準拠により、放射線部門の画像システム(PACS)や医事会計システム(レセコン)など、異なるメーカーの機器・システムとも円滑なデータ連携が可能です。
また、院内での情報伝達が迅速・正確になることで、チーム医療の質を高められます。院内全体の業務最適化は、より効率的な病院経営の実現につながります。
電子カルテ情報標準化の促進で、特定の一社にシステムを依存する「ベンダーロックイン」から脱却が可能です。将来の電子カルテ更新時にデータの移行が容易になり、性能やコストパフォーマンスに優れたシステムを自由に選択できます。
さらに、医療機関は自院のニーズに最適なベンダーを公正に比較検討できるため、健全な市場競争が促進されます。その結果、より良いサービスを安価に利用できる可能性も広がりやすいです。
電子カルテ情報標準化によって、災害や緊急時への対応力が格段に強化されます。具体的には、カルテ情報は院内サーバーだけでなく、堅牢なデータセンターのクラウド上にも安全に保管されます。
そのため、地震や水害で院内設備が破損しても、最重要の診療情報を失うリスクを最小限に抑えやすいです。また、避難先での迅速な診療再開等、事業継続計画(BCP)の実効性が高まります。国民の命と健康を守る医療機関のレジリエンス(回復力)が大きく向上できます。
電子カルテ情報標準化による社会全体のメリットは、以下の4つです。
それぞれ解説します。
電子カルテ情報標準化が促進することで、限りある医療資源の最適化と、国全体の医療費抑制につながります。全国の医療機関で情報共有が進むと、不要な重複検査や薬剤の過剰投薬が削減され、医療費の適正化が期待できます。
少子高齢化が進む日本において、質の高い国民皆保険制度を未来へ維持するために不可欠な取り組みです。効率的な医療提供体制の構築は、社会全体の持続可能性を高められます。
電子カルテ情報標準化は、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続ける「地域包括ケアシステム」の実現を後押ししてくれます。たとえば、地域の病院や診療所、介護施設や薬局などが、一人の患者の情報をシームレスに連携・共有できるようになります。
結果的に、医療と介護が一体となった、切れ目のないサポート体制が構築可能です。地域全体がひとつのチームとなり、高齢者の生活を支える社会が現実になります。
電子カルテ情報標準化によって、医療ビッグデータの活用とイノベーション創出につながりやすいです。全国から集まる標準化・匿名化された質の高い医療データを研究開発に活用し、画期的な新薬や治療法の開発、個別化医療(プレシジョン・メディシン)の実現も加速できます。
そのため、とくに治療困難な病気に苦しむ人々を救う希望の光です。日本の医療技術が、世界をリードする原動力となる可能性も秘めています。
新型コロナウイルスのような新興感染症発生時の、国全体の対策能力の強化が可能です。たとえば、全国の感染状況やワクチン接種歴、治療経過を迅速・正確に把握できるため、科学的根拠にもとづく効果的な公衆衛生対策を講じられます。
さらに、正確なデータにもとづく迅速な意思決定は、感染拡大防止と社会経済活動維持の両立に極めて重要な役割を果たします。

電子カルテ情報標準化のデメリットを、以下にそれぞれ紹介します。
ひとつずつ解説します。
電子カルテ情報標準化による医療機関側のデメリットは、以下の4つです。
それぞれ解説します。
既存システムの改修やリプレイス費用は、医療機関にとって最大のデメリットです。標準規格対応にはソフトウェア更新だけでなく、サーバー等ハードウェアの一新も必要になる場合があり、多額の投資が求められます。経営体力に乏しい小規模クリニックにとって、費用負担は導入断念の大きな理由です。
新システムの操作に全職員が慣れるまで時間と労力がかかります。日々の多忙な業務の合間に研修時間を確保し、全医師、看護師、事務員が新操作方法を習得するのは容易ではありません。導入直後は操作に手間取り、一時的に業務効率が落ちる覚悟も必要です。
電子カルテ情報標準化のシステムが、各医療機関で最適化された独自の業務フローに適合せず、非効率な作業が発生する可能性もあります。従来1クリックの作業が新システムでは3クリック必要になるなど、現場の感覚とズレが生じやすい要因です。細かなストレスの蓄積が、職員のモチベーション低下につながる懸念も指摘されます。
過去の膨大な診療情報を旧システムから新システムへ正確に移行する作業には、専門知識と多くの時間が必要です。データ形式の変換や文字化け等のエラーチェックを慎重におこなう必要があり、移行作業中は診療制限も考えられます。データ移行の負担の大きさが、医療機関の導入躊躇の一因です。
電子カルテ情報標準化による患者側のデメリットは、以下の3つです。
ひとつずつ解説します。
個人情報の漏洩やプライバシー侵害の懸念は、患者にとって最大のデメリットです。医療情報がネットワークで共有されると、外部からのサイバー攻撃による情報流出リスクはゼロではありません。自分の意図しない範囲で情報が閲覧されるプライバシーへの不安感も払拭が必要です。
デジタル格差(デジタルデバイド)が、医療格差につながる場合もあります。スマートフォンやPC操作に不慣れな高齢者等が、オンラインでの情報確認や手続きの恩恵を十分に受けられず、取り残される懸念です。誰もが等しくメリットを享受できるよう、電話や窓口でのサポート体制の併設が不可欠です。
自分の知らないところで医療情報がやり取りされることや、万一のシステム障害で適切な医療が受けられなくなる可能性に対し、漠然とした不信感を抱く患者も少なくありません。自身の健康というデリケートな情報のデジタル管理への心理的抵抗感は根強いです。丁寧な説明を通じた国民の理解と信頼の醸成が求められます。

電子カルテ標準化がなかなか進まない背景には、根深い理由があります。核心は、多くの医療機関が導入に踏み切れない「コスト」「人材」「しがらみ」の三つの壁です。主に以下が、普及を阻む大きな要因です。
複合的な課題が絡み合い、多くの医療機関は「必要性はわかるが、すぐには動けない」ジレンマに陥っています。

電子カルテ標準化に対応を考える医療機関にとって、成功のポイントは周到な準備です。費用対効果の高いスムーズなシステム移行を実現し、導入後の混乱を最小限に抑えるには、ポイントの着実な実行が重要です。
とくに、国の方針や補助金制度に関する正確な情報収集は重要です。また、情報にもとづき自院の現状課題を洗い出して複数ベンダーから具体的な提案と見積もりを受けることや、院内に推進体制を整えて全職員の理解と協力を得ることなどが不可欠です。

電子カルテの情報標準化は、導入コストや人材不足、セキュリティの懸念など乗り越えるべき多くの課題を抱えています。しかし、困難を乗り越えた先には、患者や医療機関、社会全体に計り知れないメリットをもたらします。
患者一人ひとりに寄り添う安全で質の高い医療、すなわち「患者中心の医療」実現に不可欠な要素です。国や医療機関、システムベンダーだけでなく、国民一人ひとりが重要性を深く理解し、各立場で協力すれば、日本の医療は新たなステージへ進化できるでしょう。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
