レガシーシステム統合で実現する医療DXのメリットとは?
医療

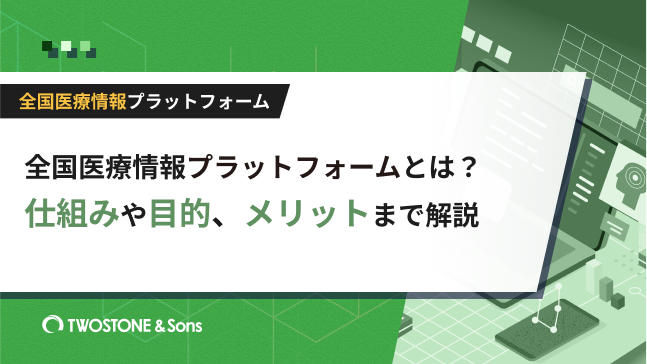
全国医療情報プラットフォームは、マイナンバーカードのICチップや健康保険証の記号番号などを利用する「オンライン資格確認等システム」を基盤として機能する仕組みです。この記事では、全国医療情報プラットフォームの仕組みや目的、メリットまでを紹介します。
全国医療情報プラットフォームは、医療情報を全国で共有・活用するための新しい社会インフラです。患者はより安全で質の高い医療を、医療従事者にとっては負担の少ない労働環境を実現する可能性を秘めています。
本記事では、全国医療情報プラットフォームの仕組みや目的、メリットまでを解説していきます。全国医療情報プラットフォームに関連するサービスまで紹介しているため、ぜひ最後までご覧ください。

医療DXについて、以下に紹介していきます。
それぞれ解説します。
政府が医療DXを強力に推進する理由は、日本の医療が直面する深刻な社会課題の解決です。少子高齢化で医療を必要とする人は増え続けているため、担い手となる労働人口は減少し、医療従事者の負担は増大し続けています。
国民医療費の増大も喫緊の課題であり、デジタル技術の活用による業務効率化と医療の質の向上が不可欠な状況です。政府は持続可能な医療提供体制を構築するため、医療DXを国家戦略として位置づけています。
政府が掲げる「医療DX令和ビジョン2030」の全体像は、主に、以下の3つの柱で構成されています。
3つの施策は相互に連携しており、情報の断絶を防ぎ、データにもとづいた質の高い医療の実現を目指します。このビジョンが、日本の医療の未来を形作る設計図です。
出典参照:医療DXについて|厚生労働省
出典参照:「医療DX令和ビジョン2030」厚生労働省推進チーム|厚生労働省

全国医療情報プラットフォームについて、以下に紹介します。
ひとつずつ解説します。
出典参照:医療DXについて|厚生労働省
全国医療情報プラットフォームは、マイナンバーカードのICチップや健康保険証の記号番号などを利用する「オンライン資格確認等システム」を基盤として機能する仕組みです。患者が医療機関の窓口でマイナンバーカードを提示し同意すると、医師や薬剤師はシステムを通じてその患者の薬剤情報や特定健診情報などを閲覧できます。
医療従事者は、患者の最新かつ正確な情報を即座に把握し、診療や服薬指導に活かすことが可能です。オンライン資格確認のネットワークが、全国の医療情報をつなぐ土台となります。
全国医療情報プラットフォームには、主に3つの特徴があります。
3つの特徴が組み合わさり、国民が安心して自身の医療情報を預け、活用できる環境が実現します。

全国医療情報プラットフォームの創設と背景について、以下に紹介していきます。
それぞれ解説します。
全国規模での情報共有基盤が必要とされた背景には、いくつかの重要な経緯があります。これまで地域単位での医療情報連携ネットワーク(EHR)の試みはありましたが、全国的な広がりには至りませんでした。
しかし、東日本大震災などの大規模災害時にお薬手帳が流されるなどして患者情報がわからなくなる事態が発生し、情報連携の重要性が再認識されました。また、新型コロナウイルス感染症対策では、患者情報の迅速な共有が急務となり、全国統一のプラットフォーム構築に向けた動きが一気に加速しています。
出典参照:東日本大震災時におけるお薬手帳の活用事例 東日本大震災関連 | 日本薬剤師会オフィシャルWebサイト
全国医療情報プラットフォームが目指す最終的なゴールは、医療に関わるすべての人にメリットをもたらし、日本の医療全体の質を底上げすることです。具体的には、以下の3つです。
三方よしの実現が、プラットフォームの根本的な目的といえます。この構想で、持続可能でより良い医療システムの構築が進められます。
全国医療情報プラットフォームは、「医療DX令和ビジョン2030」が掲げる目標を実現するための中核的な基盤です。電子カルテ情報の共有や電子処方箋といったほかの重要な施策も、このプラットフォームという土台があって初めて成り立ちます。
医療DXは大きな建物を支える最も重要な基礎部分であり、その成否が日本の医療の未来を左右するといっても過言ではありません。この基盤整備が、今後の医療改革の進展を決定づけます。

全国医療情報プラットフォームの課題は、以下の4つです。
ひとつずつ紹介します。
プラットフォームが真価を発揮する大前提として、各医療機関への電子カルテ導入が不可欠です。この状況が改善されない限り、プラットフォーム上に共有される情報は限定的なものになってしまいます。
日本の一般診療所における電子カルテの普及率は2020年時点で約49.9%、まだ半数に留まっています。資金面やIT人材の確保が難しい中小規模の医療機関では導入が遅れています。電子カルテの普及促進が喫緊の課題です。
医療機関の規模や地域によって、ITリテラシーやシステム投資への余力に大きな差がある「情報格差(デジタルデバイド)」も深刻な課題です。この格差を放置すると、プラットフォームに参加できる医療機関に偏りが生じ、医療の地域間格差につながる懸念も指摘されています。
都市部の大病院と地方の小規模な診療所とでは、デジタル技術を導入・活用する能力に隔たりがあります。すべての医療機関が足並みを揃えてDXを進められるよう、国による手厚い支援策が重要です。
国民が安心してプラットフォームを利用するため、プライバシー保護に関するルールを正しく理解しておく必要があります。大前提として、本人の同意なしに医療情報が共有されることはありません。
患者は医療機関の窓口で、どの情報をどこまで共有するかに同意したうえで、マイナンバーカードによる認証をおこないます。プライバシー保護の仕組みと、自分自身の情報がどのように扱われるかを国民一人ひとりが知ることが、制度への信頼につながります。
出典参照:マイナンバーカードの健康保険証利用について|厚生労働省
プラットフォームを長期的に維持・発展させていくうえで、運用面の課題も存在します。全国民の機微な情報を扱う巨大システムであるため、24時間365日の安定稼働、巧妙化するサイバー攻撃への万全な対策が不可欠です。
今後蓄積されていく膨大な医療データを適切に管理・保守していく技術力や人材、継続的な予算の確保も大きな課題となります。運用課題を着実にクリアしていくことが、信頼される社会インフラとなるための条件です。

全国医療情報プラットフォームのメリットは、以下の3つです。
それぞれ解説します。
全国医療情報プラットフォーム促進により、患者はいつでもどこでも、自分に最適化された安全な医療を受けられます。たとえば、旅先での急な体調不良や救急搬送時でも、駆け込んだ病院で過去の病歴やアレルギー、服用中の薬といった正確な情報が共有されることで、迅速で的確な診断・治療が可能です。
結果的に、複数の医療機関から同じ薬が処方される重複投薬や、危険な飲み合わせのリスクを大幅に低減できます。医療の質と、安全性の大きな向上が期待されています。
医療従事者の業務負担軽減について、以下3つを紹介していきます。
ひとつずつ解説します。
全国医療情報プラットフォームを通じて、医療機関同士でやり取りされる紹介状などの文書を電子的に交換できるようになります。
従来おこなわれていた文書の印刷や郵送、受け取り後のスキャンといった手作業が不要になるため、文書作成や管理にかかる時間とコストの大幅な削減につながります。
難病医療や子ども医療費助成など、さまざまな公費負担医療制度の受給者証もデジタル化の対象です。現在は受付で目視による確認が必要ですが、オンライン資格確認システムと連携することで、資格情報の確認が自動化されます。
窓口業務の負担軽減と、確認漏れなどのヒューマンエラーの防止につながります。
個人の予防接種履歴を一元的に管理し、プラットフォーム上で共有する仕組みも構想されています。医療機関は患者の接種状況を正確かつ迅速に把握でき、接種計画の立案や重複接種の防止が容易になりやすいです。
自治体への接種実績報告などもデジタル化されるため、医療機関と行政双方の事務負担の軽減が期待されます。
全国医療情報プラットフォームは、未来の医療を進化させる貴重な資源にもなり得ます。たとえば、全国から集まる膨大な医療データを、個人が特定できないように匿名化したうえで分析・活用します。
その結果、これまで見過ごされてきた病気の予兆の発見や、特定の治療法がどのような患者に効果的かを明らかにすることが可能です。データ活用は、画期的な新薬や治療法の開発、効果的な予防医療の確立につながり、国民の健康増進に貢献することが期待されています。

全国医療情報プラットフォームに関連するサービスについて、以下に紹介していきます。
それぞれ解説します。
電子処方箋は、プラットフォームを活用した代表的なサービスです。これまで紙で発行されていた処方箋を電子化し、その情報を複数の医療機関や薬局で共有する仕組みです。
患者はどの薬局でおこなっても同じ情報にもとづいた服薬指導を受けられます。重複投薬や危険な飲み合わせをシステムが自動でチェックしてくれるため、医療の安全性が向上します。医療機関や薬局にとっても、処方箋の管理コスト削減や業務効率化につながり、双方にメリットのある仕組みです。
全国の医療機関が持つ電子カルテの情報を、プラットフォーム上で共有するためのサービスも始まっています。患者の同意のもと、診療情報提供書(紹介状)や退院時サマリー、健診結果といった詳細な医療情報を、医療機関同士でスムーズに閲覧が可能です。
国は、このサービス導入の障壁を下げるため、電子カルテの改修費用などを補助する制度を設けています。支援策を活用し、多くの医療機関が参加することが、サービス全体の価値を高めます。
出典参照:電子カルテ情報共有サービス|厚生労働省

全国医療情報プラットフォームで求められる取り組みは、以下の3つです。
ひとつずつ紹介します。
まずは、電子処方箋への対応が求められます。この変化に積極的に対応することが、患者の利便性と安全性の向上に直接貢献します。
医療機関や薬局は、電子処方箋の送受信が可能になるよう、既存のシステムを改修したり、新しいシステムを導入したりする必要があります。単にシステムを導入するだけでなく、受付から会計までの業務フロー全体を見直し、スタッフへの研修をおこなうのも重要です。
現在、電子カルテはメーカーごとに仕様が異なり、データの相互利用が難しい一因となっています。国が定めた標準規格(HL7 FHIR)に準拠した電子カルテの導入が強く推奨されています。
これから電子カルテを新規導入したり、更新を検討したりする診療所などにとって、国が開発した「標準型電子カルテ」は有力な選択肢です。標準化への取り組みが、真のデータ連携を実現する礎となります。
電子カルテ情報共有サービスへ積極的に参加することが求められます。プラットフォームのメリットを最大限に享受するため、自院の情報を共有し、他院の情報を活用する姿勢が不可欠です。
サービスの導入にはコストや手間がかかりますが、得られる医療の質の向上や業務効率化といった大きな恩恵が得られます。共有の輪に加わることが、自院の競争力を高め、地域医療に貢献する道筋です。

全国医療情報プラットフォームは、医療情報を全国で共有・活用するための新しい社会インフラであり、今後の日本の医療に不可欠な存在です。
患者にとってはより安全で質の高い医療を、医療従事者にとっては負担の少ない労働環境を実現する大きな可能性を秘めています。
電子カルテの普及や医療機関の格差など、乗り越えるべき課題は少なくありません。その先にある未来を見据え、医療関係者、私たち国民一人ひとりがこの大きな変化を正しく理解し、来るべき時代に向けて今から準備を始めることが極めて重要です。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
