レガシーシステム統合で実現する医療DXのメリットとは?
医療

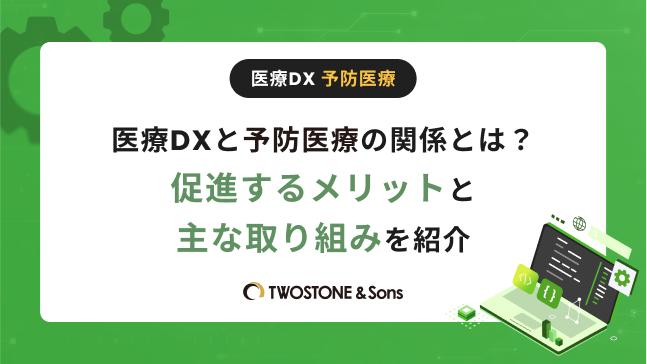
医療DXによる予防医療は、データやデジタル技術で医療全体を変革し、病気予防を促進する取り組みです。持続可能な社会保障制度を維持し、国民一人ひとりが質の高い医療を受け続けるために重要です。この記事では、医療DXと予防医療の関係や促進するメリットと主な取り組みまでを紹介します。
医療DXによる予防医療は、持続可能な社会保障制度を維持し、国民一人ひとりが質の高い医療を受け続けるために重要です。データやデジタル技術で医療全体を変革し、病気予防の促進につながります。
本記事では、医療DXと予防医療の関係や促進するメリットとまでを解説していきます。医療DXの代表的な取り組みまで紹介しているため、ぜひ最後までご覧ください。

医療DXは、単なる医療現場のデジタル化ではありません。データやデジタル技術を駆使して個人の健康状態に合わせた最適な医療・ヘルスケアを提供し、国民の健康寿命を延ばす「医療全体の変革」を指します。病気の治療中心の考え方に加え、病気の予防にも貢献する点が医療DXの本質です。
日々の健康データと電子カルテ情報が連携されると、AIが将来の疾病リスクを予測し、発症前の対策を促せます。医療DXは、健康との向き合い方を根本から変える未来に向けた重要な取り組みです。

医療DXは、「病気になってから治す」医療から「病気を未然に防ぐ」予防医療へのシフトを強力に後押しします。スマートフォンアプリやウェアラブルデバイスを通じて個人の健康データを継続的に収集・分析し、一人ひとりに最適な予防策を導き出せます。
年に一度の健康診断でしか把握できなかった体の変化を、日常的に「見える化」が可能です。専門家はデータにもとづいた的確なアドバイスを提供でき、個人は主体的な健康管理に取り組めます。医療DXは、個人の健康意識と医療の専門性を結びつけ、効果的な予防医療の実現につながります。

医療業界の課題は、以下のとおりです。
それぞれ解説します。
現在の医療システムは、少子高齢化の進行で限界に近づいています。医療を必要とする高齢者の急増に対し、社会を支える現役世代は減少し、医療の担い手も財源も不足している状態です。
厚生労働省のデータでは、2025年に「団塊の世代」が75歳以上となり医療需要がピークを迎えると予測しています。現状維持では必要な時に十分な医療を受けられない事態も起こりかねません。そのため、状況打開にはテクノロジーを活用した効率的な医療体制の構築が急がれます。
出典参照:全国高齢者医療・国民健康保険主管課(部)長及び後期高齢者医療広域連合事務局長会議《保険局調査課説明資料》令和3年3月 ホーム|厚生労働省
日本の質の高い医療は、多くの医療従事者の自己犠牲的な長時間労働に支えられてきました。その反面、過酷な労働環境は心身の疲弊を招き、医療従事者の離職につながるケースも少なくありません。
現状のままでは、医療の質維持自体が困難になる危機感が高まります。医療従事者が専門性を活かし働き続けられるよう、DXによる業務効率化を進め、働き方改革の実現が不可欠です。医療の未来を守るには、まず医療の担い手である人々の労働環境改善が必要です。
居住地や診療科で、受けられる医療の質に大きな差が生まれているのが日本の現状です。都市部に医療機関が集中する一方、地方やへき地では専門医が不足し、満足な医療を受けられない「医療過疎」が深刻化しています。いざという時に、最適な治療を受けられないリスクをはらみます。
そのため、オンライン診療等のデジタル技術活用は、地理的な制約を乗り越え全国どこにいても質の高い医療へのアクセスの確保につながります。医療の地域格差是正は、国民全員の命と健康を守るうえで重要な課題です。
日本の国民医療費は年々増加の一途をたどり、国の財政を圧迫する要因です。医療費の多くは、生活習慣病等の病気「治療」に使われています。
しかし、医療費が増え続ければ、公的医療保険制度が立ち行かなくなり、個人の医療費負担が増える未来も避けられません。病気になる前の「予防」に力を入れ、健康な人を増やす活動が、結果的に将来の医療費抑制につながります。医療DXによる予防医療の推進は、日本の社会保障制度を持続可能にする切り札です。
医療現場には、いまだに紙カルテやFAXでのやり取りといったアナログ業務が多く残っています。非効率な作業は、医療従事者の大きな負担であり、医療の質にも影響をおよぼしかねません。また、病院やクリニック間で患者情報が分断されることで、転院や救急搬送の際、過去の病歴やアレルギー情報が迅速に伝わらないリスクが存在しています。
医療情報のデジタル化と、安全なネットワークでの共有は、業務負担の軽減と、より安全で質の高い医療の提供を期待できます。複雑に絡み合う課題を解決し、全国民が将来にわたり安心して医療を受けられる社会を維持するには、医療DXの推進が不可欠な解決策です。

政府が推進する医療DXの方針は、以下のとおりです。
ひとつずつ解説します。
出典参照:医療DXについて|厚生労働省
政府は、個人の医療・健康情報を全国の医療機関で安全に共有・活用できる「全国医療情報プラットフォーム」の創設を目指しています。生涯にわたる自身の健康情報を一元管理し、どの医療機関にかかっても最適な医療を受けられる環境を整える仕組みです。
たとえば救急搬送された際、本人の意識がなくてもアレルギーや既往歴といった重要な情報が即座に共有されます。創設されるプラットフォームは、一人ひとりが安心して医療を受けるための社会的インフラとなります。
電子カルテ情報の標準化は、医療機関同士の連携を円滑にし、より質の高い医療や予防を実現するために重要な取り組みです。現状、電子カルテの仕様がメーカーごとに異なり、情報の共有や活用が難しいといった問題がありました。
しかし、政府は仕様を統一(標準化)し、どの医療機関でもデータを円滑にやり取りできる環境を整備しています。もし実現すれば紹介状作成などが効率化され、膨大な医療データを分析し、新たな治療法や予防策の開発につなげることも可能です。
診療報酬改定DXは、医療機関の請求業務等を効率化し、医療従事者がより専門性の高い業務に集中できる環境を作る取り組みです。従来、医療機関は2年に一度の診療報酬改定のたび、複雑な作業に多くの時間と労力を費やしてきました。
そのため、プロセスのデジタル化・共通化によって事務的な負担を大幅に軽減し、リソースを患者との対話や予防指導といった本来の業務に振り向けさせます。結果的に、医療の質そのものの向上も期待されます。

医療DXで予防医療を促進するメリットを紹介していきます。
それぞれ解説します。
医療DX促進による【個人】のメリットは、以下のとおりです。
ひとつずつ解説します。
医療DXが進むと、スマートフォンアプリなどを通じて、日々の歩数や睡眠時間や血圧といった健康データを、ゲーム感覚で管理できます。データがグラフ等で「見える化」されると、自身の頑張りが一目瞭然となり、健康への意識が自然と高まりやすいです。
また、漠然とした健康不安を具体的な行動へ変えられる手段となります。その結果、自身の体をより深く理解し、主体的にコンディションを整える習慣を身につけられます。
集めた自身の健康データにもとづき、AIが「専用」の食事や運動プランを提案してくれます。優秀なパーソナルトレーナーが、常に寄り添ってくれる感覚です。
たとえば、「昨日の塩分摂取量が多めだったので、今日の昼食は推奨メニューをどうぞ」といった具体的な助言を受けられます。画一的な健康情報ではなく、自身のデータにもとづいた最適な助言によって、より効果的に病気を予防し健康を維持できます。
病院に行くほどではない体調変化や、健康診断の結果について、自宅からオンラインで気軽に医師や保健師に相談できます。仕事や育児で多忙な人も、移動時間や待ち時間を気にせず専門家のアドバイスを受けられるため、不安を早期に解消しやすいです。
また、相談のハードルが下がることで、病気の兆候を早期に発見し重症化を防げます。日々の暮らしに、大きな安心感をもたらします。
全国医療情報プラットフォームが整備されると、自身の医療情報や健診データは生涯にわたり一元管理されます。引っ越しや転院をした場合でも、新しい病院で過去の正確な医療情報が即座に共有が可能です。
また、アレルギーや副作用歴や既往歴なども確実に伝わるため、いつでもどこでも、より安全で質の高い医療を受けられます。自身の健康記録を、生涯にわたる資産として活用が可能です。医療DXは一人ひとりの健康意識を高め、生涯にわたる安心と主体的な健康管理を実現するうえで、中心的な役割を果たします。
医療DX促進による【医療従事者】のメリットは、以下のとおりです。
それぞれ解説します。
医療従事者は、診察時情報に加え、患者の日常的な生活習慣データ(PHR)も踏まえ、より科学的根拠に基づいた的確な予防指導が可能です。血圧の変動パターンから、特定の時間帯の降圧剤服用を提案するなど、個別性の高い介入が実現できます。
また、従来の経験や勘に頼る部分が補完され、予防医療の精度が格段に向上します。データという客観的な指標は、患者と医療従事者の双方を助けるメリットです。
膨大な医療データをAIが解析すると、自覚症状がない段階でも、将来の心筋梗塞や脳卒中等の発症リスクが高い患者を早期に発見できます。医療従事者は、重症化する前に予防的な治療や生活指導を開始できるため、救える命の増加が期待されます。
対症療法から先制医療への転換です。未来のリスク予測と先手を打つ医療の実現は、医療従事者にとってのやりがいにつながります。
医療DXは、カルテ入力や書類作成、情報収集といった事務作業の自動化・効率化が可能です。医療従事者は煩雑な業務から解放され、患者との対話や治療計画策定といった、本来の専門性を活かす業務に多くの時間を割けます。
また、業務負担の軽減は働き方改革を推進し、医療従事者の離職防止にも直結しやすいです。結果的に、患者一人ひとりと向き合う時間が増えるため、より温かみのある医療の提供が可能になります。
患者一人の情報を、医師や看護師、薬剤師やリハビリ専門職など、関わる全スタッフがリアルタイムでの共有が可能です。各専門的視点から意見を出し合い、多角的なアプローチで治療や予防にあたる「チーム医療」の質が飛躍的に向上できます。
医師の処方意図を薬剤師が正確に理解し、看護師が日々のケアに活かすといった円滑な連携も生まれやすいです。組織全体で患者を支える体制の強化は、医療の安全性と効果を高められます。
医療DX促進による【社会・企業】のメリットは、以下のとおりです。
それぞれ解説します。
国民一人ひとりが予防医療に取り組み健康になると、生活習慣病などの治療費が減り、国全体の医療費の伸びを抑制できます。結果的に、増大し続ける医療費で危機に瀕する日本の公的医療保険制度を守れます。
また、削減できた財源を、より先進的な医療技術開発や真に医療を必要とする人々のために使うことも可能です。予防医療への投資は、未来の社会保障を安定させる最も効果的な手段です。
企業による従業員の健康管理支援「健康経営」は、従業員の心身の健康を保ち、仕事への意欲や集中力を高めやすいです。結果的に、組織全体の生産性が向上し、企業の業績向上にもつながります。
医療DXは、従業員の健康状態把握やオンラインでの健康相談などを通じて、健康経営を強力にサポートしてくれます。従業員の健康は、企業にとって最も重要な経営資源であるという認識が、今後の企業成長につながる鍵です。
全国から集まる匿名化された膨大な医療・健康データ(ビッグデータ)は、宝の山です。データを製薬会社や研究機関が活用することで、これまでになかった革新的な医薬品や治療法、新しいヘルスケアサービスの開発も加速させやすいです。
さらに、日本の医療産業が国際的な競争力を持ち、新たな成長分野となることも期待されます。医療DXは、国民の健康を守るだけでなく、日本の経済を活性化させる原動力にもなり得ます。
医療DXは、個人の健康に加え、社会全体の健康を守る「公衆衛生」分野でも力を発揮します。各地の医療データをリアルタイムで分析すると、新型コロナウイルスのような感染症の流行を早期に察知し、迅速な対策を講じることが可能です。
また、特定地域の健康課題をデータから明らかにし、効果的な健康増進施策を打てます。データにもとづいた科学的な公衆衛生は、私たちの暮らす社会をより安全で安心なものへ導きます。医療DXは国民の健康寿命を延ばすだけでなく、日本の社会経済全体を持続可能なものにする重要な基盤です。

医療DXの代表的な取り組みは、以下のとおりです。
それぞれ紹介します。
PHR(Personal Health Record)は、一人ひとりが自身の健康・医療情報を電子的に管理・活用する仕組みです。健康診断結果や日々の血圧、体重、歩数といったデータをスマートフォンアプリなどで一元管理し、必要に応じ医療機関に提供できます。
医療DX時代における、個人の健康手帳です。PHRの普及は、主体的な健康管理を促し、あらゆる予防医療サービスの基盤となります。
出典参照:かかりつけ連携手帳アプリで医療情報を患者の手に|一般社団法人 かかりつけ連携手帳推進協議会
出典参照:子育てに役立つアプリ「OYACOplus(オヤコプラス)」をぜひご利用ください!|群馬県前橋市役所
出典参照:健康経営とESG。従業員の健康が企業価値となる時代|株式会社 メディカルリソース
スマートウォッチに代表されるウェアラブルデバイスは、PHRを充実させるツールです。たとえば、心拍数や睡眠の質、血中酸素濃度といった健康データを、意識することなく24時間365日自動で収集・記録します。
データはPHRアプリと連携し、日々の体調変化を客観的に捉えるのに役立ちます。常に健康を見守る、見えないパートナーのような存在です。
出典参照:着るだけで生体情報の計測が可能な衣料型ウェアラブルシステムグンゼがNECのIoT技術協力で開発2016年1月の「ウェアラブルEXPO」に出展|日本電気株式会社
出典参照:グーグルが涙で血糖を測定する「スマート・コンタクトレンズ」を開発|株式会社 創新社
PHRに蓄積された個人の健康データや、全国から集まる医療ビッグデータをAIが解析し、将来の病気の発症リスクを高い精度で予測できます。たとえば、数年後の糖尿病や心疾患のリスクを算出し、個人に合わせた予防策の提案が可能です。
AIは、膨大なデータのなかから人間では見つけられない病気のサインを読み解きます。未来の健康アドバイザーとして、予防医療に革命をもたらす可能性を秘めています。
出典参照:「AI創薬プラットフォーム事業と生成AI 」参画のTXP Medicalがwebinarを開催 「がん×生成AI」がもたらす医療データの可能性 | TXP Medical 株式会社
出典参照:NEC 、理化学研究所、日本医科大学、 電子カルテと AI 技術を融合し医療ビッグデータを多角的に解析 |日本電気株式会社、理化学研究所、日本医科大学
オンライン診療は、通院負担を軽減するだけでなく、予防医療で重要な役割を果たせます。具体的には、高血圧や糖尿病等の生活習慣病患者が、定期的にオンラインで医師や看護師の指導を受けると、治療の継続率を高められます。
また、専門医がいない地域に住む人が、都市部の専門医から予防的な助言を受けることも可能です。医療へのアクセスを向上させられるため、病気の早期発見や重症化予防にもつながります。
出典参照:オンライン診療その他の遠隔医療に関する事例集|厚生労働省

医療DXを促進して予防医療をおこなう方法は、以下のとおりです。
ひとつずつ解説します。
まず、自院が抱える課題の洗い出しから始めます。たとえば以下のように具体的な問題をリストアップしてみましょう。
DXによって「どのような医療を実現したいのか」というビジョンを明確に描くことが重要です。ビジョンが、今後の取り組みの方向性を決めます。
医療DXは、一部署だけで進められるものではありません。院長の強力なリーダーシップのもと、医師や看護師、事務職員やIT担当者など、部署を横断した推進チームの組織が不可欠です。
チームが中心となり、現場の意見を吸い上げながらDXの計画立案や導入支援、効果検証などを主導します。全職員を巻き込み、一体感を持って取り組む姿勢が成功のポイントです。
DXの目的達成に、どのようなシステムが必要かを見極めます。たとえば、以下のような選択肢です。
重要なのは、いきなり大規模なシステムを導入せず、特定部署や業務に限定し試験的に導入するスモールスタートです。小さな成功体験の積み重ねは、本格導入への抵抗感を減らし、円滑な移行の促進につながります。
新しいシステムの導入だけでは、DXは成功しません。全職員がシステムを効果的に使いこなせるよう、丁寧な研修やマニュアル整備が不可欠です。また、同時にデジタル化を前提とした新しい業務プロセスへの再設計(リデザイン)も重要です。
従来の紙業務をデジタルに置き換えるだけでなく、DXのメリットを最大限活かす、より効率的で質の高い働き方への変革視点が求められます。
DXの取り組みが、当初の目的を達成できているか客観的に評価するのが重要です。たとえば、「患者の平均待ち時間」「書類作成にかかる時間」「職員の残業時間」といった指標(KPI)を設定し、導入前後の変化を測定します。
その結果を分析し、「改善点は無いか」「新たな課題は発生していないか」などを検討し、次の計画に反映させます。PDCAサイクルを回し続けることで、医療DXは一過性のイベントではなく、継続的な改善活動として組織に根付きやすいです。ステップの着実な実行が医療DXを成功に導き、最終的に患者と医療従事者の双方にとって価値ある変革を実現します。

医療DXによる予防医療の推進は、データやデジタル技術で医療全体を変革し、病気予防を促進する取り組みです。持続可能な社会保障制度を維持し、国民一人ひとりが質の高い医療を受け続けるために不可欠です。
また、少子高齢化や医療費増大といった社会課題の解決策として、政府も推進しています。個人は健康管理が容易になり、医療従事者は業務負担が軽減、社会全体では医療費抑制にもつながります。この変革を理解し活用することで、未来の健康を守っていきましょう。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
