レガシーシステム統合で実現する医療DXのメリットとは?
医療

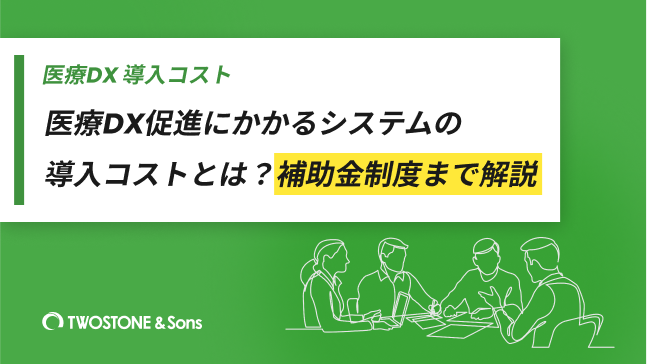
医療DXの推進には、システム導入コストの大きなハードルがあります。その負担を軽減するためには、国や自治体などの補助金制度を活用するのがおすすめです。この記事では、医療DX促進にかかるシステムの導入コストや補助金制度までを紹介します。
医療DXの推進には、システム導入コストにおける高いハードルがあります。そして、その負担を軽減するためには、国や自治体の補助金制度をリサーチして活用するのがおすすめです。
この記事では、医療DX促進にかかるシステムの導入コストや補助金制度について解説します。医療DXでシステムの導入コストを抑えながら取り組む方法まで解説しているため、ぜひ最後までご覧ください。

医療DXは、単なるデジタルツールの導入ではありません。データとデジタル技術を駆使して医療システム全体を変革し、「医療の質の向上」「業務効率化」「患者体験の向上」を実現する国家的な取り組みです。
背景に厚生労働省主導の「データヘルス改革」があり、医療情報の効果的な活用を目指します。また、全国の医療機関で診療情報を確認できる仕組みや、電子カルテ情報の標準化が進められています。医療DXは国策として重要視され、今後の医療提供体制の根幹をなしているのが現状です。
出典参照:医療DXについて|厚生労働省
出典参照:データヘルス改革推進本部|厚生労働省
医療DXのシステム導入における課題は、以下の4つです。
それぞれ紹介します。
医療DX推進の最大の課題は、導入コスト負担です。システムの購入や開発の高額な初期費用に加え、毎月の利用料や保守・メンテナンス費用などのランニングコストが継続的に発生します。
また、電子カルテのような大規模システムは、初期費用だけで数百万円以上かかる場合があります。システム導入には、目先の費用だけでなく、中長期的な視点の資金計画策定が不可欠です。
医療情報は、個人の病歴や遺伝情報などを含む極めて機密性の高い個人情報(要配慮個人情報)です。そのため、システムの導入にあたっては、サイバー攻撃による情報漏洩やデータの改ざんを防ぐための高度なセキュリティ対策が不可欠です。
また、ファイアウォールの設置や不正侵入検知システムの導入、データの暗号化、定期的な脆弱性診断など多層的な防御策を講じる必要があり、そのための費用も継続的に発生します。万が一、情報漏洩事故が発生した場合、患者への損害賠償はもちろん、医療機関としての社会的信用を損なうリスクを常に抱えることになります。
医療DXのシステムの導入は、契約後すぐに完了せず、安定稼働までには相当な時間と労力がかかります。自院の課題に合ったシステムを複数のベンダーから比較検討し、選定するプロセスが必要です。
システムを院内に設置して、既存データから移行作業や職員への操作研修が重要です。全職員がスムーズに使いこなせるまで、運用ルールの策定や改善期間を含め、数ヶ月単位の時間を見込む必要があります。システムの安定稼働には、導入プロセス全体で相応の時間と労力がかかる理解が求められます。
院内のデジタル格差やIT人材の不足も、医療DXを阻む要因です。職員間のITリテラシーに差があると、一部の職員に業務負担が偏り、業務が非効率になるリスクもあります。
防止策として、全職員を対象とした継続的な研修や、気軽に質問できるサポート体制の構築が欠かせません。人材育成には研修費用や指導に割く時間等の人的・時間的コストが発生する点も、あらかじめ考慮すべき重要なポイントです。

医療DXを促進する目的・必要性は、以下の4つです。
ひとつずつ解説します。
医療DXの目的の一つは、逼迫する医療現場の業務効率化と負担軽減です。日本の医療現場は、医師や看護師の長時間労働が常態化し、診断書作成やカルテ入力等の事務作業が原因です。
Web問診やAIによる文書作成支援を導入することで、作業を自動化・効率化できます。医療スタッフは本来の専門業務である患者ケアに、より多くの時間を充てられるようになります。DX化は、医療従事者の働き方改革を実現するうえで不可欠な手段です。
医療DXは、データ活用を通じて医療の質を向上させます。全国の医療機関で患者の診療情報や健診データを共有できる「全国医療情報プラットフォーム」が整備されることで、重複投薬や不要な検査を防ぎ、安全で効果的な医療の提供が可能です。
蓄積された膨大な診療データをAIで解析し、個々の患者に最適化された治療法の選択や、新たな診断技術の開発につなげます。経験と勘に頼る部分があった従来の医療から、データにもとづいた科学的な医療(EBM)への転換を加速させます。
医療DXは、病院経営の健全化につながります。紙や個別のシステムで管理されていた診療報酬(レセプト)データやコスト情報を一元化し、病院経営の状況をリアルタイムで「見える化」できます。
どの診療科がどれくらいの収益を上げているか、薬剤や医療材料のコストは適切かなどの分析が容易になり、データに基づいた客観的な経営判断が可能です。無駄をなくし、資源を重点分野に再配分するなど、より戦略的な病院経営が実現できます。
患者の利便性を高め、より良い医療体験(ペイシェント・エクスペリエンス)の提供も、医療DXの重要な目的です。スマートフォンのアプリで診療予約からWeb問診、会計まで完結することで、患者は院内での待ち時間を大幅に短縮できます。
また、オンライン診療の普及により、通院が困難な高齢者や遠隔地に住む人々も、質の高い医療サービスを受けやすくなります。患者中心の医療サービスの実現は、医療機関が地域社会で選ばれ続けるためには重要です。

医療DXの推進でシステムを導入するメリットは、以下の4つです。
それぞれ解説します。
医療DXのシステム導入のメリットには、業務効率化を通じた人材不足の解消が挙げられます。慢性的な人手不足に悩む多くの医療機関にとって、限られた人員で質の高いサービスを維持できる極めて有効な解決策です。
また、診療予約システムを導入することで電話応対業務が大幅に削減され、受付スタッフはほかの業務に集中できます。その結果、職員一人ひとりの負担が減り、離職率の低下につながる期待が持てます。
システム導入には初期投資が必要ですが、長期的には大きなコスト削減効果が見込めます。業務効率化による職員の残業時間減少は、人件費の抑制につながります。
最も分かりやすい例は、電子カルテ導入によるペーパーレス化です。主に、紙代や印刷代、カルテの保管スペースにかかる費用を大幅に削減できます。削減効果を積み重ねることで、システムの導入費用を十分に回収可能です。
待ち時間の短縮や会計の簡素化など、システム導入による利便性の向上は、患者満足度に直接結びつきやすいです。小さな改善の積み重ねが、「あの病院はスムーズで快適だ」といった良い評判を生み出します。
Web問診システムを導入することで、患者は来院前に自宅でゆっくり問診票を入力でき、院内での記入の手間が省けます。患者満足度の向上は、地域における医療機関の競争力を高め、将来的な増患につなげるために重要です。
医療DXにおけるシステムの導入は、診療の質を改善する効果をもたらします。最新の診療ガイドラインや医薬品情報をシステム上で確認できる機能も、日々の診療をサポートします。
たとえば、電子カルテを使うことで、医師は瞬時に患者の過去の病歴やアレルギー情報、検査結果を参照でき、より正確で安全な診断が可能です。医師が必要な情報に素早くアクセスできる環境の整備は、医療の質の均てん化と向上に不可欠です。

医療DX促進にかかるシステム導入コストの目安は、以下の4つです。
ひとつずつ解説します。
電子カルテは医療DXの中核をなすシステムで、導入コストも比較的高額です。院内にサーバーを設置する「オンプレミス型」とインターネット経由で利用する「クラウド型」で、異なります。
オンプレミス型電子カルテ | クラウド型電子カルテ | |
|---|---|---|
初期費用 | 300万円~500万円程度 | 0円~100万円程度 |
月額費用 | 2万円~5万円程度 | 1.5万円~5万円程度 |
クラウド型はオンプレミス型に比べて、導入コストを大幅に抑えられる特徴があります。
Web問診システムは、比較的低コストで導入でき、費用対効果を実感しやすいシステムです。主にクラウド型が普及しており、初期費用は「0円〜20万円程度」、月額費用は「1万円〜3万円程度」が相場です。
また、電子カルテと連携できるタイプや多言語に対応しているタイプなど、機能によって価格は変動します。スモールスタートでDXを始めたい場合、最初の選択肢として検討しやすいシステムです。
オンライン診療システムの費用は、機能やサポート体制によって価格帯が幅広い特徴があります。たとえば、初期費用と月額が「0円」から始められるものから、月額数万円以上の高機能なものまでさまざまです。
また、ビデオ通話機能のみのシンプルなものや、予約や問診、決済から処方箋配送まで一気通貫で対応できる高機能なものまであります。自院がオンライン診療で何を実現したいかを明確にし、必要な機能を備えたシステムを選ぶのが重要です。
診療予約システムも、比較的導入しやすいシステムです。初期費用は「0円〜30万円程度」、月額費用は「1万円〜5万円程度」が相場とされています。
診療予約システムを導入することで、WebサイトやLINEから24時間予約を受け付けられるようになり、患者の利便性向上と受付業務の効率化につながります。電子カルテやWeb問診システムとの連携機能の有無で価格が変わるため、将来的な拡張性も考慮して選ぶのが望ましいです。

医療DX促進のためのシステム導入に使える補助金制度は、以下の4つです。
それぞれ解説します。
IT導入補助金は、中小企業・小規模事業者の労働生産性向上を目的とし、ITツール(ソフトウェア、アプリ、サービス等)の導入費用の一部を補助する制度です。医療機関も対象で、電子カルテや予約システム、Web問診の導入に活用できます。
申請する枠(通常枠、インボイス枠等)で補助率や上限額が異なり、費用の1/2から最大で4/5が補助される場合もあり、非常に有用な制度です。
医療情報化支援基金は、厚生労働省が所管する、医療分野の情報化を推進するための基金です。電子カルテの標準化や、医療機関同士が安全に情報を共有・連携するネットワーク構築など、公益性の高い取り組みを支援対象としています。
補助対象事業や公募期間は年度で異なるため、厚生労働省のWebサイトで最新情報の確認が重要です。
出典参照:医療情報化支援基金等|厚生労働省
厚生労働省は、へき地医療の確保や感染症対策の観点から、遠隔医療(オンライン診療等など)の普及を推進し、設備導入を支援する補助金事業を実施しています。たとえば、オンライン診療をおこなうための情報通信機器(カメラ、マイク、モニターなど)の購入費用などが補助対象です。
初期投資のハードルが下がるため、より多くの医療機関がオンライン診療を導入しやすくなります。
出典参照:遠隔医療に関するホームページ|厚生労働省
国の制度に加え、各都道府県や市区町村が独自に医療DXを支援する補助金制度を設けている場合もあります。地域内の診療所を対象とした電子カルテ導入補助や、感染症対策のための設備投資支援等、内容はさまざまです。
各自治体における補助金の情報は、自院が所在する自治体のホームページや広報誌で告知されるケースも多いです。そのため、Web上で「(自治体名) 医療DX 補助金」などのキーワードで検索し、利用できる制度がないか調べてみるのがおすすめです。

医療DXでシステムの導入コストを抑えながら取り組む方法は、以下の6つです。
ひとつずつ解説します。
導入コストを抑えてDXを成功させるためには、「何のために、どの業務をデジタル化するのか」といった目的の明確化が重要です。いきなり全業務をDX化しようとすると、莫大なコストと時間がかかり、失敗のリスクも高まります。
たとえば「予約業務の電話応対を減らしたい」「紙の問診票をなくしたい」など、具体的な課題をひとつに絞り、小規模に始める「スモールスタート」が成功のポイントです。
導入システムの目的が決まったあとは、早い段階から利用できる補助金や助成金がないか、徹底的にリサーチしましょう。補助金には公募期間が定められており、「気づいたときには締め切られていた」という事態も少なくありません。
国の制度だけでなく、都道府県や市区町村、関連団体が提供する制度まで視野を広げ、常に最新の情報をチェックする習慣が大切です。
システム導入の初期費用を大幅に抑えたい場合、クラウド型システムの検討が有効な戦略です。たとえば、クラウド型は自前で高額なサーバーを購入・管理する必要がなく、月額利用料でサービスを利用できるため、導入時のコスト負担を大きく軽減できます。
システムのアップデートも提供者側でおこなわれるため、メンテナンスの手間やコストを削減できるメリットもあります。
医療DXを促進するシステムを選定する際は、必ず複数のベンダーから見積もりを取り、機能とコストを比較検討する「相見積もり」を実施しましょう。1社の話だけで決めてしまうと、割高な契約や、自院に合わないシステムを導入する場合もあります。
しかし、多くのクラウド型システムでは無料トライアルが提供されているため、実際に現場のスタッフが操作性を試し、自院の業務フローに合うかどうかの見極めが不可欠です。
導入するシステムが決まったあとは、目的や導入範囲、スケジュールや費用などを具体的にまとめた導入計画を策定しましょう。導入計画は、補助金を申請する際の事業計画書としても活用できるため重要なものです。
また、補助金の申請には計画書をはじめ、見積書など必要書類があります。システム導入時は、計画的な準備が、スムーズな申請と採択の可能性アップにつながります。
医療DXを促進するシステムは、導入して終わりではありません。定期的に、「導入による業務効率化の度合い」「目標通りのコスト削減」などの効果測定が重要です。
もし期待した効果が出ていない場合は、運用方法の見直しやベンダーへの改善相談が必要です。そのため、PDCAサイクルを回し続けることが、DXを真の成功に導きます。

医療業界でDX化を促進する際の注意点は、以下の4つです。
それぞれ解説します。
システム導入にあたり、初期費用や月額費用だけでなく、将来発生しうるコストも見据えた中長期的な視点の管理が不可欠です。たとえば、数年後のシステムのメジャーアップデートや、法改正に対応する追加費用が発生する場合もあります。
将来的な支出もあらかじめ予算計画に組み込むことで、安定した運用を続けられます。
システムの導入・運用において、患者の命と健康に関わる情報を守るため、常にセキュリティリスクを念頭に置く必要があります。厚生労働省のガイドラインに準拠した対策に加え、職員へのセキュリティ教育を徹底し、情報管理に対する意識を高く保つのが重要です。
万全のセキュリティ対策は、患者からの信頼を維持し、医療機関の社会的責任を果たすうえで最優先の課題です。
どれほど優れたシステムを導入しても、扱う職員が使いこなせなければ意味がありません。システム導入時の研修だけでなく、導入後も定期的な勉強会開催や、習熟度に応じたフォローアップ研修など、継続的な人材育成の仕組みが不可欠です。
職員一人ひとりがシステムを有効活用できて初めて、DXによる業務効率化が実現します。
DXを進めるうえで、院内と院外、両方のデジタル格差への配慮が必要です。院内では、PC操作が苦手な職員でも無理なく使えるよう直感的なインターフェースのシステム選定や、丁寧なサポート体制の整備が大切です。
医療従事者だけでなく、患者側にも、スマートフォンなどの操作に不慣れな高齢者がいることを念頭に置きましょう。オンラインだけでなく、従来通りの電話予約や対面での対応も継続するなど、誰一人取り残さない姿勢が求められます。

医療DXの推進には、システム導入コストの大きなハードルがあります。そのため、システム導入コストの負担軽減には、国や自治体などの補助金制度を徹底的にリサーチし、賢く活用するのがおすすめです。
また、いきなり大規模な改革を目指さず、自院の課題を明確化して解決につながるシステムから「スモールスタート」するのが望ましいです。推進の先には「業務効率化による負担軽減」や「医療の質の向上」等、計り知れないメリットがあります。自院で活用できる補助金の情報収集から始めましょう。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
