レガシーシステム統合で実現する医療DXのメリットとは?
医療

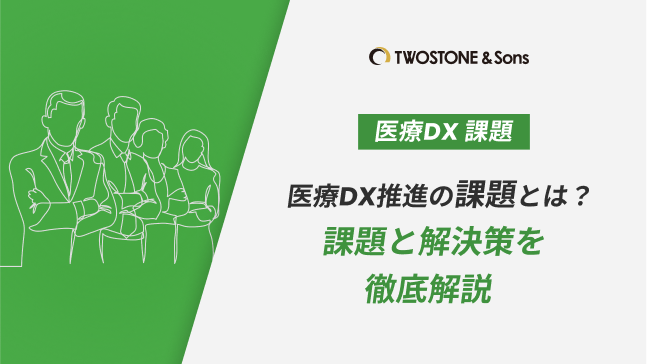
医療DX推進における課題とその解決策を徹底解説します。医療従事者不足、アナログ業務、ITリテラシーの低さなど、実際の成功事例を交えながら、効率化や改善に向けた具体的なアプローチを紹介します。
医療業界において、DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進は、効率的な医療サービスの提供と患者ケアの質向上に不可欠な要素となっています。しかし、多くの医療機関では、デジタル化の進展に伴いさまざまな課題が浮き彫りになっています。たとえば、医療従事者の不足、アナログ業務の残存、ITリテラシーの低さ、さらには初期投資の負担などが挙げられます。
これらの課題に直面している中、果たして医療DXはどのように進めるべきなのでしょうか?本記事では、医療DXを推進するための具体的な課題を取り上げ、その解決策を徹底的に解説します。
医療機関が抱える現実的な問題をどのように解決し、デジタル化を進めることができるのか、実際の成功事例を交えながら詳しく説明します。記事を読むことで、医療現場でのDX導入に必要な戦略や実践的なアプローチが明確になり、導入を一歩踏み出すためのヒントを得ることができます。
とくに、医療機関の経営層やDX推進担当者、医療従事者に向けて、今すぐ取り組むべき具体的な解決策を紹介します。デジタル化を進めるために何をすべきか、どういったツールを導入すべきかを悩んでいる方々には必見の記事です。

医療業界は、デジタル化の進展に対する大きな潜在能力を持っていますが、実現には多くの課題があります。これらの課題を克服することが、医療機関が効率的で質の高い医療サービスを提供し続けるためには不可欠です。
医療DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進には、ただのシステム導入にとどまらず、従業員の意識改革、業務の見直し、そして高額な初期投資を克服するための戦略が必要です。以下では、医療DXを進めるうえで直面する主な課題を具体的に解説します。
医療分野の人材不足は、とくに少子高齢化が進行する日本において深刻な課題です。2020年時点で、医師や看護師、その他の医療従事者が慢性的に不足しており、2040年には医療・福祉分野で約96万人の人材が不足すると予測されています。
この人材不足は、医療DXの進行を遅らせる要因のひとつです。限られた人員で効率的に業務をこなすためには、業務のデジタル化が必須です。とくに、電子カルテや診療記録のデジタル化により、医師や看護師が必要な情報を迅速に取得でき、業務負担を軽減できる可能性があります。
しかし、デジタル化を推進するには、従業員数の不足に加え、既存のスタッフに新たな業務を割り振ることに対する抵抗もあります。これを解決するためには、効率的な業務分担と、ITツールの積極的な導入が求められます。
日本の医療機関では、依然として多くの業務がアナログでおこなわれています。紙カルテや手書きの問診票、FAXでの情報やり取りなど、従来の方法に依存しているため、医療従事者の業務負担が増しています。
アナログ業務は、時間がかかり、エラーの発生リスクが高いという問題もあります。たとえば、紙カルテの記録や手書きの処方箋では、患者情報の確認に時間がかかり、また誤字や漏れが生じる可能性もあります。
さらに、紙の書類を手動で整理するため、物理的な管理に多大な労力がかかります。これを解消するためには、ペーパーレス化が不可欠です。電子カルテやオンライン診療の導入を進め、業務を効率化することで、医療従事者の負担を減らし、患者への対応を迅速に行えるようになります。
医療機関がDXを進めるためには、医療従事者がITツールやシステムを適切に活用できるようになる必要があります。しかし、現状ではITリテラシーの不足が深刻な課題です。とくに、高齢の医療従事者が多い施設では、デジタルツールの導入に対する抵抗感が見られます。
また、多忙な業務の中で、新しいシステムやツールを習得する時間が十分に確保できないため、導入しても使いこなせないケースが多いのが現状です。医療機関としては、デジタルツールを効果的に活用できるように、十分な教育とサポート体制を整えることが必要です。
具体的には、IT研修やマニュアルの充実、実践的なサポート体制を提供し、スタッフのITスキルを向上させることが、デジタル化を進めるうえで重要となります。
医療業界は他の産業に比べて、デジタル化の進展が遅れています。実際、医療機関のDXに取り組んでいる施設は全体の約9%にとどまり、他の業界に比べてかなり低い割合です。この遅れにはいくつかの要因があります。
まず、医療現場が持つ特有の複雑さや、患者情報の取り扱いに関する法的な制約が影響しています。また、デジタル化に必要な設備やシステムの導入には多大なコストがかかるため、予算的な制約を感じている医療機関も多いです。
さらに、医療従事者の間でデジタル化に対する理解や意識が足りないことも影響しています。医療DXを推進するためには、国の支援や補助金制度の拡充、さらには業界全体でのデジタル化の重要性に対する意識向上が必要です。
医療DXを進めるためには、高額な初期投資が必要です。電子カルテシステムや診療情報のデジタル化には、システム構築費用や機器の導入費用、運用のための人材教育費用などがかかります。
とくに中小規模の医療機関にとっては、これらの初期投資が大きな負担となり、導入をためらう原因となっています。また、投資に対するリターンがすぐに見込めない場合、経営者がその必要性を認識しづらいこともあります。
この問題を解決するためには、政府からの補助金や低利融資制度を活用し、初期投資の負担を軽減することが必要です。また、段階的に導入できるシステムを選定することで、コストを抑えつつデジタル化を進める方法も考慮すべきです。
医療DXを導入しても、その効果を実感しにくいと感じる医療機関が多いです。たとえば、オンライン予約システムや電子処方箋などは、長期的に見れば医療機関の効率化に貢献するものの、導入してすぐに目に見える効果を感じにくいことがあります。
とくに、診察時間の短縮や業務の効率化が少しずつ進むため、直後にはその効果がはっきりしないことが多いです。そのため、医療機関は効果を実感しやすい部分からDXを始め、段階的に進めていくことが有効です。
たとえば、キャッシュレス決済や予約システムの導入からスタートし、次に電子カルテやオンライン診療の導入を進めることで、医療従事者の負担軽減と効率化を感じやすくなります。
デジタル化が進む中で、患者情報を守るためのセキュリティ対策が一層重要になります。医療データは非常にプライバシーの高い情報であるため、サイバー攻撃やウイルスによる情報漏洩のリスクが高まります。
もし情報が漏洩すれば、患者の信頼を失い、医療機関の信用にも大きな影響を与える可能性があります。医療機関は、デジタル化を進めると同時に、高度なセキュリティ対策を導入し、データの保護を強化する必要があります。
たとえば、データの暗号化やアクセス権限の管理、ログ監視システムの導入などが求められます。
医療情報は個人の健康や病歴に関する機微な情報であり、その取り扱いには高度な個人情報保護が求められます。医療情報のデジタル化や共有には、個人情報保護法に加えて、医療特有のルールやガイドラインが必要です。
しかし、現行の個人情報保護法は医療分野に特化しておらず、具体的な運用に課題が残ります。このため、医療情報を適切に管理し、患者のプライバシーを守るための法的枠組みや規制がさらに強化されることが必要です。

医療業界は、デジタル技術を導入することで効率性やサービス品質を向上させる大きな可能性を持っていますが、多くの課題が存在します。
医療機関が抱える課題を解決するためには、医療DX(デジタルトランスフォーメーション)の導入が不可欠であり、その進行には適切な解決策が必要です。
ここでは、医療機関が直面する課題に対する具体的な解決策をいくつか紹介します。
ペーパーレス化は、医療機関の業務を効率化する最も効果的な方法のひとつです。医療現場で使用される紙カルテや処方箋、問診票、同意書などの紙媒体を電子化することで、書類の管理や情報の共有にかかる時間を大幅に削減することができます。
紙媒体を電子化することで、物理的な保管スペースの削減や、書類紛失のリスクを防止できます。さらに、タブレット端末を用いて患者情報を入力し、リアルタイムで医師や看護師と共有できる環境を整えることで、業務を迅速化することができます。
また、電子処方箋の導入により、薬剤師の処方箋確認時間や患者への薬歴説明を短縮することができ、全体的な業務の効率化が期待できます。結果的に、スタッフは患者により集中した対応ができるようになり、患者満足度の向上にも繋がります。
オンライン予約システムと問診システムの導入は、患者と医療機関の両方にとって大きなメリットがあります。患者が自宅や外出先からスマートフォンやPCを利用して、予約を取ったり、事前に問診票を入力したりできるため、医療機関の受付業務の負担が大きく軽減されます。
また、患者の待機時間も短縮され、医療機関でのスムーズな診察が可能となります。オンライン問診を通じて、患者の状態を事前に把握することができ、診察の効率化を図ることができます。
とくに、遠隔地に住む患者や高齢者にとっては、便利で迅速なサービスを提供することができ、医療機関のサービス範囲を広げることが可能です。さらに、患者の個人情報や過去の病歴を簡単にデータベース化でき、診察に役立てることができます。
AI(人工知能)は、医療業務の支援において非常に大きな可能性を秘めています。たとえば、AI事前問診ツールは、患者が記入した問診内容を解析し、医師の診察を効率化します。
結果的に、診察時間の短縮や、診察前に必要な情報を事前に把握することができ、医師の負担を軽減することができます。また、AIを活用した画像診断支援は、内視鏡やレントゲン画像を解析して病変の早期発見を支援します。
また、診断精度の向上と、医師が見落とすリスクの低減が期待できます。さらに、医療文書の作成支援においても、大規模言語モデル(LLM)を活用することで、診療記録や紹介状などの文書作成の時間を大幅に削減でき、医療従事者の負担を軽減することができます。AIによる業務支援は、医療機関の業務効率化と医師の負担軽減に大きく貢献します。
RPAは、定型的で時間のかかる事務作業を自動化する技術です。医療機関では、データ入力や情報移行などの作業が多く、これらをRPAで自動化することで、医療従事者はより専門的な業務に集中できる時間を確保できます。
たとえば、医療法人社団創福会ふくろうクリニックでは、RPAを導入して、旧電子カルテから新しい電子カルテへのデータ移行作業を効率化しました。これにより、手作業によるミスや遅延を防ぎ、医療現場での作業効率を大幅に改善することができます。
RPAは、業務の自動化だけでなく、スタッフの業務負担を軽減し、医療従事者が患者ケアに集中できる環境を作り出すことに貢献します。
タスクシフトとタスクシェアは、業務の効率化を目指して、業務分担の見直しをおこなう方法です。デジタル化を進めることで、業務が効率化され、医師や看護師はより高度な医療行為に専念できるようになります。
たとえば、事務作業や簡単な診療補助作業は、他の職種やシステムに移行させることができます。タスクシフトにより、スタッフのスキルを活かした業務分担が実現し、医師や看護師は専門的な医療業務に集中できるようになります。タスクシェアは、職種間の協力を促進し、チーム医療の質を向上させることにも繋がります。
医療機関では、非医療業務を外部に委託することが、業務の効率化に役立ちます。電話対応やメール対応、データ入力、オンライン診療のアフターケアなど、医療従事者がおこなうべきでない業務を外部の専門業者に委託することで、医療機関の負担を軽減できます。
これにより、医療従事者は診療に専念することができ、より多くの患者を対応することが可能になります。とくに、オンライン診療を実施している医療機関では、患者からの問い合わせ対応を外部に任せることが、医療現場のスムーズな運営に役立ちます。
医療機関でのITツール活用を促進するためには、医療従事者のITリテラシー向上が欠かせません。デジタルツールの導入に際して、医療従事者への十分な操作研修をおこない、活用事例を共有することが必要です。
また、IT人材の育成を進めることも重要です。医療機関内でDX推進を担う専門人材を確保することや、外部のDX支援サービスやコンサルタントを活用することで、デジタル化を効果的に進めることができます。
研修や人材確保に投資することは、医療機関のDX化を成功に導くための鍵となります。
クラウド型システムは、初期費用を抑え、運用の負担も軽減できるため、医療機関にとって非常に有益です。クラウド型システムは、オンプレミス型システムと比較して低コストで導入でき、システムのメンテナンスもベンダーに任せることができるため、医療機関のスタッフが管理負担を減らすことができます。
また、クラウド上にデータを保管することで、データのバックアップやリストアが簡単におこなえるようになり、災害時の対応力も強化されます。さらに、医療機関間でデータの共有が容易になり、医療の質を向上させることができます。
医療機関でのデジタル化が進む中、セキュリティ対策は最も重要な課題のひとつです。患者の診療情報は極めてプライバシー性が高いため、その取り扱いには厳格なセキュリティ対策が求められます。
データの暗号化、アクセス権限管理、ログ監視など、複数のセキュリティ対策を講じることが必要です。また、医療機関内で定期的なセキュリティ研修をおこない、スタッフの意識を高めることも重要です。
さらに、クラウドサービスを利用する場合は、契約前にセキュリティ対策が十分であることを確認し、信頼できるベンダーと契約を結ぶことが求められます。
オンライン診療は、医療現場の効率化と患者へのサービス向上に貢献する方法です。オンライン診療を導入することで、遠隔地に住む患者や高齢者に対しても、医療サービスを提供することができます。
診療報酬の見直しやインセンティブの充実によって、医療機関がオンライン診療を積極的に導入できる環境が整います。患者への周知活動をおこない、オンライン診療の利便性を説明することで、利用者の増加が期待できます。
また、デジタルサポートを提供することで、オンライン診療に不安を持つ高齢者などにもスムーズに利用を促進できます。

医療DX(デジタルトランスフォーメーション)を導入した医療機関の成功事例は、業務の効率化や診療の質向上に大きな効果をもたらしています。以下は、医療機関がどのようにデジタル技術を活用し、改善を実現した事例です。
日本赤十字社では、AIを活用した事前問診ツールを導入しました。患者が来院前に自宅などで問診票を入力できるシステムを提供し、AIが入力された問診内容を解析します。この取り組みは、医師の診察を効率化する目的で導入されました。
医師の負担軽減と診療効率の向上を実現し、患者の待ち時間短縮や診療回転率の向上にも寄与しています。AIを活用することで、患者にとっても医師にとっても負担が減り、よりスムーズな診療が提供されています。
出典参照:小児科、心臓血管外科でAI問診が利用できます|日本赤十字社
国立がん研究センターでは、NECと共同でAIを活用した内視鏡検査支援ソフトウェアを開発しました。このソフトウェアは、内視鏡検査時にリアルタイムで早期の大腸がんや前がん病変を発見する機能を持っています。
この取り組みの効果として、医師の見落としを防ぎ、がんの早期発見と早期治療の推進に貢献しました。診断精度の向上が図られ、医師の診断支援に大きな役割を果たしました。とくに、がんの早期発見は治療の成否に大きな影響を与えるため、この技術の導入は患者の命を守るうえでも非常に重要です。
出典参照:国立がん研究センターと日本電気株式会社が共同開発した内視鏡AI診断支援医療機器ソフトウェア「WISE VISION 内視鏡画像解析AI」医療機器承認|国立がん研究センター
東北大学病院では、日本語に対応した大規模言語モデル(LLM)を活用した医療文書作成支援システムを導入しました。医療従事者が電子カルテなどの情報を基に、診療記録や紹介状などの医療文書を自動で作成する実証実験をおこないました。
これにより、医療文書作成時間が47%削減されるという成果を上げました。医師が診療に専念できる時間が増え、働き方改革の推進にも大きく貢献しています。これまで時間をかけていた文書作成が効率化され、医師の負担が軽減されたことが、医療現場の改善に繋がりました。
出典参照:NEC、東北大学病院、橋本市民病院、「医師の働き方改革」に向けて、医療現場におけるLLM活用の有効性を実証 ~医療文書の作成時間を半減し、業務効率化の可能性を確認~ |東北大学病院
東京ミッドタウンクリニックでは、AIを用いて患者の疾病リスクを正確に予測するシステムを導入しました。このシステムは、個々の患者に合わせた予防医療の推進を可能にし、健康寿命の延伸に貢献しています。
予防医療の重要性が高まる中で、疾病リスクを事前に把握できるこのシステムは、患者の健康維持をサポートし、医療資源の無駄を減らすことに繋がっています。個別化された予防プランが提供され、患者にとってより最適な医療が実現される結果となりました。
出典参照:AI解析可能な新問診票が2020年中にスタートいたします|東京ミッドタウンクリニック

医療DXの推進は、効率的な医療サービスの提供と患者ケアの向上に不可欠ですが、導入には多くの課題があります。医療従事者の不足やアナログ業務の残存、ITリテラシーの不足、さらには高額な初期投資の負担など、さまざまな障害が存在します。しかし、これらの課題には実践的な解決策が存在します。
ペーパーレス化やオンライン予約システム、AIの導入、RPAの活用など、最新の技術を積極的に導入することで、業務の効率化や診療精度の向上が実現できます。また、タスクシフトや外部委託サービス、クラウドシステムの導入は、業務負担を軽減し、医療従事者がより高度な医療に集中できる環境を整えます。
さらに、IT人材育成やセキュリティ対策の強化も重要で、医療機関がDXを成功させるためには、適切な支援と体制整備が求められます。これらの解決策を講じることで、医療機関はDXを効果的に推進し、患者にとっても医療従事者にとってもより良い医療環境を提供することが可能です。
本記事を通じて、医療DXを進めるために必要な具体的なアクションや戦略を理解し、今後の取り組みをさらに強化できることを願っています。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
