レガシーシステム統合で実現する医療DXのメリットとは?
医療

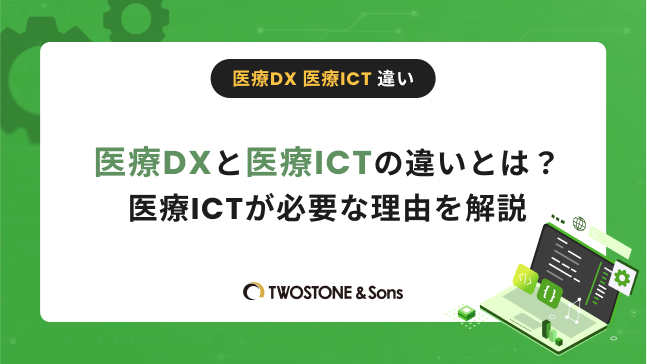
医療DX・ICTを促進するメリットには、業務効率化による働き方改革の実現や医療の質と安全性の向上、地域医療連携の強化などが挙げられます。この記事では、医療DXと医療ICTの違いや医療ICTが必要な理由までを紹介します。
医療DXは、ICTを駆使して医療の仕組み全体を変革して新たな価値を創造する目的であり、医療ICTは業務効率化の手段です。とくに、超高齢化社会や労働力不足に直面する日本の医療業界にとって、これらの取り組みは欠かせません。
本記事では、医療DXと医療ICTの違いや医療ICTが必要な理由までを解説していきます。医療DX・医療ICT化を促進するメリットや活用方法まで紹介しているため、ぜひ最後までご覧ください。

医療DXと医療ICTの違いについて、以下に紹介していきます。
それぞれ解説します。
医療DXとは、デジタル技術で医療の仕組みや文化を根本から変革し、新しい価値を創造する取り組みです。業務プロセスの一部電子化に留まらず、データ活用を基盤に質の高い医療サービスや効率的な運営体制の構築を目指す、広範な概念になります。
たとえば、収集した診療データのAI解析による、個別化された予防医療の提供は医療DXの具体例です。医療DXは技術導入による組織全体の変革です。
医療ICTとは、情報通信技術(Information and Communication Technology)を医療現場に導入し、既存の業務を効率化・自動化するための「手段」を指します。具体的には、電子カルテの導入による情報共有の迅速化や、Web予約システムの導入による受付業務の負担軽減などが挙げられます。
これらは、現在の業務をよりスムーズに進めるためのツールとして機能します。このように、医療ICTは特定の業務課題を解決するための具体的な技術やシステムの導入と活用に焦点を当てています。
医療ICTと医療DXは密接に関連しつつ、目指すゴールとスコープに明確な違いがあります。ICTは「手段」、DXはICTを用いて達成する「目的」です。以下の表で、両者の違いを比較していきます。
比較項目 | 医療DX (Digital Transformation) | 医療ICT (Information and Communication Technology) |
|---|---|---|
目的 | 新たな価値創造・組織全体の変革(目的) | 既存業務の効率化・自動化(手段) |
焦点 | データ活用を基盤とした組織・文化の変革 | ツールの導入・業務プロセスの部分的なデジタル化 |
具体例 |
|
|
関係性 | ICTを手段として活用して大きな変革を目指す | DXを実現する構成要素 |
電子カルテ(ICT)の導入は、業務の電子化です。データを地域医療連携や新しい治療法の開発に活用して初めてDXが実現できます。両者の違いの理解は、今後の医療のあり方を考えるうえで重要です。

医療業界でICT化が必要とされる理由は、以下の4つです。
ひとつずつ解説します。
将来的に超高齢化社会と生産年齢人口の減少に対応するためには、ICT化による業務効率化で限られた医療資源を最大限活用する必要が生じています。2040年に高齢者人口がピークに達し、医療・介護需要が急増する一方、支え手の現役世代は大幅に減少すると予測されます。
需給ギャップを埋めるには、ICT活用で医師や看護師の業務負担を軽減し、専門業務に集中できる環境整備が不可欠です。ICT化は、日本の医療が未来にわたり機能し続けるための鍵です。
出典参照:我が国の人口について|厚生労働省
ICT化による医療情報の正確で迅速な共有・活用は、ヒューマンエラーを防止し、データにもとづく質の高い医療を実現します。電子カルテは、患者の既往歴やアレルギー情報を瞬時に確認できるため、投薬ミスや重複検査のリスクを低減させます。
また、複数の診療科や医療機関での情報連携は、多角的で精度の高い診断・治療につながりやすいです。ICTは医療現場の安全性を高め、エビデンスに基づく医療を提供するうえで重要な基盤です。
医師や看護師の長時間労働が問題視されるなか、ICT化による業務負担の軽減は、医療従事者の働き方改革推進と離職防止に不可欠です。2024年4月開始の「医師の働き方改革」で時間外労働の上限規制が設けられましたが、業務の絶対量を減らさなければ実現は困難です。
ICT活用は、カルテ入力や書類作成の事務作業を自動化・効率化し、本来患者と向き合う時間を創出できます。医療従事者が心身ともに健康に働き続けられる環境整備は、医療の質維持に極めて重要です。
オンライン診療やPHR(Personal Health Record)の活用は、患者の主体的な健康管理への関与を促し、場所を選ばない医療アクセス環境を整備します。患者自身の健康への意識向上に加え、災害時や救急搬送時にも正確な医療情報を迅速に伝達できます。
またPHRは、個人の健康診断結果や服薬履歴をスマートフォンアプリで一元管理する仕組みです。ICTの活用は、患者中心の医療を実現し、健康寿命の延伸に貢献する可能性を秘めています。

医療DX・医療ICT化を促進するメリットは、以下の4つです。
それぞれ解説します。
電子カルテやWeb予約システムは事務作業を大幅に削減し、医療従事者が本来の専門業務に集中できる環境を作れます。たとえば、手書きや紙媒体のカルテ記録、検査データの転記、レセプト作成業務は多くの時間を要していました。
ICTによる業務の自動化・効率化は、医師や看護師が患者の診察やケアのような、付加価値の高い仕事に時間を使うことを可能にしています。また、組織全体の生産性が向上することで、質の高い医療サービスを提供できます。
待ち時間の短縮やオンラインでの情報提供、個別化された医療の提供は、患者の利便性と満足度を高められます。たとえば、Web予約や自動精算機の導入は、患者の院内滞在時間を大幅に短縮し、ストレスを軽減しやすいです。
また、オンライン診療は通院負担を無くし、マイナンバーカードによるオンライン資格確認は受付手続きを円滑にできます。ICTの活用は、患者本位のサービスを実現し、選ばれる医療機関となるために重要です。
地域医療情報連携ネットワークは、かかりつけ医と大病院の患者情報共有を円滑にし、地域全体で一貫した医療を提供して医療格差を是正できます。都市部と地方、医療機関間の情報の壁を無くし、どこに住んでいても質の高い医療を受けられる体制を整えられます。
たとえば患者さんが専門治療で大病院を受診する際、紹介状や検査データの電子的共有ができていると、重複検査を防止でき、迅速な治療開始にもつながります。ICTは、地域全体の医療の質の底上げにつながります。
質の高い医療ビッグデータの収集・解析は、創薬や新たな治療法の研究開発を飛躍的に進展させやすいです。電子カルテに蓄積された膨大な匿名加工医療情報の解析は、見過ごされてきた疾患の要因や、特定治療法が有効な患者層を明らかにする場合もあります。
さらに、開発期間の短縮やコスト削減が期待され、多くの患者を救う革新的な医薬品や治療法が生まれる土壌も育ちやすいです。医療データの活用は、未来の医療を切り拓く大きな力となります。

医療DX・医療ICT化を促進するデメリットは、以下の3つです。
ひとつずつ解説します。
デジタル化は、機微な個人情報である医療情報をサイバー攻撃や情報漏洩の危険に常に晒すため、高度なセキュリティ対策が必須です。医療情報は個人のプライバシーの中でもとくに慎重な取り扱いが求められ、一度流出すれば甚大な被害につながりかねません。
ランサムウェアによるサイバー攻撃で電子カルテが使用不能になり、診療停止に追い込まれた病院の事例も報告されています。システムの導入と同時に、堅牢なセキュリティ体制の構築が不可欠です。
新システム導入直後は、操作への不慣れによる業務の混乱や、研修など一時的な負担増が避けられません。とくに、長年慣れ親しんだ紙のカルテや業務フローからデジタルへ移行する過程で、多くの医療従事者が戸惑いを感じやすいです。
そのため、操作方法の習得や新旧システムの並行稼働期間は、業務負担を増加させる場合もあります。移行期を乗り越えるには、十分な研修期間の確保や、現場の意見を反映した丁寧な導入計画が求められます。
システムの導入には高額な初期費用がかかり、継続的な運用・保守にもコストが発生するため、中小規模の医療機関には大きな負担です。電子カルテシステムの導入には数百万から数千万円規模の投資が必要な場合も珍しくありません。
具体的には、サーバー維持費やソフトウェア更新費用、セキュリティ対策費のランニングコストも継続的に発生します。国や自治体の補助金制度はありますが、経営体力のない医療機関がICT化に踏み切れない大きな要因です。

医療ICT化の活用方法は、以下の5つです。
それぞれ解説します。
スマートフォンやPCを活用したオンライン診療は、通院困難な患者の医療アクセスを改善し、専門医が少ない地域での高度な診断を可能にします。へき地や離島の患者さん、身体的事情で通院が難しい高齢者も、自宅から専門医の診察を受けられます。
CTやMRI画像を専門医が遠隔で読影する「遠隔画像診断」も普及し、地域の診断能力向上にも役立てられています。ICTは、地理的制約を超えて医療を届ける強力なツールです。
出典参照:令和4年度診療報酬改定の概要 個別改定事項II(情報通信機器を用いた診療)|厚生労働省
電子カルテや電子版お薬手帳は、情報の参照性や共有性を高め、重複投薬の防止や災害時の医療提供に役立ちます。紙のカルテと異なり、必要情報を瞬時に検索・閲覧できるため、診療効率が格段に向上できます。
また、複数の医療機関や薬局で服薬情報が共有されることで、危険な飲み合わせや重複投薬を防止しやすいです。さらに、災害でカルテが消失しても、データがバックアップされていれば、避難先で継続的な医療を受けられる利点があります。
出典参照:薬局薬剤師DXの推進について|厚生労働省
RFID(無線自動識別)技術は、患者の取り違え防止や医薬品・医療機器の在庫管理を自動化し、医療安全と業務効率を向上させます。患者さんへのRFIDタグ付きリストバンド装着は、投薬や検査時の本人確認を自動化し、人為的ミスを防げます。
また、医薬品や医療機器へのタグ付けによって、棚卸し作業の瞬時完了や使用期限管理の徹底が可能です。RFIDは、目に見えない形で医療現場の安全性と生産性を支える技術です。
出典参照:群大病院における医療DX推進基盤・体制の重要性について|厚生労働省
複数の医療機関や介護施設が患者情報を共有するネットワーク構築は、地域全体で切れ目のない医療・介護サービスを提供しています。たとえば、患者さんは住み慣れた地域で、入退院を繰り返すことなく安心して療養生活を送れます。
また、病院退院後に在宅医療へ移行する際、病院主治医と地域の開業医、訪問看護師、ケアマネジャーが患者情報を共有することも可能です。地域包括ケアシステムの実現に向けて、ネットワークは中核的な役割を担っています。
出典参照:全国医療情報プラットフォームと地域医療情報連携ネットワークに関する論点|厚生労働省
AI(人工知能)による画像診断支援や診断・治療方針の提案は、医師の判断を補助し、精度の高い医療の実現につながります。たとえば、膨大なレントゲン写真や病理画像を学習したAIは、人間が見逃す微細な病変の発見を助けてくれます。
そのほか最新の論文や臨床データを解析し、個々の患者に最適な治療法の候補を提示することも可能です。AIは医師に取って代わる存在ではなく、能力を拡張し、良い医療判断を導く強力なパートナーです。

医療DX・医療ICTを促進する際の注意点は、以下の4つです。
ひとつずつ解説します。
流行を理由に技術導入するのではなく、自院の課題解決といった目的の明確化が成功のポイントです。たとえば「患者さんの待ち時間短縮」「病棟での情報共有円滑化」のような具体的課題を特定し、解決に最適な技術を検討するのが望ましいです。
また、目的が曖昧では導入システムが活用されず、費用対効果も得られません。あくまで技術導入は手段であり、課題解決という目的を見失わないことが肝要です。
システムの実際の使用者である医療従事者や、サービスを受ける患者の意見を聞かない導入は、システムの形骸化を招きやすいです。たとえば、経営層のみの導入決定は、現場の業務フローとの不一致や、操作の複雑化を招き、業務効率を低下させるリスクもあります。
導入計画の初期段階から、医師や看護師、事務職員といった多様な職種を巻き込み、意見交換を重ねるのが必要不可欠です。現場の納得感なくして、真のDXは成し遂げられません。
利便性追求で、セキュリティ対策を疎かにしてはなりません。国のガイドラインを遵守し、安全な情報管理体制を構築する必要があります。
どこからでも電子カルテにアクセスできる仕組みは便利ですが、不正アクセスリスクも高まるため事前に注意しておくのが重要です。具体的には、多要素認証の導入やアクセスログの監視、職員への定期的セキュリティ研修など、利便性と安全性の両立を図る対策が求められます。患者さんの信頼を損なわないため、セキュリティは最優先で取り組むのが望ましい課題です。
ITに不慣れな高齢者や、資金力のない小規模医療機関が取り残されないよう、丁寧なサポートや公的支援策が重要です。もしオンライン診療が普及しても、スマートフォンを持たない、操作できない高齢者は恩恵を受けられません。
また、ICT化を進める大病院と導入が遅れる診療所の間で機能差が拡大した場合、地域医療連携に支障をきたします。すべての人がデジタル化の恩恵を受けられるよう、社会全体でデジタルデバイド解消に取り組む視点が不可欠です。

医療ICTは業務効率化の「手段」、医療DXはICTを駆使して医療の仕組み全体を変革し、新たな価値を創造する「目的」です。超高齢化社会や労働力不足に直面する日本の医療では、これらの取り組みは不可避となります。
医療DX・ICTの促進は、業務効率化による働き方改革の実現や医療の質と安全性の向上、地域医療連携の強化などメリットは計り知れません。
重要なのは、技術導入自体を目的とせず、自院の課題解決といった明確なビジョンを持ち、現場の声を尊重して着実に歩むことです。医療DX・ICT化は、日本の医療の未来を支え、すべての人が質の高い医療を受けられる社会を実現する重要な一歩です。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
