レガシーシステム統合で実現する医療DXのメリットとは?
医療

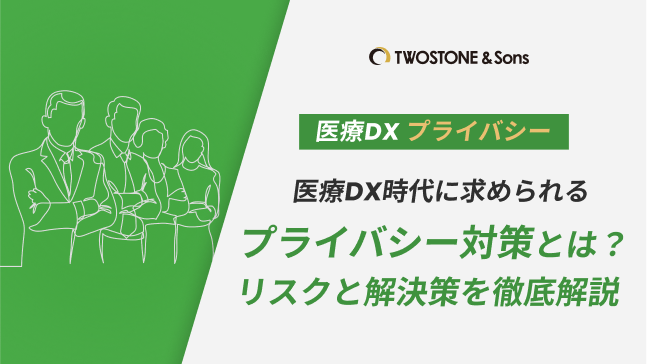
医療DXの進展に伴い、増す情報リスク。法令遵守、セキュリティ対策、スタッフ教育、患者同意取得など、医療機関が実践すべきプライバシー対策を徹底解説します。
電子カルテやオンライン診療など、医療現場におけるデジタル化が急速に進むなか、「本当に患者情報は守られているのか」と不安を感じる方も多いのではないでしょうか。
医療DXは業務効率や診療の質を高める一方で、情報漏洩やサイバー攻撃といった新たなリスクにも直面しています。
こうした時代において重要なのは、技術だけに頼らず、法令・運用・人の意識まで含めた総合的なプライバシー対策を講じることです。
この記事では、医療DXの普及に伴って高まるセキュリティリスクの具体例を挙げながら、その背景と必要な対策を段階的にわかりやすく解説します。法令遵守のポイント、患者への説明方法、多層的なセキュリティ対策、教育・運用体制の整備まで、実践的な解決策をご紹介します。
医療現場でプライバシー対策に関心を持つ医療従事者・情報管理担当者・院内DX推進担当の方々に、ぜひご一読いただきたい内容です。
読後には、「何を優先し、どう対処すべきか」が明確になるはずです。

医療DXの推進においては、プライバシー保護の課題に正面から向き合う必要があります。以下の5つのポイントに分けて、主な課題を整理します。
医療機関は、高度なサイバーセキュリティ対策を講じる必要があります。診療録や検査データなどには、患者の詳細な個人情報が含まれており、万が一流出すれば深刻な信頼失墜につながるためです。
近年では、ランサムウェア攻撃や内部不正による漏洩事例も報告されており、医療機関を狙った攻撃は年々巧妙化しています。ファイアウォールやウイルス対策ソフトに加え、侵入検知システムやゼロトラスト型のネットワーク設計など、多層的な対策が求められます。
個人情報の取り扱いに関しては、法令に則った厳格な運用が必要です。医療情報は「要配慮個人情報」に該当し、収集や保管、第三者への提供にあたっては、患者本人の明確な同意が前提となります。
また、電子カルテやクラウド型システムの活用が進む中でも、利用目的の明示、アクセス制限、ログ管理など、法的ルールを踏まえた対策を常に維持しなければなりません。
医療DXを推進する上で、データの利活用とプライバシー保護の両立が不可欠です。ビッグデータやAIによる診断支援、個別化医療などの精度を高めるには、質の高い医療データが必要になります。
一方で、患者の情報を保護するためには、匿名加工情報や仮名加工情報を用いて個人が特定されないよう工夫が求められます。共有範囲の設定や、ブロックチェーンを使った安全な連携手段など、技術的な工夫も必要になります。
情報の閲覧権限は、職務内容に応じて制限を設けることが大切です。医師、看護師、事務職員では、必要とする情報の種類が異なるため、一律の権限設定では安全性が担保されません。
役職や職務に応じてきめ細かくアクセス範囲を設定し、定期的に見直すことが求められます。退職や異動の際に、速やかに権限を変更・削除する運用も欠かせません。
プライバシー保護を支えるのは、現場の一人ひとりの意識です。いかに強固なシステムを導入しても、運用する人が無防備では情報流出のリスクは防げません。
職種を問わず、全職員に対して定期的なセキュリティ研修を実施し、電子メールの取り扱いや、インシデント発生時の対応方法について理解を深めることが重要です。実際の事例や模擬訓練を取り入れることで、現場に即した実効性のある教育が可能になります。

プライバシー保護に配慮した医療DXの導入は、医療機関にとってさまざまなメリットをもたらします。以下の5つの視点から、その効果を整理します。
プライバシー保護を徹底することで、患者との信頼関係が深まり、受診のきっかけをつくりやすくなります。医療情報の取り扱いに慎重である姿勢を示すことは、患者にとって非常に重要な判断材料です。
個人情報の漏洩を心配して受診をためらうケースもあり、特に性感染症や精神疾患などのセンシティブな分野では慎重な配慮が求められます。
たとえば、受付時にプライバシーの説明を丁寧に行う、診療内容が聞こえにくいように声のトーンを調整する、記録の保存先や閲覧者を限定するなど、細かな配慮が信頼の積み重ねにつながります。
患者の安心感を高めることで、継続的な通院や予防医療の活用にもつながり、結果として地域医療の質の向上にも貢献します。
セキュリティが担保された環境では、情報共有がスムーズになり、診療の正確性とスピードが両立します。
複数の医療従事者が一つの情報にアクセスすることで、チーム医療の連携が円滑になり、ミスや伝達漏れを防ぐ効果があります。
プライバシーに配慮したアクセス管理を導入していれば、閲覧できる範囲が明確になり、関係者以外による誤操作や不正閲覧の防止にもつながります。
具体的には、アクセスログを常時記録し、定期的に監査を行うことで、異常な操作を即座に検知できます。また、クラウド型の電子カルテを導入すれば、他院との連携や在宅医療にも対応しやすくなります。
診療の質と作業の効率性が高まることで、限られた人員での医療提供にも柔軟に対応できます。
プライバシーを守りながら医療データを分析することで、新たな医療技術の開発や疾患予測モデルの構築が進みます。
医療DXでは、仮名加工情報や匿名加工情報といった形で個人情報を保護しつつ、大量の診療データを利活用することが可能になります。これにより、AIによる病状予測、新薬開発、治療効果の可視化などが進展しています。
たとえば、がんの罹患傾向や生活習慣病の進行パターンをAIが解析することで、症状が出る前の段階での対応が期待されます。また、予後の予測にも活用されており、患者ごとの治療計画の個別化にも貢献しています。
データの活用は、プライバシー保護とのバランスが求められる分野ですが、ルールと技術を両立させることで、革新が継続的に進む環境を整えることができます。
プライバシー保護に積極的に取り組む姿勢は、医療機関の社会的評価を高める重要な要素となります。患者に対してはもちろん、行政や業界団体からも「信頼できる施設」として評価される基盤が整います。
サイバー攻撃の標的となりやすい医療業界では、事故が発生すれば多大な損失が発生する可能性があり、事前の対策が評価指標の一つとして重視されるようになっています。
実際に、ISO27001(情報セキュリティマネジメントシステム)の認証取得や、厚労省が示す「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に準拠した体制づくりは、ブランド力の強化につながります。
患者からの信頼を得るだけでなく、優秀な医療従事者の採用や企業との連携においても、プライバシー対策の有無が選定基準となることがあります。
プライバシー保護が徹底されている環境では、医療従事者が情報漏洩の不安から解放され、診療や業務に専念しやすくなります。
特に電子カルテやクラウドシステムの活用が進むなかでは、セキュリティ事故が発生すると、責任追及や風評被害などによって精神的な負担が増す可能性があります。予防的に強固な仕組みが整っていれば、安心して日常業務を進めることができます。
たとえば、在宅医療や訪問診療の場面では、モバイル端末から安全にアクセスできる仕組みがあると、現場の判断スピードが向上します。また、職員がセキュリティ意識を共有していれば、内部不正やヒューマンエラーのリスクも低減できます。
従業員が安心して働ける環境づくりは、結果として医療の質の維持や人材の定着にもつながります。

プライバシー保護を強化するには、組織全体で明確な対策を講じる必要があります。以下のような複数の取り組みを組み合わせることが、医療DXにおける安全な情報管理の基盤となります。
セキュリティ対策を機能させるには、組織全体として明確な基本方針と管理体制を定めることが欠かせません。個別の対策を導入するだけでは、属人的な対応になり、リスクが見過ごされる恐れがあります。全体で共通認識を持つには、セキュリティポリシーやマニュアルの作成、組織内の責任体制の明文化が必要です。
例えば、情報セキュリティ管理規程を整備し、院内LANの運用方針やUSBメモリの持ち出しルールなどを明記することで、現場での判断のばらつきを防げます。
加えて、情報セキュリティ委員会を設置し、方針の見直しや実施状況の確認を定期的に行うことも重要です。全員が方針を理解し、自身の役割を把握している状態が、安定したセキュリティ運用の土台になります。
外部からの侵入や盗聴に備えて、患者情報は保存時と送信時の両方で暗号化して扱う必要があります。医療機関では、検査会社・調剤薬局・他院などとの連携が日常的に行われるため、第三者の通信傍受や中間者攻撃への対策が求められます。
保存時にはAES256などの暗号化方式を使用し、サーバーのハードディスク全体を暗号化する「フルディスク暗号化」も有効です。送信時には、TLS1.2以上の通信プロトコルの採用が望ましく、内部ネットワークでもVPNの導入が推奨されます。
さらに、メール添付ファイルにはパスワード付きZIPを避け、ワンタイムURLなどセキュリティの高い共有方法を採用することもポイントです。暗号化の設定状況は定期的に確認し、アップデートに対応することが欠かせません。
アクセス制御の強化によって、内部不正や操作ミスによる情報漏洩のリスクを最小限に抑えられます。すべての職員に同じ権限を与えてしまうと、過剰な情報閲覧や誤操作が起こりやすくなります。個人の職務に応じて、業務に必要な範囲の情報だけにアクセスできるよう制限を設けることが重要です。
たとえば、看護師は診療記録を閲覧できても、保険証情報や請求データにはアクセスできないように設定します。加えて、多要素認証を導入し、ID・パスワードに加えワンタイムコードや生体認証を組み合わせれば、不正ログインの防止にもつながります。
アクセス権は人事異動・退職時に即時見直しが必要であり、運用体制と自動化の仕組みがあると安全性と効率性の両立が図れます。
医療機関のシステムは常に外部からの攻撃にさらされており、脆弱性は時間とともに変化します。定期的にセキュリティの状態を点検し、脆弱性を早期に発見・修正する体制が必要です。問題を放置すれば、古いソフトウェアの脆弱性を突かれた侵入や、内部設定ミスによる情報流出が発生するおそれがあります。
具体的には、年2回以上の脆弱性スキャン、OSやソフトウェアのアップデート、セキュリティログの定期分析を通じて、リスクを事前に特定する方法が効果的です。加えて、外部専門家によるセキュリティ監査の実施も有効です。定期点検の内容と結果は記録に残し、次回対策の参考として活用することが望まれます。
システム障害や自然災害など、予期せぬ事態にも診療を継続できるよう、データ保全と復旧計画を整備することが不可欠です。特に電子カルテが中心となる医療DXでは、システム停止=診療停止につながるため、早期復旧とデータの保全は最優先課題といえます。
対策としては、オンサイト(院内)とオフサイト(外部)の両方に定期的なバックアップを保存し、遠隔地サーバーによる二重管理が望ましいです。加えて、BCP(事業継続計画)を策定し、災害時における代替拠点・職員連絡網・データ復旧手順などを明文化します。
実際に復旧訓練を行い、マニュアルが機能するか検証することも大切です。
インシデントが発生した際に迅速かつ適切に対応できるよう、対応手順を事前に整えておく必要があります。医療機関は患者の生命や健康に直結する業務を担っており、情報漏洩・改ざん・サイバー攻撃などのトラブルは深刻な影響を及ぼします。
対応の基本は「初動対応→調査→通知→再発防止」の流れを明確にし、関係部署・外部業者・監督官庁・患者への報告の順番と方法を決めておくことです。緊急連絡網の整備と訓練も重要です。
報告義務のある内容や期間は法律やガイドラインで定められているため、法務部門や外部顧問との連携も欠かせません。初動対応の速さが信頼回復にも直結します。
クラウドの利便性を活かしながら、安全性を確保するには、事前に明確なセキュリティ基準を設定することが大切です。医療情報をクラウドに保存する場合、データの保管場所、冗長性、監査ログの有無、アクセス制御など、運用面での要件を契約前に確認する必要があります。
たとえば、ISO27001やISO27799といった国際認証を取得しているクラウドベンダーを選定し、SLA(サービスレベル合意)に障害対応やデータ返却義務などの内容を盛り込むことが望ましいです。
また、サービス終了時のデータ削除ルール、メンテナンス中の対応、アクセス権限の委譲可否といった細部まで基準を定めることで、安全なクラウド運用が可能になります。
データ活用を推進する際には、個人を特定できない状態に加工することで、プライバシーへの影響を抑えながら活用の幅を広げることができます。医療機関では、研究・統計・業務改善などの目的で患者情報を分析する場面が増えていますが、匿名性が担保されなければ情報の活用には限界があります。
仮名加工情報は一部特定可能性を残しつつ業務内での共有に使われる情報であり、匿名加工情報は第三者への提供も可能です。データ加工の際は「識別性の除去」「結合リスクの評価」「利用目的との整合性確認」が重要です。
加工方法は統計的手法やマスキング、データシャッフルなどがあり、第三者検証も行うことで透明性を保つことができます。

医療DXにおいてプライバシーを守るためには、技術的・組織的・人的な視点を組み合わせた多面的な取り組みが欠かせません。以下の5つのポイントを軸に進めることが効果的です。
プライバシーを守るには、常に進化するサイバー攻撃に対応できる技術を積極的に取り入れることが重要です。従来のセキュリティ対策だけでは不正アクセスや情報漏洩を防ぎきれないケースも多く、医療機関は高度な技術を導入する必要があります。
暗号化、アクセス制御、ログ監視、多要素認証に加え、最近ではゼロトラストネットワークやEDR(エンドポイント検出と対応)といった仕組みが注目されています。
たとえば、ログイン時に複数の認証要素を確認することで、パスワードの漏洩リスクを大幅に軽減できます。技術選定の際は、自院の体制や予算に合わせて柔軟に取り入れることが求められます。
プライバシー保護を徹底するには、現場任せではなく組織全体で共通のルールを整えることが不可欠です。属人的な対応では情報管理にばらつきが生じ、リスクの把握や対策が困難になります。情報セキュリティポリシーを明文化し、誰が何をどのように扱うかを明確にする必要があります。
さらに、セキュリティ責任者の配置、監査体制の整備、インシデント発生時の対応計画なども事前に用意しておくと、迅速かつ正確に対応できます。定期的な訓練や点検も不可欠で、システム更新時や業務変更時にはポリシーを見直す習慣づけが求められます。
情報漏洩のリスクを抑えるには、スタッフ一人ひとりが「自分ごと」としてセキュリティを捉える意識が必要です。どれだけ高機能なセキュリティシステムを導入しても、操作ミスや内部不正が起これば意味がありません。定期的な研修や勉強会を通じて、日常業務に潜むリスクと対処法を共有しておくことが大切です。
特に注意すべきなのが、フィッシング詐欺や不審メールへの対応です。職員が安易にリンクをクリックしてしまうと、外部攻撃者に情報が抜き取られる可能性があります。
事例を交えた教育や疑似攻撃による訓練など、実践的な対策が効果的です。
患者の理解と信頼を得るには、情報の使い方や保管方法を丁寧に説明し、本人の同意を適切に得ることが大切です。医療データは非常にデリケートな情報であり、患者にとっては「どう使われるのか」がわからないままでは不安に感じてしまいます。
どの範囲の情報を、どの目的で、どこまで共有するのかを、わかりやすい言葉で伝えることが求められます。専門用語の多用は避け、図や例を使って説明すると理解が深まりやすくなります。
同意のプロセスは一度で終わらせず、変更や撤回の権利についても併せて説明する姿勢が信頼構築に効果的です。
プライバシー対策を形骸化させないためには、定期的に運用状況を見直し、新しい脅威に対応する姿勢が欠かせません。サイバー攻撃の手法は日々進化しており、導入当初に設計した体制が1年後も有効であるとは限りません。最新のリスクに備えるには、常に情報を収集し、改善を積み重ねていくことが求められます。
たとえば、新しいランサムウェアの動向や行政からの通達をもとに、システム構成やポリシーの更新を行う必要があります。加えて、ヒヤリ・ハットの共有など日常業務の中での気づきを全体で反映できる体制が理想的です。現状維持ではなく、変化に対応できる柔軟性こそが、プライバシー保護を続ける上での基盤になります。

医療DXにプライバシー保護の視点を組み込む際は、技術的・法的・組織的な観点からいくつかの注意点を押さえる必要があります。以下の5つのポイントを中心に対策を進めることが重要です。
プライバシー保護を適切に行うには、関係する法令や行政指針を正確に理解し、遵守する姿勢が欠かせません。医療情報は「要配慮個人情報」に分類され、一般的な個人情報よりも厳格な扱いが求められています。取得や利用の際には、本人の同意が必要であり、目的外利用の制限や保管ルールも明確に定められています。
たとえば、個人情報保護法では利用目的の明示や開示請求への対応義務があり、違反した場合は罰則が科される可能性もあります。また、厚生労働省の「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」は、医療機関が取るべきセキュリティ措置の参考になります。
医療法や医師法、さらには電気通信事業法なども関係する場面があるため、複数の法令を横断的に理解し、施設ごとに対応策を整理することが必要です。
出典参照:医療情報システムの安全管理に関するガイドライン|厚生労働省
情報の扱いについては、患者に対して事前に丁寧な説明を行い、理解と納得を得たうえで同意を得るプロセスが非常に重要です。診療の信頼関係は、情報の透明性と本人の理解に支えられています。情報共有が進む中、患者自身が何のためにどのような情報を提供するのかを明確に理解していなければ、不安や拒否感を抱かれることがあります。
説明は専門用語を避け、パンフレットや図解なども活用し、視覚的に伝える工夫が有効です。また、説明後にすぐサインを求めるのではなく、質問に答える時間を設け、必要に応じて再説明を行う柔軟さも必要です。さらに、同意には撤回の権利があることを明示し、撤回手続きも明文化しておくことで、患者の安心感を高めることができます。
情報漏洩を防ぐには、単一の対策では不十分であり、複数の対策を重ねて運用する「多層防御」の考え方が有効です。医療機関では、内部不正・外部攻撃・システム障害など、さまざまなリスクが存在します。
ファイアウォールやウイルス対策ソフトに加えて、侵入検知システム(IDS/IPS)やゼロトラストネットワークの構築など、段階的な防御策が求められます。アクセス制御では、職種や役職に応じて閲覧可能な情報を制限し、アクセスログを記録することが基本です。
また、データは通信時だけでなく、サーバー保存時にも暗号化する必要があります。システム導入後も定期的な脆弱性診断や第三者機関によるセキュリティ監査を通じて、リスクの変化に対応することが重要です。これらを継続的に運用する体制を整えることが、安定したプライバシー保護につながります。
セキュリティリスクを抑えるためには、システムそのものよりも「使う人」の意識と行動が大きく影響します。現場で働く医師、看護師、事務職員が情報セキュリティの重要性を理解していなければ、どれだけ強固なシステムを導入しても意味がありません。
定期的な研修を通じて、個人情報の取り扱い方法、持ち出しルール、不審メールへの対応などを実践的に学ぶことが必要です。特に、標的型攻撃やフィッシング詐欺など、巧妙な手口が日々進化しているため、最新情報を踏まえた教育が効果的です。
また、部署ごとに責任の所在を明確にし、「自分の行動がリスクになるかもしれない」という意識を浸透させることが求められます。
情報漏洩やシステム障害が起きた際に混乱を防ぐためには、事前に対応体制を整えておくことが不可欠です。医療機関では、万が一のトラブルが診療の停止や患者の不信感につながるため、スムーズな初動対応が求められます。
緊急連絡網の整備や、各部署の担当者とその役割を事前に決めておくことで、混乱を最小限に抑えることができます。さらに、トラブル発生時の対応フローを文書化し、定期的に訓練を行うことで、実際の場面でも迷いなく行動できます。調査や報告、説明責任の遂行、そして再発防止策の策定までを含めた一連の流れを確立しておくことが、継続的な信頼維持に欠かせません。

医療DXの進展に伴い、患者情報の利便性が高まる一方で、情報漏洩やサイバー攻撃といったリスクも増加しています。こうした背景から、法令やガイドラインの遵守に加え、多層的なセキュリティ対策、職員への教育、患者への丁寧な説明と同意取得、そしてトラブル対応体制の整備が求められています。
テクノロジーだけでなく、運用や人の意識も含めた総合的な視点から対策を進めることが、安心・安全な医療の提供につながります。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
