レガシーシステム統合で実現する医療DXのメリットとは?
医療

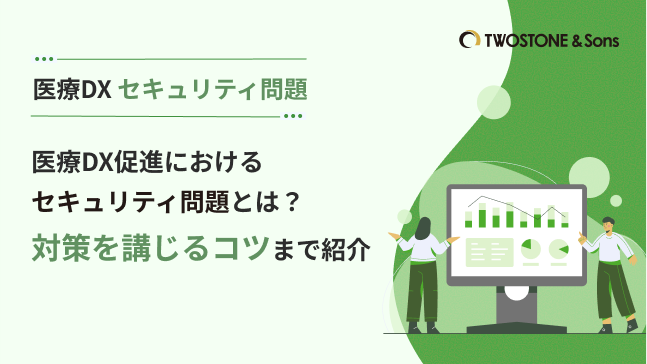
医療DXにおけるセキュリティ対策は、患者の信頼獲得や安定した経営維持、安全な医療提供のための経営中心課題です。この記事では、医療DX促進におけるセキュリティ問題や対策を講じるコツまでを紹介します。
医療DXにおけるセキュリティ対策は、「患者の信頼獲得」「安定した経営維持」「安全な医療提供」を促進するための経営が中心となる課題です。
本記事では、医療DX促進におけるセキュリティ問題や対策を講じるコツまでを解説していきます。医療DXに欠かせないプライバシー保護の重要性まで紹介しているため、ぜひ最後までご覧ください。

医療DXについて、以下に紹介していきます。
それぞれ解説します。
医療DXは医療現場へのデジタルツール導入に留まりません。データとデジタル技術の駆使で、医療サービスの質、効率、患者体験を根本から変革します。
未来の医療に新たな価値を創造する国家的な取り組みです。患者一人ひとりの医療体験向上と、多忙な医療従事者の負担軽減、働き方改革という二つの目的達成を目指します。
医療DX推進には、電子カルテ情報の標準化やオンライン診療導入が進みます。全国の医療機関で医療情報をスムーズに連携させ、患者がどこでも質の高い医療を受けられる体制を構築します。
「全国医療情報プラットフォーム」の創設、どこでも正確な診療情報が確認できる「電子カルテ情報の標準化」、煩雑な請求業務を効率化する「診療報酬改定DX」が三本柱です。多角的なアプローチが医療現場の変革を確実に進めます。

医療業界の抱える課題は、以下の4つです。
ひとつずつ解説します。
医療現場は深刻な人材不足に直面し、業務効率化が喫緊の課題です。特定の診療科や地域での医師偏在、高齢化社会の進展に伴う看護師や介護職員の需要急増が、人材不足を深刻化させます。
医療従事者一人ひとりの負担軽減と質の高い医療維持には、テクノロジー活用による効率的な業務遂行が求められます。
多くの医療機関は、紙カルテやFAX等アナログな手法が業務の中心で、デジタル化の大きな障壁です。新しいシステム導入の多額なコスト、職員へのITツール教育の遅れが原因です。
電子カルテの普及が進む一方、中小規模の診療所では導入が未整備な場合も多いです。情報共有の遅延や転記ミスなど、非効率な業務プロセスが残り、DXの恩恵を十分に受けられていません。
デジタル化の遅れは、医療従事者の長時間労働を招く一因です。手書きの書類作成、電話やFAXによる部門間の情報伝達は、多くの時間的ロスを生みます。
患者情報の他部門への共有は、システム化されていれば瞬時に完了しますが、手作業は多くの手間と時間を要します。非効率な情報共有や煩雑な事務作業の積み重ねは、患者ケアの時間を圧迫し、職員の過重労働を招く問題です。
度重なる診療報酬改定、近年の物価・光熱費高騰は、多くの医療機関の経営を圧迫する要因です。そのため、医療の質維持・向上には、最新の医療機器や医薬品への投資が不可欠です。
医療機関の収入は伸び悩み、支出は増加の一途をたどります。全国公私病院連盟の調査は、多くの病院が赤字経営に苦しむ状況を報告しています。厳しい経営環境を乗り越えるには、医療DXによる業務効率化とコスト削減が極めて重要です。
出典参照:令和6年病院運営実態分析調査の概要(令和 6 年 6 月調査)一般社団法人 全国公私病院連盟 調査報告および要望書等| 全国公私病院連盟
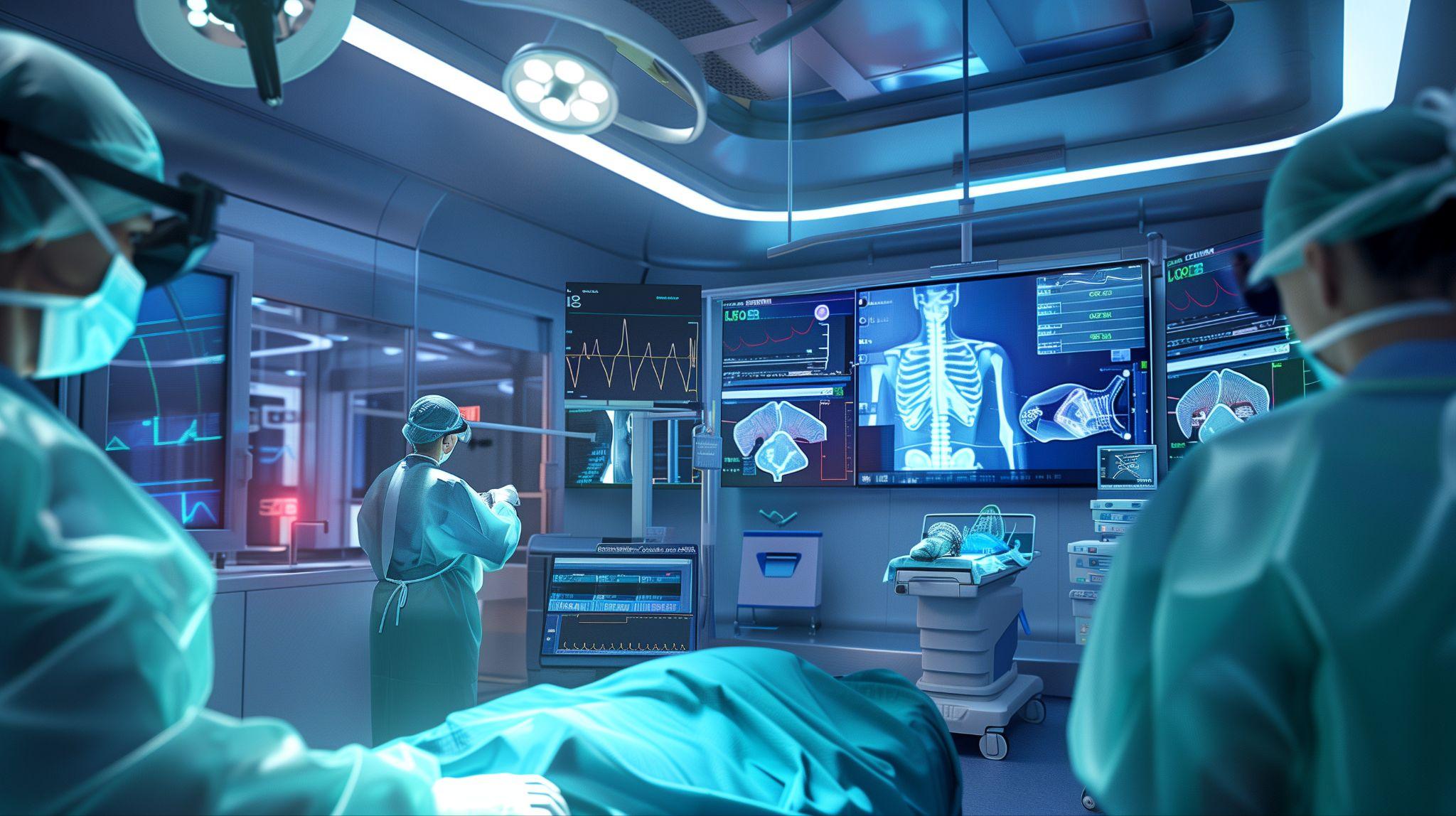
医療DXが進まない理由である【セキュリティ問題】について、以下に紹介していきます。
それぞれ解説します。
近年、医療機関を標的としたサイバー攻撃、特にランサムウェアによる被害が増加傾向にあり、セキュリティの脅威は極めて身近な問題です。医療情報は金銭的価値が高いとされ、人命に関わる業務を停止させることで身代金の支払いを要求しやすいため、攻撃者の標的になりやすいと考えられます。
警察庁の報告では、ランサムウェア被害の報告件数が高水準で推移し、医療・福祉分野の被害も多数含むと示しています。どの医療機関も攻撃を受ける可能性があるという課題が浮き彫りになります。
出典参照:サイバー事案の被害の潜在化防止に向けた検討会報告書2023 令和5年3月
医療DX促進において、最も懸念される点は、患者の生命やプライバシーを直接脅かす事態に発展する危険です。医療機関のセキュリティインシデント発生は、システム停止に留まりません。電子カルテが閲覧不能になると、正確な診断や治療が困難になり、医療過誤の恐れがあります。
また、病歴や遺伝子情報等、機微な個人情報の漏洩は、患者に計り知れない精神的苦痛や社会的差別を与える場合もあります。医療のセキュリティインシデントは、経営的損失以上に、患者の安全と尊厳を根底から揺るがす深刻なリスクです。
セキュリティインシデントは、全ての医療機関に関わる問題です。2021年、徳島県のつるぎ町立半田病院はランサムウェア攻撃を受けました。
電子カルテシステムが暗号化され、約2ヶ月間、通常診療がほぼ停止しました。新規患者の受け入れ停止、紙カルテによる限定的な診療を余儀なくされ、地域医療に甚大な影響をおよぼしました。
十分なセキュリティ対策を講じなければ、どの医療機関でも同様の被害に遭う可能性を示す重要な教訓です。
出典参照:コンピュータウイルス感染事案有識者会議調査報告書について|つるぎ町立半田病院

医療DXを安全に進めるには、一般的な情報セキュリティ対策以上の厳格なプライバシー保護が求められます。医療情報には、以下のような個人の尊厳や人生設計に深く関わる「要配慮個人情報」を数多く含みます。
個人情報が漏洩・悪用されると、就職や保険加入での不当な差別など、取り返しのつかない被害を生む場合もあるため注意が必要です。医療機関は個人情報保護法にもとづき、個人情報をとくに慎重に取り扱う法的・倫理的義務を負います。
そのため、医療DXの推進は、患者のプライバシーを最高レベルで保護する大前提のうえに成り立ちます。

医療DXでセキュリティ問題に取り組むメリットは、以下の6つです。
ひとつずつ紹介します。
セキュリティ対策へ真摯に取り組む姿勢は、患者からの信頼獲得につながります。自分の大切な命と個人情報を預ける患者にとって、病院の安全対策への注力度は、病院選びの判断基準です。
情報漏洩などのニュースが頻繁に報じられる現代、「あの病院なら安心してかかれる」という評判は、何物にも代えがたいブランドイメージを構築します。セキュリティへの投資は、患者に選ばれる病院となるためには重要です。
適切なセキュリティ対策の実施は、インシデント発生による経営リスクを低減させ、安定した病院経営の土台を築きます。もしサイバー攻撃を受けた場合、以下のようなリスクが生じる場合もあります。
将来にわたり持続可能な経営を実現するには、予期せぬリスクを事前に回避する対策が極めて重要です。
自院のセキュリティレベル向上は、地域全体の医療の質向上にも貢献します。安全な情報連携基盤がなければ、近隣の病院やクリニック、介護施設との間で患者情報をスムーズに共有する「地域医療連携」は成り立ちません。
たとえば、救急搬送された患者の情報を連携先病院が即座に確認できると、より迅速で的確な処置が可能です。自院のセキュリティ強化は、地域医療ネットワークの信頼性を高め、より安全で質の高い医療を提供するうえで重要な役割を果たします。
堅牢なセキュリティ基盤の整備は、より先進的なデジタル技術導入の前提条件です。AIによる画像診断支援システムや、患者の状態を遠隔でモニタリングするIoT機器など、革新的なテクノロジーは大きな可能性を秘めますが、同時に新たなセキュリティリスクも伴います。
情報漏洩やシステム乗っ取りの不安なく、先進技術を安心して活用できる環境整備が、自院の競争力を高め、患者により良い医療を提供していくポイントです。
組織全体でのセキュリティ対策への取り組みは、職員一人ひとりの意識と知識を向上させる絶好の機会です。全職員を対象とした研修の実施や、分かりやすいルールの策定・共有を通じて、「セキュリティは自分ごと」といった意識をつくりだせます。
技術的対策(外的セキュリティ)に加え、職員の意識(内的セキュリティ)向上は、うっかりミスによる情報漏洩等のヒューマンエラーの防止が可能です。働く環境の良い循環が、組織全体の総合的な防御力を高めます。
セキュリティ対策の実施は、実効性の高いBCP(事業継続計画)強化に不可欠です。サイバー攻撃は、地震や水害等の自然災害と同様、病院の事業継続を根底から脅かす重大なリスクです。
万が一のシステム停止時に診療を継続し、迅速に復旧させる計画を立てるのが重要です。たとえば、対応計画にサイバー攻撃を明確に位置づけ、具体的な手順を定めることで、患者の命と病院の機能を守ることにつながります。

医療DXを促進した医療機関の事例は、以下のとおりです。
それぞれ紹介します。
ペーパーレス化は、医療DXの身近な第一歩で、大きな効果が期待できる取り組みです。愛知県の刈谷豊田総合病院は、院内で使用される約1,800種類の帳票の電子化・ペーパーレス化を推進しました。
結果的に、紙の印刷や保管、運搬にかかるコストと手間が大幅に削減され、承認プロセスも迅速化されました。職員は煩雑な事務作業から解放され、より専門性が求められる本来の業務に集中できる環境を実現しています。
出典参照:医療法人豊田会 刈谷豊田総合病院のワークフローシステム導入事例|株式会社エイトレッド
岩手県の湯田内科病院もまた、ペーパーレス化によって業務効率を飛躍的に向上させた事例です。同院では、勤怠管理や各種申請業務などを電子化し、院内の情報共有基盤を整備しました。
その結果、従来は紙ベースでおこなっていた回覧や承認作業がなくなり、情報伝達のスピードと正確性が格段に向上しました。職員間のスムーズな連携が可能になったことで、組織全体の生産性が高まり、患者サービスの向上にもつながっています。
出典参照:医療法人健誠会 湯田内科病院のワークフローシステム導入事例|株式会社エイトレッド
オンライン資格確認システムの導入は、受付業務の効率化と医療の質の向上につながります。愛知県のあま市民病院では、このシステムを導入することで、患者の保険資格情報をリアルタイムで正確に確認ができるようになりました。
結果的に、受付での入力作業や確認の手間が削減されただけでなく、薬剤情報や特定健診情報を患者の同意のもとで閲覧が可能となり、より安全で質の高い医療提供の基盤が整いました。国の推進するインフラを活用することも、DX成功のポイントとなります。
出典参照:医療DX推進の体制に関する事項及び情報の取得・活用等について|あま市民病院

医療DXでセキュリティ対策を講じる際のポイントは、以下の7つです。
ひとつずつ解説します。
セキュリティ対策の成否は、経営層のリーダーシップにかかっています。セキュリティを情報システム部門の仕事と捉えず、病院全体の「経営課題」として院長自らの主導が不可欠です。
経営層が明確な方針を示し、必要な予算と人員を確保して初めて全組織的な取り組みが可能です。全部門を巻き込み、一丸となって対策を進める文化の醸成が、堅牢なセキュリティ体制につながります。
技術とルール遵守が揃って、初めて組織を守れます。パスワードの適切な管理方法や個人情報の取り扱いなど、職員が遵守すべき具体的ルールを策定するのが大切です。また、ルール徹底のための教育・研修を、セットで実施しておくのも重要です。
最新のセキュリティソフト導入だけでは、対策は不十分です。多くの情報漏洩は、技術的欠陥でなく、人的ミスやルール違反で引き起こされていることを理解しておきましょう。
インシデントは、起こりうる前提で備えておくのが重要です。万全な対策でも、サイバー攻撃を100%は防げません。
万が一の攻撃時に、誰が指揮を執り、どの部署が何をおこない、どう外部へ報告し、どのように迅速にシステムを復旧させるかを考慮しておくのが大事です。一連の流れを「インシデントレスポンスプラン」として事前に文書化し、定期的な訓練をおこなうことで、被害を最小限に食い止める準備を常にしておきましょう。
厚生労働省策定の「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」は、全医療機関が遵守すべき基本ルールです。医療情報の取り扱いには、国が定める厳格な基準が存在します。
ガイドラインは、技術的安全対策から組織的体制整備まで、医療機関が講じるべき具体的項目を網羅しています。ガイドライン内容を正確に理解し、自院の対策が基準を満たすか確認することが、法的・倫理的責任を果たす最低条件です。
出典参照:医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第 6.0 版 概説編 [ Overview ](令和5年5月)|厚生労働省
出典参照:医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第 6.0 版 経営管理編
出典参照:医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第 6.0版 企画管理編
出典参照:医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第 6.0 版 システム運用編 [Control](令和5年5月)|厚生労働省
医療DXにおけるセキュリティ対策の導入時は、現場の医療従事者の意見を十分ヒアリングしておきましょう。安全性と日々の業務の利便性のバランスが取れた、現実的な落としどころを見つける視点が欠かせません。
また、セキュリティ強化のためルールを厳しくしすぎると、現場の業務効率を著しく低下させる恐れがあります。パスワードの頻繁な変更、過度なアクセス制限は、職員を疲弊させ、抜け道「シャドーIT」の温床になるため注意が必要です。
電子カルテシステムやクラウドサービスなど、外部事業者へ業務を委託する場合も、情報管理の最終的な責任は医療機関にあります。委託先での情報漏洩は、自院の信頼失墜につながりやすいです。
そのため、システムやサービスの契約時には、委託先のセキュリティ管理体制を厳格に評価・選定しておきましょう。また、契約後も定期的な監査をおこなうなど、丸投げにしない姿勢が重要です。
最新の脅威動向や技術進展に合わせて、自院のセキュリティ対策を定期的に見直し、継続的に改善するプロセスが不可欠です。攻撃者の手口は日々巧妙化しており、新たな脆弱性が次々発見されています。
セキュリティ対策に「完璧」はありません。導入したシステムや策定したルールはすぐ時代遅れになるため、地道なアップデートが、未来の脅威から組織を守る最も確実な方法です。

医療DXにおけるセキュリティ対策は、単なるコストやIT部門の課題ではありません。患者の信頼獲得や安定した経営維持、安全な医療提供のための「経営の中心課題」です。
また、医療DXは、人材不足や長時間労働等の医療業界の構造的課題を解決してくれます。国民一人ひとりが、質の高い医療を受けられる未来を実現する強力な推進力です。
経営層がリーダーシップを発揮し、組織全体で継続的に取り組むことで、医療DXの真価を発揮する明るい未来を実現していきましょう。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
