レガシーシステム統合で実現する医療DXのメリットとは?
医療

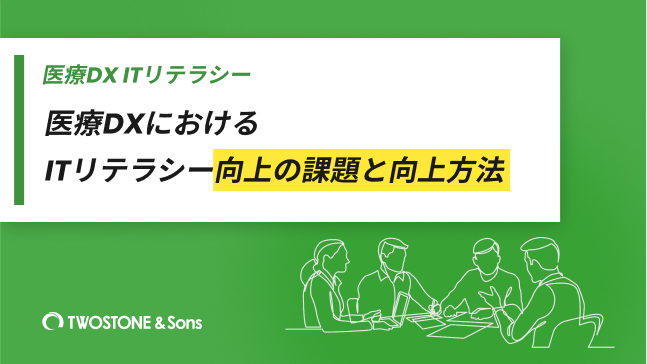
医療DXを進めるうえでのITリテラシー不足の課題と、現場での育成方法について解説。職種別の研修や先進事例も紹介します。
医療現場で「パソコン操作に戸惑う」「新システムの使い方がわからない」といった声を耳にしたことはありませんか?
デジタル化が進むなかで、医療DXの導入に苦手意識を持つ職員も多く、かえって業務の負担が増してしまうケースもあります。
本来、DXは業務の効率化や安全性の向上につながるはずです。しかし、その効果を十分に発揮するためには、ITリテラシーの底上げが不可欠です。現場でよく見られる課題を正しく把握し、現実的な育成方法を知ることが重要です。
この記事では、医療従事者のITスキル不足や教育の偏りといった課題に触れつつ、職種ごとの研修内容や先進的な人材育成の取り組みを紹介します。読後には、医療機関がどのようにしてリテラシー向上に取り組めるか、具体的なヒントが得られます。
医療機関でDX推進を担当している方、情報システム部門のご担当者、また教育体制の見直しを検討している病院経営者の方にこそ、ぜひ最後までお読みいただきたい内容です。

医療DXを推進するうえで、現場のITリテラシーには以下のような課題があります。
・医療従事者のITスキルが不足している
・IT人材が不足している
・高齢者などがデジタル機器を使いこなせない
・新しいシステム導入に対する現場の抵抗
それぞれ解説していきます。
医療従事者のITスキル不足は、情報セキュリティ対策の妨げとなります。医師や看護師の業務は患者対応が中心であり、パソコン操作やシステムの設定に触れる機会が少ない職場もあります。
そのため、基本操作に時間がかかったり、セキュリティ上の設定ミスにつながったりする可能性があります。こうしたリスクを軽減するには、現場の業務に沿ったIT研修を定期的に実施することが大切です。
医療機関において、ITと医療の両方に精通した人材が不足しています。電子カルテの管理やサイバーセキュリティ対策には専門知識が必要ですが、それを担うスタッフが限られている状況です。
ネットワークの監視、トラブル発生時の対応、セキュリティ設定などを適切に行うためには、専任の人材が不可欠です。外部委託だけに頼らず、院内での人材育成やIT部門の強化が求められます。
高齢の患者がデジタル機器を扱えないことが、セキュリティ上の課題につながる場合があります。
例えば、オンライン診療や予約システムを誤操作して個人情報を入力したり、不審なサイトにアクセスしてしまったりする可能性があります。
医療DXを安心して利用してもらうためには、患者へのサポート体制が必要です。操作に不安がある方には、職員が丁寧に説明を行うなどの対応が重要です。
新しいシステムの導入に対し、現場が抵抗感を示すことがあります。業務の流れが変わることへの不安や、操作への戸惑いが原因となり、セキュリティ強化の妨げになる場合もあります。
特に、ログ管理やアクセス制限などの機能があっても、うまく活用されないまま運用されず形骸化するリスクも想定されます。導入に際しては、段階的な説明や職種別のトレーニングを取り入れることで、スムーズな運用につなげることができます。

ITリテラシーの向上は、医療現場の質を高め、業務効率やセキュリティの面でも大きな効果をもたらします。具体的なメリットは以下のとおりです。
業務の効率化により、医療従事者の負担を減らすことができます。紙のカルテや手書きの記録がデジタル化されることで、情報の記録や共有が迅速におこなえるようになります。
記録ミスや転記の手間が減るだけでなく、院内の情報連携もスムーズになります。作業の重複や確認作業の時間も削減され、本来の診療業務に集中しやすくなる点が大きな利点です。
AIの導入により、診断や治療の質を高めることが可能です。画像診断や病歴データの分析をAIがサポートすることで、見落としや判断の偏りを減らせます。
また、過去の症例や統計情報をもとに、最適な治療方針を提示するツールの活用も進んでいます。医師の判断を補完する形で活用することで、診療の質を安定させやすくなります。
オンラインサービスの導入は、患者の利便性向上につながります。予約や問診をスマートフォンで完結できることで、待ち時間の短縮やスムーズな受付が可能になります。
また、遠方に住む人や移動が困難な方でも、遠隔診療を通じて医療にアクセスしやすくなります。再診の効率化や定期フォローにも役立ち、患者にとって負担の少ない通院環境をつくることができます。
医療データの分析を通じて、個人の状態に合わせた対応が可能になります。過去の診療記録や検査結果をもとに、疾患リスクの予測や生活習慣の指導が行えるようになります。
一人ひとりの症状や背景に応じたアプローチがとれるようになることで、より丁寧な診療が可能になります。データの蓄積と分析を継続することで、将来の予防医療にもつながります。
セキュリティへの意識を高めることで、情報漏洩のリスクを下げることができます。IDやパスワードの管理、アクセス制限の設定、定期的なソフトウェア更新といった基本的な対策の徹底が求められます。
また、不審なメールやアクセスに対する警戒意識も重要です。ITリテラシーが高まることで、日常業務のなかで自然と安全性を意識した行動が取れるようになります。

医療DXを円滑に進めるためには、職種に応じた人材育成が必要です。全職員に対する基本的な研修から、専門職ごとの実務対応、さらには推進役となるリーダー層への高度な教育まで、段階的なプログラムを整備することが求められています。
すべての職員がDXの意義を理解し、基本的なデジタルスキルを身につけることが出発点となります。安全で効率的な運用のために、全員が共通の認識を持つことが重要です。
医療DXの考え方と目的を明確に理解することは、すべての職員にとっての出発点となります。医療業界では、少子高齢化や人材不足といった構造的課題を背景に、デジタル技術による業務効率化と質の向上が求められています。
その中で、単なる技術導入ではなく、医療のあり方そのものを見直す視点が必要です。DXの定義や社会的背景を把握し、自身の職務がどう関わっていくのかを理解することが、スムーズな運用と協力体制の構築につながります。
患者の命や生活に直結する医療情報を守ることは、医療機関の基本的な責務です。パスワードの定期変更やアクセス権限の制限といった基本的な管理の徹底はもちろんのこと、フィッシングメールや不正アクセスのリスクについても事例を交えて学ぶ必要があります。
また、USBの私的使用や個人端末での業務データ保存といったヒューマンエラーの防止も重要です。セキュリティ対策は技術的なものだけでなく、現場職員一人ひとりの意識と習慣によって支えられています。
PC操作の基礎力を身につけることは、どの職種においてもデジタル業務を遂行するうえで不可欠です。文字入力やマウス操作、ファイル管理、印刷設定など、日常業務でよく使用する操作に加えて、フォルダの階層構造やクラウド環境でのファイル共有といった応用も含めて練習します。
さらに、インターネット検索の精度を高めるコツや、業務に関連したWebリソースの活用法も学ぶことで、情報収集力の底上げにもつながります。
DXが進む中で、チーム医療のコミュニケーションも紙や電話からチャット・ビデオ会議へと変化しています。メールの文面作成ルール、グループチャットの使い分け、Web会議でのカメラ・マイク設定や画面共有といった基本操作に加えて、オンライン特有のマナーや注意点も理解する必要があります。
情報共有のスピードを高め、誤解を防ぐためには、伝達の正確さとリアルタイム性を意識したデジタルコミュニケーションスキルが求められます。
診療や看護の実務に関わるスタッフは、実際の機器やシステムを操作する立場にあります。安全かつ正確に活用するために、実務に即した知識と技術の習得が求められます。
診療内容を正確に記録し、必要な情報を迅速に確認するためには、電子カルテとオーダリングシステムの操作スキルが不可欠です。
画面の見方、入力形式、検索機能、過去記録の呼び出し方、テンプレートの活用法など、現場で使用する機能に即したトレーニングを行います。
また、診療科ごとに異なる入力ルールや、診療報酬請求に関わる注意点も理解しておく必要があります。正確で効率的な情報管理が、診療の質と患者安全の向上につながります。
非対面での診療には、通常とは異なるスキルと配慮が求められます。例えば、通信状況の確認、映像と音声のチェック、患者の表情や反応の把握、対話中の視線の位置、説明資料の画面共有方法など、細かな対応が問われます。
また、セキュリティを意識したログイン・ログアウト管理、患者情報の取り扱い、トラブル発生時の対応手順なども併せて確認します。安心して診療を受けてもらうためには、患者との関係性を維持する接遇力も大切です。
血圧計や心電図モニターなどの医療機器、さらにウェアラブルデバイスなどから収集されたデータをシステムに統合し、診療や看護に活用するには、正確な操作と読み取り力が求められます。
リアルタイムでのバイタル管理、異常値のアラート通知、データのトレンド把握など、現場の意思決定を支援する手段としての活用法を学びます。機器との接続エラーやネットワークの不具合時に対応する力も重要です。
医療現場では、画像診断支援や診療補助ツールとしてAIが導入されつつあります。AIが判断を下すプロセスや、どのような情報に基づいて結果を提示するのかといった仕組みを理解することで、過信や誤用を防ぐことができます。
また、AIの活用範囲や限界、バイアスへの配慮、倫理的課題なども含めた基礎知識を持つことが、医師や看護師が安心して補助的に活用するうえでの前提となります。
医療DXの中核を担う層には、高度な知識とマネジメント力が求められます。システム運用だけでなく、現場を巻き込みながら継続的な改善を進める力が必要です。
新たなシステムを現場に浸透させるためには、単なる導入だけでなく、その後の運用・保守体制の整備が不可欠です。仕様選定から業者との連携、ユーザー向けマニュアル作成、障害対応のフロー設計など、実務に沿った計画が求められます。
また、定期的なメンテナンスやソフトウェア更新の手順、職員への通知ルールも明確にしておくことで、継続的な安定稼働を支えることができます。
医療現場に蓄積される診療データを分析・活用することで、経営指標の改善や業務プロセスの見直しが可能になります。
BIツールや統計ソフトを用いて、患者数の推移、平均在院日数、診療科別の稼働状況などを可視化することで、具体的な課題が明らかになります。分析結果を現場の業務改善にどう落とし込むかを意識した活用法が重要です。
DX関連プロジェクトでは、多職種が関わるため、進行の管理や合意形成が重要になります。スケジュール設定、進捗状況の見える化、タスク管理の徹底に加え、途中で発生する課題の共有と対応策の議論が欠かせません。
また、現場からの声を取り入れつつ、計画の見直しや優先順位の調整ができる柔軟性も求められます。
日々進化するデジタル技術を正しく理解し、適切な判断材料とするためには、基礎的な知識と活用事例の両方を知っておくことが必要です。
クラウドコンピューティングによる情報共有の迅速化、AIによる自動解析支援、ブロックチェーンを用いた改ざん防止技術など、現場に導入された際の利点と制約を踏まえて学びます。
DXを現場で根づかせるためには、リーダー自身のビジョンとコミュニケーション力が問われます。異なる職種間での理解促進や、現場の反発に対する丁寧な対話、成果が見えにくい初期段階でのモチベーション維持など、状況に応じたファシリテーションが必要です。
また、定期的な情報共有や研修の仕組みづくりも、継続的なDX推進には欠かせません。

医療DXを推進するには、現場で働く人々がITに慣れ、日常業務で活用できる状態を整えることが欠かせません。全国の医療機関では、実践的な研修や教育プログラムを通じて、ITリテラシーを底上げする取り組みが進められています。以下に、先進的な取り組みをおこなっている事例を紹介します。
スタッフがAIを使いこなせる環境づくりに成功しています。全国の施設で導入が進むAI事前問診ツールを定着させるため、導入前後で段階的な操作研修を実施しています。
具体的には、医療スタッフ向けにツールの使用方法や入力画面の確認方法をわかりやすく説明し、診療現場での混乱を防ぐ工夫を重ねています。さらに、導入後も継続的にサポートを続けることで、現場の不安を払拭し、診察時間の短縮や患者対応の迅速化につなげています。
出典参照:「AI問診システム」導入による外来業務改善に向けた取り組み|大津赤十字病院
医師の業務負担を軽減する仕組みとして、医療文書作成の効率化が進んでいます。大規模言語モデルを日本語で活用するため、医師に対して文書作成支援ツールの使用トレーニングを実施しています。
これにより、カルテや診療情報提供書の下書きを短時間で生成できるようになり、確認・修正作業に集中できる環境が整っています。単なる時短だけでなく、文章の標準化による品質向上にもつながっており、文書業務の最適化という観点で注目されています。
出典参照:NEC、東北大学病院、橋本市民病院、「医師の働き方改革」に向けて、医療現場におけるLLM活用の有効性を実証 ~医療文書の作成時間を半減し、業務効率化の可能性を確認~|東北大学病院
現場で自ら課題を解決できるIT人材の育成が進んでいます。院内でのデータ処理や業務自動化を担当者自身が対応できるよう、「実践型医療DX人材育成プログラム」を導入しています。
このプログラムでは、PerlやPowerShell、VBA、Rといったプログラミングやスクリプト言語を基礎から学び、現場業務に合わせたカスタマイズスキルを習得します。既存システムの手直しや自作ツールの構築なども行えるようになり、コストを抑えつつ即応性の高いIT対応が可能となっています。
出典参照:実践型!医療DX人材育成プログラム | 【公式】熊本県甲佐町の内科・総合診療科・コミュニティホスピタル谷田病院

医療DXを推進するうえで、ITリテラシーの格差や教育機会の不足は大きな課題となっています。医療従事者全体が基本的なデジタルスキルを身につけ、職種ごとに適した研修を受けることが、システムの円滑な運用と安全な情報管理につながります。
現場の実例や人材育成プログラムを参考にしながら、医療機関全体で継続的なスキル向上に取り組むことが重要です。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
