レガシーシステム統合で実現する医療DXのメリットとは?
医療

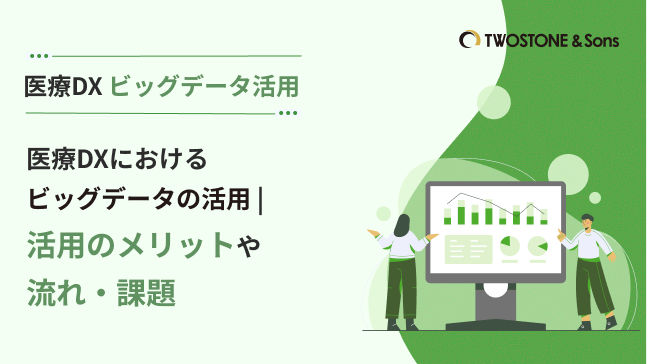
多くの医療機関が直面する経営や業務における課題を解決する切り札として、「医療DX」、とくに「ビッグデータ活用」に大きな期待が寄せられています。そこでこの記事では、医療ビッグデータの概要から活用するメリットや流れなどを徹底解説しています。


・6万名以上のエンジニアネットワークを活用して課題を解決※
・貴社のDX戦略立案から実行・開発までワンストップで支援可能
※エンジニア数は2026年8月期 第1四半期決算説明資料に基づきます。
超高齢社会の進展による医療需要の増大と、それに伴う医療スタッフの負担増。多くの医療機関が直面する課題を解決する切り札として、「医療DX」、とくに「ビッグデータ活用」に大きな期待が寄せられています。
そこでこの記事では、以下の内容を解説しています。
また、記事の後半では医療ビッグデータ活用の具体的な事例や導入の流れについても解説しています。医療ビッグデータ活用について理解を深めたい医療関係者の方は、ぜひ最後までご覧ください。

医療DXにおいて、より質の高い医療の実現を目指すために注目されているのが「ビッグデータ活用」です。
これまで医師個人の経験や勘に頼る部分も大きかった医療分野が、客観的なデータにもとづいて判断をおこなう「データ駆動型医療」へと進化していくうえで、ビッグデータは中心的な役割を果たします。
ここでは、医療ビッグデータの概要について解説していきます。
医療ビッグデータとは、日々の診療や健康診断などで生まれる、人々の健康や医療に関する膨大なデジタル情報のことです。この情報には、病院で処方された薬の種類や量、おこなわれた手術の記録、血液検査の結果、さらには個人の遺伝子情報まで、非常に多岐にわたるデータが含まれます。
以前は紙のカルテによって医療機関ごとでバラバラに保管されていたデータが、デジタル化が進んだことによって、一箇所に情報を集約し、大規模なデータとして分析することが可能になっています。
集められた膨大な医療情報を詳しく分析すると、これまで見えてこなかった病気の根本原因や、新しい治療法の開発につながるヒントが発見できる可能性があるのです。まさに医療の未来を切り拓く宝の山といえるでしょう。
医療ビッグデータには、主に以下の4種類があります。
一つずつ解説します。
レセプトデータとは、病院や薬局が健康保険組合などへ医療費を請求するために作成する「診療報酬明細書」を電子化したデータです。レセプトデータには、「いつ、誰が、どの医療機関を受診し、どのような病名で、どんな治療・検査・投薬を受けたか」という一連の情報が記録されています。
日本全国の膨大なレセプトデータを集計すると、特定の病気がどの地域や年代で流行しているか、あるいは特定の薬がどれくらい処方されているかといった、国民全体の医療の動向を大きな視点で把握できます。また、数カ月単位でデータが蓄積されていくため、ある病気にかかった人がその後どのような治療を受けているか、長期的な経過を追跡する研究にも活用される非常に価値の高い情報です。
DPCデータとは、大学病院などの急性期病院が、入院患者一人ひとりに対しておこなった医療行為を記録したデータのことです。
DPCは「診断群分類包括評価」という日本の医療費計算方法の名称で、患者が入院してから退院するまでの間に、「いつ、どのような手術や検査・注射・リハビリがおこなわれたか」が日付に沿って詳細に記録されています。そのため、レセプトデータよりも、入院期間中の医療の質や具体的な内容をより詳しく分析できるのが大きな特徴です。
病院ごとの治療方法の違いを比較したり、より質の高い入院医療の標準的な進め方を探ったりする研究に活用されています。
電子カルテとは、これまで医師や看護師が紙に記録していた診療録を、デジタル情報としてコンピューターで一元的に記録・管理するシステムです。電子カルテには、医師の診察所見や診断内容はもちろん、日々のバイタルサインや処方した薬の履歴、アレルギーの有無、さらにはレントゲンやCTといった検査画像まで、患者に関するあらゆる情報が集約されています。
電子カルテのデータを個人が特定できないように匿名化したうえで大量に集めて分析することで、ある薬を使い始めたあとの血圧の変化や、ある手術を受けた後の回復過程など、非常に詳細な医療研究をおこなうのが可能になります。
まさに、医療ビッグデータの中でもとくに情報密度が高いデータの一つです。
健診・ゲノム・ライフログデータとは、健康診断の結果や個人の遺伝情報、そして日常生活の活動記録といった、病院の外で生まれる健康に関する多様な情報群です。
健診データは、企業や自治体でおこなわれる健康診断の結果であり、病気になる前の「未病」の状態を把握するのに役立ちます。ゲノムデータは、生まれ持った遺伝子の情報で、将来かかりやすい病気のリスクや、薬の効果が出やすい体質かどうかを予測するのに活用されます。そしてライフログデータは、スマートウォッチなどで計測される心拍数、歩数、睡眠時間といった日々の生活記録です。
これらの多様なデータを病院のデータと組み合わせると、一人ひとりの体質や生活習慣に合わせた最適な医療の実現に大きく近づきます。

近年医療ビッグデータの活用が重要視されているのには、以下5つの理由が関係しています。
一つずつ見ていきましょう。
AIやクラウド技術が目覚ましく発展したことで、これまで処理しきれなかった膨大な医療データを高速かつ高度に分析できるようになったのが、医療ビッグデータ活用が重要視される大きな理由です。
とくにAIは、人間の目では見逃してしまうような微細な病気の兆候を画像から発見したり、数多くの患者データから特定の治療法が効きやすい人の特徴を見つけ出したりする能力に長けています。また、クラウド技術の普及により、様々な医療機関が持つデータを安全な環境で集約し、共同で分析・研究をおこなう基盤が整いました。
こうした技術的な進化が、単なる情報の集まりであった医療データを、新たな価値を生み出す「知の源泉」へと変えたのです。
医療ビッグデータの活用と同時に、個人のプライバシー保護に関する意識が社会全体で高まったことで、安全なデータ活用のための技術やルール作りが進みました。
医療データは極めて繊細な個人情報のため、その利用には細心の注意が求められます。この課題に対し、データを加工して個人が特定できないようにする「匿名化」の技術が大きく進歩しました。さらに、国が「次世代医療基盤法」という法律を整備し、プライバシー保護の厳格なルールのもとで、医療情報を研究開発などに利用できる仕組みを整えています。
出典参照:次世代医療基盤法について|内閣府
データを安全に利用するための環境が整備され、人々が安心して自身のデータを提供できるようになり、さらなるデータ活用につながるという好循環が生まれ始めています。
日本が直面する超高齢社会と、それに伴う国民医療費の増大という大きな課題を解決する切り札として、医療ビッグデータの活用に期待が寄せられています。
高齢化が進むと、病気にかかる人の数が増え、医療サービスの需要は高まり続けます。その結果、国の医療費は年々増加しており、質の高い公的医療保険制度を維持するのが困難になりかねません。そこで、医療ビッグデータを分析し、病気の重症化を効果的に予防したり、無駄な検査や投薬を減らして医療を効率化したりする必要があるのです。
出典参照:高齢化と医療資源の逼迫 2025年問題と2040年問題をどう対策するか|日本調剤
限られた医療資源を最大限に活かし、質の高い医療と持続可能な制度を両立させるために、データにもとづくアプローチが不可欠とされています。
人々の価値観やライフスタイルが多様化したことで、画一的な医療ではなく、一人ひとりに合わせた最適な医療(個別化医療)へのニーズが高まったことも、医療ビッグデータ活用が注目される理由です。
以前は、「標準治療」と呼ばれる多くの人に効果が認められた同じ治療法が中心でした。しかし現在では、同じ病気でも、個人の遺伝的な体質や生活習慣によって、薬の効き方や副作用の出方が異なることが分かっています。
そこで、膨大な患者データやゲノム情報などを分析し、その人にとって最も効果が高く、かつ安全な治療法や予防法を提案する「個別化医療」の実現が目指されています。きめ細やかな医療を提供するためには、個人の詳細なデータの活用が欠かせません。
政府が国策として医療DXを強力に推進し、医療ビッグデータを活用するための法整備や基盤作りを積極的におこなっているのが、この流れを加速させている大きな要因です。
国は「データヘルス改革」を掲げ、国民の健康増進と持続可能な医療制度の実現を目指しています。その一環として、医療情報の安全な利活用を促す「次世代医療基盤法」を施行したり、全国の医療情報を連携させるためのプラットフォームを整備したりする取り組みが進められています。
出典参照:「国民の健康確保のためのビッグデータ活用推進に関するデータヘルス改革推進計画・工程表」及び「支払基金業務効率化・高度化計画・工程表」について|厚生労働省
国の強力な後押しによって、これまで各医療機関の中に閉じていたデータが、研究開発などのために利用しやすい環境が整いつつあるのです。これにより、企業や研究機関も安心してデータ活用に取り組めるようになります。

では、医療ビッグデータを利用・活用することにはどのようなメリットがあるのでしょうか。以下3つの立場別に、具体的なメリットを解説していきます。
詳しく見ていきましょう。
患者にとって最大のメリットは、ビッグデータの活用によって、より質の高く、自分に最適化された安全な医療を受けられるようになる点です。
患者は、多くの人の治療データを分析した結果をもとに、自分にとって最も効果が期待でき、副作用のリスクが少ない治療法を選択できるようになります。また、AIによる画像診断支援などによって、がんなどの病気をより早い段階で発見できる可能性が高まります。
そして将来的には、健康診断の結果や日々の生活習慣のデータから、将来かかりやすい病気を予測し、発症を未然に防ぐための具体的なアドバイスを受けられる「予防医療」が充実していくでしょう。健康な生活をより長く送るにあたって大きなメリットとなるでしょう。
医療機関や医師にとってのメリットは、膨大な臨床データを根拠とした、より正確で効率的な診断や治療をおこなえるようになり、業務負担を軽減できる点です。
過去の膨大な症例を瞬時に参照できると、珍しい病気の診断精度を高めたり、治療方針の決定に役立てることが可能です。また、AIがカルテ入力を補助したり、最新の医学論文の中から必要な情報を探し出してくれたりすることで、医師は事務作業から解放され、医療行為により多くの時間を確保できるようになります。
さらに、院内のデータ分析によって無駄な業務プロセスが改善されることで、医療の質を維持しながら病院経営を効率化することにもつながります。
研究者や製薬会社にとってのメリットは、これまでアクセスが難しかった大規模かつリアルな医療データを活用し、画期的な治療法や新薬の開発を加速させられる点にあります。
何十万人ものリアルな患者データを分析すると、希少疾患の原因究明や、特定の遺伝子と病気との関連性を発見する研究が大きく進展します。また、新薬の開発プロセスにおいては、どのような特徴を持つ患者に効果が現れやすいかを開発の初期段階で高精度に予測できます。
これにより、開発期間の大幅な短縮とコスト削減が実現し、これまで治療法がなかった病気に対する新しい薬が、より早くより安く患者のもとに届くようになるでしょう。
社会や行政にとってのメリットは、国民全体の健康状態や医療提供体制をデータに基づいて正確に把握し、より効果的で公平な医療政策を立案・実行できるようになる点です。
たとえば、どの地域でどのような病気が増えているかを分析すると、限られた医療資源(医師、病院、予算など)を本当に必要な場所に重点的に配分できます。また、感染症の流行を早期に検知し、迅速な拡大防止策を講じるうえでも医療ビッグデータ活用は不可欠です。
医療ビッグデータに基づく政策は、より公平で質の高い医療を社会全体で実現するための基盤となるのです。

医療ビッグデータを有効に活用するためには、以下の流れに沿って計画的に進めることが重要です。
この一連のプロセスを正しく踏むことで、データは初めて価値あるものに変わります。一つずつ解説します。
まずは、「データを使って何を解決したいのか」「何を明らかにしたいのか」という目的や課題を明確に設定してください。
正しい目的設定が、プロジェクト全体の方向性を決める最も重要な羅針盤の役割を果たします。目的が曖昧なままでは、どのデータを集めれば良いか、どのように分析すれば良いかが分からず、時間と労力が無駄になりかねないためです。
たとえば、「院内の待ち時間を短縮したい」「生活習慣病の重症化を予防したい」といった具体的なテーマを掲げます。さらに、「待ち時間を平均10分短縮する」といったように、達成度を測れる具体的な目標を設定することで、のちの効果検証がしやすくなります。
次に、設定した目的に合わせて、院内の電子カルテやレセプトデータ、あるいは外部の公開データなど、必要な情報を様々な場所から集めて一つに統合します。
たとえば、病院の経営改善が目的なら院内の診療報酬データが中心となり、地域の健康増進が目的なら特定健診のデータも必要になるでしょう。ただし、これらのデータは異なるシステムや形式でバラバラに存在しているのが一般的です。そのため、それらを一カ所に集め、同じルールで扱えるように「統合」する作業が不可欠になります。
この段階で、データの正確性や網羅性を確認したうえで信頼できる情報を集めるのが、のちの分析結果の質を大きく左右します。
収集したデータは分析にすぐ使える状態ではなく、患者のプライバシーを厳格に守るため、氏名や住所、電話番号など個人を特定できる情報を削除したり、別の記号に置き換えたりする「匿名加工」をおこなう必要があります。
また、データには入力ミスによる誤字や、必要な情報が抜けている「欠損値」などが含まれていることもあります。これらを手作業やプログラムで修正・補完する「データクレンジング」という地道な作業によって、分析の精度と信頼性を高める工程が必要です。
データ内に隠されている有益なパターン、相関関係、あるいは異常値などを見つけ出すために、データの分析と可視化をおこないます。
分析の手法は、単純な平均値や合計値を計算するものから、AIを用いて将来の数値を予測する高度なものまで様々です。また、多くの人が問題点や改善のヒントをひと目で把握できるように、結果をグラフや地図、ダッシュボードといった形式で表現する「可視化」が最も大切になります。
最後のステップは、データの分析と可視化によって得られた知見を、実際の医療現場の改善や新たな研究開発へと活かし、その効果を評価して次の改善につなげることです。
データ分析は、それ自体がゴールではなく、あくまで課題解決のための手段です。分析で「特定の疾患を持つ患者の再入院率が高い」という結果が出たなら、その患者への退院指導を強化するといった具体的なアクションを起こします。そして対策後は、実際に再入院率が下がったかを再びデータで測定し、効果を評価します。
「計画・実行・評価・改善」のサイクルを継続的に回し続けることで、持続的な医療の質の向上が実現するのです。

医療ビッグデータの活用には大きな期待が寄せられる一方、以下のような3つの課題とも常に隣り合わせの状態です。
これらの課題は、医療DXを社会全体で推進していくうえで、必ず乗り越えなければならない壁といえるでしょう。どのような課題なのか、それぞれ解説します。
最大の課題の一つは、各医療機関が使用している電子カルテなどのシステムが異なり、データの形式や用語が統一されていない「標準化」の問題です。
たとえば、ある病院では病名を正式名称で入力し、別の病院では一般的な略称で入力するなど、データの記録方法が施設ごとにバラバラなのが現状です。これでは、複数の医療機関からデータを集めて分析しようとしても、単純に統合できません。
国もデータの標準化に向けた取り組みを進めていますが、データの分断は広域でのデータ連携や活用を阻む大きな壁となっています。
医療データは非常に機微な個人情報を含むため、その取り扱いには徹底したプライバシー保護と、サイバー攻撃からの防御を目的とした高度なセキュリティ対策が不可欠です。このようなセキュリティ体制の構築と維持には、専門知識と継続的なコストが必要となります。
万が一、病歴などの情報が外部に漏洩すれば、患者には計り知れない不利益が生じ、医療機関の社会的信用は著しく失われます。そのため、データを扱う際は、法律やガイドラインに従った厳密な匿名化処理が必須です。
さらに、データ保管用のサーバーや情報を送受信するネットワークには、外部からの不正アクセスを防ぐために多層的な防御システムが求められます。
医療ビッグデータを効果的に活用するために不可欠とされる、医療とデータサイエンスの両方に精通した専門人材が不足しているのが現状です。
データを分析するスキルを持つデータサイエンティストは、IT業界をはじめ様々な分野で需要が高く、獲得競争が激化しています。とくに医療分野では、単にプログラミングや統計学の知識があるだけでなく、医療現場の業務内容や特有の倫理観も深く理解している必要があります。こうした分野横断的なスキルを持つ人材の育成には時間がかかり、すぐには需要に追いつかないのが実情です。
専門人材の不足が、多くの医療機関でビッグデータ活用が思うように進まない根本的な原因となっています。

では、分野別に医療ビッグデータの具体的な活用事例を見ていきましょう。
医療ビッグデータは、医師の診断や治療を直接サポートし、医療の精度と質を飛躍的に向上させるために活用されています。その代表例が、AIによる画像診断支援です。
AIが過去の膨大なレントゲンやCTの画像を学習し、人間の目では見逃してしまうような、ごく初期のがんの兆候などを発見する研究が進んでいます。また、患者一人ひとりの遺伝子情報を解析し、その人に最も効果が期待できる薬を選んだり、副作用のリスクを予測したりする「ゲノム医療」もビッグデータ活用の一例です。
医療ビッグデータは、本来は長い年月と莫大な費用を要する新薬の開発を大幅に効率化するために活用されています。
たとえば、新しい薬の「種」となる化合物を探す際、膨大な医療データや論文をAIが解析し、有望な候補を短時間で絞り込む研究がおこなわれています。また、新薬の有効性を確かめる臨床試験においても、大規模な患者データベースの中から、その薬の対象となる条件に合った患者を迅速に見つけ出すことが可能です。
これにより、新薬の開発期間短縮とコスト削減が実現します。結果として、今までよりも効果の高い新薬が、いち早く患者のもとに届くようになるのです。
医療ビッグデータは、病院の業務を効率化し、安定した経営を実現するためにも活用されています。
院内の患者の流れや各部署の稼働状況をデータで分析すると、どこに業務のボトルネックがあるかを客観的に把握できます。その分析結果をもとに、外来の予約枠やスタッフの配置を最適化し、患者の待ち時間を短縮するといった改善策を講じることが可能です。
また、使用される医薬品や医療材料のデータを分析し、在庫管理を最適化して無駄なコストを削減する取り組みも進められています。
医療ビッグデータは、個人の治療や病院経営の枠を超え、地域全体の健康を守り、効果的な医療政策を立案する「公衆衛生」の分野でも不可欠なツールとなっています。国や自治体は、地域のレセプトデータや健診データを分析し、どの年代で、どのような病気が増えているかを詳細に把握します。そのデータにもとづいて、「この地域では糖尿病の予防に力を入れよう」といった、根拠のある地域医療計画を策定するのです。また、感染症の発生状況をリアルタイムで監視し、流行の兆しをいち早く察知して、迅速な対策を講じる上でも活用されています。データは、社会全体の健康を守るための羅針盤の役割を果たしているのです。

最後に、医療ビッグデータ活用の今後の展望について、以下3つの視点から解説します。
「個別化医療(プレシジョン・メディシン)」が本格化する
「未病・予防医療」へのシフトが加速する
ウェアラブルデバイスとの連携で日常データ活用の幅が広がる
それぞれ解説します。
医療ビッグデータの活用が進む未来では、「個別化医療(プレシジョン・メディシン)」が本格化し、一人ひとりの体質や生活習慣に合わせたオーダーメイドの医療が当たり前になります。これは、遺伝子情報、生活習慣、環境といった膨大なデータを総合的に分析し、その人にとって最も効果が高く、副作用の少ない治療法や予防法を導き出すアプローチです。
たとえば、同じがんでも、その人の遺伝子の特徴を詳しく調べることで、「あなたのがんにはAという薬が最も効きやすい」と高精度に予測できます。これにより、無駄な治療を避け、患者の身体的・経済的な負担を大きく減らすことが可能になるでしょう。
医療ビッグデータの活用は、病気になってから治療する「治療医療」から、病気になる前に防ぐ「未病・予防医療」への大きなシフトを加速させます。
未病とは、健康と病気の中間の状態を指します。毎年の健康診断データや日々の生活習慣データを時系列で分析すると、AIが「このままの生活を続けると、5年後に糖尿病になるリスクは70%です」といった将来の病気のリスクを予測できるようになります。その予測にもとづき、「塩分を一日2グラム減らしましょう」といった、個人に合わせた具体的な予防策を早期に提案できるようになるのです。
病気そのものを未然に防ぐこのアプローチは、人々の健康寿命を延ばし、社会全体の医療費を抑制するうえでも極めて重要です。
スマートウォッチなどのウェアラブルデバイスと医療情報システムとの連携が、今後のデータ活用の幅を大きく広げます。
ウェアラブルデバイスは、心拍数や血中酸素飽和度、睡眠の質、活動量といった日々の健康データを24時間365日自動で記録し続けます。年に一度の健康診断だけでは見えなかった日常の中での体調の変化や、異常の兆候をリアルタイムで捉えるのが可能になるのです。
日常のライフログデータと、病院の電子カルテ情報が連携すると、より精度の高い予防や診断、そして日々の健康管理が実現していくでしょう。

この記事では、医療DXの核となるビッグデータ活用について、その概要から具体的なプロセス、そして乗り越えるべき課題までを解説しました。
医療ビッグデータ活用には、データの標準化や専門人材の不足といった課題が確かに存在します。しかし、それ以上にビッグデータがもたらす「医療の質の向上」と「業務の効率化」というメリットは、これからの病院経営において不可欠な要素です。
医療ビッグデータの活用は、もはや一部の先進的な大病院だけのものではありません。まずは自院の課題を洗い出し、「どのデータを集めれば、どの業務が楽になるか」という小さな一歩を踏み出すことが、持続可能な医療の未来を築くための最も確実な変革の始まりとなるでしょう。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
