レガシーシステム統合で実現する医療DXのメリットとは?
医療

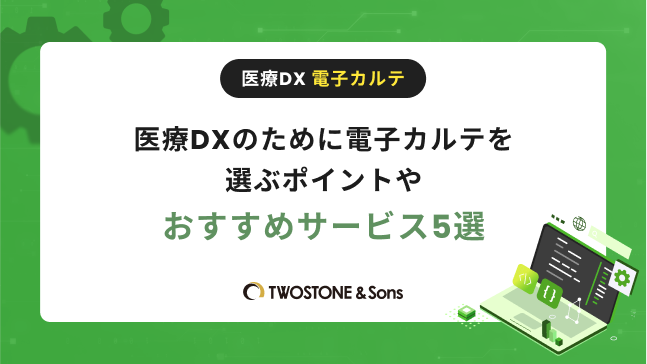
医療DXの第一歩であり、その成否を分けるのが「電子カルテ」の導入です。この記事では、医療DXにおける電子カルテの役割から、最適なサービスの選び方、おすすめのサービスまで徹底的に解説していきます。
院内に山積みになった紙カルテ、手書きによる指示の伝達ミスへの不安、そして非効率な事務作業。日々の診療でこうした課題を感じつつも、「何から手をつければ良いか分からない」とお悩みの医療関係者の方も多いのではないでしょうか。
医療DXの第一歩であり、その成否を分けるのが「電子カルテ」の導入です。そこでこの記事では、電子カルテに関する以下の内容を網羅的に解説します。
電子カルテの導入を検討されている医療関係者の方は、ぜひ最後までご覧ください。

電子カルテは、医療DXにおいて院内の医療情報をデジタル形式で一元管理し、院内外での情報共有を円滑にする最も基本的な土台の役割を担います。
今までは紙のカルテに記載されていた診療記録、検査結果、処方箋といったあらゆる情報をデジタルデータとして集約することで、医療DXの様々な取り組みが可能になります。
電子カルテの基本機能は、患者の診療情報をデジタルで記録する「診療録機能」を中心に、処方箋を作成する「オーダー機能」や会計を支援する機能など多岐にわたります。医師の所見や診断、看護記録などをテキストや画像で保存し、院内のどこからでも瞬時に閲覧可能です。
また、検査や投薬の指示を関係部署へ正確に伝達したり、診療内容にもとづいた会計データを自動で作成したりするなど、医療現場の業務を幅広く支援する役割を担っています。
電子カルテの導入が急務となっているのは、国が医療DXを強力に推進し、医療情報の全国的な共有を目指しているほか、医療現場の業務効率化が喫緊の課題となっているからです。
出典参照:医療DXについて|厚生労働省
政府は、患者がどの医療機関にかかっても質の高い医療を受けられるよう、全国医療情報プラットフォームの創設を進めています。この構想は、電子カルテのデータ連携が前提です。
また、医師の働き方改革や人手不足への対応として、業務の無駄をなくし、対人業務に集中できる環境作りが急務となっています。

電子カルテに頼ることなく、紙カルテや旧式システムを使用し続けることには、以下のようなリスクがあります。
一つずつ解説します。
紙カルテを使い続けると、判読しにくい手書き文字の読み間違いや、処方・指示の伝達ミスといったヒューマンエラーが発生し、重大な医療過誤につながるリスクがあります。たとえば、医師の書いた薬の用量を看護師が読み間違えたり、アレルギー情報が正しく伝わらなかったりするケースが考えられます。
電子カルテであれば、活字で明確に情報が記録・共有されるため、こうした単純ではあるものの命に関わるミスを防ぐのに大きく貢献するのです。
紙カルテの運用は、カルテ保管場所への移動や検索、そして手書きによる転記作業に多くの時間がかかり、医療スタッフの業務を著しく非効率にします。
紙カルテでは、診察のたびに書庫からカルテを探し出し、診察後は元の場所に戻さなくてはなりません。また、複数の医師や看護師が同時に一人の患者のカルテを見るのも困難です。
電子カルテなら、自席のPCから瞬時に必要な情報を検索・閲覧できるため、こうした物理的な手間や待ち時間が大幅に削減されます。
紙カルテは、火災や水害、地震といった災害が発生した際に、物理的に焼失・破損してしまい、患者の貴重な診療記録が永久に失われてしまうリスクを抱えています。とくに、地域の基幹病院が被災した場合、多くの患者の情報が一度に失われ、地域の医療提供体制そのものが麻痺しかねません。
クラウド型の電子カルテであれば、データは遠隔地の安全なデータセンターに保管されるため、院内が被災しても診療情報が守られ、迅速な事業継続が可能になります。
紙カルテの情報は集計や分析が極めて困難なため、自院の診療傾向や経営状況をデータにもとづいて把握できず、改善の機会を逃す「機会損失」につながるのです。たとえば、「どのような疾患の患者が増えているか」「どの診療科の収益性が高いか」といった経営判断に必要な情報を、紙カルテから得るには膨大な手間がかかります。
電子カルテであれば、蓄積されたデータを容易に集計・分析し、客観的な根拠にもとづいた効率的な病院経営や、診療の質向上へとつなげられます。
国が推進する地域医療情報連携ネットワークは電子データを前提としており、紙カルテのままでは、ほかの病院や診療所、薬局との円滑な情報共有ができず、地域連携から孤立してしまいます。紹介状や検査結果を郵送や手渡しでやり取りするのは時間がかかり、緊急時の対応も遅れる可能性があるのです。
出典参照:医療情報連携ネットワーク支援ナビ(アーカイブ)|厚生労働省
電子カルテを導入し、地域のネットワークに参加することで、患者の同意のもと紹介先の病院が事前に診療情報を確認できるなど、よりスムーズで質の高い医療連携が実現します。

電子カルテには、いくつかの種類があります。2つの観点に分けて、それぞれ解説していきます。
電子カルテは、サーバー管理の方法によって以下の2種類に分類できます。
それぞれのメリット・デメリットを解説していきます。
クラウド型のメリットは、初期費用が安く、サーバー管理の手間がかからない点です。自院に高価なサーバーを設置する必要がなく、インターネット環境さえあれば導入できます。また、システムの保守や更新は提供会社がおこなうため、専門スタッフを置く必要がありません。
一方デメリットとして、月額利用料が発生し、カスタマイズの自由度が低い点が挙げられます。毎月の利用料を払い続ける必要があり、機能の追加や変更は提供会社のプランに依存します。
オンプレミス型のメリットは、自院の運用に合わせて自由にカスタマイズでき、他システムとの連携がしやすい点です。院内にサーバーを設置するため、独自の機能を追加したり、既存の検査機器と細かく連携させたりするなどの柔軟な対応が可能です。
一方デメリットは、高額な初期費用とサーバーの維持管理コストがかかる点です。最初に数百万円以上の導入費用がかかる場合が多く、サーバーを管理する専門知識を持った人材や、定期的なメンテナンスも必要になります。
電子カルテの種類によって、各診療科の業務内容に合わせて、よく使う病名や薬のセットや専門的な検査機器との連携など、診療をスムーズにするための特化機能が搭載されている場合があります。
たとえば、眼科用では、眼の検査機器で撮影した画像を直接カルテに取り込めます。また、整形外科用では、骨や関節のイラストに、患部の状態を直感的に描き込める機能が充実しているといった具合です。
こうした専門機能によって、各科の医師はより効率的に診療をおこなえます。

これから電子カルテを導入したいとお考えの医療関係者の方向けに、電子カルテ導入に伴うリスクと対策を以下の4点に分けて解説します。
詳しく見ていきましょう。
電子カルテの導入には、システム本体の費用だけでなく、パソコンやタブレットなど周辺機器の購入費や、スタッフの研修費といった様々な初期コストと、継続的な維持費がかかります。オンプレミス型では数百万円以上の初期投資が必要になるケースも珍しくありません。
対策としては、国や自治体が提供するIT導入補助金などを活用すると、費用負担を軽減できる場合があります。導入前に、利用できる補助金制度がないかを確認しておくのが賢明です。
出典参照:IT導入補助金|TOPPAN株式会社
電子カルテはネットワークに接続するため、不正アクセスやコンピューターウイルスによる情報漏洩、あるいはデータを人質にとるランサムウェアなどのサイバー攻撃を受けるリスクが常に伴います。そのため、最新のセキュリティソフトを導入し、常に最新の状態に保つのが基本です。
また、技術的な対策だけでなく、「不審なメールは開かない」「パスワードを使い回さない」といった、スタッフ一人ひとりのセキュリティ意識を高めるための継続的な教育も極めて重要となります。
サーバーの故障やネットワークの不具合、あるいはソフトウェアのバグなどによってシステムが停止すると、カルテの閲覧や会計ができなくなり、診療業務全体が止まってしまう可能性があります。
電子カルテのシステムを利用する際は、データのバックアップを定期的におこない、体制を整えておくのが大前提です。また、万が一の障害発生時に備え、一時的に紙で運用するなどの緊急時対応マニュアルを事前に作成し、スタッフ全員で共有しておくことが混乱を最小限に抑えるうえで重要です。
新しいシステムの操作に慣れていない導入直後は、かえって入力に時間がかかるなど、一時的に業務効率が低下し、スタッフの不満やストレスが増大する可能性があります。
システム移行期の混乱を最小限に抑えるには、導入前にトレーニング期間を確保する必要があります。操作に習熟するための研修会を複数回おこなったり、導入後しばらくはサポート担当者に常駐してもらったりするなどの対策が有効です。また、焦らずに定着させるための経営層の理解も求められます。

電子カルテにはさまざまなサービスがありますが、選定する際は以下6つのポイントを重点的に確認してください。
それぞれ解説します。
まずは、自院が抱える「待ち時間が長い」「会計業務が大変」といった具体的な課題を洗い出し、それを解決できる機能が搭載されているかを確認してください。
たとえば、電子カルテに付随して予約管理やWeb問診の機能があれば、受付業務の負担を大きく減らせます。また、レセプトコンピューター(医事会計システム)と一体型の製品を選べば、会計処理がスムーズになります。
多機能な製品に目を奪われず、自院の課題解決に直結する機能を見極めるのが大切です。
電子カルテは、入院設備のない無床診療所向けから、病床を持つ有床診療所や病院向けまで、規模に応じて機能が異なります。そのため、自院の規模に合った製品を選ぶことが大切です。
無床診療所であれば、外来診療に特化したシンプルな機能で十分な場合が多いです。しかし、有床診療所の場合は、入院患者の管理や看護支援、栄養管理といった専門的な機能が不可欠となります。
将来の規模拡大も視野に入れ、自院の現在と未来に合ったシステムを選びましょう。
毎日使うツールだからこそ、ITに不慣れなスタッフでもマニュアルをあまり見ずに、直感的に操作できる分かりやすい画面デザインであるかは極めて重要です。どんなに優れた機能があっても、操作が複雑で分かりにくいと、かえって業務効率を下げてしまいかねません。
電子カルテの導入前には必ずデモンストレーション版を体験し、実際に使う医師や看護師、事務スタッフの意見を聞きましょう。誰にとっても使いやすいことが、自院に電子カルテを定着させる鍵となります。
システムにトラブルはつきものなので、導入後の操作に関する問い合わせやシステム障害時に、電話やリモートですぐに対応してくれる手厚いサポート体制があるかを確認すべきです。
とくに、診療時間内にトラブルが発生した場合、迅速に対応してもらえないと診療が止まってしまいます。サポートの受付時間や対応方法(電話、メール、訪問など)、そして対応の評判などを事前にしっかり調べておくと、導入後も安心して運用を続けられるでしょう。
患者の命に関わる機密情報を扱うため、不正アクセスや情報漏洩、サイバー攻撃を防ぐためのセキュリティ対策が、国が定めるガイドラインに準拠しているかの確認も必須です。データが暗号化されているか、誰がいつ情報にアクセスしたかの記録が残るか、といった基本的な対策は必ず確認しましょう。
とくに、クラウド型の場合は、システムの提供会社がどのようなセキュリティ体制を敷いているかを詳しく確認する必要があります。
導入にかかる初期費用と、毎月の利用料や保守費用といったランニングコストを正確に把握し、IT導入補助金などの公的支援を最大限活用できるか十分に検討してください。システム費用だけでなく、パソコンの購入費やネットワーク工事費なども含めた総額で見積もりを取りましょう。
そのうえで、国や自治体が提供している補助金制度の対象となるかを確認し、申請をサポートしてくれる販売代理店を選ぶと、費用負担を大きく軽減できる可能性があります。

ここからは、おすすめの電子カルテサービスとして以下の5つをご紹介します。
システムの特徴を解説するので、ぜひサービス選定の参考にしてください。
エムスリーデジカルは、8年連続クラウド電子カルテシェアNo.1を獲得した、医師の声から生まれたクラウド型電子カルテです。最大の特長は、AIによる自動学習でカルテ記入時間を80%削減し、診療を大幅に効率化できる点です。
また、初期費用0円、月額11,800円〜の料金体系で、15年間で約1,000万円のコスト削減も期待できます。iPadやスマホ連携、多様な院内システムとの連携も充実しており、導入後の手厚いサポートプランも用意されています。日々アップデートを重ね、診療現場の「ラク」を追求し続ける、進化する電子カルテです。
Medicomシリーズは、1972年に日本初の医事コンピュータを発売して以来、医療IT分野を牽引するメディコムが運営する電子カルテです。クリニック、薬局、病院、健診事業者など多様な医療機関向けの製品・ソリューションを提供しており、特に電子カルテは一般診療所向けシェアNo.1を誇ります。
クラウド型・ハイブリッド型電子カルテ、医事コンピューター、Web予約・問診管理システムなど幅広いラインナップが特徴です。AIを活用した自動学習機能で入力時間を削減し、初期費用や更新費用を抑えることで、医療機関の業務効率化とコスト削減に貢献します。
手厚いサポート体制や、他社クラウドサービスと連携できるAPI提供により、医療DXを強力に推進します。
出典参照:メディコムパーク(メディコム公式) | ウィーメックス株式会社
CLIUS(クリアス)は、日本医師会標準レセプト「ORCA」と一体化したクラウド型電子カルテです。最大の特長は、AIオーダー推薦機能による直感的でサクサクとした操作性で、カルテ記入業務のストレスを軽減します。オンライン診療や在宅診療にも標準対応し、ミニマム開業から大規模医院まで多様なクリニックで導入実績があります。
300種類以上の豊富な機器・システム連携を誇り、Web予約や問診とのスムーズな連携で院内業務のDX化を支援。また、SaaS勤怠人事システム「ジョブカン」を運営するDONUTSが開発しており、ジョブカンシリーズとの割引連携も可能です。
手厚いサポート体制で、導入から運用まで安心して利用できる電子カルテです。
CLINICSカルテは、同社が提供する予約システムやオンライン診療システム「CLINICS」と完全に一体化しているのが最大の特徴で、オンラインと対面診療を両立したい医療機関に最適なクラウド型電子カルテです。予約から問診、オンライン診療、対面診療、そして決済まで、患者の一連の体験を一つのシステムで完結できます。これからオンライン診療に本格的に取り組みたい、あるいは患者サービスのデジタル化を推進したいと考えるクリニックにとって、非常に魅力的な選択肢です。
出典参照:CLINICSカルテ|株式会社メドレー
富士通のHOPE LifeMarkシリーズは、大中規模病院から精神科病院まで、幅広い施設規模に対応するクラウド型・オンプレミス型電子カルテサービスを提供しています。
特に、300床以上の大学病院向け「HOPE LifeMark-HX Cloud/HX/Type G」は、データ活用や連携を強化し、医療機関の課題解決と医療社会の実現に貢献。300床以下の中堅病院向け「HOPE LifeMark-MX」や、いつでもどこでも医療を支える「HOPE Cloud Chart II」も提供しています。
病院の課題や状況に合わせて、最適なサービスを選ぶことが可能です。
出典参照:病院様向けソリューション|富士通

電子カルテ導入を成功させるために、以下4つの流れに沿って導入を進めましょう。
順を追って解説していきます。
電子カルテ導入前に、なぜ電子カルテを導入するのかという目的を明確にし、その目的を達成するために「絶対に外せない機能」は何かという必須要件を定義します。たとえば、「受付業務の効率化」が目的なら、予約システムやWeb問診との連携が必須要件です。
この目的と要件が曖昧なままでは、製品選びの軸がぶれてしまい、導入後に「こんなはずではなかった」と後悔する原因になります。導入前に、時間をかけて目的と必須要件を固めることが重要です。
次に、ステップ①で定めた要件をもとに、複数の電子カルテサービスの資料請求やデモンストレーションをおこない、機能、費用、操作性などを多角的に比較検討します。
その際、一つの製品だけを見て決めてしまわないことが大切です。いくつかの製品を実際に見て、触ってみるとで、自院の診療スタイルに本当に合っているか、スタッフが使いこなせそうかといった点が見えてきます。
比較検討表などを作成し、客観的な視点で評価するのが、最適な製品を選ぶための近道となるでしょう。
導入する製品が決まったら、具体的な導入スケジュールや役割分担、研修計画などを盛り込んだ詳細な導入計画を策定し、関係するスタッフ全員に共有します。
電子カルテの導入は、医師だけでなく、看護師や事務スタッフなど院内全体の協力が不可欠です。いつまでに何を準備し、誰が責任者で、どのような研修をおこなうのかを明確にした計画を示します。
事前に全員で情報を共有し、目的意識を一つにしておくと、サービスの導入がスムーズに進みます。
最後に、紙カルテや旧システムから患者データを新しい電子カルテへ正確に移行するに伴い、いきなり全ての業務を切り替えるのではなく、段階的に運用を開始するのがスムーズな定着の鍵です。
過去の診療情報を正確に移行するのは、非常に重要かつ手間のかかる作業です。また、導入初日から全ての機能を完璧に使いこなすのは困難でしょう。
そのため、たとえば最初の1週間は新規の患者のみ新システムで対応するなど、徐々に慣れていく期間を設けるのが、現場の混乱を最小限に抑える賢明な方法です。

この記事では、電子カルテの役割から、導入のメリット・リスク、そして失敗しないための選び方と導入ステップまでを具体的に解説しました。
電子カルテの導入は、単なるペーパーレス化ではありません。医療の安全性を高め、スタッフの業務負担を軽減し、データにもとづく質の高い医療と効率的な経営を実現するための、未来への戦略的投資です。
確かに導入にはコストも労力もかかりますが、その価値は計り知れません。この記事で解説した内容を参考に、自院の課題を整理し、「どんな機能があれば理想のクリニックに近づけるか」を考えることから始めてみてください。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
