レガシーシステム統合で実現する医療DXのメリットとは?
医療

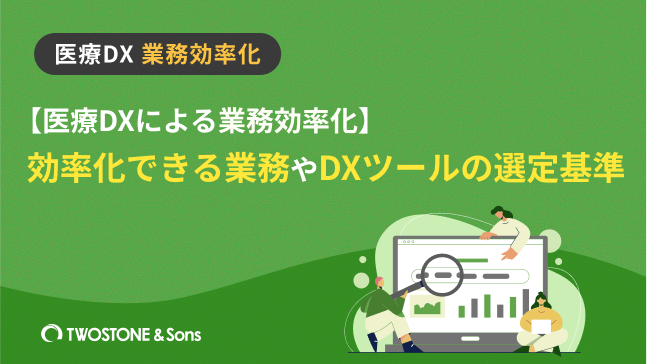
医療現場の人手不足やコスト高騰を解決するためのキーワードが、業務を効率化させる「医療DX」です。この記事では、医療DXによる具体的な業務効率化の方法を、受付や問診、会計といった業務エリアごとにおすすめのツールと合わせて徹底解説していきます。
患者の待ち時間が長引いたり、予約の電話がひっきりなしに鳴ったり、書類が山積みになったり…医療現場の慢性的な人手不足の中、「これ以上、現場の負担を増やせない」と頭を悩ませていませんか。その深刻な課題を解決するためのキーワードが、業務の無駄をなくし生産性を高める「医療DX」です。
この記事では、明日からでも検討できる、医療DXによる具体的な業務効率化の方法を、受付や問診、会計といった業務エリアごとにおすすめのツールと合わせて徹底解説していきます。
現場の労働環境を改善したいと考えている医療関係者の方は、ぜひ最後までご覧ください。

そもそも、医療現場ではなぜ業務が非効率になりがちなのでしょうか。それには、以下4つの構造的問題が関係しています。
詳しく解説します。
医療現場では、いまだに紙の書類や電話による受付、FAXでの情報伝達が多用されており、このアナログな文化が業務を煩雑にする大きな原因となっています。
たとえば、ほかの病院への紹介状をFAXで送り、届いたかどうかを電話で確認するといった二度手間が発生します。また、紙のカルテは保管場所から探し出すのに時間がかかり、同時に複数人での閲覧もできません。
こうした一つ一つの作業に費やされる時間が積み重なり、現場全体の生産性を大きく下げているのです。
医師や看護師をはじめとする医療従事者の慢性的な人手不足により、一人ひとりの業務量が増えています。
限られた人数で多くの患者に対応しなければならないため、日々の業務をこなすだけで精一杯になってしまいます。新しいデジタルツールを導入したり、業務プロセスを見直したりする時間的・精神的な余裕がありません。
その結果、非効率なやり方が改善されることなく業務をしなければならないという悪循環に陥っています。
医療は専門分野が細かく分かれているため、特定の業務に関する知識や情報が、「あの人でなければ分からない」という「属人化」の状態に陥りやすいです。
たとえば、ベテランの医療事務スタッフだけが知っている特殊なレセプト請求のルールや、特定の医師の頭の中にしかない申し送りの内容などが属人化にあたります。担当者が不在だったり退職したりすると、途端に業務が滞ってしまうリスクがあるのです。
日本の医療保険制度は、2年ごとに改定される複雑な診療報酬のルールに基づいており、その計算と請求業務が非常に煩雑なうえ専門知識を要するのが非効率の原因です。
おこなった診療行為の一つ一つを点数に換算し、定められたルールに従ってレセプトを作成する作業は、医療事務スタッフの大きな負担となっています。また、頻繁な制度改定に対応するための学習も常に必要です。

医療分野の業務効率化で注目される医療DXとは、デジタル技術を活用して、医療のあり方そのものを変革する取り組みです。単なるデジタル化にとどまらず、診療・事務作業の効率化、医療サービスの質の向上、患者の利便性向上を目指します。
ここからは、医療DXの具体的な概要と医療DXを取り入れるメリットについて解説していきます。
医療DXとは、単に紙をデジタルに置き換える「デジタル化」だけでなく、データを活用して新しい価値を生み出し、医療の仕組み自体を変革するのを目指す考え方のことです。主に、以下のような取り組みが挙げられます。
電子カルテに蓄積されたデータをAIが解析して病気の兆候を早期発見したり、オンライン診療で遠隔地の患者を診察したりするなど、これまでにない医療サービスを創出するのが医療DXのゴールとなります。
医療DXを取り入れるメリットとして、以下の6点が挙げられます。
一つずつ解説します。
医療DXによって、予約や受付、会計といった事務作業が自動化されることで、医療現場の業務効率を大幅に向上します。
たとえば、Web予約システムを導入すると、電話応対の時間を削減できます。また、電子カルテを使えば、カルテを探したり運んだりする手間がなくなり、医師や看護師は瞬時に必要な情報へアクセス可能です。
業務効率が大幅に向上することで、患者一人ひとりへの対応時間を増やすことができます。
医療情報がデジタル化されることで、正確かつリアルタイムな院内共有が可能になり、ヒューマンエラーを防ぎ、医療の質と安全性を高めます。たとえば、電子カルテに記録されたアレルギー情報が、処方時に医師や薬剤師の画面に警告として表示されると、危険な投薬ミスを未然に防ぐことが可能です。
また、AIがレントゲン画像を解析し、医師の診断をサポートする技術も実用化が進んでいます。デジタル技術が、医療の安全性をより強固にするのです。
医療DXは、紙のカルテやレントゲンフィルムの印刷・保管費用といった物理的なコストや、事務作業にかかる人件費削減に貢献します。
ペーパーレス化を進めると、紙代や印刷代はもちろん、カルテを保管するための広大なスペースも不要になります。
医療DXによるWeb予約やオンライン診療、自動精算機などの導入を通じて、患者の方の医療体験と満足度が向上します。
スマートフォンから24時間いつでも好きなときに予約が取れたり、診察後の会計待ちがなくなったりするのは、患者にとって大きなメリットです。また、オンライン診療が普及すると、通院の負担が軽減され、自宅で気軽に医師の診察を受けられます。
こうした医療体験が、患者から選ばれる医療機関となるための重要な要素となります。
医療DXによって無駄な事務作業を減らし、医療機関内の情報共有が円滑になることで、医師や看護師など従業員の業務負担が軽減され、労働環境の改善につながります。
たとえば、カルテの転記作業や書類探しといった単純作業がなくなると、スタッフは本来の専門性を活かせる対人業務により多くの時間とエネルギーを注げます。
医療DXは、患者の満足度を高めるだけでなく、従業員の就労満足度向上にもつながり、過重労働による心身の疲弊や離職を防ぐ効果が期待できるでしょう。
医療DXによって蓄積された診療データや経営データを分析すると、客観的な根拠に基づいた病院経営の改善をおこなえます。
たとえば、どのような疾患や年代の患者が多いのか、あるいはどの時間帯に混雑が集中するのかをデータで正確に把握できます。その分析結果をもとに、地域のニーズに合わせた新しい診療科を開設したり、スタッフのシフトを最適化したりするなど、勘や経験だけに頼らない戦略的な経営判断が可能になるのです。

医療DXでは、以下6つの業務エリアを効率化することが可能です。
それぞれ解説します。
Web予約システムや自動受付機を導入すると、電話応対や窓口業務の負担が減り、予約・受付業務を効率化できます。
患者はスマートフォンなどから24時間いつでも予約が取れるため、電話予約の必要がなくなります。また、来院時は自動受付機で診察券を読み込むだけで受付手続きが完了するのです。
このように医療DXを取り入れることで、予約から受付まで、患者はスムーズに医療サービスを受けられるようになります。
Web問診システムは、患者が来院前にスマートフォンなどで問診に回答できる仕組みです。院内での問診票の記入や内容の転記作業をなくし、問診業務を効率化します。
事前に回答された問診内容は、電子カルテに自動で取り込まれるため、看護師が内容を書き写す手間を省けます。さらに、AIが回答内容を分析し、医師が確認すべき重要なポイントを要約して提示するような高度なシステムも登場しており、診察の質向上にもつながります。
電子カルテは、診察情報をデジタルで一元管理し、カルテの検索や作成、共有にかかる時間を劇的に短縮するツールです。
紙のカルテを探しに行く必要がなく、パソコンの画面で瞬時に過去の診療履歴を確認できます。また、よく使う所見や処方をセットとして登録しておくと、数回のクリックで入力が完了します。医師がカルテ入力にかける時間を短縮できると、その分、患者と対話する時間を増やすことが可能です。
自動精算機やキャッシュレス決済を導入すると、会計スタッフが現金を扱う手間や計算ミスをなくし、患者の会計待ち時間を短縮できます。
診察が終わった患者は、自動精算機で診察券を読み込み、表示された金額をクレジットカードや電子マネーで支払います。また、会計スタッフにとっても、現金の取り扱いや一日の売上を締める作業の負担が大幅に軽減されるのです。
電子カルテと連携したレセプトコンピューター(レセコン)は、診療内容に基づいて診療報酬を自動で計算し、煩雑なレセプト(診療報酬明細書)作成業務を効率化することが可能です。
医師が電子カルテに入力した診療行為のデータが、自動でレセコンに反映され、複雑な点数計算がおこなわれます。とくに、日本医師会が提供する「ORCA」などと連携できるシステムは、多くの医療機関で利用されています。
院内用のビジネスチャットツールを導入すると、電話や口頭での伝言に頼ることなく、スタッフ間で確実かつ迅速な情報共有をおこなえます。
たとえば、「〇〇さんの検査結果が出ました」といった連絡や、全スタッフへの業務連絡などを、パソコンやスマートフォンから一斉に送信できます。口頭での伝言と違い、メッセージが記録として残るため、「言った、言わない」のトラブルを防ぐことが可能です。

ここからは、医療DXツールを選ぶ際に最も大切になる選定基準を5つに分けて解説していきます。
それぞれ解説します。
最も重要なのは、そのツールが自院が抱えている一番の課題を解決する機能を持っているかどうかです。たとえば、待ち時間短縮が最優先課題であれば、Web予約や自動受付の機能が充実している製品を選ぶべきです。
多機能であっても、自院の課題と関係ない機能ばかりでは意味がありません。まずは解決したい課題を明確にし、それを満たすツールは何か、という視点で選ぶのが成功の秘訣です。
毎日使うツールだからこそ、ITが得意ではないスタッフでも直感的に操作できる、シンプルで分かりやすい画面デザインであるかは非常に重要です。
どんなに高機能なツールでも、操作が複雑で分かりにくいと、現場で使われなくなり、宝の持ち腐れになってしまいます。導入を検討する際は、必ず複数のスタッフでデモ版を体験し、「これなら自分でも使えそう」と感じられるかどうか、現場の意見をしっかり聞くようにしましょう。
患者の個人情報を守るため、厚生労働省などが定める「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に準拠した、信頼できるセキュリティ対策が講じられているかを確認するのは必須です。
出典参照:医療情報システムの安全管理に関するガイドライン|厚生労働省
万が一の情報漏洩は、医療機関の信用を根底から揺るがします。セキュリティ対策は妥協せずおこなうようにしてください。
導入を検討しているツールが、現在使用している電子カルテやレセコンなど、ほかのシステムとスムーズにデータを連携できるかは、業務全体の効率を左右する重要なポイントです。
たとえば、Web予約システムの情報が、自動で電子カルテの予約表に反映されなければ、スタッフが手で入力する二度手間が発生してしまいます。それぞれのツールがバラバラに動くのではなく、互いに連携し、データが自動で流れる仕組みを構築できるか、事前にしっかり確認しましょう。
システム導入後に発生する操作の疑問やトラブルに迅速に対応してくれるサポート体制が充実しているかどうかも、安心して使い続けるために欠かせない基準です。
システムにトラブルはつきものです。とくに、診療時間中に問題が発生した際、すぐに対応してもらえなければ診療が止まってしまいます。
サポートの対応時間や連絡方法、そして実際に利用しているほかのユーザーからの評判などを確認し、信頼できるツールを選びましょう。
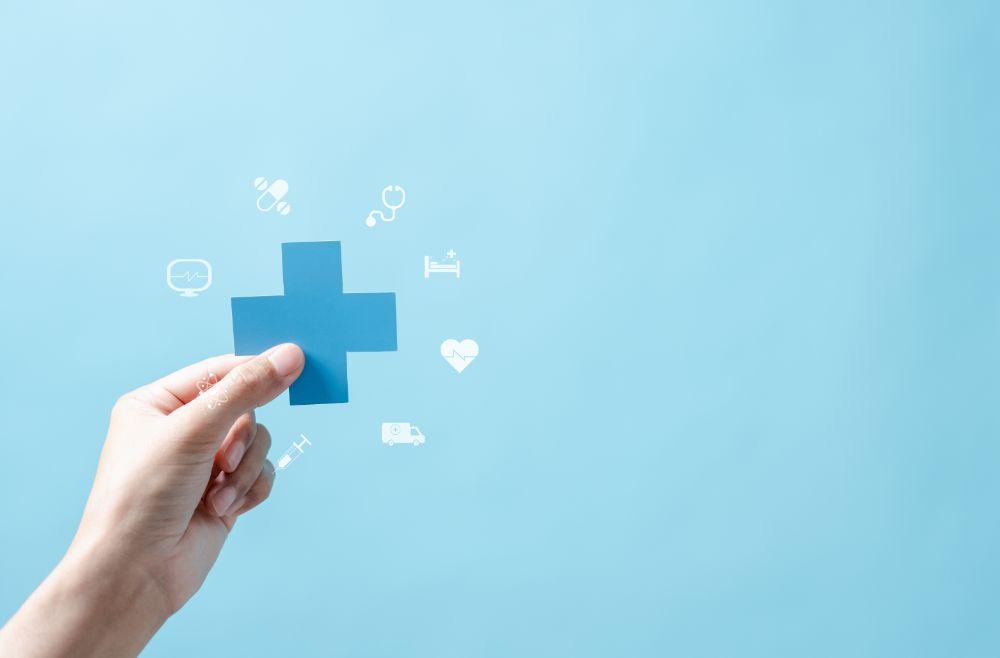
医療分野の業務効率化を実現するおすすめのDXツールカテゴリーとしては、以下4つのカテゴリーが挙げられます。
一つずつ見ていきましょう。
Web予約・問診システムは、患者が来院する前に予約や問診を済ませられるようにすることで、受付業務の負担を軽減するツールです。このツールを導入すれば、診察を希望する患者は24時間いつでもスマートフォンから予約できるようになります。
また、事前にWebで回答された問診内容は電子カルテに自動で反映されるため、患者が院内で問診票を書いたり、スタッフが内容を転記したりする手間がなくなります。
医療機関と患者双方にとって予約から診察までの流れが劇的にスムーズになるのが、Web予約・問診システムを導入する最大のメリットです。
クラウド型電子カルテは、初期費用を抑えつつ、院内のどこからでも情報にアクセスできる環境を構築する、業務効率化の中核となるシステムです。
高価なサーバーを院内に設置する必要がなく、インターネット経由でサービスを利用するため、とくに新規開業や小規模なクリニックでも導入しやすいのが特徴です。また、場所を選ばずにカルテを確認できるため、訪問診療やオンライン診療との相性も非常に良いといえます。
自動精算機やキャッシュレス決済システムは、会計窓口の混雑を緩和し、受付スタッフの業務を削減するのに非常に有効です。
患者が自ら会計をおこなえるため、窓口での待ち時間が短縮され、医療満足度の向上につながります。医療機関側にとっても、現金の数え間違いやレジ締めの作業といった負担が軽減され、よりスムーズで正確な会計業務が実現します。近年では、感染症対策の観点からも導入が進んでいます。
院内用のビジネスチャットなどのコミュニケーションツールは、スタッフ間の情報伝達を迅速かつ確実なものにし、伝言ミスや確認の手間をなくします。医師や看護師、事務スタッフなどが、パソコンやスマートフォンからリアルタイムにメッセージをやり取りできます。
たとえば、「〇〇さんの検査の件です」といった緊急でない要件を、相手の仕事を中断させずに伝えることが可能です。やり取りが記録として残るため、「言った、言わない」のトラブルを防ぐ効果もあります。

医療DXによる業務効率化を成功させるために、以下4つのステップを踏むようにしてください。
順を追って解説します。
最初のステップは、自院の「何が一番大変か」という現状の課題を洗い出し、「それをどう改善したいか」という具体的な目標を設定することです。
たとえば、「電話応対に追われて、ほかの業務に集中できない」という課題があれば、「電話の本数を一日あたり3割減らす」といった数値目標を立てます。この目的と目標が、数あるツールのなかから自院に本当に必要なものを選ぶための、最も重要な判断基準となります。
次に、実際にツールを使う医師や看護師、事務スタッフの意見を十分にヒヤリングし、現場の悩みを解決できるツールを選定しましょう。
経営層だけで選んだツールは、現場の運用に合わず、結局使われなくなったり使い方が浸透せず余計に業務を煩雑にしたりする可能性があります。ツールのデモンストレーションには必ず現場のスタッフにも参加してもらい、操作性や画面の見やすさを評価してもらってください。
全院で一斉に導入するのではなく、まずは一つの部署や特定の業務から小さく始め(スモールスタート)、その効果を検証してから、段階的に対象範囲を拡大していくのが失敗の少ない進め方です。
たとえば、まずはWeb予約システムだけを導入してみて、本当に電話応対の時間が減るのか、患者からの評判はどうか、といった効果を測定します。そこで得た手応えや改善点をもとに、次のツール導入へと進めることで、着実な業務改革が実現します。
新しいツールの導入を成功させるには、全スタッフがスムーズに使いこなせるようになるための丁寧な研修と、導入後に困ったときにすぐ相談できるサポート体制を構築することが不可欠です。ツールの提供会社による研修会はもちろん、院内でも操作方法を気軽に質問できる担当者を決めたり、分かりやすいマニュアルを整備したりする工夫が求められます。
導入して終わりではなく、全スタッフが安心して使いこなせるようになるまで、継続的にサポートする姿勢が大切です。

最後に、医療DXで業務を効率化したクリニックの例を、4つご紹介します。
内科クリニックでは、発熱患者やお子様を持つ親の対応を改善するため、オンライン診療と予約システムを導入しました。
WEB問診で患者の状態を事前に把握し、診療効率が向上したうえ、予約制の導入によって待機時間の大幅な削減につながったそうです。さらに、再診率や診療の流れも改善しました。医療DXツールの導入により、診療全体がスムーズになった事例です。
矯正歯科では、急患対応や患者負担軽減を目的に、2018年にオンライン診療が導入されました。
とくに、矯正治療のトレーニングをオンラインで実施することで、患者の負担を減らし、モチベーションを維持できるようになりました。患者からは「楽で嬉しい」と好評で、対面とオンラインを組み合わせたトレーニングが人気です。
また、診療後のフォローアップが充実しており、オンライン診療は働き方改革にも寄与しています。
精神科クリニックでは、急速に増加する患者に対応するため、2021年に精神科向けの電子カルテを導入しました。導入の決め手は、使い勝手の良さや汎用性、低コストであったことです。
電子カルテ導入後、患者数の増加にも対応でき、カルテ入力の時間や手間が大幅に削減され、業務効率が向上しました。特に、患者との情報共有が迅速になり、処方や会計がスムーズに進行。更に、医師と看護師間での情報連携も向上にもつながっています。
出典参照:メディコムパーク|ウィーメックス株式会社
皮膚科クリニックでは、感染症対策と業務効率化のため、2022年11月にセミセルフレジを導入しました。スタッフが少ないなか、業務負担を軽減し、現金のやり取りを避けることが導入の決め手です。
セルフレジの導入後、毎日の締め作業が正確でスムーズになり、スタッフのシフトにも余裕が生まれました。また、高齢者を含む多くの患者が簡単に使いこなすことができ、業務の効率化と患者対応の質向上に貢献しています。

この記事では、受付からスタッフ間の情報共有に至るまで、医療現場の様々な業務を効率化する医療DXツールと、その導入を成功させるためのステップを解説しました。
医療DXによる業務効率化は、単に時間を短縮するだけではありません。スタッフを煩雑な作業から解放し、患者と向き合う本来の業務に集中できる環境を作ります。そして、従業員の満足度と医療の質の向上に直結するのです。
まずは自院の業務で「一番時間がかかっている」ボトルネックを一つ見つけ、それを解決するツールを検討することから始めてみてください。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
