レガシーシステム統合で実現する医療DXのメリットとは?
医療

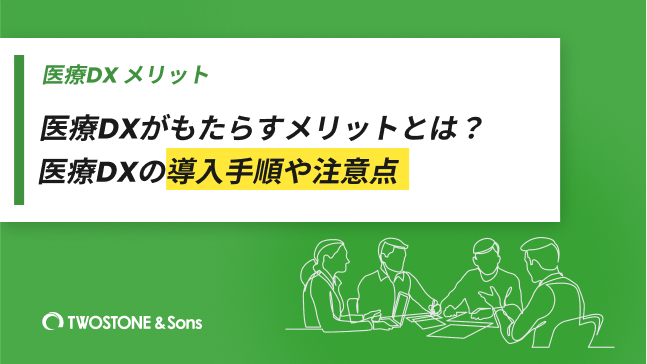
「医療DXが重要とは聞くけれど、具体的にどんなメリットがあるの?」と疑問に思っていませんか?この記事では、医療DXがもたらすメリットを、患者、現場の医師・スタッフ、そして医療機関の経営層という3つの立場から、具体的かつ多角的に解説します。
スタッフの疲弊やいまだに多いアナログ業務。多くの医療機関が抱えるこれらの根深い課題を解決する鍵として、今「医療DX」に大きな注目が集まっています。ですが一方で、「医療DXが重要とは聞くけれど、具体的にどんなメリットがあるの?」と疑問に思っていませんか?
そこでこの記事では、医療DXがもたらす恩恵を、患者、現場の医師・スタッフ、そして医療機関の経営層という3つの立場から、具体的かつ多角的に解説します。
医療の現場や経営に課題を感じている医療関係者の方は、ぜひ最後までご覧ください。

まずは、医療DXの定義と、医療業界が抱える5つの課題について解説していきます。
医療分野におけるDXとは、単に情報を電子化するだけでなく、そのデータを活用して新しい診断法や治療法を生み出し、一人ひとりの患者に最適な医療を提供するのが目的です。
たとえば、紙のカルテを電子カルテに置き換えるのは単なる「デジタル化」にすぎません。医療DXはさらにその先の、蓄積されたデータをAIで解析して病気の予測をおこなったり、オンラインで診察から薬の受け取りまでを完結させたりするなど、医療の仕組み自体を変革する取り組みを指します。
近年医療DXの注目度が高まっているのは、以下のような医療業界が抱える課題が浮き彫りになっているためです。
それぞれ解説します。
現在の医療業界は、人材不足と過重労働の問題が深刻化しています。
とくに、医師や看護師をはじめとする医療従事者の慢性的な人材不足は深刻で、現場の一人ひとりが過重な労働を強いられており、医療の質や安全の維持が危ぶまれています。
長時間労働が当たり前となり、心身ともに疲弊してしまうスタッフがあとを絶たないのが大きな問題です。
ほかの産業に比べて、医療分野ではいまだに紙の書類やFAXでのやり取りが多く、デジタル化の遅れが業務の非効率や情報共有の障壁となっています。
たとえば、他の病院への紹介状を郵送やFAXで送ったり、検査結果を手でカルテに書き写したりする作業に、多くの時間と手間が費やされているのです。これにより、迅速な情報連携が妨げられ、結果的に医療サービスの提供が遅れる原因にもなっています。
都市部と地方では、アクセスできる医療機関の数や専門医の数に大きな差があり、住んでいる場所によって受けられる医療の質が変わってしまう「医療格差」が問題となっています。
地方やへき地に住む人々は、専門的な治療を受けるために、都市部まで長時間をかけて移動しなければならない場合が多いです。また、高齢により移動が困難な方々が、必要な医療サービスを受けられないケースも増えており、公平な医療アクセスの確保が課題です。
人口減少や社会保障費の抑制といった社会背景のもと、多くの医療機関、とくに中小規模の病院や診療所は厳しい財政状況に直面しています。
最新の医療機器への投資や、人材確保のための人件費は年々増加する一方、診療報酬は抑制傾向にあることが、医療機関の経営を圧迫しています。その結果、必要な設備投資やサービスの改善がおこなえず、医療の質の低下につながる懸念があるのです。
医療情報は極めて重要な個人情報であるため、デジタル化を進めるうえで、サイバー攻撃による情報漏洩やプライバシーの侵害に対する懸念が大きな課題となっています。
電子カルテなどのシステムが外部からハッキングされた場合、患者個人の病歴や疾患など非常に繊細な情報が流出する恐れがあります。そのため、デジタル化の推進と同時に、データを安全に守るための高度なセキュリティ技術や、厳格なルール作りが不可欠とされているのです。

では、医療DXの導入にはどのようなメリットがあるのでしょうか。ここからは、以下3つの立場別に、医療DXを取り入れていくメリットを解説します。
それぞれ見ていきましょう。
医療DXの導入は、患者にとって以下3つのメリットが生まれます。
詳しく解説します。
医療DXは、Web予約やオンライン診療、自動精算機などを通じて、病院での待ち時間を大幅に短縮し、通院にかかる身体的・時間的な負担を軽減します。
たとえば、スマートフォンで予約から決済まで済ませられることで、院内での滞在時間が短くなります。また、オンライン診療を利用すると、自宅にいながらでも診察を受けられるため、通院そのものの負担がなくなります。
電子カルテによる正確な情報共有やAIによる診断支援は、人為的なミスを減らし、医療の質と安全性を大きく向上させます。医師や看護師がリアルタイムで同じ情報を確認できるため、指示の伝達ミスの防止にもなります。
また、過去の膨大な医療データを学習したAIが、レントゲン画像から微細ながんの兆候を見つけ出すなど医師の診断をサポートする技術も進んでおり、より精度の高い医療サービスの提供が可能です。
医療DXによって、個人の遺伝子情報や生活習慣データを活用し、一人ひとりに最適な治療法や薬を選択する「個別化医療」の確立が進みます。これまでの「多くの人に効く標準的な治療」から、一人ひとりの体質や病気の特性に合わせた、オーダーメイドの治療へと進化するのです。
これにより、治療効果を最大限に高めると同時に、副作用のリスクを最小限に抑えるなど、より質の高い医療の実現が期待されています。
次に、医療DXによる医師・スタッフにとってのメリットとして以下の3点を解説します。
それぞれ確認してください。
電子カルテや各種自動化ツールは、手書きの書類作成やカルテの検索、会計業務といった時間のかかる事務作業を大幅に削減します。
たとえば、Web問診システムを導入すると、患者によって入力された情報が自動でカルテに反映されるため、スタッフによる転記作業が不要です。こうした事務作業の負担が軽減されると、医師やスタッフによって、より専門性の高い医療サービスの提供に多くの時間を充てられるようになります。
院内の情報がデジタルで一元管理されることで、医師や看護師、スタッフ間での情報共有がリアルタイムで正確に行われ、チーム医療の質が向上します。
電子カルテを利用すれば、誰でも患者の状態を即座に確認でき、ビジネスチャットを活用することで、院内のどこにいても迅速な連携が可能になります。
医療DXの導入により、医療現場での働き方改革が実現します。デジタル技術を活用することで、業務の効率化が進み、医師や看護師の負担が軽減されるためです。
たとえば、電子カルテの導入により、紙ベースでの記録管理が不要になり、情報の共有が迅速かつ正確になります。また、オンライン診療やリモートワークの導入により、患者対応の柔軟性が向上し、勤務時間や場所の選択肢も広がります。
これにより、スタッフのワークライフバランスが向上し、医療の質も向上するという相乗効果が期待されます。
医療DXの導入は、医療機関の経営にとっても大きなメリットがあります。主に以下の4点です。
一つずつ解説します。
ペーパーレス化による消耗品費や保管コストの削減、また業務自動化による人件費の最適化など、医療DXは直接的なコスト削減と生産性向上に貢献します。
紙のカルテやレントゲンフィルムが不要になると、印刷代や保管スペースのコストが削減可能です。また、受付や会計業務を自動化することで、より少ない人数で効率的に業務を回せるようになります。
これにより、医療機関全体の生産性が向上し、経営体質の強化につながります。
蓄積された診療データや経営データを分析すると、「どの診療科が伸びているか」などを客観的に把握し、勘や経験に頼らないデータにもとづいた経営改善を実行できます。
たとえば、来院患者の地域や年齢層、疾患の傾向などをデータで分析すると、地域の医療ニーズを正確に捉えられます。そのデータをもとに、設備投資の優先順位を決めたり、新しい診療サービスを企画したりするなど、的確な経営戦略を立てられるようになるのです。
医療DXの導入によって患者満足度が高まると、地域におけるクリニックの評判が高まり、ほかの医療機関との差別化を図るなど、競争力の強化と増患につながります。
Webで簡単に予約が取れたり、オンラインで診察を受けられたりする医療機関は、患者にとって魅力的です。利便性の高いサービスを提供しているという事実そのものが、クリニックのブランド価値を高め、新しい患者を惹きつける力となります。
適切なデジタルツールを導入すると、誰がいつ情報にアクセスしたかの記録が残るため、紙媒体よりもかえって情報管理のガバナンスが強化され、セキュリティレベルが向上します。
また、紙のカルテは、誰でも手に取れてしまう可能性がある一方、電子カルテであれば、役職に応じて閲覧権限を細かく設定したり、アクセス履歴をすべて記録したりすることも可能です。
これにより、不正な情報の持ち出しなどを防ぎ、厳格な情報管理体制を構築できます。

医療DXの導入手順は、以下の通りです。
順を追って解説します。
最初のステップは、「なぜ医療DXをおこなうのか」という目的と、「今、何に一番困っているのか」という自院の課題を明確に言語化することです。
たとえば、「スタッフの残業時間を減らしたい」という目的を掲げ、「電話応対と書類作成に時間がかかりすぎている」という具体的な課題を特定します。この目的が全ての判断基準となるため、院長だけでなく、現場のスタッフも交えて議論し、全員の共通認識を揃えることが重要となります。
次に、患者の来院からお会計までの業務の流れを一つ一つ書き出して「可視化」し、どこに問題があるか、どの部分をデジタル化すれば最も効果的かを判断します。
受付、問診、診察、会計といった各段階で、「誰が」「何を」「どのように」おこなっているかを洗い出してください。すると、「ここの手作業に一番時間がかかっている」といった非効率な部分が明確になります。そのボトルネックを解消できる領域を、優先的に医療DXの対象とするのがベストです。
DX化する領域が決まったら、それを解決するのに最適なツールを複数比較検討のもと選定し、具体的な導入スケジュールや担当者を決めた計画を策定します。
たとえば、受付業務の効率化が目的なら、複数のWeb予約システムの機能や料金を比較します。そして、導入するツールが決まったら、「いつまでに何を準備し、誰が責任者で、どのような研修をおこなうか」という詳細な計画書を作成します。
計画を事前にしっかり立てることが、導入の混乱を防ぐ鍵です。
導入を開始するときは、まず一つの部署や特定の業務からスモールスタートで試験的に導入し、本当に効果があるのかを検証しましょう。
たとえば、新しいWeb問診システムを、まずは午前中の新患の患者だけに使ってみる、といった方法です。そして、実際にスタッフの入力時間が短縮されたか、患者からの評判はどうか、といった効果を測定します。
全体でトラブルを起こさないよう、本格的な導入の前に段階的に導入していくことがおすすめです。
試験導入で効果を確認できたら、全院へ本格的に導入を開始します。導入後も定期的に効果を測定しながら、さらに改善を続けていくことが重要です。
医療DXツールの導入は、ゴールではなくスタートです。実際に運用してみると、「もっとこうすれば使いやすい」といった新たな改善点が見えてきます。スタッフから定期的にフィードバックを集め、ツール設定の見直しや運用ルールの改良を継続しましょう。
医療DXを導入するうえで、以下4つの注意点とその対策を理解していく必要があります。
それぞれ解説します。
医療DXの推進には、システムの導入費用だけでなく、毎月の利用料や保守費用といった継続的な運用コストがかかります。そのため、長期的な視点での資金計画が必要です。
国や自治体が中小規模の医療機関向けに提供している「IT導入補助金」などの支援制度を積極的に活用するのが有効です。
出典参照:IT導入補助金|TOPPAN株式会社
自院が補助金の対象となるか、どのような経費が補助されるのかを事前に情報収集し、申請を検討しましょう。
医療情報をデジタルで扱う以上、サイバー攻撃による情報漏洩のリスクは常に存在するため、従来以上に強固なセキュリティ対策を講じる必要があります。そのため、厚生労働省のガイドラインに準拠した、信頼性の高いシステムを選ぶようにしてください。
出典参照:医療情報システムの安全管理に関するガイドライン|厚生労働省
それに加え、スタッフ一人ひとりのセキュリティ意識の向上も不可欠となります。「不審なメールは開かない」「パスワードは定期的に変更する」といった基本的なルールを徹底するための研修を定期的におこないましょう。
導入したツールを全スタッフが有効に活用するためには、一定のITリテラシーが必要となり、ITに不慣れなスタッフへの教育が不可欠です。導入前に十分なトレーニング期間を設けるようにしてください。
また、院内にITツールに詳しい担当者をリーダーに任命し、ほかのスタッフからの質問に答えられる体制を作ると、現場での定着がスムーズに進みます。全員で学び、助け合う雰囲気作りが成功の鍵です。
デジタルツールの導入は、スマートフォンやパソコンの操作が苦手な高齢の患者などが、必要な医療サービスから取り残されてしまう「デジタル格差(デジタルデバイド)」を生む可能性があります。そのため、デジタルツールを導入した後も、必ず従来通りのアナログな選択肢を残しておくべきです。
たとえば、Web予約を基本としつつも、必ず電話予約の枠も確保しておく、といった配慮が求められます。誰一人取り残さない姿勢が、地域医療には不可欠です。

最後に、医療DX導入で実現できる具体的な業務効率化の例を5つご紹介します。
それぞれ見ていきましょう。
Web予約・問診システムによって、患者が来院前に予約や問診を済ませられるようにすることで、受付スタッフの電話応対や事務作業を大幅に削減します。
また、事前にWebで回答された問診内容は電子カルテに自動で取り込まれるため、患者が院内で問診票を書いたり、スタッフが内容を転記したりする手間がなくなります。
電子カルテは、患者情報をデジタルで一元化し、院内の誰でも瞬時に最新情報を共有できるため、診療の質と安全性を向上させます。
医師の診察内容、看護師の記録、検査結果などがリアルタイムで共有されると、スタッフ間のスムーズな連携が可能です。手書きの文字の読み間違いや、口頭での伝達ミスといったヒューマンエラーを防げるため、より安全な医療の提供につながります。
また、過去の診療履歴もすぐに参照でき、的確な診断をサポートします。
クラウド型の医用画像管理システムなどを活用すると、院内で撮影したCTやMRIの画像を、遠隔地にいる専門医に送り診断を依頼する「遠隔読影」が可能になります。放射線診断の専門医が常駐していない中小規模の病院や診療所でも、質の高い画像診断を受けられるようになるのです。
遠隔読影があれば、患者はわざわざ専門医のいる大病院まで足を運ぶ必要がありません。地域による医療格差を是正し、病気の早期発見に貢献する重要な技術です。
オンライン診療やオンライン服薬指導は、患者が自宅にいながら診察や薬の説明を受けられるようにし、通院の負担を軽減します。
体が不自由な方や、子育て・仕事で忙しい方、あるいは遠隔地にお住まいの方でも、スマートフォン一つで気軽に医師による診察を受けられます。これにより、これまで通院をためらっていたような人々にも医療を届けられるようになり、病気の重症化予防や、継続的な治療のサポートがしやすくなるのです。
自動精算機やキャッシュレス決済を導入すると、会計窓口での現金のやり取りや待ち時間がなくなり、患者と会計スタッフ双方の負担を軽減します。
診察が終了した患者は、自動精算機で診察券を読み込み、表示された金額をクレジットカードなどで支払うだけです。また、スタッフは現金の管理やレジ締めの作業から解放され、業務の正確性が向上します。

この記事では、医療DXがもたらすメリットを、患者・スタッフ・経営という3つの視点から解説しました。
医療DXの真価は、業務の効率化によって生まれた余裕が、スタッフの働きがいと医療の質の向上につながり、それが患者満足度と経営の安定を生み出すという「価値の好循環」を創出する点にあります。
導入にはコストも労力も伴いますが、それは未来への「費用」ではなく、持続可能な医療を実現するための「投資」です。まずは自院の課題と向き合い、どうしたらその課題を解決できるのか、最適な医療DXの方法を検討してみてください。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
