不動産DXアプリが必要な理由 | DXアプリ導入で得られるメリット
不動産
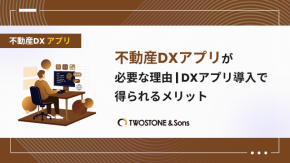
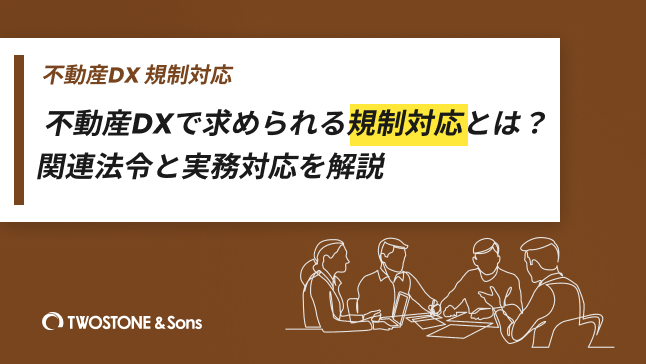
不動産DXを進めるうえで求められる規制対応について、関連法令の概要と実務上の注意点をわかりやすく解説します。
不動産業界でも急速に進むDX(デジタルトランスフォーメーション)。しかし、便利な電子契約やクラウド活用の裏には、複雑化する法規制への対応が欠かせません。
電子帳簿保存法や個人情報保護法、さらには宅建業法の改正など、無視できない法的リスクが多岐にわたっています。
本記事では、不動産DXを円滑に進めるうえで把握すべき主要な規制と、実務で気をつけるべきポイントをわかりやすく解説します。

不動産DXにおける規制対応は、業務効率化と顧客満足度向上に貢献しながら、法令遵守を徹底する重要な要素です。電子契約の導入が進んでいる一方で、個人情報保護やデータセキュリティの確保も重大な課題です。これらの規制対応を適切に行うことが、企業の信頼性を高め、事業運営のリスクを軽減させます。
不動産業界では、デジタル化の進展により契約書類の電子化やオンライン取引が進み、業務効率化が実現しています。宅地建物取引業法改正により、重要事項説明書や売買契約書、媒介契約書などの書類を電子データで交付できるようになり、取引の迅速化が図られています。これにより、顧客の利便性が向上し、企業にとっても業務負担の軽減が達成されています。
一方で、デジタル化の進展に伴い、個人情報保護法やデータセキュリティに関する規制に適切に対応することが不可欠です。顧客情報をオンラインで取り扱う際には、サイバー攻撃や内部不正、誤操作による情報漏洩のリスクが高まります。これを防ぐためには、適切なセキュリティ対策と情報管理体制の強化が求められます。
不動産DXの規制対応は、業務効率化とリスク管理を両立させるために不可欠な取り組みです。法令に基づいた規制遵守を徹底し、顧客の信頼を得るためには、企業全体での情報セキュリティ意識の向上が重要となります。
引用元:デジタルトランスフォーメーション推進レポート|経済産業省
引用元:宅地建物取引業法 法令改正・解釈について|国土交通省

不動産業界では、業務効率化や顧客体験向上を目的としたデジタルトランスフォーメーション(DX)が急速に進展しています。
この変化には、法改正や社会情勢の変化が影響しており、業界のデジタル化を加速させる要因となっています。
・デジタル社会実現に向けた法整備
・IT重要事項説明の解禁
・電子契約の普及
・「囲い込み」規制の強化
・不動産登記法改正
・建築基準法改正
ここでは、上記6つの観点から解説していきます。
不動産関連法の改正により、書面化義務の緩和や押印義務の廃止が進められました。これにより、重要事項説明書や契約書類の電子化が可能となり、オンラインでの取引完結が促進されています。
これらの法整備は、不動産業界のデジタル化を支える重要な基盤となり、業務の効率化と顧客の利便性向上に寄与しています。
引用元:電子帳簿保存法|経済産業省
従来、対面で行う必要があった重要事項説明が、IT技術を活用してオンラインで実施できるようになりました。
この改正により、遠隔地の顧客との取引がスムーズに行えるようになり、複数拠点での業務効率も向上しました。オンラインでの重要事項説明は、不動産業務の透明性を高め、契約プロセスを大幅に迅速化しています。
電子契約の導入が進み、従来の書面契約に比べて印紙税の削減や契約手続きの迅速化が可能となりました。
不動産取引がオンラインで完結することが容易になり、事業者にとっても時間とコストの削減が実現しています。特に契約のデジタル化は、不動産業務における効率性を飛躍的に高める要因となっています。
引用元:電子署名法|法務省
不動産取引における「囲い込み」行為に対する規制が強化され、取引状況の正確な登録と情報開示が義務化されました。
不動産業者は取引情報を正確にレインズ(不動産流通標準システム)に登録しなければならなくなり、取引の透明性が大きく向上しました。DXツールを活用することで、情報の管理と共有が迅速かつ正確に行われ、業界全体の信頼性が向上しています。
引用元:不動産流通標準システム(レインズ)|東日本不動産流通機構
不動産登記法が改正され、相続登記の義務化や住所変更登記の義務化が進行しています。これらの法改正は、所有者不明土地問題を解決するための重要な措置であり、不動産情報のデジタル化やシステム間の連携が求められます。
特に、2025年4月から始まる「スマート変更登記」の導入により、登記手続きがさらに効率化される見込みです。
引用元:スマート変更登記|法務省
建築基準法の改正により、すべての新築建物に対して省エネ基準への適合が義務付けられました。この改正は、建築確認手続きの中で適合性検査が行われることを意味しており、建築設計や施工におけるデジタル化が加速しています。
また、省エネ基準への適合を確実にするためには、設計段階からのデータ連携が不可欠であり、DXの推進が重要な役割を果たしています。
引用元:建築基準法改正|国土交通省

不動産DXを推進するためには、法令遵守を徹底し、規制に適切に対応することが欠かせません。特に、業界のデジタル化を加速するためには、法改正に基づいた正確な対応が求められます。
・宅地建物取引業法関連
・個人情報保護法
・不動産登記法関連
それぞれ解説していきます。
宅地建物取引業法(宅建業法)は、不動産業界における基盤となる法律であり、DX推進における重要な規制の一つです。
この法律に基づく規制変更に迅速に対応することで、不動産業者は法令遵守と業務の効率化を同時に実現できます。これにより、業務効率化と信頼性の向上が達成され、顧客との長期的な信頼関係を築くことが可能です。
2022年の法改正により、重要事項説明書や契約書類の電子交付が認められ、オンラインでの取引が可能となりました。
この改正により、遠隔地にいる顧客との契約や、複数拠点での業務が効率化されました。これにより、顧客利便性の向上と業務負担軽減が実現し、顧客のロイヤリティ向上にもつながります。また、適切なセキュリティ対策を講じることは、トラブル回避とコスト削減にも寄与します。
不動産売買における「囲い込み」行為に対する規制が強化され、取引状況の正確な登録と情報開示が義務化されました。不動産業者はレインズ(不動産流通標準システム)に取引情報を迅速かつ正確に登録する必要があります。
これにより、業界全体の信頼性向上と情報共有の迅速化が実現し、顧客満足度の向上に繋がります。また、効率的な情報連携が可能となり、法令遵守の徹底とトラブル回避が実現します。
従業者名簿の記載ルールが改正され、旧姓併記や宅地建物取引士の氏名記載が不要になるなど、簡素化されました。個人情報保護の観点から、名簿の適切な管理が求められています。
これにより、法令遵守の強化と同時に、名簿管理が効率化され、業務負担の軽減が実現されます。デジタルシステムを活用することで、業務効率化とコスト削減が達成できます。
個人情報保護法では、顧客の個人情報を適切に管理・利用する義務が定められています。これに違反した場合には、罰金や損害賠償請求、さらには企業の信用低下といった重大なリスクが生じます。
適切な情報管理を徹底することは、顧客の信頼を得るために不可欠です。また、最新のセキュリティ技術を導入し、データ漏洩のリスクを減少させることで、トラブル回避とコスト削減に寄与します。
不動産登記法の改正により、登記手続きのデジタル化が進んでいます。この改正により、登記情報の管理が効率化され、業務の迅速化と透明性の向上が期待されます。
特に、相続登記や住所変更登記の義務化が進んでおり、企業の効率化と顧客満足度向上に貢献しています。また、法的リスクの回避により、業務運営のコスト削減が可能です。
不動産の相続により所有権を取得した相続人は、相続を知った日から3年以内に相続登記を申請しなければならないことになりました。
不動産事業者は取引の際に相続登記の状況を確認し、顧客への情報提供やサポート体制を強化する必要があります。これにより、顧客サービスの質向上と業務効率化が実現し、顧客満足度の向上と業務負担の軽減が達成されます。
不動産の所有者が住所を変更した場合、変更後2年以内に住所変更登記を申請しなければならない義務が課されています。
この改正により、顧客への適切な情報提供や住所変更登記のサポートが求められます。これにより、顧客満足度の向上と業務の迅速化が実現され、トラブル回避とコスト削減にも寄与します。2025年4月からは、スマート変更登記の導入により、登記手続きがさらに効率化されます。

不動産DXの推進により、業務の効率化や利便性の向上が期待される一方で、法的リスクの顕在化も進んでいます。
・電子契約の不備による契約無効リスク
・不動産登記法改正に伴う遅延登録による罰則
・個人情報保護法違反による罰金や訴訟リスク
・「囲い込み」規制違反による行政処分や罰則
・クラウドシステムにおけるデータ漏洩リスク
電子契約やクラウドサービスの活用が拡大する中で、契約の無効や情報漏えいといった具体的なリスクに備えることが不可欠です。
電子契約の導入にあたって、法的要件を満たしていない場合は、契約が無効と判断されるおそれがあります。
たとえば、顧客の同意を適切に取得していない場合や、電子署名やタイムスタンプなど必要なセキュリティ措置が不十分な場合には、契約の効力が認められない可能性があります。
特に不動産取引のような高額かつ重要な契約では、事前に電磁的方法による交付の同意を得る手続きの厳格な運用や、改ざん防止措置の実施が重視されます。形式的な不備が取引全体の信頼を損ね、再交渉や訴訟といったトラブルに発展するリスクがあります。
不動産登記法の改正により、相続登記や住所変更登記の申請が義務化されました。これらの登記を所定の期間内に行わない場合、過料が科される可能性があります。
たとえば、相続を知った日から3年以内に相続登記を申請しなかった場合、最大10万円の過料が発生します。住所変更登記も変更から2年以内の申請が義務づけられており、違反時には同様の行政処分が適用されます。
不動産会社においては、登記状況の適切な確認と顧客への情報提供、さらに登記手続きの支援体制を整えることが、法的リスクの軽減に直結します。
個人情報保護法では、顧客の個人情報を適切に管理・利用する義務が定められています。これに違反した場合には、罰金や損害賠償請求、さらには企業の信用低下といった重大なリスクが生じます。
たとえば、顧客の同意を得ずに個人情報を第三者に提供した場合や、管理体制の不備によって情報漏えいが発生した場合には、法的責任を問われる可能性があります。
不動産業界では、住所・年収・家族構成など、機微な情報を多く取り扱うため、利用目的の明確化、同意取得、アクセス制限の徹底、定期的な監査など、厳格な情報管理体制が求められます。
不動産業界においては、公正な取引を確保するため、「囲い込み」行為に対する規制が強化されています。たとえば、レインズへの取引情報を正確に登録しない、売主に対して適切な取引状況の説明を行わないといった行為は、行政処分や業務停止命令の対象となるおそれがあります。
2022年以降、囲い込み行為は明確に処分対象とされており、コンプライアンスの徹底が求められています。業務プロセスにおいては、情報共有体制の構築や、対応履歴の記録・保存を行うことで、リスクを未然に防ぐことが可能です。
クラウドシステムの導入によって、不動産業務の柔軟性や効率性が向上する一方で、データ漏えいのリスクも増加しています。
とくに、セキュリティ対策が不十分なクラウドサービスを利用した場合には、顧客情報や契約情報などの重要データが外部に漏れる可能性があります。
このような事態は、個人情報保護法に違反する恐れがあり、罰金や訴訟リスク、社会的信用の失墜に直結します。不動産業者は、ID・パスワードの厳格な管理、多要素認証、アクセス権限の明確化、バックアップ体制の整備、インシデント対応計画の策定など、包括的なセキュリティ対策を講じる必要があります。

不動産DXを推進するには、各種規制や運用体制への対応を見据えた事前準備が欠かせません。
デジタル技術を活用した業務改革には、以下のような多方面からの取り組みが必要です。
・法令遵守体制の構築
・既存業務フローの見直し
・デジタル人材の育成と確保
・情報連携とデータ活用
・顧客体験の向上
それぞれ解説します。
DX推進においては、関係法令やガイドラインを踏まえたコンプライアンス体制の整備が最優先事項です。法改正や規制強化に迅速に対応できる体制を整えることで、企業の信頼性を維持できます。
具体的には、宅地建物取引業法、電子帳簿保存法、個人情報保護法などの動向を定期的に確認し、社内規定やマニュアルに反映する仕組みを構築しましょう。専門家と連携しながら、継続的にコンプライアンス体制を強化する姿勢が重要です。
DXの効果を最大化するには、従来の業務フローを前提にせず再設計することが不可欠です。アナログの手続きに依存したままでは、デジタル技術の利点を活かせません。
たとえば、紙ベースの契約業務や手動での情報共有は、電子契約やクラウドシステムを活用することで大幅な効率化が可能です。システム導入とあわせて、業務手順全体の抜本的な見直しを進めましょう。
DXを継続的に推進するには、現場で実務を担う人材のスキル向上と、新たな専門人材の確保が重要です。
単にシステムを導入するだけでは十分な成果に結びつきません。業務にデジタル知識を活かせる人材を育てるためには、OJT、外部研修、eラーニングの活用が効果的です。また、高度な専門性を持つエンジニアやデータ分析担当者については、外部採用も視野に入れた戦略的な人材確保が求められます。
部門間や外部機関との情報連携を強化することで、業務効率化と顧客サービスの質向上が期待できます。たとえば、不動産IDや物件情報の共通化により、営業、契約、管理などの各部門でデータを一元的に活用できるようになります。一方で、連携が進むほどセキュリティやプライバシー保護の重要性が増すため、技術的な安全対策とあわせて、内部統制やガバナンス体制の強化も必要です。
DXの取り組みは、最終的に顧客の利便性や安心感の向上につながるものでなければなりません。オンライン接客やチャットボットによる対応、電子契約の導入により、非対面でも円滑なサービス提供が可能となります。
また、顧客の行動データを分析し、最適な提案を行うことで、体験価値の向上と顧客満足度の強化が図れます。業務効率化と並行して、顧客接点の質を高める取り組みを進めましょう。

不動産DXを推進するうえでは、電子契約やクラウドの活用といった技術面だけでなく、法令遵守・業務フローの見直し・人材育成など、組織全体の体制づくりが求められます。
宅建業法や電子帳簿保存法、個人情報保護法といった関連法令の正確な理解と運用に加え、顧客体験の向上や情報セキュリティにも対応する必要があります。持続的にDXを進めるには、法規制への対応を経営課題として捉えることが重要です。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
