不動産DXアプリが必要な理由 | DXアプリ導入で得られるメリット
不動産
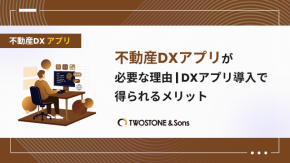
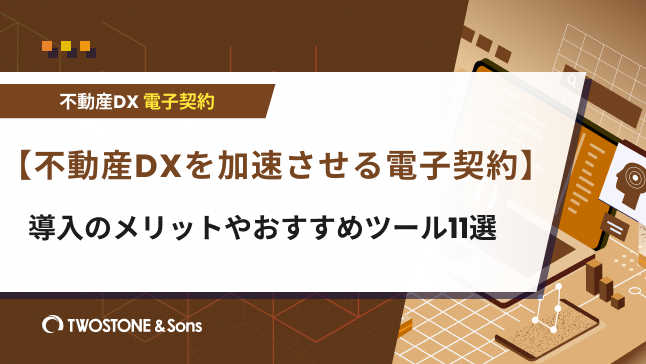
2022年の法改正で不動産取引の電子契約は解禁されましたが、導入のメリットやデメリット、自社に合ったサービスの選び方が分からない方も多いのではないでしょうか。そこでこの記事では、電子契約の基本から、メリット・デメリットなどを網羅的に解説しています。
不動産業界の契約書製本や郵送、収入印紙の管理。いまだに多くの時間とコストを要する、紙とハンコの契約業務に課題を感じていませんか?
2022年の法改正で不動産取引の電子契約は解禁されましたが、導入のメリットだけでなく、デメリットや自社に合ったサービスの選び方が分からず、一歩を踏み出せない方も多いでしょう。
そこでこの記事では、電子契約の基本から、メリット・デメリット、そして自社に最適なサービスの選び方とスムーズな導入ステップまでを網羅的に解説します。
不動産業界で契約のプロセスや書類管理などに課題を感じている担当者の方は、ぜひ最後までご覧ください。

不動産DXの一環として、契約の手続きをオンラインで完結させる「電子契約」は、2022年5月の法改正を機に、業界全体で急速に注目度が高まっています。
それまでは紙とハンコが必須だった不動産取引が、デジタルで完結できるようになったのです。これにより、業務効率化やコスト削減はもちろん、顧客側の利便性も大きく向上します。
電子契約は、不動産取引のあり方を根本から変える、非常に重要な取り組みといえます。
電子契約とは、紙の契約書に署名・捺印する代わりに、電子データで作成した契約書に「電子署名」と「タイムスタンプ」を付与することで、本人性と非改ざん性を担保する仕組みです。
電子署名は、手書きの署名や印鑑の代わりとなり、契約者本人であることを証明する役割を果たします。また、タイムスタンプは、その時刻にその電子文書が存在し、それ以降改ざんされていないことを証明します。
これらの技術によって、紙の契約書と同等の法的な証拠力が認められており、安全なオンライン取引を可能にしたのです。
2022年5月に施行された宅地建物取引業法の改正における最大のポイントは、これまで義務付けられていた「重要事項説明書(35条書面)」と「契約締結時書面(37条書面)」の、紙での交付が不要になったことです。
これにより、いわゆる「IT重説」で重要事項をオンラインで説明したのち、契約書も電子データのまま、電子署名で締結できるようになりました。押印も不要です。
この法改正が、不動産取引の完全なオンライン化を阻んでいた最後の壁を取り払い、業界のDX化を大きく加速させるきっかけとなりました。
参考:不動産業:宅地建物取引業法 法令改正・解釈について|国土交通省
不動産取引における電子契約は、一般的に以下の流れで進みます。
まず、不動産会社は顧客の本人確認をおこないます。次に、ビデオ通話などを利用して宅地建物取引士が重要事項説明をおこない、顧客は合意の上で、電子契約サービスから送られてきた契約書データに電子署名をおこないます。
このプロセスによって、顧客は一度も店舗に足を運ぶことなく、安全に不動産契約を締結できるのです。

不動産DXにより電子契約を導入するメリットは、以下の5つです。
それぞれ解説していきます。
電子契約を導入する最大のメリットは、これまで必須だった収入印紙代や書類の郵送費といった、物理的なコストを大幅に削減できる点です。
印紙税法では、電子データでやり取りされる契約書は「課税文書」に該当しないと解釈されています。そのため、高額になりがちな不動産売買契約書でも、印紙を貼る必要がありません。
また、契約書を印刷する紙代やインク代、郵送するための切手代や封筒代も全て不要になります。目に見える形で経費を削減できるのが、電子契約の分かりやすいメリットです。
電子契約は、契約書の作成から署名、そして回収までの一連のプロセスがスムーズになり、契約締結までにかかる時間を劇的に短縮します。
紙の契約書では、書類を郵送し、相手が署名・捺印して返送するまで、数日から一週間以上かかることも珍しくありませんでした。一方電子契約なら、契約書データをメールなどで送り、相手はパソコンやスマートフォンでその場で署名できます。
電子契約によるスピード感は、顧客の契約意欲が冷めないうちに契約を進められるため、機会損失を防ぐ効果もあります。
契約書を電子データとしてクラウド上で保管すると、物理的な書類の管理や保管の手間がなくなり、紛失や不正な改ざんのリスクを減らせます。
大量の紙の契約書を保管するには、キャビネットや倉庫といった物理的なスペースが必要です。電子契約なら、保管スペースは不要になり、過去の契約書もキーワード検索で瞬時に見つけ出せます。
また、電子署名やタイムスタンプの技術は、契約が「いつ、誰によって、どのような内容で」結ばれたかを証明し、あとからの改ざんを防ぎます。安全かつ効率的な書類管理を実現できるのが、不動産取引における電子契約の大きなメリットです。
電子契約を活用すると、遠方に住んでいる顧客や、多忙で来店する時間がない顧客とも、場所や時間の制約なくスムーズに契約手続きを進められます。
これまでは、契約のためだけに、顧客に何度も足を運んでもらう必要がありました。ですが電子契約なら、顧客は自宅にいながら、パソコンやスマートフォンを通じて重要事項説明(IT重説)を受け、そのまま契約の電子署名をおこなえます。
顧客の負担を大幅に軽減できるため、商圏を全国に広げ、新たなビジネスチャンスを掴むことが可能です。
適切な電子契約サービスを利用すると、契約プロセスの透明性が高まり、企業のコンプライアンス(法令遵守)とセキュリティ体制が強化されます。
「いつ、誰が契約書を閲覧し、署名したか」といった操作の履歴(ログ)が、システム上に正確に記録として残るためです。これにより、契約締結のプロセスが客観的に証明可能となります。
また、契約書のデータは暗号化され、アクセス権限も設定できるため、部外者による不正な閲覧や持ち出しを防げます。紙の契約書よりも厳格な管理が可能となり、企業の信用度を高めます。
参考元:電子契約で内部統制を強化する方法を解説|株式会社マネーフォワード

不動産取引での電子契約には、以下のようなデメリットがあるのも事実です。
メリットだけでなく、デメリットについても理解しておきましょう。
電子契約を導入する場合、これまでの紙とハンコを前提とした契約業務のフローを、根本から見直す必要があります。たとえば、誰が契約書を作成し、どのタイミングで上司が承認し、どうやって顧客に送信するか、といった一連のルールを再設計しなければなりません。
また、従業員全員が新しいフローを理解し、正しく運用するための研修も不可欠です。電子契約の業務フロー構築には、一定の時間と労力がかかることを覚悟しておく必要があります。
これまで紙の契約に慣れ親しんできた既存の顧客や取引先に対しては、電子契約への変更が混乱や不信感を招く恐れがあります。とくに、なぜ電子契約になったのか、その安全性は大丈夫なのか、といった点について、事前に丁寧な説明をおこなうことが重要です。
十分な説明がないまま手続きを進めると、顧客が不安を感じ、契約そのものに消極的になってしまうかもしれません。相手方の理解と協力を得ながら、丁寧に進めていく姿勢が求められます。
パソコンやスマートフォンの操作に不慣れな高齢者の方との不動産取引では、電子契約がスムーズに進まず、かえって不利に働く場合があります。
メールで送られてきた契約書の開き方が分からない、電子署名の操作ができない、といった問題が現実に存在します。無理に電子契約を進めようとすると、顧客に大きなストレスを与え、会社への不信感にも繋がるリスクも否定できません。
相手のITスキルに合わせて、従来通りの紙の契約書と併用するなど、柔軟な対応ができる体制を整えておくことが大切です。
電子契約には、フィッシング詐欺や不正アクセス、通信障害といった、デジタルならではのトラブルを招く可能性があります。
たとえば、正規の契約案内メールを装ったフィッシングメールによって、個人情報が盗まれるリスクがあります。また、利用している電子契約サービスに障害が発生し、一時的に契約業務が完全に停止してしまうことも考えられます。
このような事態に備え、信頼性の高いサービスを選定し、社内でのセキュリティ教育を徹底することが重要です。

不動産DXを加速させるために、電子契約サービスの選び方を5つに分けて解説します。
一つずつみていきましょう。
最も重要なのは、その電子契約サービスが、宅地建物取引業法で定められた要件に完全に対応しているかを確認することです。
2022年の法改正により、重要事項説明書(35条書面)や契約書(37条書面)の電子化が可能になりました。今後選ぶサービスは、これらの書面を法令に準拠した形で作成・交付できるものでなければなりません。不動産取引に特化したサービスや、専用のプランが用意されているかを確認しましょう。
顧客の重要な個人情報や、高額な取引の契約書を扱うため、サービス提供会社のセキュリティ対策が万全であるかを確認することは不可欠です。
通信の暗号化(SSL)や、不正アクセスを防ぐIPアドレス制限、二要素認証といった機能の有無をチェックしてください。また、情報セキュリティに関する国際規格である「ISMS認証」や、「プライバシーマーク」を取得しているかどうかも、信頼性を判断するうえでの重要な指標となります。
参考元:「プライバシーマークとISMS認証について」|一般財団法人 日本情報経済社会推進協会
実際にシステムを操作する社内の従業員と、契約相手となる顧客の双方にとって、直感的で分かりやすい「操作性」であるかどうかも、重視すべきポイントです。
社員にとっては、日々の業務内でストレスなく使えることが、電子契約サービス定着の鍵です。また、顧客にとっては、ITに不慣れな方でも迷わずに署名まで進められる簡単さが求められます。
無料トライアルなどを活用し、複数の立場の人間で実際に試してみるのがおすすめです。
すでに社内で顧客管理(CRM)や物件管理システムを利用している場合、それらの既存システムと電子契約サービスが連携できるかを確認しましょう。システム連携ができると、顧客情報や物件情報を、契約書作成時に再度入力する手間が省けます。
これにより、入力ミスを防ぎ、業務効率をさらに向上させることが可能です。多くのサービスが連携機能をアピールしているので、自社のシステムに対応しているかを確認してください。
自社の契約件数や利用人数に見合った料金体系であるかと、導入後のサポート体制が手厚いかを確認してください。
料金プランは、月額固定制や、契約書の送信件数に応じた従量課金制など様々です。自社の利用頻度を予測し、最もコストパフォーマンスの良いプランを選びましょう。
また、操作で困った際に、電話やチャットですぐに質問できるかといったサポート体制も、安心して運用を続けるために重要です。
長期的な視点で、コストとサポートの両面から、自社に最適なサービスを見極める必要があります。

不動産業界向けのおすすめ電子契約サービスを、「不動産に特化したサービス」と「不動産にも対応したサービス」に分けて解説していきます。
不動産に特化した電子契約サービスとして、以下の5つをご紹介します。
それぞれ確認してください。
「いえらぶサイン」は、総合業務支援システム「いえらぶCLOUD」に搭載された電子契約機能です。最大の特徴は、いえらぶCLOUD内の物件・顧客データを直接契約書作成に活用できる、シームレスなデータ連携です。これにより、情報の手入力や転記ミスがなくなります。
複数人への署名依頼は自動で転送され、押印漏れもシステムが警告するため、契約業務の時間を劇的に短縮します。信頼性の高い他社サービスとも連携しており、安心して不動産契約の完全電子化を実現可能です。
「電子契約くん」は、書類登録、IT重説・電子署名、完了通知という簡単な3ステップで、契約業務を誰でもスムーズにおこなえるサービスです。
紙の契約書で発生しがちな捺印漏れや記入ミスを防ぎ、郵送が不要になるため、最短当日でのスピーディーな契約締結も可能です。「BOXIL SaaS AWARD 2024」を受賞するなど、その利便性は高く評価されています。
書類の郵送費や保管料といったコストを削減し、従業員の事務作業の負担を大幅に軽減します。
引用元:電子契約くん|ITANDI BB + (イタンジビービープラス)
「レリーズ」は、電子契約機能も備えた、不動産売買取引に特化した業務支援プラットフォームです。
顧客一人ひとりに提供される専用の「マイページ」が最大の特徴です。取引の進捗確認からチャットでの連絡、書類のやり取りまで、全ての情報をマイページに集約し、これまでにない透明性と利便性を提供します。
事業者側は、電子契約や書類作成の自動化で業務を効率化できるうえ、生成AIが契約書のミス検知なども検知します。顧客体験の革新と生産性向上を同時に実現するツールです。
「PICKFORM 電子契約」は、国土交通省から宅地建物取引業法に適合する旨の回答を国内で唯一取得している、信頼性の高い不動産取引特化型の電子契約サービスです。
元不動産会社が開発しており、現場の業務フローに寄り添った、誰でも間違えずに操作できるシンプルな設計が魅力です。売買・賃貸だけでなく、工事請負契約や雇用契約など、幅広い契約に対応できます。
法的な安心感を最優先しつつ、現場での使いやすさを求める企業に適しています。
「スマート契約」は、大手不動産情報サイトのアットホームが、アドビ社と提携して提供する電子契約サービスです。
契約業務のスピードアップやコスト削減、進捗の見える化といった、不動産会社が抱える悩みを解決します。世界的なアドビ社の電子サインサービスを基盤とした高いセキュリティと、ISMS認証が、取引の安全性を担保しているのも特徴です。
賃貸・売買契約はもちろん、管理委託契約や駐車場契約、更新・退去手続きなど、幅広い契約シーンに対応します。
引用元:スマート契約|アットホーム
次に、不動産にも対応している電子契約サービスとして、以下の6つをご紹介します。
一つずつみていきましょう。
「freeeサイン」は、会計ソフトで有名なfreeeが提供する電子契約サービスです。「freee会計」とのシームレスな連携が最大のメリットです。電子契約を結ぶと、その情報をもとに請求書や入金管理などをfreee会計上でスムーズにおこなえます。
契約から会計まで、バックオフィス業務全体の効率化を図りたいと考えている企業、とくに既にfreeeの他サービスを利用している不動産会社にとっては、非常に親和性の高いツールです。
「クラウドサイン」は、弁護士ドットコムが提供する、国内でトップクラスのシェアを誇る電子契約サービスです。
不動産取引に特化したプランでは、宅地建物取引業法に完全に準拠した形で、重要事項説明書(IT重説)から契約締結までをオンラインで完結できます。弁護士がサービスを監修しているという高い信頼性と、多くの企業で導入されている実績が大きな強みです。
法的な安心感を最優先し、業界標準ともいえるサービスを利用したい企業に最適な選択肢となります。
「GMOサイン」は、全宅連との協業や国交省のマニュアルに準拠した、不動産業界向けの安心・安全な電子契約サービスです。
その大きな特徴は、契約の重要度に応じて選べる、多彩で強力な本人確認機能にあります。メールだけでなくSMSでの署名依頼や、本人確認書類の画像添付、マイナンバーカードによる認証など、なりすましを防ぐ高度なセキュリティを確保。手頃な料金体系と無料の電話サポートも充実しており、多くの大手企業に選ばれています。
引用元:GMOサイン 不動産DX|GMOインターネットグループ
「契約大臣」は、専門知識がなくても「見たまま操作」できる、シンプルさと低料金を追求した電子契約サービスです。月額4,000円台からと導入しやすく、契約件数に応じて毎月プランを柔軟に変更できるため、無駄なコストが発生しません。
その大きな特徴は、契約相手がアカウント登録不要で署名できる手軽さです。これにより、取引先に負担をかけることなく、スムーズに電子契約への移行が可能です。
初めて電子契約を導入する企業や、中小企業に最適なツールです。
引用元:契約大臣|株式会社TeraDox
「ベクターサイン」は、基本料金0円・送信料のみで全機能を利用できる、コストパフォーマンスに優れた電子契約サービスです。
最大の特徴は、他社のサービスで締結した契約書もアップロードし、全ての電子契約をまとめて管理できる「一元管理」機能です。取引先ごとに利用サービスが異なっていても、管理が煩雑になる問題を解決します。
承認ルートを柔軟に設定できる機能や、業界標準の認証局を採用した高いセキュリティも備えています。電子署名法などの各種法令にも準拠しており、コストを抑えながら、安全で効率的な契約業務を実現したい企業に最適です。
「Adobe Acrobat Sign」は、PDFを開発したアドビ社が提供する、世界標準の電子サインソリューションです。多くの人が使い慣れているAcrobatやPDFとの完璧な連携が可能で、PDF文書の作成・編集から、署名の依頼、そして署名済み文書の管理まで、一連の流れをスムーズにおこなえます。
グローバル基準の高いセキュリティと信頼性を備えており、とくに多数の契約書を扱う大手企業や、コンプライアンスを厳格に遵守する必要がある企業にとって、最適な選択肢の一つです。

これまでは紙での対応をおこなってきた不動産会社が、電子契約をスムーズに導入するために、以下4つのステップで導入を進めてください。
一つずつ解説します。
最初のステップは、「なぜ電子契約を導入するのか」という目的を社内ではっきりとさせることです。
目的が曖昧なままでは、関係者の協力が得られにくく、導入プロジェクトが迷走してしまいます。「契約業務の時間を50%削減する」「印紙代や郵送費を年間〇〇円削減する」といった、具体的な数値目標を設定すると、導入効果も明確になります。
次に、これまでの紙とハンコを前提とした社内の契約に関するルールや規定を、電子契約に合わせて見直す必要があります。たとえば、契約書の承認プロセス(稟議規定)や、文書の管理方法(文書管理規定)、そして押印に関するルール(印章管理規定)などを、電子署名やクラウド保管を前提としたものへ改訂することが必要です。
事前に社内ルールを整備しておくと、導入後に「このケースはどう対応すればいいのか」といった現場の混乱を防げます。
社内の目的とルールが固まったら、それらを満たす複数の電子契約サービスを比較検討し、最終候補で無料トライアルを実施します。カタログスペックだけでは分からない、実際の操作性や、自社の業務フローとの相性を確認するためです。
とくに、ITに不慣れな従業員や、お客様となる高齢者の方でも簡単に使えるかどうかは重要な視点です。現場の担当者を交えて実際に試し、自社にとって本当に最適なサービスを見極めましょう。
導入するサービスが決定したら、従業員全員に対して、導入の目的や新しい業務フロー、そして具体的な操作方法について、丁寧な説明会や研修をおこないます。
新しいシステムの導入は、一時的に現場の負担を増やすため、その必要性やメリットを十分に理解してもらうことが、円滑な移行には不可欠です。分からないことをいつでも質問できる窓口を設けるなど、導入後のサポート体制もあわせて伝えましょう。
従業員の不安を取り除き、前向きな協力体制を築くことが、電子契約を社内に定着させるうえで最も重要です。

この記事では、不動産取引における電子契約について、そのメリット・デメリットから、自社に合ったサービスの選び方、そして導入を成功させるための具体的なステップまでを解説しました。
電子契約サービスの導入には業務フローの見直しなど、いくつかのハードルがあります。ですがその分、コスト削減や業務効率化といったメリットは計り知れません。
電子契約への対応は、もはや避けては通れない、企業の未来を左右する重要な経営判断です。この記事を参考に、まずは自社の契約業務の課題を洗い出すことから、DX化への第一歩を踏み出してください。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
