不動産DXアプリが必要な理由 | DXアプリ導入で得られるメリット
不動産
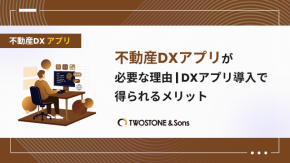
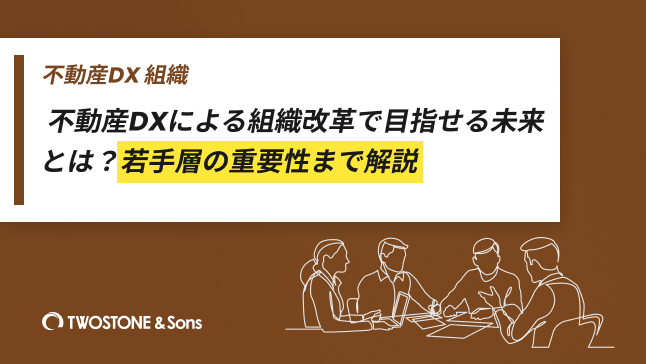
不動産DXによる組織改革を進めることで、「新しいビジネスモデルの構築」「業務効率化と生産性の向上」「顧客満足度の向上」などが目指せます。この記事では、不動産DXによる組織改革で目指せる未来や、若手層の重要性までを紹介していきます。
不動産DXによる組織改革を進めることで、「新しいビジネスモデルの構築」「業務効率化と生産性の向上」「顧客満足度の向上」などが目指せます。また、不動産DXを導入するうえでは、若手人材の活用が成功の鍵を握ります。
本記事では、不動産DXによる組織改革で目指せる未来や、若手層の重要性までを解説していきます。不動産DX導入による組織改革の流れや注意すべきポイントまで紹介しているため、ぜひ最後までご覧ください。

不動産DXによる組織改革で目指せる未来は、以下の4つです。
それぞれ解説します。
不動産DXの導入によって、新たなビジネスモデルの展開が可能になります。デジタル技術を活用すれば、従来の仲介や管理の枠組みを超えたサービス提供が実現できます。
たとえば、サブスクリプション型の賃貸サービスやバーチャル内見などが増えてきました。こうした動きにより、顧客接点を拡大し競合との差別化がしやすくなります。収益構造の見直しを後押しする手段として、DXは有効といえるでしょう。
デジタル化によって、業務効率と生産性を両立できます。紙や電話に依存した作業を見直すことが時間と手間の削減につながるからです。
たとえば、クラウドツールやRPAの導入により、事務作業の自動化や情報の共有がスムーズに進みます。社員がより価値の高い業務に集中できる体制が整い、成果も出やすくなります。全体として、組織力の底上げに貢献するのがDXの魅力です。
不動産DXの活用は、顧客満足度の向上にも役立ちます。電子契約やオンラインでのやり取りにより、時間や場所を選ばずサービスが受けられるためです。
たとえば、チャット相談やバーチャル内見の提供によって、利便性と柔軟性が両立します。その結果、顧客との信頼関係が深まりやすくなります。体験の質を高めることで、リピーターの獲得にもつながるでしょう。
DXの推進により、慢性的な人手不足の課題も軽減できます。AIやRPAの活用で定型業務を自動化できるため、少人数でも対応が可能です。
たとえば、契約書の作成や問い合わせ対応などがシステムで処理されるようになっています。人材にかかる負荷を減らしつつ、サービス品質を保てるのが大きな利点です。結果として、安定した事業運営が実現しやすくなります。
不動産DXを導入するうえでは、若手人材の活用が成功の鍵を握ります。若手層はITリテラシーが高く、新しい環境への順応も早いです。
現場に近いポジションにいることから、課題の把握や改善提案にも積極的に関われます。加えて、ボトムアップ型の変革を支える存在として期待されます。柔軟な発想力と行動力が、DXの前進を支える原動力になりやすいです。

不動産業界でDXを導入するうえでの課題は、以下の5つです。
ひとつずつ解説します。
紙中心や対面重視のアナログ業務が、不動産業界には根強く残っています。これまでの業務手順を変えるには、一定の抵抗が生じるケースも多いです。
そのため、契約書や資料の電子化、オンラインでの内見といった対応が求められます。この移行には社内の意識改革と時間が必要です。古い習慣からの脱却こそが、変化の起点になります。
DXを推進するうえで、デジタル人材の不足は大きな障害となります。IT分野への投資が後回しにされてきた影響が残っているため、現場スタッフの多くがITツールの扱いに慣れておらず、学習機会も限られています。
このような現状を変えるには、外部人材の活用や社内教育が重要です。人材戦略の再構築が、取り組みの基盤となります。
既存のシステムと新しい技術の連携には、課題が残ります。従来の仕組みが、最新ツールとの互換性を欠くケースは多いです。
そのため、顧客管理システムと契約処理ツールの連携ができないと、情報の整合性に支障が出ます。このような状況を打開するには、段階的な刷新や設計の見直しが不可欠です。現場と技術部門が連携しながら対応していく必要があります。
顧客の価値観やライフスタイルの多様化が進み、画一的な対応では限界が生まれています。
たとえば、LINEなどのチャットでの問い合わせや、非対面での内見への対応などが一般化しているため、このような流れに合わせた体制づくりが企業には求められます。多様な期待に応えることは、選ばれる企業になる条件です。
DXの導入には、一定の初期費用や運用コストがかかります。とくに中小企業にとっては、大きな負担となる場合もあります。
たとえば、システム導入費や教育コストがネックとなるケースも珍しくありません。長期的には効率化や人件費削減により費用対効果が期待されますが、踏み切るには慎重な判断が必要です。投資の効果を見極めながら段階的に進めることが現実的といえるでしょう。

不動産DXの成功事例を、以下に3つまとめました。
それぞれ紹介します。
株式会社ジョイテックでは、DXを導入することで業務の見直しと効率化を実現しました。手作業を減らし、社員の業務時間を顧客対応へと再配分できた点が特徴です。
とくに、クラウドベースの情報共有ツールが迅速な対応に貢献しています。その結果、顧客満足度が向上し、企業としての評価も高まりました。業務改革とサービス品質の両立が達成された事例といえるでしょう。
出典参照:AIやDXの導入で顧客とのコミュニケーションに割く時間が増加。GMO賃貸DXで「お客様ファースト」がますます進化・深化。|GMOインターネットグループ株式会社
株式会社のうか不動産は、収支報告書の電子化によって業務負担を軽減しました。紙帳票からデジタルへ切り替えたことで、情報の管理と共有がスムーズになりました。
また、クラウド環境を整備したことで、どこからでもリアルタイムでデータを扱えるようになっています。こうした電子化の取り組みが、業務のスピードと正確性を向上させ、効率と信頼の両面に効果を発揮したといえます。
出典参照:「GMO賃貸DX」で毎月の収支報告書をデータ化し、顧客とのコミュニケーションもより“マメ”に |GMOインターネットグループ株式会社
株式会社ミライズプロパティでは、自社開発の業務アプリを導入することで業務手順を改善しました。スタッフごとに異なっていた作業内容を、アプリのフローに合わせて統一したことが成果の要因です。
結果的に、引き継ぎや教育の効率が上がり、業務の安定性も高まりました。また、組織全体の対応力が強化され、柔軟な働き方にもつながっています。アプリ活用は、継続的な改善と効率向上の土台となっています。
出典参照:【導入事例インタビュー】ドクターの不動産管理を支援。アプリ導入で業務と知見の属人化を防ぎ、入居率99.6%を実現 |GMOインターネットグループ株式会社

不動産DX導入による組織改革の流れは、以下のとおりです。
ひとつずつ解説します。
組織改革を進める第一歩は、自社の現状を正確に把握することです。業務の流れや社内リソースの状態を分析することで、改善すべき領域が浮かび上がります。
たとえば、紙業務が多い部署や属人化した業務があれば、それが課題と捉えられます。こうした情報を整理することで、取り組むべき優先順位も見えてきます。課題の可視化が、DX推進の出発点となります。
DXを成功させるためには、明確なビジョンと戦略が欠かせません。目的が曖昧な状態では、現場の理解が得られず、施策の本来の機能や役割を失ってしまいます。
そのため、「顧客接点を増やす」や「契約業務の自動化」といった具体的な目標を設定することで、必要な施策も明確になります。戦略の策定は、全社で同じ方向を共有するのが重要です。
DXを実行に移すには、明確な推進体制が求められます。誰が何を担当し、どのように進捗を管理するかを定めなければ、計画は停滞しやすいです。
計画の停滞を事前に防ぐためには、部門横断型のDX推進チームを組成し、定例で進捗確認をおこなう方法が効果的です。情報共有や意思決定のスピードが向上し、全体の足並みもそろいやすくなります。
ビジョンと戦略を具現化するには、段階的なロードマップの作成が必要です。導入の各ステップを明確にしていないと、現場が混乱してしまうリスクもあります。
たとえば、「フェーズ1で電子化、フェーズ2で自動化」など、期間や担当部署を具体的に区切ると進めやすくなります。進行状況を見える化し、定期的な見直しの機会を設けながら、着実に実行へ移していきましょう。
最初から全社導入するのではなく、小規模な試行導入から始めるのが重要です。小さく始めることで、失敗時のリスクを抑え、改善しながらスムーズに展開できます。
具体的には、1部署に限って新システムを試用し、現場の声をフィードバックとして収集する手法が有効です。得られた知見を次の展開に生かすことで、導入効果も高まります。段階的な進行が、全社展開を成功させるポイントです。
試行結果をもとに、本格的な導入段階へ移行します。社内への周知徹底やマニュアル整備、サポート体制の構築を並行して進めるのが重要です。
そのため、説明会や動画マニュアルを活用し、理解度を高める工夫が求められます。こうした取り組みによって、全社員が自分事としてDXに取り組みやすくなります。
DXは導入すれば終わりではなく、継続的に見直しと改善が必要です。社内外の環境は変化し続けるため、柔軟に対応しなければ効果は持続しません。
定期的にKPI(中間目標)を設定し、現場からのヒアリング結果を分析する仕組みを整えることが大切です。こうした評価から得た示唆を次の施策に反映させることで、継続的な成長が可能になります。評価と改善の繰り返しが、組織を強くしていきます。

不動産DX導入で組織改革を進める際に注意すべきポイントは、以下の3つです。
それぞれ解説します。
DXを進める際は、ツールの導入が目的化しないよう注意が必要です。本来の目的は業務改善や顧客満足の向上であり、ツールはその手段にすぎません。
もし業務フローが変わらないまま新しいツールだけを導入しても、効果は限定的です。常に、「何を改善したいのか」という視点を持って取り組むことが重要です。目的意識を保ち、手段を正しく活用しましょう。
DXの推進には、経営トップの積極的な関与と姿勢が不可欠です。現場任せでは全体最適が実現しにくく、取り組みが中途半端になるリスクがあります。
そのため、トップ自らが定例会議で進捗を確認したり、施策の方向性を明言することで、社員の意識も変わってきます。こうした姿勢が社内全体に浸透すれば、協力体制が強化されます。リーダーシップの有無が、DXの成否を左右するといえるでしょう。
現場との連携を重視し、段階的に導入を進めることがDX定着のポイントです。実際にツールを使うのは現場の担当者であるため、納得感がなければ形だけの導入で終わってしまいます。
たとえば、初期段階では現場の意見を反映したカスタマイズをおこない、運用しながらフィードバックを取り入れる方法が効果的です。導入を一方的に進めるのではなく、歩調を合わせる姿勢が求められます。信頼関係の構築が、スムーズな定着を生み出します。

不動産DXにおける組織改革は、業務効率化や顧客対応力の向上、人手不足の解消といった複合的な課題に対応できる有力な手段です。しかし、効果を最大化するには、明確な戦略と段階的な導入、そして継続的な評価が欠かせません。
また、現場との連携や若手人材の活用も成功に向けた重要な要素といえます。最初から完璧を目指すのではなく、小さな成功を積み重ねていく姿勢が大切です。
未来を見据えたDXの取り組みが、不動産業界の持続的成長を支える力となるでしょう。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
