不動産DXアプリが必要な理由 | DXアプリ導入で得られるメリット
不動産
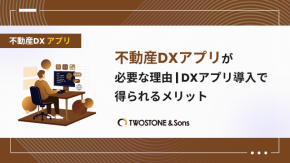
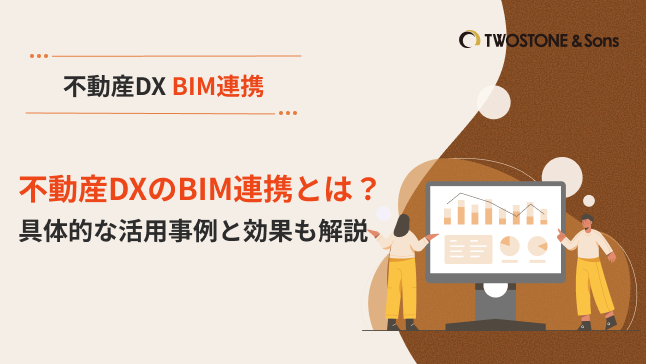
不動産DXでBIM連携を促進すると、設計・工事でのコスト削減、関係者とのスムーズな意思疎通がスムーズ、完成後のビル管理・運営の効率化などのメリットがあります。この記事では、BIM連携の基本から使い方、成功させるポイントまで解説しているため、不動産DXでBIM連携を進める際に、参考にしてみましょう。
「不動産DXの活用で、BIMと不動産管理システムを連携させて、建物情報を一元管理したい」
「不動産DXでBIM連携を活用して、設計・施工・管理の情報をつなぎ、業務効率を向上させたい」
「不動産DXのBIMデータを活用して、資産価値の可視化や維持管理コストの最適化をおこないたい」
不動産DXに取り組む方でBIMを活用したいと考える方のなかには、上記のお悩みを抱える方もいるのではないでしょうか。
不動産DXでBIM連携を活用した場合、コストの削減、関係者とのスムーズな意思疎通、完成後のビル管理・運営の効率化などのメリットがあります。この記事では、BIM連携とは何か、BIM連携のメリットや使い方を解説します。
不動産DXでBIM連携を活用した企業の事例や、BIM連携を成功させるためのポイントまでご紹介しているため、ぜひ最後までご覧ください。
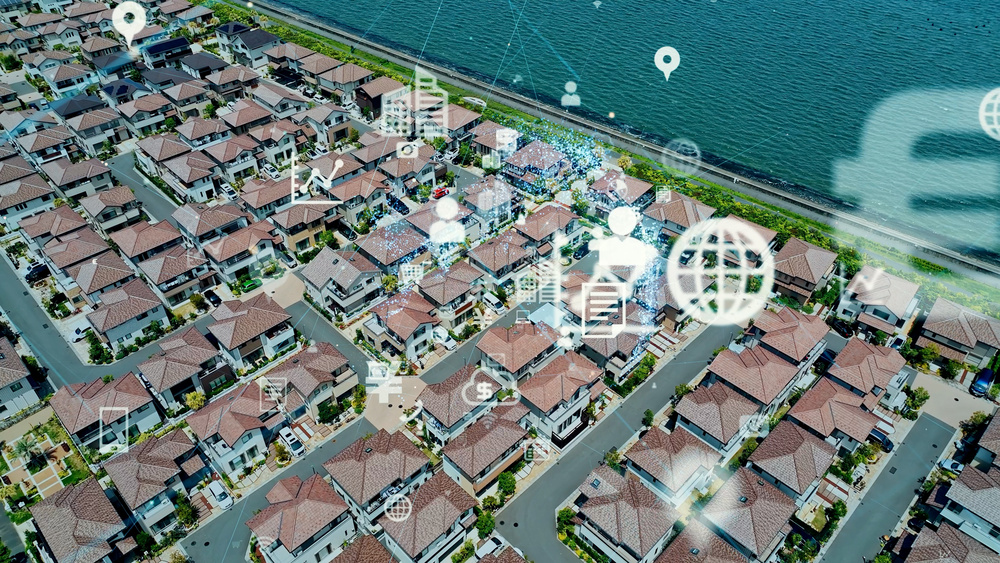
不動産DXにおけるBIM連携とは、3Dモデルと建築・管理に関するあらゆる情報を一体化する仕組みです。BIM(Building Information Modeling)は、以下の建物に関わる情報をすべてデジタル化して記録できる技術です。
この技術を不動産業の設計、施工、販売、運用管理といった各工程に連携させた場合、情報の引き継ぎミスや作業の重複が減り、効率的な業務が可能になります。
たとえば、管理部門が施工時の情報をBIMからすぐに確認できれば、メンテナンスの手間が減ります。関係者全員が同じデータをリアルタイムで見られるため、認識のズレも起きにくいです。BIM連携は、情報の流れをスムーズにし、不動産の運用全体をスマートに変えていくのに有効な手段です。

BIM連携が創る不動産の未来は、以下の3つです。
1つずつ見ていきましょう。
BIM連携とAIやIoTと組み合わせた場合、自動的に最適な管理をおこなうスマートビルを実現できます。たとえば、建物の3次元モデル情報とセンサーから得られるリアルタイムデータをAIが分析し、自律的な管理が可能です。
また、空調や照明のコントロールや設備異常の早期発見など、誰もいない会議室の電気を自動で消す、温度の上がりすぎを防ぐなどの仕組みができます。BIM連携とAIやIoT(Internet of Things)を活用したスマートビルは、無駄なエネルギー消費を防ぎながら快適性を両立する次世代の建物として、今後も注視したい取り組みです。
BIM連携は、建物単体ではなく、街全体のデータと組み合わせて活用できる仕組みです。国土交通省が推進する「PLATEAU(プラトー)」のような3D都市モデルとBIMを結びつけることで、都市の景観や機能を仮想空間に再現できます。結果的に、新しいビルの建設が周辺環境に与える影響や、避難経路の安全性などを事前に検証できます。
たとえば、新しく建てる高層ビルが隣の住宅の日当たりをどの程度遮るかを、事前に確認可能です。 また、道路の混雑や人の流れなどのシミュレーションにも活用できるため、より良い街づくりに役立ちます。BIM連携は、都市全体の課題解決に有効な技術です。
出典参照:PLATEAU [プラトー] | 国土交通省が主導する、日本全国の3D都市モデルの整備・オープンデータ化プロジェクト|国土交通省
出典参照:スマートシティ官民連携プラットフォーム|国土交通省
BIMを活用した場合、建物の完成前にメタバース内でリアルな建築シミュレーションが可能です。BIMで作成された3Dデータをもとに、仮想空間上に実際の建物そっくりのモデルを再現し、設計の確認や打ち合わせを視覚的におこなえます。これは「デジタルツイン」と呼ばれる手法で、仮想空間の中をアバターが自由に移動し、天井の高さや部屋の広さ、家具の配置などをその場で体験が可能です。
デジタルツインによって、壁の色を変えて比較したり、通路の広さを歩きながら検証したりするのが簡単にできます。BIMを活用した建築シミュレーションによって、完成後の不満や認識違いを防ぐだけでなく、施主や関係者の合意形成もスムーズになり、質の高い設計を実現する強力なサポートになります。

不動産DXのBIM連携がもたらすメリットは、以下の4つです。
1つずつご紹介します。
BIM連携は、設計と工事におけるミスの削減とコストの最適化に役立ちます。BIMでは、建物の構造と設備を3Dで再現するため、設計段階での不具合を発見しやすいです。電気の配線とダクトが交差してしまうといった「干渉」を、施工前に見つけて修正でき、工事中のやり直しや中断を防げます。
また、3Dモデルには部材の数や大きさ、価格などの情報も含まれており、正確な見積もりを自動で計算可能です。結果、BIM連携の活用は、余分な材料の発注を防ぎ、コスト削減につながります。BIM連携は、プロジェクト全体の質を高めるうえで重要な技術です。
BIM連携は、建築に関わるすべての関係者が共通で使える情報を可視化できる状態で提供し、意思疎通の精度を高めます。3Dモデルは、専門知識がなくても一目で建物の完成イメージを理解できるため、施主や投資家にとって分かりやすいツールです。
設計者や施工会社も同じ情報を共有するため、認識のズレが起きにくく、伝達ミスも減少します。BIM連携によって、設備の配置変更をその場で3D上に反映し、具体的に見せながら説明できるため、短時間で合意形成が可能です。BIM連携は、関係者全体の連携を強化させ、プロジェクトの進行をスピーディーにします。
BIM連携は、建物の完成後もデジタル情報を活用し、管理や運営の効率化を実現できます。設計や施工時に作成したBIMデータは、建物の「デジタルツイン」として引き継がれ、維持管理の場面でも有効なツールです。
たとえば、BIM連携を活用した場合、エレベーターの型番や照明の寿命、配管の材質などを3Dモデル上で確認できるため、現場で図面を探す必要がなく、点検や修繕のスピード向上につながります。
また、設備ごとの交換時期や費用の目安も管理できるため、無駄のない修繕計画を立てることが可能です。BIM連携は、建物のライフサイクル全体のコストと手間を削減するために有効です。
BIM連携は、建物が持つ本来の価値を見える形で伝えられるため、不動産の魅力を最大限に引き出せます。たとえば、3Dモデルは外観や内装だけでなく、日当たりや風通し、省エネ性能などの情報も視覚的に表現可能です。BIM連携を活用すると、季節による室内や温度の違いをシミュレーションでき、近くの建物による眺望の影響も確認できるため、顧客は実際の生活を想像しやすいです。
収集した情報をVR見学やWeb内覧に活用すると、遠方の顧客にも物件の良さを訴求できます。さらに、リフォーム時には複数のプランを比較しやすくなり、意思決定の支援にもつながります。BIM連携は、建物の「強み」を可視化するために有効的なツールです。

不動産DXにおけるBIM連携の使い方を、段階別に紹介しています。
詳しく見ていきましょう。
企画・設計の段階において、BIMは建物の性能検証や設計の正確性を高め、手戻りを減らすのに有効です。なぜなら、建設前に様々なシミュレーションをおこない、関係者間で完成イメージを正確に共有できるからです。
たとえば、3Dモデル上で日照条件のチェックや、柱と配管の衝突リスクの可視化ができます。また、部材の数量やコスト情報も自動算出されるため見積もり精度も高いです。
BIMは3Dで完成後のイメージを共有できるため、施主とのズレを減らし、設計段階から合意形成がスムーズに進められます。
工事段階でBIMを連携すると、3Dモデルをもとにしたシミュレーションや、リアルタイムでの進捗管理ができるため、施工図作成や現場管理の効率化が可能です。
具体的には、BIMモデルから自動で正確な施工図を生成できるため、図面間の整合性を保ちつつ、作業時間の短縮につながります。BIMを活用した場合、クレーンの動線や資材搬入経路のシミュレーションを事前におこなうことで、安全性の高い作業計画が可能です。BIMは、工事の安全性と生産性の両方を高めるのに向いています。
販売や賃貸の段階では、BIMをマーケティングツールとして活用するのが効果的です。顧客が完成後の生活を具体的にイメージしやすくなるため、物件の魅力を最大限に伝えやすいです。
一例として、3Dモデルを使った「バーチャル内覧」を提供した場合、建物の完成前でもリアルな居住体験を顧客に届けられます。
BIMをマーケティングツールとして活用できると、顧客の反応や要望はデータとして蓄積され、今後の販売戦略に活かせるため、営業の質向上にもつながります。
完成後の建物管理において、BIMは「デジタルツイン」としての役割を果たし、保守管理の効率化が可能です。たとえば、建物内の設備や構造の情報がすべて3Dモデルに記録されているため、点検時に必要な情報をすぐに確認できます。また、配管の位置や材質、照明器具の型番といった情報をモデル上でクリックすれば即座に表示され、現場調査の手間が省けます。
さらに、耐用年数や点検履歴も記録できるため、メンテナンスの計画も立てやすいです。BIMによるデジタルツインは、建物全体の維持コストを抑えながら、品質を長く保つ運用に役立ちます。

以下は、不動産DXにおけるBIM連携の活用事例です。
BIM連携を活用している企業の事例を1つずつ解説します。
プロパティデータバンク株式会社は、自社のクラウド型不動産管理システムとBIMを連携させ、建物管理業務の効率化と品質向上を実現しました。この仕組みでは、BIMが持つ3Dモデルや設備の詳細情報と、賃料・契約者情報といった経営データがひとつにまとめられています。BIMモデル上の部屋をクリックすると、入居者の情報や契約内容がすぐに表示されるため、現場でもスピーディーな対応が可能です。
結果、業務の属人化を防ぎつつ、建物の価値を継続的に維持する管理体制が整備され、資産価値の最大化につながっています。
出典参照:プロパティデータバンクがBIMとの連携で実現する不動産管理のDX|プロパティデータバンク株式会社
美保テクノス株式会社は、BIMを用いたフロントローディング手法で、設計と施工の連携を強化し、生産性の向上を図っています。フロントローディングとは、プロジェクト初期に多くの課題を洗い出しておくことで、あとからの修正ややり直しを減らす考え方です。
同社は、BIMモデルを企画段階から活用し、着工前に配管経路や構造の干渉箇所の確認をおこない、設計者と施工者が同じ情報を見ながら問題を共有しています。この取り組みにより、無駄な修正が減り、全体の工程がスムーズに進むようになりました。結果として、高い施工精度と効率的な現場運営が実現されています。
出典参照:BIM未来図地域建設業のいま|美保テクノス株式会社
株式会社長谷工コーポレーションは、自社開発の「HASEKO BIM」を全社に導入し、マンション開発に関わるすべての業務の効率化を実現しています。このシステムは、企画から設計、施工、販売、そして竣工後の管理やリフォームに至るまで、BIMデータを一貫して活用する仕組みです。情報が常に最新の状態で各部門に共有されるため、業務の二重入力や確認ミスといった無駄が排除されます。
また、過去のプロジェクトデータをもとに改善点を分析しやすくなり、業務の質も向上します。HASEKO BIMの導入による全社的なデータ連携によって、高品質な住宅供給と持続的な業務改善が可能となった事例です。
出典参照:【不動産DX③】不動産業界のDX推進4事例|業務の効率化、売上向上 – DXportal|株式会社MU

不動産DXのBIM連携を成功させるポイントは、以下の4つです。
1つずつ解説します。
BIM連携を成功させるには、導入の目的と開始する範囲を最初に明確にするのが重要です。具体的には、「施工ミスの削減」や「設計の効率化」などの成果目標を定める必要があります。
目的がはっきりしないまま導入を進めてしまうと、効果の検証が困難になり、期待した成果が得られないリスクもあります。まずは小規模なプロジェクトや部署でBIMを試験的に導入する「スモールスタート」が有効です。
BIMを社内に定着させるには、専任チームの設置と人材育成に取り組むのが効果的です。BIMの定着には、専門的な知識と全社的な協力体制が必要です。
まずは、BIM推進の責任者を中心としたチームを結成し、各部門の代表者をメンバーに加えて全体をけん引します。そのうえで、社員の現在のスキルを把握しながら、必要な教育内容を明確にするのが大切です。組織的な体制を整えることが、BIM導入の成功につながります。
BIMを効果的に運用するには、自社の業務に合ったソフトウェアの選択が重要です。たとえば、既存システムとの連携性や導入後のサポート体制が充実しているかを事前に確認しましょう。操作が複雑すぎると社員の習得に時間がかかり、現場での利用が定着しません。
また、将来的にBIMを活用した他部門との連携を考える場合は、拡張性や互換性の高いツールが望ましいです。価格や機能だけでなく、長期的に信頼できるベンダーかどうかを慎重に見極めましょう。
BIM連携を円滑に進めるには、関係会社との間で共通ルールを設定するのが重要です。たとえば、データの命名規則や図面の精度を示す「LOD(詳細度)」の基準、ファイルの共有方法などを事前に取り決めておく必要があります。こうしたガイドラインがないと、各社が独自の形式でデータを作成してしまい、整合性がとれずにトラブルの原因になりかねません。
すべての関係者が同じルールを守ることで、モデルの品質と使いやすさが保たれ、業務のスピードと精度向上につながります。

不動産DXにおけるBIM連携は、不動産の資産価値を高めるための有効な手段です。BIMは設計や施工の効率化だけでなく、完成後の維持管理にまでデータをつなげると、建物の全ライフサイクルを通じた最適な運用を可能にします。たとえば、施工ミスを防ぎ、修繕や点検の計画を立てやすくなり、費用や時間の無駄を最小限に抑えられます。
また、BIM連携によって建物の情報が可視化されると、購入者や入居者への説明も理解が得やすくなり、信頼感の向上にもつながります。
ただし、こうした効果を引き出すには目的の明確化や人材育成、関係会社とのルール整備といった段階的な準備が欠かせません。BIM連携は、これからのスマートシティや環境対応型都市づくりを支えるため、今後の不動産業界でますます注目される技術です。
自社の業務にどのように取り入れられるかを検討し、段階的な導入を進めていきましょう。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
