小売DXの第一歩はペーパーレス化!メリットや書類管理の課題を解説
小売

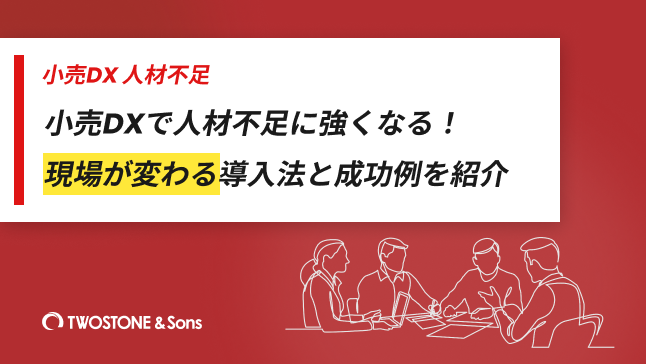
「求人を出しても応募が来ない」「スタッフが定着しない」といった小売業の人材不足。この記事では、その解決策として注目される「小売DX」について、具体的な導入方法から成功事例までを分かりやすく解説します。レジや在庫管理の自動化が現場をどう変えるのか、人材不足に負けない強い組織を作るためのヒントが得られます。
「求人を出しても応募が来ない」「スタッフがすぐに辞めてしまう」といった人材不足は、多くの小売業が抱える深刻な悩みです。人手が足りないことで、サービス品質の低下や売上減少につながってしまいます。
この記事では、人材不足の解決策として注目される「小売DX」について、具体的な導入方法から成功事例までを分かりやすく解説します。
デジタル技術で人材不足にも負けない、強い現場を作るヒントをお届けします。ぜひ参考にしてください。

なぜ小売業では、これほどまでに人材不足が深刻なのでしょうか。その背景には、社会全体の大きな変化と、業界が抱える特有の課題があります。
小売業で人材不足が進んでいる2つの理由について、それぞれ見ていきましょう。
日本が直面している少子高齢化は、働く世代である生産年齢人口の減少を招いています。1995年をピークに減り続けている人口は、今後も回復の見込みが立っていません。
これは全ての産業に影響しますが、特に多くの人手を必要とする小売業にとっては非常に深刻な問題です。働き手の母数自体が減っているため、これまでと同じ方法で求人を出しても、人が集まりにくくなっています。
この社会構造の変化が、小売業の人材確保を根本から難しくしている大きな理由といえるでしょう。
小売業は、他の産業に比べて離職率が高い傾向にあります。その背景には、土日祝日の出勤や不規則なシフト制といった労働条件、他の業種と比較して低い賃金水準など、構造的な問題が存在します。
また、日々の業務に追われ、キャリアアップの道筋が見えにくいと感じる従業員も少なくありません。店舗という限られた空間での人間関係のストレスも、離職につながりやすい一因です。
これらの要因が重なることで、「きつい仕事」というイメージが定着し、新しい人材が集まりにくいだけでなく、せっかく入社したスタッフも長く続かないという悪循環に陥っています。
人材不足は、単に「忙しくなる」というだけでは済まされない、店舗運営の根幹を揺るがす問題を引き起こします。
ここでは、主な2つの課題について解説します。
人手が足りなくなると、そのしわ寄せは必然的に今いるスタッフに向かいます。一人当たりの業務量が増え、長時間労働や休日出勤が常態化し、心身ともに疲弊してしまうでしょう。
このような状態では、集中力の低下からレジの打ち間違いや品出しミスが増えたり、お客様への対応が雑になったりするなど、サービス品質の低下は避けられません。
本来であれば売上向上につながるはずの、丁寧な接客やお客様一人ひとりに合わせた商品提案といった付加価値の高い業務に時間を割く余裕がなくなり、店舗全体の魅力も失われてしまいます。
新たな人材を確保できなければ、事業を維持すること自体が困難になります。実際に、「スタッフが集まらない」という理由で、やむを得ず営業時間を短縮したり、定休日を増やしたりする店舗は少なくありません。
これは企業にとって大きな機会損失であると同時に、地域のお客様にとっても不便を強いることになります。さらに状況が悪化すれば、店舗そのものを閉鎖せざるを得ないという最悪のケースも考えられます。
人材不足が事業の縮小、ひいては撤退に直結するリスクをはらんでいるのです。
こうした深刻な人材不足の課題を解決する鍵として、「小売DX」*が大きな注目を集めています。
小売DXとは、単にITツールを導入することではありません。AIやIoTといった最先端のデジタル技術を活用して、レジ業務、在庫管理、発注、顧客対応といった店舗運営のあらゆるプロセスを根本から見直し、変革することです。これにより、業務効率を飛躍的に高め、全く新しい顧客体験やビジネスモデルを生み出すことを目指します。
人材不足との関係で言えば、小売DXは人の仕事を奪うものではなく、人を単純作業や過酷な労働から解放するための強力な手段です。
自動化できる業務はテクノロジーに任せることで、人はより創造的で付加価値の高い仕事、例えば心のこもった接客や魅力的な売場づくりなどに集中できるようになります。
結果として、従業員の負担が軽減され、働きがいが向上し、人材の定着と確保につながるという好循環が生まれるのです。
小売DXと一言でいっても、その活用方法は多岐にわたります。ここでは、具体的な業務ごとに、どのようにDXが人材不足の解消に貢献しているのか、その成功事例を見ていきましょう。
店舗の顔ともいえるレジ業務ですが、ピークタイムには長蛇の列ができ、お客様にとってもスタッフにとっても大きなストレスの原因となります。
この課題を解決する第一歩が、セルフレジやスマホレジの導入です。お客様自身が会計を行うことで、レジ待ち時間を大幅に短縮できるだけでなく、スタッフはレジ業務から解放されます。
これにより、これまでレジに割いていた人員を、品出しやお客様への声かけ、売り場のメンテナンスといった、より付加価値の高い業務に再配置することが可能です。
さらに、カメラやセンサーが自動で商品を認識し、ウォークスルーで決済が完了する無人決済店舗も登場しており、究極の省人化と未来の購買体験を実現する切り札として注目されています。
「この商品は、長年の勘でこれくらい発注する」といった、特定のベテランスタッフの経験に頼った在庫管理は、その担当者が不在の際に業務が滞るなど、大きなリスクをはらんでいます。
AI(人工知能)を活用することで、こうした属人化からの脱却が可能です。AIは、過去の販売実績や天候、曜日、近隣のイベント情報、さらにはSNSのトレンドといった膨大なデータを瞬時に分析し、人間では不可能な精度で最適な発注量を算出します。
これにより、担当者の発注業務にかかる時間を劇的に削減できるだけでなく、欠品による販売機会の損失や、過剰在庫による廃棄ロスを未然に防ぐことができます。
これは店舗の利益改善に直接貢献するだけでなく、フードロス削減といった社会的な課題解決にもつながる取り組みです。
「お店の営業時間は?」「商品の在庫はありますか?」といった、日々繰り返される定型的な問い合わせへの対応に、貴重なスタッフの時間が奪われていることも少なくありません。
Webサイトや公式アプリにチャットボットやよくある質問ページを整備することで、これらの簡単な質問には24時間365日、人手を介さずに自動で応答できるようになります。
これにより、お客様はいつでも気軽に疑問を解決でき、スタッフはより複雑な相談や、丁寧な商品説明といった人間ならではの温かみのある接客に集中できます。
結果として、問い合わせ対応のコストを削減しながら、顧客満足度とスタッフのエンゲージメントを同時に向上させることが可能になるのです。
日々の売上データをExcelに転記する、スタッフの勤怠データを集計して給与計算システムに入力する、請求書を作成して取引先に送付するなど、店舗の裏側には多くの定型的なパソコン作業が存在します。
こうした「誰がやっても同じ結果になる」単純作業を自動化する技術がRPA(Robotic Process Automation)です。RPAは、ソフトウェア上のロボットが、これまで人が行っていたマウス操作やキーボード入力を正確に記憶し、代行してくれます。RPAを導入することで、ヒューマンエラーを防ぎながら、作業時間を大幅に削減できます。
これにより、事務スタッフを単純作業から解放し、売上データの分析や販促企画の立案といった、より創造的で付加価値の高い仕事に時間を使ってもらうことができ、人的リソースを最大限に有効活用できます。
小売DXの効果は、日々の業務効率化だけにとどまりません。デジタル技術を活用することで、スタッフの教育や採用活動といった、人材に関する課題にもアプローチが可能です。
ここでは、具体的な取り組みについて紹介します。
新人スタッフが入るたびに、教育担当者がつきっきりで指導するのは大変な負担です。
eラーニングシステムを導入すれば、接客の基本マナーや商品知識、レジの操作方法などを、スタッフが自身のスマートフォンやタブレットを使い、空いた時間に自分のペースで学べるようになります。これは、経済産業省が示す「DXリテラシー標準」で求められる、個々人がデジタル技術を活用して主体的に学ぶ姿勢を育むことにもつながります。
特に、実際の業務手順を撮影した動画マニュアルは、言葉で説明するよりも直感的に理解しやすく、教育の質を均一に保つ上でも非常に効果的です。
これにより、教育にかかる時間を大幅に短縮し、教える側・教わる側双方の負担を軽減できます。
出典参照:デジタルスキル標準|経済産業省
働きやすい環境を整えることは、人材の定着率を高める上で非常に重要です。
たとえば、クラウド型のシフト管理ツールを導入すれば、スタッフはスマートフォンから手軽に希望シフトを提出したり、急な休み希望を伝えたりできます。管理者にとっても、シフト調整や作成の手間が大幅に削減されるでしょう。
また、店舗間の情報共有にビジネスチャットツールを活用すれば、連絡事項がスムーズに伝わり、組織としての一体感が生まれます。こうしたITツールの活用は、従業員の利便性を高め、柔軟で働きやすい職場環境の実現につながります。
小売DXを推進することは、人材不足の解消だけでなく、経営全体にプラスの影響をもたらします。
ここでは、DXによって得られる代表的な3つのメリットについて、具体的に解説していきます。
DXによる業務の自動化や効率化は、人件費の削減に直接的に貢献します。
たとえば、セルフレジの導入でレジに必要な人員を減らしたり、RPAでバックオフィス業務を自動化したりすることで、その分の人件費を抑えることが可能です。
また、AIによる需要予測で発注業務の時間を短縮するなど、従業員一人ひとりの生産性が向上します。
これにより生まれた時間やコストといった経営資源を、新たなサービス開発や販促活動など、さらなる売上向上を目指すための戦略的な投資に振り向けることができるようになります。
DXは、従業員の負担を減らし、働きがいのある職場環境を実現します。単純作業や長時間労働から解放されることで、スタッフは心身ともにゆとりを持って働くことができるようになります。
また、eラーニングなどを通じてスキルアップの機会が提供されれば、仕事に対するモチベーションも向上するでしょう。ITツールを活用してシフトの希望が通りやすくなったり、情報共有がスムーズになったりすることも、働きやすさにつながります。
こうした従業員満足度の向上は、エンゲージメントを高め、結果として離職率の低下という形で表れるはずです。
DXによって効率化され、創出された時間や人的リソースを、顧客サービスの向上に振り向けることができます。
たとえば、スタッフが単純作業から解放され、お客様への丁寧な声かけや商品提案に時間を使えるようになれば、顧客体験は格段に向上するでしょう。
また、データ分析に基づき、顧客一人ひとりの好みに合わせた商品をオンラインでおすすめしたり、レジの待ち時間を短縮したりすることも、顧客満足度の向上に直結します。
満足したお客様はリピーターとなり、店舗のファンになってくれる可能性が高まり、長期的な売上アップに貢献してくれます。

実際にDXを活用して人材不足という大きな壁を乗り越え、成長を続ける企業の事例を見ていきましょう。
自社のビジネスに近い事例を参考にすることで、具体的な導入イメージが湧きやすくなるはずです。
コンビニ大手のローソンは、業界に先駆けてDXに積極的に取り組んできました。
特に有名なのが、AIを活用した発注システムです。過去の販売実績や天候、周辺のイベント情報などをAIが分析し、最適な発注量を提案することで、店舗オーナーやスタッフの発注業務にかかる時間を大幅に削減しました。
これにより、経験の浅いスタッフでも精度の高い発注が可能になり、店舗運営の属人化を防いでいます。
また、スマートフォンで決済が完了する「スマホレジ」や、一部店舗での無人決済システム「Lawson Go」の導入など、レジ業務の省人化にも力を入れ、少人数での店舗運営モデルを追求しているのです。
出典参照:働き手不足をデジタルイノベーションでサポート!|株式会社ローソン
ウォークスルー決済導入店舗 「Lawson Go」10月11日(火)から、新たに展開開始|株式会社ローソン
人気アパレルブランドのナノ・ユニバースは、オンラインストアでの接客にDXをうまく活用しています。
公式サイトに導入されたチャットボットが、サイズ感やコーディネートに関する簡単な質問に24時間自動で回答。これにより、これまでスタッフが対応していた多くの問い合わせ業務を自動化し、業務負担を大幅に軽減しました。
さらに、AIが顧客の閲覧履歴や購買データを分析し、一人ひとりの好みに合わせたスタイリングを提案するパーソナライズ機能も実装しています。オンラインでありながら、まるで店舗で接客を受けているかのような顧客体験を提供し、売上アップにつなげている例です。
出典参照:株式会社空色は、株式会社ナノ・ユニバースとAIを活用したチャットボットによるカスタマーサポート体験の提供に着手いたします。|株式会社ナノ・ユニバース
多くのスーパーマーケットで導入が進み、成果を上げているのが、IoT重量計「スマートマットクラウド」です。
これは、飲料の箱や調味料のボトルといった商品の下にマットを敷くだけで、その重さの変化から在庫量をリアルタイムで自動計測できる画期的なシステムです。これまでスタッフが多くの時間を費やしていた、目視による在庫確認や手作業での棚卸し業務が不要になります。
さらに、在庫が設定した量を下回ると自動で発注する機能もあり、発注忘れによる欠品を防ぎ、安定した売場づくりに貢献しています。
小売DXを成功に導くためには、やみくもに最新ツールを導入するのではなく、しっかりとした事前準備が不可欠です。
ここでは、導入を検討する際に必ず押さえておきたい3つの準備ポイントを解説します。
まず最初に行うべきは、「何のためにDXを導入するのか」という目的を、社内ではっきりと共有することです。目的が曖昧なままでは、最適なツールを選ぶことも、導入効果を測ることもできません。
そのためには、まず現場が抱えている課題を具体的に洗い出す必要があります。「レジの待ち時間が長くお客様からクレームが多い」「月末の棚卸し作業でスタッフの残業が常態化している」「発注ミスによる欠品や過剰在庫が減らない」など、現場のスタッフにヒアリングするなどして、生の声を集めましょう。
全ての課題を一度に解決するのは難しいため、洗い出した課題の中から、最も経営への影響が大きく、解決が急がれるものは何か、優先順位をつけることが重要です。
DXは、誰かが「やれ」と指示するだけでは決してうまくいきません。実際にDXを推進していく中心的な担当者やチームを決め、経営層も含めた全社的な協力体制を整えることが不可欠です。
また、どんなに優れたシステムを導入しても、現場のスタッフが使いこなせなければ宝の持ち腐れになってしまいます。従業員がどの程度ITツールに慣れているのか、そのITリテラシーのレベルを事前に把握しておきましょう。
もし不安がある場合は、導入前に簡単な研修会を開いたり、分かりやすい動画マニュアルを用意したりするなど、現場の不安を和らげるサポート体制をあらかじめ計画しておくことが大切です。新しいことへの抵抗感をなくし、前向きに取り組んでもらうための配慮が成功を左右します。
解決したい課題と社内の状況が整理できたら、それを基にツールを選ぶための「ものさし」となる判断基準を明確にします。
優先順位をつけた課題を解決できる機能があるか、自社の事業規模や予算に見合っているか、といった点はもちろん重要です。それに加えて、現場のスタッフが直感的に操作できるか、将来的に機能を追加できる拡張性はあるか、導入後にトラブルがあった際のサポート体制は充実しているか、といった運用面での基準も忘れてはいけません。
これらの基準をリストアップし、複数のツールを客観的に比較検討することが、自社にとって本当に価値のある「賢い道具」選びにつながるのです。

入念な準備が整ったら、いよいよDXの推進ステップに進みます。
ここでは、DX推進を成功させるための3つのステップを紹介します。
いきなり全店舗、全部署で大々的に新しいシステムを導入するのはリスクが伴います。まずは特定の店舗や一部の業務に限定して試験的に導入する「スモールスタート」がおすすめです。
たとえば、「A店の在庫管理業務だけ」といった形で始めることで、導入コストを抑えられるだけでなく、万が一問題が発生した際の影響も最小限に食い止められます。
そして最も重要なのは、その試験導入で「作業時間が何時間削減できたか」「欠品率が何%改善したか」といった成果を具体的に測定・評価することです。この客観的なデータが、本格導入に向けた社内での説得材料になります。
DXは、経営層や情報システム部門だけで進めてもうまくいきません。なぜなら、実際にそのツールを毎日使うのは現場のスタッフだからです。
導入後も、「この機能が使いにくい」「もっとこうなれば便利なのに」といった現場の声を定期的にヒアリングする場を設けましょう。そして、その声を無視するのではなく、ツールの設定変更や運用ルールの見直しに積極的に反映させていくことが重要です。
現場のスタッフを「やらされる側」ではなく、「一緒に改善していくパートナー」として巻き込む姿勢が、DXを現場に根付かせるための鍵となります。
「社内にITに詳しい人材がいない」「何から手をつけていいか分からない」。そんな時は、無理に自社だけで解決しようとせず、外部の専門家の力を借りるのも賢明な選択です。
DX導入を支援するコンサルティング会社や、業界の事情に詳しいITベンダーなど、信頼できるパートナーに相談することで、自社に最適な解決策への近道が見つかるでしょう。
また、国や地方自治体は、中小企業のITツール導入を支援するための「IT導入補助金」をはじめとする、様々な補助金制度を用意しています。
こうした制度をうまく活用すれば、導入にかかるコスト負担を大幅に軽減できる可能性がありますので、積極的に情報収集することをおすすめします。
出典参照:IT導入補助金2025|サービス等生産性向上IT導入支援事業事務局
少子高齢化が進む今、小売業の人手不足は、もはや特別なことではなくなりました。「気合と根性で乗り切ろう!」というやり方だけでは、大切なお店とスタッフを守り抜くのは難しい時代です。
そこで大きな力になるのが、今回ご紹介した「小売DX」です。単純な作業を任せることで、スタッフの負担はぐっと軽くなります。生まれた時間で、お客様ともっと丁寧に向き合えるようになれば、お店のファンも自然と増えていくでしょう。
つまりDXは、単なる経費削減の道具ではありません。スタッフの笑顔を増やし、お客様にもっと喜んでもらい、結果としてお店の売上もアップさせる、未来に向けた大切な投資なのです。
「何から始めればいいか分からない…」と感じるかもしれません。まずは「この作業、もっと楽にならないかな?」と、身の回りを見渡すことから始めてみましょう。
その小さな気づきこそが、人手不足の課題を乗り越え、未来のお店を守るために大切な第一歩になるはずです。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
