小売DXの第一歩はペーパーレス化!メリットや書類管理の課題を解説
小売

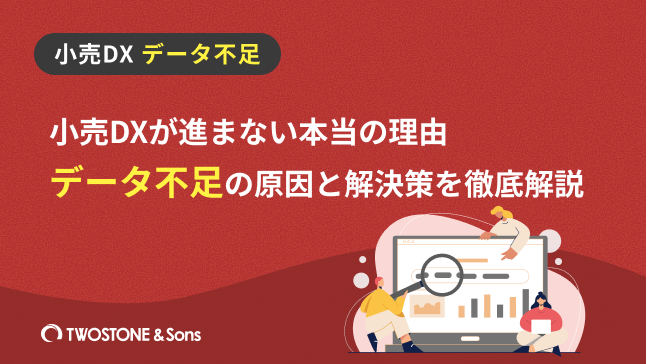
【小売DXが進まない本当の理由】多くの企業が直面する「データ不足」の壁。本記事では、データ不足に陥る4つの原因を深掘りし、ツールの活用法や人材育成など、具体的な解決策をステップで解説します。成功事例も交え、データで競合に差を付けるための実践的なノウハウが満載です。
多くの小売業が直面する売上停滞や人手不足。その解決策として「小売DX」が注目されていますが、「何から手をつければいいか分からない」という声も少なくありません。
実は、その停滞の根本には深刻な“データ不足”が隠されています。この記事では、なぜ小売DXにデータが不可欠なのか、データ不足に陥る構造的な原因と、それを乗り越えるための具体的な解決策を、成功事例を交えながら徹底的に解説します。
データ不足を解決し、競合に差を付ける一歩を踏み出しましょう。
小売DXとは、AIやIoTといった最先端のデジタル技術を駆使して、従来のビジネスモデルや業務プロセス、さらには企業文化に至るまでを根本から変革する取り組みのことです。
これは単にデジタルツールを導入する「デジタル化」とは一線を画し、データをビジネスの核に据えて、全く新しい顧客体験と企業価値を創造することを最終的な目標としています。
それでは、なぜ今、多くの小売企業にDXが求められているのでしょうか。その背景を見ていきましょう。
現代の消費者は、スマートフォンを片手に、いつでもどこでも情報を収集し、商品を購入するようになりました。
たとえば、朝の通勤電車でSNSの広告を見て商品を認知し、昼休みにはレビューサイトで口コミを比較検討、仕事帰りに実店舗で商品を手に取って確認し、最終的には自宅のソファでくつろぎながらECサイトの最安値で購入する、といった行動はもはや珍しくありません。
このように、オンラインとオフラインの境界線が曖昧になったOMO(Online Merges with Offline)時代においては、顧客がいつ、どこで、どのような情報に触れ、購買に至ったのかという一連の行動をデータとして捉えることが極めて重要になります。
顧客一人ひとりの複雑な購買ジャーニーを理解し、その時々で最適なアプローチをしなければ、顧客の心を掴むことはできないでしょう。
日本の社会問題である少子高齢化の波は、労働集約型である小売業界に特に深刻な影響を及ぼしています。
多くの店舗が慢性的な人手不足に悩み、現場で働く従業員一人ひとりへの負担は増大し続けています。限られた人員で日々の店舗運営を維持するためには、発注、在庫管理、品出し、レジ応対といった多岐にわたる業務をこなさなければならず、従業員は疲弊し、サービスの質の低下にもつながりかねません。
このような状況を打破するためには、人間の勘や経験だけに頼るのではなく、デジタル技術を活用して業務を効率化・自動化することが急務です。データを活用した需要予測による発注の最適化や、ロボットによる品出し、セルフレジの導入などは、従業員を単純作業から解放し、より付加価値の高い接客や売り場づくりに集中させるための鍵となるのです。
商品の機能や品質、価格といった要素だけで競合と差別化を図ることが非常に困難な時代になりました。インターネットの普及により、消費者は瞬時に価格を比較でき、多くの商品はコモディティ化(均質化)しています。
このような市場環境の中で企業が生き残るためには、商品そのものの価値(モノ消費)だけでなく、その商品を購入する過程で得られる感動や満足感といった「購買体験」の価値を高めることが不可欠です。
たとえば、「自分の好みを理解してくれて、ぴったりの商品を提案してくれた」「レジで全く待つことなく、スムーズに買い物ができた」といったポジティブな体験は、顧客のロイヤルティを高め、リピート購入へとつながります。
こうした質の高い体験を提供するためには、顧客データや店舗運営データを精密に分析し、サービスの精度を極限まで高めていく努力が求められるのです。
データに基づいた小売DXを本格的に推進することで、企業は単なる業務改善に留まらない、経営の根幹に関わる大きな変革の果実を手にすることができます。
ここでは、DX導入によって得られる代表的な3つのメリットについて、具体的な内容を深く掘り下げていきましょう。
小売業の現場では、長年にわたり従業員の勘や経験則に依存した業務が数多く存在しました。たとえば、商品の発注業務では、ベテラン担当者が過去の売れ行きや季節、近隣のイベントなどを頭の中で考慮して発注量を決めていました。
しかし、小売DXはこうした属人的なプロセスを劇的に変革します。AIによる需要予測システムを導入すれば、過去の膨大な販売データや天候、曜日、販促キャンペーンといった多様な変数を統合的に分析し、人間では到底不可能な精度で未来の需要を予測してくれるのです。
これにより、発注業務は半自動化され、従業員は最終確認を行うだけで済むようになり、作業時間を大幅に削減できます。
同様に、在庫管理や従業員のシフト作成といった煩雑な業務も、データを活用することで最適化され、現場の負担軽減と生産性の向上に直接的に貢献します。
小売DXの中核は、顧客一人ひとりを深く理解し、最高の体験を提供することにあります。
そのために不可欠なのが、顧客データの活用です。会員アプリやポイントカードを通じて収集された顧客の年齢や性別といった属性データと、購買履歴データを組み合わせることで、顧客の解像度が飛躍的に高まります。「30代女性で、オーガニック食品を好む顧客」「週末に家族で来店し、まとめ買いをする傾向がある顧客」といった具体的なペルソナが見えてくるのです。
この深い顧客理解に基づき、一人ひとりの興味関心に合わせた商品をメールやアプリで推薦したり、誕生日月に特別なクーポンを配信したりといった、きめ細やかなパーソナライズ施策が可能になります。
これにより、顧客は「自分のことを分かってくれている」と感じ、店舗への愛着を深めるでしょう。これが顧客満足度の向上、ひいてはLTV(顧客生涯価値)の最大化につながるのです。
かつての小売業の経営判断は、社長や役員といった一部の経営層が持つ経験や勘、そして月次で報告される売上データといった限られた情報に頼らざるを得ませんでした。
しかし、小売DXはこうした状況を一変させます。店舗のPOSデータ、ECサイトのアクセスログ、顧客データ、在庫データ、さらには市場のトレンドデータまで、社内外のあらゆるデータがリアルタイムで収集・統合され、BIツールなどを通じて可視化されます。
これにより、経営層は「どの店舗のどの商品が、どの顧客層に、いつ売れているのか」「実施したマーケティング施策が売上にどれだけ貢献したのか」といったビジネスの現状を、正確かつ即座に把握できるようになるのです。
このようなデータに基づいた客観的な事実(ファクト)を土台とすることで、場当たり的な意思決定ではなく、より戦略的で確度の高い経営判断、すなわちデータドリブン経営を実践することが可能になります。

小売DXという壮大な変革プロジェクトにおいて、データはエンジンであり、羅針盤でもあります。
DXにおいてデータが欠かせない理由を、「業務効率化」「顧客体験」「競争力」という3つの重要な側面に分解、解説します。
店舗運営における永遠の課題は、「機会損失の最小化」と「廃棄ロスの削減」という、相反する目標をいかに両立させるかという点にあります。
人気商品が棚から消えれば機会損失となり、売れない商品を過剰に仕入れれば廃棄ロスとなって利益を蝕みます。このジレンマを解消する鍵こそが、日々の売上データや在庫データ、来店客数といった“効率化データ”なのです。
これらのデータをAIで分析することで、需要を高い精度で予測し、欠品と過剰在庫を同時に抑制する最適な発注量を算出できます。また、時間帯ごとの売上や客数を分析すれば、混雑する時間帯に人員を厚く配置するなど、データに基づいた効率的な人員配置が実現できるのです。
現代の消費者は、単にモノを手に入れるだけでなく、購買プロセス全体に満足や楽しさを求めるようになりました。このような優れた顧客体験を設計するための設計図となるのが、顧客の購買履歴や行動データです。
たとえば、ECサイトである顧客が特定ブランドの化粧水を購入したデータがあれば、次はそのブランドの乳液を推薦できます。さらに、サイト上でどの商品を長く閲覧していたか、といった行動データを組み合わせることで、顧客の潜在的なニーズまで推測することが可能になります。
このように、顧客一人ひとりの行動を深く理解することで、画一的なアプローチから脱却し、「まるで自分のためのサービスだ」と感じてもらえるようなパーソナライズされた体験を提供できるのです。これは、顧客との長期的な信頼関係を築く上で極めて重要な戦略と言えるでしょう。
多くの小売企業がPOSデータを保有していますが、その多くは「何がどれだけ売れたか」という結果の記録に留まっています。しかし、本当の競争力は、そのデータから「なぜ売れたのか」「なぜ売れなかったのか」というインサイト(洞察)を導き出す“分析力”に宿ります。
たとえば、POSデータと店内の動線データを組み合わせることで、「商品は手に取られるが購入に至らない」という事実が判明するかもしれません。このインサイトから、「商品説明が不十分ではないか」といった仮説を立て、具体的な改善アクションに繋げることができます。
データから仮説検証のサイクルを高速で回す能力こそが、変化の激しい市場で競合他社をリードし続けるための最強の武器となるのです。
多くの企業がデータの重要性を認識しながらも、いざDXを推進しようとすると「活用できるデータがない」という深刻な壁に突き当たります。
この“データ不足”という問題は、複数の要因が複雑に絡み合って生じています。ここでは、その代表的な4つの原因を深掘りします。
多くの歴史ある小売企業では、長年にわたって業務ごとにシステムを導入・改修してきた結果、「レガシーシステム」と呼ばれる、複雑で老朽化したITインフラを抱えています。
店舗のPOSシステム、本社の基幹システム、ECサイトの管理システムなどがそれぞれ独立した「サイロ」のように存在し、互いに連携することができません。この状態では、店舗の売上データとECサイトの顧客データを統合して分析するといった、全社横断的なデータ活用は極めて困難です。
データを抽出しようにも特殊な技術が必要だったり、そもそも出力機能がなかったりするため、宝の持ち腐れ状態に陥っているケースが少なくありません。これはDX推進の大きな足かせとなっています。
たとえ各システムからデータを取り出せたとしても、次なる壁が「データの品質」の問題です。各部門や店舗が独自のルールでデータを入力・管理してきたため、データ形式や粒度がバラバラで、そのままでは統合して分析することができません。
たとえば、同じ顧客であっても、店舗の会員登録では「東京都新宿区」と入力されているのに、ECサイトでは「東京都新宿」と登録されているかもしれません。商品マスタも同様で、同じ商品に複数のコードが割り振られていることもあります。
こうした不整合なデータを統合するためには、「データクレンジング」や「名寄せ」と呼ばれる地道なデータ整備作業が必要不可欠ですが、これには膨大な時間とコスト、そして専門的なノウハウが求められます。こうしたデータの標準化という基盤がなければ、より高度な分析をすることはできないのです。
小売業が保有するデータとして最も一般的なのは、POSシステムから得られる購買結果のデータです。しかし、このデータだけでは「誰が」「なぜ」買ったのかという、顧客理解の核心に迫ることはできません。
特に、現金払いの非会員客が大半を占めるような業態では、顧客の顔が見えず、その属性や購買動機は全くのブラックボックスです。
顧客像を明確にするためのデータを収集する仕組み、たとえば、メリットのある会員プログラムや便利なスマートフォンアプリといった施策を展開してこなかった企業は、必然的に深刻なデータ不足に陥ります。顧客とのデジタルな接点がなければ、パーソナライズされたマーケティング施策を打つことは極めて難しいでしょう。
仮に、最新のシステムを導入し、クリーンなデータを大量に収集できたとしても、それをビジネス価値に転換できる人材がいなければ意味がありません。
データ分析のスキルを持つDX人材は多くの業界で引く手あまたであり、確保が難しいのが現状です。さらに重要なのは、分析結果を解釈し、具体的なビジネスアクションに繋げる能力です。専門家が高度な分析を行っても、現場の担当者がそれを理解し、活用できなければ宝の持ち腐れになってしまいます。
データを活用するためには、専門人材の育成・確保と同時に、組織全体でデータを重視する文化を醸成することが不可欠であり、この組織変革こそが最も困難な課題の一つと言えるかもしれません。

データが不足している状態は、単にDXが進まないという問題に留まらず、日々の店舗運営や企業の収益性に深刻な悪影響を及ぼします。
ここでは、データ不足が引き起こす3つの具体的なリスクについて、現場で起こりがちなシナリオを交えながら解説します。
データという顧客を映し出す鏡がなければ、マーケティング担当者は過去の成功体験や漠然としたイメージといった、いわば勘と経験に頼って販促施策を企画せざるを得ません。
たとえば、「若者向けのキャンペーンだから、若者が集まるエリアにチラシを重点的に配布しよう」と計画したとします。しかし、実際にはその商品のコアなファンは、少し離れた郊外に住む主婦層だったかもしれません。結果として、多額の広告費を投じたにもかかわらず、ターゲットに全く響かず、効果はゼロに終わる可能性があります。
このように、顧客像が曖昧なままでは、あらゆる販促活動が的を外し、貴重なマーケティング予算を浪費してしまうリスクが常に付きまといます。これは、マスマーケティングの限界が露呈している典型的な例と言えるでしょう。
データに基づいた標準的な業務プロセスが存在しない職場では、業務の品質が特定の個人のスキルや経験に大きく依存する「属人化」が進みます。
たとえば、「A店の発注業務は、ベテランのBさんがいるから常に的確だ」という状況があったとします。これは一見すると良いことのように思えますが、組織全体で見た場合、非常に大きなリスクをはらんでいます。もしBさんが急に退職したり異動したりすれば、A店の発注精度は途端に低下し、売上や利益に直接的なダメージを与えかねません。
Bさんが長年培ってきたノウハウは、他の従業員が簡単に引き継ぐことができないのです。このように、改善活動が個人商店化してしまうと、組織としての学習や成長が阻害され、全体としての生産性はいつまで経っても向上しないのです。
正確な需要予測データがなければ、在庫管理は常に当てずっぽうの状態になります。その結果として頻発するのが、人気商品の「欠品」です。顧客が期待して来店したにもかかわらず、「申し訳ありません、品切れです」と伝えなければならない状況は、顧客を深く失望させます。
これは単にその一回の売上を逃す「販売機会の損失」であるだけでなく、「あの店はいつ行っても欲しいものがない」というネガティブなブランドイメージを植え付け、顧客離れを引き起こす原因にもなります。
その一方で、売れない商品を過剰に仕入れてしまう「過剰在庫」も経営を圧迫します。最終的には値下げや廃棄処分となり、企業の利益を大きく損なうことになるのです。
深刻なデータ不足という課題を克服し、小売DXを本格的な成長軌道に乗せるためには、戦略的かつ段階的なアプローチが不可欠です。
ここでは、その核心となる「収集」「整備・可視化」「活用体制の構築」という3つのステップについて、具体的な取り組みを解説します。
データ活用の第一歩は、何よりもまず、質の高いデータを継続的に収集するための基盤を構築することから始まります。これまで取得できていなかった顧客データを手に入れるためには、顧客にとってメリットのある仕組みを設計することが重要です。
たとえば、登録すれば限定クーポンがもらえたり、ポイントが貯まったりする魅力的な会員プログラムやスマートフォンアプリを開発します。これにより、顧客は自らの意思でデータを提供してくれるようになります。
また、店舗というオフラインの場でも、AIカメラやIoTセンサーを導入することで、来店客数や顧客の属性、店内での動きといった貴重な行動データを自動的に収集することが可能になります。
スモールスタートで効果を検証しながら段階的に展開していくことが成功のポイントです。
様々なチャネルから収集したデータは、そのままではただの数字の羅列に過ぎません。これらのデータを真の資産に変えるためには、誰もが理解し、活用できる形に整備し、可視化するプロセスが不可欠です。
まず、店舗、ECサイト、アプリなど、サイロ化されたシステムに散在するデータをCDP(後述)のような基盤に集約し、顧客一人ひとりを軸に統合します。次に、BIツール(後述)を活用し、これらの統合されたデータをグラフやダッシュボードといった直感的なインターフェースで表示します。
これにより、専門的な知識を持たない現場のスタッフでも、リアルタイムで状況を把握し、データに基づいた会話や議論ができるようになります。
最新のツールを導入し、データを可視化したとしても、それを使いこなす人間と、データ活用を是とする組織文化がなければ、DXは絵に描いた餅に終わってしまいます。
したがって、ツール導入と並行して、データを活用するための人材育成と組織体制の構築に全社を挙げて取り組む必要があります。全社員を対象としたデータリテラシー向上のための研修を実施し、データを見て考えることの重要性を浸透させましょう。
同時に、データ分析を専門に行う部署を設置したり、外部の専門家と協業したりすることも有効です。最も大切なのは、経営層が率先してデータに基づいた意思決定を行い、その重要性を社内に浸透させていくことです。

データ不足を解消し、その活用を加速させるためには、目的に応じた適切なデジタルツールを導入することが極めて効果的です。
ここでは、小売DXの実現に欠かせない代表的な4種類のツールについて、それぞれの役割と機能、そして互いの関係性を詳しく解説します。
CDP(カスタマー・データ・プラットフォーム)とは、小売DXにおけるデータ活用の心臓部とも言える基盤です。その最大の役割は、店舗のPOSシステム、ECサイトの購買履歴、アプリの利用ログなど、社内外に散在している顧客に関するデータを収集・統合することにあります。
CDPは、これらのバラバラなデータを「名寄せ」という技術を使って、一人の顧客として正確に紐付けます。これにより、これまで分断されていた顧客のオンラインとオフラインの行動を横断的に把握し、360度の顧客像を鮮明に描き出すことが可能になるのです。
この統合されたリッチな顧客データは、他のツールと連携することで、高度な分析や精緻なマーケティング施策の実行を支える土台となります。
CDPが顧客データを統合・分析するための「頭脳」だとすれば、CRM(顧客関係管理)とMA(マーケティング・オートメーション)は、その分析結果に基づいて顧客とのコミュニケーションを実行する「手足」の役割を担います。
CRMは、顧客情報や対応履歴を一元管理し、良好な関係を維持・向上させるために使われます。一方、MAは、メール配信やキャンペーン管理といったマーケティング活動を自動化するツールです。
たとえば、CDPで特定の顧客リストを抽出し、MAと連携すれば、その顧客の状況に応じたシナリオを自動で実行できます。このように、各ツールを連携させることで、きめ細やかなアプローチを効率的に実行できるのです。
BI(ビジネス・インテリジェンス)ツールとは、企業内に蓄積された膨大なデータを、専門家でなくても理解できる形に変換してくれる強力な翻訳機です。
その主な役割は、売上データ、在庫データ、顧客データなどを取り込み、グラフやチャート、ダッシュボードといった直感的なビジュアル形式で「見える化」することです。
たとえば、全国の店舗売上を地図上に色分けして表示したり、時間帯別の売上推移を折れ線グラフで示したりできます。これにより、本社の経営層から現場の店長まで、複雑なデータの中からビジネスに役立つインサイトを迅速に見つけ出すことが可能になります。
レポート作成にかかる時間も大幅に削減され、より本質的な分析や議論に時間を費やせるようになるでしょう。
IoTとAIは、特に実店舗におけるデータ活用を飛躍的に進化させる技術です。
IoTの役割は、これまでデータ化が難しかった現実世界の事象をデジタルデータとして捉えることです。たとえば、「どの棚の前で何秒立ち止まったか」「どの商品が手に取られたか」といった、これまで把握しきれなかった細かい事実をすべて記録します。
次に、その膨大な記録をAIが「超優秀な分析官」として分析します。人間では気づけないような「雨の日にはA商品がよく売れる」「B商品を買う人は、C商品も一緒に見る傾向がある」といった、ビジネスに役立つ隠れた法則やパターンを発見します。
このように、IoTが集めた「事実」を、AIが分析して「ビジネスに役立つ知見」に変えることができます。この連携によって、より正確な需要予測や、お客様が本当に欲しいと思う商品の提案が可能になるのです。
データ不足という壁を乗り越え、DXを推進することで目覚ましい成果を上げている企業は、実際にどのようにデータと向き合っているのでしょうか。
ここでは、日本の小売業界を代表する2社の先進的な取り組みを深掘りし、その成功の秘訣を探ります。
総合スーパーのイトーヨーカ堂は、AIを活用した商品発注システムを導入し、長年の課題であった発注業務の最適化を実現しました。
このシステムは、過去の販売実績や天候、客数といった多様なデータをAIが分析し、最適な販売予測数を算出します。担当者はAIが提示する客観的な予測値を参考にすることで、発注作業にかかる時間を大幅に削減できました。
これにより、欠品による販売機会の損失を防ぎつつ、過剰在庫による廃棄ロスも削減するなど、業務効率化と社会課題の解決を同時に達成しています。データに基づいた判断が、従業員の負担を減らし、より良い店舗運営につながった好例です。
出典参照:セブン&アイグループが目指すニューノーマル|株式会社セブン&アイ・ホールディングス
ディスカウントストアを運営するトライアルカンパニーは、「スマートショッピングカート」と「リテールAIカメラ」を組み合わせた独自のスマートストアを展開しています。
顧客はカートで商品をスキャンしながら買い物をするため、レジ待ちが不要になり、快適な買い物体験が実現しました。同時に、店内に多数設置されたAIカメラは、顧客の動線や棚の状況をリアルタイムで分析。欠品を自動で検知してスタッフに通知するなど、店舗運営の劇的な効率化に貢献しています。
データ活用によって、顧客満足度の向上と業務効率化を両立させた先進的な事例と言えるでしょう。
出典参照:トライアルホールディングス リテールDX挑戦事例紹介|株式会社トライアルホールディングス
この記事では、小売DXが進まない根本原因である「データ不足」に焦点を当て、その原因から解決策までを解説しました。
購買行動が複雑化し、人手不足が深刻化する現代において、データに基づかない経営は、羅針盤を持たずに荒波の海へ漕ぎ出すようなものです。顧客が何を求め、店舗で何が起きているのかを正確に把握することが、生き残りの鍵となります。
データ不足を克服するための道筋は、「収集」「見える化」「活用体制」の3ステップです。まずはスモールスタートで、確実なデータを手に入れることから始めましょう。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
