小売DXの第一歩はペーパーレス化!メリットや書類管理の課題を解説
小売

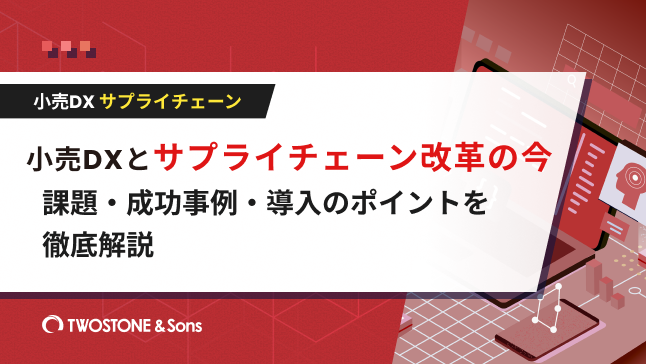
小売DXでサプライチェーンの課題を解決しませんか?この記事では、AIによる在庫最適化や物流自動化のメリットから、キリンなどの成功事例、導入で失敗しない5つのステップまでを徹底解説。DX推進の具体的なヒントが見つかります。
消費者のニーズが多様化し、人手不足が深刻化する現代の小売業界で、DXは避けて通れない課題です。特に、商品の調達からお客様の手元に届くまでのサプライチェーンの改革は、企業の競争力を大きく左右します。
この記事では、小売DXとサプライチェーン改革の基本から、業界が抱える課題、具体的な成功事例、そして導入を成功させるためのポイントまで、わかりやすく解説していきます。

小売DXとは、単にデジタルツールを導入することだけを指すのではありません。AIやIoT、ビッグデータといった先進技術を使って、業務の進め方やビジネスの仕組みそのものを根本から変え、新しい顧客価値を生み出す取り組みのことです。
これまでの画一的な店舗運営やサービス提供から一歩進んで、オンラインとオフラインを融合させたスムーズな購買体験を提供したり、お客様一人ひとりのデータに基づいて最適な商品を提案したりすることが可能になります。この変革は、単なる業務効率化やコスト削減にとどまらず、お客様の満足度を高め、競争上の優位性を確立するための重要な戦略といえるでしょう。
出典参照:DX推進指標(サマリー)|経済産業省
サプライチェーンとは、商品が原材料の調達から生産、在庫管理、配送、販売を経て、最終的にお客様に届くまでの一連の流れ(供給連鎖)を指します。
そして、サプライチェーンのDXとは、この一連の流れをデジタル技術の力で変革し、全体の透明性を高めて最適化を図ることです。具体的には、これまで各部門や企業の間でバラバラになりがちだった情報をデータでつなぎ、誰でも状況が見えるようにします。その上で、AIによる需要予測や物流の自動化などを進めていくのです。
これにより、サプライチェーン全体がより効率的で、急な変化にも強いしなやかな体制へと進化していきます。
多くの小売企業が、サプライチェーンにおいて様々な課題を抱えています。DXによる改革が急務とされる背景には、見過ごすことのできない問題点が潜んでいます。
多くの小売業の現場では、いまだに電話やFAXでの発注、手作業での在庫確認、Excelでの管理といったアナログな手法が残っています。これらの方法は担当者の経験や勘に頼る部分が大きく、業務の属人化を招いてしまいます。特定の担当者しか業務内容を把握しておらず、その人が不在だと業務が滞る、といったリスクを常に抱えているのです。
その結果、調達、在庫、販売といった各部門や取引先との間で情報がリアルタイムに共有されず、データがバラバラに分断されてしまいます。
このようにサプライチェーン全体の状況が見えないことが、過剰在庫や欠品といった、より大きな問題を引き起こす根本的な原因となっています。
担当者の経験や勘に頼った需要予測は精度に限界があり、過剰在庫や欠品を頻繁に引き起こします。過剰在庫は、倉庫の保管コストを圧迫するだけでなく、商品の品質劣化や流行遅れによる陳腐化を招きます。最終的には、利益を度外視したセール販売や廃棄処分に至り、企業のキャッシュフローを直接的に悪化させる大きな要因となります。
一方で、欠品は「せっかく来店したのに商品がなかった」という顧客の失望を招き、その場の販売機会を失うだけではありません。顧客満足度の低下やブランドからの離反にもつながり、長期的な売上にも悪影響を及ぼします。
在庫が多すぎても少なすぎても、それはどちらも経営に深刻なダメージを与えるため、サプライチェーンにおける最重要課題の一つなのです。
アナログな情報伝達や手作業は、発注から納品までの時間、すなわちリードタイムの長期化を招きます。FAXでの注文確認や電話での在庫問い合わせなど、一つ一つの工程に時間がかかることで、サプライチェーン全体が停滞してしまうのです。市場のトレンドが目まぐるしく変化する現代において、この時間のロスは致命的です。せっかくの新商品を投入しても、市場の熱が冷めた頃にしか店頭に並べられない、といった事態を招きかねません。
さらに、リアルタイムで正確な状況を把握できないため、問題が発生しても発見が遅れ、対応が後手に回りがちです。データに基づいた迅速な経営判断も困難になり、勘や経験に頼った場当たり的な対応に終始してしまいます。
この意思決定の遅れが、変化への対応力を失わせ、企業の競争力を根本から削いでしまう深刻な課題なのです。
サプライチェーンのDXは、これまで述べてきたような課題を解決し、企業に大きなメリットをもたらします。
AIを活用することで、過去のPOSデータや会員データはもちろん、天候、地域のイベント情報、SNSのトレンドといった多様な外部データを組み合わせて、人間では不可能なレベルで精度の高い需要予測が可能になります。
これにより、欠品による販売機会の損失を防ぎつつ、過剰在庫による保管コストや廃棄ロスを大幅に削減する「在庫の最適化」が実現します。発注業務そのものも自動化できるため、担当者は日々のルーティンワークから解放され、販促企画や顧客分析といった、より付加価値の高い戦略的な業務に集中できるようになります。
精度の高い予測は、キャッシュフローの改善に直接つながるだけでなく、企業の利益体質を根本から強化する強力な武器となるのです。
物流倉庫内でのピッキングや搬送を行うAGV(無人搬送車)やロボットアーム、商品を自動で格納・出庫する自動倉庫システムなど、物流現場の自動化技術は急速に進化しています。これらの技術は、深刻化する人手不足や「2024年問題」への有効な対策となるだけでなく、業務効率を飛躍的に向上させます。24時間365日の稼働も可能になり、生産性は格段にアップします。
また、ピッキングミスや数量間違いといったヒューマンエラーを根本からなくすことができるため、誤出荷の防止や配送品質の安定化にもつながります。これは顧客満足度の向上に直結する重要なポイントです。重労働から作業員を解放し、より安全な労働環境を構築できるというメリットも見逃せません。
出典参照:物流の2024年問題について|国土交通省
DXによって実店舗とECサイトの在庫情報を一元管理できるようになると、OMO(Online Merges with Offline)と呼ばれる、オンラインとオフラインの垣根をなくしたシームレスな顧客体験を提供できます。
たとえば、「ECサイトで注文した商品を最寄りの店舗で受け取る」「店舗のサイネージからEC限定商品を注文する」「アプリで店舗の在庫状況を確認してから来店する」といったことが可能になります。
その結果、顧客は時間や場所にとらわれず、最も都合の良い方法で買い物を楽しむことができます。企業側にとっても、店舗とECの在庫を相互に活用することで販売機会の損失を防ぎ、顧客データを統合して一人ひとりに最適なアプローチができるようになるため、顧客満足度とLTV(顧客生涯価値)の両方を高めることができるのです。

実際に、多くの企業がサプライチェーンのDXに挑戦し、素晴らしい成果を上げています。ここでは、その中からいくつかの事例をご紹介します。
キリンビバレッジは、物流の「2024年問題」や人手不足といった社会課題に対応するため、AIによる需要予測システムを導入しました。特に天候に左右されやすい自動販売機の飲料補充において、過去の販売データや気象情報、周辺のイベント情報などをAIが複合的に分析し、商品ごとの最適な補充量を算出します。
これにより、これまで担当者の経験に頼っていた発注業務を自動化。欠品による販売機会のロスを50%以上も削減し、同時にオペレーションコストを20%削減するという大きな成果を上げています。必要な商品を必要な数だけ補充できるため、廃棄ロスの削減にもつながり、収益性と環境配慮の両立を実現した好事例といえるでしょう。
出典参照:輸送量の平準化を実現するPSI情報プラットフォーム「MOVO PSI」導入開始|キリンビバレッジ株式会社
セレクトショップ大手のユナイテッドアローズは、コロナ禍を機に「顧客起点」のサプライチェーン改革を加速させました。これまでの経験や勘に頼った商品計画から脱却し、AIを活用した需要予測システムを導入。商品ごとの精緻な販売数予測に基づき、店舗への最適な在庫配分や自動発注を実現しています。
この改革によって、データに基づいた客観的な意思決定が可能となり、過剰在庫と機会損失の削減に大きく貢献しました。さらに重要なのは、担当者が発注などの定型業務から解放され、顧客分析や売場づくりといった、より付加価値の高い創造的な業務に集中できるようになった点です。DXが業務効率化だけでなく、人材の価値を最大化することにもつながることを示しています。
出典参照:Integrated Report 2023統合レポート 2023|株式会社ユナイテッドアローズ
パナソニック コネクトは、自社が製造業として培ってきた現場改善ノウハウを活かし、物流現場のDXを加速する倉庫実行管理システム(WES)などを提供しています。このシステムは、倉庫内の人やAGV(無人搬送車)、ロボットといったリソースをリアルタイムに最適化し、現場全体の生産性を向上させます。人手不足が深刻化する中、少ない人員でも効率的に業務を回せる体制を構築することが可能になります。
これまでブラックボックスになりがちだった現場の状況をデータで把握し、ボトルネックを解消することで、変化する需要にも柔軟に対応できる、しなやかなサプライチェーンの構築に貢献します。
出典参照:パナソニック コネクト、日本企業のSCM変革に向けて「現場から始める全体最適化」をコンセプトに物流ソリューションの提供を強化|パナソニック株式会社
サプライチェーンのDXを成功させるためには、計画的に一歩ずつ進めることが大切です。ここでは、導入の際に押さえておきたい5つのステップをご紹介します。
DXの第一歩は、自社のサプライチェーン全体を俯瞰し、どこに、どのような課題があるのかを具体的に洗い出すことから始まります。まずは業務フローを可視化し、「どの工程に時間がかかっているか」「どこで情報が途切れているか」といった非効率な点やボトルネックを特定しましょう。このとき、データ分析だけでなく、実際に現場で働く従業員へのヒアリングが欠かせません。彼らの感じる不便さや問題意識の中に、解決すべき本質的な課題が隠れていることが多いからです。
ここで課題を曖昧なまま進めてしまうと、導入したツールが使われなかったり、的外れな改革になったりする危険性があります。現状を正確に「見える化」することが、DXプロジェクトの成否を分ける最も重要なステップです。
洗い出した課題のすべてに一度に取り組むのは現実的ではありません。リスクを抑え、着実に成果を出すためには、最もインパクトが大きく、かつ実現可能性の高い業務から優先的にデジタル化する「スモールスタート」が有効です。
たとえば、「在庫管理の精度向上」や「受発注業務の自動化」など、費用対効果(ROI)が高く、多くの従業員が効果を実感しやすい領域から着手するのが良いでしょう。小さな成功体験を積み重ねることで、社内に「DXは自分たちの業務を楽にしてくれる」というポジティブな認識が広がり、その後のより大きな改革への協力も得やすくなります。
いきなり大規模なシステムを導入するのではなく、まずは特定の課題を解決するツールで効果を検証し、成功モデルを横展開していくアプローチが成功への近道です。
部分的なデジタル化を進めるだけでなく、将来的にはサプライチェーン全体でデータを連携させ、全体最適を図ることを見据えたシステム基盤の構想が重要です。各部門でバラバラのツールを導入してしまうと、かえってデータのサイロ化が進み、DXの目的である「全体最適化」から遠ざかってしまいます。将来的な拡張性を考慮した設計を初期段階で行いましょう。
同時に、新しいツールやシステムを使いこなせる人材を育成することも不可欠です。単なる操作研修だけでなく、データをどう読み解き、業務改善に活かすかという「データリテラシー」を高める教育が求められます。DXは「最新の技術」とそれを活用する「人」の両輪が揃って初めて前に進むことを忘れてはいけません。
サプライチェーン改革は、調達、製造、物流、販売といった複数の部門が一体となって取り組まなければ成功しません。特定の部門だけで改革を進めても、部門間の壁に阻まれて効果が限定的になってしまいます。
これを防ぐためには、経営層が強いリーダーシップを発揮し、「なぜ今DXが必要なのか」「会社としてどこを目指すのか」というビジョンを全社に明確に伝えることが不可欠です。DXを「情報システム部門だけの仕事」と捉えるのではなく、全従業員が「自分たちの未来のためのプロジェクト」として当事者意識を持てるよう、目的や進捗を丁寧に共有し、社内の意識を一つにまとめていくことが成功の鍵となります。
DXはシステムを導入して終わりではありません。むしろ、導入してからが本当のスタートです。改革の効果を客観的に評価するために、プロジェクト開始前に「在庫削減率」「欠品率」「リードタイム短縮日数」といった具体的なKPI(重要業績評価指標)を設定しましょう。
そして、導入後は定期的にこれらの数値を測定し、目標達成度を検証します。もし期待した効果が出ていなければ、その原因を分析し、改善策を講じる。このPDCAサイクル(計画・実行・評価・改善)を継続的に回していく仕組みを構築することが、DXを一時的なイベントで終わらせず、企業の競争力を高め続けるための原動力となります。変化に対応し続ける姿勢こそが、DXの本質です。

これからは、一社だけでDXを進めるだけでなく、業界全体で連携していくことがますます重要になるでしょう。たとえば、メーカー、卸売業者、小売業者が共同で利用できる物流網を築いたり、商品の受発注で使うデータの形式を業界内で統一したりする取り組みが考えられます。
経済産業省も、流通業界のサプライチェーン全体を最適化するため、電子データ交換の標準仕様である「流通BMS」の普及を後押ししています。このような業界標準の仕組みを活用することで、企業間のデータ連携が格段にスムーズになり、サプライチェーン全体の効率が飛躍的に向上することが期待されます。
出典参照:流通システム標準化事業|経済産業省
小売業界を取り巻く環境が厳しさを増す中で、サプライチェーンのDXは、もはや選択肢ではなく、生き残りのために必須の戦略といえます。AIによる需要予測や物流の自動化は、コスト削減や業務効率化はもちろんのこと、新しい顧客価値を生み出し、企業の競争力を高める大きな力になります。
しかし、だからといって、いきなり大規模な改革を目指す必要はありません。成功への確実な第一歩は、自社の現状を正確に把握し、課題を「見える化」することです。
本記事でご紹介したステップや事例を参考に、まずはあなたの会社の身近な課題から、デジタル化の一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
