小売DXの第一歩はペーパーレス化!メリットや書類管理の課題を解説
小売

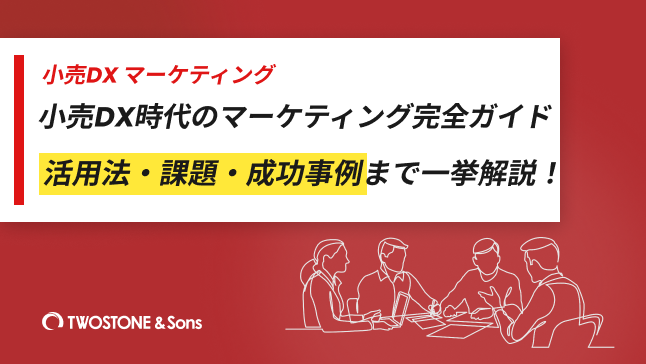
小売DX時代のマーケティングに悩んでいませんか?本記事では、OMO戦略やAI活用、CDPの基本から、無印良品やUNIQLOなどの成功事例、推進の課題までを網羅的に解説。データに基づいた顧客理解で売上向上を目指す、小売業の担当者様は必見です。
スマートフォンの普及で、顧客の購買行動は大きく変わりました。この変化の激しい時代を勝ち抜く鍵が、小売DXと新しいマーケティングです。
「DXの重要性は分かるけど、何から始めれば…」「マーケティングにどう活かせば売上につながるの?」
この記事では、そんなお悩みに応え、小売DX時代のマーケティング戦略を、具体的な手法から成功事例まで分かりやすくご紹介します。
小売DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、単にデジタルツールを導入することではありません。AIやビッグデータといったデジタル技術を使いこなし、業務の進め方からビジネスの仕組み、そして何より顧客体験そのものを根本から変えていく取り組みを指します。
たとえば、ネットと実店舗を連携させてスムーズな購買体験を提供したり、AIによる需要予測で在庫を最適化したりすることも小売DXの一環です。これらは、人手不足の解消やコスト削減といった経営課題の解決にも直結するため、変化に対応し競争力を高める上で欠かせない経営戦略といえるでしょう。
出典参照:DX推進指標(サマリー)|経済産業省

では、なぜ今、小売業界でマーケティングDXがこれほどまでに重要なのでしょうか。その背景には、顧客とマーケティング手法の大きな変化があります。
スマートフォンの普及により、顧客はいつでもどこでも情報を得られるようになりました。SNSで口コミを調べ、店舗で実物を確認し、購入は最も条件の良いECサイトで行うなど、購買に至るまでの道のりは非常に複雑で、一人ひとり異なります。
かつて有効だった画一的なチラシやマス広告といった「勘」や「経験」に頼るマーケティング手法では、多様化する顧客のニーズを捉えきれなくなっているのが現状です。このような「なんとなく」の施策では、顧客の心に響かないばかりか、貴重な予算を浪費してしまうことにもなりかねません。顧客の行動が大きく変わった今、これまでのやり方の限界を認識し、新しいアプローチへと舵を切ることが急務なのです。
複雑化する顧客行動に対応する鍵が、データに基づいた意思決定、すなわち「データドリブン」なマーケティングへの転換です。
店舗のPOSデータ、ECサイトの購買履歴、アプリの利用ログといった、これまでバラバラに管理されていた様々なデータを統合・分析することで、顧客一人ひとりの解像度を飛躍的に高めることができます。「この顧客はどんなことに興味があり、次に何を求めているのか」をデータから読み解き、最適なタイミングで最適な情報や商品を届けるパーソナライズされたアプローチが可能になります。
これにより、施策の精度が格段に向上し、顧客エンゲージメントを高め、売上に直接貢献する、効果的なマーケティングが実現できるのです。
マーケティングDXを考える上で欠かせないのがOMO(Online Merges with Offline)という考え方です。これは、オンライン(ECサイトやアプリ)とオフライン(実店舗)の垣根を取り払い、一体化させることで、顧客にとって一貫性のあるスムーズな購買体験を提供する戦略を指します。
OMO戦略の具体的な施策として、ECサイトと店舗の在庫情報をリアルタイムで連携させることが挙げられます。「ECで注文して店舗で受け取る」「店舗にない商品をその場でECから取り寄せる」といった自由な買い方を可能にし、顧客が感じていた在庫切れによる不便さを解消します。これまで分断されていた購買チャネルをつなぐことで、顧客はいつでもどこでも商品を手に入れられるというシームレスな体験を得られるのです。
さらに、店舗とECサイトでバラバラだったポイントプログラムを統合することも、顧客の利便性を大きく高めます。どこで買い物をしても同じようにポイントが貯まり、使えるという一貫したサービスは、顧客満足度を向上させ、継続的な利用を促すでしょう。こうした体験の積み重ねが、顧客とブランドとの間に強い信頼関係を築く上で非常に重要となります。
OMO戦略において、スマートフォンアプリやSNSは、顧客が商品を購入していない時間にもブランドとのつながりを保つための重要な役割を担います。これらは単なる情報発信ツールではなく、顧客一人ひとりに寄り添うコミュニケーションチャネルとして機能します。アプリを通じてお得なクーポンを届けたり、顧客の好みに合わせた新着情報を通知したりすることで、顧客との継続的な接点を生み出すことができるのです。
たとえば、来店やレビュー投稿といった購買以外の行動にインセンティブを設けることも有効です。企業はそこで得られたデータを活用し、顧客が「自分のことをよく分かってくれている」と感じるような特別な情報を提供できます。このような心地よいコミュニケーションが顧客のブランドへの愛着を深め、自然な形で次の来店や購買へとつながるでしょう。

データに基づいたマーケティングを実現する上で、その心臓部ともいえるのがCDP(カスタマーデータプラットフォーム)です。
CDPとは、オンライン・オフラインを問わず、社内のあちこちに散らばっている顧客に関するデータを集め、一つに統合・管理するための基盤(プラットフォーム)のことです。
よく似た言葉にDMPやMAがありますが、役割が少し異なります。DMPは主に広告配信のために外部の匿名データを活用するのに対し、MAはメール配信など具体的なマーケティング施策を自動化するツールです。CDPは、これら施策の元となるあらゆる顧客データを集約する「ダム」のような存在と考えると分かりやすいでしょう。
多くの企業では、店舗のPOSデータやECサイトの購買データなどが部署ごと、ツールごとにバラバラに管理されている「データのサイロ化」が課題となっています。CDPを導入してこれらのデータを一つにまとめることで、一人の顧客を様々な角度から深く理解することが可能になります。「店舗でよくこの商品を買うAさんは、ECサイトではこんな商品も見ている」といった、これまで見えなかった顧客の姿が浮かび上がってくるのです。
大切なのは、集めたデータを分析し、施策に活かすことです。データをただ貯めるだけでなく、分析から仮説を立て、施策を実行し、効果を検証するサイクルを回していくことが成功の鍵となります。
CDPの導入は、まず「何のために導入するのか」という目的をはっきりさせることがスタートです。次に、社内のどこにどんなデータがあるかを洗い出し、目的に合ったツールを選びます。そして、実際にデータをCDPに集約し、MAなどの他のツールと連携させていきます。最後に、CDPのデータを活用した施策を実行し、その効果を確かめながら改善を繰り返すという流れになります。
ここで注意したいのは、ツール導入そのものがゴールにならないようにすることです。CDPはあくまで顧客を理解し、より良い体験を届けるための手段。導入前に、どんなマーケティングを実現したいかを具体的に描いておくことが大切です。
AI(人工知能)、特に近年大きな注目を集めている生成AIは、小売業のマーケティングを劇的に進化させる大きな可能性を秘めています。
AIの活用方法は多岐にわたります。たとえば、顧客の購買データなどをAIが分析し、「あなたへのおすすめ」として最適な商品を提案するAIレコメンドは、顧客が知らなかった好みの商品と出会う機会を創出します。
また、24時間365日、問い合わせに自動で応答するAIチャットボットは、顧客満足度を高めると同時に、スタッフの負担を軽減してくれるでしょう。さらに、生成AIを使えば、「20代女性向けの夏物ワンピースの広告画像を作って」と指示するだけで、広告用の画像やキャッチコピーを自動で作成することも可能になります。
小売業界が抱える深刻な人手不足は、サービスの質の低下に直結する大きな課題です。この課題に対し、AIチャットボットは有効な解決策となります。簡単な問い合わせに24時間対応することで顧客を待たせず、従業員は定型業務から解放されます。その結果、より丁寧な接客など、人でなければできない付加価値の高い仕事に集中できるようになるのです。
同様に、生成AIが広告コピーなどを作成すれば、マーケティング担当者の負担は軽減され、企画立案といった創造的な業務に時間を使えるようになります。AIは単に業務を自動化して対応速度を上げるだけではありません。従業員がコア業務に専念できる環境を作り、企業全体の生産性を高める強力なパートナーとなるのです。
生成AIは、単なる業務効率化のツールにはとどまりません。たとえば、顧客との対話を通じてその人のニーズを深く理解し、その顧客のためだけの特別な商品をデザインするといった、新しい価値を生み出す活用も考えられます。AIが作ったクリエイティブが、企業のブランドイメージを形作っていく未来もそう遠くないかもしれません。
ただし、AIの生成物には誤った情報が含まれる可能性もあるため、最終的には人の目による確認が不可欠です。AIを「優秀なアシスタント」として上手に活用し、人間の創造性をさらに広げていく視点が求められます。
リテールメディアとは、小売企業が自社で運営するECサイト、アプリ、店舗のデジタルサイネージなどを広告媒体として、メーカーなどの広告主に提供する新しいビジネスです。これまで商品を「売る」場所だった小売の現場が、これからは広告を「見せる」場所としての価値も持つようになります。
リテールメディアの仕組みは、小売企業が持つオンライン・オフラインの顧客接点を「広告枠」として販売するという、非常にシンプルなものです。たとえば、メーカーは小売企業のECサイトのトップページに新商品のバナー広告を掲載したり、特定の商品カテゴリページで自社製品を目立たせたりすることができます。
小売企業の収益は、この広告枠の販売による広告掲載料が主となります。これにより、小売企業は商品販売による利益だけでなく、広告事業という新たな収益の柱を確立できる可能性を秘めているのです。
リテールメディアの最大の強みは、小売業者が自社で収集した信頼性の高い「ファーストパーティデータ」を広告配信に活用できる点にあります。従来のWeb広告が閲覧履歴などから「おそらく興味があるだろう」と推測してターゲティングするのに対し、リテールメディアでは「実際にこの商品を購入した人」「特定の商品をカートに入れたままの人」といった、購買行動そのものに基づいたターゲティングが可能です。
これにより、顧客の曖昧な興味関心ではなく、明確な購買意欲の高さでセグメント分けできるため、極めて精度の高い広告配信が実現できます。まさに「その商品を求めている人」の目の前に、広告を直接届けることができる仕組みなのです。
広告主にとって、この高精度なターゲティングは大きく2つのビジネスメリットにつながります。
第一に、広告費の無駄をなくし、高い費用対効果(ROAS)が期待できることです。購買意欲の高い顧客に絞って広告を届けられるため、効率的に予算を使い、売上向上に直結させやすくなります。
第二に、広告効果を正確に測定できる点です。広告に接触した顧客が、その後実際に商品を購入したかまでをデータで追跡できるため(クローズドループ測定)、施策の成果を明確に把握し、次の改善につなげやすいという利点があります。購買の瞬間に最も近い場所で、成果の見える広告を展開できることが、広告主にとっての最大の魅力といえるでしょう。
ここでは、実際にマーケティングDXに取り組み、大きな成果を上げている企業の事例を3つご紹介します。
無印良品は、公式アプリ「MUJI passport」を軸としたOMO戦略で大きな成功を収めています。このアプリの特徴は、買い物でマイルが貯まるだけでなく、店舗へのチェックインや商品の口コミ投稿といったアクションでもマイルが付与される点です。
この仕組みが、買い物をしない日でも顧客がアプリに触れる機会を作り出し、企業と顧客の継続的なコミュニケーションを可能にしました。集まった顧客の行動データを分析し、一人ひとりに合わせた情報発信を行うことで、顧客の心を掴み、来店頻度の向上につなげています。
出典参照:MUJI REPORT 2024|株式会社良品計画
家電量販大手のビッグカメラは、ECサイトの問い合わせ件数の増加と、それに伴うオペレーターの負担増大という課題を抱えていました。この課題を解決するため、同社はSalesforceを導入し、顧客が自分で問題を解決できる仕組みの強化に着手しました。具体的には、FAQサイトを刷新して情報を見つけやすくすると同時に、24時間365日対応可能なAIチャットボットを設置したのです。
このAIチャットボットは、簡単な質問に自動で答えるだけでなく、解決できない場合はスムーズにオペレーターによる有人チャットへ引き継ぐ仕組みも備えています。この取り組みにより、顧客の自己解決率が向上し、電話での問い合わせが減少。結果として、顧客満足度を高めながらオペレーターの負担を軽減し、より専門的な対応に集中できる環境を整えることに成功しました。
出典参照:ビックカメラ、DX宣言の実現に向けてSalesforceを全面的に採用|株式会社ビックカメラ
ユニクロは、ECサイトと店舗の垣根をなくすオムニチャネル戦略の先進企業です。ECサイトで購入した商品を送料無料で店舗受け取り可能にするなど、顧客の利便性を追求したシームレスな購買体験を提供しています。
また、「情報製造小売業」への変革を掲げ、AIなどを活用した需要予測の精度向上に注力。顧客の声や販売実績といった膨大なデータを分析し、商品の生産量や在庫配分を最適化することで、欠品による機会損失と売れ残りによる廃棄ロスの両方を削減し、販売効率を最大化する取り組みを進めています。
出典参照:有明プロジェクトについて~“情報製造小売業”の実現に向けて~|株式会社ファーストリテイリング
多くのメリットがある小売DXですが、その道のりは平坦ではありません。推進にあたって直面しがちな課題と、その対策について解説します。
多くの企業では、店舗のPOSデータやECサイトの購買履歴といった重要な顧客データが、部署ごとにバラバラに管理される「データのサイロ化」が起きています。これでは顧客の全体像を把握できず、一貫したアプローチができません。また、各部門が場当たり的にツールを導入した結果、連携が取れないツールが乱立し、業務が複雑化するケースも少なくないのです。
この課題への対策は、まず社内のデータを洗い出す「データの棚卸し」から始めます。その上で、CDPなどを活用してデータを一元管理できる基盤を整えることが重要です。ツール導入ありきではなく、全社的な目的を明確にしてから、必要なものを選択・連携させていく視点が求められます。
小売DXを推進する上で大きな障壁となるのが、部門間の連携不足です。たとえば、店舗は「店舗売上」、EC部門は「サイトのPV数」など、それぞれが異なる目標(KPI)を追いかけていると、組織としての一体感は生まれません。時には、店舗とECサイトで顧客を奪い合うような、本来あるべきではない対立構造に陥ってしまうことさえあります。
この問題を是正するためには、まず「顧客生涯価値(LTV)の最大化」といった、部門の垣根を越えた全社共通の目標を設定することが不可欠です。そして、その共通目標に対し各部門がどう貢献できるかを明確にし、連携を促すような評価制度に見直すことも有効な手段となります。組織全体が顧客という同じ方向を向いて初めて、DXは力強く前進します。
経営層がDXの重要性を説いても、実際にツールを使う現場スタッフの協力なしに成功はあり得ません。しかし現場からは「新しいことを覚えるのが大変」「なぜ変える必要があるのか」といった、変化に対する抵抗や不安の声が上がることが少なくありません。一方的に変革を押し付けるのではなく、丁寧なコミュニケーションとサポートが不可欠です。
この問題を乗り越える鍵は、現場を「巻き込む」姿勢です。導入の目的やメリットを根気強く説明し、十分な研修の機会を設けることはもちろん、現場の意見を吸い上げる仕組みも重要です。また、いきなり全社で大規模な変革を目指すのではなく、特定の店舗などで小さく始めて成功事例を作り、徐々に展開していく「スモールスタート」も、現場の不安を和らげる上で非常に有効なアプローチです。
出典参照:デジタルスキル標準|経済産業省
マーケティングDXを力強く進めるためには、目的に合ったツールを選び、それを正しく活用することが成功の鍵を握ります。
マーケティングDXでよく使われるツールには、MA、CRM、BIなどがあります。MA(マーケティングオートメーション)はメール配信などを自動化し、見込み客の育成を得意とします。CRM(顧客関係管理)は顧客情報を一元管理し、顧客との良好な関係づくりをサポートするものです。そしてBIツールは、膨大なデータを分析・可視化し、経営の意思決定に役立てるために使われます。
これらのツールはそれぞれ得意なことが違うため、自社が「何を解決したいのか」という目的をはっきりさせてから選ぶことが何よりも大切です。
どんなに優れたツールも、現場で使われなければ意味がありません。導入を成功させるには、計画段階から現場スタッフを巻き込み、導入の目的やメリットを丁寧に共有することが重要です。一方的に「使え」と押し付けるのではなく、彼らの意見や不安に耳を傾ける姿勢が求められます。
十分な研修で操作の不安を取り除き、実際に使った上での意見を吸い上げて改善するサイクルを作ることも不可欠です。ツールを「会社から与えられたもの」ではなく、「自分たちの仕事を良くする武器」だと感じてもらうことが、現場への定着を成功させる鍵となります。
自社だけでDXの専門知識が不足している場合、外部パートナーの活用は有効な手段です。しかし、ツールの機能や価格だけで安易に選んでしまうと、「導入したものの使いこなせない」といった失敗に陥りがちです。パートナー選びでは、別の視点が重要になります。
最も重視すべきは、自社のビジネスや業界特有の課題への深い理解度、そして導入後の定着まで「伴走」してくれるサポート体制です。単なる「業者」としてではなく、自社のDXチームの一員として信頼できるパートナーを見つけることが、プロジェクト成功の確率を大きく高めるでしょう。

小売DXにおけるあらゆる施策の成功は、結局のところ、いかに顧客を深く、そして正しく理解できるかにかかっています。
顧客理解の第一歩は、データを客観的に分析することから始まります。その際に役立つのが、古くから使われている基本的な分析フレームワークです。たとえば、顧客を年齢や性別といった属性でグループ分けし、それぞれの特徴を把握する「セグメンテーション分析」は、どのような顧客層が存在するのかを明確にする上で欠かせません。
さらに、優良顧客や離反しそうな顧客を見つけ出すためには、「最終購入日(Recency)」「購入頻度(Frequency)」「購入金額(Monetary)」の3つの指標で顧客をランク付けする「RFM分析」が有効です。また、短期的な売上だけでなく、一人の顧客が将来にわたってもたらしてくれる利益の総額を測る「LTV(顧客生涯価値)分析」も重要となります。これらのフレームワークを活用することで、データの中から顧客の本当の姿を浮かび上がらせることができます。
データ分析によって顧客の姿がはっきりと見えてきたら、次に行うべきはマーケティング戦略そのものの見直しです。
分析で見えてきた優良顧客や、これからファンになってくれそうな人は「誰」なのか。その人たちは、どのような商品や情報を「何を」求めているのか。そして、メールやアプリ、SNS、店舗での接客など、どのチャネルで、どのようなコミュニケーションを取るのが最も効果的か(どう届けるか)。データという客観的な事実に基づいてこれらの要素を一つひとつ再設計することで、マーケティングの精度は格段に向上するはずです。
データを分析して顧客を理解するだけで終わってしまっては、DXの成果は生まれません。最も重要なのは、その分析結果を日々の業務や経営の意思決定に活かし、組織の文化として根付かせることです。これまでの経験や勘だけに頼るのではなく、「データがこう示しているから、この施策を試してみよう」という会話が、会議室や現場で日常的に生まれる組織を目指す必要があります。
そして、施策を実行したら必ずデータを元にその効果を検証(Check)し、成功・失敗の要因を分析して次の改善策を考える(Action)という、PDCAサイクルを回し続けることが不可欠です。この地道な繰り返しこそが、勘や思い込みから脱却し、データに基づいた精度の高いマーケティングを実践するための唯一の道といえるでしょう。
小売業界を取り巻く環境は、これからもきっと目まぐるしく変化し続けるでしょう。この変化の時代を勝ち抜くために何よりも大切なのは、デジタル技術を上手に活用して「顧客」を深く、正しく理解することに他なりません。
OMO、CDP、AIといったテクノロジーは、すべて顧客理解を深めるための強力な武器です。しかし、忘れてはならないのは、最も大切なのはツールそのものではなく、「お客様に最高の体験を届けたい」という真摯な想いです。データとテクノロジーの力を借りて、一人ひとりのお客様と丁寧に向き合う。その先にこそ、小売DX時代のマーケティングの成功が待っています。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
