小売DXの第一歩はペーパーレス化!メリットや書類管理の課題を解説
小売

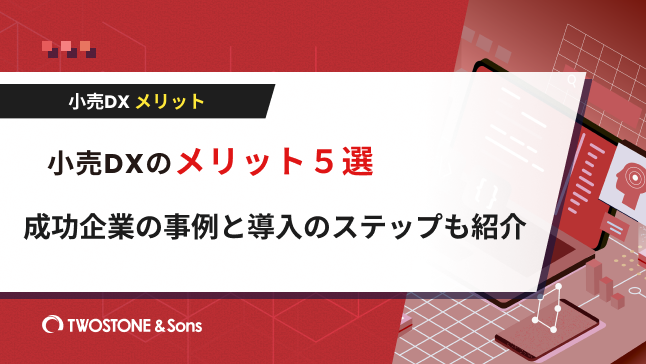
小売業の人手不足や多様化するニーズにお悩みですか?その解決の鍵は小売DXにあります。本記事では、DXがもたらす5つのメリットを、成功事例や導入の具体的なステップとともに分かりやすく解説。失敗しないためのポイントも紹介します。


・6万名以上のエンジニアネットワークを活用して課題を解決※
・貴社のDX戦略立案から実行・開発までワンストップで支援可能
※エンジニア数は2026年8月期 第1四半期決算説明資料に基づきます。
人手不足や多様化するお客様のニーズに、どう応えればいいか悩んでいませんか?ECサイトとの連携がうまくいかない、という声もよく聞きます。こうした小売業の課題を解決する鍵が「小売DX」です。
この記事では、DXがもたらすメリットから成功企業の事例、導入の具体的なステップまでを分かりやすく紹介します。未来を切り拓くヒントがここにあります。
小売DXとは、単にITツールを導入して業務を楽にする、という話ではありません。AIやIoTといったデジタル技術を使い、ビジネスの仕組みやお客様への価値提供の方法を根本から変えていく取り組みを指します。
例えば、AIがお客様一人ひとりの好みを分析して商品を提案したり、店舗とECサイトの情報を連携させて、いつでもどこでもスムーズな買い物体験を提供したりすることです。
これまでの「モノを売る」という考え方から一歩進んで、デジタルを通じてお客様との新しい関係を築き、特別な体験を生み出すことが、小売DXの本当の目的なのです。この考え方は、経済産業省がDX推進の指針として示している定義にも沿ったものです。
出典参照:DX推進指標(サマリー)|経済産業省

それでは、どうして今、多くの小売企業がDXに注目しているのでしょうか。その背景には、小売業界全体が抱える、避けては通れないいくつかの大きな変化があります。これからの時代を生き抜くために、なぜDXが必要なのかを見ていきましょう。
日本の少子高齢化による人手不足は、特に店舗運営を多くのスタッフで支える小売業にとって、非常に深刻な問題です。レジ業務や品出し、在庫管理といった日々の仕事は欠かせませんが、その担い手となる人材の確保は年々難しくなっています。求人を出しても、なかなか応募が集まらないのが現状です。
この状況は、単に現場が忙しくなるだけでなく、サービスの質の低下や、既存スタッフへの過度な負担につながりかねません。結果として、お客様の満足度が下がり、大切な従業員の離職を招く悪循環に陥る恐れもあります。こうした事態を避け、限られた人数でも質の高い店舗運営を続けるために、これまで人の力に頼ってきた業務をデジタルで効率化するDXの推進が急務となっているのです。
スマートフォンの普及は、お客様の購買行動を大きく変えました。商品を買う前に、SNSの口コミをチェックし、複数のECサイトで価格を比較するのは当たり前の光景です。人々は単に「モノ」を手に入れるだけでなく、その商品から得られる特別な「体験」や、自分の価値観に合ったストーリーを求めるようになっています。
このような時代に、かつてのようにすべての人に同じ商品を同じように提供する手法では、お客様の心をつかむことはできません。一人ひとりの購買履歴やサイトでの行動を分析し、その人の興味に合わせた「あなただけの」特別な提案、つまりパーソナライズされたアプローチが求められています。顧客データを活用し、この高度なニーズに応えるための鍵が、小売DXなのです。
Amazonに代表されるECサイトの成長は、小売業の競争を全く新しいものに変えました。価格の安さ、豊富な品揃え、そして自宅まで届く利便性を武器に、オンラインでの購買は多くの人にとって日常の一部となっています。このような状況で、実店舗が価格や品揃えだけでECサイトと勝負するのは非常に困難です。
そこで重要になるのが、ECサイトにはない実店舗ならではの強みを活かすことです。専門知識を持つスタッフとの会話や、商品を実際に手にとって試せる安心感といった体験価値を高める必要があります。小売DXは、オンラインと店舗のデータを連携させ、こうした実店舗の価値をさらに高めながら、ECの利便性も取り込むための強力な戦略ツールとなるのです。
出典参照:EC(eコマース)とは?ECサイトやECビジネスの 定義、メリットおよびデメリット|Amazon.com, Inc.
新型コロナウイルスの影響は、私たちの消費行動に大きな変化をもたらしました。感染対策として物理的な接触を避ける意識が広まり、小売の現場でも「非接触・非対面」へのニーズが急速に高まりました。お客様自身で会計を行うセルフレジや、現金に触れずに済むキャッシュレス決済の普及が加速し、ECサイトの利用も幅広い世代に浸透しました。
この変化は、一過性のものではなく、新しい生活様式として定着しつつあります。お客様は、利便性に加えて「安全・安心」という価値を店舗に求めるようになりました。こうした新たな期待に応えるためには、モバイルオーダーやオンライン接客といったデジタル技術の活用が欠かせません。コロナ禍で顕在化したこれらのニーズへの対応は、お客様から選ばれ続けるための必須条件となっているのです。
こうした厳しい環境を乗り越え、成長を続けるために、小売DXは非常に強力な武器になります。ここでは、DXを進めることで得られる代表的な5つのメリットについて、一つひとつ見ていきましょう。
これまで多くの時間と人手を要していた業務を、デジタル技術で自動化・効率化できるのがDXの大きなメリットです。例えば、AIが天候や過去のデータから最適な発注量を予測すれば、担当者は発注業務から解放されます。また、売上報告の作成といった定型的なパソコン作業も、RPAツールで自動化が可能です。
こうした効率化は、従業員の作業負担を軽くするだけでなく、人件費の削減にも直結します。さらに、単純作業から解放された従業員は、お客様への丁寧な接客や魅力的な売り場づくりといった、人でなければ生み出せない付加価値の高い業務に集中できます。これは従業員のモチベーション向上にもつながり、店舗全体の競争力を高める好循環を生み出すのです。
小売DXは、お客様一人ひとりに寄り添った、きめ細やかなサービスを実現します。CRMツールでお客様の購買履歴などを分析し、その人の好みに合わせた商品情報やクーポンを最適なタイミングで届けることが可能です。「自分のことを分かってくれている」と感じられるアプローチは、お客様の満足度を大きく高めるでしょう。
また、店舗での体験も向上します。スマートフォンで商品をスキャンしながら買い物ができるシステムやセルフレジは、レジ待ちのストレスからお客様を解放します。こうしたスムーズで快適な買い物体験は、「またこのお店に来たい」という気持ちを育み、長期的なファン、つまりリピーターの獲得につながるのです。
これまでの小売業では、仕入れや品揃えなどを店長の「勘」や「経験」に頼ることが少なくありませんでした。小売DXは、この状況を大きく変えます。POSデータやECサイトのアクセスログなどを統合的に分析することで、これまで見えなかった事実が明らかになります。「どの商品が一緒に買われやすいか」といった傾向を客観的なデータで把握できるのです。
これにより、データという明確な根拠に基づいた意思決定が可能となります。感覚だけに頼るのではなく、事実に基づいて戦略を立てることで、機会損失や過剰在庫のリスクを大幅に減らし、より精度の高い店舗運営が実現します。
人手不足が深刻化する中で、限られた人材の能力を最大限に引き出すことは避けては通れない大きな課題です。小売DXは、この課題に対する有効な解決策となります。在庫数を自動でカウントするIoTセンサーや、簡単な問い合わせに自動で答えるチャットボットを導入すれば、従業員が担っていた定型業務を大幅に削減できます。
これにより、従業員は接客や商品提案といった、より創造的で付加価値の高い仕事に時間とエネルギーを注ぐことができます。これは従業員のスキルアップや仕事へのやりがいにもつながり、サービスの質を向上させます。人にしかできない温かみのあるサービスと、デジタルによる効率化を両立させることで、省人化と顧客満足度の向上を目指せるのです。
OMOとは、ECサイト(オンライン)と実店舗(オフライン)の垣根を取り払い、お客様が双方を自由に行き来できるような購買体験を提供することです。例えば、「ECサイトで注文し、最寄りの店舗で受け取る」「店舗で気になった商品のバーコードをアプリで読み込み、後でECサイトで購入する」といった体験がこれにあたります。
このOMOこそ、実店舗を持つ小売業がEC専業の事業者と差別化するための最大の武器です。実際に商品を見て触れられる実店舗の強みと、24時間いつでも買い物ができるオンラインの利便性を組み合わせることで、お客様との深い関係づくりが可能になります。DXは、このOMO戦略を実現するためのデータ連携やシステム基盤を支える、不可欠な要素なのです。
小売DXを実現するためには、様々なデジタル技術の力が欠かせません。
例えば、お客様の購買データを分析して最適な商品を予測するAI(人工知能)は、まさにDXの中核を担う存在です。また、店舗内のカメラやセンサーで人の流れや在庫状況を把握するIoT(モノのインターネット)は、これまで見えなかったオフラインの情報をデータに変えてくれます。
これらの膨大なデータを安全に管理し、いつでもどこでも活用できるようにするのがクラウド技術です。そして、集めた顧客情報を元に、一人ひとりに合った情報発信を自動で行うMA/CRMツールも、お客様との関係づくりに不可欠といえるでしょう。こうしたテクノロジー、特にAIの活用は、国が産業競争力を高めるために推進する戦略とも合致するものです。

理論だけでなく、実際にDXに取り組んで大きな成果を上げている企業の事例から、成功のヒントを学んでいきましょう。
セブン-イレブン・ジャパンでは、発注業務がベテラン従業員の経験と勘に頼りがちで、属人化していることが課題でした。そこでAI技術を活用した発注システムを導入しました。このシステムは、過去の販売実績だけでなく、天候や地域のイベント情報といった膨大なデータをAIが分析し、客観的なデータから最適な発注数を提案します。
これにより、経験の浅い従業員でも精度の高い発注が可能になり、欠品による販売機会の損失や、過剰在庫による廃棄ロスを大幅に削減しました。店舗によっては発注業務の時間を大幅に削減できたといいます。創出された時間で、従業員はより丁寧な接客や売り場づくりに注力でき、顧客満足と従業員の働きがい向上に成功しています。
出典参照:店内作業効率化の取り組み|株式会社セブン‐イレブン・ジャパン
老舗百貨店の大丸松坂屋は、新たな顧客体験の創造を目指し、先進的なDXに挑戦しています。その象徴的な取り組みが、アバターがお客様をご案内する「アバターインフォメーション」です。これにより、従業員は遠隔地からでも勤務でき、多様な働き方を実現しました。お客様にとっても、アバターになら気軽に質問しやすいというメリットがあります。
さらに、インターネット上の仮想空間に店舗をオープンする「バーチャル大丸・松坂屋」では、メタバース内でのショッピングを通じて、これまでにない買い物体験を提供しています。 このようにリアルとバーチャルを巧みに融合させることで、従来の百貨店のイメージを刷新し、新たな顧客層との関係を築き上げています。
出典参照:日本初!大丸松坂屋百貨店にてアバターを利用した「リモート型」接客案内サービスの実証実験を開始!|株式会社大丸松坂屋百貨店
家具やインテリアは「部屋に置いたらイメージと違った」という購入後のミスマッチが課題でした。この課題を解決するため、ニトリはAR(拡張現実)技術を使ったスマートフォンアプリを提供しています。このアプリを使えば、スマートフォンのカメラを通して、自分の部屋に実物大の3D家具を仮想的に配置することができます。
サイズ感や色、部屋全体の雰囲気との相性を購入前に自宅でじっくり確認できるため、お客様は安心してオンラインでの購入を決められます。この取り組みは、ECサイトでの購入のハードルを下げただけでなく、購入後のミスマッチによる返品率の改善にも大きく貢献しました。返品対応のコストを削減し、顧客満足度を高める、企業と顧客の双方にメリットのあるDX事例です。
出典参照:⾃宅で家具の試し置きができる、AR(拡張現実)サービス「スマホで簡単!3Dで試し置き」を開始|株式会社ニトリホールディングス
総合スーパーのイオンでは、レジの待ち行列による顧客満足度の低下が課題でした。この課題を解決するため、お客様が自身のスマートフォンなどで商品をスキャンしながら買い物をする「レジゴー」を導入しました。お客様は、買いたい商品のバーコードをその場でスキャンし、最後に専用レジでQRコードをかざすだけで、スピーディーに会計を済ませられます。
このシステムの裏側では、高性能なバーコード読み取り技術が快適なスキャン体験を支えています。レジ待ち時間が大幅に短縮されただけでなく、合計金額を常に確認しながら買い物ができるため、買い忘れ防止にもつながっています。レジ業務の省人化と顧客体験の向上を両立させた好例です。
出典参照:利用者の67%以上がリピート意欲を示す、超高速で革新的なセルフスキャン・レジ|イオンリテール株式会社
小売DXを成功させるために最も大切なのは、最新のツールを導入することよりも、会社全体で取り組むための体制を整えることです。
まず、経営トップが「なぜDXが必要なのか」という明確なビジョンを示し、本気で推進する姿勢を見せることが不可欠です。その上で、実際にシステムを使うことになる現場の従業員の声を丁寧に聞き、一方的に押し付けるのではなく、一緒に作り上げていく意識が重要になります。
新しい変化には戸惑いや不安がつきものですから、導入の目的やメリットを根気強く説明し、現場を巻き込んでいく仕組みづくりが、DX成功の鍵を握っているのです。
DXを始めたいと思っても、何から手をつければいいか分からないかもしれません。ここでは、成功に向けた具体的な進め方を、いくつかのステップに分けてご紹介します。
DXの第一歩は、自社の現在地を正確に知ることから始まります。まずは、日々の業務プロセスや組織の体制、顧客との関わり方などを徹底的に洗い出し、「どこに、どのような課題が潜んでいるのか」を具体的に見える化しましょう。例えば、「在庫管理に多くの時間を費やしている」「顧客データが部署ごとにバラバラで活用できていない」「手作業による発注ミスが多い」といった問題点をリストアップします。
この作業は、経営層だけで行うのではなく、実際に現場で働く従業員へのヒアリングや、お客様へのアンケートなどを通じて、多角的な視点から情報を集めることが重要です。課題を具体的に言語化し、関係者全員で「これが私たちの解決すべき問題だ」という共通認識を持つこと。これが、その後のDXの方向性を定めるための、最も重要な土台となります。
現状の課題が明らかになったら、次に「DXを通じて、どのような状態になりたいのか」という目的を明確に設定します。この目的は、「顧客満足度を向上させる」といった漠然としたものではなく、「データ活用によって、お客様一人ひとりに最適な買い物体験を提供する」のように、具体的でなければなりません。この明確な目的が、プロジェクトの羅針盤となります。
そして、その目的が達成できたかどうかを客観的に測るための指標、つまりKPI(重要業績評価指標)を定めます。例えば、「ECサイト経由での店舗送客数を月間10%増やす」「AI発注による廃棄ロス率を5%削減する」といった、誰が見ても達成度が分かる具体的な数値目標を設定しましょう。明確なKPIがあることで、チームの進捗管理がしやすくなり、関係者のモチベーション維持にもつながります。
DXの目的とKPIが決まっても、いきなり全社的に大規模なシステムを導入するのは非常にリスクが高い行為です。大きな投資が無駄になったり、現場が混乱したりする可能性があります。そこで重要になるのが、特定の店舗や部門に限定して小さく試してみる「スモールスタート」という考え方です。
例えば、新しい取り組みに協力的で、課題が明確な店舗をパイロット店舗として選び、そこで新しいツールや仕組みをテスト運用します。このテストを通じて、操作性や業務への影響、顧客の反応、費用対効果などを検証し、本格導入に向けた課題を洗い出します。小さな成功体験を積み重ねることで、社内のDXへの理解や期待感が高まり、全社展開をスムーズに進めるための貴重なノウハウを蓄積できるのです。
テスト運用で効果が確認でき、改善点も明確になったら、いよいよ本格的な導入と社内への展開フェーズに移ります。この段階で最も重要なのは、現場で働く従業員への手厚いサポート体制を整えることです。新しいシステムや業務フローは、現場にとって一時的に負担が増えることもあり、不安や抵抗感を生む可能性があります。
分かりやすいマニュアルの作成や、丁寧な研修会を複数回実施することはもちろん、各店舗にDX推進のキーパーソンを置いたり、いつでも相談できるヘルプデスクを設置したりといった施策が有効です。ただシステムを導入して終わりにするのではなく、現場の従業員が新しいやり方に慣れ、そのメリットを実感できるまで、本部が粘り強く伴走する姿勢が、DXを社内に根付かせるための鍵となります。
DXは、システムを導入したら終わり、という一過性のプロジェクトではありません。むしろ、導入してからが本当のスタートです。市場環境や顧客のニーズは常に変化し続けるため、一度作った仕組みが永遠に最適であり続けることはありません。だからこそ、継続的な効果測定と改善のサイクル(PDCAサイクル)を回し続けることが不可欠です。
ステップ2で設定したKPIの数値を定期的に測定し、計画通りの効果が出ているかを客観的に評価します。もし期待した成果が出ていない場合は、その原因をデータに基づいて分析し、改善策を立案・実行します。この地道な改善活動を繰り返すことで、DXの取り組みはより洗練され、企業の競争力を高め続ける力となるのです。
DXを推進するには、デジタル技術やデータ分析、プロジェクトマネジメントなど、多岐にわたる専門知識が求められます。しかし、これらのスキルを持つ人材がすべて社内に揃っている企業は多くありません。そんな時は、無理に自社だけで完結させようとせず、外部の専門家やITベンダーといったパートナーと連携することも非常に有効な選択肢です。
パートナーを選ぶ際は、単に技術力が高いだけでなく、自社の業界やビジネスの課題を深く理解し、同じ目線で伴走してくれる姿勢があるかを見極めることが重要です。外部の客観的な視点や専門知識を取り入れることで、自社だけでは気づけなかった課題を発見したり、プロジェクトの推進を加速させたりできます。ただし、「丸投げ」は禁物です。あくまで自社が主体性を持ち、パートナーと協力してプロジェクトを進める意識を持ちましょう。
多くのメリットがある小売DXですが、進め方を間違えると失敗に終わってしまうこともあります。ここでは、よくある失敗パターンとその対策を知り、同じ過ちを繰り返さないためのヒントを探ります。
DXの推進には投資が必要ですが、最初から完璧なシステムを目指し、想定以上の初期費用がかかって計画が頓挫するのはよくある失敗です。経営層が費用対効果をシビアに見ている場合、高額な見積もりはプロジェクトの承認を得る上での大きな障壁となります。
これを回避するには、スモールスタートを徹底することが重要です。まずは、月額で利用できるクラウドサービス(SaaS)などを活用し、少ない投資で始められる方法を検討しましょう。これにより、リスクを最小限に抑えながら効果を検証できます。
また、国や自治体が提供しているIT導入補助金やDX関連の助成金制度を事前にリサーチし、活用できないか調べてみるのも賢明な方法です。小さな成功を積み重ね、その効果を示しながら段階的に投資を拡大していくアプローチが、結果的に大きな失敗を防ぎます。
経営陣が良いと思っても、現場から「操作が複雑」「仕事が増えた」と不満が出て使われなくなる。これは最も多い失敗例かもしれません。DXの成功には現場の協力が不可欠ですが、トップダウンで一方的に導入を進めてしまうと、現場に「やらされ感」が蔓延し、結局システムが使われなくなってしまいます。
この失敗は、現場とのコミュニケーション不足が主な原因です。これを防ぐには、計画の初期段階から現場の従業員を巻き込み、彼らの意見や悩みに耳を傾けることが不可欠です。「なぜDXが必要か」「導入で仕事がどう楽になるか」といった目的やメリットを丁寧に説明し、納得感を得ることが何よりも大切です。一方的な導入ではなく、現場と一体となってプロジェクトを進める姿勢が求められます。
新しい顧客管理システムを導入したものの、既存のPOSレジなどと連携できず、手作業での二重入力が発生してしまいます。これは効率化を目指したはずが、逆に現場の負担を増やす典型的な失敗です。データの不整合も起こりやすく、結局、信頼性の低いデータしか集まらないという事態にもなりかねません。
これを防ぐには、ツール選定時に機能や価格だけでなく、既存システムとの連携性(API連携など)の確認が必要です。導入実績が豊富で、様々なシステムとの連携を前提に設計されたツールを選ぶのが賢明です。システムの「サイロ化(孤立化)」を防ぎ、データが分断されることなく、全社で一元的に活用できる基盤を築くという視点が成功の鍵を握ります。
「世の中がDXと騒いでいるから」と目的が曖昧なまま流行りのツールを導入するのも、よくある失敗です。最新ツールを導入したものの、自社のビジネス課題と合っておらず、明確な成果を実感できないまま高額な利用料だけを払い続けることになりかねません。
このような「手段の目的化」を避けるには、「自社のどの課題を、どのように解決するためにDXに取り組むのか」という目的と、その達成度を測るKPIを明確にすることが最も重要です。
ツール導入がゴールではありません。明確な目的意識を持つことで、投資対効果を正しく評価でき、プロジェクトの方向性がブレるのを防ぎます。常に本来の目的に立ち返る姿勢が、効果の出ない投資を防ぐのです。
DXを進めたいが、「何から手をつけていいか分かる人材がいない」という課題に多くの企業が直面します。専門知識がないまま手探りで進め、時間とコストを浪費したり、外部ベンダーに「丸投げ」してしまい、自社でコントロールできなくなるケースも少なくありません。
この課題には、すべてを自社でまかなおうとせず、外部の専門家の力を借りるという選択肢が有効です。DXコンサルタントなどと連携し、自社に足りない知見を補いましょう。ただし、主体性は自社が持つことが大前提です。並行して、社内での勉強会などを通じ、長期的な視点で計画的にDX人材を育成していくことも、持続的な成長のためには不可欠です。

この記事では、小売DXがもたらす様々なメリットや、成功に向けた具体的な進め方について解説してきました。人手不足やお客様のニーズの変化といった厳しい課題は、見方を変えれば、DXを通じて新しい成長を遂げるためのチャンスでもあります。
最も大切なのは、DXを魔法の杖のように考えるのではなく、あくまで「自社の課題を解決するための道具」として捉えることです。他社の成功事例をそのまま真似るのではなく、自社の現状と真摯に向き合い、何のためにDXに取り組むのかを明確にすることから、ぜひ始めてみてください。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
