小売DXの第一歩はペーパーレス化!メリットや書類管理の課題を解説
小売

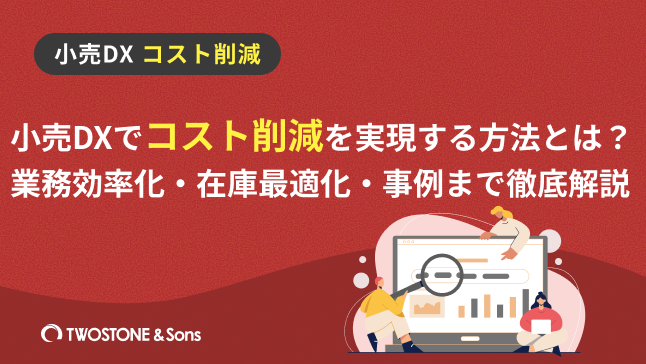
物価高や人手不足にお悩みの小売業様へ。小売DXでコスト削減を実現しませんか?本記事では、業務効率化や在庫最適化など具体的なコスト削減方法を徹底解説。成功企業の事例や、導入に使える補助金情報まで網羅し、あなたの会社の利益改善をサポートします。


・6万名以上のエンジニアネットワークを活用して課題を解決※
・貴社のDX戦略立案から実行・開発までワンストップで支援可能
※エンジニア数は2026年8月期 第1四半期決算説明資料に基づきます。
物価や人件費が上がり続ける中で、どうすれば利益を確保できるのか。多くの小売業の方が抱えるこの切実な悩みに、小売DXが解決の糸口を示してくれます。
本記事では、DXでコストを削減する具体的な方法から成功企業の事例、導入の進め方まで、分かりやすく解説します。この記事を読めば、あなたの会社の利益改善に繋がる、最初の一歩が見つかるはずです。

小売DXとは、単にデジタルツールを導入することではありません。AIやIoTといった技術を使って、日々の仕事のやり方からビジネスの仕組み全体を変革し、新しい価値を生み出す取り組みのことです。
これまで人の経験や勘に頼ることが多かった発注や在庫管理、接客といった業務をデジタル化することで、無駄をなくし、業務を効率化します。これにより、人件費などのコストを削減できるだけでなく、データに基づいた正確な判断が可能になり、お客様一人ひとりに合ったサービスを提供できるようになるのです。
それは、単なる業務改善にとどまらず、最終的には顧客満足度を高めて売上向上に繋げることも大きな目的と言えるでしょう。こうしたDXの定義は、経済産業省が示す指針とも合致しています。
多くの小売企業がコスト削減のためにDXに注目する背景には、無視できない社会の変化があります。ここでは、DXが強く求められている3つの大きな理由を具体的に見ていきましょう。
昨今、原材料費やエネルギー価格の上昇はとどまることを知らず、商品の仕入れコストや店舗の光熱費を大きく圧迫しています。さらに、最低賃金の上昇に伴う人件費の増加も、経営上の大きな負担となっています。一方で、お客様は物価高の影響で節約志向を強めており、スマートフォンで簡単に価格を比較し、少しでも安いお店を選ぶのが当たり前になりました。
このような状況で、コスト増加分を単純に販売価格へ転嫁するだけでは、深刻な顧客離れを引き起こしかねません。だからこそ、DXを活用して業務プロセス全体から無駄を徹底的に排除し、コスト構造そのものを見直すことが急務なのです。これにより、価格競争力を維持しながら、しっかりと利益を確保する経営体質へと転換することが求められています。
少子高齢化が進む日本では、多くの産業で人手不足が深刻化しており、特に労働集約的な小売業はその影響を強く受けています。募集をかけても人が集まらず、少ない従業員で日々の業務を回さなければならない店舗も少なくありません。その結果、従業員一人ひとりの負担が増え、サービスの質が低下し、離職率が増加するといった悪循環に陥る危険性があります。
また、長年の経験を持つベテラン従業員の勘や記憶に頼った「属人化」した業務も大きな課題です。DXによって業務をマニュアル化・自動化することは、こうした属人化から脱却し、誰でも一定の品質で効率的に働ける体制を築くために不可欠な取り組みと言えるでしょう。
Amazonなどの大手ECサイトだけでなく、多くのライバル企業がすでにDXに着手し、その成果を上げています。例えば、AIを使って顧客の購買データを分析し、一人ひとりに合った商品を推薦したり、効率的な在庫管理で欠品や廃棄ロスを減らしたりする取り組みは、もはや珍しくありません。
このような状況で自社だけがアナログな経営を続けていれば、どうなるでしょうか。業務効率、コスト競争力、そして何より顧客体験の質といったあらゆる面で、競合との差は開く一方です。お客様はより便利で快適な購買体験を提供してくれるお店に流れていくでしょう。
もはやDXは、一部の先進的な企業だけのものではありません。激化する競争の中で企業が生き残り、持続的に成長していくためには、避けては通れない必須の経営戦略となっているのです。こうしたDXへの取り組みの遅れは、経済産業省のレポートでも「デジタル競争の敗者」となる可能性が指摘されています。
出典参照:DXレポート ~ITシステム「2025年の崖」克服とDXの本格的な展開~|経済産業省
出典参照:EC(eコマース)とは?ECサイトやECビジネスの 定義、メリットおよびデメリット|Amazon.com, Inc.
小売DXでコストを削減するためには、具体的にどこから手をつければ良いのでしょうか。特に効果が出やすい5つの領域について、具体的な方法を見ていきましょう。
小売業の現場は、レジ打ちや品出し、清掃、発注、シフト管理など、日々多くの定型業務に追われています。これらの作業に多くの時間が割かれると、人件費がかさむだけでなく、従業員がお客様への丁寧な対応といった付加価値の高い業務に集中できなくなります。
DXは、こうした定型業務を自動化・効率化する強力なツールです。例えば、会計業務はセルフレジやキャッシュレス決済端末を導入することでお客様自身に操作してもらい、スタッフの負担を軽減できます。また、売上報告や勤怠データの入力といったパソコン上の単純作業は、RPAという技術を使えばロボットに自動で任せることが可能です。
これにより創出された時間を接客や売り場づくりに充てることで、人件費を最適化しつつ、店舗の魅力を高めるという好循環を生み出せるでしょう。
「欠品による販売機会の損失」と「過剰在庫による廃棄ロス」は、小売業の利益を大きく損なう二大要因です。特に過剰在庫は、廃棄コストだけでなく、商品を保管するためのスペース費用や管理の手間、さらにはキャッシュフローの悪化まで引き起こします。
このジレンマを解決するのが、AIによる高精度な需要予測です。過去の販売実績やPOSデータに加え、天候、気温、周辺のイベント情報、SNSのトレンドといった多様なデータをAIが分析し、将来どれくらい商品が売れるかを予測します。
この客観的なデータに基づいて発注量を決めれば、担当者の経験や勘といった属人的な要素に頼ることなく、廃棄と欠品の双方を最小限に抑えることが可能になります。在庫管理システムと連携させれば、リアルタイムで在庫状況を把握し、より精度の高い発注が実現できます。
商品の仕入れや店舗間の移動、お客様への配送にかかる物流コストは、売上規模が大きくなるほど経営を圧迫するようになります。特に燃料費や人件費が高騰している現在、この領域の効率化はコスト削減に直結する重要なテーマです。
例えば、複数の店舗や顧客へ商品を配送している場合、AIが最適な配送ルートと巡回順を瞬時に計算してくれるシステムを導入すれば、無駄な走行距離を減らし、ガソリン代やドライバーの労働時間を大幅に削減できます。また、倉庫内では、WMS(倉庫管理システム)を活用することで、商品の保管場所を最適化し、ピッキング作業の動線を短縮することが可能です。
これにより、庫内作業の効率が上がり、人件費の削減や出荷ミスの防止に繋がります。物流はコストセンターと捉えられがちですが、DXによって大きな改善効果が期待できる領域なのです。
店舗を運営する上で必ず発生する電気代やガス代といったエネルギーコストは、利益を圧迫する固定費として見過ごされがちです。しかし、この領域もDXによって大きな削減効果が期待できます。
第一歩は、スマートメーターやBEMS(ビルエネルギー管理システム)を導入し、エネルギーの使用状況を「見える化」することです。時間帯や設備ごとに、どこでどれくらいのエネルギーが使われているかを正確に把握することで、初めて具体的な削減策を立てられます。
さらに、IoTセンサーを活用すれば、より積極的な省エネが可能です。例えば、人感センサーで従業員やお客様がいないバックヤードやトイレの照明を自動で消灯したり、外気温や日差しを検知して空調やブラインドを自動制御したりすることで、快適性を損なうことなく、無駄なエネルギー消費を徹底的に排除することができるでしょう。
新聞の折り込みチラシやDM(ダイレクトメール)といった紙媒体での販促は、多くの小売店にとって馴染み深い手法ですが、印刷費、折込料、郵送費、デザイン費など、多額のコストがかかります。さらに、効果を正確に測定することが難しいという課題もありました。
こうした販促活動をデジタルに置き換えることで、コストを抑えつつ、費用対効果の高いアプローチが可能になります。例えば、店内にデジタルサイネージを設置すれば、ポスターを印刷・貼り替える手間なく、時間帯や客層に合わせて表示内容を柔軟に変更できます。
また、公式アプリやSNS、メールマガジンを活用すれば、低コストで直接お客様のスマートフォンに情報を届けられ、開封率やクリック率といったデータから効果を測定し、次の施策に活かすことも容易になるのです。

日々の運営で直接かかる人件費や仕入れ費だけでなく、会社の利益を目に見えにくい形で圧迫しているのが「間接コスト」です。ここでは、特に見落としがちな3つのポイントについて解説します。
これまで、業務システムを導入する際は自社でサーバーを購入・設置し、専門の担当者が運用・保守を行うのが一般的でした。しかしこの方法では、高額な初期投資に加え、サーバーの維持費、電気代、セキュリティ対策、そして何より専門知識を持つIT人材の人件費といった継続的なコストが発生します。
そこで注目したいのが、インターネット経由でサービスを利用するクラウドやSaaSです。これらを活用すれば、自社でサーバーを持つ必要がなくなり、月額や年額の利用料だけで常に最新かつ安全なシステムを利用できます。面倒なアップデート作業やセキュリティ管理はサービス提供会社に任せられるため、IT部門の負担が大幅に軽減され、保守運用にかかるコストと手間を劇的に削減することが可能になるのです。
現場から「こんなツールがあれば業務がもっと楽になるのに」という声が上がっても、専門の開発会社に依頼すれば、小規模なアプリでも数十万から数百万円の開発費用がかかることは珍しくありません。このコストの壁が、業務改善の足かせになっているケースは多いでしょう。
こうした課題を解決するのが、プログラミングの専門知識がなくても、まるでパワーポイントやエクセルを操作するような感覚で業務アプリを開発できる「ノーコード/ローコード」ツールです。現場の業務を最もよく知るスタッフ自身が、自分たちの手で必要なツールを素早く、かつ低コストで作成できます。これにより、高額な外注費を削減できるだけでなく、現場のニーズに即した改善がスピーディーに進むようになり、組織全体の生産性向上にも大きく貢献してくれるでしょう。
DXの推進は、顧客情報や販売データといった重要なデジタル資産が増えることを意味します。これはビジネスチャンスの拡大に繋がる一方で、サイバー攻撃の標的になるリスクを高めることにもなります。万が一、ランサムウェア攻撃によるシステム停止や、顧客情報の漏洩といったセキュリティインシデントが発生すれば、その被害は計り知れません。事業の停止による売上損失、顧客への賠償金、システムの復旧費用といった直接的な金銭被害に加え、長年かけて築き上げてきた企業の社会的信用も一瞬で失墜してしまいます。
セキュリティ対策への投資は、目先の利益を生むものではないため、後回しにされがちです。しかし、これは将来起こりうる壊滅的な損失を防ぐための、最も重要な「予防コスト」なのです。安全な事業環境を維持することは、お客様からの信頼を守る上でも不可欠な責務と言えます。実際に、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)の調査でも、企業などの組織が直面する脅威として「ランサムウェアによる被害」が筆頭に挙げられています。
出典参照:情報セキュリティ10大脅威 2024|独立行政法人情報処理推進機構(IPA)
理論だけではイメージが湧きにくいかもしれません。ここでは、私たちにも身近な大手企業が、どのように課題を乗り越え、成果を出しているのか、3つの事例をご紹介します。
コンビニエンスストア最大手のセブン-イレブン・ジャパンは、社会的な課題でもある食品ロスの削減と、深刻化する人手不足という経営課題の解決にDXを活用しています。その中核を担うのが、AIによる発注支援システムです。このシステムは、過去の販売データはもちろん、天候や気温、曜日、地域の催事といった複雑な情報をAIがリアルタイムで分析し、商品ごとに最適な発注数を高い精度で予測します。
これにより、これまで従業員の長年の経験と勘に頼らざるを得なかった発注業務の負担が大幅に軽減され、業務効率化による人件費コストの削減に繋がっています。さらに、発注精度が向上することで、売れ残りによる廃棄コストと、品切れによる販売機会の損失という、相反する二つの課題を同時に解決し、コスト削減に大きな成果を上げています。
出典参照:店内作業効率化の取り組み|株式会社セブン‐イレブン・ジャパン
「お、ねだん以上。」のキャッチフレーズで知られるニトリは、顧客体験の向上とコスト削減を両立させる巧みなDX戦略を展開しています。その代表例が、Webブラウザ上で部屋のレイアウトを3Dシミュレーションできる「NITORI STUDIO」です。お客様は自宅の間取りに合わせて家具などを配置し、サイズ感や色合いを確認できるため、「イメージと違った」といった購入後のミスマッチを大幅に減らすことができます。
返品には輸送費や人件費など多くの間接コストが発生するため、この返品率の低下は、企業のコスト構造の改善に大きく貢献しているのです。
出典参照:(株)Forgers、ニトリにEC向けAR/3D導入サービス「RITTAI」とVR空間シミュレーター「RITTAI ROOM」を提供、XR活用を支援|株式会社ニトリホールディングス
関東地方を地盤とする人気スーパーマーケットのヤオコーは、特に複雑で属人化しがちだったデリカ(惣菜)部門の発注業務において、画期的なDXを実現しました。AIを活用した自動発注システムを全店舗に導入することで、これまでベテランの経験と勘に頼っていた業務の自動化に成功しました。
これにより発注業務は大幅に効率化され、創出された貴重な時間を、従業員が商品づくりや売場づくり、お客様とのコミュニケーションといった、より付加価値の高い業務に振り分けることを可能にしました。この取り組みは、業務効率化によるコスト削減はもちろん、店舗の魅力と顧客満足度の向上にも直接繋がる、優れたDX事例です。
出典参照:統合報告書2024|株式会社ヤオコー
DXを成功させるには、ただツールを入れるだけでなく、計画的な導入と社内の協力体制が大切です。どんなに優れたシステムも、現場に受け入れられ、正しく使われなければ意味がありません。ここでは、コスト削減というゴールを着実に達成するための、具体的な導入ステップと組織づくりのポイントを解説します。
DXでコスト削減を目指す際、いきなり全社規模で大規模なシステムを導入しようとするのは非常に危険です。多額の投資が無駄になるリスクがあるだけでなく、現場の業務フローを一度に大きく変えることは、従業員の混乱や反発を招き、かえって生産性を低下させる原因にもなりかねません。
成功への近道は、まず課題が明確で、投資対効果が見えやすい特定の業務や一部の店舗に絞って試験的に導入する「スモールスタート」です。例えば、まずは1店舗の在庫管理システムだけを刷新してみる、といった形です。そこで得られた成功体験や改善点を次の展開に活かすことで、リスクを最小限に抑えながら、着実にDXの範囲を広げていくことができます。
小さな成功を積み重ねることが、最終的に大きな変革を成し遂げるための最も確実な道筋となるでしょう。
DXの成否を分ける最も重要な要素は、経営層のトップダウンだけでなく、実際にシステムを使う現場の従業員をいかに巻き込むかにかかっています。新しいシステムの導入は、慣れ親しんだ仕事のやり方を変えるため、現場からは「面倒くさい」「覚えるのが大変」といった抵抗感や不安の声が上がるのが自然です。
これを乗り越えるためには、なぜDXが必要なのか、導入によって自分たちの仕事がどう楽になるのか、会社にとってどんなメリットがあるのかを、経営層が自分の言葉で丁寧に説明し、ビジョンを共有することが不可欠です。また、導入計画の段階から現場の意見をヒアリングしたり、各部署から推進メンバーを選出したりするなど、当事者意識を持ってもらう工夫も重要です。
全社一丸となって取り組む雰囲気を作ることが、DXを成功に導くための土台となります。
自社だけでDXを推進するための知識や人材が不足している場合、専門的な知見を持つ外部のパートナー企業と協力して進めるのが現実的な選択肢です。
その際に絶対に避けたいのが、システム開発を「丸投げ」してしまうことです。パートナー企業はあくまでもDXを実現するための伴走者であり、プロジェクトの主体は自社にあるという意識を強く持つ必要があります。
成功の鍵は、プロジェクト開始時に「在庫ロスを15%削減する」「発注業務にかかる時間を1人あたり1日30分短縮する」といった、具体的で測定可能な数値目標(KPI)をパートナーと明確に共有することです。そして、そのKPIの達成度を定期的に一緒に確認しながらプロジェクトを進めることで、目的から逸れることなく、着実にコスト削減というゴールに向かって進むことができるでしょう。
DXを単なるツールの導入で終わらせず、本当に会社の利益に繋げるためには、いくつかの大切な考え方があります。ここでは、常に心に留めておきたい重要な視点を4つご紹介します。
DXプロジェクトを進めていると、「AI」や「IoT」といった最新技術の導入そのものが目的化してしまうことがあります。しかし、本当に大切なのは「何のためにDXをやるのか」という本来の目的を見失わないことです。
「コスト削減」が最優先の目的なのであれば、その課題解決に最も直接的に貢献するツールや手法は何かを、冷静かつ客観的に判断しなくてはなりません。例えば、多機能で高価な最新システムよりも、特定の業務を自動化するシンプルなツールの方が、費用対効果が高い場合もあります。
常に「この投資は、コスト削減という目的に本当に合っているか?」と自問自答する姿勢が、無駄な投資を避け、着実に成果を出すための羅針盤となるのです。流行りの技術に振り回されず、自社の課題に根差した判断を心がけましょう。
どんなに高機能で優れたシステムを導入したとしても、それを実際に使う現場の従業員が価値を理解し、使いこなせなければ、ただの「高価な置物」になってしまいます。DXを成功させるためには、技術的な側面だけでなく、人的な側面への配慮が不可欠です。
システム導入の計画段階から、現場の従業員が日々の業務で何に困っているのかを丁寧にヒアリングし、その声をシステム選定や設計に反映させることが重要です。また、導入後も「あとはマニュアルを読んでおいて」と突き放すのではなく、集合研修の機会を設けたり、気軽に質問できるサポート窓口を設置したりするなど、継続的な教育体制を整える必要があります。
DXは、現場の従業員が主役であるという認識を持ち、彼らが前向きに取り組める環境を作ることが、成果を出すための絶対条件です。
DXは、企業のあり方を大きく変える可能性を秘めた取り組みですが、その分、失敗したときのリスクも大きくなります。特に、体力に限りがある中小企業にとって、大規模な初期投資が失敗に終わることは経営の根幹を揺るがしかねません。
そこで重要になるのが、一気に全面展開するのではなく、段階的に進めるという考え方です。まずは特定の店舗や部門を「パイロット(試験)導入」の対象とし、そこで限定的にシステムを運用してみます。その過程で、想定外の問題点や現場からの改善要望などを洗い出し、それらを修正した上で次の店舗へと展開していくのです。
このアプローチを取ることで、もし問題が発生しても影響を最小限に食い止められますし、小さな成功体験を積み重ねることで、社内のDXへの機運を高める効果も期待できます。
DXを推進する上で、外部のITベンダーやコンサルティング会社といったパートナー企業の力は非常に重要です。しかし、パートナーを単に指示通りに動く「下請け業者」として捉えていては、プロジェクトの成功はおぼつきません。優れたパートナーとは、技術力があるだけでなく、自社のビジネスモデルや業界特有の課題を深く理解し、同じ目線で「どうすればもっと良くなるか」を一緒に考えてくれる存在です。
そのため、パートナーを選ぶ際は、過去の実績や料金だけで判断するのではなく、担当者のコミュニケーション能力や、自社の事業への情熱を感じられるかどうかといった点も重視すべきです。信頼できるパートナーを見つけ、長期的な関係を築くことは、単なる業者選定ではなく、自社のDX戦略そのものを成功に導くための重要な一部であると認識しましょう。特に、パートナー企業との連携は、自社のセキュリティ体制だけでなく、サプライチェーン全体での対策が求められます。独立行政法人情報処理推進機構(IPA)の調査でも「サプライチェーンの弱点を悪用した攻撃」は重大な脅威として認識されており、パートナー選定の際にはセキュリティ体制の確認も不可欠です。
出典参照:情報セキュリティ10大脅威 2024|独立行政法人情報処理推進機構(IPA)

DXを進めるには、システム導入などで初期費用がかかりますが、国や自治体が用意している補助金や助成金を活用すれば、負担を軽くすることができます。
例えば、中小企業がITツールを導入する際に経費の一部を補助してくれる「IT導入補助金」や、販路開拓や業務効率化の取り組みを支援する「小規模事業者持続化補助金」などがあります。他にも、革新的な設備投資を支援する「ものづくり補助金」など、目的によって様々な制度が存在します。
これらの制度は返済が不要な場合がほとんどなので、自社で活用できるものがないか、中小企業庁のウェブサイトなどで情報を確認してみることをお勧めします。申請手続きは複雑な場合もあるため、早めに情報を集め、計画的に準備を進めることが採択に繋がります。中でも「IT導入補助金」は、POSシステムや在庫管理システムといった小売DXに直結するツールが幅広く対象となるため、まず確認したい制度の一つです。
出典参照:IT導入補助金2025|サービス等生産性向上IT導入支援事業事務局
ここまで、小売DXによるコスト削減の方法について、様々な角度から解説してきました。物価の上昇や人手不足といった厳しい環境は、これからも続くと考えられます。このような時代において、DXは単にコストを削減するだけの手段ではありません。会社の競争力を高め、持続的に成長していくための土台となる、非常に重要な経営戦略です。
もし、何から手をつければ良いか迷っているなら、まずは自社の仕事の流れを一つひとつ見直し、「どこに無駄があるのか」「何に一番時間がかかっているのか」を明らかにすることから始めてみてください。その現場の課題の中にこそ、コスト削減に繋がるDXのヒントがきっと隠されています。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
