小売DXの第一歩はペーパーレス化!メリットや書類管理の課題を解説
小売

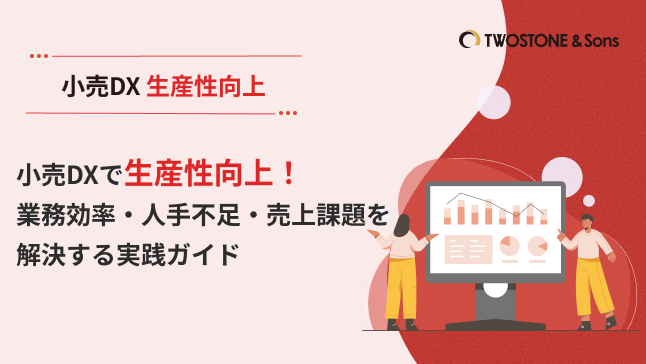
小売業の人手不足や売上課題を「小売DX」で解決しませんか?この記事では、DXによる生産性向上の具体的な効果から、失敗しない導入5ステップ、ビックカメラなどの成功事例までを分かりやすく解説。明日から実践できるヒントが満載です。


・6万名以上のエンジニアネットワークを活用して課題を解決※
・貴社のDX戦略立案から実行・開発までワンストップで支援可能
※エンジニア数は2026年8月期 第1四半期決算説明資料に基づきます。
「人手不足で現場が回らない」「オンラインの競争が激しい」。多くの小売業が抱えるこうした悩みを解決する鍵が、小売DXによる生産性向上です。これは単なるIT化ではなく、デジタル技術でビジネスそのものを変革し、新たな価値を生み出す取り組みを指します。
この記事では、小売DXがもたらす効果から具体的な進め方まで、成功事例を交えて分かりやすく解説します。未来へ向けた最初の一歩を、ここから踏み出しましょう。
小売DXとは、単に新しいITツールを導入することではありません。AIやIoT、ビッグデータといったデジタル技術を深く活用して、日々の業務の流れ、ビジネスの仕組み、そして働く人々の意識や文化までを根本から変革していくことを意味します。
これまでの小売業は、店舗での対面販売が中心でしたが、小売DXが進むと、オンラインとオフラインの境界線が溶け合い、顧客一人ひとりのデータに基づいた最適な買い物体験を提供できるようになります。また、バックヤード業務の自動化で作業効率を高めるなど、小売業のあらゆる側面が新しく生まれ変わるのです。これにより、生産性を大きく向上させ、激しい市場競争を勝ち抜くための力を育てていくことができます。
出典参照:DX推進指標(サマリー)|経済産業省

現在、多くの小売企業がDXの推進を重要な経営課題として捉えています。その背景には、もはや避けて通ることのできない、社会や市場の大きな環境変化が存在します。
日本の深刻な少子高齢化は、小売業の現場を支える人材の不足という形で、経営に直接的な影響を与えています。特に店舗運営は人手に頼る部分が多く、慢性的な人手不足は従業員の負担増を招き、サービスの質の低下につながりかねません。このままでは、お客様の満足度を維持することさえ難しくなってしまいます。
こうした状況を打開するためには、多くの人手と時間に頼ってきた従来のやり方を見直すことが急務です。デジタル技術を活用して、発注や在庫管理といった定型業務を自動化することができれば、従業員は接客や売り場づくりといった、人でなければできない付加価値の高い仕事に集中できます。DXによる業務効率化は、人手不足という大きな課題を乗り越え、持続可能な店舗運営を実現するための鍵となるのです。
スマートフォンの普及により、お客様の購買行動はオンラインへと大きくシフトしています。経済産業省の調査によると、日本のBtoC-EC(消費者向け電子商取引)市場は拡大を続けており、2022年には物販系分野だけで約14兆円に達しました。EC化率も年々上昇しており、オンラインでの購入が消費行動の中で確固たる地位を築いていることがわかります。
このように市場が拡大する中では、全国のECサイトはもちろん、海外から直接商品を販売する事業者や、SNSでファンを掴む新しいブランドなど、あらゆるプレイヤーが競争相手となります。このような厳しい環境で選ばれ続けるためには、ただ商品を並べるだけでは不十分です。DXを通じて顧客データを活用し、店舗とECを連携させたシームレスな購買体験を提供することが、生き残りのための必須条件となっています。
出典参照:令和4年度電子商取引に関する市場調査報告書|経済産業省
長年使い続けてきた古い業務システムや、紙と手作業に依存した業務フローが、変化への対応を妨げる足かせとなっています。部署ごとにデータが分断されている状態では、全社的な状況をリアルタイムに把握できず、迅速な意思決定の妨げになります。また、古いシステムの維持管理には多額のコストがかかり、新しい技術との連携も困難なため、経営上の大きな負担となりがちです。
手作業による非効率な業務は、ミスの原因になるだけでなく、従業員のモチベーション低下にもつながります。DXを推進し、こうした古い仕組みを刷新することは、業務を効率化する以上の価値を持ちます。データを一元管理し、柔軟に活用できる最新の基盤を整えることは、変化の速い市場に対応し、将来の成長を確実にするための重要な投資と言えるでしょう。
出典参照:DXレポート ~ITシステム「2025年の崖」克服とDXの本格的な展開~|経済産業省
小売DXは、業務を効率化するだけでなく、企業全体の生産性を高める様々な良い影響をもたらします。ここでは、その代表的な5つの効果について見ていきましょう。
これまで多くの時間を費やしてきた発注や在庫管理、日報作成といった定型業務は、デジタル技術によって自動化することが可能です。例えば、AIが天候や過去の販売実績などを分析して精度の高い需要予測を行えば、担当者の負担は大幅に軽減されます。。これにより、勘や経験だけに頼ることで生じていた過剰在庫や欠品のリスクを減らし、手作業によるデータ入力のミスも防ぐことができます。
日々の煩雑な作業から解放されることで生まれた時間は、従業員がより創造的で付加価値の高い仕事に集中するために使えます。政府が推進するAI戦略でも、人間は定型的な作業から解放され、より創造性が求められる業務へシフトすることが重要だとされています。お客様に寄り添った丁寧な接客や、季節感あふれる魅力的な売り場づくりなど、人でなければできない業務に注力できるようになり、店舗全体のパフォーマンス向上につながるのです。
セルフレジやキャッシュレス決済端末の導入は、レジ業務にかかる時間を短縮し、店舗運営の省人化・省力化に直接的に貢献します。ここで重要なのは、単に人を減らすのではなく、限られた人材という貴重な資源を、より価値のある業務に再配置することです。生まれた時間的な余裕を、お客様との会話や商品に関する専門的なアドバイス、お困りごとの解決といった、人でなければ提供できない温かみのあるサービスに使うことができます。
こうした取り組みは、従業員にとっても大きなメリットがあります。単純作業から解放され、自身の知識やスキルを活かせる場面が増えることは、仕事へのやりがいやモチベーションの向上につながります。従業員の満足度が高まることで、より質の高いサービスが提供され、それがお客様の満足度も高めるという好循環を生み出し、結果として人材の定着にも貢献します。
DXによる業務の自動化や省人化は、人件費という大きなコストの最適化につながります。さらに、その効果はそれだけにとどまりません。AIによる精度の高い需要予測は、売れ残りによる廃棄ロスや、過剰在庫を保管するための倉庫コストを削減します。また、契約書や請求書の電子化を進めれば、紙代や印刷代、郵送費といった細かな経費も着実に削減できます。
さらに、自社でサーバーを持たずに済むクラウドサービスを活用すれば、システムの初期導入費用や維持管理コストを大幅に抑えることができます。データが一元管理されることで、店舗間の在庫移動がスムーズになったり、本部での状況把握が迅速になったりと、運営全体の効率が向上します。こうした多角的なコスト削減と効率化が、企業の利益体質を強化していくのです。
DXを通じて収集されたお客様の購買データやWebサイトでの行動履歴は、まさに「宝の山」です。これらのデータを分析することで、一人ひとりの興味や関心に合わせた商品を最適なタイミングでおすすめしたり、誕生日クーポンといった特別なご案内を届けたりと、パーソナライズされたアプローチが可能になります。これにより、お客様は「自分のことを理解してくれている」と感じ、企業への信頼感や愛着を深めていきます。
ECサイトと店舗の会員情報が連携され、どこで買い物をしても同じようにポイントが貯まり、使えるといったシームレスな体験も、顧客満足度を大きく高める要素です。こうした満足度の高い体験の積み重ねが、お客様の再来店や継続的な購入を促し、一人のお客様が長期的に企業にもたらす利益(LTV)の向上に直結していくのです。
これまでの小売業では、店長の勘や長年の経験が意思決定の大きな拠り所でした。もちろん、その知見は非常に貴重なものですが、DXはそこに「データ」という客観的な根拠を加えることで、判断の精度を飛躍的に高めます。POSデータや顧客データ、ECサイトのアクセスログなどを統合的に分析することで、これまで見えなかった新たな事実や顧客インサイトを発見できるのです。
例えば、「どの商品が一緒に買われやすいか」「雨の日によく売れる商品は何か」といった分析結果は、売り場のレイアウト改善や効果的な販促キャンペーンの企画に直結します。データに基づいて「なぜ売れたのか」を深く理解し、仮説検証(PDCA)のサイクルを高速で回していくことで、より的確でスピーディーな経営判断が可能になり、ビジネスの成功確率を高めていきます。

小売DXを成功に導くためには、やみくもに進めるのではなく、計画的にステップを踏んでいくことが大切です。ここでは、そのための実践的な5つのステップをご紹介します。
DXの第一歩は、自社が今どのような課題を抱えているのかを正確に把握することから始まります。まずは「どの業務に一番時間がかかっているか」「人手不足が原因でどのような問題が起きているか」「お客様はどのような点に不満を感じているか」など、人手・時間・顧客体験という3つの視点から現状を洗い出しましょう。現場で働く従業員へのヒアリングや、お客様へのアンケートなどを通じて、具体的な声を集めることが重要です。
漠然とした問題意識のままでは、的確な解決策は見つかりません。「棚卸作業に毎月〇時間かかっている」「レジの待ち時間に関するクレームが月に〇件ある」といったように、できるだけ課題を具体的に、可能であれば数値化してリストアップすることが、後のステップへ進む上での確かな土台となります。
現状の課題が見えたら、次はDXによって「何を達成したいのか」という目的を明確にします。ここで重要なのは、「DXを導入すること」自体が目的になってしまわないように注意することです。あくまでDXは課題解決のための手段であるということを忘れてはいけません。「従業員の残業時間を20%削減する」「ECサイト経由の売上を半年で1.5倍にする」といった、具体的で測定可能な目標(KPI)を設定しましょう。
このような目的や戦略の策定は、経営者が主体となって進めることが極めて重要です。経済産業省が定める「デジタルガバナンス・コード」においても、経営者が明確なビジョンを示し、DX戦略を策定・実行することの重要性が強調されています。この目的とKPIを経営層から現場のスタッフまで、社内全体で共有することで、全員が同じ方向を向いてプロジェクトを進めることができます。この共通認識が、DX推進の大きな力となるのです。
出典参照:デジタルガバナンス・コード|経済産業省
いきなり全社的に大規模なシステムを導入するのは、コスト面でも運用の面でもリスクが大きすぎます。そこでおすすめしたいのが、特定の店舗や部門に限定して試験的に導入する「スモールスタート」というアプローチです。
独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が公開している「DX実践手引書」においても、DXの推進では、小規模かつ迅速に仮説検証を繰り返すアプローチが有効であるとされています。
例えば、まずは一つの店舗にだけセルフレジを導入してみる、特定の商品カテゴリーでAIによる需要予測を試してみるといった形で、小さな範囲から始めてみましょう。
このトライアル期間を通じて、導入による効果や課題、現場の従業員の反応などを具体的に検証します。小さな成功体験を積み重ねることで、本格導入に向けた社内の理解と協力を得やすくなるだけでなく、万が一失敗したとしてもその影響を最小限に抑えることができます。この学習期間が、最終的な成功の確率を大きく高めてくれるのです。
出典参照:DX実践手引書 ITシステム構築編 完成第1.1版|独立行政法人情報処理推進機構(IPA)
どんなに優れたツールやシステムを導入しても、実際にそれを使う従業員がうまく使いこなせなければ、期待した効果は得られません。DXを成功させるためには、技術の導入と並行して、社内に広め、定着させるための取り組みが不可欠です。なぜこの新しい仕組みを導入するのか、それによって仕事がどう良くなるのかを丁寧に説明し、研修の機会を設けたり、分かりやすいマニュアルを用意したりといったサポートを行いましょう。
また、新しいシステムに合わせて、これまでの仕事のやり方そのものを見直すことも重要です。時には、長年続けてきた業務フローを捨てる勇気も必要になります。現場からのフィードバックを積極的に収集し、改善に活かしながら、新しいツールが最も効果を発揮できるような業務プロセスを、会社全体で作り上げていく姿勢が求められます。
DXは、一度システムを導入したら終わりというプロジェクトではありません。市場やお客様のニーズは常に変化し続けるため、その変化に合わせて継続的に改善を繰り返していくことが成功の鍵となります。スモールスタートで得られた結果をKPIと照らし合わせて客観的に評価し、費用対効果や現場の定着度などを分析しましょう。
その分析結果から改善点を洗い出して修正し、効果が実証された成功モデルを、他の店舗や部門へと展開していきます。この「横展開」を行う際には、成功事例を社内で共有し、各部門の状況に合わせて微調整を加えることが重要です。このように「試行→評価→改善→展開」というサイクルを回し続けることで、DXは企業文化として根付き、会社全体の生産性を継続的に高めていく力となるのです。
すでに多くの企業が小売DXに取り組み、素晴らしい成果を上げています。ここでは、参考になる3つの企業の事例を見ていきましょう。
家電量販大手のビックカメラは、店舗とECサイトの垣根をなくす「OMO戦略」を強力に推進しています。顧客情報を一元管理し、お客様一人ひとりに合わせた情報提供を行うことで、快適な買い物体験を実現しました。
ネットで注文した商品を最寄りの店舗で受け取れるサービスは、顧客の利便性を大きく向上させています。また、これまで多くの時間を要していた棚卸作業にRPA(ロボットによる業務自動化)を導入することで、作業を大幅に効率化。
これにより、従業員がお客様への丁寧な接客により多くの時間を割けるようになり、サービスの質と業務効率の両方を高めることに成功しています。
出典参照:パーパス実現に向けて DX 宣言を発表|株式会社ビックカメラ
コンビニエンスストア大手のローソンは、深刻化する人手不足という社会課題に対し、テクノロジーで挑んでいます。
お客様自身のスマートフォンで商品のバーコードを読み取り、そのまま決済できる「スマホレジ」を導入。さらに、レジ自体が存在せず、商品を手に取って店を出るだけで自動的に決済が完了するウォークスルー型の無人店舗「Lawson Go」の実証実験も進めています。
これらの取り組みは、レジ待ちのストレスを解消すると同時に、店舗運営の省人化を大きく前進させるものであり、未来のコンビニの形を示唆しています。
出典参照:<参考資料>ローソンと日本マイクロソフト、AIやデータを活用した店舗のデジタルトランスフォーメーションにおいて協業|株式会社ローソン
世界的な家具・インテリア企業のイケアは、オンラインと店舗を融合させる「オムニチャネル戦略」で、顧客体験を大きく向上させています。その代表例が、AR技術を活用したアプリ「IKEA Place」です。これにより、お客様は購入前に自宅の部屋に家具を仮想的に配置でき、オンライン購入の不安を解消すると同時に、返品率の低下にもつなげています。
また、オンライン注文品を店舗で受け取るサービスや、全チャネル共通の会員プログラム「IKEA Family」などを通じて、顧客との長期的な関係を築いています。これらの施策は、顧客がどこで接しても一貫した素晴らしい体験ができるように設計されており、高い満足度と信頼を生み出しています。
出典参照:イケア・ジャパン、自宅に家具をバーチャルで設置できるアプリ「IKEA Place」の配信スタート|イケア・ジャパン株式会社
多くのメリットがある小売DXですが、その導入過程ではいくつかの壁に直面することもあります。しかし、それらの課題は、事前に対策を考えることで乗り越えることが可能です。
DXを推進するための専門的なIT知識を持つ人材を、自社内だけで確保するのは簡単ではありません。また、新しいツールを導入しても、現場の従業員がその使い方に慣れず、戸惑ってしまうことも考えられます。
これを乗り越えるためには、外部の専門家の力を借りたり、コンサルティングサービスを活用したりすることが有効な手段となります。同時に、社内でDXを推進するチームを作り、従業員向けの分かりやすい研修や勉強会を定期的に開くなど、内部での育成にも力を入れていくことが大切です。
新しいシステムの導入は、これまで慣れ親しんだ仕事のやり方を変えることを意味するため、現場の従業員から「今のままで十分だ」「新しいことを覚えるのは大変だ」といった抵抗感が生まれることも少なくありません。
こうした状況を乗り越えるには、経営トップが「なぜ今DXが必要なのか」というビジョンを明確に、そして繰り返し全社に伝えることが重要です。また、新しい仕組みによって仕事がどれだけ楽になるのか、お客様にどんな良い影響があるのかを具体的に示し、従業員一人ひとりの理解と協力を得ていく必要があります。
DXの推進には、新しいシステムの導入などに伴う初期投資がどうしても必要になります。しかし、その投資が将来どれくらいの利益となって返ってくるのかを、事前に正確に予測することは非常に難しいものです。そのため、経営層が投資の決断に踏み切れないというケースもよく見られます。
この課題に対しては、まずは小さな範囲で試験的に導入する「スモールスタート」が有効です。特定の店舗で「人件費がこれだけ削減できた」といった具体的な成功実績を示すことができれば、それが全社展開に向けた経営判断を後押しする、説得力のある材料となるでしょう。
小売DXをさらに加速させ、生産性を飛躍的に高める力を持つ最新のテクノロジーは、私たちの想像を超える可能性を秘めています。
AI(人工知能)は、もはや特別な技術ではなく、小売業の生産性を高めるための強力なパートナーです。過去の膨大な販売データや天候、地域のイベント情報などを機械学習させることで、未来の需要を高い精度で予測します。これにより、勘や経験だけに頼らない最適な発注が可能となり、欠品による機会損失や過剰在庫による廃棄ロスを大幅に削減できます。
IPAの「AI白書」においても、多くの企業がAIを「業務効率化」や「既存サービスの付加価値向上」のために活用していると報告されており、小売業でのこうした取り組みはまさにその実践例と言えるでしょう。政府が推進するAI戦略の観点からも、AIの社会実装による生産性向上は重要なテーマとされています。
出典参照:出典参照:AI戦略会議2025中間とりまとめ|内閣府
出典参照:独立行政法人情報処理推進機構(IPA)「AI白書」
IoT(モノのインターネット)は、店舗や倉庫にある様々な「モノ」をインターネットに繋ぎ、リアルタイムで状態を把握する技術です。例えば、商品棚に重量センサーを設置すれば、在庫が減ったことを自動で検知し、発注システムに通知することができます。これにより、従業員が目視で確認する手間が省け、棚卸業務の大幅な効率化が実現します。
さらに、店内に設置したカメラやビーコン(近距離無線技術)は、お客様の動線や滞在時間を分析するための貴重なデータを収集します。どの売り場に人が集まり、どの商品がよく手に取られているかを「見える化」することで、店舗レイアウトや商品陳列の最適化につなげられます。IoTは、これまで見えなかった現場の状況をデータとして捉え、改善のための具体的なヒントを与えてくれるのです。
デジタルツインとは、現実にある店舗や倉庫などを、コンピュータの中にそっくりそのまま再現する「デジタルの双子」を作る技術です。この仮想空間上では、現実世界に影響を与えることなく、様々なシミュレーションを行うことができます。例えば、「レジの配置を変えたらお客様の流れはどう変わるか」「新しい業務プロセスを導入したら、作業効率はどれくらい向上するか」といったことを、事前に何度も試すことが可能です。
これにより、実際に店舗の改装やシステムの導入を行う前に、その効果や問題点を予測し、リスクを最小限に抑えることができます。また、新人スタッフのトレーニングを仮想店舗で行うといった活用も考えられます。デジタルツインは、コストや時間をかけずに最適な答えを見つけ出すための「仮想実験室」として、小売業の意思決定をより確実なものにしてくれます。
従来の据え置き型のレジスターに代わり、タブレットなどの持ち運び可能な端末で利用できるクラウドPOSシステムが、小売業の常識を変えつつあります。データはインターネット上のクラウドで一元管理されるため、いつでもどこでもリアルタイムに売上状況を確認でき、迅速な経営判断につながります。また、高価な専用機材が不要なため、導入コストを抑えられるのも大きなメリットです。
このシステムの強みは、その柔軟性にあります。レジカウンターに行列ができた際には、スタッフがモバイル端末を持ってお客様の元へ向かい、その場で会計を済ませることができます。催事などの店舗外での臨時販売にも容易に対応可能です。クラウドPOSは、単なる会計ツールではなく、顧客データの活用や外部サービスとの連携も容易な、店舗運営の神経系とも言える重要な基盤となります。
EC事業の拡大に伴い、その裏側を支える物流倉庫のオペレーション効率化は、企業の競争力を左右する重要な要素となっています。特に人手不足が深刻な倉庫内作業において、ロボティクスの活用は不可欠です。注文された商品が保管されている棚を作業員の元まで自動で運んでくる「GTP(Goods to Person)」型の自動搬送ロボットは、広大な倉庫内を歩き回る時間を劇的に削減します。
これにより、ピッキング作業の大幅な省力化とスピードアップが実現し、従業員は検品や梱包といった、より丁寧さが求められる業務に集中できます。24時間稼働も可能なため、注文から発送までのリードタイム短縮にもつながり、顧客満足度の向上に貢献します。ロボティクスは、過酷な労働環境を改善し、EC事業の成長を支えるための強力なソリューションなのです。

ここまで見てきたように、小売DXはもはや一部の先進的な企業だけのものではありません。人手不足や激化する競争といった厳しい環境を乗り越え、これからもお客様に選ばれ、成長を続けていくために、すべての小売業にとって必要不可欠な取り組みとなっています。
大切なのは、最初から壮大で完璧な計画を立てようと気負うのではなく、自社の課題をありのままに見つめ、できることから一歩ずつ着実に始めてみることです。
まずは、あなたの日々の業務の中で「この作業、もっと楽にならないかな?」と感じる点や、お客様からいただく「もっとこうだったら嬉しいのに」という声に、改めて耳を傾けてみてはいかがでしょうか。その小さな気づきこそが、あなたの会社の未来を大きく変える、価値あるDXの第一歩になるはずです。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
