小売DXの第一歩はペーパーレス化!メリットや書類管理の課題を解説
小売

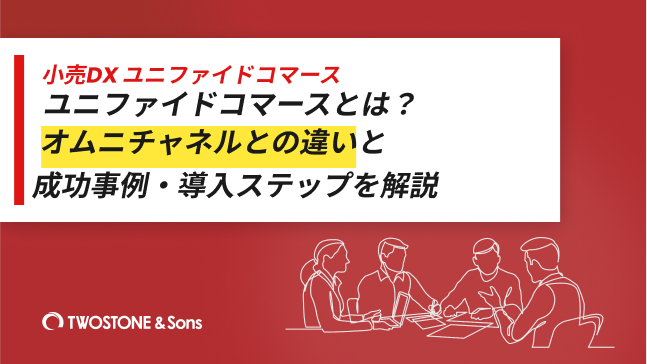
小売DXでデータ分断に悩んでいませんか?本記事ではユニファイドコマースを徹底解説します。オムニチャネルやOMOとの違い、LTV向上などのメリット、オルビスやナイキの成功事例から導入の3ステップまで、図や表で分かりやすく紹介します。


・6万名以上のエンジニアネットワークを活用して課題を解決※
・貴社のDX戦略立案から実行・開発までワンストップで支援可能
※エンジニア数は2026年8月期 第1四半期決算説明資料に基づきます。
ECサイトと実店舗で顧客情報が別々に管理されていて、一貫したサービスを提供できない。そんな悩みを抱えていませんか。顧客の購買スタイルが多様化する中で、データの分断は大きな機会損失に繋がる可能性があります。
この記事では、そうした課題を解決する鍵として注目される「ユニファイドコマース」を解説します。オムニチャネルとの違いや国内外の成功事例、導入の具体的なステップまでをわかりやすくご紹介します。LTV(顧客生涯価値)を高めるためのヒントがきっと見つかるでしょう。

近年、小売業界のDX(デジタルトランスフォーメーション)を推進する上で、ユニファイドコマースという考え方が重要視されています。まずはその基本的な概念と、なぜ今注目を集めているのかを見ていきましょう。
ユニファイドコマースとは、その名の通り「統合された商取引」を意味します。ECサイトや実店舗、公式アプリ、コールセンターといった顧客とのあらゆる接点で得られる情報を、一つのデータベースに集約して管理する考え方や仕組みのことです。
多くの企業では、システムごとに顧客データがバラバラに保管される「データのサイロ化」が課題となっています。ユニファイドコマースはこのサイロ化を解消し、顧客の行動や購買の履歴をチャネルの垣根なく、多角的に理解することを目指します。これは単にシステム同士を連携させるのではなく、初めからすべての情報を一元管理する点が大きな特徴といえるでしょう。
顧客データが完全に統合されると、一人ひとりの顧客に対して、一貫性のあるパーソナライズされた体験を提供できるようになります。
例えばECサイトでカートに入れた商品を、後日来店した際に店舗スタッフが「こちらの商品もご検討でしたか?」と提案することが可能になります。また、店舗での会話や試着した商品の情報を基に、後日その顧客に合わせたクーポンやおすすめ商品をアプリで通知することも考えられます。
このように、顧客がどのチャネルを利用しても「自分のことを理解してくれている」と感じられるような、スムーズな購買体験を創出することが、ユニファイドコマースの大きな目的です。
ユニファイドコマースとよく似た言葉に「オムニチャネル」や「OMO」があります。これらは目指す方向性に共通点もありますが、データの扱い方やアプローチに明確な違いが存在します。
これらの概念の最も大きな違いは、データの扱い方に表れます。オムニチャネルはECサイトと実店舗といったチャネル間の「連携」を強化し、顧客の利便性を高めることを目指します。しかし、データ自体はそれぞれのシステムに分散したままであることも少なくありません。
一方でユニファイドコマースは、データの「統合」そのものを目的とします。最初からすべてのデータを一つの場所で管理することで、真にパーソナライズされた体験をあらゆるチャネルで提供する土台を築きます。OMO(Online Merges with Offline)はオンラインとオフラインの「融合」による新たな顧客体験の創出に主眼を置く概念であり、ユニファイドコマースはOMOを実現するための基盤戦略と位置づけることができます。
これまで解説してきた3つの概念の違いを、以下の表で整理しました。特に注目すべきは「データ管理」と「顧客視点」の違いです。オムニチャネルが各チャネルの連携を主眼に置くのに対し、ユニファイドコマースは最初からデータを一元管理し、顧客「個人」に焦点を当てます。
OMOが目指すオンラインとオフラインが融合した滑らかな顧客体験も、この強力なデータ基盤があってこそ、より高いレベルで実現できるといえるでしょう。この表を通じてユニファイドコマースが他の施策の土台となる、より根本的なデータ戦略であることが視覚的に理解できるはずです。
比較軸 | ユニファイドコマース | オムニチャネル | OMO |
|---|---|---|---|
目的 | データの統合 | チャネル間の連携 | オンラインとオフラインの融合 |
データ管理 | 一元管理(単一データベース) | 分散管理(システム間連携) | 連携・統合 (施策による) |
顧客視点 | 個人(顧客中心) | チャネル(チャネル横断) | 体験 (オンライン・オフラインの区別がない) |

ユニファイドコマースを導入することは、企業側だけでなくサービスを利用する顧客側にも多くの利点をもたらします。このセクションでは、その代表的なメリットを3つの側面からご紹介します。
企業側の大きなメリットとして、LTV(顧客生涯価値)の向上が期待できます。顧客一人ひとりの行動や購買履歴をチャネル横断で深く理解できるため、より精度が高く心に響くマーケティング施策を展開できるようになります。
例えば、顧客の好みに合わせた商品を適切なタイミングでおすすめしたり、特別なクーポンを提供したりすることで、顧客は「自分だけの特別なサービス」と感じるでしょう。こうした体験の積み重ねが顧客満足度を高め、ブランドへの信頼と愛着を育み、長期的な関係構築に繋がります。一人の顧客と長く付き合うことで、結果的にLTVの向上を実現するのです。
全社で統一された正確なデータを活用できるようになるため、よりデータに基づいた経営判断、いわゆるデータドリブン経営への移行を後押しします。これまでの経験や勘に頼った仕入れではなく、客観的なデータに基づいた高精度な需要予測が可能になるでしょう。
どの店舗でどの商品が、どの時期によく売れるのかといった動向をリアルタイムで把握できます。これにより品切れによる販売機会の損失を防ぎつつ、過剰な在庫を抱えるリスクを低減させ、在庫管理全体の最適化を実現します。これは収益改善に直結する重要なメリットです。
データが一元管理されることで、これまでチャネルごとに行っていた業務の効率が大きく向上します。特に在庫管理や顧客対応において、その効果が顕著に現れるでしょう。
例えばECサイトで受けた注文を、顧客の最寄り店舗の在庫から発送するといった柔軟な対応がスムーズに行えるようになります。また、顧客からの問い合わせに対しても、店舗スタッフとコールセンタースタッフが同じ情報を参照できるため、迅速で一貫性のある案内が可能です。これによりスタッフの負担を軽減し、より質の高い顧客サービスに集中できる環境が整います。
理論だけでなく、実際にユニファイドコマースを導入して成果を上げている企業の事例から、具体的な取り組みを見ていきましょう。
化粧品ブランドのオルビスは、2022年10月にリリースした新しい公式アプリを顧客接点の中心に据え、ユニファイドコマースを推進しています。このアプリではECサイトと店舗の購入履歴はもちろん、過去の肌診断データやカウンセリングの履歴まで一元的に管理されています。
顧客はアプリを通じて自分の肌状態の変化を時系列で確認したり、AIによるパーソナルメイクアドバイスを受けたりすることが可能です。このようにオンラインとオフラインのデータを統合し、アプリ上で一貫したパーソナライズ体験を提供することで、顧客との長期的な関係構築に成功しています。
出典参照:オルビス、アプリを核に新たなCRM戦略を加速|オルビス株式会社
スポーツ用品大手のナイキは公式アプリ「Nike App」を通じて、オンラインと実店舗の体験をスムーズに融合させています。アプリ会員は限定商品へのアクセスや特典といったオンラインでのメリットに加え、店舗での体験もより豊かなものになります。
例えば来店前にアプリで店舗の在庫を確認したり、気になる商品のバーコードをスキャンして、オンライン上のレビューや他のカラーバリエーションをチェックしたりすることが可能です。このようにアプリがオンラインとオフラインの架け橋となり、顧客がナイキブランドと繋がるあらゆる場面で、一貫した質の高いサービスを提供しています。
ユニファイドコマースの実現には、計画的なアプローチが求められます。このセクションでは、導入を成功に導くための基本的な手順を3つのステップに分けて解説します。
導入プロジェクトを始めるにあたり、最も重要なのが目的の明確化です。「なぜユニファイドコマースを導入するのか」という問いに対し、自社の具体的な課題と結びつけて答えを出す必要があります。この目的が曖昧なままでは関係者間の認識がずれ、プロジェクトが迷走する原因となりかねません。
例えば「分断された顧客体験を改善し、リピート購入率を15%向上させる」あるいは「データに基づいた需要予測で、在庫廃棄率を20%削減する」といった、数値で計測できるKPI(重要業績評価指標)を設定することが望ましいでしょう。この最初の目的設定が、プロジェクト全体の方向性を決定づけます。また、明確なゴールは、社内の関連部署から協力を得る上でも不可欠な要素です。
次に、社内の様々な場所に散らばっている顧客データを、一つの場所に集めて管理するためのデータ基盤を構築します。店舗のPOSシステムやECサイトの基幹システム、MAツール、公式アプリなど、どこにどのようなデータが存在するのかをすべて洗い出す作業から始めます。
その上でこれらのデータをどのように統合し、活用していくのかを設計します。この段階では、後述するCDP(Customer Data Platform)のような専門的なシステムの導入が中心的なテーマとなることが多いです。自社の目的を達成するために、どのような機能を持つシステムが最適かを慎重に検討することが求められます。
最初から全社的に大規模なシステムを導入するには、相応のリスクが伴います。そのため、まずは特定の顧客層や一部のチャネルに絞って、小規模な施策から試してみる「スモールスタート」が有効なアプローチです。
例えば、「優良顧客に限定して、ECサイトの閲覧履歴に基づいた商品を店舗で提案してみる」といった施策を実行し、その前後で購買率がどう変化したかを計測します。このような小さな成功体験と学びを積み重ねながら、徐々に取り組みの範囲を広げていくことが、着実に成果を出すための堅実な進め方といえるでしょう。
ユニファイドコマースを実現するためには、データを統合し、活用するための様々なシステムが連携して機能することが求められます。このセクションでは、その中核を担う3つの主要なシステムとその役割を紹介します。
CDP(Customer Data Platform)は、オンライン・オフラインを問わず、あらゆるチャネルから顧客データを収集・統合し、顧客一人ひとりの詳細な情報(プロファイル)を作成するためのプラットフォームです。まさにユニファイドコマースの心臓部ともいえるシステムといえるでしょう。
CDPの役割は、単にデータを集めるだけではありません。統合・整理されたデータを、後述するMAやCRMといった他のマーケティングツールにスムーズに連携させるハブとしての機能も担います。CDPを導入することで、これまでバラバラだった顧客情報を初めて一元的に捉え、活用する準備が整います。
CRM(Customer Relationship Management)は、顧客の基本情報や購買履歴、問い合わせ履歴などを管理し、顧客との良好な関係を長期的に築くためのシステムです。一方、MA(Marketing Automation)は、メール配信やWebサイトでの接客といったマーケティング施策を自動化し、効率的に運用するためのツールを指します。
ユニファイドコマースの文脈では、CDPによって統合された質の高い顧客データを活用し、これらのCRMやMAを通じて、顧客一人ひとりに最適化されたコミュニケーションを実行します。データと施策を結びつける重要な役割を担っているのです。
店舗での販売情報を管理するPOSシステムも、ユニファイドコマースを実現する上で欠かせない要素です。ここで求められるのは従来のスタンドアロン型のPOSではなく、顧客情報やECサイトのデータとリアルタイムに連携できる統合POSシステムです。
このシステムがあれば、店舗スタッフは目の前のお客様が「ECサイトでどの商品を見ていたか」や「過去に何を購入したか」といった情報をその場で把握しながら接客できます。これにより、より顧客のニーズに寄り添った、質の高いサービスを提供することが可能になるでしょう。

本記事では、ユニファイドコマースの基本から導入ステップまでを解説しました。これは単なるシステム導入ではなく、データ統合によって顧客を深く理解し、最高の体験を提供する経営戦略です。
ECと店舗のデータ分断という課題を乗り越えることが、今後の小売市場で競争優位性を築く鍵となるでしょう。まずは自社のデータがどこに、どのように存在しているのかを把握することから、一歩先の顧客体験実現に向けた取り組みを始めてみてはいかがでしょうか。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
