小売DXの第一歩はペーパーレス化!メリットや書類管理の課題を解説
小売

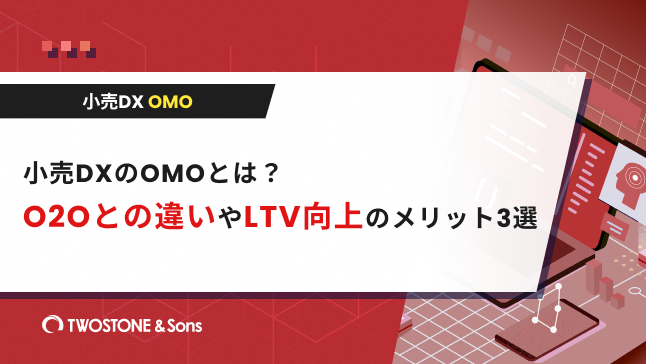
小売DXの鍵「OMO」とは何か、基本からメリットまで分かりやすく解説します。店舗とECの連携不足といった課題を解決し、無印良品などの成功事例から自社で実践する5ステップまでを知ることができます。DX戦略を加速させるヒントを見つけましょう。


・6万名以上のエンジニアネットワークを活用して課題を解決※
・貴社のDX戦略立案から実行・開発までワンストップで支援可能
※エンジニア数は2026年8月期 第1四半期決算説明資料に基づきます。
店舗売上の伸び悩みや、ECサイトとの連携不足に課題を感じていませんか。顧客がオンラインとオフラインを自由に行き来する今、小売業のDXを成功に導く考え方が「OMO」です。
この記事ではOMOの基本的な意味から、導入のメリット、国内外の成功事例、そして自社で始めるための具体的なステップまでを分かりやすく解説します。OMOの本質を理解し、自社のDX戦略を加速させるヒントを見つけていきましょう。

小売業界のDXを考える上で、OMOは中心的な概念となりつつあります。まずはOMOがどのような考え方なのか、そして混同されやすい他のマーケティング用語とどう違うのかを整理していきましょう。
OMOとは「Online Merges with Offline」を略した言葉です。日本語に訳すと「オンラインとオフラインの融合」となり、ECサイトやアプリといったオンラインの場と、実店舗などのオフラインの場との境界線をなくすことを目指すマーケティング戦略を指します。
OMOの大きな特徴は、オンラインとオフラインを区別せず、顧客体験を第一に考える点にあります。顧客がチャネルの違いを意識することなく、まるで一つの大きなお店で買い物をしているかのように、商品を認知してから購入後のサポートまで、一貫したサービスを受けられる状態を目指す考え方です。
OMOと似た言葉に「O2O」や「オムニチャネル」があります。これらの言葉は目指す方向性が少しずつ異なります。O2Oは「Online to Offline」の略で、オンラインからオフライン、つまりECサイトから実店舗へ顧客を誘導することを主な目的としています。
一方、オムニチャネルは実店舗やECサイト、SNSなど、顧客とのあらゆる接点(チャネル)を連携させ、どこからでも商品の購入や受け取りができるようにする戦略です。これは顧客の利便性を高めるものですが、視点は企業側にあり、各チャネルのデータを連携させることが中心となります。OMOはこれらの概念をさらに発展させ、顧客視点でオンラインとオフラインの体験を完全に融合させることを目指す点で異なっています。
OMOを導入することは、顧客の利便性を高めるだけでなく、企業経営の観点からも多くの利点があります。このセクションでは、代表的な3つのメリットについて見ていきましょう。
OMOがもたらす最大のメリットは、一貫性のある質の高いサービスを提供することで、顧客満足度を大きく向上させられる点です。例えばECサイトでチェックした商品を最寄りの店舗で試着予約したり、店舗で接客を受けた店員から後日オンラインで個別の提案を受けたりといった体験が可能になります。
このようなスムーズな購買体験は、ブランドへの信頼や愛着を育みます。その結果、顧客一人が生涯にわたって企業にもたらす利益を示すLTV(顧客生涯価値)の最大化に繋がるでしょう。一度きりの関係で終わらせず、長期的なファンを育てていくことが期待できます。
OMOでは、これまで別々に管理されがちだったオンラインでの行動データと、オフラインでの購買データを、顧客IDを軸に一つに統合します。これにより顧客一人ひとりの行動や好みをより深く理解できるようになり、マーケティングの精度を高めることが可能です。
例えば、「店舗で特定の商品をよく購入する顧客に対し、オンラインで関連商品のクーポンを配信する」といった、個々のニーズに合わせたアプローチが実現します。データに基づいて的確な施策を行うことで、マーケティング活動の効果を大きく向上させることが期待できるでしょう。
「ECサイトでは在庫切れでも、店舗には在庫が残っている」「店舗に希望のサイズがなく、顧客が購入を諦めてしまった」といった状況は、多くの小売業が直面する課題です。これは大きな販売機会の損失といえます。
OMOによって店舗とECの在庫情報がリアルタイムで連携されれば、ECサイトから店舗の在庫を確認したり、取り寄せたりすることが可能になります。これにより、販売の機会損失を大幅に減らすことができます。また、店舗をEC商品の受け取り拠点として活用することもでき、顧客の利便性向上と売上増加の両方に貢献します。
OMO戦略にいち早く取り組み、成果を上げている企業は少なくありません。このセクションでは、具体的な企業の事例を通じて、OMOがどのように実践されているのかを見ていきましょう。
無印良品を展開する株式会社良品計画は、公式アプリ「MUJI Passport」をOMO戦略の中心に置いています。このアプリは単なる会員証ではなく、オンラインとオフラインの顧客体験をつなぐ重要な役割を果たしています。来店時のチェックインや商品購入で「MUJIマイル」が貯まる仕組みは、顧客が店舗へ足を運ぶきっかけになっています。
また、アプリ上で各店舗の在庫状況を確認できるため、顧客は欲しい商品があるかどうかを事前に知ることが可能です。さらに購入履歴に基づいた情報提供や、ユーザーがレビューを投稿できる機能も備えており、顧客との継続的な関係構築に貢献しています。アプリを軸に顧客データを活用し、一貫したサービスを提供することで、ファンの育成に繋げている好例です。
出典参照:MUJI REPORT 2024|株式会社良品計画
アパレル大手の株式会社オンワード樫山は、「ONWARD CROSSET STORE」をはじめとするOMO型店舗の展開を積極的に進めています。これらの店舗は商品を販売するだけの場所ではなく、新しい顧客体験を提供する場として機能しているのが特徴です。
店舗には一部のサンプル商品のみを置き、顧客は実際に商品を試着しながら、タブレット端末を使ってECサイト上の豊富な在庫から注文します。商品は後日自宅に配送されるため、顧客は手ぶらで買い物を楽しむことが可能です。この仕組みは、企業側にとっても店舗の在庫を最適化できるというメリットがあります。顧客の利便性と企業の収益性を両立させた、先進的なOMO戦略といえるでしょう。
出典参照:OMO型店舗戦略の加速 スタートから3年で全国137店舗へ拡大|株式会社オンワードホールディングス

OMOは、単に新しいツールを導入するだけで実現できるものではありません。明確な戦略を立て、段階的に進めていくことが成功への近道です。このセクションでは、OMO導入を5つのステップに分けて解説します。
最初に最も重要なことは、「何のためにOMOを導入するのか」という目的をはっきりさせることです。「顧客満足度を高めたい」「店舗とECの売上を両方伸ばしたい」など、自社の課題に合わせた具体的な目的を設定しましょう。
目的が決まったら、その達成度を測るための指標であるKPI(重要業績評価指標)を設定します。例えばLTV(顧客生涯価値)やNPS(顧客推奨度)、店舗とECを両方利用する顧客の割合などがKPIとして考えられます。目的とKPIを最初に定めることで、プロジェクトの方向性がぶれるのを防ぐことができます。
次に設定した目的を達成するために、顧客がどのような体験をすれば満足度が最も高まるか、理想の顧客体験ジャーニーを描きます。このとき企業側の都合ではなく、徹底して顧客の視点で考えることが大切です。
顧客が商品を認知して興味を持ち、比較検討し、購入し、利用し、そしてファンになるまでの一連のプロセスを想像します。その中で、オンラインとオフラインの各接点でどのような情報やサービスを提供すれば、顧客がストレスなく楽しく買い物ができるかを具体的に設計していくのです。
設計した顧客体験ジャーニーを実現するためには、これまでバラバラに管理されていた顧客データを一つにまとめる基盤が不可欠です。その中心的な役割を担うのが、CDP(カスタマーデータプラットフォーム)と呼ばれるシステムです。
CDPは、店舗のPOSデータやECサイトの購買履歴やアプリの行動ログなど、社内に点在するあらゆる顧客データを収集・統合します。そして、顧客一人ひとりを軸にデータを整理するためのプラットフォームとして機能します。このデータ基盤を構築することで、初めて顧客を深く理解し、一人ひとりに合わせたアプローチが可能になるのです。
最初から全店舗で大規模な改革を行うのは、リスクが大きくなる可能性があります。まずは特定の店舗や施策に絞って小さく始め、その効果を検証していくのが賢明な進め方です。
例えば、「モデル店舗を一つ選んで、店舗受け取りサービスを試験的に導入する」「特定の顧客層に向けて、オンラインとオフラインを連携させたキャンペーンを実施してみる」といった形が考えられます。小さく始めて成功体験を積み重ね、課題を洗い出しながら、徐々に展開範囲を広げていくアプローチが成功の確率を高めるでしょう。
施策を実行した後は、必ずステップ1で設定したKPIに基づいて効果を測定します。データ分析を通じて、どの施策が顧客満足度や売上の向上に貢献したのか、あるいは効果が薄かったのかを客観的に評価することが重要です。
そしてその分析結果をもとに、顧客体験ジャーニーや施策の内容を常に見直し、改善を続けていく(PDCAサイクルを回す)ことが求められます。OMOは一度導入すれば終わりではなく、顧客の変化や市場の動向に合わせて進化させ続ける取り組みなのです。
OMOは多くのメリットをもたらす一方で、その導入にはいくつかの壁が存在します。事前にどのような課題があるかを認識し、対策を考えておくことが、スムーズな導入に繋がります。
OMOを実現するためには、社内で使われている様々なシステムを連携させる必要があります。例えば店舗のPOSシステムやECサイトのカートシステム、在庫管理システム、顧客管理システム(CRM)などを、CDPを中心に連携させることが求められます。
しかし、これらのシステムは導入された時期や開発した会社が異なる場合が多く、連携には高度な技術力や相応のコストがかかることも少なくありません。自社のIT部門のリソースや予算を考慮し、どこまでの連携を目指すのか、現実的な計画を立てることが大切です。
日本の企業では、店舗を管轄する部門とECサイトを運営する部門が縦割りになっていることがよくあります。それぞれの部門が独自の目標や評価制度を持っていると、お互いに顧客や売上を奪い合うような状況が生まれやすく、全社的なOMO推進の大きな妨げとなる可能性があります。
この壁を乗り越えるためには、経営層が強いリーダーシップを発揮し、OMOを会社全体の戦略として位置づけることが不可欠です。部門を横断するプロジェクトチームを作ったり、店舗とECの売上を合算して評価するような新しい仕組みを導入したりといった、組織的な改革が求められるでしょう。
OMOを推進していくには、データ分析やデジタルマーケティング、UI/UX設計、プロジェクトマネジメントといった、多様な専門スキルを持つ人材が必要です。しかし、これらのスキルをすべて兼ね備えた人材は市場全体でも限られており、確保や育成が大きな課題となっています。
社内で人材を育成するには時間がかかるため、プロジェクトの初期段階では外部の専門家やコンサルティング会社の力を借りることも有効な選択肢です。外部の知見を取り入れながら、並行して社内での人材育成計画を進めていくことが、現実的なアプローチといえるかもしれません。

ここまでOMOの各要素を解説しましたが、その成功の鍵は「顧客体験の再設計」にあります。OMOは単なるシステム導入やマーケティング手法ではなく、顧客を主語に置いてオンラインとオフラインの境界をなくすという思想そのものです。
この記事を参考にぜひ貴社のビジネスに置き換えて、「私たちのお客様にとって、最高の購買体験とは何か?」を問い直すことから始めてみてください。それが、OMO成功への第一歩となるでしょう。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
