小売DXの第一歩はペーパーレス化!メリットや書類管理の課題を解説
小売

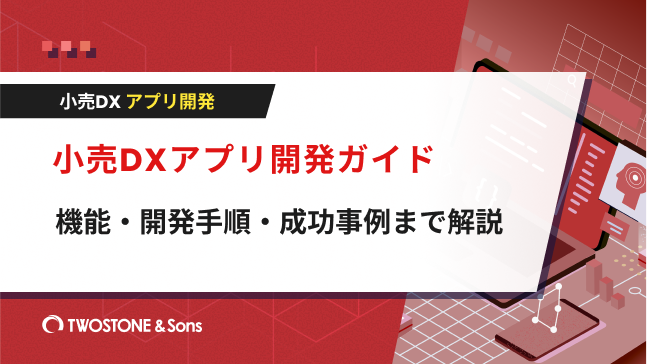
小売DXでアプリ開発を検討中の方へ。顧客接点を強化し売上向上に繋がる機能、フルスクラッチやパッケージ開発の費用相場、具体的な開発手順、成功事例までを網羅的に解説。失敗しない開発会社の選び方のポイントも紹介し、貴社のDX推進を強力にサポートします。


・6万名以上のエンジニアネットワークを活用して課題を解決※
・貴社のDX戦略立案から実行・開発までワンストップで支援可能
※エンジニア数は2026年8月期 第1四半期決算説明資料に基づきます。
店舗運営やECサイトに加えて、アプリやSNS、カスタマーサポートなど、顧客との接点が急速に多様化しています。その一方で、それぞれのチャネルがバラバラに管理されていては、統一感ある顧客体験を提供するのは難しくなります。
DX(デジタルトランスフォーメーション)が求められる今、単にITツールを導入するだけでは、顧客ロイヤルティの向上や売上改善にはつながりません。重要なのは、すべての接点で一貫性ある「CX(顧客体験)」を提供すること。そしてその要となるのが、顧客と直接つながる“アプリ”の活用です。
この記事では小売DXにおけるアプリの重要性を起点に、導入目的や具体的な機能、開発の進め方、成功事例までをわかりやすく解説します。これからアプリ開発を検討している企業にとって、全体像を掴む手がかりとなる内容をまとめました。

多くの小売企業がアプリ開発に注目する背景には、顧客との関係性や販促活動における大きな変化があると考えられます。
アプリは顧客との関係を深め、ビジネスを成長させるための重要なツールとなり得るでしょう。
アプリは顧客のスマートフォンに直接アプローチできる、非常に身近なチャネルといえます。
例えば、プッシュ通知機能を活用してセールや新商品の情報をタイムリーに届けることや、アプリ限定のクーポンを配信することができます。
こうした施策は顧客の関心を引きつけ、再来店を促す効果が期待できるでしょう。また紙のポイントカードとは異なり、紛失や持参し忘れの心配がありません。顧客はいつでも手軽に企業との接点を持つことが可能になります。
このような継続的なコミュニケーションを通じて、顧客のファン化、すなわちロイヤルティの向上が見込めるのではないでしょうか。
新聞購読率の低下などを背景に、従来の折込チラシやDMといった紙媒体による販促効果は、以前よりも限定的になっている可能性があります。
一方でこれらの施策にかかる印刷費や配送費は、企業のコスト負担としてのしかかる場合も少なくありません。
アプリを導入し販促活動をデジタルに移行することで、これらのコストを削減できる可能性があります。それによって生まれた予算をより効果的なプロモーションやアプリの機能改善に再投資することで、ROI(投資対効果)の向上が期待できるでしょう。
アプリはコスト効率の良い販促活動を実現する、有効な選択肢の一つです。
自社アプリは、顧客データを収集・分析するための強力な基盤となり得ます。
顧客の属性情報(年齢、性別など)に加え、アプリ内での行動履歴、例えば「どの商品ページを閲覧したか」「どのクーポンを利用したか」「どの店舗をお気に入り登録したか」といった詳細なデータを蓄積することが可能です。これらのデータを分析することで、顧客一人ひとりの興味や関心に合わせ、パーソナライズされた情報提供が実現できるでしょう。
例えば、「特定の商品を購入した顧客に対し、関連商品のクーポンを配信する」といった施策が考えられます。こうしたきめ細やかなアプローチは、顧客満足度の向上や売上アップに繋がる重要な要素といえます。
OMO(Online Merges with Offline)とは、オンライン(ECサイトなど)とオフライン(実店舗)の垣根をなくし、顧客に一貫した購買体験を提供することを目指すマーケティング戦略の一つです。
アプリはこのOMO戦略を実現する上で、中心的な役割を担うと考えられています。例えば、アプリを通じて「ECサイトで商品を注文し、最寄りの店舗で受け取る」「店舗で商品のバーコードをスキャンし、ECサイト上のレビューや詳細情報を確認する」「実店舗とECサイトで共通のポイントを貯め、利用する」といった連携が可能になります。
アプリがオンラインとオフラインのハブとなることで、顧客の利便性を高め、ブランド全体での相乗効果を生み出すことが期待できるでしょう。

小売業向けのアプリには、売上向上や顧客満足度アップに繋がる様々な機能が考えられます。
ここでは、多くの企業で導入されている代表的な機能を紹介します。自社の目的や顧客層に合わせて、必要な機能を選択することが重要です。
プッシュ通知とはユーザーがアプリを起動していなくても、スマートフォンの待受画面に直接メッセージを配信できる機能です。
セール情報や新商品の入荷、タイムセールといった鮮度の高い情報を能動的かつタイムリーに顧客へ届けることが可能になります。
メールマガジンなど他の通知手段と比較して開封率が高い傾向にあるともいわれ、顧客の来店やサイト訪問を促す強力なきっかけとなり得るでしょう。
ただし配信頻度が高すぎると顧客に不快感を与え、通知オフやアンインストールの原因にもなりかねないため、配信内容やタイミングには注意が必要です。
アプリ限定で利用できるクーポンを配信することは、顧客にとってアプリをダウンロードする強い動機付けとなり得ます。
また、継続的に利用してもらうための有効な施策の一つとも考えられるでしょう。例えば「初回ダウンロード特典クーポン」や「お誕生日クーポン」、あるいは「特定の商品群にのみ使える割引クーポン」など、様々な種類のクーポンを企画・配信することが可能です。
こうした魅力的な特典を提供することで顧客の購買意欲を刺激し、来店頻度や購入単価の向上が期待できるのです。
従来プラスチックカードで提供されていた、会員証やポイントカードの機能をスマートフォンアプリで代替するものです。
顧客にとってはカードを財布に入れて持ち歩く必要がなくなり、紛失のリスクが低減するなど、利便性が大きく向上するでしょう。企業側にとっても、物理的なカードの発行や管理にかかるコストを削減できるというメリットが考えられます。
またアプリ上でポイント残高や有効期限をいつでも手軽に確認できるようにすることで、ポイントの利用を促進し、顧客の囲い込み効果も期待できるでしょう。
スマートフォンのGPS機能と連携して現在地から最も近い店舗を検索したり、ルートを案内したりする機能は、顧客の来店をサポートする上で非常に有効です。
各店舗の営業時間や電話番号、取り扱いサービスといった基本情報も合わせて提供できるとより利便性が高まるでしょう。
さらに、顧客が探している商品の在庫がどの店舗にあるかをリアルタイムで確認できる機能も、顧客満足度の向上に大きく貢献すると考えられます。これにより、「店舗に行ったのに目当ての商品がなかった」という顧客の不満や機会損失を防ぐことが可能になります。
実際にアプリを導入し、DXを推進している企業の事例を見ていきましょう。
自社の課題と照らし合わせることで、アプリ活用の具体的なイメージが掴めるかもしれません。
小売業のDX支援を行う株式会社デジクルは、LINEミニアプリを活用した販促プラットフォーム「デジクル」を提供しています。
あるスーパーマーケットではこのサービスを導入し、LINE上でデジタル会員証やクーポンを配信しました。
その結果、従来の紙クーポンと比較して利用率が2倍以上になるという成果が報告されています。これは多くの顧客が日常的に利用するLINEというプラットフォームを活用することで利便性を高め、スムーズな利用体験を提供できた結果といえるでしょう。
出典参照:デジクル、「さんすて福山」に「デジクル for LINEミニアプリ」を導入し販促キャンペーンのデジタル化を支援|株式会社デジクル
「無印良品」を展開する株式会社良品計画の公式アプリ「MUJI passport」は、小売業におけるアプリ活用の代表的な成功事例の一つとして知られています。
このアプリは、単なるデジタル会員証や商品情報ツールにとどまらない機能を提供している点が特徴です。
例えば店舗へのチェックインや商品の口コミ投稿によってもマイルが貯まる仕組みを導入し、購買以外の行動も顧客エンゲージメントに繋げています。その結果、年間アクティブユーザー数は1,569万人を超える規模に成長しています。
アプリを通じて顧客との多様な接点を創出し、強固な関係を築いている好例といえるでしょう。
出典参照:無印良品 スマートフォンアプリ「MUJI passport」を「MUJI アプリ」へ全面リニューアル|株式会社良品計画
アプリを開発するには、主に3つの手法が考えられます。
それぞれにメリット・デメリット、そして想定される費用や期間が異なるため、自社の目的や事業フェーズに合わせて最適な方法を選択することが重要です。
フルスクラッチ開発とは既存のテンプレートなどを使用せず、ゼロから完全にオリジナルのアプリをオーダーメイドで開発する手法です。
デザインや機能を自由に設計できるため、他社にはない独自性の高いアプリを実現できる可能性を秘めています。また既存の社内システムとの連携など、複雑な要件にも柔軟に対応しやすい点が大きなメリットといえるでしょう。
一方で、開発費用は高額になる傾向があり、一般的には数百万から数千万円規模の投資が必要になるといわれます。開発期間も半年から1年以上と長期に及ぶことが多いため、潤沢な予算と時間が見込める場合に適した手法と考えられます。
パッケージ・SaaS利用とは、アプリ開発会社があらかじめ用意した既存の機能やテンプレート(パッケージ)を組み合わせてアプリを構築する手法です。クラウド経由でサービスが提供されるSaaS形式が主流となっています。
フルスクラッチ開発と比較して、開発費用を大幅に抑えられる点が最大のメリットでしょう。また開発期間も比較的短く、数ヶ月程度でスピーディーにアプリを導入できる可能性があります。
一方でデザインや機能のカスタマイズ性には一定の制約があるため、提供されている機能の範囲内で要件を満たせるかどうかの見極めが重要です。コストを抑えつつ、標準的な機能のアプリを迅速に導入したい場合に適した手法といえます。
ノーコード・ローコード開発とは、プログラミングの専門知識をほとんど必要とせず、画面上のパーツをドラッグ&ドロップするなどの直感的な操作でアプリを開発できるプラットフォームを利用する手法です。
3つの開発手法の中では、最もコストと時間を抑えられる可能性があります。専門の開発担当者がいない場合でも、事業部門のスタッフが主体となってアプリを開発・改修できる場合がある点も特徴です。
ただしカスタマイズの自由度は最も低く、複雑な機能の実装や大規模なデータ処理には向かないケースが多いでしょう。まずは試験的にアプリを導入してみたい場合や、特定のシンプルな機能に絞って運用したい場合に有効な選択肢と考えられます。

アプリ開発は一般的に「企画・要件定義」から始まり、「設計・デザイン」「開発・テスト」を経て、「リリース・運用保守」へと至るプロセスで進められます。
各ステップを着実に進めることが、プロジェクトの成功に繋がるでしょう。
企画・要件定義は、アプリ開発プロジェクトの土台を築く最も重要な工程といえるでしょう。
まず「何のためにアプリを作るのか?」という目的を明確にし、「売上〇%向上」「リピート率〇%改善」といった具体的な目標(KGI/KPI)を設定することが求められます。
その上で、ターゲットとなる顧客像(ペルソナ)を具体的に描き、その顧客が抱える課題を解決するためにどのような機能が必要かを洗い出していきます。この段階での検討が不十分だと、手戻りが発生したり、完成したアプリが誰にも使われないといった事態を招きかねません。
要件定義で固まった機能や仕様をもとに、アプリの具体的な設計図を作成する工程です。
まずアプリの画面構成や画面間の遷移を定めた「ワイヤーフレーム」を作成し、機能の骨格を可視化します。
その後ブランドイメージやターゲットユーザーの好みを考慮しながら、具体的な配色やアイコン、フォントなどを決定し、ビジュアルデザインを制作していきます。
この際、ユーザーが直感的に操作できるか(UI)、使っていて心地よいか、満足できるか(UX)といった視点がアプリの継続利用率を左右する重要な要素となるでしょう。
設計書に基づいてエンジニアが実際にプログラミングを行い、アプリの機能を実装していく工程です。
iOS向けとAndroid向け、両方のOSに対応するアプリを開発するのが一般的です。開発が完了したら、リリース前に徹底的なテストを実施します。要件定義通りに機能が動作するか、特定の操作でエラーが発生しないか、様々な機種やOSバージョンで表示崩れが起きないかなど、多角的な視点から品質を検証します。
このテスト工程を丁寧に行うことでリリース後のトラブルを未然に防ぎ、ユーザーに快適な利用体験を提供できるでしょう。
テストをクリアしたアプリは、各プラットフォームの公式ストアに公開申請を行います。
各社の審査を通過すると、晴れて一般のユーザーがダウンロードできる状態(リリース)となります。
しかしアプリはリリースして終わりではありません。ユーザーからのフィードバックを収集し、データ分析に基づいて機能を改善していく必要があります。
またOSのバージョンアップへの対応やサーバーの監視といった、安定稼働を支えるための運用・保守業務も継続的に発生します。アプリを「育てる」という視点を持つことが重要です。
自社のパートナーとなる開発会社を選ぶことは、アプリ開発プロジェクトを成功させるための重要な鍵となります。
実績やサポート体制、将来性といった観点から慎重に比較検討することが求められるでしょう。
開発会社を選定する際には自社と同じ小売業界、あるいはアパレル、スーパーマーケット、専門店といった近しい業種でのアプリ開発実績が豊富かどうかを確認することが重要です。
小売業界特有の商習慣や課題を深く理解している会社であれば、より的確な提案やスムーズな開発が期待できるでしょう。
過去に手掛けたアプリの事例を見せてもらい、どのような課題に対してどのような機能で解決を図ったのかなど、具体的にヒアリングすることをおすすめします。これにより、自社のプロジェクトを任せるに足る知見を持っているか判断しやすくなります。
アプリはリリースしてからが本当のスタートともいえます。そのため開発後のサポート体制が充実しているかどうかは、非常に重要な選定ポイントになるでしょう。
具体的には、サーバーの監視や障害発生時の対応といった保守体制、OSのアップデートに迅速に対応してくれるかなどの確認が必要です。
さらにアプリの利用状況を分析し、改善提案をしてくれるような運用支援サービスを提供している会社であれば、より心強いパートナーとなります。どこまでのサポートが契約に含まれているのか、事前にしっかりと確認しておくことが大切です。
事業環境は常に変化するため、将来的にアプリの機能を拡張したり、外部システムと連携したりする必要が出てくる可能性があります。
そのため開発会社の提供するサービスが、どの程度のカスタマイズに対応できるかを確認しておくことが重要です。
例えば「最初は基本的な機能でスタートし、将来的には自社の基幹システムやECサイトと連携させたい」といった展望がある場合、そうした拡張に柔軟に対応できる技術力やプラットフォームを持っているかを見極める必要があります。
目先の機能要件だけでなく中長期的な事業戦略も見据えた上で、拡張性の高いパートナーを選ぶことが将来の投資対効果を高めることに繋がるでしょう。
小売業におけるアプリ開発は単なるデジタル施策の一つではなく、DXを本格化させるための土台となる存在です。プッシュ通知や会員証、OMO対応など、アプリがもたらす機能は顧客接点の強化だけではありません。販促効率の向上、データ活用によるパーソナライズ、そして実店舗とECの統合など多岐にわたります。
また開発手法や費用感、成功事例を知ることで自社に合った導入プランの検討も進めやすくなります。最終的には、自社の目的や顧客ニーズに合わせた機能設計に加え、信頼できる開発パートナー選びがプロジェクト成功のカギを握るといえるでしょう。
小売DXを加速させる第一歩として、アプリ開発の全体像を改めて整理してみてはいかがでしょうか。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
