小売DXの第一歩はペーパーレス化!メリットや書類管理の課題を解説
小売

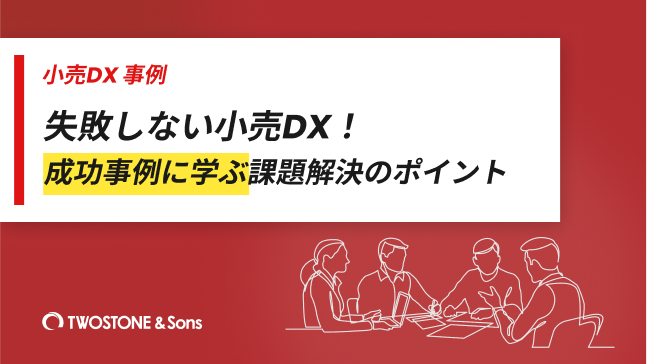
小売業のDX(デジタルトランスフォーメーション)成功事例を業態別に解説。ファミリーマートの無人決済店舗、無印良品アプリ、カインズのIT小売企業宣言など、現場課題を解決する最新事例と取り組みポイントを分かりやすく紹介します。


・6万名以上のエンジニアネットワークを活用して課題を解決※
・貴社のDX戦略立案から実行・開発までワンストップで支援可能
※エンジニア数は2026年8月期 第1四半期決算説明資料に基づきます。
小売企業でDX推進を担う多くの方々が、「何から手をつければ良いか分からない」という悩みに直面しているのではないでしょうか。
この記事では、小売業界が抱える課題を解決するためのDXについて、具体的な成功事例を交えながら分かりやすく解説します。
課題別・業態別の事例から、自社の状況に近いヒントを見つけ、社内提案や施策立案にお役立てください。
小売DXとは、単にデジタルツールを導入することではありません。 デジタル技術やデータを活用し、これまでのビジネスモデルや業務プロセス、顧客体験を根本から変革することで新しい価値を生み出す取り組みのことです。
例えば、レジを新しくするだけなら「IT化」です。一方で、レジから得られる購買データを分析し、顧客一人ひとりに合った商品をおすすめしたり、無駄のない在庫管理を実現したりすることでビジネス全体を変革するのが「DX」です。
多くの小売企業がDXに取り組む今、その本質を理解し、自社の課題解決に繋げることが成功の鍵となります。

多くの小売企業が直面する「人手不足」「顧客体験」「在庫管理」「データ活用」といった課題。このセクションでは、それぞれの課題をDXによってどのように解決したのか、具体的な成功事例を見ていきましょう。
ファミリーマートでは、人材不足や深夜営業への対応策として「無人決済店舗」の取り組みを進めています。
日中は有人店舗の商品棚として運営し、その他の時間帯は店舗の一部区画を無人店舗として活用するハイブリッド型の運営です。
天井カメラや電子タグ(RFID)を用いた無人決済システムにより、従業員が常駐しない時間帯でも買い物が可能となっています。レジ対応業務の削減によってオペレーションコストの低減が期待され、人材不足の解消にも繋がる取り組みです。
出典参照:全国初!売り場面積・品揃え・決済ゾーンの最小モデル無人決済店舗 TTG-SENSE SHELF 甲南大学内に9月20日(金)オープン|株式会社ファミリーマート
パルコは2014年に公式アプリ「POCKET PARCO」をリリースし、顧客行動データを収集・分析してマーケティングに活用しています。
アプリではポイント保有状況や利用履歴に合わせた、パーソナライズプッシュ通知を配信。さらに、パルコ独自のQRコード決済機能「ポケパル払い」、特典クーポンの配布、ショップニュースのクリップ、店舗来店時にポイント交換可能なコイン付与機能なども搭載されています。
これらの機能により、リアルとオンラインをつなぐOMO推進の取り組みが進められています。
出典参照:Repro、「POCKET PARCO」へのソリューション導入成果を発表|株式会社パルコ
カインズは店舗をEC在庫の一部として活用する、「店舗の倉庫化」戦略を進めています。
全国約250店舗の在庫情報をリアルタイムで連携することで、オンラインでの欠品時にも店舗在庫を引き当てることが可能になり、販売機会の損失を減らす取り組みとなっています。
また、近隣店舗からの配送により、配送コストの削減とスピーディな商品提供も実現。こうした店舗とECの在庫一元化は、カインズの物流効率化とEC強化を支える重要な施策です。
出典参照:ロジスティクス|株式会社カインズ
無印良品を展開する株式会社良品計画は、2013年に会員アプリ「MUJI passport」を導入し、2025年9月に「MUJI アプリ」へ全面リニューアルする予定です。
このアプリは会員証機能として購入履歴やチェックインなどでマイルを貯められるほか、パーソナライズされた情報配信や商品検索、在庫検索機能も搭載。2024年度の年間アクティブユーザー数は1,569万人に達しました。
今後は貯まったポイントを寄付や買い物に使える「MUJI GOOD PROGRAM」として、新しい会員サービスを展開する計画が発表されています。
出典参照:無印良品 スマートフォンアプリ「MUJI passport」を「MUJI アプリ」へ全面リニューアル|株式会社良品計画
次に、スーパーやアパレルといった業態ごとの特徴的なDX事例を見ていきましょう。自社の業態に近い事例は、より具体的な参考になるはずです。
トライアルでは、AIカメラ搭載のスマートショッピングカート(SSC)を導入したスマートストアをオープンしています。このカートはセルフレジ機能やスキャン漏れ防止アラート、デジタルサイネージ機能を備え、キャッシュレス決済にも対応。
2022年には最新モデル90台を追加し、SSCは累計約8,000台、月間約120万人が利用する世界最大級の規模となっています。AIカメラで収集した購買データを分析し、売り場最適化や非計画購買の促進にも活用している事例です。
出典参照:トライアルグループ初、環境に配慮したZEB認証取得のスマートストア※1「メガセンタートライアル荒尾店」2月11日(火)オープン|株式会社トライアルホールディングス
アダストリアが展開する公式WEBストア「.st(ドットエスティ)」は、会員数約1,400万人を抱えるOMOプラットフォームとしてアパレル業界内でも存在感を高めています。
スタッフ約4,000名が毎日最新コーデを投稿する「STAFF BOARD」では、店舗スタッフの提案力をオンラインでも発揮し、顧客がコーデを参考にEC購入できる仕組みを構築。
ライブショッピング機能も開始し、スタッフやモデルによる配信をアプリやECサイト上で展開するなど、リアルとデジタルを融合した購買体験の提供を進めています。
出典参照:ドットエスティがアプリでのライブ配信を本格化、ライブコマースツール「Bambuser」を導入|株式会社アダストリア
ローソンは人手不足や深夜対応の課題解決と多様な働き方の実現を目指し、アバター接客システム「AVACOM」を展開しています。
2022年に運用を開始し、2025年6月時点で国内28店舗・約80名のオペレーター体制へと拡大。導入店舗ではセルフレジ利用率が15%以上向上し、年間約1.5時間のレジ業務削減も確認されています。
さらに、青森県内3店舗で東北初の実証実験を開始し、3D表示や多言語対応といった新たな機能検証も進行中。アバターを通じた非対面接客は、省人化と接客品質向上の両立を目指す先進的な取り組みです。
カインズは「IT小売企業宣言」を掲げ、デジタル戦略本部の設立やIT人材採用、システム内製化を強化してきました。
表参道の「CAINZ INNOVATION HUB」でアジャイル開発体制を整え、現場ニーズに合わせた店舗アプリ機能やマスク抽選販売を短期間で開発。
さらに、オウンドメディア戦略にも注力し、DIY情報を発信する『となりのカインズさん』は正式オープンから1年未満で月間400万PVを達成しました。ペット領域に特化した『WanQol(わんクォール)』や、くらしに役立つYouTubeチャンネル『カインズTV』など多彩な情報発信も展開しています。
こうしたリアルとデジタルを融合する取り組みが評価され、日経コンピュータ「IT Japan Award 2021」グランプリも受賞しています。
出典参照:デジタル戦略|株式会社カインズ
多くの小売企業がDXの推進を経営の重要課題として位置づけていますが、その背景には業界全体を取り巻く深刻な変化が存在します。
このセクションでは、なぜ小売DXが不可欠とされているのかについて、3つの側面から解説します。
スマートフォンの普及により、消費者はいつでもどこでも情報を収集し商品を購入できるようになりました。SNSで口コミを調べてから店舗に行く、ECサイトと実店舗の価格を比較するなど、購買行動は複雑化しています。
このような「欲しい」と思った瞬間に購買を検討する「パルス型消費」ともいえる行動に対応するためには、オンラインとオフラインを連携させ、顧客一人ひとりに合った体験を提供することが不可欠です。
DXによるデータ活用は、その実現のための鍵となります。顧客がチャネルを意識しない以上、企業側も垣根のないサービス設計が求められるのです。
少子高齢化に伴う労働人口の減少は、小売業界にとって深刻な問題です。人手不足は従業員の負担増を招き、サービスの質の低下や離職に繋がりかねません。
DXによって発注や在庫管理、レジ業務などを自動化・効率化し、従業員がより付加価値の高い業務に集中できる環境を整えることが急務となっています。
これは従業員満足度の向上にも寄与すると考えられます。
ECプラットフォーマーやテクノロジー企業(リテールテック)が小売市場に参入するなど、業界の垣根を越えた競争が激化しています。
従来のビジネスモデルのままでは、こうした新しい競合に太刀打ちできなくなる可能性があります。彼らはデータを駆使した高度なマーケティングや、効率的な物流網を武器にしています。
データ活用による顧客理解の深化や新たな購買体験の創出といったDXの取り組みを通じて、自社の競争力を高めていく必要があります。もはや同業他社だけがライバルではない時代なのです。
DXを推進することで、企業は多くのメリットを得ることができます。これらは単独で得られるだけでなく、互いに影響し合い、企業の成長を加速させる効果が期待できます。
顧客データを分析することで、顧客一人ひとりのニーズに合わせた商品やサービスを提案(アップセル・クロスセル)できるようになり客単価の向上が期待できます。
また、AIによる需要予測で在庫を最適化し、欠品による販売機会の損失や過剰在庫による廃棄ロスを削減することで、利益率の改善にも繋がります。
さらに、データに基づいた価格最適化(ダイナミックプライシング)なども可能になり、収益性を最大化する道筋が見えてくるでしょう。
DX導入によって、これまで手作業で行っていた発注、在庫管理、レジ業務などをデジタルツールで自動化・効率化できます。これにより従業員は単純作業から解放され、より創造的で付加価値の高い業務に時間を使うことができます。
例えば、顧客へのコンサルティング的な接客や季節やトレンドに合わせた魅力的な売り場づくりなどです。
結果として、少ない人数でも質の高い店舗運営が可能になり、深刻な人手不足問題の解消に貢献します。従業員満足度の向上にも繋がるでしょう。
オンラインと実店舗のデータを連携させることで、顧客にシームレスで一貫した購買体験を提供できます。
例えば、ECサイトで注文した商品を最寄りの店舗で受け取れたり、アプリで個人の好みに合ったクーポンが届いたりするなど、利便性と満足度の高いサービスは顧客のロイヤリティを高めます。
これは価格競争から脱却し、顧客に選ばれ続けるための強力な差別化要因となります。顧客に「自分のことを理解してくれている」という特別感を与えることが重要です。
売上データや顧客データなどを一元的に管理・分析することで、勘や経験だけに頼らない、客観的なデータに基づいた意思決定(データドリブン経営)が可能になります。
どの商品がどの顧客層に売れているのか、どの施策が効果的だったのかを正確に把握し、迅速かつ的確な経営判断を下すことができます。
これにより新商品の開発や不採算部門の見直し、キャンペーン効果の正確な測定など、ビジネスの精度とスピードを飛躍的に高めることが期待できます。
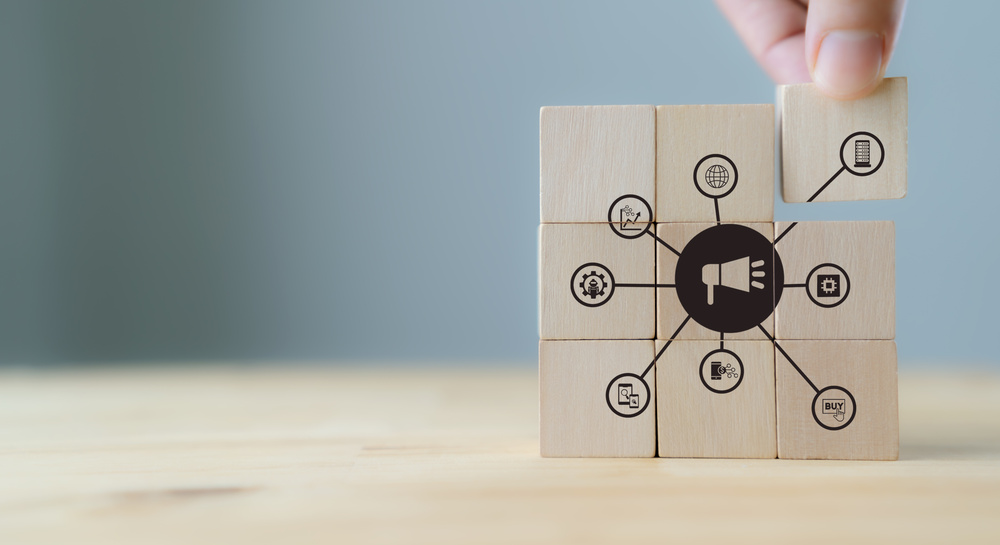
小売DXを成功させるためには、具体的にどのような施策に取り組むべきでしょうか。このセクションでは、代表的な4つの施策を紹介します。自社の課題に合わせた施策を検討することが重要です。
OMOとはオンライン(ECサイトやアプリ)とオフライン(実店舗)の垣根をなくし、顧客に一貫した体験を提供する戦略です。現代の顧客はチャネルを意識せずに情報を収集し購買するため、企業側もその行動に合わせたサービス設計が求められます。
具体的には、ECサイトと店舗の会員情報の統合やECサイトで注文した商品の店舗受け取りサービス、店舗在庫のオンラインでの可視化などが挙げられます。
これにより、顧客の利便性を最大化することが目的です。
収集した顧客データや購買データを活用することで、マーケティングの精度を高めることができます。
例えば購買履歴から顧客をセグメント分けし、それぞれの層に合ったアプローチを行うことが可能です。さらにAIを活用すれば、天候やイベント情報なども加味して将来の需要を予測し、発注業務の自動化や在庫の最適化も実現できます。
こうした取り組みによって、勘や経験に頼らない科学的なアプローチが可能になります。データに基づいたパーソナライズ施策は、顧客満足度の向上にも直結するといえるでしょう。
デジタルツールを導入し、店舗スタッフの業務負担を軽減します。セルフレジやキャッシュレス決済はレジ業務を効率化し、電子棚札は価格変更作業を自動化します。
これにより従業員は接客など、より付加価値の高い業務に集中できるようになります。AIカメラによる品出しタイミングの通知や清掃ロボットの導入なども、省人化に貢献する施策として注目されています。
創出された時間をいかに顧客価値の向上に繋げるかが、成功の鍵となります。
ECサイトと全店舗の在庫情報をリアルタイムで連携させ、一元管理します。
これにより、顧客がECサイトで品切れの商品を在庫のある他店舗から取り寄せられるようにするなど、販売機会の損失を防ぎ顧客満足度を向上させることが期待できます。
企業側も全社の在庫を最適に配置・活用できるため、過剰在庫の削減やキャッシュフローの改善にも繋がります。OMO戦略を推進する上での、まさに土台となる重要な仕組みといえるでしょう。
DXは闇雲に始めても成功しません。このセクションでは、着実に成果を出すための4つのステップを紹介します。このプロセスを丁寧に踏むことが、成功への近道となります。
まずは自社の現状を正確に把握することから始めます。 「人手不足で店舗が回らない」「在庫が多くて利益を圧迫している」など、現場の声も参考にしながら課題を洗い出しましょう。
そして「半年後にレジ業務の時間を30%削減する」「1年後にEC経由の売上を20%向上させる」といった、具体的で測定可能な目標(KPI)を設定します。
この目標が後の効果測定の基準となり、プロジェクトの羅針盤としての役割を果たします。
ステップ1で設定した目標を達成するために、どのようなDX施策を実行するかを計画します。
例えば「レジ業務の効率化」が目標なら、セルフレジの導入などが考えられます。その際、期待できる効果やコスト、導入難易度などを考慮して施策の優先順位をつけ、いつまでに何をするのかというロードマップを作成することが重要です。
誰が責任者なのかを明確にし、関係部署との連携体制を整えることも忘れてはなりません。
いきなり全店舗に新しいシステムを導入するのはリスクが大きいため、まずは特定の店舗や部門に限定して小さく始める「スモールスタート」をお勧めします。
これはPoC(概念実証)とも呼ばれます。試験的に導入し、「本当に業務は効率化されたか?」「顧客はスムーズに使えているか?」といった効果を検証します。
この段階で課題が見つかれば、本格展開の前に改善することができるため大きな失敗を防ぐことに繋がります。
スモールスタートで効果が確認できたら、他の店舗や部門へ本格的に展開していきます。
ただし、導入して終わりではありません。設定したKPIを定期的に測定し、目標が達成できているかを確認します。
思うような効果が出ていない場合は、その原因をデータに基づいて分析し、改善策を実行するというPDCAサイクルを回し続けることが重要です。効果測定と改善の継続はDXを成功に導き、企業文化として根付かせるための鍵となります。

多くの企業がDX推進の過程で様々な壁に直面します。あらかじめ課題を想定し、対策を考えておくことが重要です。このセクションでは
代表的な壁と、その対処法を解説します。
DXは全社的な取り組みであり、経営層の強いコミットメントが不可欠です。しかし、短期的なコストを懸念され理解を得られないことも少なくありません。
成功事例や具体的な費用対効果(ROI)の試算を示し、DXが単なるコストではなく、将来への投資であることを粘り強く説明しましょう。
スモールスタートで小さな成功実績を作り、効果を具体的に示すことも有効です。経営層が理解できる言葉でDXの価値を伝える努力が求められます。
DXを推進したくても、「社内にデジタル技術に詳しい人材がいない」という課題は深刻です。全てを自社でまかなおうとせず、外部の専門家やコンサルティング会社の支援を積極的に活用することが現実的な解決策です。
同時に、長期的な視点で社員向けの研修(リスキリング)を実施するなど、社内でのDX人材育成に計画的に取り組んでいくことも重要になります。外部の知見を吸収しながら、社内にノウハウを蓄積していく両輪のアプローチが効果的です。
長年使用してきた古い基幹システム(レガシーシステム)が、新しい技術の導入を妨げる障壁となることがあります。経済産業省も「2025年の崖」として警鐘を鳴らしています。
ただし、一度に全てを刷新するのは困難です。まずはAPIなどを活用して既存システムと連携させ、段階的に新しいシステムへ移行していく計画を立てることが賢明です。
既存のシステムを前提とした上で、実現可能なDXの形を考えるという柔軟な視点も必要になります。
出典参照:DXレポート ~ITシステム「2025年の崖」克服とDXの本格的な展開~|経済産業省
部門ごとにデータがバラバラに管理(サイロ化)されていると、全社横断的なデータ活用はできません。
例えば「ECの優良顧客が店舗で何を買っているか」といった分析ができず、機会損失に繋がります。まずは、各部門が持つデータを一元的に集約・管理するためのデータ活用基盤(CDPなど)を整備することが第一歩です。
その上で、部門の垣根を越えてデータを活用する文化を醸成していく必要があります。データは特定の部門の所有物ではなく、企業全体の資産であるという意識改革が求められます。
小売DXを推進するためには、様々なツールの活用が欠かせません。このセクションでは、目的別に代表的なツールを紹介します。自社の課題解決に繋がるツールを選定することが重要です。
店舗の日常業務を効率化し、スタッフの負担を軽減するツールです。
売上・顧客・在庫情報を連携できるPOSレジシステムや、多様な決済手段に対応するキャッシュレス決済端末、シフト作成を自動化する勤怠管理システム、本部との情報共有を円滑にするビジネスチャットツールなどが挙げられます。
これらは店舗の生産性向上に直結し、従業員がより重要な業務に集中できる環境を作り出します。会計の迅速化は顧客満足度にも繋がるでしょう。
顧客との関係を深め、販売促進に繋げるためのツールです。
なかでも代表的なのが、CRM(顧客関係管理)ツールです。顧客情報を一元管理し、購買履歴などから「優良顧客」や「離反リスクのある顧客」を見極めてくれるため、個別に最適なアプローチができるようになります。
さらに「カゴ落ちメール」や誕生日クーポンの自動配信が可能なMA(マーケティングオートメーション)ツールや、プッシュ通知で来店を促す店舗アプリも効果的な販促手段として注目されています。
これらのツールを活用すれば、顧客一人ひとりとの関係を強化し顧客生涯価値(LTV)の向上も期待できます。
店舗とECの在庫や注文情報をまとめて管理するシステムです。
リアルタイムで在庫状況を把握する在庫管理システムや、複数ECモールの注文情報を一元管理するOMS(注文管理システム)などが代表的です。
特に商品にICタグを取り付け、電波で一括読み取りするRFID技術を活用すれば、棚卸し作業の大幅な効率化も可能です。
これらは機会損失の削減とキャッシュフローの改善に貢献する、OMO戦略の基盤となる重要なツール群です。
蓄積されたデータを可視化・分析し、経営判断に役立てるツールです。
売上や顧客データをグラフなどで分かりやすく可視化するBI(ビジネスインテリジェンス)ツールや、オンライン・オフラインのあらゆる顧客データを統合・分析し顧客理解を深めるCDP(顧客データ基盤)などがあります。
専門家でなくても直感的に操作できるツールも増えており、現場レベルでのデータ活用を促進します。これにより、データドリブンな意思決定を組織全体で推進することを支援します。
この記事では、小売DXの成功事例から具体的な進め方、役立つツールまでを網羅的に解説しました。
重要なのは他社の成功事例をそのまま真似るのではなく、まず自社が抱える最も大きな課題は何かを明確にすることです。人手不足が深刻なのか、顧客満足度の向上が急務なのか、それによって打つべき施策は大きく異なります。
DXはそれ自体が目的ではなく、あくまで課題を解決し企業を成長させるための手段に過ぎません。
まずはこの記事で得た知識をヒントに自社の現状を冷静に分析し、取り組むべき課題の優先順位を明確にすることから始めてみてください。その地道な一歩こそが、失敗しない小売DX推進の最も確実なスタートラインとなるはずです。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
