小売DXの第一歩はペーパーレス化!メリットや書類管理の課題を解説
小売

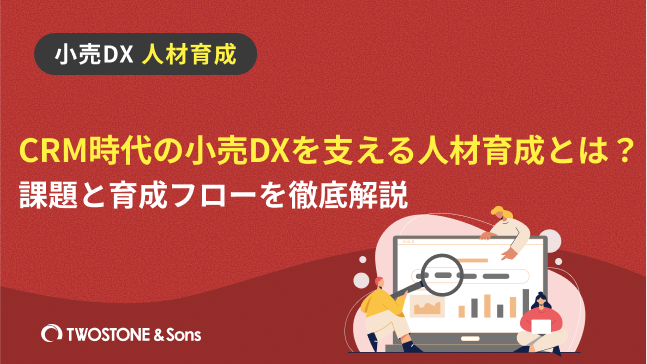
小売業のDX推進で「人材育成」の壁に悩んでいませんか?この記事を読めば、DX人材が育たない原因である3つの壁から、育成すべき人材タイプ、具体的な4つの育成ステップまでがわかります。成功事例や補助金活用法も紹介しており、明日から使える実践的なヒントが満載です。


・6万名以上のエンジニアネットワークを活用して課題を解決※
・貴社のDX戦略立案から実行・開発までワンストップで支援可能
※エンジニア数は2026年8月期 第1四半期決算説明資料に基づきます。
小売業のDX推進が「人材育成」の壁に直面することは、決して珍しいことではありません。「DX推進と言われても、何から手をつければ良いかわからない」「デジタルツールを導入したものの、現場で使いこなせる人材がいない」といった課題を、多くの担当者が抱えています。
この記事では、小売DXにおける人材育成の課題を整理し、成功に導くための具体的なステップを解説します。最後まで読めば、自社で取り組むべきことの全体像が明確になり、明日から具体的な一歩を踏み出せるようになるでしょう。

なぜ、これほどまでに小売業界でDXと人材育成が重要視されているのでしょうか。その背景には、業界を取り巻く環境の大きな変化があります。このセクションでは、人材育成に取り組むべき3つの理由を解説します。
現代の消費者は、オンラインとオフラインを自由に行き来する購買行動が当たり前になっています。このような行動様式は「OMO(Online Merges with Offline)」と呼ばれ、小売業はこの変化への対応を迫られています。
顧客一人ひとりの行動履歴や購買データを分析し、パーソナライズされた体験を提供することが、顧客満足度を高める上で重要です。顧客とのあらゆる接点で最適なアプローチをするためには、データに基づいた戦略が欠かせません。そのためには、データを読み解き、具体的なマーケティング施策に落とし込む企画力を持った人材の育成が不可欠といえるでしょう。
少子高齢化を背景とした人手不足は、小売業界にとって大きな課題です。この課題を解決するため、多くの企業がセルフレジや自動発注システムといったデジタルツールを導入しています。
しかし、単にツールを導入するだけでは不十分です。大切なのは、導入したツールを全従業員がスムーズに使いこなし、それによって生まれた時間やデータをより付加価値の高い業務に活かすことです。ツールを使いこなすスキルがなければ、せっかくの投資も効果を発揮しきれないのです。データを読み解き業務改善につなげる思考力を持った人材を育てることが、持続的に成長するための鍵となります。
POSデータやECサイトの行動履歴といったデータは、今や企業の競争力を左右する貴重な経営資源です。これらのデータを正しく分析・活用することで、これまで見過ごされてきた顧客の隠れたニーズを発見したり、精度の高い需要予測によって欠品などを削減したりすることが可能になります。
これまでの勘や経験にデータという客観的な裏付けを加えることで、施策の精度や再現性を高めることができます。データという事実に基づいて新たな顧客体験を創出し、ビジネスを成長させていくためには、データを活用できる人材の育成が欠かせないのです。
多くの企業が人材育成の重要性を理解しながらも、計画通りに進まないのが実情です。そこには、小売業界ならではの課題が潜んでいます。このセクションでは、多くの担当者が直面する3つの壁について解説します。
最初の壁として、自社に必要な「DX人材」がどのような役割を担い、どんなスキルを持つべきかが明確に定義できていないケースが挙げられます。「DX人材」という言葉は非常に幅広く、様々な階層の人材を含んでいます。
この定義が曖昧なままでは、育成のゴールが定まらず、「誰に」「何を」教えれば良いのかという育成計画の根幹が揺らいでしまいます。結果として、研修が現場のニーズと合わずに育成効果を正しく測定できないといった事態に陥りがちです。まずは自社のDX戦略と照らし合わせ、必要な人材像を具体的に定義することが、効果的な育成の第一歩となります。
DXで求められるデータ分析などのスキルは、従来の小売業における人材育成では中心的なテーマではありませんでした。そのため、これらの専門スキルを教えられる指導者が社内にいなかったり、育成のノウハウそのものが蓄積されていなかったりする企業が少なくありません。
人事部やDX推進担当者が手探りの状態で育成プランを立てなければならず、外部の研修サービスを利用しようとしても、自社に合ったものを見極めることは容易ではありません。結果として育成計画が場当たり的になり、体系的なスキルアップにつながらないという課題に直面するのです。
新しいツールや業務プロセスの導入は、現場の従業員にとって大きな変化を伴います。長年慣れ親しんだやり方を変えることに対して、「新しいことを覚えるのが大変そう」といった心理的な抵抗感が生まれることは、決して珍しいことではありません。
また、「DXは本部や一部の専門部署がやること」という他人事の意識が広がっていると、従業員の学習意欲は高まりにくいでしょう。この心理的な壁があるままでは、導入したツールが結局使われなくなってしまうことも考えられます。そのため、全社的な協力体制を築き、従業員一人ひとりがDXを「自分ごと」として捉えられるような働きかけが重要です。
「DX人材」をひと括りにせず、社内での役割に応じて分類することで、育成の方向性がより具体的になります。このセクションでは、育成すべき人材を大きく3つのタイプに分け、それぞれに求められるスキルを説明します。
このタイプは、DXを通じて会社のビジネスモデルそのものを変革し、全社的な取り組みを力強く牽引する役割です。主に経営層や各部門の責任者クラスが、この役割を担うことになります。
求められるのは、業界動向や最新技術を理解して自社のビジネスの未来像を描くビジネス構想力です。さらに、その構想を具体的な戦略に落とし込み、投資対効果を経営陣に説明する責任も伴います。また、DXプロジェクト全体を管理するマネジメントスキルや、多くの関係者を巻き込んで協力を得るための優れたリーダーシップが求められます。
このタイプは、データ分析やデジタルマーケティングといった専門スキルを駆使して、具体的なDX施策を実行していく専門家です。情報システム部やマーケティング部などの実務担当者がこれにあたります。リーダーが描いた戦略を、具体的な施策に落とし込む「実行部隊」としての役割が期待されます。
POSデータなどを分析してビジネスに役立つ知見を見つけ出すデータ分析スキルはもちろん、その分析結果をBIツールなどでわかりやすく可視化し、現場に伝える能力も重要です。Web広告やSNSなどを活用するデジタルマーケティングスキルも、これからの小売業に不可欠な専門性といえるでしょう。
DXを全社的な取り組みにするためには、特定の専門家だけでなく、全従業員のデジタルスキルを底上げすることが大切です。このスキルアップこそが、いわゆる「DXの土台」を支えることになります。
個人情報の取り扱いやセキュリティ対策など、安全にデジタルツールを利用するための基本的な知識は、顧客からの信頼を守る上で必須です。また、日々の業務で発生するデータを正しく入力し、そのデータがどのように活用されるのかを理解することも求められます。ビジネスチャットなどのコミュニケーションツールを円滑に使いこなして情報共有のスピードを上げることも、組織全体の生産性を高める上で重要なスキルです。

育成すべき人材像が明確になったら、具体的な育成計画を立てて実行に移します。このセクションでは、場当たり的にならず計画的に人材育成を成功させるための4つのステップを紹介します。
人材育成の最初のステップは、自社の「現在地」を正確に把握することです。まず、自社のDX戦略に必要な人材像とスキルを体系的に整理した「スキルマップ」を作成します。これは、育成という航海における「地図」の役割を果たすものです。
次に、従業員へのアンケートなどを通じて現状のスキルレベルを可視化します。この理想のスキルマップと現実を照らし合わせることで、「どのスキルが」「どれくらい不足しているのか」というギャップが明確になり、育成すべき優先課題を客観的に判断できるようになります。
現状分析で明らかになった課題に基づき、具体的で測定可能な育成目標を設定します。例えば、「半年後までに全店舗の店長がBIツールを使って週次レポートを作成できる」といった、誰が見ても達成度がわかるような目標を立てることが重要です。
目標が決まったら、それを達成するための具体的な育成計画、いわゆる「育成ロードマップ」に落とし込んでいきます。このロードマップには、育成の対象者、期間や学習内容、提供方法、評価方法といった要素を具体的に盛り込みます。計画を確実に実行するためにも、現場の通常業務への負担も考慮しながら現実的なスケジュールを組むことが成功の鍵となります。
育成計画に沿って、いよいよプログラムを実行に移します。このステップで大切なのは、一つの方法に偏るのではなく、育成目標や対象者のレベルに合わせて複数の手法を最適に組み合わせることです。
例えば、体系的な知識を学ぶには集合研修やeラーニングが適しており、学んだ知識を実践で使えるスキルへと昇華させるためには、実際の業務を通じて学ぶOJTが効果的です。基礎的なデジタルリテラシーは全社員対象のeラーニングで底上げし、専門スキルは外部研修を活用、現場でのデータ活用はOJTでサポートするといった形です。それぞれの育成手法の長所を活かして組み合わせることで、学習効果を最大化することができます。
育成は「やりっぱなし」で終わらせず、その効果をきちんと測定して次の施策に活かすことが極めて重要です。研修後の理解度テストや資格取得者数の推移だけでなく、受講者へのアンケートで行動変容を測ることも有効です。
さらに、育成された人材が関わったプロジェクトの成果(売上向上、コスト削減など)を追跡し、育成が事業貢献にどうつながったかを評価することも求められます。これらの測定結果を分析し、育成計画を継続的に改善していくPDCAサイクルを回しましょう。この地道な改善の繰り返しが、組織全体のスキルを継続的に高めていく上で不可欠なプロセスです。
他社がどのように人材育成に取り組み、成功しているのかを知ることは、自社の施策を考える上で非常に有益です。このセクションでは、小売業界における人材育成の先進的な取り組みを2つ紹介します。
アスクル株式会社は、従業員の自律的なキャリア形成を支援して学び合う風土を醸成することを目的に、社内大学「ASKUL ACADEMIA」を設立しました。この取り組みは、単なるスキル研修にとどまらない点が特徴です。
テクノロジー人材の育成プログラムに加え、全社員を対象としたデータ分析講座などを提供することで、全社的に学び続ける文化を育んでいます。会社がキャリアを用意するのではなく、社員一人ひとりが自ら未来を創る力を育むことを目指している点が、これからの時代の人材育成のあり方を示唆しています。役職や部門に関わらず、誰もが主体的に学べる環境を整備したことが同社の成長を支える一つの要因となっているようです。
出典参照:アスクル、社内におけるDX人材育成のため独自の研修プログラム「ASKUL DX ACADEMY」を開校|アスクル株式会社
株式会社Regnioは、専門家でなくてもAIによるデータ活用を可能にするノーコードツールを提供しています。同社のサービスは小売業がDX人材を育成する上でのヒントを与えてくれます。
ツール導入と並行して、伴走型の支援やOJT形式でのトレーニングを提供することで、現場の担当者が実践的なスキルを習得できるようサポートしています。ツールを導入して終わりではなく、その活用が定着するまで専門家がサポートする「伴走型」の支援体制が、育成の成功率を高める上で重要なポイントです。専門家を待つのではなく、現場のスタッフが自らデータを基に考え、行動できるようになるための環境づくりは、多くの企業にとって参考になるでしょう。
出典参照:【外側からと内側からのDX】株式会社Regnioが老舗企業向けに事業変革プログラムと人材育成プログラムを開始|株式会社Regnio
自社だけで全ての人材育成を担うのは、ノウハウやリソースの面で難しい場合もあります。外部の専門的な研修サービスや、国・自治体の補助金制度を賢く活用することで、育成を効率的に進めることが可能です。
外部研修サービスは、社内に不足している専門知識や育成ノウハウを補う上で非常に有効な選択肢です。しかし、数多くのサービスの中から自社に合うものを選ぶには、いくつかのポイントを押さえる必要があります。
まず、自社で作成したスキルマップと照らし合わせ、育成目標に合致した体系的なプログラムが提供されているかを確認しましょう。その上で、自社の課題に合わせてカリキュラムをカスタマイズできるかどうかも重要な選定基準です。複数のサービスを比較検討して費用対効果を見極めながら、自社のDX推進をサポートしてくれるパートナーを見つけましょう。
DX推進のコストが課題となる場合、活用を検討したいのが国が中小企業・小規模事業者を支援する「IT導入補助金」です。この制度は企業の生産性向上を目的として、ITツールの導入にかかる経費の一部を補助するものです。
小売業においては、POSレジシステムや在庫管理ソフトなど、業務効率化に直結するツールの導入に活用できる可能性があります。特に2025年の制度ではインボイス制度への対応が重視されており、対応ソフトなどを導入する「インボイス枠」は、高い補助率が設定されているのが特徴です。補助対象となるのは事務局に登録されたITツールに限られるため、導入したいツールが対象か事前に確認することが重要です。
出典参照:IT導入補助金2025|サービス等生産性向上IT導入支援事業事務局
補助金を活用する際は、いくつか注意が必要です。最も重要な点として、多くの補助金は研修の契約や支払いを実行する前に申請し、交付決定を受ける「事前申請」が原則であることです。研修が終わってから申請しても受理されないため、計画段階で申請スケジュールを組み込んでおくことが不可欠です。
また、申請には事業計画書や経費の見積書など、様々な書類の準備が求められます。さらに、補助金は研修終了後の報告を経て支払われる「後払い」が基本であるため、研修費用は一度自社で立て替える必要がある点も理解しておきましょう。制度によって要件や申請期間は異なるため、公式サイトで常に最新の情報を確認することが大切です。

この記事では、小売DXにおける人材育成の重要性から、具体的な課題、育成ステップ、成功事例、そして活用できる外部サービスや制度までを解説しました。
DXの推進は、単に最新のデジタルツールを導入することではありません。その本質は、デジタル技術を活用してビジネスモデルや組織文化を変革し、新たな価値を創造することにあるといえます。そして、その変革の主役は、間違いなく「人」です。
今回ご紹介した内容を参考に、まずは自社の課題を整理し、育成すべき人材像を明確にすることから始めてみてはいかがでしょうか。場当たり的ではない、計画的で継続的な人材育成に取り組むことが、未来の小売業をリードしていくための確かな一歩となるでしょう。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
