小売DXの第一歩はペーパーレス化!メリットや書類管理の課題を解説
小売

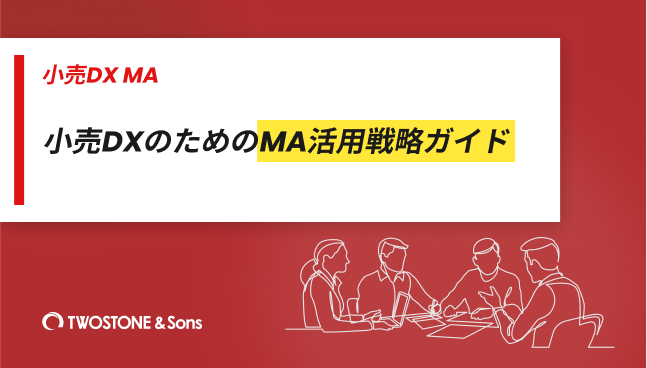
小売業の顧客データ活用にお悩みですか?この記事ではMAで散在するデータを統合し、売上向上と業務効率化を実現する方法を解説します。One-to-Oneマーケティングを叶える活用シナリオから、成功企業の事例、失敗しないツールの選定ポイントまで網羅しています。


・6万名以上のエンジニアネットワークを活用して課題を解決※
・貴社のDX戦略立案から実行・開発までワンストップで支援可能
※エンジニア数は2026年8月期 第1四半期決算説明資料に基づきます。
「店舗とECの顧客データがバラバラで、一貫したアプローチができていない」「日々のメルマガ配信やキャンペーン告知に追われ、もっと戦略的な業務に集中したい」といった課題を、小売業のマーケティング担当者として感じていませんか。
この記事では、そうした悩みを解決に導く「MA(マーケティングオートメーション)」について解説します。MAがなぜ必要なのか、具体的な機能や活用シナリオ、企業の成功事例からツールの選び方まで、分かりやすく紹介していきます。

近年の小売業界では、DX(デジタルトランスフォーメーション)を推進する一環として、MAの導入が活発化しています。それは現代の小売業が直面する特有の課題を解決する上で、MAが大きな役割を果たすためです。
多くの小売企業では店舗のPOSデータやECサイトの購買履歴、アプリの利用状況といった顧客に関する情報が、それぞれのシステムで個別に管理されている状況です。この状態では、一人の顧客が店舗とECサイトでどのような行動をとっているのか、その全体像を正確に把握することは難しいでしょう。
MAツールは、これらの異なる場所に散らばったデータを一つにまとめる役割を担います。データを一元的に管理することで、顧客一人ひとりの行動や購買の傾向を深く理解できるようになり、より精度の高いマーケティング施策を考えるための土台ができます。
顧客の価値観や購買行動が多様化している現代では、すべての人に同じメッセージを送る画一的なアプローチの効果は薄れつつあります。顧客は「自分のために」選ばれた情報や提案を期待しており、この期待に応えることが顧客満足度やLTV(顧客生涯価値)の向上に繋がるのです。
MAを活用すると、集めたデータをもとに「先月、特定の商品を購入した顧客」や「商品をカートに入れたままサイトを離れた顧客」といった細かい条件で顧客を分類できます。そして、それぞれの顧客に合ったタイミングで最適な情報を自動で届ける「One-to-Oneマーケティング」の実現が期待できます。
メールマガジンの作成や配信、キャンペーンの告知、クーポンの発行といった日々の販促業務に、多くの時間と労力を費やしているケースは少なくありません。これらの手作業による業務は、本来もっと時間をかけるべき戦略の立案や企画といった業務の時間を圧迫する一因にもなります。
MAは、こうした定型的な業務を自動化するためのツールです。あらかじめシナリオを設定しておけば、MAが自動で顧客へのアプローチを実行してくれます。これにより、マーケティング担当者は単純作業から解放され、より創造的で戦略的な業務に集中する時間を確保しやすくなるでしょう。
MAツールが小売業の課題解決に役立つことは分かりましたが、具体的にはどのような機能があるのでしょうか。このセクションでは、MAが持つ代表的な4つの機能と、それによって何が実現できるのかを説明します。
MAの基本的な機能として、あらゆる顧客接点から得られる情報を一つに集約し、管理する能力が挙げられます。具体的には店舗のPOSシステム、自社のECサイトや公式アプリ、さらにはWeb広告やSNSからの流入データまで、様々なチャネルの情報を統合することが可能です。
これにより、例えば「店舗でAという商品を購入した顧客が後日ECサイトで関連商品Bを閲覧した」といった、チャネルを横断した顧客の行動履歴を時系列で追えるようになります。このように一元化されたデータは、あらゆるマーケティング施策の精度を高めるための重要な基盤となるのです。
集約した顧客データをもとに、特定の条件で顧客をグループ分けする機能が「セグメンテーション」です。年齢や性別といった基本的な属性だけでなく、「過去3ヶ月以内に購入がない休眠顧客」や「特定カテゴリの商品を頻繁に購入する顧客」など、顧客の行動や状態に基づいた細かいセグメントを作成できます。
そして、そのセグメントごとに最適化されたメッセージを配信することが可能になります。例えば、しばらく購入のない顧客には再来店を促す特別なクーポンを、優良顧客には新商品の先行案内を送るなど、顧客の状況に合わせた丁寧なコミュニケーションが実現するでしょう。
あらかじめ設定したシナリオ(ルール)に基づいて、顧客へのアプローチを自動化する機能は、MAの大きな特徴の一つです。「もし顧客が〇〇という行動をしたら、△日後に□□というメールを送る」といった一連の流れを設計できます。
例えば、「商品をカートに入れたものの購入しなかった顧客に対し、24時間後にリマインドメールを自動で送る」といったシナリオが考えられます。また、「初回購入した顧客に対し、1週間後にお礼のメールを送り、1ヶ月後に関連商品をおすすめする」といった継続的なアプローチも可能です。これにより機会損失を防ぎながら、顧客との関係を育んでいくことが期待できます。
実行したマーケティング施策が、どれほどの効果を上げたのかを可視化することもMAの重要な機能です。メールの開封率やクリック率、Webサイトへのアクセス数、そして最終的な購入率まで、施策ごとの成果をダッシュボードなどで簡単に確認できます。
これにより勘や経験だけに頼るのではなく、データに基づいた客観的な評価と改善(PDCAサイクル)を進めやすくなります。「どのセグメントへのアプローチが効果的だったか」や「どのようなメッセージが顧客の心に響いたか」を分析し、次の施策をより良いものへと改善していくことができるのです。

MAの機能が理解できたところで、次はそれらをどのように活用すれば売上の向上に繋がるのか、小売業における具体的な4つの活用シナリオを紹介します。自社のビジネスに置き換えてイメージを膨らませてみてください。
ECサイトを運営する上で大きな課題となるのが「カゴ落ち」です。これは商品をカートに入れたものの、購入せずにサイトを離れてしまうことを指します。MAを活用することで、こうした機会損失を減らす取り組みができます。
具体的には、「カートに商品が追加されてから24時間経過しても購入に至らない」という条件をきっかけとして、リマインドメールを自動で送信するシナリオを設定します。メールにはカートに入っている商品の画像を載せて「お買い忘れはありませんか?」と優しく問いかけることで、顧客の購買意欲を再び高め、購入へと繋げることが期待できるでしょう。
顧客のLTV(顧客生涯価値)を高める上で有効な手法の一つに「クロスセル」があります。これはある商品を購入した顧客に対し、関連性の高い別の商品を提案するアプローチです。
MAでは顧客の購買履歴データをもとに、「A商品を購入した顧客」といったセグメントを作成します。そしてそのセグメントに対し、「A商品と相性の良いB商品のご案内」といった内容のメールを、購入から数日後などの適切なタイミングで自動配信します。これにより顧客一人ひとりの興味に合わせた自然な形で、追加の購入を促すことが可能になります。
企業の売上は、一部の優良顧客によって支えられていることも少なくありません。MAはこうした優良顧客を特定し、さらにファンになってもらうための特別なアプローチにも活用できます。
例えば、「年間購入金額が10万円以上」といった条件で優良顧客セグメントを作成します。そして、その顧客だけに「限定セールの先行案内」や「シークレットイベントへの招待」といった特別な情報を提供します。「自分は大切にされている」という体験は、顧客のロイヤルティを高め、長期的な関係を築く上で重要な要素となるでしょう。
OMO(Online Merges with Offline)、つまりオンラインとオフライン(実店舗)を融合させることは、現代の小売業における重要な戦略です。MAはこのOMO施策を推進する上でも役立ちます。
例えばECサイトで特定の商品ページを何度も見ている顧客に対し、「お探しの商品は、お近くの〇〇店に在庫がございます」といった内容のメールやアプリ通知を送ります。さらに、「今なら店舗で使える10%OFFクーポンをプレゼント」といった特典をつけることで、オンラインでの興味を実店舗への来店動機へと転換させ、店舗全体の売上向上に貢献することが期待できます。
このセクションでは、実際にMAツールを導入し、成果を上げている企業の具体的な取り組みを紹介します。他社の事例から、自社で活用する際のヒントを見つけていきましょう。
紳士服などを展開する株式会社AOKIは、顧客一人ひとりのニーズに応える商品開発やサービス提供に力を入れています。例えば、顧客の声をもとに開発された大きいサイズのビジネスウェア「SizeMAX」シリーズは、顧客理解を起点とした取り組みの一例です。
こうした顧客中心の考え方は、MA活用におけるOne-to-Oneマーケティングの思想と通じます。MAを導入することで、顧客の購買データやWebサイトでの行動履歴に基づき、個々の顧客に合った商品情報やスタイリング提案を自動で届けることが可能になります。これにより顧客満足度を高め、より深い関係性を築いていくことが期待できるでしょう。
出典参照:株式会社AOKIが展開するビジネス・ビジカジ専門「ORIHICA(オリヒカ)」にMAツール『R∞(アール・エイト)』の提供を開始|株式会社AOKI
株式会社丸井グループは顧客体験の向上を目指し、デジタル技術を活用した新しい取り組みを積極的に進めています。その一環としてECサイト「マルイウェブチャネル」において、AIと3DCGを活用したバーチャル試着サービスを導入しました。
このようなオンラインでの新しい購買体験の提供は、顧客の利便性を高めるだけでなく、貴重な顧客データを収集する機会にもなります。MAと連携させることで、バーチャル試着を体験した顧客に対し関連商品のおすすめや店舗での試着を促すクーポンを送るなど、オンラインからオフラインへのスムーズな連携が考えられます。デジタル接点を活用して顧客との繋がりを深める、先進的な事例といえるでしょう。
出典参照:スーパーマーケット マルイとDearOne、限定クーポンやイベント情報をタイムリーに配信「マルイ公式アプリ」を共同開発|株式会社マルイ
スキンケアブランド「N organic」などを展開する株式会社シロクは、顧客のLTV(顧客生涯価値)向上を目的として、株式会社Macbee Planetが提供するMAツール「b-dash」を導入しました。導入以前はデータが分散し、施策が属人化しているといった課題を抱えていました。
MAの導入によりこれまで別々に管理されていた顧客データや行動データを統合し、一元的に分析できる基盤を構築しました。これによりデータに基づいた顧客理解を深め、一人ひとりの顧客に合わせたコミュニケーションの実現を目指しています。将来的には顧客のファン化を促進し、LTVを最大化させるための施策を展開していく計画です。
出典参照:シロク、コスメブランド事業でBrazeを導入|株式会社シロク
MA導入を成功させるには、自社のビジネスに合ったツールを選ぶことが重要です。このセクションでは、小売業がMAツールを選ぶ際に特に考慮すべき4つのポイントを解説します。
まず大切なのが、現在利用している店舗のPOSシステムやECカートシステムとスムーズに連携できるかという点です。ここが連携できなければ、顧客データを一元管理するというMA導入の大きな目的を達成することが難しくなります。特に独自にカスタマイズしたシステムを利用している場合は、個別に対応可能かどうかの確認が不可欠です。
導入を検討しているMAツールが、自社のシステムに対応しているかを事前に確認することが求められます。公式サイトで連携可能なシステムの一覧をチェックしたり、提供会社に直接問い合わせたりして、確実な情報を得ることが大切です。スムーズなデータ連携は、導入後の運用効率にも大きく影響します。
MAツールには、幅広い業種で使える汎用的なものから、特定の業種に特化したものまで様々です。小売業で活用するのであれば、店舗での利用を想定した機能や、ECサイトとの連携を前提とした機能が充実しているツールを選ぶと良いでしょう。これらの機能はオンラインとオフラインをシームレスに繋ぎ、顧客体験を向上させる上で大きな役割を果たします。
例えば店舗スタッフが顧客情報をその場で確認できる機能や、ECの在庫データと連携して「再入荷通知」を自動化する機能などが挙げられます。これらの機能が標準で備わっているか、あるいはオプションで追加できるかを確認することで、より自社の業務に合ったツール選びが可能になります。
「MAを導入したものの、専門知識がなくて使いこなせない」という状況は、避けたい失敗の一つです。特にMAを初めて導入する場合には、ツールの提供会社によるサポート体制が非常に重要になります。自社の担当者のITスキルレベルに合わせて、どの程度のサポートが必要かを事前に検討しておくことも大切です。
ツールの基本的な使い方を教えてくれる初期設定のサポートはもちろん、導入目的を達成するためのシナリオ設計を一緒に考えてくれるコンサルティングなど、伴走型のサポートを提供してくれるかを確認しましょう。手厚いサポートがあることで、導入後の成果に繋がりやすくなることが期待できます。
MAツールの費用は、初期費用と月額費用で構成されることが一般的です。月額費用は、管理する顧客データの数やメールの配信数によって変動する料金体系が多く見られます。月額費用以外にオプション料金が発生する場合もあるため、トータルコストを把握しておくことが重要です。
また、導入にかかる期間も考慮に入れる必要があります。ツールの契約から初期設定、データ連携、シナリオ設計を経て本格的な運用が始まるまで、一般的には数ヶ月程度の期間を見込むと良いでしょう。すぐに成果が出るものではないことを理解し、中長期的な視点で計画を立てることが成功の鍵となります。

MAツールの導入は、計画的に進めることが成功に繋がります。このセクションでは、導入を決定してから運用を開始するまでの具体的な4つのステップを説明します。
最初に、「何のためにMAを導入するのか」という目的を明確化します。ツール導入が目的化すると、方向性が定まらず成果に繋がりにくくなります。「店舗とECの顧客データを統合してLTVを向上させたい」「販促業務を自動化して業務効率を上げたい」など、自社の具体的な課題と結びつけて目的を設定しましょう。目的を明確にすれば、部署間の認識のズレを防ぎ、プロジェクトを円滑に進められます。
次に、目的の達成度を測るためのKPI(重要業績評価指標)も具体的に定めます。「メール経由の売上を月間〇〇円にする」「顧客単価を前年比で10%向上させる」といった、客観的な数値目標を設定することが望ましいです。この目的とKPIは、後のツール選定やシナリオ設計において重要な判断基準となります。
目的とKPIが明確になったら、それを実現できるMAツールを選定します。前の章で解説した「機能」「料金」「サポート体制」「連携性」といったポイントをもとに、複数のツールをリストアップし、比較検討を進めましょう。各ツールの特徴を比較表にまとめると、客観的な判断がしやすくなります。
公式サイトの情報収集だけでなく、デモ画面の操作も有効です。デモにはマーケティング担当者だけでなく現場スタッフも参加し、実際の業務で使いやすいかどうかを確認することをおすすめします。また、自社と似た課題を持つ企業の導入事例を参考にすることも、最適なツールを見つけるための重要なヒントになります。複数の視点からツールを評価し、自社にとって最良の選択をしましょう。
導入するツールが決まったら、社内の運用体制を整えます。「導入後に誰も使わない」という事態を防ぐため、このステップは重要です。MA運用は複数部署にまたがることが多いため、部署間の連携が欠かせません。
まず、プロジェクト全体を推進する主担当者を決めます。その上で、「シナリオを設計する人」「コンテンツを作成する人」「効果を分析する人」といった具体的な役割分担を明確にしましょう。役割を明確にすることで、責任の所在がはっきりし、スムーズな運用に繋がります。定期的なミーティングで情報を共有し、円滑なコミュニケーションの仕組みを築くことが、MAを組織全体で活用していくための成功の鍵です。
いよいよMAの具体的な設定に入ります。最初から完璧なシナリオを目指すのではなく、スモールスタートを意識することが成功のコツです。「カゴ落ち対策」や「初回購入者フォロー」など、成果を実感しやすく、かつ重要な施策から始めるのが良いでしょう。
シナリオ設計では、顧客視点で最適な情報提供のタイミングを考えることが大切です。施策を実行した後は、必ず効果測定を行いましょう。MAは導入後も効果測定と改善を繰り返しながら「育てていく」ツールです。開封率やクリック率などのデータを確認し、「なぜこの結果になったのか」を分析します。A/Bテストなどで継続的に改善し、MAの効果を最大限に引き出しましょう。
ここまで、小売DXにおけるMAの重要性から具体的な活用法、導入ステップまでを解説してきました。MAの導入は、単に新しいツールを一つ加えること以上の意味を持ちます。
それはこれまで分断されていた顧客データを繋ぎ、勘や経験に頼りがちだったマーケティングを、データに基づいたアプローチへと進化させることに他なりません。MAは、理想的な顧客との関係構築を実現するための心強いパートナーとなり得ます。
この記事が、MA導入への第一歩を踏み出し、自社のマーケティングを次のステージへと引き上げるきっかけとなれば幸いです。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
