小売DXの第一歩はペーパーレス化!メリットや書類管理の課題を解説
小売

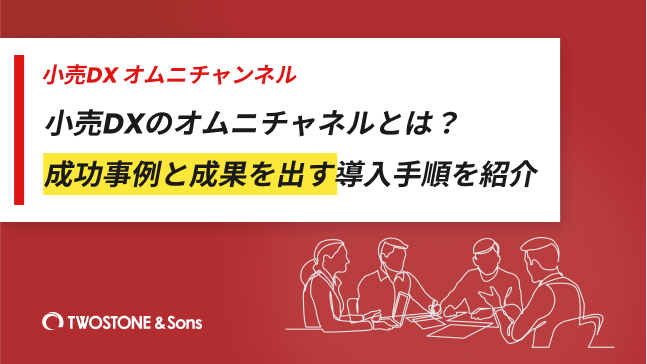
店舗とECの連携にお悩みの小売DX担当者様へ。本記事では、オムニチャネルの基本からメリット・課題、ユニクロ等の成功事例、具体的な導入ステップまでを網羅的に解説します。顧客体験を向上させ、成果を出すためのヒントがわかります。


・6万名以上のエンジニアネットワークを活用して課題を解決※
・貴社のDX戦略立案から実行・開発までワンストップで支援可能
※エンジニア数は2026年8月期 第1四半期決算説明資料に基づきます。
店舗とECサイトの連携がうまくいかず、顧客情報や在庫データが分断されていることに、課題を感じている小売企業の担当者の方は多いのではないでしょうか。顧客の購買行動が多様化する現代において、オンラインとオフラインの垣根を越えた一貫性のある顧客体験の提供は、企業の成長に欠かせない要素です。
その解決策として注目されるのが「オムニチャネル」という戦略です。この記事では小売業界でDXを推進する担当者の方に向けて、オムニチャネルの基本から、導入のメリットや課題、先進企業の成功事例、そして自社で成果を出すための具体的な導入手順までを分かりやすく解説していきます。

オムニチャネル戦略を成功させるためには、まずその基本的な概念を正しく理解することが第一歩です。このセクションでは、オムニチャネルが何を指し、しばしば混同される他の用語とどう違うのかを明確にしていきます。この基礎的な知識が、今後の戦略立案の確かな土台となるでしょう。
オムニチャネルとは、実店舗やECサイト、スマートフォンアプリ、SNSといった、企業が持つあらゆる顧客接点(チャネル)を緊密に連携させる戦略を指します。「オムニ(Omni)」は「すべての」という意味を持ち、その名の通り、すべてのチャネルを統合して顧客にアプローチします。
その最大の目的は、顧客がチャネルの違いを意識することなく、いつでもどこでも一貫性のあるサービスを受けられるシームレスな購買体験を提供することにあります。例えば、店舗で下見した商品を後からECサイトで購入したり、ECサイトで注文した商品を最寄りの店舗で受け取ったりといった行動を、ストレスなく実現することを目指します。
こうした優れた顧客体験は顧客満足度を高め、最終的にはブランドへの信頼と愛着を育み、長期的な関係性を築くことにつながります。
オムニチャネルとしばしば混同される用語に、「マルチチャネル」や「OMO」があります。それぞれの戦略は目指す方向性が異なるため、違いを理解しておくことが大切です。
マルチチャネルは、企業が複数のチャネルを持っている状態そのものを指します。しかし各チャネルは独立して運営されており、在庫情報や顧客データは連携されていません。
一方、OMO(Online Merges with Offline)は、オンラインとオフラインの融合を意味し、特にオンラインでの体験を軸に、オフラインである実店舗での体験価値を高めることに重きを置く考え方です。
オムニチャネルは、これらの概念を発展させ、企業側の視点ではなく「顧客視点」ですべてのチャネルが途切れなくつながっている状態を目指す、より包括的な戦略といえるでしょう。
オムニチャネルを導入することで、企業は具体的にどのような価値を得られるのでしょうか。このセクションでは代表的な3つのメリットについて、詳しく見ていきましょう。
オムニチャネルがもたらす最大のメリットは、顧客満足度の向上にあります。顧客は自身のライフスタイルに合わせて「ECサイトで注文して、仕事帰りに店舗で受け取る」といったように、時間や場所に縛られない自由な購買が可能になります。
このようなストレスのないシームレスな購買体験は、ブランドに対する信頼感や愛着を深めることにつながります。一度高い満足度を体験した顧客は、継続的に自社の商品やサービスを選んでくれる優良顧客になる可能性が高まります。
その結果、一人の顧客が取引期間中にもたらす利益の総額、いわゆるLTV(顧客生涯価値)の最大化が期待できるのです。
「店舗に行ったのに欲しい商品の在庫がなかった」「ECサイトでは売り切れだった」という経験は、顧客をがっかりさせるだけでなく、企業にとっては大きな販売機会の損失に直結します。
オムニチャネルではすべてのチャネルの在庫情報をリアルタイムで一元管理するため、こうした機会損失を大幅に減らすことが可能です。例えば顧客が訪れた店舗に在庫がなくても、近隣の店舗やECサイトの倉庫から商品を取り寄せて販売するといった対応ができます。
これは会社全体の在庫を有効に活用し、販売機会を逃すことなく売上を最大化することに貢献します。
これまでは店舗とECサイトで別々に管理されていた顧客の行動データや購買履歴を、オムニチャネルでは一つに統合できます。これにより顧客一人ひとりをより深く、立体的に理解することが可能になります。
一元化された豊富な顧客データを分析することで、「店舗で特定の商品をよく見ている顧客に対して後日アプリで関連商品のクーポンを配信する」といった、チャネルを横断したきめ細やかなアプローチが実現します。
このように、データに基づいたパーソナライズされたマーケティング施策を展開することで、顧客とのエンゲージメントを高め、購買率の向上に大きく貢献するでしょう。
多くのメリットがある一方で、オムニチャネルの導入は決して簡単な道のりではありません。このセクションでは、多くの企業が直面する3つの代表的な壁について解説します。
オムニチャネルを実現するためには、顧客データや在庫情報を一元管理するためのシステム基盤が不可欠です。CDP(顧客データ基盤)や統合在庫管理システム、ECと店舗を連携させるPOSシステムなど、新たなシステムを導入するには相応の初期投資が必要となります。
また、システムは導入して終わりではなく、その後の保守・運用にも継続的なコストが発生します。これらの投資に見合うだけの効果が得られるのか、事前に慎重な費用対効果の検証が求められるでしょう。計画段階で、現実的な予算と期待されるリターンを明確にしておくことが重要です。
オムニチャネル導入における障壁は、技術的な問題よりも組織的な問題であるケースが少なくありません。従来実店舗部門とEC部門は、それぞれが独立した売上目標や評価制度を持っていることが多く、協力体制を築きにくい構造になっていることがあります。
「ECサイトの売上が伸びると、店舗の売上が落ちるのではないか」といった考え方が根強いと、部門間の連携は円滑に進みません。この壁を乗り越えるには、経営層の強いリーダーシップのもとに全社共通の目標を設定し、組織の縦割りを打破する意識改革や評価制度の見直しが求められます。
オムニチャネルを効果的に推進するには、従来の店舗運営やEC運営のスキルだけでは十分とはいえません。全チャネルから集まる膨大なデータを分析するスキルや、その分析結果をもとにマーケティング施策を企画・実行する能力が求められます。
さらに、各部門と円滑に連携するためのコミュニケーション能力など、複合的なスキルを持つ人材の存在がプロジェクトの成否を分けます。しかしこうした人材は市場全体で不足しており、確保や育成が大きな課題となるでしょう。外部の専門家の協力を仰いだり、社内で計画的に人材を育成したりする視点が必要です。
オムニチャネル戦略を導入しても、現場での運用が定着しなければ期待する成果は得られません。システムを導入するだけでは不十分であり、実際に業務を担当するスタッフが無理なく運用できる設計が求められます。
定着の鍵となるのは、明確な役割分担と効率的な業務フローの確立、そして属人化しない仕組みづくりです。店舗とEC、本部の3者が連携しながら、それぞれの負担を適切に配分していく必要があります。
ここからは、現場に定着する運用設計の具体的なポイントを3つの視点から解説していきます。
オムニチャネルでは、店舗とECの境界が曖昧になるため、誰が何を担当するのかを明確にしておかなければ、現場で混乱が生じてしまいます。
まず、在庫管理の責任範囲を定めましょう。店舗の在庫をECでも販売する場合、在庫の引き当てルールや更新頻度を決めておく必要があります。例えば、店舗での接客中に商品を確保する際の優先順位や、ECからの注文が入ったときの対応手順などを具体的に定めておくことが重要です。
次に、顧客対応の役割分担も整理します。ECで購入した商品を店舗で受け取る際の接客対応や、店舗で確認した商品を後日ECで購入したいという要望への対応など、チャネルをまたぐ顧客接点では、どちらが主体となって対応するのかを決めておきましょう。
オムニチャネル対応によって、店舗スタッフの業務が増えてしまうと、接客品質の低下や離職率の上昇につながりかねません。そのため、新しい業務を追加する際には、既存の業務フロー全体を見直して効率化を図る必要があります。
まず、重複している作業を洗い出しましょう。例えば、店舗とECで別々に在庫を管理していた場合、システム統合によって二重入力が不要になります。また、顧客情報も一元管理することで、チャネルごとに異なる顧客台帳を更新する手間を省けます。
次に、業務の自動化を検討します。ECからの注文通知を自動で店舗に送る仕組みや、在庫の引き当てを自動で行うシステムを導入すれば、手作業での確認や連絡が不要になるでしょう。ただし、自動化しすぎると現場の状況が見えなくなる恐れもあるため、重要な判断が必要な部分は人の手を残しておくバランス感覚も求められます。
オムニチャネル運用が特定のスタッフのスキルや経験に依存してしまうと、その人が異動や退職した際に業務が回らなくなってしまいます。誰でも対応できる標準化された仕組みを構築することが、長期的な定着には欠かせません。
まず、業務マニュアルを整備しましょう。オムニチャネル特有の業務について、手順を明文化しておくことで、新人スタッフでも迷わず対応できるようになります。マニュアルは文字だけでなく、画面のキャプチャや動画を活用すると理解しやすくなるでしょう。また、想定されるトラブルとその対処法もあらかじめ記載しておくと、現場の不安を軽減できます。
次に、定期的な研修とナレッジ共有の場を設けます。成功事例や失敗事例を現場間で共有することで、組織全体のスキルが底上げされていきます。月に1回程度、店舗やEC担当者が集まって課題や改善案を話し合う場を設けるのも効果的です。

このセクションでは、実際にオムニチャネル戦略で大きな成果を上げている企業の事例を2つ紹介します。先進企業がどのような課題を持ち、どのように乗り越えてきたのかを知ることは、自社で施策を検討する際の大きなヒントになるはずです。
ユニクロは公式アプリを顧客との重要な接点と位置づけ、オンラインとオフラインの体験を融合させる戦略で成果を上げています。その施策の一つが、2021年10月から開始された「ORDER & PAY」です。
このサービスは来店した顧客が店舗に在庫のない商品を、その場で店舗のレジを通じてECサイトから注文・決済できる仕組みです。顧客は後日指定の場所で商品を受け取ることができ、「店舗に行ったのに欲しいものが手に入らない」という体験をなくすことに貢献しています。
このように、アプリを軸として店舗とECサイトの垣根を取り払い、顧客にとって最も便利な購買方法を提供することで、ユニクロは高い顧客満足度を実現しています。
出典参照:三井ショッピングパーク公式通販サイト「&mall(アンドモール)」にユニクロも参加 店舗在庫活用型ECの特長を活かし、オムニチャネル化をさらに推進|株式会社 ファーストリテイリング
家具・インテリア業界のニトリも、オムニチャネル戦略に早期から取り組み、顧客の利便性を高めています。特に特徴的なのが、公式アプリ「ニトリアプリ」を活用した「手ぶらdeショッピング」です。
この機能を使うと、顧客は店舗で気に入った商品のバーコードをアプリでスキャンするだけで、簡単にECサイトのカートに追加できます。これにより、特に持ち運びが大変な大型家具などを検討する際に、その場で商品を持ち帰る必要がなくなります。
顧客は自宅に帰ってからゆっくりと購入を検討し、決済することが可能です。店舗をショールームのように活用しながら、購入はECサイトで行うという現代の購買スタイルに対応し、販売機会の損失を防ぐ優れた仕組みといえるでしょう。
出典参照:ニトリが「Repro App」を導入し、アプリ会員向けのオムニチャネル戦略をさらに強化|株式会社ニトリ
実際にオムニチャネルを導入するには、どのような手順で進めればよいのでしょうか。このセクションでは、プロジェクトを成功に導くための具体的な4つのステップを解説します。
最初に行うべき最も重要なことは、「何のためにオムニチャネルを導入するのか」という目的と、「それによって顧客にどのような価値を提供したいのか」を明確に定義することです。「競合がやっているから」といった曖昧な理由で始めると、プロジェクトの軸がぶれてしまい、後の判断に一貫性がなくなってしまいます。「在庫の偏りをなくして機会損失を5%削減したい」「店舗とECの顧客情報を統合し、リピート率を10%向上させたい」など、自社の具体的な課題に基づいた測定可能なゴールを設定することが大切です。
この目的は経営層から現場スタッフまで全社で共有し、全員が同じ方向を向いて進むための北極星となります。この目的が明確であればこそ、後のシステム選定や組織体制づくりにおいて、数ある選択肢の中から最適なものを選べるようになるのです。
次に、設定した目的を達成するために、顧客の行動を可視化する「カスタマージャーニーマップ」を作成します。これは顧客が商品を認知してから購入し、リピートするまでの一連のプロセスにおける思考や感情、行動を地図のように描き出すものです。まず具体的な顧客像(ペルソナ)を設定し、その顧客がどのようなタッチポイント(店舗、ECサイト、アプリ、SNSなど)で自社と接点を持つのかを洗い出します。そして、各接点において顧客が「何を考え、どう感じ、どう行動するのか」を想像し、「どこに不便や不満を感じているのか(ペインポイント)」を特定していきます。
例えば、「店舗で在庫切れだった時、顧客はがっかりして離脱する」という課題が見つかれば、「その場でEC在庫を確認し、自宅配送を提案する」といった具体的な改善策のヒントが得られます。このマップが、後の施策の優先順位付けやシステム要件定義の土台となります。
カスタマージャーニーマップで見えてきた課題を解決するために、それを支えるシステム基盤と、実行部隊となる組織体制を構築します。優れたシステムがあっても、それを使いこなす組織がなければ意味がなく、逆もまた然りです。技術と組織は、プロジェクトを推進する両輪と考えることが重要になります。
システム面では、顧客データや在庫データを一元管理できるCDPや統合在庫管理システム、ECと連携可能なPOSシステムなどを、自社の目的や既存システムとの連携性を考慮して選定・導入します。
組織面では店舗運営、EC、マーケティング、情報システムなど、各部門から担当者を集めた部門横断的なプロジェクトチームを発足させることが成功の鍵を握ります。特に部門間の利害を調整し、プロジェクト全体を牽引する専任のリーダーを置くことが、円滑な推進には欠かせません。
準備が整ったら、いよいよ施策を実行に移します。ただし、最初から全店舗で大規模な改革を目指すのではなく、まずは特定の店舗や商品に限定して小さく始める「スモールスタート」が賢明です。これによりリスクを最小限に抑えつつ、効果を検証して運用上の課題を洗い出せます。
例えば「ECで購入した商品の店舗受け取りサービス」など、インパクトが大きく実現可能性の高い施策から着手しましょう。そして、「店舗受け取り利用率」や「クロスユース率」といった指標(KPI)を定点観測し、得られたデータや顧客からのアンケート、スタッフへのヒアリングといったフィードバックをもとに、高速でPDCAサイクル(計画・実行・評価・改善)を回していきます。オムニチャネルは一度きりのプロジェクトではなく、顧客の変化に合わせて改善を続ける継続的な活動なのです。
オムニチャネルという壮大な戦略を裏側で支えているのは、強力なITシステムです。これらのシステムが有機的に連携することで、初めてシームレスな顧客体験が実現します。このセクションではその中核となる3つの必須システムについて、それぞれの役割を解説します。
CDP(カスタマーデータプラットフォーム)やCRM(顧客関係管理)は、オムニチャネルの心臓部ともいえる重要なシステムです。これらのシステムは店舗のPOSデータ、ECサイトの購買履歴、アプリの行動ログといった、あらゆるチャネルから収集される顧客データを統合し、一人の顧客として管理する役割を担います。
これまでバラバラだった情報が一つにまとまることで、「誰が、いつ、どこで、何を購入したか」という詳細な顧客像が浮かび上がります。この深い顧客理解こそが、一人ひとりに合わせた最適なアプローチを可能にし、効果的なマーケティング施策の基盤となるのです。
POS(販売時点情報管理)システムは、もはや単なる会計を行うためのレジ機能にとどまりません。現代のPOSシステムは、店舗とECサイトのデータを繋ぐハブとしての役割を果たします。
店舗での販売情報が会計と同時にリアルタイムで基幹システムに連携されることで、ECサイトの在庫表示も常に最新の状態に保たれます。また、顧客情報と購買情報を紐づけることで、店舗での購入履歴も顧客データとして蓄積することが可能です。このリアルタイムなデータ連携が、チャネルを横断したサービスを実現する上で不可欠な要素となります。
すべてのチャネルの在庫情報をリアルタイムで一元管理する在庫管理システムも、オムニチャネルの成功に欠かせない基盤です。このシステムにより、ECサイトの倉庫にある在庫、各店舗にある在庫、さらには移動中の在庫まで、会社が持つすべての在庫状況を正確に把握できます。
在庫情報が一元化されることで、「ECサイトで注文した商品を店舗で受け取る」サービスや、「来店した店舗に在庫がなくても他店舗から取り寄せる」といった柔軟な対応が可能になります。これにより販売機会の損失を最小限に抑え、顧客の満足度を高められるのです。

本記事では小売DXの中核となるオムニチャネルについて、基本から導入手順まで解説しました。
オムニチャネルは単なるシステム導入ではなく、「顧客を第一に考える」という思想に基づき、企業活動を変革する経営戦略です。導入には課題も伴いますが、その先には顧客満足度の向上と企業の持続的な成長が待っています。
まずは自社の現状を見つめ、「最高の顧客体験とは何か」を考えることから始めてみてください。その一歩が、次世代の小売を創出する礎となるでしょう。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
