小売DXの第一歩はペーパーレス化!メリットや書類管理の課題を解説
小売

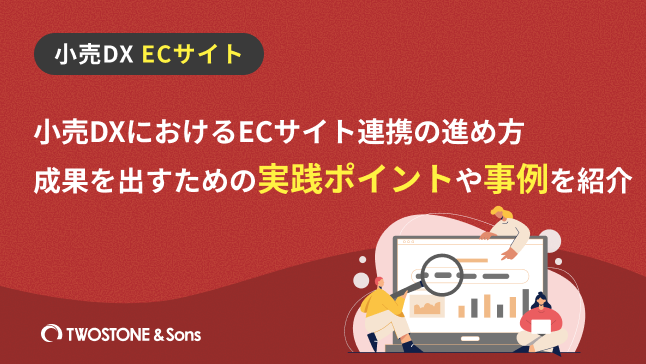
店舗とECの在庫・顧客情報が分断されていませんか?小売DXの第一歩「ECサイト連携」について、メリットや具体的な方式を解説。ユニクロなどの成功事例から、失敗しないシステムの選び方、導入の進め方まで。DX推進担当者が知りたい情報を凝縮しました。


・6万名以上のエンジニアネットワークを活用して課題を解決※
・貴社のDX戦略立案から実行・開発までワンストップで支援可能
※エンジニア数は2026年8月期 第1四半期決算説明資料に基づきます。
「実店舗とECサイトで在庫が合わない」「顧客データが分散していて活用できない」といった課題は、多くの小売業が抱える共通の悩みです。この状況を打破する鍵が「ECサイト連携」にあります。
ECサイト連携は店舗とオンラインで別々に動いていた情報を一つに統合し、業務効率を向上させながら、顧客一人ひとりへのサービス品質を高めるための重要な戦略です。
本記事では、ECサイト連携がもたらす価値から具体的な実現方法、成功事例、導入のステップまでを詳しく解説していきます。

ECサイト連携は、企業の成長を後押しする重要な一手です。経済産業省の調査でも確認できるように、EC市場は拡大を続けています。
この成長市場で勝ち抜くために、店舗とECの情報を繋ぐことで得られる5つの具体的なメリットを解説します。
出典参照:令和5年度電子商取引に関する市場調査の結果を取りまとめました|経済産業省
ECサイトで「在庫なし」と表示されていても、実は店舗には商品が残っているといった状況は、顧客満足度を下げ、貴重な販売機会を逃す原因となります。店舗とECの在庫情報をリアルタイムで同期させることで、こうした機会損失を大幅に減らすことが可能です。
例えば、ECサイトの注文に対して、お客様の最寄りの店舗在庫を引き当てて発送したり、逆に店舗で欠品している商品をECの在庫から取り寄せて販売したりできます。
全社の在庫を一つの大きな倉庫のように捉え、顧客の「今欲しい」というニーズにいつでも応えられる体制を築けるのです。
実店舗の顧客とECサイトの顧客が別々のリストで管理されていては、一人の顧客の全体像を把握できません。ECサイト連携によって顧客データを統合すると、チャネルを横断した購買行動や興味関心を分析できるようになります。
例えば店舗での購入履歴とECサイトでの閲覧履歴を組み合わせることで、より精度の高いレコメンドが可能になります。お客様一人ひとりのニーズに寄り添ったコミュニケーションを重ねることで、ブランドへの信頼感や愛着が育ちます。
これは、顧客一人当たりの生涯にわたる売上、すなわちLTV(顧客生涯価値)を高める上で非常に効果的なアプローチです。
受注処理や在庫引き当て、出荷指示といった一連のバックオフィス業務は、手作業が多いと時間的コストがかさむだけでなく、人為的なミスの原因にもなります。ECサイト連携は、これらの定型業務を自動化し、業務プロセスを大幅に効率化します。
ECサイトで受けた注文情報が自動的に在庫管理システムや倉庫管理システムに連携され、ピッキングリストが生成されるといった仕組みを構築できます。
スタッフは煩雑な手作業から解放され、より付加価値の高い業務、例えば顧客対応の品質向上や販売促進策の検討に注力できるようになります。結果として組織全体の生産性が向上し、コスト削減にもつながるでしょう。
実店舗とECサイトのデータが分断されている状態では、全社的な視点での正確な状況把握は困難です。ECサイト連携によって売上や在庫、顧客といった経営の重要指標が一元化されると、ビジネス全体の動向をデータで可視化できます。
例えばどの商品がどのチャネルで売れているのか、顧客層と販売チャネルにどのような相関があるのか、といった多角的な分析が可能になります。こうしたデータに基づいたインサイトは、仕入れ計画の最適化やマーケティング施策の精度向上に役立ちます。
経験や勘に頼るのではなく、客観的な事実に基づいて意思決定を行うことで、変化の速い市場での競争力を高められるのです。
OMO(Online Merges with Offline)は、オンラインとオフラインの境界をなくし、顧客にシームレスな体験を提供する考え方です。ECサイト連携は、このOMO戦略を実現するための技術的な基盤となります。
例えば、「ECサイトで注文した商品を最寄りの店舗で受け取る(BOPIS)」や、「店舗で在庫がない商品をその場でECから注文する」といったサービスが代表例です。これらは、顧客の都合に合わせてチャネルを自由に選択できる利便性を提供します。
また、店舗のサイネージからECサイトの特集ページに誘導するなど、オンラインとオフラインを相互に活用した新しい顧客接点も創出できます。こうした一貫性のある快適な体験は、顧客満足度を向上させ、ブランドへのエンゲージメントを強化できるのです。
ECサイト連携を実現するためには、いくつかの主要なシステムを連携させる必要があります。自社の事業内容や解決したい課題によって、最適な組み合わせは異なります。このセクションでは、連携の核となる代表的な4つのシステム連携方式について、それぞれの役割と特徴を解説します。
店舗運営の心臓部であるPOSシステムには、販売実績に関する詳細なデータが蓄積されています。このPOSシステムとECサイトを連携させることで、実店舗とオンラインの売上情報をリアルタイムで統合管理することが可能になります。これにより全社的な売上動向を即座に把握し、迅速な意思決定に繋げられるのです。
クラウドPOSレジとして広く利用されている「スマレジ」なども、こうした連携を実現する代表的なサービスです。
また、顧客のポイントプログラムを共通化すれば、チャネルを問わず一貫したサービスを提供でき、顧客の利便性と満足度を高められます。店舗ごとの販売データとECのアクセスデータを組み合わせることで、より精度の高いマーケティング施策の立案にも役立つでしょう。
出典参照:スマレジ|株式会社スマレジ
倉庫や店舗にどれだけの商品があるかを正確に把握するのが、在庫管理システムの役割です。このシステムとECサイトを連携させると、全ての販売チャネルの在庫情報が常に最新の状態に保たれます。
例えばある店舗で商品が一つ売れた瞬間に、ECサイトの在庫数も自動で一つ減ります。これによりネットで注文したのに在庫がなかったという「売り越し」や、本当は在庫があるのに品切れと表示される「売り逃し」といったトラブルを防ぎます。
クラウド型の在庫管理サービスである「ロジクラ」なども、こうした在庫最適化を実現する選択肢の一つです。会社全体の在庫を効率的に動かすことが、無駄をなくすことにも繋がるのです。
出典参照:ロジクラ|株式会社ロジクラ
顧客との良好な関係を築くためには、顧客を深く理解することが不可欠です。CRM(顧客管理システム)とECサイト、POSシステムを連携させることで、これまで分断されていた顧客情報を統合できます。これにより一人の顧客がオンラインとオフラインでどのような行動をとっているのかを、一元的に把握することが可能になります。
例えば、世界的に広く利用されている「Salesforce」のようなCRMプラットフォームは、こうした顧客データの一元管理と分析を強力に支援します。顧客理解に基づいたきめ細やかなアプローチは、顧客満足度を高め、ブランドへのロイヤリティを育む上で欠かせない要素となるのです。
出典参照:Salesforce|株式会社セールスフォース・ジャパン
複数のECモールに出店している場合、それぞれの管理画面で受注処理や在庫更新を行うのは、非常に手間がかかります。EC一元管理システムはこうした複数の販売チャネルの情報を一つの画面に集約し、受注管理、在庫管理、商品登録などをまとめて行えるようにするツールです。
例えば、多くのEC事業者に利用されている「ネクストエンジン」は、複数サイトの注文情報を自動で取り込み、在庫数を一括で更新する機能などを提供しています。煩雑な手作業から解放されることで、マーケティング施策の立案や顧客対応の品質向上といった、売上に直結する戦略的な業務により多くの時間を割けるようになります。
出典参照:ネクストエンジン|Hamee株式会社

ECサイト連携に成功している企業はただシステムを導入するだけでなく、それを活用してお客様に新しい価値を提供しています。業界の先進的な企業の取り組みから、自社の戦略を考える上でのヒントを見つけていきましょう。このセクションでは、3社の事例をご紹介します。
ユニクロは公式アプリを顧客との重要な接点と位置づけ、ECサイト連携を活かしたOMO戦略を展開しています。お客様が店舗やECサイトで買い物をする際にアプリの会員証を提示すると、購入履歴が一つにまとまります。この統合されたデータをもとに、一人ひとりに合わせたおすすめ商品を提案しています。
これにより顧客は自分の購買傾向に合った情報を得やすくなり、より快適な買い物を楽しめます。また2021年1月からは、アプリ上で決済できるサービス「UNIQLO Pay」を開始し、レジに並ばずキャッシュレスで購入できる、よりスムーズな購買体験を提供しています。
出典参照:1月19日から、ユニクロアプリにウォレット機能「UNIQLO Pay」が登場
ユニクロでのお買い物が、より便利に簡単になります|株式会社ユニクロ
ニトリではお客様の利便性を高めるために、ECサイトと店舗の連携を強化しています。その代表的な取り組みが「店舗受取サービス」です。ニトリ公式通販サイト「ニトリネット」で注文した商品を、お客様が指定したニトリの店舗で受け取ることができます。
2022年2月からは注文から最短翌日で受け取れるようになり、送料もかからないため、お客様は「すぐに欲しい」「送料を節約したい」といったニーズに合わせて、より便利に買い物ができるようになりました。これは、全国の店舗網をECの物流拠点としても活用する、効果的な連携事例です。
出典参照:ニトリ店舗でのお買い物がもっと便利に!利用者1400万人突破のニトリアプリに新機能「アプリde注文」が登場 |株式会社ニトリホールディングス
ホームセンター大手のカインズはお客様向けのサービスだけでなく、従業員の働きやすさを向上させるためのDXにも積極的に取り組んでいます。その一環として開発されたのが、従業員専用アプリ「Find in CAINZ」です。このアプリを使えば、従業員は売り場にいながら、商品の在庫数や陳列場所を瞬時に確認できます。
これによりお客様をお待たせする時間が減り、より丁寧な接客に集中できるようになりました。従業員が商品知識や専門性を活かした質の高い提案をできる時間が増え、お客様の購買体験そのものを豊かにしているのです。従業員の体験価値を高めることが、結果としてお客様の満足度向上にもつながるという、好循環を生み出しています。
出典参照:セールスフォース・ドットコム、カインズのデジタルトランスフォーメーションを支援|株式会社カインズ
ECサイト連携を成功させるためには、自社に合ったシステムを選ぶことが何よりも大切です。多機能で高価なシステムを導入しても、自社の課題や業務の流れに合っていなければ、十分に活用することはできません。このセクションでは、システム選びで後悔しないために、確認しておきたい4つのポイントを解説します。
システムを選ぶ際にまず考えるべきは、そのシステムが自社の最も解決したい課題に対応しているか、という点です。「在庫管理を効率化したい」のか、「顧客データをマーケティングに活かしたい」のか、目的によって最適なシステムは変わってきます。ただ機能の一覧を比較するだけでなく、自社の具体的な業務を思い浮かべながら、「この機能を使えば、あの課題がこのように解決される」と具体的にイメージすることが、ミスマッチを防ぐ上で重要になります。
可能であればシステムのデモンストレーションや無料トライアルを活用し、実際の操作感や自社の業務フローに本当にフィットするかを確かめましょう。その上で、課題解決へのインパクトや費用対効果を見極め、最適なシステムを選ぶ視点が大切です。
多くの企業では、すでに何らかの基幹システムやPOSシステムが稼働していることでしょう。新しいシステムを導入する際は、これらの既存システムとスムーズにデータをやり取りできるかを確認することが不可欠です。
特に、異なるシステム同士を繋ぐための仕組みである「API連携」に対応しているかは、重要なチェックポイントです。APIが公開されていれば、比較的スムーズに連携を進められます。連携できるデータの種類や更新頻度といったAPIの具体的な仕様まで確認し、自社の業務要件を満たせるかを判断しましょう。追加開発が必要な場合は、そのコストや期間も事前に見積もっておく必要があります。ベンダーに既存システムとの連携実績を問い合わせることも、リスクを減らす上で有効です。
ビジネスは常に変化し、成長していくものです。システムを選ぶ際は、今の要件を満たすことだけでなく、将来の事業拡大にも柔軟に対応できる「拡張性」があるかを見極めることが大切です。
例えば将来的に取り扱い店舗やECチャネルが増える可能性はあるか、新しい機能を追加する必要が出てくるか、といった視点で評価します。システムの処理能力の上限(扱える商品数や注文数など)も確認し、事業成長のボトルネックにならないかを見極めます。カスタマイズの柔軟性や、ベンダーが描く機能開発のロードマップも、システムの将来性を判断する上で参考になるでしょう。
システムは導入したら終わりではありません。実際に使っていく中で操作方法が分からなかったり、予期せぬトラブルが発生したりすることもあります。そうした時に迅速で的確なサポートを受けられるかどうかは、システムを選ぶ上で非常に重要なポイントです。
サポートの対応時間や連絡手段が自社の運用体制に合っているか、またサポート費用が基本料金に含まれるのかを確認しましょう。導入時の支援だけでなく、運用が軌道に乗るまで伴走し、システムの活用方法を積極的に提案してくれるようなベンダーであれば、より心強いパートナーとなります。
ECサイト連携は一部の部署だけでなく、会社全体を巻き込む大きなプロジェクトになります。明確な計画を立て、手順に沿って着実に進めることが、手戻りを防いでプロジェクトを成功に導く鍵となります。このセクションでは、そのための具体的な4つのステップをご紹介します。
プロジェクトの第一歩は、「なぜECサイト連携を行うのか」という目的をはっきりさせることです。現場のスタッフや各部門の責任者に話を聞き、日々の業務で何に困っているのか、どのような課題があるのかを具体的に洗い出します。この時に表面的な問題だけでなく、その根本原因まで深掘りすることが重要です。
そして、洗い出した課題の中から今回のプロジェクトで解決すべき課題の優先順位を決めます。「在庫の可視化によって機会損失を1割減らす」「バックオフィス業務にかかる時間を3割削減する」のように、できるだけ具体的なゴールを設定することが、関係者の意識を一つにし、プロジェクトを推進する力になります。
次に、システムを導入した後の理想の業務フローを設計します。現在の業務の流れを整理し、どの部分がシステムによって自動化され、仕事のやり方がどのように変わるのかを具体的に描いていきます。この理想のフローを実現するために、新しいシステムにどのような機能が必要かをリストアップする作業が「要件定義」です。
この時、「絶対に譲れない必須要件」と「できれば実現したい希望要件」を分けて整理すると、後のシステム選定がスムーズに進みます。この要件定義が曖昧だと、導入後に「欲しかった機能が足りない」といった問題が起こりがちなので、時間をかけて慎重に行うことが大切です。
ステップ2で作成した要件定義書をもとに、複数のシステム開発会社やベンダーから提案と見積もりを取り寄せます。それぞれのシステムが自社の要件をどれだけ満たしているか、機能やコスト、サポート体制などを多角的に比較検討します。この時単に機能の多さや価格の安さだけで判断するのではなく、自社の業界での導入実績や、担当者の対応力なども含めて総合的に評価することが重要です。
提案内容について不明な点があれば遠慮なく質問し、自社のビジネスへの理解度や課題解決への熱意を見極めましょう。長く付き合っていくパートナーとして、信頼できる企業を選ぶという視点が求められます。
導入するシステムとパートナー企業が決まったら、いよいよ導入プロジェクトがスタートします。プロジェクトを成功させるには、経営層から現場のスタッフまで、会社全体で協力する体制を作ることが欠かせません。なぜこのシステムを導入するのか、それによってどのようなメリットがあるのかを社内全体に丁寧に説明し、関係者の理解と協力を得ることが大切です。
また、導入後の運用ルールを決めたりスタッフ向けの研修会を開いたりするなど、新しいシステムが現場にスムーズに根付くための働きかけを継続的に行いましょう。導入後も定期的に効果を測定し、現場からのフィードバックを収集して改善を続けることで、システムの効果を最大化できます。
ECサイト連携は多くのメリットをもたらしますが、その道のりではいくつかの壁に直面することもあります。多くの企業が経験する共通の課題をあらかじめ知っておき、対策を考えておくことで、プロジェクトをより円滑に進められます。
長年使ってきた古い基幹システムやPOSシステム、いわゆる「レガシーシステム」が、新しいシステムとの連携の妨げになることがあります。これらの古いシステムは外部とデータをやり取りするための仕組み(API)が備わっていないことが多く、連携を実現するために大きな改修費用がかかる場合があります。
また、長年の運用でデータが不整合を起こしていたり、仕様がブラックボックス化していたりすると、新しいシステムへのデータ移行作業も困難を極めます。この壁に直面した際は既存システムを改修して使い続けるのか、これを機にシステム全体を新しくするのか、会社の将来を見据えた大きな判断が求められることになるでしょう。
ECサイト連携のようなDXプロジェクトを進めるには、ITの知識とビジネスの知識の両方を理解している人材が欠かせません。しかし多くの企業では、こうしたDX人材が社内に不足しているのが実情です。プロジェクトを主導し、各部門と調整しながらゴールに向かう推進役がいないと、計画が頓挫してしまうことも少なくありません。
社内で一から育てるには時間がかかるため、外部の専門家やコンサルティング会社の力を借りることも有効な選択肢です。ただし外部に丸投げするのではなく、社内にノウハウを蓄積する意識を持ち、プロジェクトを通じて自社のDX人材を育成していく視点も大切になります。
ECサイト連携には、システムの導入費用や月々の運用費用といったコストがかかります。経営層にプロジェクトの承認を得るためには、「今回の投資によって、どれくらいの効果が見込めるのか」という投資対効果(ROI)を具体的に示すことが求められます。
「業務効率化による人件費の削減」といった直接的な効果だけでなく、「顧客満足度の向上」といった数値化しにくい間接的な効果も、ストーリーとして説明することが重要です。最初は小規模な範囲で導入して成功実績を作り、その効果を提示して全社展開の承認を得る、といった段階的なアプローチも有効な手段の一つです。
ECサイト連携では、業務効率化やデータ活用が注目されやすい一方、セキュリティと法令対応が設計段階で十分に検討されない場面が見受けられます。その結果、運用開始後に対応方針の見直しが発生し、現場負担が増える流れにつながります。こうした状況を避けるためには、連携前に整理すべき観点を理解し、運用まで見据えた設計を進める姿勢が大切です。
ここからは、実務で特に見落としやすい三つの観点を順に整理します。
ECサイト連携で最初に意識すべき点は、個人情報の取り扱い範囲を明確にする作業です。理由として、連携先が増えるほど情報の流通経路が複雑になり、管理責任が不透明になりやすいためです。まず、連携によって取得、参照、保存される情報を洗い出し、業務上必要な範囲に限定します。
次に、利用目的ごとに同意管理の流れを整理します。個人情報保護法では、利用目的の特定と本人同意が重要視されるため、連携単位で管理方針を分ける考え方が有効です。こうした整理により、不要な情報連携を抑え、運用時の確認作業も簡素化されます。結果として、法令対応と業務効率の両立を意識した運用設計につながります。
次に検討すべき要素として、API連携における認証と権限管理があります。結論として、処理内容に応じた権限制御を前提に設計する姿勢が求められます。理由は、広範な権限付与が不正アクセス時の影響範囲を拡大させる要因になるためです。
API連携では、トークンなどの認証情報を用いて通信を制御しますが、誰がどの処理を実行できるかを細かく定義する点が重要になります。さらに、運用フェーズを想定し、権限の棚卸しや更新ルールを整備すると、安全性を維持しやすくなります。このように設計すると、外部サービスとの連携を進めながらも、リスク管理の視点を保てます。
最後に、ログ管理と監査対応を前提とした運用ルールの整理が欠かせません。理由として、障害対応や不正利用調査では、操作履歴やアクセス履歴が重要な判断材料となるためです。
ログを取得する際は、取得対象と利用目的を明確にし、過剰な収集を避けます。その上で、閲覧権限や保管方針を定めると、内部統制の観点でも効果が期待されます。
また、監査対応を想定した手順をあらかじめ整理しておくと、確認依頼への対応も円滑になります。こうした取り組みが、安定したECサイト連携運用を支える基盤となります。

ここまで、小売DXにおけるECサイト連携のメリットや方法、導入のステップについて解説してきました。ECサイト連携は、単にバラバラだったシステムを繋ぐだけの技術的な話ではありません。在庫や顧客といった会社の大切な資産を一つにまとめ、お客様一人ひとりと真摯に向き合うことで、これまでにない新しい顧客体験を生み出すための重要な経営戦略なのです。
導入の過程ではいくつかの課題に直面するかもしれませんが、それを乗り越えた先には、お客様からの深い信頼と会社の持続的な成長が待っているはずです。
この記事が、皆様の会社が顧客中心のDXへ踏み出すための一助となれば幸いです。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
