小売DXの第一歩はペーパーレス化!メリットや書類管理の課題を解説
小売

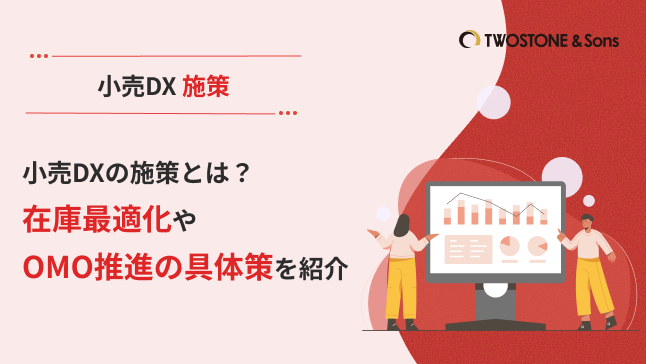
小売業の経営者・DX担当者様へ。人手不足や売上向上といった課題を解決する具体的なDX施策を、成功事例を交えて解説します。失敗しないための導入ステップから、活用できるツールや補助金情報まで網羅。自社の状況に合った進め方が見つかります。


・6万名以上のエンジニアネットワークを活用して課題を解決※
・貴社のDX戦略立案から実行・開発までワンストップで支援可能
※エンジニア数は2026年8月期 第1四半期決算説明資料に基づきます。
「売上が伸び悩む」「人手不足が深刻だ」といった悩みを抱える小売企業の担当者の方は多いかもしれません。その解決策であるDX(デジタルトランスフォーメーション)は重要ですが、何から手をつければ良いか分からずにいるケースも少なくないでしょう。
この記事では、小売DXの具体的な施策を企業の課題別に分かりやすく解説します。成功事例や役立つツール、失敗しない進め方まで網羅的に紹介していきます。自社の課題を解決し、競争力を高めるヒントとして、ぜひお役立てください。
DXへの取り組みを始める前に、まずはその基本的な考え方と、なぜ今小売業界でこれほどまでに重要視されているのかについて理解を深めていきましょう。
小売DXとしばしば混同されがちなのが「IT化」です。小売DXとは、単にデジタルツールを導入することではありません。その本質はデジタル技術の活用を前提として、ビジネスモデルや業務の進め方、さらには企業文化そのものを変革し、新しい価値を生み出すことにあります。
一方のIT化は既存の業務プロセスはそのままに、効率化やコスト削減を目的としてデジタルツールを導入することを指します。例えば、手書きの報告書をパソコン入力に変えるのはIT化です。それに対してDXは、POSデータと顧客情報を連携させて一人ひとりに最適な商品を提案するなど、事業のあり方そのものを見直すより大きな変革を意味します。
現在小売業界でDXが急務とされている背景には、主に2つの大きな環境の変化が存在します。
一つ目は、消費者ニーズの多様化です。スマートフォンの普及により、人々は時間や場所を選ばずに情報を集め、商品を購入するようになりました。オンラインと実店舗の境界線は曖昧になり、顧客の購買行動は複雑化しています。この変化に対応できなければ、顧客を失うことにも繋がりかねません。
二つ目の背景は、深刻化する人手不足です。少子高齢化による労働人口の減少は、多くの業務を人手に頼ってきた小売業界にとって大きな課題となっています。限られた人員で質の高いサービスを提供し続けるためには、業務の効率化や自動化が不可欠なのです。

多くの小売企業は、「人手不足」「売上向上」「顧客体験」「在庫管理」という4つの課題に直面しています。このセクションではそれぞれの課題を解決するための代表的なDX施策と、その目的について解説します。
慢性的な人手不足を解消し、従業員がより創造的で付加価値の高い業務に集中できる環境を整えることが、この領域の施策の主な目的です。例えばセルフレジやキャッシュレス決済を導入すれば、会計業務の自動化や省人化が進み、お客様の待ち時間を短縮できます。これにより生まれた時間は、より丁寧な接客や売り場作りといった、人でなければできない業務に充てることが可能になります。
また、AIによる需要予測や自動発注システムは、担当者の経験や勘に頼りがちだった発注業務の負担を大きく軽減します。天候や過去の販売データから最適な発注量を算出することで、欠品による機会損失や過剰在庫のリスクを低減させる効果も期待できるでしょう。
データに基づいて顧客一人ひとりを深く理解し、その人に響くアプローチを行うことで、売上の最大化を目指します。店舗の購買履歴やECサイトの閲覧履歴といった顧客データをCRM(顧客関係管理)ツールなどで一元管理し、分析することがその第一歩です。
購買頻度や単価、最終購買日などを分析することで、優良顧客や離反しそうな顧客を特定し、それぞれに合った施策を展開できます。その分析結果に基づき、個々の興味に合わせた誕生日クーポンやおすすめ商品を配信すれば、画一的な情報発信よりも高い効果が期待でき、顧客との良好な関係構築、すなわちLTV(顧客生涯価値)の向上にも繋がるでしょう。
OMO(Online Merges with Offline)とは、オンラインとオフラインの垣根をなくし、顧客に一貫した快適な購買体験を提供するための考え方です。現代の消費者はスマートフォンを片手に、店舗とECサイトを自由に行き来しながら購買を検討します。ECサイト上で店舗の在庫状況を確認できたり、「店舗受け取り」の選択肢があったりすることは、顧客の利便性を大きく向上させます。
また、公式アプリを会員証として活用して店舗とECでポイントや購買情報を共通化すれば、顧客との継続的な接点が生まれます。こうしたシームレスな体験は、顧客満足度を高め、ブランドへの愛着を育む上で非常に重要な要素となります。
煩雑になりがちな在庫管理業務を効率化し、欠品や過剰在庫による機会損失やコスト増加を防ぐこともDXの重要な目的です。特に、商品にICタグを取り付けて専用リーダーで情報を一括で読み取るRFID技術は、棚卸しや検品にかかる時間を劇的に短縮する可能性を秘めています。
また、複数のECモールや自社サイトに出店している場合、在庫情報を手動で調整するのは大変な労力がかかり、売り越しなどのミスも発生しがちです。EC一元管理システムを導入すれば、各チャネルの在庫・受注情報を自動で連携・管理できるため、バックヤード業務の負担を大幅に減らすことができます。これらの業務効率化は、キャッシュフローの改善にも繋がります。
このセクションでは実際にDXへ取り組み、大きな成果を上げている企業の事例を紹介します。自社の施策を検討する上でのヒントにしてください。
株式会社ニトリホールディングスは、「製造物流IT小売業」という独自のビジネスモデルを掲げ、企画から製造、物流、販売までを一気通貫で行っています。このモデルの根幹を支えているのが、徹底したデータ活用です。
顧客の購買データや問い合わせ、SNS上の意見などを多角的に分析し、それを商品企画や改善に直接反映させています。これにより、顧客が本当に求めている商品をスピーディーに開発することが可能になっています。
さらに、需要予測に基づいて製造計画や物流網を最適化することで、サプライチェーン全体の無駄をなくし、高品質な商品を手に取りやすい価格で提供するという価値を実現しています。まさにデータが事業の成長を牽引する好例といえるでしょう。
出典参照:NITORI HOLDINGS 統合報告書 2024|株式会社 ニトリホールディングス
株式会社ユニクロは公式アプリを中心に店舗とECサイトをシームレスに連携させ、顧客体験価値を大きく向上させています。その代表的な施策が、ECサイトで購入した商品を最寄りの店舗で受け取れるサービスです。
これにより顧客は送料を気にせず、自分の都合の良いタイミングで商品を受け取れるようになりました。また、アプリ会員証を提示すれば、店舗とECサイトどちらの購買履歴も一元管理され、顧客は自身の購入履歴をいつでも確認できます。
ユニクロはこれらのデータに基づき、一人ひとりの顧客に合わせたパーソナライズ提案も実施しています。こうした一貫性のある便利な購買体験が、顧客との強い信頼関係を築き、ブランドへの支持に繋がっているのです。
株式会社ローソンはコンビニ業界共通の課題である食品ロスや、店舗スタッフの発注業務の負担軽減に対し、AIによる需要予測システムを導入することで対応しています。
このシステムは過去の販売実績や曜日、天候、近隣のイベント情報といった数十種類のデータをAIが分析し、商品ごとの最適な販売数を予測します。店舗の従業員はこの予測値を参考にすることで、経験や勘だけに頼ることなく、より精度高く発注業務を行えるようになりました。
この取り組みは発注にかかる時間を削減し、従業員の業務負担を軽減しただけでなく、欠品による販売機会の損失や、過剰在庫による食品ロスの削減にも大きく貢献しています。
出典参照:働き手不足をデジタルイノベーションでサポート!|株式会社ローソン
ホームセンター大手の株式会社カインズは、デジタル技術を駆使して、これまでにない新しい購買体験を創出しています。その象徴的なサービスが、アプリで注文した商品を店舗の専用ロッカーで非対面で受け取れる「CAINZ PickUp」です。
これにより、顧客は広い店内を探し回ったりレジに並んだりする必要がなくなり、スムーズに買い物を終えることができます。また、DIYの作り方を動画で学べる「CAINZ DIY Square」といったデジタルコンテンツも充実させています。
これらの取り組みは単に商品を販売するだけでなく、顧客の「くらし」に寄り添い、買い物のプロセスそのものを楽しんでもらおうという意図が感じられます。デジタルを通じて顧客とのエンゲージメントを高めている先進的な事例です。
出典参照:Cloudpickの技術を採用し、「CAINZ Mobile Store」がリニューアル・オープン|株式会社カインズ

DXは、やみくもに進めても良い結果には繋がりません。このセクションでは、小売DXを成功に導くための基本的な5つのステップを紹介します。
小売DXを成功させるための第一歩は、自社が置かれている状況を正確に把握することから始まります。まずは「売上が落ちている」「人手が足りない」といった漠然とした問題意識を、より具体的な課題へと落とし込んでいく作業が必要です。
例えば、「どの店舗の、どの商品カテゴリーの売上が、いつから落ち込んでいるのか」「現場では、どの業務に最も時間がかかっており、従業員は何に負担を感じているのか」といったレベルまで深掘りします。
POSデータのような定量的な情報だけでなく、従業員へのヒアリングや顧客アンケートといった定性的な情報も集め、多角的に分析することが重要です。この現状分析が、後のステップで的確な目的を設定するための、しっかりとした土台となります。
現状分析によって自社の課題が明確になったら、次に「DXによって、その課題をどう解決し、何を実現したいのか」という目的(ゴール)を設定します。この目的が、DX推進プロジェクト全体の羅針盤の役割を果たします。
目的を設定する際は、「業務を効率化する」といった曖昧なものではなく、「データ活用による若年層の売上を前年比で10%向上させる」「セルフレジ導入により、ピークタイムのレジ業務時間を30%削減する」といった、具体的で測定可能な数値目標(KPI)も合わせて設定することが極めて重要です。
KPIがあることで、施策の進捗状況や効果を客観的に評価できるようになり、関係者間での共通認識も生まれやすくなります。
目的とKPIが定まったら、いよいよそれを達成するための具体的なアクションプランを立てる段階に入ります。これまでのステップで明確になった課題と目的に基づき、数ある選択肢の中から自社にとって最も効果的と考えられる施策を選び出します。
例えば、顧客体験の向上を目指すならOMOの強化、業務効率化が目的ならバックヤードシステムの導入などが考えられるでしょう。施策が決まったら、それを実行するためのツールを選定します。
その際は、機能やコストはもちろんのこと、現場の従業員がスムーズに使えるかという操作性や、導入後のサポート体制が充実しているかといった点も慎重に比較検討することが大切です。
有望な施策やツールが見つかっても、いきなり全社的に大規模な導入を行うのはリスクが高い場合があります。そこで重要になるのが、特定の店舗や部門、商品などに限定して試験的に導入する「スモールスタート」という考え方です。
この小規模な試みを通じて、実際の業務の中で本当に効果があるのか、何か想定外の問題は起きないかなどを検証します。この段階で、ステップ2で設定したKPIを用いて効果を客観的に測定することが重要です。
うまくいった点と改善すべき点を具体的に洗い出し、次の本格導入に向けた改善のサイクル(PDCA)を回していきます。小さな成功体験を積むことが、全社を巻き込む上での大きな推進力となるでしょう。
スモールスタートで有効性が確認され、改善点も洗い出せたら、いよいよ本格的に導入範囲を全社へと拡大していくステップに移ります。試験導入で得られた成功のノウハウや運用マニュアルなどを活用しながら、他の店舗や部門へと展開していきます。
ここで忘れてはならないのが、DXは一度導入したら終わりではない、ということです。市場の環境や顧客のニーズは絶えず変化します。そのため導入後も定期的にデータを分析し、施策の効果をモニタリングし続ける必要があります。
そして、状況の変化に合わせて施策やツールを柔軟に見直し、改善を続けていく姿勢が不可欠です。こうした活動が企業文化として根付いてこそ、DXは真の成功を収めたといえるでしょう。
このセクションでは、具体的な施策の実行に役立つ代表的なDXツールをカテゴリ別に紹介します。自社の課題解決に繋がるツールを見つける参考にしてください。
現代のPOSレジは会計処理だけでなく、売上や顧客、在庫データをリアルタイムで収集・分析し、店舗運営の意思決定を支える「司令塔」の役割を担います。
クラウド型のPOSレジを導入すれば、経営者はいつでもどこでも店舗状況を把握でき、データに基づいた迅速な判断が可能です。例えば「スマレジ」は、豊富なアプリで自社の業種や規模に合わせて機能を柔軟にカスタマイズできます。
また、iPadなどで手軽に始められる「Airレジ」は、直感的な操作性と決済やシフト管理といった他の「Air」シリーズとのスムーズな連携が魅力です。こうしたツールは、データドリブンな店舗運営を実現するための第一歩となります。
出典参照:スマレジ|株式会社スマレジ
出典参照:Airペイ|株式会社リクルート
実店舗と複数のECサイトを運営する場合、在庫管理の煩雑さは大きな課題です。各チャネルの在庫を手動で調整するのは手間がかかる上、「売り越し」や「販売機会の損失」といったリスクも伴います。
こうした課題を解決するのが、在庫一元管理システムです。導入すれば、各販売チャネルの在庫情報が自動で連携され、一つの画面で全ての在庫を正確に把握できます。
業界の定番ツール「ネクストエンジン」は、多くのECモールに対応し、受注から在庫管理までを幅広く自動化します。また、「LOGILESS」のように受注管理と倉庫管理が一体化したシステムもあり、物流業務まで含めた効率化を目指せます。バックヤード業務の負担を軽減し、OMO戦略の基盤を築く上で欠かせません。
出典参照:ネクストエンジン|Hamee株式会社
出典参照:LOGILESS|株式会社ロジレス
顧客との良好な関係を長期的に築くには、一人ひとりの顧客を深く理解することが不可欠です。CRM(顧客関係管理)ツールは、顧客の基本情報や購買履歴などを一元管理し、そのデータを分析・活用するためのプラットフォームです。
CRMを活用すれば、「誰が、いつ、何を、購入したか」といった情報が可視化され、顧客の属性に合わせたパーソナライズされたアプローチが可能になります。世界的に高いシェアを誇る「Salesforce」は、顧客管理から営業支援まで、非常に高機能で幅広い業務に対応できます。
一方、「HubSpot」は無料プランから始められる手軽さと、マーケティングやセールス機能が統合されている点が魅力です。こうしたツールは、顧客満足度とLTV(顧客生涯価値)を向上させる上で、強力な武器となるでしょう。
出典参照:Salesforce|株式会社セールスフォース・ジャパン
出典参照:HubSpot|HubSpot Japan株式会社
人手不足が深刻化する小売業において、従業員のシフト管理は店長の大きな負担です。従業員の希望やスキル、法令などを考慮しながらシフトを組むのは、非常に複雑で時間がかかります。
シフト管理ツールを導入すれば、こうした煩雑な作業を大幅に効率化できます。従業員はスマートフォンから希望シフトを提出でき、管理者はそれらの情報をもとに、最適なシフトを自動で作成することが可能になります。
例えば、「Airシフト」はスタッフとのやり取りからシフト作成までをスマホで完結できる手軽さが特徴です。また、「ジョブカン勤怠管理」のように勤怠管理システムと連携し、予実管理まで行える高機能なツールもあります。従業員が働きやすい環境を整えることは、離職率の低下にも繋がります。
出典参照:Airシフト|株式会社リクルート
出典参照:ジョブカン勤怠管理|株式会社DONUTS
DXの推進にはコストが伴いますが、国や自治体が提供する補助金を活用することで、その負担を軽減できる場合があります。このセクションでは代表的な補助金を紹介します。
IT導入補助金は、中小企業や小規模事業者が自社の課題解決や生産性向上を目的としてITツールを導入する際に、その経費の一部を補助してくれる制度です。小売業においては、まさにDX推進の心強い味方となります。
例えば、多機能なPOSレジシステムや在庫管理システム、顧客管理を行うCRMツール、あるいは新たにECサイトを構築するための費用などが補助の対象となり得ます。インボイス制度への対応を目的とした枠も用意されています。
自社の課題に合わせて適切なツールを選ぶことで、業務効率化や売上アップといったDXの目的達成を、コスト負担を抑えながら目指すことが可能です。まずは自社の導入したいツールが対象になるか確認してみると良いでしょう。
出典参照:IT導入補助金2025|サービス等生産性向上IT導入支援事業事務局
事業再構築補助金は、社会経済の大きな変化に対応するため、中小企業などが思い切った事業の再構築、つまり新しいビジネスモデルへ挑戦するのを支援する制度です。単なるツール導入に留まらない、より大きな変革を目指す場合に活用を検討できます。
例えばこれまで店舗での対面販売を主軸としてきた企業が、新たに本格的なECサイトを立ち上げてオンライン販売事業へ進出するケースや、店舗を体験型のショールームへと改装し、ECでの販売を主軸に据えるといった業態転換などが考えられます。
このように、既存事業の枠を超えた新しい取り組みを後押ししてくれる補助金であり、企業の成長戦略を大きく加速させるきっかけになり得ます。
出典参照:事業再構築補助金|事業再構築補助金事務局
ものづくり補助金は、その名称から製造業向けという印象が強いかもしれませんが、小売業でも活用できる可能性があります。この補助金は中小企業などが行う革新的な製品・サービス開発や、生産プロセス改善のための設備投資などを支援するものです。
小売業においては、例えばAIを活用した独自の需要予測システムを開発・導入したり、バックヤード業務を自動化するためのロボットを導入したり、あるいは顧客体験を向上させるための新しいデジタルサービスを開発したりといった、先進的な取り組みが対象となり得ます。
自社の生産性や競争力を飛躍的に高めるための、革新的なチャレンジをサポートしてくれる制度といえるでしょう。
出典参照:ものづくり補助金総合サイト|全国中小企業団体中央会

最後に、小売DXを推進する上で多くの企業が陥りがちな失敗パターンと、その対策について解説します。事前に知っておくことで、リスクを回避しやすくなるでしょう。
「DXが注目されているから」「競合他社が導入したから」といった、漠然とした理由でツール導入に踏み切ってしまうのは、よくある失敗パターンの一つです。
自社の課題や目的が明確でないままでは、導入したツールを十分に活用できず、結果としてコストだけがかさんでしまうことになりかねません。ツールを導入すること自体が目的化してしまうのです。
このような事態を避けるためには、まず自社の業務プロセスや経営状況を分析し、「何のためにDXを行うのか」という目的を社内全体で明確に共有することが不可欠です。この目的意識が、DX推進のぶれない軸となります。
DXは一部門の取り組みではなく、企業文化の変革にも関わる全社的なプロジェクトです。そのため、経営層の強いリーダーシップとコミットメントが成功の鍵を握ります。
しかし、経営層がDXの重要性を十分に理解せずに必要な投資や権限委譲に消極的な場合、プロジェクトは途中で推進力を失い、停滞してしまいがちです。
DX担当者はDXによってどのような経営課題が解決され、どれくらいの投資対効果が見込めるのかを、具体的なデータや事例を用いて経営層に説明し、理解を求める必要があります。経営層を巻き込むことが、DXを力強く前進させる原動力となるのです。
新しいツールの導入や業務プロセスの変更は、日々の業務に慣れ親しんだ現場の従業員にとって、一時的に大きな負担となることがあります。
その変化の必要性やメリットが十分に伝わらないまま、トップダウンでDXを進めてしまうと、現場から抵抗感や義務感が生まれ、協力が得られなくなってしまう恐れがあります。
これを防ぐためには、計画の早い段階から現場の従業員を巻き込み、彼らの意見や不安に耳を傾けることが重要です。そしてDXによって業務がどのように改善されるのかを丁寧に説明し、変革の当事者であるという意識を共有してもらう努力が不可欠です。
DXを効果的に推進するには、デジタル技術の知識と、自社のビジネスや業務内容の両方に精通した人材が求められます。しかし多くの中小企業では、そのような「DX人材」が社内にいないのが実情です。
人材がいないからといってDXを諦める必要はありません。対策として、無理に自社だけで完結させようとせず、外部の専門家やコンサルティング会社の支援を受けることも有効な選択肢の一つです。
また、長期的な視点に立って補助金などを活用して従業員向けの研修を実施するなど、社内での人材育成に取り組むことも重要です。外部の知見と内部の育成を組み合わせることが、持続可能なDX推進体制を築く鍵となります。
この記事では小売DXの具体的な施策から成功事例、導入ステップまでを網羅的に解説しました。
小売DXは、もはや一部の先進企業だけのものではありません。消費者ニーズが多様化し、人手不足が深刻化する現代において、事業を継続し成長させていくための重要な経営戦略となっています。
最も大切なのは、他社の成功事例をそのまま真似するのではなく、自社の課題は何かを正しく見極め、その解決に繋がる施策を着実に実行していくことです。まずは自社の現状分析から始め、小さな成功を積み重ねながら、自社ならではのDXを推進していきましょう。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
