小売DXの第一歩はペーパーレス化!メリットや書類管理の課題を解説
小売

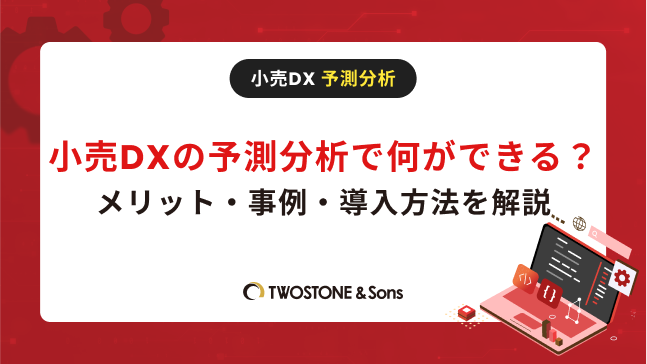
小売業の在庫ロスや機会損失にお悩みですか?本記事では、小売DXの中核となる「予測分析」について、メリットや具体的な活用事例、導入方法までを分かりやすく解説します。データに基づいた経営判断で、収益改善を実現するためのヒントがここにあります。


・6万名以上のエンジニアネットワークを活用して課題を解決※
・貴社のDX戦略立案から実行・開発までワンストップで支援可能
※エンジニア数は2026年8月期 第1四半期決算説明資料に基づきます。
商品の欠品や過剰在庫は、多くの小売業が抱える共通の課題です。経験や勘に頼る経営に限界を感じるなか、解決策として注目されているのがAIを活用した予測分析です。
予測分析はデータから未来の需要を高精度で予測し、在庫最適化や業務効率化を実現します。これにより、データに基づいた的確な経営判断、いわゆるデータドリブン経営への移行が期待できるでしょう。
本記事では予測分析の基本から具体的な活用法、成功事例、導入ステップまでを分かりやすく解説します。
予測分析と聞くと、少し難しく感じるかもしれません。しかし、その基本的な仕組みを理解することで、自社のビジネスにどう活かせるかのイメージが湧きやすくなります。このセクションでは、予測分析の土台となる技術や従来の手法との違いについて見ていきましょう。
予測分析の心臓部となっているのが、AI(人工知能)と機械学習です。機械学習とは、コンピューターが大量のデータからパターンや法則性を自動で学習し、それに基づいて未来を予測する技術を指します。
小売業においては過去の販売実績、天気、イベント、プロモーションといった様々なデータをAIに学習させることが一般的です。これにより、「来週のこの商品の売上は〇個になる」といった高精度な予測が可能になります。つまり、熟練の担当者が長年の経験で培ってきた「勘」に近い判断を、AIがデータに基づいて再現・進化させるのが、予測分析の基本的な仕組みといえるでしょう。
これまでの小売業では、店長やベテラン担当者の「勘」や「経験」に頼った発注・在庫管理が主流でした。この方法には個人のスキルに依存するため業務が属人化しやすい、担当者の異動や退職でノウハウが失われるといった課題が考えられます。
一方、予測分析はデータという客観的な事実に基づいて判断します。これにより、誰が担当しても一定の精度で予測が可能になり、業務の標準化が期待できます。また、人間では処理しきれない膨大な量のデータ(天候、SNSのトレンド、競合の動向など)を分析に組み込めるため、より精度の高い予測につながる点も大きな違いです。
予測分析の精度は、学習させる「データ」の質と量に大きく左右されます。主に活用されるのはPOSデータや在庫データ、顧客データといった社内で蓄積された情報です。例えば「いつ」「どこで」「何が」売れたかというPOSデータは、分析の根幹をなす重要な情報源となります。
さらに、これらの社内データに加えて、天気予報や地域のイベント情報、SNSの投稿データといった外部のデータを組み合わせることで、予測の精度はよりいっそう高まる傾向にあります。多様なデータを統合的に分析することが、精度の高い予測分析を実現する鍵といえるでしょう。

予測分析は、小売業が長年抱えてきた課題を解決する有力な手段となり得ます。このセクションでは、特に代表的な3つの課題に対して、予測分析がどのようにアプローチし、解決に導くのかを解説します。
「売れると思って多めに仕入れたら、大量に売れ残ってしまった」という経験は、多くの小売業者にとって悩みの種です。特に食品スーパーなどでは過剰在庫はそのまま廃棄ロスに直結し、経営を圧迫する要因となります。
予測分析は過去の販売実績や天候、イベント情報などから未来の需要を高精度で予測します。これにより、必要以上の仕入れを防ぎ、常に最適な在庫量を維持することが可能になります。結果として、保管コストや廃棄コストを大幅に削減できる可能性が高まります。これは、企業の収益性向上に直結する重要なポイントです。
過剰在庫とは逆に、欠品は「買いたい」という顧客のニーズに応えられず、売上を得るチャンスを逃す機会損失につながります。さらに「欲しい商品がいつもない」という状況が続けば、顧客満足度が低下し、店舗から足が遠のいてしまう原因にもなりかねません。
予測分析を活用すれば、特売やメディアで紹介されたことによる突発的な需要の増加なども予測し、欠品が起こる前に追加発注を行うといった対策が可能です。これにより販売機会を逃さず、売上の最大化を目指せるでしょう。安定した商品供給は、顧客からの信頼を獲得する上で不可欠な要素です。
「発注業務はベテランの〇〇さんにしか任せられない」といった状況は、多くの店舗で見られる光景です。このような業務の属人化は、担当者の負担を増やすだけでなく、異動や退職によって店舗の運営が立ち行かなくなるリスクをはらんでいます。
予測分析を導入すればAIがデータに基づいて最適な発注量を自動で算出してくれるため、担当者の経験やスキルに依存することなく、誰でも精度の高い発注業務を行えるようになります。これにより、業務の標準化と大幅な効率化を実現し、従業員はより付加価値の高い業務に集中できる環境が整います。その結果組織全体としての業務継続性を高め、安定した店舗運営を実現します。
課題解決の先には、どのようなメリットが待っているのでしょうか。予測分析の導入はコスト削減や業務効率化だけでなく、企業の競争力を高める上でも大きな効果をもたらすと考えられます。
予測分析の大きなメリットは、KKD(勘・経験・度胸)から脱却し、データという客観的な根拠に基づいた意思決定(データドリブン経営)が可能になることです。
例えば新しいプロモーションを企画する際に、「どの商品を対象にすれば効果が高いか」「どれくらいの売上増が見込めるか」をデータで予測できれば、より効果的な施策を打つことができます。また、社内で予算を確保する際にもデータに基づいた説得力のある説明ができるため、合意形成がスムーズに進むでしょう。このようなデータ活用は場当たり的な対応を減らし、より戦略的な事業運営を可能にします。
予測分析は、間接的に顧客体験価値(CX)の向上にも貢献します。欠品のない売場は顧客が「欲しい」と思ったときに、いつでも商品が手に入る状態を維持することにつながります。
また、トレンド予測などを活用し、顧客が求める商品を先回りして提供することも可能です。来店客数を予測することで、レジの待ち時間を短縮するなどのスムーズな買い物体験を提供することも期待できます。これらの積み重ねが、顧客にとって「快適で信頼できる店」というポジティブなブランドイメージを構築し、再来店を促すことにつながります。
市場の変化が激しい現代において、競合他社と同じことをしていては生き残りが難しい側面があります。予測分析をいち早く導入し、データ活用を推進することで、他社にはない競争優位性を築くことにつながるかもしれません。
例えば、他社がまだ気づいていない新たなトレンドをいち早く掴んで商品化したり、徹底した在庫最適化によって収益性を高めたりすることが考えられます。データに基づいた迅速かつ的確な意思決定を繰り返すことで、市場における優位なポジションを確立し、持続的な成長を目指せるでしょう。このような市場への迅速な対応力と経営の効率化こそが、厳しい競争環境下での持続的な優位性を生み出す源泉となります。
予測分析が具体的にどのような場面で活用できるのか、4つの代表的なシーンを挙げて解説します。自社のどの業務に適用できそうか、イメージしながらご覧ください。
予測分析の力を最も実感しやすいのが、商品ごとの需要予測でしょう。これは過去の販売データだけでなく、天気や気温、地域のイベント、チラシの配布計画といった様々な要因をAIが統合的に分析するものです。
例えば「週末の気温低下と雨予報から、鍋物関連商品の需要が40%増加する」といった、具体的な数値を伴う予測が可能になります。これにより勘や経験だけに頼るのではなく、データに基づいた客観的な仕入れ判断が下せるようになります。
この予測に基づき仕入れ量を調整することで販売チャンスを逃すことなく、同時に廃棄ロスの削減も実現でき、店舗の収益向上に直接貢献します。
精度の高い需要予測は、発注業務の自動化へと発展させることが可能です。AIが予測した需要量と現在の在庫数、安全在庫、納品までのリードタイムを考慮し、最適なタイミングで最適な数量を自動的に発注するシステムを構築できます。
これにより、担当者は日々の複雑な発注計算というルーティンワークから解放され、人的エラーのリスクも低減します。
生まれた時間を売場改善や接客、販促企画といった、より創造的で付加価値の高い業務に振り分けられるようになります。これは従業員のモチベーション向上にもつながり、店舗全体のサービス品質向上に貢献するでしょう。
発注業務の効率化は、従業員のモチベーション向上と店舗全体のサービス品質向上にも貢献するのです。
店舗運営における大きな課題の一つが、人手不足と人件費の最適化です。予測分析は過去の来店客数の推移に、曜日や天候、給料日といった要素を加えて、未来の来店客数を予測します。
この予測に基づけば、レジが混雑する時間帯にはスタッフを増員し、客足が落ち着く時間帯には人員を絞るといった、効率的なシフト作成が可能になります。
結果としてお客様の待ち時間を減らして満足度を高めつつ、無駄な人件費を抑制できるため、店舗の収益性向上に貢献します。従業員の負担を平準化し、働きやすい環境を整える効果も期待できるでしょう。
消費者のリアルな本音を掴む手段として、SNSデータの分析が注目されています。X(旧Twitter)やInstagramなどのプラットフォームには、商品に対する消費者の率直な意見や感想が日々投稿されています。
AIを用いてこれらの膨大なテキストデータを分析することで、「この新商品が話題になり始めている」といったトレンドの兆候を、初期段階で検知できます。
これは、次のヒット商品を仕入れるためだけではありません。顧客の不満点を把握してサービスを改善したり、消費者の声をヒントに自社商品を開発したりと、様々な形で活用できます。これらのインサイトを商品開発や品揃えに活かすことで、顧客ニーズに即した店舗づくりを進め、競合との差別化を図ることが可能になります。

このセクションでは実際に予測分析を導入し、成果を上げている企業の事例を3つ紹介します。自社で導入を検討する際の参考にしてください。
ディスカウントストアを展開する株式会社トライアルホールディングスは、リテールAIカメラを活用したユニークな取り組みで成果を上げています。店内に設置したAIカメラが商品棚を常時監視し、商品の在庫が少なくなると自動で検知してスタッフの持つ端末に補充指示を送るシステムを構築しました。この「欠品検知ソリューション」により、欠品による機会損失を削減することに成功しています。
さらに顧客の店内での動き(動線)を分析し、最適な商品配置や売場づくりにも活用している点が特徴です。この取り組みは全国の店舗に約5万台という大規模なAIカメラ網を構築することで実現しており、店舗運営の効率化と顧客体験の向上を両立させています。
出典参照:日本初!スマートレジカート・スマートカメラを導入した革新的なスーパーマーケットが福岡に誕生!|株式会社トライアルホールディングス
ホームセンター大手の株式会社カインズは、需要予測・自動発注システム「CAINZ-Demand-Forecasting-System」を導入し、在庫の最適化に取り組んでいます。このシステムは過去の販売実績や商品特性、販促計画などのデータを基にAIが需要を予測し、店舗ごとの最適な在庫量を算出するものです。
この取り組みにより欠品率を改善しつつ、在庫回転率を向上させるなど、大きな成果を上げています。このシステムは約40万点にも及ぶ膨大な商品を対象としており、従業員の作業負荷を軽減し、より創造的な業務に集中できる環境づくりにも貢献しています。将来的には天候やイベント情報などの外部データも活用し、さらなる精度向上を目指しています。
出典参照:P&Gとカインズ 包括的なサプライチェーン協働を強化|株式会社カインズ
株式会社マルイはAIによる需要予測ソリューション「AI-Order Foresight」を導入し、特に惣菜部門での発注業務改革に成功しました。天候や曜日、イベントなどの条件をAIが分析し、惣菜の品目ごとに最適な製造数を予測します。これにより担当者の経験に頼っていた発注業務の精度が向上し、食品ロスの削減に貢献しました。
同時に、発注にかかる作業時間を短縮することにも成功しており、業務効率化と販売精度の両面で成果を上げています。特に天候や時間帯によって需要が大きく変動する惣菜部門での成功は、予測分析の有効性を示す好例といえるでしょう。
出典参照:マルイ、日本IBMのAI需要予測を活用し、客数と販売予測精度の向上と発注時間の大幅な削減を実証|株式会社マルイ
予測分析の導入を成功させるためには、事前の準備が非常に重要です。ツールを導入する前に、以下の3つのポイントを必ず確認しておきましょう。
まず最も重要なのは、「予測分析を使って、何を解決したいのか?」という目的を明確にすることです。「在庫を最適化したい」「発注業務を効率化したい」「食品ロスを10%削減したい」など、具体的な課題や目標を設定しましょう。目的が曖昧なままツールを導入しても、思うような効果は得られにくいものです。
予測分析はあくまで課題解決のための手段であり、導入そのものが目的にならないよう注意が必要です。解決したい課題が明確であれば、どのようなデータが必要で、どのツールが最適なのかもおのずと見えてきます。
予測分析の精度はデータの質と量で決まります。特に、POSデータ(販売実績)と在庫データは分析の根幹となるため、これらが正確に、かつ継続的に収集できる体制が整っているかを確認することが大切です。データが店舗ごとにバラバラの形式で管理されていたり、そもそもデータが蓄積されていなかったりする場合は、まずデータを一元管理し、整備するところから始める必要があるでしょう。
「Garbage In, Garbage Out(ゴミからはゴミしか生まれない)」という言葉があるように、不正確なデータからは精度の低い予測しか生まれません。データの正確性を担保する仕組みづくりも同時に検討することが望ましいです。
予測分析は、ツールを導入すれば終わりではありません。分析結果を解釈し、実際の業務に活かしていくための推進体制が求められます。必ずしもデータサイエンティストのような専門家が必要なわけではありませんが、DX推進室や各部門の担当者など、プロジェクトを主導するメンバーを決めることが重要です。
また、現場のスタッフが予測結果をスムーズに活用できるよう、導入の目的やメリットを丁寧に説明し、協力体制を築くことも成功の鍵となります。経営層がDX推進の旗振り役となり、全社的な協力体制を後押しすることも、プロジェクトを円滑に進める上で大きな力となるでしょう。
このセクションでは、実際に予測分析を導入する際の具体的な手順を4つのステップに分けて解説します。
予測分析の導入プロジェクトを始めるにあたり、最初のステップは目的の明確化と、その達成度を測るためのKPI(重要業績評価指標)の設定です。これはプロジェクト全体の方向性を定める重要な工程です。
例えば「在庫最適化による収益改善」を目的とするならば、KPIには「在庫回転率の〇%向上」「欠品率の〇%低下」「廃棄ロス額の〇%削減」といった、具体的で測定可能な数値を設定します。
このKPIがあることで、導入後に「どれだけの効果があったのか」を客観的に評価し、投資対効果を明確にすることが可能になります。設定したKPIは経営層への報告だけでなく、現場スタッフと目標を共有するためにも活用します。
分析に必要なデータを集めたら、次はその「質」を高める工程に入ります。収集したデータには入力ミスによる異常な数値(外れ値)や、記録漏れによる欠損データ、表記の揺れ(例:「商品A」と「ショウヒンA」)などが含まれていることが一般的です。
これらの不正確なデータをそのまま分析に使うと、予測結果も不正確なものになってしまいます。そのため外れ値を除去したり、欠損しているデータを平均値などで補ったり、表記を統一したりする「データクレンジング」という地道な作業が不可欠です。
さらに、クレンジング後のデータをAIが学習しやすい形式に加工する「前処理」も行います。この工程は、最終的な予測モデルの精度を大きく左右する非常に重要なステップであり、専門家の支援を受けながら丁寧に進めることが推奨されます。
データの準備が整ったら、予測モデルの構築に入ります。予測モデルとはデータから未来を予測するための計算式やルールのことで、その中核には様々なAIアルゴリズムが存在します。
どのアルゴリズムを選ぶかは、解決したい課題によって異なります。例えば、季節による売上の変動を予測したい場合は「時系列分析モデル」が、複数の要因が売上にどう影響するかを見たい場合は「回帰モデル」が使われるなど、目的に応じて最適なモデルを選定することが重要です。
このステップは専門知識を要する場合が多いため、AIツールベンダーや専門家と協力しながら進めるのが一般的です。自社の課題やデータの特性を正確に共有し、最適な予測モデルを構築していくことが成功への近道となるでしょう。
予測モデルが完成しても、すぐに全社展開するのはリスクが伴います。そこで推奨されるのが、まずは特定の店舗や商品カテゴリに限定して試験的に導入する「スモールスタート」というアプローチです。
この方法により初期投資を抑えつつ、実際の業務環境で予測モデルがどの程度の精度を発揮するのか、現場のオペレーションに問題はないかといった点を安全に検証できます。この検証段階はPoC(Proof of Concept:概念実証)とも呼ばれます。
ここで得られた知見や課題を基にモデルや運用方法を改善し、成功の確率を高めてから段階的に対象範囲を広げていくことで、全社展開時の失敗リスクを大幅に低減させることが可能になります。

予測分析を実現するためのツールやサービスは数多く存在します。このセクションでは代表的なツールの種類と、自社に合ったツールを選ぶ際のポイントを解説します。
予測分析ツールのなかでも、特に小売業の需要予測や在庫最適化といった課題に特化して開発された製品があります。これらは、POSデータや天気といった業界特有のデータを扱うことを前提に設計されているのが大きな特徴です。
専門的な知識がなくても、画面の指示に従って操作するだけで、比較的簡単に高精度な予測モデルを構築できるものが多く見られます。
「まずは在庫問題を解決したい」といった明確な目的があり、迅速に成果を出したいと考えている企業にとって、特化型ツールは非常に有力な選択肢となるでしょう。
BI(ビジネスインテリジェンス)ツールは企業が持つデータを可視化し、経営状況を把握するためのツールです。多くのBIツールには簡易的な予測機能が搭載されていたり、外部のAIツールと連携したりする機能が備わっている場合があります。
もし社内で既にBIツールが活用されているのであれば、その延長線上で予測分析を始めることは、導入のハードルを下げる有効なアプローチです。
既存のデータ基盤や使い慣れたインターフェースを活用できるため、コストや学習時間を抑えられる可能性があります。ただし、より高度な分析には専門ツールとの連携も視野に入れると良いでしょう。
最適なツールを選ぶには、いくつかの基準で比較検討することが重要です。まず「課題解決への適合性」です。自社の目的、例えば「需要予測だけできれば良いのか」「発注の自動化まで見据えるのか」によって、必要な機能は大きく異なります。自社のゴールを達成できる機能が備わっているかを最初に見極めましょう。
次に「使いやすさとサポート体制」も大切です。実際にツールを使う現場の担当者が直感的に操作できるか、また導入後に不明点が出てきた際に、気軽に相談できるサポート体制が整っているかを確認します。
最後に「コストと費用対効果」の視点です。初期費用や月額利用料といったトータルコストと、導入で得られるメリット(廃棄ロス削減額など)を比較し、投資に見合うかを慎重に判断することが求められます。
予測分析は、単なる業務効率化ツールではありません。その本質は勘や経験に頼った経営から脱却し、データという客観的な根拠に基づいて未来を見通す「データドリブン経営」を実現することにあります。
変化の激しい市場においてデータに基づいた迅速な意思決定は、企業の競争力を大きく左右します。予測分析という羅針盤を手にすることで、持続的な成長の基盤を築くことができるでしょう。
まずは自社の課題を洗い出し、予測分析活用の第一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
