小売DXの第一歩はペーパーレス化!メリットや書類管理の課題を解説
小売

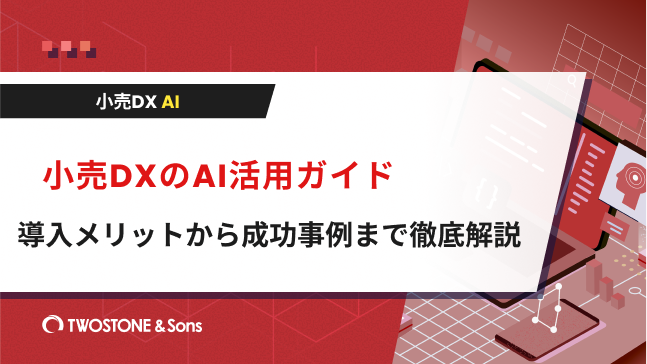
小売業でAIをどう活用?本記事では、AI導入で実現できることやメリット・デメリットを解説します。トライアルやイオンなどの成功事例から、導入を成功させるための具体的な4ステップ、さらには活用できる補助金制度まで、DX担当者が知りたい情報を網羅的にご紹介します。


・6万名以上のエンジニアネットワークを活用して課題を解決※
・貴社のDX戦略立案から実行・開発までワンストップで支援可能
※エンジニア数は2026年8月期 第1四半期決算説明資料に基づきます。
小売業界で深刻化する人手不足や激化する競争環境のなか、「AIを活用して新たな活路を見出したい」と考える方は多いのではないでしょうか。
しかしAIで具体的に何ができるのか、どうすれば導入を成功させられるのか、情報収集に課題を感じてしまうのも事実です。特に業務への適用範囲やコスト面、既存システムとの連携など、不安要素が多く足踏みしている企業も少なくありません。
一方で、実際にAIを導入して業務効率化や売上向上、廃棄ロス削減といった成果を上げている小売企業も着実に増えています。
この記事では、具体的な企業の成功事例を交えながら、小売DXにおけるAI活用の全体像を分かりやすく解説します。ぜひ参考にしてください。

AI技術は小売業が抱える発注、在庫、接客といった様々な課題を解決する力を持っています。AIが店舗運営やマーケティングをどのように変革するのか、具体的な活用シーンを理解することで自社の課題解決に繋がるヒントが見つかるはずです。
このセクションでは、5つの代表的な活用方法を詳しく見ていきましょう。
AIによる高精度な需要予測と発注の自動化は、小売業の収益性を大きく左右する重要な技術です。従来、担当者の経験と勘に頼っていた発注業務は、欠品による機会損失や過剰在庫による廃棄ロスといった課題を常に抱えていました。
AIは過去の販売実績や天候、イベント情報、SNSのトレンドといった膨大なデータを分析し、人間では見抜けなかったパターンを学習します。これにより、特定の商品が「いつ、どれくらい売れるのか」を高い精度で予測し、最適な発注量を自動で算出することが可能になります。
この仕組みは担当者を複雑な発注業務から解放するだけでなく、店舗の販売機会を最大化し、同時に過剰在庫を抑制するという経営の根幹に関わる問題を解決に導きます。
AIは需要予測と緊密に連携して在庫管理の精度を飛躍的に向上させ、社会問題ともなっている食品ロスや廃棄ロスの削減に大きく貢献します。
AIを活用した在庫管理システムは、各店舗や倉庫にある在庫数をリアルタイムで正確に把握し可視化します。そして高精度な需要予測データと照らし合わせることで、「どの商品を、どの店舗に、いつ、どれだけ配置すべきか」という最適な在庫配分を自動で導き出します。
さらに消費期限が迫っている商品に対しては、AIが最適な値引き率と実行タイミングを提案することも可能です。これにより、廃棄せざるを得なかった商品を効率的に売り切り、損失を最小限に抑えることができるのです。
ダイナミックプライシングとは、需要と供給のバランスに応じて商品の価格をリアルタイムで変動させる価格戦略のことです。AI技術の活用により、この先進的な手法を自動かつ科学的な根拠に基づいて実行できます。
AIは在庫状況や競合店の価格、天候、時間帯、さらには周辺のイベント情報といった、価格に影響を与える無数の要因を常に監視・分析します。そして、利益が最大化されると予測される最適な価格を瞬時に算出し、電子棚札などと連携して自動で価格表示を変更します。
これにより需要が高い時には価格を上げて収益性を高め、需要が低い時には価格を下げて販売機会の損失を防ぐといった、柔軟で戦略的な価格設定が実現します。
AIは顧客一人ひとりのニーズを深く理解し、パーソナライズされた体験を提供することで顧客満足度の向上とファンの育成に貢献します。
例えば顧客の過去の購買履歴やアプリの閲覧履歴、店内の行動データなどをAIが分析し、その顧客が次に関心を持つであろう商品やクーポンをスマートフォンのアプリやデジタルサイネージを通じて最適なタイミングで提案します。
またWebサイトやアプリにAIチャットボットを導入すれば、24時間365日、顧客からの在庫問い合わせや店舗情報に関する質問に即座に自動応答できます。こうしたきめ細やかな対応は、顧客に「自分のことを理解してくれている」という特別感を与え、店舗への信頼と愛着を深めることに繋がります。
店内に設置されたAIカメラは、もはや単なる防犯用途のデバイスではありません。映像をリアルタイムで解析する「知能を持った目」として店舗運営を劇的に効率化し、売上向上に貢献するデータを提供します。
AIは顧客が店内をどのように移動し、どの棚の前で足を止め、どの商品を手に取ったかを分析します。このデータは顧客にとって魅力的な売り場レイアウトや効果的な商品陳列を考える上で、客観的で強力な根拠となります。
さらに商品棚を常時監視し、商品が少なくなったり欠品したりした際に、スタッフの持つ端末へ即座に通知を送ることも可能です。これにより迅速な商品補充が実現し、販売機会の損失を未然に防ぐことができるのです。
国内の多くの小売企業が、すでにAIを導入して具体的な成果を上げています。このセクションでは、特に先進的な取り組みで知られる4社の事例を紹介します。
各社がどのような課題に対し、AI技術をどう活用しているのかを見ていきましょう。
トライアルカンパニーはAIカメラとスマートショッピングカートを活用し、顧客の動線や購買行動をデータ化しています。
AIカメラでは店内の顧客行動や棚前の動きなどを記録・分析し、欠品の検知や棚割り改善に活用。スマートカートでは顧客がカートに入れた商品データを取得し、購買履歴と組み合わせた売場改善や発注業務の効率化に役立てています。
こうしたデータ活用により、店舗運営の高度化を進めています。
出典参照:リテールDX挑戦事例紹介(P.23-45)|トライアルホールディングス
イオンリテールではAIを活用した需要予測システムを導入し、食品の販売計画や発注業務の最適化を進めています。
気象情報や曜日、過去の販売実績などをAIが分析し、翌日の販売予測を自動で算出。店舗スタッフの経験則だけに頼らない仕組みとすることで食品ロスの削減や欠品防止、業務効率化に繋げています。
2023年4月時点で全国約360店舗に導入され、効果が広がっています。
出典参照:ニュースリリース|イオンリテール株式会社
ウエルシア薬局は顧客の購買傾向に合わせて、最適なタイミングでクーポンや販促情報を届けるAI販促施策に取り組んでいます。
従来のような一律配信ではなく、顧客ごとに購買履歴を分析し個別にカスタマイズした情報を提供する仕組みを導入。2024年4月には、こうしたAIによる販促の自動化を本格的に推進する方針を発表しました。
お客さまにとって価値のある情報を届けることで、利便性向上と販売促進の両立を目指しています。
出典参照:ウエルシアがTrue DataのAI販促ソリューションを導入|ウエルシアホールディングス株式会社
ミスターマックスは、商品登録業務と売場状況の可視化にAIを活用しています。
商品画像から自動で情報を読み取り、商品マスタへ登録するAIサービスを導入し、従来手作業で行っていた業務を効率化。さらに、AIが各店舗の売場状況を可視化したレポートを自動作成することで、売場作りに関わる現場業務の省力化を図っています。
これらの取り組みにより従来手作業で行っていた商品登録や売場状況の把握が効率化され、現場の負担軽減に貢献しています。
出典参照:総合ディスカウントストアのミスターマックス、生成AI活用による企業変革を実現する「Graffer AI Solution」を本部の全部署で導入|株式会社ミスターマックス・ホールディングス

AIの導入は小売業に多くの恩恵をもたらします。業務の効率化やコスト削減といった直接的な効果だけでなく、データに基づいた新たな価値創出を可能にします。
このセクションでは、代表的な4つのメリットについて解説します。
AIはこれまで人間が行ってきた定型的・反復的な業務を自動化し、深刻化する人手不足の問題を解決する強力な一手となります。
例えば複雑な判断が求められる発注業務や在庫管理をAIに任せることで、従業員は接客や売り場作りといった、より付加価値の高い人間にしかできない業務に集中できるようになります。
またセルフレジや無人レジの導入は、レジ業務を省人化し顧客の待ち時間を短縮させます。これにより顧客満足度を高めると同時に、スタッフを他の業務に再配置することが可能となり、店舗全体の生産性向上に繋がるのです。
AIの最大の強みの一つは、勘や経験といった主観的な要素をなくし、客観的なデータに基づいた再現性の高い意思決定を可能にすることです。
AIによる高精度な需要予測は欠品による販売機会の損失を最小限に抑え、売上の最大化に直接的に貢献します。売れる商品を売れる時に、売れる数だけ用意するという、商売の理想形に近づけることができます。
さらに顧客一人ひとりの購買傾向をAIが分析し、その顧客が興味を持つ可能性の高い商品やクーポンを提案するパーソナライズドマーケティングも実現可能です。これにより顧客の購買意欲を効果的に刺激し、客単価の向上に繋げることができます。
AIは顧客一人ひとりにとって快適で便利な買い物体験を創出し、顧客満足度を高めることで店舗への愛着や信頼といった、いわゆるロイヤルティを強化します。
無人レジやスマートショッピングカートは、会計時の行列や待ち時間といった顧客のストレスを大幅に軽減します。またAIによる的確なレコメンデーションは、「自分のことを分かってくれている」という特別感を生み出し、顧客の心を掴みます。
さらにAIチャットボットが24時間いつでも疑問に答えてくれる安心感は、顧客の利便性を大きく向上させます。これらの優れた顧客体験の積み重ねによって、リピーターの増加と安定した店舗経営に繋がっていくのです。
AIによる精度の高い需要予測と在庫管理は、企業の収益改善だけでなく、社会的な課題でもある食品ロスや廃棄ロスの削減に直結します。
必要なものを必要な時に、必要なだけ仕入れるというデータに基づいた最適なサプライチェーンを構築することで、売れ残りによる廃棄を大幅に減らすことが可能です。
またAIが消費期限の近い商品の在庫状況や販売データを分析し、最適なタイミングで値引きを提案することで商品を売り切りやすくなります。
これは企業の収益性を高めると同時に環境負荷を低減し、企業の社会的責任(CSR)を果たす上でも非常に重要な取り組みです。
AI導入には多くのメリットがある一方で、事前に理解し対策を講じておくべきデメリットや課題も存在します。
計画段階でこれらのリスクを直視することが、プロジェクトの成功確率を高めます。
AIシステムの導入には、初期費用として高額なコストがかかる場合があります。AIツールやソフトウェアのライセンス料、AIカメラやサーバーといったハードウェアの購入費用などがこれにあたります。
また、自社の業務に合わせてシステムをカスタマイズする場合、追加の開発費用が発生します。さらに導入後もシステムのメンテナンスやデータの管理、クラウドサービスの利用料といった運用・保守費用が継続的に発生することも忘れてはなりません。
これらのコストを事前に正確に見積もり、後述する費用対効果を慎重に検討することが導入の意思決定において不可欠です。
AIを効果的に活用するためには、専門的な知識を持つ人材とAIの学習に不可欠な質の高いデータ、この二つが揃っている必要があります。
AIの知見を持ちビジネス課題を解決できるデータサイエンティストやAIエンジニアは、社会全体で需要が高く、採用や育成が難しいのが現状です。またAIの予測精度や分析能力は、学習させるデータの質と量に大きく依存します。
POSデータや在庫データ、顧客データなどが部署ごとに分散していたり、データ形式が不揃いだったりすると、AIはその性能を十分に発揮できません。導入プロジェクトを始める前に、まず自社にどのようなデータ資産があるのかを棚卸し、それを整備する計画を立てることが成功の鍵となります。
多くの企業では、すでに受発注システムや会計システム、顧客管理システムなど様々なITシステムが稼働しています。
新たにAIシステムを導入する際には、これらの既存システムとデータをスムーズに連携させ、業務プロセス全体を最適化する必要があります。しかしシステムの仕様が古かったり、ベンダーが異なっていたりすると、連携のための開発が複雑化し想定以上の時間とコストを要する可能性があります。
導入を検討するAIツールが現在使用しているシステムと連携可能かどうか、技術的な課題はないかを事前に確認しておくことが極めて重要です。
AIは顧客の購買履歴や個人情報、店舗の売上データなど、非常に機密性の高い情報を大量に扱います。
そのため、外部からのサイバー攻撃や不正アクセスに対する万全のセキュリティ対策が求められます。万が一情報漏洩が発生すれば、金銭的な損害だけでなく、企業の社会的信用を大きく損なう事態に発展しかねません。
またAIカメラで顧客の行動を分析する際には、個人情報保護法や関連ガイドラインを遵守することが絶対条件です。データの匿名化処理を行うなど、顧客に不安を与えないようプライバシー保護に最大限配慮した運用が不可欠となります。
AI導入を成功させるためには思いつきで進めるのではなく、計画的なアプローチが不可欠です。特に「PoC」と呼ばれる手法を取り入れ、小さな成功を積み重ねながら進めるのが一般的です。
このセクションでは、その基本的な4つのステップを解説します。
AI導入プロジェクトの成否は、最初のステップである課題設定で決まると言っても過言ではありません。「AIを導入すること」自体が目的とならないよう注意が必要です。
まずは、「AIを使って何を解決したいのか」という自社の課題を明確にします。「人手不足で困っている」といった漠然としたものではなく、「夕方の惣菜コーナーの品出しが間に合わず機会損失が出ている」のように、具体的で解像度の高い課題を設定することが重要です。
そしてその課題に対し、「廃棄ロスを月間50万円削減する」「発注業務にかかる時間を1日30分短縮する」といった、数値で測定可能な目標(KPI)を定めることでプロジェクトの進捗と成果を客観的に評価できるようになります。
ステップ1で設定した目標を達成するためにどのようなデータが必要かを洗い出し、それを収集・整備する工程に入ります。AIの性能は学習データの質と量に大きく左右されるため、このステップはプロジェクトの土台を作る重要な作業です。
例えば需要予測を行うのであれば、過去の販売実績(POSデータ)や在庫データ、天候データ、地域のイベント情報などが必要になります。社内の様々なシステムに散在するデータを集約し、欠損や重複、表記の揺れなどを修正して、AIが学習しやすいように整える作業が求められます。
同時に収集したデータを保管し、AIが高速に分析処理を行うためのITインフラ(サーバーやクラウド環境など)を準備することも必要です。
PoC(Proof of Concept:概念実証)とは、本格的な導入の前に限定された小規模な環境でAIの有効性を検証する試みのことです。いきなり全店舗に多額の投資をするのではなく、まずは小さく試して本当に効果があるのかを見極めます。
例えば、「1店舗の特定の商品カテゴリだけ」にAIによる需要予測を適用してみるといった形でスモールスタートします。そして一定期間テスト運用を行い、ステップ1で設定したKPI(予測精度や廃棄ロス削減額など)が達成できるか、客観的なデータで評価します。
このPoCを通じて本格導入に向けた課題を洗い出し、改善に繋げることができます。これにより大きな失敗のリスクを回避し、確信を持って次のステップに進むことが可能になります。
PoCで有効性が確認でき改善点が洗い出せたら、いよいよ本格的な導入フェーズへと移行します。
PoCの結果を踏まえてシステムを改修し、対象店舗や商品カテゴリを段階的に拡大していきます。一気に全社展開するのではなくエリアごとや業態ごとなど、管理できる範囲で徐々に広げていくのが安全策です。この際、新しいシステムを実際に使う現場の従業員への丁寧な説明とトレーニングが欠かせません。
そして最も重要なのは、AIは導入して終わりではないということです。運用開始後も定期的に効果を測定し、改善を繰り返すPDCAサイクルを回し続ける必要があります。市場や顧客のニーズは常に変化するため、AIモデルも継続的に再学習させ進化させていく姿勢が求められます。

AI導入プロジェクトは技術的な側面だけでなく、ビジネス戦略や組織運営の視点も同様に重要です。このセクションでは、導入を成功に導き、投資を無駄にしないための4つの重要なポイントを解説します。
AI導入の成否は、パートナーとなるベンダーやツールの選定に大きく左右されるため慎重な見極めが必要です。
まず自社と同じ小売業界での導入実績が豊富か、業界特有の課題を深く理解しているかを確認しましょう。その上で導入前のコンサルティングから導入後の運用サポートまで、手厚い体制が整っているベンダーを選ぶとプロジェクトを円滑に進めやすくなります。
また将来的に他のシステムと連携したり、分析項目を追加したりする可能性を考慮し、機能の拡張性や柔軟性が高いツールを選んでおくことも重要です。複数のベンダーから話を聞き、自社の課題と文化に最もフィットするパートナーを選びましょう。
AI導入には相応のコストがかかるため、どれくらいの投資でどれくらいのリターンが見込めるのか、すなわち費用対効果(ROI)を具体的に試算することが不可欠です。
まずシステムの導入費用や開発費用、月々の運用費用など、AI導入にかかる全てのコストを洗い出し、「投資(Investment)」額を算出します。次いで「人件費の削減額」「廃棄ロス削減額」「売上向上額」など、AI導入によって得られる金銭的なメリットを可能な限り数値化し「効果(Return)」を算出します。
このROI試算は、経営層から導入の承認を得るための客観的で強力な説得材料となります。また、「顧客満足度の向上」といった数値化しにくい定性的な効果も判断材料として忘れずに加えましょう。
いきなり大規模な投資をして全社展開を目指すのは、非常にリスクの高いアプローチです。前述の「PoC(概念実証)」の考え方に基づき、まずは特定の店舗や部門、商品カテゴリなどに限定して小規模に始める「スモールスタート」を強く推奨します。
このアプローチの最大のメリットは、リスクの最小化です。もし計画通りに効果が出なくても、投資額が小さいため経営へのダメージを最小限に抑えられます。
また小さな範囲で成功事例を作ることで、社内でのAIに対する懐疑的な見方を払拭し、協力体制を築きやすくなります。スモールスタートで得られた知見や課題を次のステップに活かすことで、より精度の高いシステムをより確実性の高い方法で展開していくことができるのです。
AIシステムを実際に活用し日々の業務を変えていくのは、本社の企画部門ではなく、店舗で働く現場の従業員です。そのため、現場の協力なくしてAI導入の成功はありえません。
まず「なぜAIを導入するのか」「導入によって現場の業務がどう楽になるのか」といった目的やメリットを現場の言葉で丁寧に説明し、理解と共感を得ることが全ての始まりです。
またシステム開発の初期段階から現場のスタッフにヒアリングを行い、彼らの意見や要望を積極的に機能に反映させましょう。「使いにくい」と思われたシステムは、どんなに高機能でも形骸化してしまいます。トップダウンで導入を押し付けるのではなく、現場をプロジェクトの主役として巻き込み一体となって進める姿勢が成功の鍵を握ります。
小売業向けのAIツールは、その目的や機能によって様々な種類が存在します。
このセクションでは、代表的な4つのカテゴリに分けて、どのようなツールがあるのかをご紹介します。自社の課題がどのカテゴリに当てはまるかを考えながらご覧ください。
このカテゴリのツールは小売業の根幹業務である発注や在庫管理の精度を向上させ、収益改善に直結することを目的としています。
主な機能として過去の販売実績や天候、イベント情報などを基にした高精度な需要予測やその予測に基づいた、最適発注量の自動計算が挙げられます。
また店舗間や倉庫との在庫配分を最適化したり、消費期限を考慮して廃棄ロスを削減したりする機能も備わっています。
店内に設置したカメラの映像をAIが解析し、これまで可視化できなかった店舗の状況をデータ化することで運営改善に繋げるソリューションです。
顧客の動線や滞在時間を分析して売り場レイアウトの改善に役立てたり、商品棚を監視して欠品や品薄を自動で検知したりします。
その他にも、来店客の属性(年齢・性別など)を分析してマーケティング施策に活かしたり、レジ待ちの行列を検知してスタッフに通知したりと多様な機能があります。
MA(マーケティングオートメーション)やCRM(顧客関係管理)といったツールにAIを組み込むことで、顧客一人ひとりへのアプローチを高度化・自動化します。
AIが顧客の購買データを分析し将来の購買や離反の可能性を予測したり、顧客セグメントごとに最も効果的なキャンペーンを提案することができます。
これによりパーソナライズされたメールやクーポンを最適なタイミングで自動配信したり、Webサイトやアプリで個々の顧客に合わせた商品をレコメンドしたりすることが可能になります。
Webサイトやアプリ上で顧客からの問い合わせに24時間365日、自動で対応したり、遠隔からの接客を支援したりするツールです。
「よくある質問」への自動応答や在庫確認、店舗案内などを自動化することで、カスタマーサポートの業務負担を大幅に軽減します。解決が難しい問い合わせは、スムーズに有人オペレーターへ引き継ぐ機能も備わっています。
また顧客との対話データを分析することで、顧客が抱える潜在的なニーズや不満を把握しサービス改善に繋げることも可能です。
AIの導入には一定のコストがかかりますが、国や地方自治体が提供する補助金を活用することでその負担を大幅に軽減できる場合があります。制度は頻繁に更新されるため、常に最新の情報を確認することが重要です。
代表的な補助金として、中小企業や小規模事業者を対象とした「IT導入補助金」が挙げられます。これは企業が自社の課題解決のためにITツールを導入する際、その経費の一部を国が補助する制度です。AIを活用した需要予測ツールやCRMツールなども対象となる場合があります。
公募要領や対象となるITツールは公式サイトで公開されているため、導入を検討しているツールが対象になるかを確認してみましょう。
出典参照:IT導入補助金2025|サービス等生産性向上IT導入支援事業事務局
本記事では小売業におけるAI活用について、その可能性から具体的な導入事例、成功のポイントまでを網羅的に解説しました。
AIはもはや遠い未来の技術ではなく、人手不足や競争激化といった、小売業がまさに今直面している課題を解決するための現実的で強力なソリューションです。高精度な需要予測、店舗運営の効率化、パーソナライズされた販促など、その活用範囲は無限の可能性を秘めています。
もちろん導入にはコストや専門知識といったハードルも存在します。しかしスモールスタートで小さな成功体験を積み重ね、自社に合ったパートナーを選び、現場と一体となってプロジェクトを進めることでそのハードルは乗り越えられます。AI導入という未来への第一歩を、ぜひ踏み出してみてください。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
