小売DXの第一歩はペーパーレス化!メリットや書類管理の課題を解説
小売

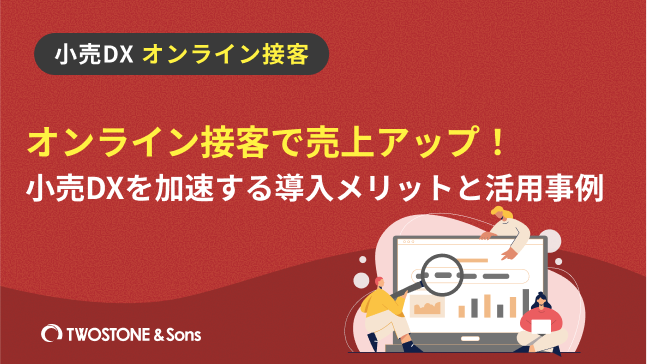
小売業のDXを推進する「オンライン接客」について、導入を検討中の担当者様へ向けて、そのメリットや種類、成功のポイントを解説します。アパレルや化粧品、百貨店など、業界別の具体的な活用事例も紹介。ECサイトの売上向上や新たな顧客体験の創出に関心のある方は、ぜひご覧ください。


・6万名以上のエンジニアネットワークを活用して課題を解決※
・貴社のDX戦略立案から実行・開発までワンストップで支援可能
※エンジニア数は2026年8月期 第1四半期決算説明資料に基づきます。
小売業界ではいま、「小売DX(デジタルトランスフォーメーション)」が重要な経営テーマとして注目を集めています。特に実店舗とECサイトの垣根が低くなった現在、顧客との接点をいかに統合し、質の高い体験を提供できるかが競争力を左右します。
その中で導入企業が増えているのが「オンライン接客」です。ビデオ通話やチャットを活用し、実店舗のようなパーソナルな接客をオンライン上で実現するこの手法は、売上向上や顧客ロイヤルティの強化にも直結するとして小売DXの中核施策のひとつとされています。
この記事ではオンライン接客の概要やメリット、業界別の活用事例、導入成功のポイントまでをわかりやすく解説します。小売DXを推進したい担当者の方は、ぜひ参考にしてください。
オンライン接客とはビデオ通話やチャットなどのデジタルツールを使って、販売スタッフがオンライン上で顧客とやり取りしながら接客を行う方法です。顧客は自宅などにいながら、まるで店舗にいるかのようなリアルな購買体験を得られるのが特徴です。
これは、ポップアップやチャットボットが自動応答する「Web接客」とは一線を画します。オンライン接客では専門知識を持った「人」が介在することで、顧客一人ひとりの細かな疑問に寄り添った温かみのある質の高いコミュニケーションが実現可能です。
このような質の高いコミュニケーションは、顧客の購買体験(CX)を大きく向上させることが期待できます。結果として顧客満足度が高まり、ブランドへの信頼や売上向上に繋がっていくでしょう。

オンライン接客の導入は、企業にとって多くのメリットをもたらす可能性があります。
このセクションでは、特に重要と考えられる「ECサイトの売上向上」「店舗への送客とオムニチャネル実現」「商圏の拡大」という3つの観点から、その利点を解説します。
オンライン接客は、ECサイトの売上向上に直結しやすい手法の一つです。スタッフがリアルタイムで顧客の質問に応え、商品の特徴や活用方法を説明することで購入前の不安や疑問を解消し、サイトからの離脱防止に繋がります。
さらに、顧客との対話を通じてニーズを把握することで、関連商品の提案(クロスセル)やより上位モデルへの誘導(アップセル)も可能となります。結果として顧客単価の向上やリピーター獲得に繋がり、EC運営における収益性を高める有効な施策と言えるでしょう。
オンライン接客はECサイトの売上向上だけでなく、実店舗との連携においても重要な役割を果たします。オンラインで事前に詳しい説明や相談を受けることで、顧客は安心して実店舗へ足を運ぶことができ店舗への送客効果が期待できるでしょう。
このようにオンラインとオフラインのチャネルを連携させ、顧客に一貫性のある購買体験を提供する戦略をオムニチャネルと呼びます。オンライン接客はまさにこのオンラインとオフラインの顧客接点を繋ぐハブとなり、チャネルを横断した質の高い顧客体験の構築に貢献します。
例えばECサイトで在庫切れの商品を実店舗で取り置きしたり、逆に店舗で接客した顧客に後日オンラインで追加提案を行ったりと、柔軟な連携が可能になります。
オンライン接客を導入することで、企業は物理的な店舗の立地に縛られることなく、ビジネスチャンスを大きく広げることが可能になります。これまで店舗がなかったエリアに住む顧客や、様々な事情で来店が困難だった顧客層にも自社の製品やサービスを届けられるようになるでしょう。
これは新たな顧客層の開拓に直結し、売上の増加に貢献する可能性があります。さらに店舗の営業時間外であっても、スタッフの勤務体制を工夫することで接客対応が可能になります。
これにより顧客が買いたいと思ったタイミングを逃さず、販売機会の損失を防ぐことにも繋がります。働き方の多様化や、人材の効率的な活用といった側面でもメリットが期待できるでしょう。
多くのメリットが期待できるオンライン接客ですが、導入にあたってはいくつかの課題も存在します。しかし、これらのデメリットは事前に対策を講じることで、その影響を最小限に抑えることが可能です。
このセクションでは、主なデメリットとその対策について解説します。
オンライン接客を始めるには、ツールの導入費用や月額利用料、接客を担当するスタッフの人件費など一定のコストが発生します。場合によっては、高画質な映像を配信するためのカメラやマイクといった機材の購入も必要になるかもしれません。
これらのコストを抑えるためには、まず自社の目的や規模に合った費用対効果の高いツールを慎重に選定することが重要です。
さらに最初から全社的に大規模導入するのではなく、特定の店舗や商品カテゴリーに絞って試験的に始める「スモールスタート」を心がけることが大切です。そうすることでリスクを抑えつつ効果を測定し、段階的に展開していくことができます。
オンラインでの接客は、対面とは異なる特有のスキルが求められます。画面越しで顧客の表情や反応を正確に読み取ったり、ツールの操作をスムーズに行ったりするには相応のトレーニングと慣れが必要になるでしょう。
この課題に対応するためには、ツールの基本的な使い方からオンラインでの効果的なコミュニケーション方法、よくある質問への対応策などを網羅した分かりやすい接客マニュアルを整備することが不可欠です。
その上で、スタッフ同士が顧客役と店員役に分かれて実践的な練習を繰り返す「ロールプレイング研修」などを定期的に実施し、スタッフ全体のスキルレベルを向上させていくことが成功の鍵となります。
ビデオ通話などを活用するオンライン接客は、店舗側と顧客側、双方のインターネット回線の速度や安定性にその品質が大きく左右されるという側面があります。接客中に映像が途切れたり音声が聞き取りづらくなったりすると、顧客にストレスを与えてしまい満足度の低下に直結しかねません。
対策として、店舗側では可能な限り安定した高速の通信インフラを整備することが望ましいです。
また予約制の接客サービスなどの場合は、事前に顧客へ通信環境の確認をお願いしたり、接続テストを案内したりといった配慮もスムーズな顧客体験を提供する上で有効な手段となるでしょう。
オンライン接客を実現するためのツールは、そのコミュニケーション方法によっていくつかの種類に分けられます。
それぞれに特徴があるため、自社が提供したいサービス内容やターゲット顧客、取り扱う商材に合わせて、最適なツールを選択することが重要です。
ビデオ通話型ツールは映像と音声を通じて、スタッフと顧客がリアルタイムで対話できるタイプのツールです。
まるで実店舗で対面しているかのような、きめ細やかでパーソナルな接客体験を提供できるのが最大の強みと言えるでしょう。スタッフと顧客がお互いの顔を見ながらコミュニケーションを取れるため、安心感が生まれ信頼関係を築きやすいと考えられます。
また商品の色合いや素材の質感といった、静止画やテキストだけでは伝わりにくい情報を映像を通して具体的に見せることが可能です。そのためアパレルや化粧品、家具といった、顧客が購入前に詳細な確認を求めることが多い商材に適していると言えます。
チャット型ツールは、テキストメッセージを主体として顧客とリアルタイムでコミュニケーションを行うツールです。顧客にとっては電話やビデオ通話に比べて心理的なハードルが低く、移動中や仕事の合間など、時間や場所を選ばずに気軽に質問できるという利点があります。
多くのツールではよくある質問に自動で回答する「チャットボット」機能と、複雑な問い合わせにスタッフが個別に対応する「有人チャット」機能を組み合わせることが可能です。
このハイブリッドな運用により、業務の効率化と顧客満足度の向上の両立が期待できるでしょう。
アバター接客ツールは、販売スタッフが自身の分身となるCGアバターを操作し顧客とコミュニケーションを取るという、比較的新しいタイプの接客ツールです。スタッフは自身の顔を出す必要がないため、プライバシーを確保しながら働くことができます。
また顧客側も直接人と対面する緊張感から解放され、より気軽に質問や相談がしやすくなるというメリットが考えられます。ブランドイメージに合わせたオリジナルのアバターを作成することで独自の世界観を演出し、ユニークな顧客体験を提供することも可能です。
商業施設の案内やショールームでの商品説明など、幅広いシーンでの活用が期待されるでしょう。
オンライン接客を導入する際は、ツール選定の前に設計段階での方針決定が重要になります。目的が曖昧なまま進めると、顧客にとって使いにくいサービスになったり、現場の運用負荷が高まったりする恐れがあります。
成果を出すには、何のために導入するのかを明確にした上で、顧客接点ごとに適したツールを選び、実店舗の接客フローを活かした導線を設計する必要があります。これらのポイントを押さえることで、顧客満足度と売上の両立が見込めるでしょう。
オンライン接客の目的は、大きく分けて売上支援と接客代替という2つです。売上支援では、購入を迷っている顧客に対して商品提案やコーディネート相談を行い、購買率を高めることを狙います。一方、接客代替は、実店舗に行けない顧客に対してオンラインで同等の接客体験を提供する役割を果たします。
この目的が曖昧だと、どの顧客にどのタイミングで接客を提供すべきか判断が困難です。売上向上を重視するなら、カート離脱率の高いページや高単価商品ページで積極的に声をかける設計が適しています。接客品質を重視するなら、予約制のビデオ接客で丁寧に対応する形が効果的でしょう。目的を明確にすることで、KPIの設定や運用体制の構築もスムーズに進みます。
オンライン接客のツールには、チャット型とビデオ通話型があり、それぞれ適した場面が異なります。チャット型は、気軽に質問できる手軽さが魅力で、サイズや在庫確認といった簡単な問い合わせに向いています。顧客は文字でやり取りできるため、心理的なハードルが低く、幅広い層に利用してもらいやすいでしょう。
一方、ビデオ通話型は、アパレルや化粧品など視覚的な説明が必要な商品で力を発揮します。スタッフが実際に商品を手に取って説明したり、顧客の要望に応じてコーディネート提案をしたりと、実店舗に近い接客が実現できます。顧客の購買段階や商品特性に応じてツールを使い分けることで、満足度の向上と業務効率化の両立が可能です。複数のツールを組み合わせて運用する企業も増えています。
オンライン接客を成功させるには、実店舗で培ってきた接客ノウハウを活かせる導線設計が重要になります。店舗では、入店から商品説明、試着提案、レジ対応まで一連の流れがあり、スタッフはそのフローに沿って接客しています。この流れをオンラインでも再現できるよう、顧客がどのページでどのタイミングで接客を必要とするか分析しましょう。
例えば、商品詳細ページの閲覧時間が長い顧客には、チャットで声をかけて疑問を解消する設計が有効です。また、カートに商品を入れたまま離脱した顧客には、後日メールで接客予約を案内する方法もあります。店舗スタッフがオンライン接客も担当する場合は、シフト管理や対応マニュアルの整備も必要でしょう。実店舗の強みをオンラインに移植することで、顧客体験の質が高まります。

オンライン接客はすでに様々な業界で導入が進んでおり、それぞれの特性を活かしたユニークな活用事例が生まれています。
このセクションではアパレル、化粧品、家具・家電、百貨店という4つの業界に焦点を当て、具体的な取り組みを紹介します。
アパレル業界では、オンライン接客が顧客一人ひとりのニーズに合わせたパーソナルなスタイリング提案を可能にしています。
例えばセレクトショップの「ベイクルーズ」では、ビデオ通話を用いて顧客が持っている服とのコーディネート相談に応じるサービスなどを展開しています。
またサイト上で各店舗スタッフのコーディネートを公開し、顧客が気に入ったスタッフを指名してオンラインで直接相談できるサービスも提供されています。
このような取り組みは、ECサイトでありながらまるで実店舗で信頼できるスタッフからアドバイスを受けるような特別な購買体験を創出し、顧客満足度と単価の向上に繋がっていると考えられます。
出典参照:お家でショップスタッフに相談ができる!Online Styling Service|株式会社ベイクルーズ
肌質や悩みなど専門的なカウンセリングが購入の決め手となることが多い化粧品業界においても、オンライン接客は非常に有効です。多くのブランドが美容部員によるオンラインでのカウンセリングサービスを提供しています。
例えば「オルビス」では、オンラインカウンセリングを導入しました。画面越しに顧客の肌の状態を確認しながら、最適なスキンケア方法やメイクのテクニックをアドバイスすることで高い満足度を得ています。
顧客は店舗に足を運ぶことなく自宅で専門的なアドバイスを受けられるため、新たな顧客体験の価値を創出していると言えるでしょう。
出典参照:いつでもどこでもORBISオンラインカウンセリング|オルビス株式会社
サイズが大きく高価格帯であることの多い家具や家電は、購入前の不安をいかに解消できるかが重要です。オンライン接客は、そのための効果的な手段として活用されています。
例えば家具・インテリア販売の「ニトリ」では、インテリアに関する相談をビデオ通話で行えるサービスを提供しています。
自宅の部屋を映しながら専門スタッフに相談できるため、より具体的で実践的な提案を受けることが可能です。
また家電量販店の「ビックカメラ」ではECサイト上で専門販売員がライブ形式で製品の実演販売を行い、使い方や性能を分かりやすく解説しています。
オンライン上で製品を立体的に見せつつ詳細なデモンストレーションを行うことで、顧客の疑問を解消し購買意欲を高める効果が期待できます。
出典参照:EC販売で差別化!オンライン接客支援サービス『接客オンデマンド』。ビックカメラ・ドットコムにおいて、オーディオメーカー製品のサービス導入を開始|株式会社ビックカメラ
豊富な品揃えと質の高い対面接客を強みとしてきた百貨店業界も、DXの一環としてオンライン接客に積極的に取り組んでいます。
代表的な事例として「三越伊勢丹」では、「三越伊勢丹リモートショッピング」という専用アプリを開発しました。このアプリを通じて、顧客はチャットやビデオ通話でスタイリスト(販売員)の接客を受けることができます。ブランドの垣根を越えた商品提案など、百貨店ならではのパーソナルな買い物体験が可能になっています。
オンライン接客を成功させるためには、思いつきで始めるのではなく、戦略的かつ計画的に導入プロセスを進めることが不可欠です。
このセクションでは、導入を成功に導くための具体的な4つのステップを解説します。
まず最初に、「なぜオンライン接客を導入するのか」という目的を明確にすることが最も重要です。目的が曖昧なままでは適切なツール選びや効果の測定ができず、プロジェクトが迷走してしまう可能性があります。
経済産業省が提唱する「デジタルガバナンス・コード」でも、デジタル施策における経営の目的・方針と成果指標の設定は、企業価値向上に向けた基本的な考え方とされています。
目的の例としては「ECサイトの購入率を向上させたい」「顧客単価を上げたい」などが考えられるでしょう。
目的が定まったら、その達成度を客観的に測るためのKPI(重要業績評価指標)を設定します。「購入率を3ヶ月で5%向上させる」「オンライン接客経由の平均顧客単価を2,000円アップさせる」 など、具体的かつ測定可能な目標を立てることが成功の鍵となります。
出典参照:デジタルガバナンス・コード3.0(P.7)|経済産業省
設定した目的とKPIを達成するためにどのような機能が必要かを考え、自社に最適なオンライン接客ツールを選定します。ビデオ通話機能は必須か、予約管理機能は必要か、既存の顧客管理システムと連携できるかなど具体的な要件を洗い出しましょう。
その上で複数のツールを機能、コスト、操作性、サポート体制といった観点から比較検討します。多くのツールでは無料トライアル期間が設けられているため、実際に試用してみてスタッフや顧客にとって使いやすいかどうかを確認することが推奨されます。
長期的な視点で自社のビジネスに最も貢献するツールを選ぶことが大切です。
優れたツールを導入しても、それを使うスタッフのスキルが伴わなければ質の高いオンライン接客は実現できません。そのためツールの導入と並行して、接客品質を標準化・向上させるための準備を進める必要があります。
具体的には、ツールの基本的な操作方法からオンラインでの話し方、画面映りのコツ、トラブル発生時の対応フローなどをまとめた接客マニュアルを作成します。
そしてそのマニュアルに基づいて、スタッフへの研修を実施します。特にスタッフ同士で顧客役と店員役を演じるロールプレイングは、実践的なスキルを身につける上で非常に効果的です。
すべての準備が整ったら、いよいよオンライン接客を開始します。しかし最初から全社的に展開するのではなく、まずは特定の店舗や商品、時間帯などに限定して小規模に始める「スモールスタート」が成功の鍵となります。
スモールスタートによって、実際の運用でしか見えてこない課題や改善点をリスクを抑えながら洗い出すことができます。そしてステップ1で設定したKPIを基に効果測定を行い、顧客アンケートやスタッフからのフィードバックを収集しましょう。
このデータ分析と改善のサイクル(PDCA)を回しながら、徐々にサービス提供の範囲を拡大していくことが成功への着実な道のりと言えるでしょう。

この記事で見てきたように、オンライン接客は単に実店舗での接客をデジタルに置き換えるだけの手法ではありません。ECサイトの売上向上に直接貢献するだけでなく、店舗への送客にもつながります。オンラインとオフラインを融合させたシームレスな顧客体験、つまりオムニチャネル戦略を推進するうえで中心的な役割を担っています。
さらに地理的な制約から解放されることでこれまでアプローチできなかった新たな顧客層との出会いを創出し、ビジネスの可能性を大きく広げるポテンシャルを秘めていると言えるでしょう。
導入にはコストや人材育成といった課題もありますが、明確な目的を持って計画的にステップを踏むことでその効果を最大限に引き出すことが可能です。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
