小売DXの第一歩はペーパーレス化!メリットや書類管理の課題を解説
小売

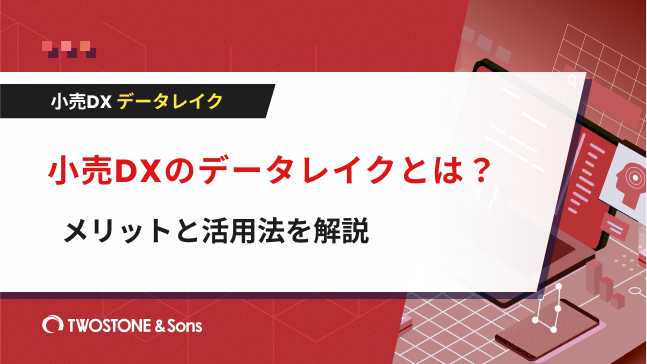
小売業のDX推進において、なぜ「データレイク」が重要視されるのか。本記事では、データレイクの基本的な定義から、DWHとの明確な違い、導入によるメリット、そして具体的な活用事例までを網羅的に解説します。散在するデータを統合し、データドリブンな意思決定を実現するための第一歩を、この記事から踏み出してください。


・6万名以上のエンジニアネットワークを活用して課題を解決※
・貴社のDX戦略立案から実行・開発までワンストップで支援可能
※エンジニア数は2026年8月期 第1四半期決算説明資料に基づきます。
デジタルトランスフォーメーション(DX)が経営の重要課題となる現代の小売業界において、顧客との接点はかつてないほど多様化しています。この状況で顧客を深く理解し最適な体験を提供するには、散在する膨大なデータを統合・活用する基盤が不可欠です。
その解決策として注目されるのが「データレイク」です。本記事では、小売企業のDX推進担当者に向けて、データレイクの基本からDWHとの違い、導入メリット、具体的な活用事例、構築ステップまでを専門的に解説します。
データレイクとは、湖(レイク)が様々な水源の水をそのまま受け入れるように、構造化・非構造化を問わずあらゆる形式のデータを元の形のまま一元的に保存できる貯蔵庫のことです。
このセクションでは、データレイクの概要について説明します。
データレイクが持つ大きな特徴の一つは「圧倒的な柔軟性」、すなわち扱うデータの種類を選ばない点にあります。
「構造化データ」(POSデータや顧客情報など、行と列で定義されたデータ)と、特定の形式を持たない「非構造化データ」(SNSの投稿、画像、音声、ログファイルなど)の両方を、区別なく一元的に管理できます。
企業の持つデータの大部分を占めるといわれる非構造化データも効率的に扱えるため、これまで見過ごされてきたデータからも価値ある知見を引き出す可能性を広げます。この包括的なデータ管理能力が、データレイクの大きな強みです。
データレイクのもう一つの重要な原則は、データを加工せずに「生データ」のまま格納することです。これは「スキーマ・オン・リード」と呼ばれ、データを読み込む(分析する)段階で初めて構造を定義します。
事前に厳密なデータ設計が不要なため、将来の活用法が未定なデータでも、とりあえず蓄積しておくことが可能です。生データをそのまま保持しておくことで、後から新しい分析手法を適用したり、過去のデータに遡って検証したりすることが容易になります。
この柔軟性が、変化の速いビジネス環境において、新たな分析の可能性を広げるのです。

データ活用基盤の構築を検討する過程で、データレイクとしばしば比較対象となるのが「データウェアハウス(DWH)」や「データマート」です。
それぞれの違いを解説します。
データ活用基盤は目的と用途で比較できます。データレイクは、将来の分析に備え多様な生データをそのまま蓄積し、データサイエンティストが未知の課題を発見するための「分析の砂場」です。
一方データウェアハウス(DWH)は、経営層などの意思決定支援が目的で、複数システムのデータを整理・統合し、BIツールでの定型レポートなどに使います。
さらにデータマートは、DWHから特定部門の目的に合わせて必要なデータだけを抽出した小規模なデータベースです。
データレイクとDWHの決定的な違いは、扱うデータ形式と処理方法にあります。
データレイクは構造化・非構造化を問わずあらゆる生データをそのまま格納し、分析時に構造を定義する「スキーマ・オン・リード」方式を採用しています。このため、多様なデータを柔軟に受け入れることが可能です。
一方、DWHが扱うのは基本的に構造化データのみです。データを投入する際にETL処理で事前に定義された形式へ加工する「スキーマ・オン・ライト」方式を採用し、データの品質と一貫性を担保します。
コストとパフォーマンスもデータレイクとDWHの重要な比較点です。
データレイクは安価なオブジェクトストレージを利用するため、大量のデータを低コストで保存できる傾向にあります。
一方、DWHは高速な分析性能のために高価なストレージや専用エンジンを利用することが多く、全体的なコストは高くなる傾向があります。
パフォーマンス面では、DWHはデータが事前に整理・最適化されているため、定型的なクエリに対して非常に高速なレスポンスを返せるのが特徴です。
最終的にデータレイクとDWHのどちらを選ぶべきか、あるいはどのように組み合わせるべきかは、「何を達成したいか」という目的で決めると良いでしょう。
AI活用や未知のインサイト発見など、多様な生データで先進的な分析をしたいならデータレイクが不可欠です。一方、売上などのKPIを定型レポートで可視化し、ビジネス部門がBIツールで分析する環境を整えたいなら、信頼性とパフォーマンスに優れたDWHが向いています。
現実的には、両者を排斥するのではなくそれぞれの長所を活かしたハイブリッド構成を採用する企業が増えています。
このセクションでは、小売業が共通して抱えるデータ活用の代表的な障壁について掘り下げていきます。
現代の消費者は実店舗、ECサイト、アプリ、SNSなど多様なチャネルを横断して購買活動を行います。この顧客接点の多様化は、企業が収集できるデータの種類と量を飛躍的に増大させました。
従来のPOSデータなどに加え、Web閲覧履歴やSNSの口コミといった膨大かつ多様な非構造化データが日々生まれています。
これらのデータをチャネルごとに分断したままでは、顧客の行動の全体像である「カスタマージャーニー」を正確に捉えることはできません。
多くの企業が抱える根深い課題が「データのサイロ化」です。これはデータが部門やシステムごとに分断され、組織全体で共有・活用できない状態を指します。
小売業でも「店舗の売上」「ECの履歴」「顧客情報」などが別々のシステムに閉じ込められているケースが多く見られます。このような状態では、部門を横断した包括的な分析が極めて困難になります。
データのサイロ化はビジネスチャンスの損失に直結し、全社的な意思決定を妨げる大きな要因となるのです。
このセクションでは、データレイクがもたらす具体的なメリットについて、3つの主要な観点から詳しく解説します。
データレイク導入による最も直接的かつ根本的なメリットは、社内に散在するあらゆるデータを、その形式を問わず一元的に集約できる点にあります。これまで部門ごと、システムごとにサイロ化されていたデータを、一つの「湖」に集約することが可能になります。
具体的には、店舗のPOSデータ、ECサイトの購買データ、Webサーバーのアクセスログといった社内のデータはもちろんのこと、SNS上の顧客の声や気象情報といった外部の非構造化データまで、ビジネスに関連する可能性のあるすべてのデータを一つの場所に蓄積できます。
このデータの一元化により、これまで不可能だった部門横断的な分析が容易になります。データを探し回る手間が省け、分析担当者が本来の業務であるインサイトの発見に集中できる環境が整います。
データレイクは、AI(人工知能)や機械学習との親和性が非常に高いという、将来を見据えた大きなメリットを持ちます。現代の高度なAIモデル、特にディープラーニングなどの技術はその精度を高めるために、膨大かつ多様な学習データを必要とします。
特に、画像やテキスト、音声といった非構造化データはAIモデルに新たな特徴量を与え、予測精度を飛躍的に向上させる上で不可欠です。データレイクは、まさにこのAI・機械学習のための「データの供給源」として理想的な環境を提供します。
加工前の生データを大量に蓄積しているため、データサイエンティストは様々な角度からデータを抽出し、モデルの学習に最適なデータセットを柔軟に作成することができるのです。
データレイクの導入は、最終的に企業の意思決定プロセスそのものを変革する力を持っています。
データレイクによって、組織内の誰もが必要なデータに迅速かつ容易にアクセスできるようになり、分析にかかる時間が大幅に短縮されることが期待できます。従来であれば、分析に必要なデータを各部門に依頼し、収集・統合・加工するまでに数週間から数ヶ月を要することも珍しくありませんでした。
しかしデータレイクがあれば、このプロセスが劇的に効率化され、ビジネスの現場で生まれた疑問に対して即座にデータを基にした回答を得ることが可能です。これにより、経験や勘だけに頼るのではなく、客観的なデータという共通言語に基づいて議論できます。データに基づいて次のアクションを決定する「データドリブンな意思決定」の文化が組織に根付いていくのです。
出典参照:DX白書2023|IPA 独立行政法人 情報処理推進機構
次に、データレイクの導入を成功させるために、事前に理解しておくべき注意点を解説していきます。
データレイク導入の有名な失敗例が「データスワンプ化」です。これは、様々なソースから無秩序にデータが投入され続けた結果、どこにどのようなデータが、どのような品質で存在するのか誰も分からなくなり、管理不能な「データの沼」と化す状態を指します。
データレイクの「あらゆるデータを受け入れる」という柔軟性が裏目に出る典型例です。データスワンプに陥ると、利用者は必要なデータを見つけられず、データの信頼性も担保されないため分析に活用できません。結果として、データレイクは価値を生まない単なるデータ置き場となり、ストレージコストだけが無駄にかかり続ける事態を招きます。
データスワンプ化を防ぎデータレイクを資産として活用するには、データガバナンス体制の構築が不可欠です。
データガバナンスとは、データのセキュリティ、品質、活用価値を維持・向上させるためのルールやプロセスのことです。これは組織全体で取り組むべき経営課題といえます。
具体的な施策として、まずはどこにどんなデータがあるかを示す「データカタログ」の整備が重要です。さらに、データの正確性や完全性を担保するための品質管理ルールを定め、継続的に監視・改善するプロセスを確立する必要があります。
データレイクからビジネス価値を引き出すには、専門知識を持つ人材が不可欠です。特に、従来のIT人材とは異なるスキルが求められます。
まず、多様なデータを収集・加工するパイプラインを構築できる「データエンジニア」。次に、膨大なデータからビジネス課題を解決する知見を見つけ出す「データアナリスト」や「データサイエンティスト」です。
彼らは統計学や機械学習を駆使して高度な分析を行います。しかし、こうした専門人材は市場で不足しており確保は容易ではありません。そのため、計画的な社内育成や外部リソースの活用が重要となります。
出典参照:DX白書2023|IPA 独立行政法人 情報処理推進機構

データレイクを導入・運用するときにかかる費用について解説します。
データレイク導入の初期構築費用は、主に3つの要素で構成されます。
第一に、AWS、GCP、Azureといったクラウドサービスの利用料です。これには基盤の初期設定や関連サービスのセットアップ費用が含まれます。
第二に、データ移行・統合費用です。既存システムからデータを抽出し、投入するためのパイプライン開発費やツールライセンス料、人件費が該当します。
第三に、コンサルティング・SIer費用です。社内に専門家がいない場合、要件定義や設計、構築を外部に依頼するための費用が必要となります。
データレイクは、構築後も継続的にランニングコストが発生します。最も大きな割合を占めるのがクラウドサービス利用料で、これは保存データ量に応じた「ストレージ費用」と、データ処理量に応じた「データ処理・転送費用」に分けられます。
次に、データ基盤の監視やパフォーマンス維持を担うエンジニア、データガバナンスを管理する担当者の保守・運用人件費も必要です。さらに、データカタログやETLツールなどをSaaS形式で利用している場合は、その年間ライセンス費用も考慮しなければなりません。
データレイクのコストは使い方で大きく変動するため、常に最適化を意識することが重要です。
コストを抑制し投資対効果を最大化するには、まず「スモールスタート」が基本です。特定の課題解決から小さく始め、効果を検証しながら段階的に拡大します。次に、技術的な工夫として「サーバーレスサービス」の活用も有効です。処理時間のみ課金されるためコストを抑えられます。
また「データのライフサイクル管理」も重要で、アクセス頻度の低い古いデータを安価なストレージへ自動的に移動させることで、ストレージコストを最適化できます。
出典参照:DX実践手引書|独立行政法人情報処理推進機構(IPA)
このセクションでは、小売業においてデータレイクが具体的にどのように活用され、競争力強化に繋がっているのか、代表的な4つの活用シナリオを掘り下げて解説します。
データレイク活用で大きな効果が期待できるのが、顧客分析によるLTV(顧客生涯価値)の最大化です。
LTVは顧客が取引期間全体でもたらす利益総額を示す経営指標です。データレイクでこれまでサイロ化されていたPOSデータ、ECサイトの閲覧・購入履歴、アプリ利用ログなどを顧客IDで統合します。これにより、顧客一人ひとりを360度の視点で深く理解することが可能になります。
複雑な条件で顧客をセグメント化し、離反の兆候を早期に発見することが可能です。パーソナライズされた施策で顧客との関係性を強化し、LTV向上を目指します。
小売業の長年の課題である在庫管理は、データレイクとAIの組み合わせで精度を飛躍的に向上できます。
適切な在庫管理は、「欠品による販売機会の損失」と「過剰在庫による廃棄ロス」という相反する二つの問題を同時に解決する鍵となります。データレイクを活用し、過去の販売実績に加え、天気予報やSNSのトレンド、競合店のセール情報といった多様な非構造化データをAIに学習させます。
これにより、人間では気づけない複雑な相関関係をAIが捉え、商品ごと・店舗ごとの需要をより高い精度で予測することが可能になるのです。
近年小売業界で注目されるOMOは、オンラインとオフラインの垣根をなくし、顧客にシームレスな購買体験を提供する戦略です。
この実現には、両チャネルのデータをリアルタイムで統合・連携させる顧客データ基盤が不可欠であり、データレイクがその心臓部を担います。
例えば、ECサイトで閲覧した商品情報を、顧客が来店した際に店舗スタッフの端末へリアルタイムで通知します。これにより、スタッフは顧客の興味に寄り添った接客ができます。このように、データレイクを中核にデータを統合することで、新しい顧客体験を創出できるのです。
データレイクは、顧客一人ひとりに合わせた高度なパーソナライズ施策の基盤となります。画一的なマスマーケティングから脱却し顧客満足度を最大化するには、個々の興味や状況を深く理解し、最適な情報や体験を最適なタイミングで提供することが重要です。
データレイクに集約された多様なデータを活用することで、このパーソナライゼーションのレベルを格段に引き上げられます。Web閲覧履歴や購買履歴などをリアルタイムで分析し、顧客の「今」の興味を推測することが可能になります。そのインサイトに基づき、最適な商品レコメンドやクーポンの配信ができるのです。
多くの企業で採用されている一般的な構築プロセスを5つのステップに分けて解説します。これらのステップを踏むことで失敗のリスクを低減し、ビジネス価値に繋がるデータレイクを実現することができるでしょう。
データレイク構築の最初の最重要ステップは、ビジネス目的の明確化です。技術導入が目的化しないよう、「優良顧客の離反率を5%削減する」といった具体的で測定可能なKPIを設定することが重要です。
目的が明確になったら、全社規模ではなく「スモールスタート」の範囲を決定します。目標達成に最も貢献する可能性が高い限定的な領域に焦点を絞るのです。
このアプローチにより、初期投資とリスクを抑えつつ早期に成功体験を積むことができ、データレイクの価値を社内に示しやすくなります。
スモールスタートの範囲が決定したら、本格的な構築に着手する前にPoC(Proof of Concept:概念実証)を実施することが強く推奨されます。
PoCとは、新しい概念やアイデア、技術が現実的に実現可能か、そして期待される効果をもたらすかを、小規模な環境で実際に試して検証するプロセスです。データレイクの文脈では、ステップ1で定めたスモールスタートの範囲内で実際にデータを収集・統合・分析し、ビジネス目標の達成に本当に貢献できるかを事前に検証する活動を指します。
PoCを実施することで、技術的な課題やデータの品質問題を早期に洗い出すことができるだけでなく、データレイクがもたらす具体的なビジネスインパクトを関係者に示すことができます。これにより、本格導入に向けた経営層の理解や予算獲得が容易になり、プロジェクト全体のリスクを大幅に低減させることが可能です。
PoCによる検証が成功しプロジェクトの続行が決定したら、次はいよいよ本格構築で対象とするデータソースを選定し、データレイクへの収集を開始するフェーズに入ります。
PoCの結果を踏まえ、当初のスモールスタート範囲からどのデータソースを次に追加していくかを計画的に決定します。POSシステム、ECサイトのデータベース、CRMシステム、Webサーバーのログファイルなど、社内外に散在する必要なデータがどこに、どのような形式で存在しているかを正確にリストアップします。
次に、それらのデータソースからデータを抽出し、データレイクに定期的あるいはリアルタイムに収集するための技術的な戦略を立てます。このデータの収集・連携プロセスにはETL/ELTツールや、各種クラウドサービスが提供するデータ連携サービスを利用するのが一般的です。
データ収集の目処が立ったら、データレイクを構築するための具体的なプラットフォーム(主にクラウドサービス)を選定し、本格的な構築作業に着手します。
現在、市場にはAmazon Web Services (AWS)、Google Cloud Platform (GCP)、Microsoft Azureといった主要なクラウドプロバイダーが存在し、それぞれがデータレイク構築のための強力なサービス群を提供しています。
プラットフォームの選定にあたっては、コスト、既存システムとの親和性、自社の技術者のスキルセット、サポート体制、セキュリティ機能などを総合的に比較検討する必要があります。プラットフォームが決定したら、PoCで得られた知見や、データガバナンスの要件を反映させた詳細なアーキテクチャを設計し、それに基づいてインフラの構築を進めていきます。
データレイクという器が完成しデータが蓄積され始めたら、いよいよそのデータを活用してビジネス価値を創出するフェーズに入ります。データレイクに蓄積されたデータをBIツールや各種分析ツールと連携させ、データの可視化や分析を開始します。
まずは、最初のスモールスタート範囲で具体的な成果を出すことに集中します。例えば、マーケティング部門がキャンペーンのROIを改善したといった成功事例を創出します。そして、その成功事例を社内に広く共有し、データレイクの価値を証明することで次の展開への弾みをつけるのです。
この成功体験を基に、対象とするデータソースやデータレイクを利用する部門を段階的に拡大していくアプローチが、全社的なデータ活用文化を醸成しプロジェクトを成功に導くための王道といえるでしょう。

このセクションでは、市場で広く利用されている代表的な3つのクラウドプラットフォームと、それぞれのデータレイク関連サービスについて解説します。
AWSは、クラウド市場において長年の実績と高いシェアを誇り、データレイク構築に関連するサービスも非常に豊富で成熟しているのが特徴です。
その中核を担うのが、高い耐久性とスケーラビリティを持つオブジェクトストレージサービスである「Amazon S3」です。データレイクの構築と管理を簡素化するために、「AWS Lake Formation」というマネージドサービスが提供されており、データ収集、セキュリティポリシーの設定、アクセス権限の管理などを一元的に行うことができます。
データの加工や変換(ETL処理)には、サーバーレスで実行できるデータ統合サービス「AWS Glue」が利用されます。そして、S3に蓄積されたデータに対して、標準的なSQLを用いて直接インタラクティブな分析を行うためのサービスが「Amazon Athena」です。
出典参照:AWS でのデータレイク|Amazon Web Services
Google Cloudは、親会社であるGoogleが持つ強力なデータ処理技術と分析能力を背景に、特にデータ分析と機械学習の分野で非常に優れたサービスを提供しています。
GCPでデータレイクを構築する際の中心的なストレージは、オブジェクトストレージ「Cloud Storage」です。GCPのデータ分析基盤の大きな特徴は、サーバーレスで高速かつスケーラブルなデータウェアハウスサービス「BigQuery」の存在です。BigQueryはCloud Storage上のデータレイク内のデータに対しても直接クエリを実行できるため、「データレイクハウス」アーキテクチャの中核をなします。
また、組織全体の分散したデータを一元的に管理・統制するためのインテリジェントなデータファブリックサービスとして「Dataplex」が提供されています。データの収集・加工には「Dataflow」や「Cloud Data Fusion」などが利用できます。
出典参照:データ レイクハウス | Google Cloud
Microsoft Azureは、多くの企業で基幹業務システムやオフィススイートとして広く利用されているWindows ServerやMicrosoft 365との親和性が非常に高い点が大きな特徴です。
Azureにおけるデータレイク専用のストレージサービスが「Azure Data Lake Storage (ADLS)」です。これは、ビッグデータ分析ワークロードに最適化されており、高いスケーラビリティと効率的なデータ管理機能を提供します。
Azureのデータ分析プラットフォームの統合サービスとして「Azure Synapse Analytics」が存在します。これは、データウェアハウスとビッグデータ分析を一つの環境に統合したもので、データ収集から分析までの一連のプロセスをオールインワンで提供します。
データの連携・加工には、「Azure Data Factory」が利用されます。これは、多くの組み込みコネクタを持ち、GUIベースで直感的にデータ統合パイプラインを設計・実行できるサービスです。
出典参照:Azure Data Lake Storage の概要|マイクロソフト
本記事では、小売DXの鍵となるデータレイクの基本から活用法までを網羅的に解説しました。
顧客行動が複雑化する現代、従来の分断されたデータ管理では顧客を深く理解することは困難です。データレイクは、散在するあらゆるデータを一元的に集約し、ビジネス価値を引き出すための経営基盤といえます。
導入にはデータスワンプ化などの課題もありますが、明確な目的を持って計画的に進めることで、その投資は大きなリターンをもたらすでしょう。データレイクの活用は、DXを次のステージへと加速させる力強い一歩となります。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
