小売DXの第一歩はペーパーレス化!メリットや書類管理の課題を解説
小売

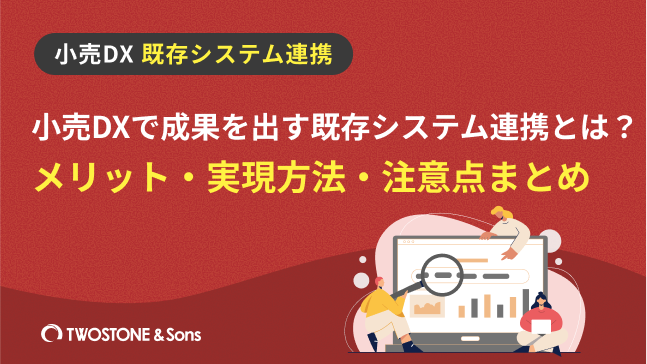
小売DX推進で壁となる既存システムとの連携。本記事では、データが分断されることによる課題を整理し、具体的な連携方法のメリット・デメリットを解説します。さらに、成功パターンやプロジェクトの進め方、レガシーシステム対応の注意点までご紹介します。


・6万名以上のエンジニアネットワークを活用して課題を解決※
・貴社のDX戦略立案から実行・開発までワンストップで支援可能
※エンジニア数は2026年8月期 第1四半期決算説明資料に基づきます。
小売業界でDX(デジタルトランスフォーメーション)の重要性が叫ばれる一方で、「導入したツールが既存システムとうまく連携できず、かえって現場が混乱した」といった声も少なくありません。点在する顧客情報や在庫データが活用されないまま放置されてしまえば、せっかくのDX投資も十分な成果には結びつかないでしょう。
本記事ではこうした「データのサイロ化」という課題に着目し、既存システムとの適切な連携によって、業務効率化と顧客体験の向上を実現するための考え方と実践法を解説します。
具体的な連携方法やツールの違い、プロジェクトの進め方、注意点、成功事例まで実務に役立つ視点でわかりやすくお伝えします。システム連携の第一歩として、ぜひご一読ください。
小売DXとはデジタル技術を用いてビジネスモデルや業務そのものを変革し、新たな価値を生み出す取り組みを指します。単にITツールを導入するだけでなく、データに基づいた意思決定を可能にし競争優位性を確立することが目指されます。
近年、小売業界でDXが強く求められる背景について詳しく見ていきましょう。
スマートフォンが一人一台のインフラとなった現代において、消費者の購買行動はかつてなく複雑かつ多様化しています。
SNSで商品を知り、比較サイトで口コミをチェックし、ECサイトでカートに入れる。さらに実店舗で実物を確認してから購入するというように、オンラインとオフラインを行き来する買い物スタイルが当たり前になっています。
このようなOMO(Online Merges with Offline)時代においては、顧客との接点も多岐にわたります。それぞれのチャネルで得られる顧客の行動データを個別に管理しているだけでは、顧客の全体像を捉えることはできません。
すべてのデータを統合し顧客一人ひとりのジャーニーを深く理解することによってはじめて、心に響く一貫した顧客体験の提供が可能になるでしょう。
日本の生産年齢人口は減少を続けており、小売業界もまた深刻な人手不足という課題に直面しています。特に店舗運営におけるスタッフの確保は年々難しくなっており、限られた人員でいかに高いサービス品質を維持し、売上を確保していくかが経営上の大きなテーマとなっています。
このような状況下でいまだに多くの手作業や非効率な業務が残っていると、従業員の負担が増大し、疲弊や離職に繋がりかねません。発注、検品、在庫管理、レジ締め、日報作成といった定型業務をデジタル技術で自動化・効率化することは、もはや選択肢ではなく必須の取り組みです。
これにより創出された時間を、接客や売り場づくりといった本来注力すべき業務に振り向けることが従業員満足度と顧客満足度の両方を高める鍵となります。
小売業界の競争環境は、かつてないほど厳しさを増しています。
高い利便性を武器にするECプラットフォーマーの存在感は増し、自社で企画・製造した商品を直接消費者に販売するD2C(Direct to Consumer)ブランドも次々と登場しています。さらには、テクノロジーを駆使した異業種からの新規参入も相次いでおり、従来の「小売業」の垣根は曖昧になりつつあります。
このような熾烈な競争の中で生き残るためには、過去の成功体験や経営者の勘だけに頼った意思決定には限界があるといえるでしょう。POSデータや在庫情報、顧客データ、市場のトレンドなどをリアルタイムで収集・分析することが重要です。そうしたデータをもとに、品揃えや価格設定、マーケティング施策をすばやく見直せる経営体制が求められています。

多くの企業がDXの重要性を認識し、新しいツールを導入しています。しかし、これらの最新システムと従来から使用している基幹システムとが分断されたままでは、DXが目指す本来の効果を得ることは難しいでしょう。
このセクションでは、既存システム連携が必要な理由についてそれぞれ解説します。
各システムが独立しデータが連携されていない状態は、企業にとって「見えないコスト」である機会損失を日々生み出しています。
例えばECサイトの在庫と実店舗の在庫が別々に管理されている場合、店舗に潤沢な在庫があるにもかかわらず、EC上では「品切れ」と表示され販売の機会をみすみす逃してしまうケースが考えられます。これは顧客にとっても不便であり、ブランドイメージの低下にも繋がりかねません。
また顧客の購買データがCRMにリアルタイムで反映されなければ、その顧客が店舗を訪れた際、直近の購買履歴に基づいた的確な接客をすることもできません。せっかくのアップセルやクロスセルのチャンスを逃すだけでなく、顧客の離反を招く原因にもなり得ます。
このようにデータの分断は、売上機会の損失と顧客満足度の低下という二重のダメージを企業に与えるのです。
システム間のデータが連携されていない場合、その隙間を埋めるのは多くの場合、人の手による非効率な作業です。
例えばECサイトの売上データを担当者が毎日手動でダウンロードし、コピー&ペーストを繰り返して基幹システムのフォーマットに合うように加工しようやく会計システムに入力する、といった作業が日常的に行われています。
これらの反復的な手作業は従業員の貴重な時間を奪うだけでなく、単純作業の繰り返しによるモチベーションの低下を招きます。さらに、手作業には必ず入力ミスや転記ミスといったヒューマンエラーのリスクが伴い、その修正作業には更なる時間と労力が必要となります。
本来より創造的で付加価値の高い業務に使われるべき人材が、こうした「システムのための作業」に忙殺されている状況は、企業全体の生産性を著しく阻害しているといえるでしょう。
データがチャネルごとに分断されていると顧客に対して一貫性のある、パーソナライズされた体験を提供することが極めて困難になります。
例えばある顧客がECサイトで特定の商品を何度も閲覧し購入を迷っているという重要なサインを発していても、その情報が店舗スタッフに共有されていなければ、来店時に「何かお探しですか?」という画一的な声かけしかできません。
これでは顧客が抱える最後の迷いを解消し、購入を後押しすることは難しいでしょう。現代の顧客は自分を一人の個人として認識し、自分の状況や好みに合った対応を期待しています。データの分断はこの期待に応えることを不可能にし、結果として顧客満足度の低下とLTV(顧客生涯価値)の毀損を招きます。
顧客一人ひとりに向き合えない企業は、いずれ競争の舞台から姿を消していくことになるかもしれません。
分断されたシステム同士を連携させ、データをスムーズに活用するためには、いくつかの実現方法があります。
このセクションでは、主な4つの方法について解説します。それぞれにコスト、開発期間、柔軟性といった面で異なる特徴があり、自社の目的、予算、技術力などに最適な手法を選択することが重要です。
API(Application Programming Interface)とは、あるソフトウェアの機能や管理する情報を外部の他のプログラムから呼び出して利用するための仕組みやルールのことです。多くのSaaSやクラウドサービスは、このAPIを公開することで外部サービスとの連携を可能にしています。
API連携の最大のメリットは、リアルタイムに近い形でのデータ交換が可能になる点です。例えば、ECサイトで注文が入った瞬間にAPIを通じて在庫管理システムに情報が送られ、在庫が引き落とされるといった処理を自動化できます。
一度連携の仕組みを構築すれば安定した運用が期待でき、将来的な機能拡張にも柔軟に対応しやすいという利点もあります。ただし、連携先のシステムに利用可能なAPIが公開されていることが前提となり、開発には相応の専門知識が求められます。
iPaaS(Integration Platform as a Service)とは、複数の異なるクラウドサービスやアプリケーションを連携させるためのハブとなる機能をクラウド上で提供するサービスです。
一方ETL(Extract, Transform, Load)は、あるデータベースからデータを抽出し、利用しやすい形式に変換・加工した上で別のデータベースに格納するという一連の処理を得意とするツールを指します。
これらのツールを活用する最大のメリットは、専門的なプログラミング知識がなくともシステム連携を構築できる点にあります。現場の業務担当者が連携フローを作成することも可能になり、開発期間の短縮とコスト削減に大きく貢献します。
ただし基本的にはツールの提供する機能の範囲内での連携となるため、特殊な要件には対応が難しい場合があるほか、月額利用料などのランニングコストが発生します。
ファイル連携は、一方のシステムからCSVやTSVといった汎用的な形式でデータファイルを出力し、それをもう一方のシステムに手動またはバッチ処理で取り込む、古くから用いられている連携方法です。
多くのシステムが標準機能としてデータのインポート/エクスポート機能を持っているため、比較的導入のハードルが低いのが特徴といえます。
この方法のメリットは仕組みが単純明快で、他の方法に比べて低コストで実現できる可能性が高いことです。特に連携の頻度が日次や月次で十分な場合や、一時的なデータ移行などでは有効な選択肢となります。
しかし連携はリアルタイムではなく、データの鮮度が求められる用途には向きません。またファイルの受け渡しに手作業が介在することも多く、業務負荷やヒューマンエラーのリスクが残りやすいというデメリットを十分に理解しておく必要があるでしょう。
スクラッチ開発はiPaaSのような既存のツールやサービスを利用せず、連携のためだけのシステムをゼロからオーダーメイドでプログラミング開発する手法です。最大のメリットは制約がほとんどなく、自社の独自の業務要件に合わせて非常に自由度の高い、理想とする連携の仕組みを細部まで作り込める点にあります。
他のどの方法でも実現が難しい業界特有の複雑なロジックや、レガシーシステムとの特殊な接続が求められる場合には、唯一の選択肢となることもあります。
その一方で開発には高度な専門知識と多くの工数が必要となるため、コストは最も高額になり、開発期間も数ヶ月から一年以上と長期化する傾向があります。また開発したシステムがブラックボックス化し、将来のメンテナンスや改修が困難になるリスクも考慮しなければなりません。

システム連携を実現することで、具体的にどのようなビジネス上の価値が生まれるのでしょうか。これらは単独の施策として終わるのではなく、複数を組み合わせることで相乗効果を生み企業全体のDXを加速させます。
このセクションでは、小売業においてよく見られる連携活用の成功パターンを解説します。
店舗のPOSシステムが日々蓄積する膨大な購買履歴とCRMに登録された顧客情報を連携させることは、顧客理解の第一歩といえます。
この連携により「誰が」「何を」買ったかという事実が結びつき、顧客一人ひとりの購買行動や嗜好がデータとして可視化されるようになります。例えば、「Aさんは3ヶ月前に特定ブランドの化粧水を購入したが、まだリピートがない」といった具体的な状況を把握できるのです。
このデータに基づき、「そろそろ化粧水がなくなる頃ではないでしょうか?」といったタイミングでECサイトやアプリを通じてリマインド通知を送ったり、関連商品のサンプルクーポンを配信したりといった、パーソナライズされたアプローチが可能になります。
顧客一人ひとりの状況に寄り添ったコミュニケーションを重ねることで顧客ロイヤルティを高め、LTV(顧客生涯価値)の最大化に繋げることが期待できるでしょう。
ECサイトの在庫情報と実店舗や倉庫の在庫管理システムをリアルタイムで連携させることは、OMO戦略を推進する上で不可欠な基盤となります。この仕組みによって企業が持つすべての販売チャネルの在庫情報を一元的に管理し、顧客にとっても企業にとっても最適な在庫配置を実現することが可能になります。
顧客にとってはECサイトで「店舗の在庫を確認する」機能や、「ECで購入して最寄りの店舗で受け取る」といった選択肢が増え、購買体験が大きく向上します。
一方、企業にとってはECサイト上での欠品による販売機会の損失を防ぐとともに、全社的な在庫状況を正確に把握することで過剰在庫の削減やキャッシュフローの改善にも繋がります。将来的には需要予測の精度を高め、自動発注の仕組みへと発展させることも視野に入るでしょう。
日々の売上データが蓄積されるPOSシステムや販売管理システムといった基幹システムと、経理業務で使用する会計ソフトを連携させることもバックオフィスDXにおける重要な取り組みです。この連携により、これまで経理担当者が手作業で行っていた売上データや仕入データの入力・転記作業を自動化することができます。
この自動化は経理担当者の業務負担を大幅に軽減し、単純作業から解放することに直結します。創出された時間は予算実績管理や経営分析といった、より付加価値の高い業務に充てることができるようになるでしょう。
また手作業による入力ミスや計上漏れといったヒューマンエラーを撲滅しデータの正確性を担保することで、月次決算の早期化や経営層に対する迅速で信頼性の高いレポーティングを実現します。
これは、データドリブンな経営判断の基盤を支える重要な改革といえます。
CRMや基幹システムなど、社内の様々な場所に点在している顧客に関するデータをMAツールに集約・連携させることで、マーケティング活動を次のステージへと進化させることができます。
購買履歴のような静的なデータだけでなく、ECサイトでの行動履歴(閲覧ページ、滞在時間など)やメールマガジンの開封・クリック状況といった動的なデータも統合して管理します。
これにより顧客の興味関心や検討の度合いをスコアリングし、「今、アプローチすべき顧客」を自動でリストアップすることが可能になります。そして「商品をカートに入れたまま離脱した顧客には24時間後にリマインドメールを送る」といった、あらかじめ設定したシナリオに基づいたコミュニケーションを自動で実行します。
One to Oneマーケティングを効率的に展開し見込み客の育成から優良顧客化まで、顧客ライフサイクル全体にわたる関係構築を支援することが期待できるでしょう。
システム連携を成功に導くためには技術的な課題だけでなく、組織的な課題にも目を向け、計画的にプロジェクトを推進することが不可欠です。
特に関係する部署や担当者を早い段階から巻き込み、全社的な協力体制を築くことが成功の鍵となります。このセクションでは、その基本的な進め方を4つのステップに分けて解説します。
まず最初に行うべきは、「何のためにシステム連携を行うのか」というプロジェクトの目的を明確に定義することです。
単に「システムを繋ぎたい」という手段の目的化に陥るのではなく、「在庫管理を効率化して欠品による機会損失を年間500万円削減する」「顧客データを一元化してリピート購入率を3ヶ月で10%向上させる」など、できるだけ具体的で測定可能なゴール(KGI/KPI)を設定することが望ましいでしょう。
そのためにはまず、現状の業務フローを詳細に可視化することが重要です。現場の担当者にヒアリングを行ったり業務の流れを図に書き出したりすることで、どこに非効率な手作業が存在するのか、どのデータが分断されているのかといった課題が浮き彫りになります。
この課題認識をプロジェクトメンバー全員で共有することが、ぶれない軸を持つための第一歩です。
目的と課題が明確になったら、次にそれを解決するために「どのシステムとどのシステムを連携させるのか」、そして「具体的にどのデータを、どのタイミングで、どちらの方向にやり取りするのか」といった要件を定義していきます。
例えば「毎晩24時に、POSシステムから売上データを抽出し、CRMの顧客DBに顧客IDをキーとして購買履歴を追加する」といったレベルまで具体化します。
この要件定義は、連携システムの設計図となる非常に重要な工程です。ここで定義が曖昧なまま進めてしまうと後の開発フェーズで仕様の認識齟齬が発覚し、大幅な手戻りや追加コスト、プロジェクトの遅延を招く原因となります。
連携するデータ項目の一つひとつについて、その意味や形式を関係者間ですり合わせ、合意形成を図っていく地道な作業がプロジェクトの成否を大きく左右するのです。
定義した要件をもとに、それを実現するための最適な方法を選定します。
前述した「API連携」「iPaaS・ETLツール」「ファイル連携」「スクラッチ開発」といった選択肢の中から、要件で定めたリアルタイム性、処理するデータ量、予算、開発期間、自社の技術力、将来的な拡張性などを総合的に評価して判断します。
この段階では複数の選択肢を比較検討し、それぞれのメリット・デメリットを客観的に評価することが重要です。特にツールを選定する際には資料請求やデモの依頼だけでなく、可能であればPoC(Proof of Concept:概念実証)を実施し、限定的な範囲で実際にツールを試してみることをお勧めします。
実際に触れてみることでカタログスペックだけでは分からない操作性や、自社の要件とのフィット感を確認でき、より確実な選定が可能になるでしょう。
連携方法とツールが決まったら、いよいよ実行フェーズに移ります。
要件定義と選定したツールに基づき、連携システムの詳細なデータフローやエラー処理のロジックなどを設計し、それに沿って開発(またはツールの設定)を進めていきます。この段階では開発パートナーやツールベンダーとの定期的な進捗確認や課題共有など、密なコミュニケーションがプロジェクトを円滑に進める上で不可欠です。
そして開発以上に重要ともいえるのが、入念なテスト工程です。データが想定通りに正しく連携されるかという正常系のテストはもちろんのこと、意図的に仕様外のデータを流したりネットワークを遮断したりしてみることも重要です。エラーが起きた際にシステムが安全に停止し、適切に通知されるかといった異常系のテストも必ず実施しましょう。
最終的には、業務の担当者自身が操作して本番同様のデータで検証する「受け入れテスト」を行い、現場の承認を得てから本番稼働へと移行します。

特に長年にわたって企業の根幹を支えてきた既存システムとの連携には、新しいSaaS同士の連携とは異なる特有の難しさや注意すべき点が存在します。
これらはプロジェクトの成否を分ける「落とし穴」になりやすく、事前にリスクを把握し適切な対策を講じておくことが極めて重要です。
長年利用されているレガシーシステムは、度重なる改修によって内部構造が複雑化していたり、導入当時の仕様書などのドキュメントが失われていたりするケースが少なくありません。
さらにシステムの内部を正確に把握している技術者が退職していると、「ブラックボックス」状態に陥っていることもあります。
このようなシステムとの連携を試みる場合、まずは専門家による現状調査(アセスメント)を行い、システムの仕様やデータの構造、連携の実現可能性を正確に把握することが不可欠です。
直接の連携が困難と判断された場合は既存システム側を一部改修してデータ出力機能を追加したり、連携しやすい形式にデータを変換するための中間データベースを構築したりといった、段階的なアプローチが必要になることもあります。
出典参照:DXレポート ~ITシステム「2025年の崖」克服とDXの本格的な展開~(P.3)|経済産業省|経済産業省
連携したい既存システムに外部連携のためのAPIが用意されていないというケースは、レガシーシステムではごく一般的です。しかし、APIがないからといって連携を諦める必要はありません。他のアプローチを検討することで、課題を解決できる可能性があります。
代表的な代替手段の一つが、RPAの活用です。これは人間がPC画面を操作するのと同じように、ソフトウェアロボットにシステムを自動操作させてデータを抽出・入力させる技術です。既存システムに一切手を加えることなく連携を実現できるメリットがありますが、画面デザインの変更に弱いという側面もあります。
もう一つの方法として、システムのデータベースに直接接続してデータをやり取りする方法も考えられますが、これには高度な専門知識と慎重な設計が求められます。
システム間でデータをやり取りするということは、その経路上での盗聴や不正アクセスによる情報漏洩といった、セキュリティリスクを常に考慮しなければなりません。特に個人情報や決済データを扱う場合には、万が一のインシデントが企業の信頼を根底から揺るがす事態に発展しかねないため、最大限の注意が必要です。
具体的な対策として通信経路を暗号化することはもちろん、アクセスを許可するIPアドレスを制限したり、連携に用いるアカウントの権限を必要最小限に絞ったりといった多層的な防御策を講じることが重要です。
また利用するツールが第三者機関によるセキュリティ認証を取得しているかどうかも、その信頼性を測る上で重要な判断基準となるでしょう。
システム連携は、一度構築すれば終わりというわけではありません。
連携先のシステムの仕様変更や予期せぬエラーなど、稼働後には様々な事態が発生し得ます。こうした問題に迅速かつ的確に対応するための運用・保守体制をあらかじめ構築しておくことが不可欠です。
具体的にはエラーが発生した際に誰が第一次対応を行い、どのような手順で原因を調査し、復旧させるのかといったエスカレーションフローを明確に定めておく必要があります。
またエラーの発生や処理の遅延を自動で検知し、担当者に通知する監視の仕組みを導入することも有効です。これらの運用業務が特定の担当者のスキルに依存する「属人化」を避けるため、手順書などのドキュメントを整備し、組織として対応できる体制を整えることが長期的な安定稼働の鍵となります。
自社のリソースだけでシステム連携を実現するのが難しい場合、専門のツールや開発会社の力を借りることが現実的な選択肢となります。
しかし世の中には数多くのツールやベンダーが存在するため、どこをどう選べば良いのか迷ってしまうことも少なくありません。パートナー選びはプロジェクトの成否を大きく左右する重要な意思決定であり、慎重な検討が求められます。
費用や期間は、連携の難易度や選択する手法によって大きく変動するため一概にはいえませんが、大まかな傾向を把握しておくことは重要です。例えばiPaaSなどのツールを利用する場合、初期費用と月額費用で構成されることが多く、比較的短期間で導入できる可能性があります。
一方でAPI連携やスクラッチ開発を外部の会社に依頼する場合、要件定義から開発、テストといった工程が必要となります。期間は数ヶ月以上、費用も要件の複雑さによって高額になることが一般的です。
安さだけで選んでしまうと品質が低かったり、後から追加費用が発生したりするリスクもあります。自社の予算とスケジュール感を明確にした上で複数の会社から見積もりを取り、内容を精査することが大切です。
iPaaSなどの連携ツールを検討する際に最も重要な確認事項となるのが、自社で利用しているシステムに正式に対応しているかどうかです。特に連携させたいと考えているPOSシステムやCRM、ECカートなどの製品名が、ツールの公式サイトなどで「連携対応コネクタ」として明記されているかを確認しましょう。
もし公式なコネクタがない場合でも、汎用的なAPIやファイル形式で接続できる可能性もあります。しかし、その場合は自社である程度の開発や設定作業が必要になるかもしれません。
ツールの提供元に直接問い合わせ、自社の具体的なシステム環境や連携要件を伝えた上で、実現可能かどうかを事前にしっかりと確認することが選定の失敗を防ぐ上で不可欠です。
開発を外部の会社に委託する場合、その会社が小売業界におけるシステム連携の実績を豊富に持っているかどうかは非常に重要な判断基準となります。
小売業特有の商習慣や業務フローを深く理解しているパートナーであれば、こちらの意図を的確に汲み取り、より実践的で効果的な提案が期待できるでしょう。
また契約前の提案内容だけでなく、導入後のサポート体制が充実しているかも必ず確認すべきポイントです。問題が発生した際に迅速に対応してくれるか、システムの安定稼働を支援してくれるかなど、長期的な視点で信頼できるパートナーを選ぶことが成功の鍵となります。過去の実績を確認する際には、具体的な事例を詳しくヒアリングすることをお勧めします。
数あるツールやパートナーの中から自社に最適なものを選ぶためには、客観的な評価軸を持って比較検討することが重要です。例えば、機能・性能面では、「連携したいシステムに標準対応しているか」「将来的なデータ量の増加にも耐えられる性能か」「非エンジニアでも直感的に操作できるか」といった点が挙げられます。
コスト面では、初期費用だけでなく月額のランニングコストも含めたトータルコストで比較することが大切です。さらにサポート・信頼性の観点では、「日本語での手厚い技術サポートが受けられるか」「自社と同じような業界・規模での導入事例があるか」といった点も加えるべきでしょう。
これらの項目をリスト化し点数付けすることで、より客観的で後悔のない選定が可能になります。
小売DXの文脈において、システム連携はもはや避けては通れない企業の競争力を左右する中心的なテーマの一つといえるでしょう。データがそれぞれのシステムに分断されたままでは、真の業務効率化もデータに基づいた高度な顧客体験の提供も実現することは困難です。
もし「何から手をつければ良いのか分からない」と感じているのであれば、まずは大掛かりなシステム導入を考える前に、自社の業務フローを改めて見直すのがおすすめです。どこに非効率な手作業やデータの分断が存在しているのか、洗い出すことから始めてみてはいかがでしょうか。
現状の課題を関係者全員で共有し、可視化することが大切です。そしてその中で最も影響が大きく、かつ解決しやすい課題を一つ見つけ、まずはそこからスモールスタートで改善に取り組んでみてください。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
