小売DXの第一歩はペーパーレス化!メリットや書類管理の課題を解説
小売

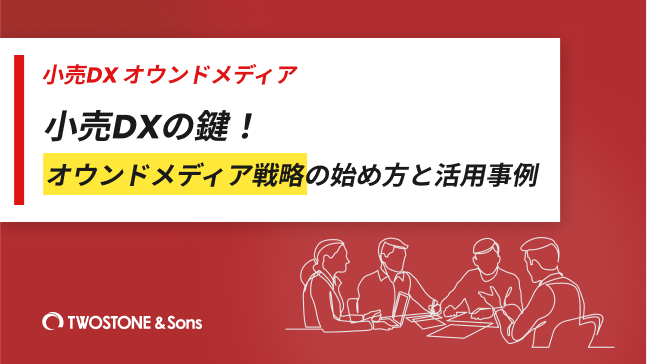
顧客との関係構築やデジタル戦略にお悩みではありませんか?この記事では、DXの鍵となる「オウンドメディア」の重要性を解説。事例や、具体的な立ち上げ5ステップ、失敗しないための注意点まで、自社のメディア戦略を成功に導くためのステップをご紹介します。


・6万名以上のエンジニアネットワークを活用して課題を解決※
・貴社のDX戦略立案から実行・開発までワンストップで支援可能
※エンジニア数は2026年8月期 第1四半期決算説明資料に基づきます。
消費者の購買行動がデジタル中心へと移行し、従来のマス広告だけでは顧客との信頼関係を築くのが難しくなっています。とくに小売業界では商品や価格だけでは差別化しづらく、DX推進の必要性を感じながらも具体的な一手が見つからずに悩んでいる企業も多いのが現状です。
そんな中で注目されているのが「オウンドメディア」の活用です。ただの情報発信ではなく、顧客との関係を深め、ブランド価値を高める“資産”として長期的に企業を支える存在となり得ます。
この記事では小売DXの文脈でオウンドメディアがなぜ重要なのか、成功企業の活用事例や立ち上げのステップ、注意点までをわかりやすく解説します。自社に合ったメディア戦略を考えるうえで、ぜひ参考にしてください。

現代の小売業界において、デジタルトランスフォーメーション(DX)は避けて通れない経営課題となっています。その中でオウンドメディアが重視される背景には、以下の3つがあります。
オウンドメディアは企業が顧客と直接的かつ継続的な接点を持ち、深い関係性を築くための基盤となり得ます。従来のマス広告のような一方的な情報伝達とは異なり、顧客が自らの意思で訪れて情報を得る場所だからです。
例えば、商品の使い方の提案や開発ストーリーの発信をすることによって、顧客は購入後もブランドに親しみを持ち続けてくれやすくなります。
経済産業省が策定した「デジタルガバナンス・コード3.0」でも、企業がデータやデジタル技術を活用して顧客提供価値を向上させることが重要と示されています。オウンドメディアはこうした顧客接点のデジタル化を通じて、企業のDX推進を支える有効な手段といえるでしょう。
出典参照:デジタルガバナンス・コード3.0 (P.2)|経済産業省
価格競争が激化しやすい小売市場において、オウンドメディアはブランドの独自性を伝え、LTV(Life Time Value:顧客生涯価値)を向上させるための強力な手段となり得ます。
製品の機能的な価値だけでなく、その背景にある企業の哲学や世界観、作り手の想いといった情緒的な価値を伝えることができるためです。顧客がブランドのストーリーに共感し深い愛着を感じるようになれば、そのブランドを指名して購入するようになります。
このようなロイヤルティの高い顧客は、継続的に商品を購入してくれるだけでなく、ポジティブな口コミを通じて新たな顧客を呼び込む可能性も秘めています。そのため、企業の持続的な収益基盤を支える重要な存在になるといえるでしょう。
オウンドメディアは、DXの核となる顧客データを収集し活用するための貴重なプラットフォームです。
ユーザーがどのようなコンテンツに興味を持ち、どのくらい閲覧したかといった行動データは、潜在ニーズやインサイトを理解するための重要な情報源となります。こうしたデータ分析によって、顧客の心に響く商品開発やパーソナライズされたマーケティング施策を立案できます。
独立行政法人情報処理推進機構(IPA)の「DX推進指標」でも、DXの本質は「顧客視点で新たな価値を創出すること」と示されています。オウンドメディアは、まさにその価値創出を支えるデータとインサイトを得る場といえるでしょう。
さらに、オンライン上で得た顧客の興味・関心を店舗での接客や品揃えに活かす、OMO(Online Merges with Offline)施策にも展開できます。こうしたデータに基づく顧客体験の向上は、小売DXを成功に導くうえで欠かせない要素です。
出典参照:「DX 推進指標」とそのガイダンス(P.7)|独立行政法人情報処理推進機構(IPA)
このセクションでは、実際にオウンドメディアを効果的に活用し、DXを推進している小売企業の事例を紹介します。
各社がどのように顧客とのエンゲージメントを深めて成果につなげているのかを分析し、自社で取り組む際のヒントにしましょう。
ホームセンター大手のカインズは、オウンドメディア「となりのカインズさん」でDIYや暮らしに役立つ情報を幅広く発信しています。
店舗スタッフやお客様、外部の専門家など、多彩な執筆者によるコラムやレビュー、体験記事を掲載。読み物として楽しめるだけでなく実用性があり、日々の暮らしに役立つ内容となっている点も特徴です。
こうした発信を通じて顧客接点を広げ、ブランド理解とファン化を促進しています。
出典参照:となりのカインズさん|株式会社カインズ
高品質な革製品で知られる土屋鞄製造所は、オウンドメディア「読み物」を運営しています。もの作りの背景や革製品の手入れ方法、職人や社員インタビューなど多彩なコンテンツを発信しているメディアです。
職人の想いや制作過程、革に込めるこだわりを丁寧に伝える発信によって、製品への理解と愛着を深めています。単なる商品紹介ではなくストーリーを届けることで、ブランドへの共感と顧客との長期的な関係作りに貢献しています。
出典参照:読み物|株式会社土屋鞄製造所
無添加化粧品や健康食品で有名なファンケルは、オウンドメディア「FANCL CLIP」で美容や健康に役立つ情報を幅広く発信しています。
スキンケアやメイクなどに関する知識だけでなく、日々の暮らしに役立つコラムや季節の健康管理法など、多様な内容を掲載しているのが特徴です。
読者が楽しみながら学べる内容構成により、商品紹介にとどまらない情報発信で顧客との信頼関係を築きブランドへの親近感を高めています。
出典参照:FANCL CLIP|株式会社ファンケル

オウンドメディアを成功に導くためには、思いつきで始めるのではなく戦略に基づいた体系的なアプローチが不可欠です。
このセクションでは目的設定から効果測定と改善に至るまで、メディア立ち上げから成長させていくための主要な5つのステップについて解説します。
オウンドメディアを立ち上げる上で最も重要なのが、「何のために運営するのか」という目的を明確に定義することです。
明確な目的は、コンテンツの方向性や評価指標の根幹をなします。目的としてはブランド認知度の向上、新規顧客の獲得、既存顧客の育成(ファン化)、採用強化などが考えられるでしょう。
目的が定まったら、その達成度を測るための具体的な指標を設定します。最終目標であるKGI(重要目標達成指標)には、「オウンドメディア経由のEC売上向上率」や「新規会員登録者数」などを設定します。そして、KGI達成に向けた中間指標であるKPI(重要業績評価指標)を、メディアの成長フェーズに合わせて設定することが重要です。
例えば、立ち上げ期は「記事本数」や「PV数」、成長期は「検索順位」や「SNSからの流入数」、成熟期には「CVR(コンバージョン率)」などを追っていくと良いでしょう。
次に、「誰に向けて情報を発信するのか」というターゲットユーザー像を具体的に描く「ペルソナ設計」を行います。
ペルソナとは年齢、性別、職業、ライフスタイル、抱えている課題やニーズなどを詳細に設定した架空の人物像のことです。ペルソナを明確にすることでコンテンツのテーマやトーン&マナーに一貫性が生まれ、チーム内での共通認識を持つことができます。
「30代の働く女性で健康と美容に関心が高いが、忙しくて十分な情報収集ができていない」といったように、ペルソナが何を求めているのかを深く掘り下げることで本当にユーザーの心に響くコンテンツ企画へと繋がっていきます。
このステップを丁寧に行うことが、読者の共感を呼ぶメディア作りの鍵といえるでしょう。
設定したペルソナが抱えるであろう課題や疑問に応える形で、具体的なコンテンツを企画していきます。
ペルソナが検索しそうなキーワードを洗い出し、それに対する答えとなるような記事テーマをリストアップします。競合他社のオウンドメディアがどのようなコンテンツを発信し、ユーザーからどのような反応を得ているかを分析することも企画の精度を高める上で有効な手段です。
同時にこれらのコンテンツを誰がどのように制作していくのかという、運用体制を構築する必要があります。社内のリソースで対応する「内製」、外部の専門家に委託する「外注」、あるいは両者を組み合わせた「ハイブリッド型」など、自社の状況に合わせて最適な体制を選択します。
継続的な情報発信がオウンドメディアの生命線であるため、無理なく運用を続けられる現実的な体制を整えることが極めて重要です。
どれだけ質の高いコンテンツを作成しても、それが読者に届かなければ意味がありません。オウンドメディアへの集客経路を複数確保し、戦略的に読者を呼び込む必要があります。
最も重要な集客チャネルの一つが、検索エンジン経由の流入を狙うSEO(検索エンジン最適化)です。長期的に安定した集客が見込めるため、コンテンツ企画の段階からSEOを意識することが求められます。
その他にもX(旧Twitter)やInstagramといったSNSでの発信による拡散、既存顧客に向けたメールマガジンでの告知、短期間でターゲットにリーチできるWeb広告の活用などが考えられます。
さらに小売業ならではの施策として、店舗のPOPやチラシでオウンドメディアを紹介し、オフラインからオンラインへの送客を図ることも有効な戦略といえるでしょう。
オウンドメディアは一度作ったら終わりではなく、継続的な効果測定と改善、いわゆるPDCAサイクルを回し続けることが成功の鍵を握ります。ステップ1で設定したKPIが達成できているか、分析ツールを用いて定期的にチェックします。
例えば「PV数が伸び悩んでいる記事は、タイトルや導入文を修正してクリック率の改善を図る」「読了率が低い記事は、図解や動画を加えて分かりやすさを向上させる」「コンバージョンに繋がっていない記事は、CTA(行動喚起)の文言や配置を見直す」といったように、データに基づいて仮説を立てて改善策を実行していきます。
この地道な改善の繰り返しがメディアの価値を徐々に高め、最終的な目標達成へと繋がっていくのです。
オウンドメディアで発信するコンテンツの形式は多岐にわたります。ターゲットとするペルソナの特性や伝えたいメッセージの内容に応じて、戦略的に組み合わせることがメディアのエンゲージメントを深める上で大切です。
このセクションでは、小売企業のオウンドメディアでよく用いられる代表的なコンテンツの種類と特徴について解説します。
ユーザーが抱える具体的な悩みや疑問に対し、専門的な知見やノウハウを提供して解決策を提示するコンテンツです。
これはオウンドメディアの基本形ともいえる形式で、例えば「上手な収納術」「季節の変わり目のスキンケア方法」といったテーマが考えられます。
ユーザーは自らの課題を解決するために検索エンジンを利用することが多いため、このようなコンテンツはSEOとの親和性が非常に高いという特徴があります。検索結果からの安定した流入を獲得し、新規ユーザーとの最初の接点となる可能性が高い重要なコンテンツ形式といえるでしょう。企業の専門性や信頼性を示す上でも効果的です。
製品やサービスの裏側にあるストーリーを伝えるコンテンツは、顧客の情緒に訴えかけ、ブランドへの共感を深める上で大きな力を発揮します。
どのような想いや哲学に基づいて商品が生まれたのか、開発過程でどのような困難があったのかといった開発秘話は、製品に人間的な温かみを与えつつ顧客の記憶に残りやすくなります。
また、実際に働く社員にスポットライトを当て、その人柄や仕事への情熱を伝えるインタビュー記事も有効です。
企業に対する親近感が生み出され、顧客は単なる売り手と買い手という関係を超え、人と人との繋がりを感じることができるようになるでしょう。
実際に商品やサービスを利用している他の顧客が、どのように活用しどのような満足を得ているかを紹介するコンテンツです。
購入を検討している潜在顧客にとって、企業からの一方的な情報よりも、同じ生活者であるユーザーのリアルな声の方が信頼性が高く感じられる傾向があります。
「この商品を買ったら自分の生活が良くなるかもしれない」と顧客が利用シーンを具体的にイメージする手助けとなり、購買への最後の一押しとなる効果が期待できます。
顧客を巻き込んだコンテンツ作りはコミュニティ感を醸成し、既存顧客のロイヤルティ向上にも繋がるでしょう。
文章や写真だけでは伝わりにくい商品の使い方や、サービスの利用手順などを動画を用いて視覚的に分かりやすく解説するコンテンツです。
例えばアパレル企業であれば着回しコーディネートの提案、食品スーパーであればオリジナルレシピの紹介動画などが考えられます。
動画は短い時間で多くの情報を伝えることができ、ユーザーの理解度を飛躍的に高める効果があります。特に実際の使用感や動きを伴う製品の場合、動画コンテンツはユーザーの購買前の不安を解消し、購入意欲を刺激する上で非常に有効な手段といえるでしょう。
近年、小売業界のDXを語る上で「リテールメディア」という言葉も頻繁に聞かれるようになりました。
オウンドメディアと混同されがちですが、両者はその目的と性質において明確な違いがあります。自社のデジタル戦略を立案する上で、この二つのメディアの違いを正しく理解しておくことは非常に重要です。
簡単にいえばオウンドメディアが「ファンを育てるための自社メディア」であるのに対し、リテールメディアは「自社の顧客接点を活用した広告媒体」と位置づけられます。
オウンドメディアの主目的は、有益なコンテンツを通じて顧客との長期的な関係を構築し、ブランド価値を高めることにあります。その成果は、LTVの向上といった形で間接的に現れることが多いといえます。
一方、リテールメディアは小売企業が自社のECサイトやアプリ、店舗のデジタルサイネージなどを広告枠としてメーカーなどの第三者に販売し、広告収入を得ることを主目的とします。小売企業が保有する購買データなどを活用して精度の高いターゲティング広告を配信できる点が特徴で、より直接的な収益獲得を目指す広告事業としての側面が強いといえるでしょう。

オウンドメディアは小売DXを推進する上で強力な武器となり得ます。しかし戦略や運用方法を誤ると、期待した成果が得られずに頓挫してしまうリスクも伴います。
このセクションでは、多くの企業が陥りがちな失敗パターンを基に、オウンドメディアを成功に導くために重要な注意点について解説します。
オウンドメディアの運用において最も多い失敗の原因の一つが、短期的な成果を性急に求めてしまうことです。
オウンドメディアは、広告のように即時的な効果が現れる施策ではありません。良質なコンテンツを地道に蓄積し、検索エンジンからの評価と顧客との信頼関係を構築するには、一般的に少なくとも半年から一年以上の時間が必要とされています。
始めてから数ヶ月で目に見える成果が出ないからといって、「効果がない」と判断し、リソースの投入をやめてしまうのは非常にもったいないことです。
オウンドメディアは中長期的な視点でブランドの資産を築いていく活動であると理解し、腰を据えて継続的に取り組む姿勢が不可欠といえるでしょう。
「競合他社が始めたから」といった曖昧な動機でオウンドメディアを立ち上げると、その多くは失敗に終わる傾向があります。
メディアの目的やターゲットが明確に定まっていないと発信するコンテンツの方向性がぶれてしまい、結果として誰の心にも響かないメディアになってしまうからです。
立ち上げに着手する前に「自社の強みを活かして、どのような顧客の、どのような課題を解決したいのか」を徹底的に議論し、言語化することが重要です。明確な方針を持つことで初めて一貫性のある有益なコンテンツを提供し続けることが可能になり、読者からの支持を得ることができるでしょう。
オウンドメディアの成功は、継続的なコンテンツの更新にかかっているといっても過言ではありません。
そのためにはコンテンツの企画、制作、公開、効果測定、改善という一連の運用サイクルを滞りなく回し続けるための、安定的かつ現実的な体制を確保することが極めて重要です。担当者が他の業務と兼任し過度な負担がかかるような状況では、いずれ更新が途絶えてメディアは放置されてしまいます。
コンテンツ制作を内製するのか、外部に委託するのか、あるいはその両方を組み合わせるのか。自社の人員、スキル、予算といったリソースを冷静に評価し、持続可能な運用体制をあらかじめ設計しておくことが失敗を避けるための重要なポイントとなります。
本記事では、小売DXにおけるオウンドメディアの重要性から具体的な始め方、成功のための注意点までを解説しました。
顧客との関係構築がますます重要になる今、オウンドメディアは単なる情報発信ツールではなく、顧客との信頼を育みブランド価値を高めるための「デジタル資産」です。短期的な成果を追うのではなく、中長期的な視点で顧客と向き合うことがこれからの小売企業には求められます。
まずは「自社の顧客に、どのような価値を提供できるか?」を考えることから、貴社だけのオウンドメディア戦略の第一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
