小売DXの第一歩はペーパーレス化!メリットや書類管理の課題を解説
小売


海外の小売業界ではDXがどのように進んでいるのでしょうか。この記事では、ウォルマートやAmazon Goなどの成功事例を詳しく解説します。OMOやAI活用といった最新トレンドから、国内でDXを成功に導くためのポイントまで、自社の戦略立案に役立つ情報をお届けします。


・6万名以上のエンジニアネットワークを活用して課題を解決※
・貴社のDX戦略立案から実行・開発までワンストップで支援可能
※エンジニア数は2026年8月期 第1四半期決算説明資料に基づきます。
国内の小売業界では人手不足や顧客ニーズの多様化を背景に、DX(デジタルトランスフォーメーション)の必要性が一層高まっています。しかし、具体的に何から始めれば良いのか悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
海外ではすでに多くの企業が先進技術を活用し、顧客体験や業務効率の向上につなげています。その取り組みは規模の大小にかかわらず、国内企業にとっても多くのヒントになるはずです。
この記事ではウォルマートやAmazonなど、海外成功事例を通じてOMOやAI、省人化、リテールメディアといった最新トレンドを解説します。まずは他社の工夫を知り、身近な課題にどうデジタルを生かすか、具体的なヒントを探る手がかりとしてご活用ください。
小売DXとはAIやIoT、ビッグデータといったデジタル技術を活用して、従来のビジネスモデルや業務、顧客体験を変革していく取り組みを指します。
単にITツールを導入するだけでなく、その先にある「顧客への新たな価値提供」や「競争力の強化」を目指す点が重要とされています。
近年消費者の購買行動は大きく変化し、実店舗とオンラインの垣根は低くなりました。このような変化への対応や深刻化する人手不足という課題を解決するためにも、小売業界におけるDXの推進が求められているのです。

それでは実際に海外の小売企業がどのようにDXを成功させているのか、具体的な事例を見ていきましょう。
世界的に有名なウォルマートやAmazon Goをはじめ、各社が独自の戦略で顧客体験の向上や業務効率化を実現している様子がうかがえます。
世界最大のスーパーマーケットチェーンであるウォルマートは、DXによって顧客体験を大きく向上させた企業の一つとされています。
特に力を入れているのが、オンラインとオフラインを融合させるOMO戦略です。オンラインで注文した商品を店舗の専用ロッカーなどで受け取れる「BOPIS」はその代表例といえるでしょう。
またAIを活用した需要予測や倉庫内のロボット導入など、サプライチェーンの自動化にも大規模な投資を行っているようです。これにより、在庫の最適化と業務効率の向上を目指していると考えられます。
出典参照:How is Walmart amplifying shop tech for its customers?|Walmart Inc.
Amazonが展開する「Amazon Go」は、レジでの精算が不要な無人決済店舗として知られています。店内に設置されたカメラやセンサー、AI技術を組み合わせた「Just Walk Out」というシステムによって、顧客が手に取った商品を自動で認識する仕組みです。
顧客はレジ待ちのストレスから解放されるという、これまでにない買い物体験ができるとされています。主にコンビニエンスストアのような小規模店舗向けに展開されており、買い物の手間を大幅に削減する新しい購買体験を実現しています。
出典参照:Amazonの「Just Walk Out」とレジ不要の技術に関する計画の最新情報|Amazon.com, Inc.
ナイキは顧客主導の成長戦略「Consumer Direct Offense」を掲げ、直販事業とデジタル領域の強化に注力しています。
オンラインと実店舗をシームレスにつなぎ、個々の顧客に最適化された購買体験を提供することで、ブランドとの関係性を深めています。
特にデジタル活用による直販の拡大と、スピーディな商品展開を成長の柱としています。
世界中の重点市場に焦点を当て、顧客接点の強化と体験価値の向上に戦略的に取り組んでいるのが特徴です。こうした動きは、ナイキの長期的な成長を支える重要な施策とされています。
家具大手のIKEAはAR(拡張現実)技術を活用し、顧客の家具選びの体験を大きく変えた事例として挙げられます。
スマートフォンやPCで利用可能な「IKEA Kreativ」は、部屋を撮影するだけで実物大の家具を正確なサイズや質感で3D配置し、配置やレイアウトの確認が可能です。
このアプリによって、顧客は「部屋に置いたときのサイズ感や雰囲気が分からない」といった購入前の不安を解消しやすくなります。オンラインでも安心して家具を選べるようにすることで、新たな購買体験を創出しているといえるでしょう。
出典参照:IKEAは、顧客がリアルな部屋のデザインを作成できるようにする、AIを搭載した新しいデジタル体験を開始します。|Inter IKEA Systems B.V.
米国大手小売チェーンのTargetは自社のECサイトやアプリ、店舗で得た顧客購買データを活用し、企業向け広告配信プラットフォーム「Roundel」を展開しています。
Targetの発表によればRoundelは2021年に10億ドル超の価値を創出し、今後数年で20億ドル規模に成長する見込みです
同社のデジタルエコシステムや会員プログラム「Target Circle」から得られる洞察を通じて、パーソナライズされた広告を提供。これにより顧客体験を向上させつつ、広告収益という新たな成長源を確立しています。
出典参照:ゲストと愛するブランドをつなぐ:RoundelのSarah Travisへの5つの質問|Target Corporation
ここまで見てきた海外の先進事例からは、小売DXにおけるいくつかの重要なトレンドが見えてきます。
OMO、AI活用、無人化技術、そしてリテールメディアといったキーワードが現代の小売業の変革を理解する上で欠かせない要素となっているようです。
OMO(Online Merges with Offline)は、オンラインとオフラインの垣根をなくし、顧客に一貫した体験を提供しようとする考え方です。
ECサイトの利便性と、実店舗ならではの体験価値を組み合わせることが目的とされています。
例えばオンラインで注文した商品を店舗で受け取ったり、店舗で見た商品を後からアプリで購入したりといった流れがこれにあたります。顧客データを連携させることで、よりスムーズで満足度の高いサービス提供が可能になると期待されています。
AI(人工知能)の活用は、小売DXの中核をなすトレンドの一つといえるでしょう。
過去の販売データや天候、地域のイベント情報など、AIが分析することで精度の高い需要予測が可能になるとされています。これにより、食品ロスの削減や在庫の最適化につながることが期待されます。
また顧客一人ひとりの購買履歴や行動データを基に、おすすめ商品を提案するパーソナライズにもAIは不可欠な技術です。顧客との関係を深める上で重要な役割を担っていると考えられます。
Amazon Goに代表される無人店舗やセルフレジなどの省人化技術は、深刻化する人手不足への対策として注目されています。
これらの技術は単に人件費などのコストを削減するだけでなく、レジ待ち時間の短縮といった形で顧客の利便性向上にも貢献する可能性があります。
最先端の無人店舗だけでなく、商品の自動陳列システムや清掃ロボットなど、店舗運営の様々な場面で省人化・効率化の動きが広がっているようです。
リテールメディアとは、小売企業が自社のECサイトやアプリ、店舗などを広告媒体としてメーカーなどに提供するものを指します。
小売企業が持つ信頼性の高い購買データ(ファーストパーティデータ)を活用できるため、広告主にとって非常に魅力的とされています。
Targetの成功事例のように、リテールメディアは小売企業にとって広告収入という新たな収益の柱となる可能性を秘めています。今後、日本国内でも市場の拡大が予測される分野の一つです。
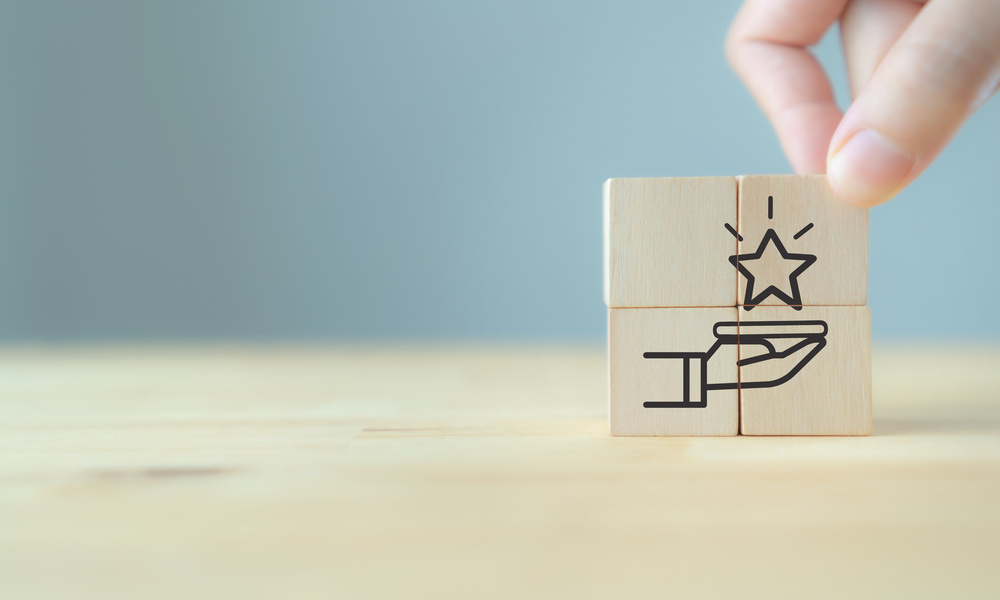
海外の事例が示すように、小売DXの推進は企業に多くのメリットをもたらすと考えられます。
顧客体験の向上はもちろん、業務の効率化や新たなビジネスチャンスの創出などその効果は多岐にわたります。
DXは、これまでにない快適で楽しい顧客体験を創出する可能性を秘めています。
例えばARによるバーチャル試着や、アプリを通じたパーソナライズされた情報提供、待ち時間のない決済などが挙げられるでしょう。
こうした体験は顧客満足度の向上に直結し、リピート購入やブランドへの愛着(ロイヤルティ)を高める上で非常に重要になると考えられます。顧客との新しい関係を築くきっかけにもなり得るでしょう。
DXは、店舗運営やバックオフィス業務の効率化にも大きく貢献すると期待されています。
AIによる需要予測は在庫の最適化を促し、RPAなどのツールは受発注や経理といった定型業務を自動化するのに役立つでしょう。
これにより、作業時間や人件費といったコストの削減が見込めます。創出された時間を、従業員がより付加価値の高い接客サービスなどに充てられるようになる点も大きなメリットといえるかもしれません。
DXによって収集・分析された顧客データや購買データは、新たなビジネスチャンスの源泉となり得ます。
例えば顧客のニーズを深く理解することで、より的確な新商品の開発につなげることが考えられます。
また、Targetの事例のようにデータを活用してリテールメディア事業を展開するなど、全く新しいサービスを立ち上げることも可能です。データは小売業にとって新たな収益の柱を築く、貴重な資産といえるでしょう。
多くのメリットがある一方で、小売DXの推進には乗り越えるべき課題も存在します。
多くの企業が直面する共通の課題について、それぞれ見ていきましょう。
DXを成功させるには、デジタル技術やデータ分析に精通した専門人材の存在が不可欠とされています。
しかし情報処理推進機構(IPA)の調査によれば、多くの日本企業がDXを推進する人材の不足を「課題」と感じているのが現状です。特にビジネスの知識とITスキルの両方を兼ね備え、変革を主導できるプロジェクトマネージャーや、データを分析してビジネス価値を創出するデータサイエンティストといった職種は、業界を問わず需要が高く獲得競争が激化しています。
社内で育成しようにも、体系的な教育プログラムの構築や実践の場を提供することの難しさがあります。そのため外部の専門家と連携したり、従業員のリスキリング(学び直し)を支援したりするなど、多角的な人材確保・育成戦略が求められるでしょう。
出典参照:DX動向2025(P.45)|独立行政法人情報処理推進機構
多くの企業では長年にわたり使用してきた基幹システムやPOSシステムなどが老朽化・複雑化し、最新のデジタル技術との連携が困難になっている場合があります。
経済産業省が警鐘を鳴らす「2025年の崖」でも指摘されているように、このような「レガシーシステム」はDX推進の大きな足かせとなり得ます。
また部門ごとに異なるシステムが導入され、データが分断されてしまう「サイロ化」も深刻な問題です。これでは、全社横断的なデータ分析や顧客に対する一貫したアプローチができません。
システムを全面的に刷新するには莫大なコストと時間がかかるため、APIなどを活用して既存システムと新しいツールを連携させ、部分的にデータを統合していくといった現実的なアプローチも検討する必要があるでしょう。
出典参照:D X レポート~ITシステム「2025年の崖」の克服とDXの本格的な展開~(P.5)|経済産業省
新たなシステムの導入や開発には、当然ながら初期投資や継続的な運用コストが発生します。特に中小企業にとっては、このコストがDX推進の大きな障壁となることも少なくありません。
さらに難しいのが、投資に対する効果(ROI)を正確に見極めることです。業務効率化によるコスト削減のように数値化しやすい効果もあれば、顧客満足度の向上やブランドイメージの向上といった、すぐには金銭的価値に換算しにくい効果もあります。
効果が表れるまでに時間がかかるケースも多いため、短期的な視点だけで判断すると本来有望な投資を見送ってしまうことにもなりかねません。
そのため金銭的な指標だけでなく、顧客や従業員の満足度といった非財務的な指標も組み合わせ、長期的かつ多角的な視点で投資対効果を評価していく姿勢が重要になると考えられます。
海外で成功したビジネスモデルやDX施策を日本に持ち込んでも、期待した成果が得られないケースは少なくありません。先進的な事例を参考にすることは有益ですが、そのまま導入しても機能しない場合があります。日本市場には独自の商習慣や顧客の期待値があり、海外とは前提条件が大きく異なるためです。
ここでは、海外事例をそのまま適用できない背景にある日本市場の特性を4つの視点から解説していきます。自国の市場特性を理解することで、海外事例を自社に適した形にアレンジできるようになるでしょう。
日本と海外では、商取引の進め方や顧客の購買行動に大きな違いがあります。例えば、欧米では契約書ベースの取引が中心ですが、日本では長期的な信頼関係を重視する商習慣が根強く残っています。
このため、効率化を追求しすぎると、取引先との関係が損なわれる恐れがあります。また、顧客の購買行動も異なる特徴を持ちます。日本の消費者は商品を慎重に比較検討する傾向が強く、店頭での接客や丁寧な説明を重視する人が多いでしょう。
一方、欧米ではオンラインで素早く購入する顧客が主流です。このような違いを無視して、海外で成功したセルフサービス型のシステムをそのまま導入しても、顧客に受け入れられない可能性があります。日本市場に適した販売プロセスや顧客接点の設計が必要です。海外事例を参考にしつつも、日本の商習慣や顧客の期待に合わせた調整を加えることが求められます。
海外と日本では、店舗の運営体制や人員配置の考え方に違いがあります。欧米の小売店では、少人数のスタッフで効率的に店舗を回す設計が一般的です。セルフレジや在庫管理の自動化が前提となっており、人手をかけないオペレーションが基本となっています。
一方、日本では手厚い接客サービスが重視され、スタッフが積極的に顧客対応を行う文化があります。このため、省人化を進めすぎると、顧客満足度の低下につながる恐れがあるでしょう。
海外の事例を導入する際には、現場のスタッフが無理なく使いこなせるかを検証する必要があります。さらに、労働時間や雇用形態に関する規制も国によって異なるため、人員計画にも影響を与えます。日本の雇用慣行に合わせた柔軟な調整が求められます。
海外事例を導入する際に見落としがちなのが、個人情報保護やデータ活用に関する法規制の違いです。日本では個人情報保護法によって、個人データの取り扱いに厳格なルールが定められています。顧客の同意なく情報を収集したり、目的外で利用したりすることはできません。
欧米でも一般データ保護規則であるGDPRなど厳しい規制がありますが、具体的な要件や解釈は国ごとに異なります。海外で問題なく運用されているデータ活用の仕組みが、日本では法令違反となる場合もあるため注意が必要です。
また、データの保管場所やセキュリティ対策についても、日本の法規制に沿った対応が必要です。クラウドサービスを利用する場合には、データの越境移転に関する規定も確認しておきましょう。法務部門や専門家と連携し、日本の法令に適合した形でシステムを設計することが求められます。
日本市場では、価格だけでなくサービスの質に対する期待の高さが高い傾向があります。海外であれば低価格を優先し、サービスは最小限という割り切りが受け入れられる場合もありますが、日本ではそうはいきません。顧客は丁寧な接客や細やかな配慮を求めており、価格が多少高くてもサービスの質を重視する消費者が多いでしょう。このため、海外の低コスト型のビジネスモデルをそのまま持ち込んでも、顧客の支持を得られない可能性があります。
また、配送や返品対応についても求められる水準が高く、迅速かつ柔軟な対応が欠かせません。海外では数日かかる配送が普通でも、日本では翌日配送が標準となっているケースもあります。こうした期待に応えるには、追加のコストや仕組みが必要となるでしょう。

海外の成功事例をそのまま日本国内に持ち込んでも、必ずしもうまくいくとは限りません。
自社の状況や日本の市場環境に合わせ、戦略を調整することが重要です。ここでは、国内でDXを成功させるためのポイントをいくつか見ていきましょう。
DXは一部門の取り組みではなく、全社的な組織改革やビジネスモデルの変革を伴います。そのため、経営層の強いコミットメントが成功の絶対条件とされています。
経営トップがDXの重要性を深く理解し、明確なビジョンや目的を社内外に示すことが全ての始まりといえるでしょう。DX推進には部門横断的なプロジェクトの組成、予算の重点的な配分が必要です。そして時には既存事業との軋轢も生じるため、経営層による強力なリーダーシップと利害調整が欠かせません。
またDXは試行錯誤の連続であり、短期的な失敗を許容する文化を醸成することも経営の重要な役割です。DXを単なるIT戦略ではなく、「企業全体の経営戦略の中心に据える」という強い意志を組織全体で共有することが求められます。
最も重要なのは、あらゆるDXの取り組みにおいて「顧客の体験をいかに向上させるか」という視点を最終目的に据えることです。
海外の成功事例を見ても、その根底には常に顧客中心の考え方があります。最新のAIやARといった技術を導入すること自体が目的化してしまうと、現場で使われなかったり、顧客に受け入れられなかったりする「自己満足なDX」に陥る危険性があります。
そうならないためには、まずカスタマージャーニーマップなどを用いて顧客の行動や感情を可視化し、どこに課題(ペインポイント)があるのかを徹底的に分析することが重要です。その課題を解決するために最適な技術は何か、という順番で考えるべきでしょう。
技術はあくまで顧客価値を創造するための手段である、という本質を見失わないことが成功への鍵となります。
実際に日々店舗に立ち、顧客と直接コミュニケーションをとっているのは現場のスタッフです。DXを成功させるためには、この現場の知見と協力が欠かせません。
新しいシステムやツールを導入する際、トップダウンで一方的に進めてしまうと、現場の業務実態に合わなかったり、変化に対する抵抗感から活用されなかったりする可能性があります。
これを防ぐためには、企画の初期段階から現場のスタッフを巻き込み、彼らの意見やアイデアを積極的に取り入れることが重要です。またDXによって業務がどう変わるのか、どのようなメリットがあるのかを丁寧に説明し、十分なトレーニングの機会を提供することで、変化への不安を和らげることができます。
現場の成功体験が、全社的なDX推進の大きな力となるでしょう。
最初から全社的に大規模なシステムを導入するには、多大なコストと時間がかかり、失敗したときのリスクも大きくなります。
そこで有効なのが特定の店舗や部門、特定の業務に絞って試験的に導入し、効果を検証しながら段階的に展開していく「スモールスタート」というアプローチです。小さく始めることで、リスクを最小限に抑えながらDXの効果を具体的に測定できます。
ここで得られた成功体験やデータは、次のステップに進む際の説得力のある材料となり、社内の協力や追加の予算獲得にもつながりやすくなるでしょう。また試験導入の過程で明らかになった課題を改善しながら進められるため、最終的なシステムの完成度も高まります。
焦らず着実に成功を積み重ねていくことが、結果的にDX成功への近道となるかもしれません。
世の中ではAIやメタバースなど常に新しい技術が注目を集めますが、流行しているからという理由だけで安易に飛びつくのは危険です。
他社の成功事例はあくまで参考とし、最終的には「自社のビジネスが抱える本質的な課題は何か」を起点に、その解決に最も貢献する技術を選ぶという「課題ドリブン」のアプローチが重要になります。
まずは顧客からのクレームが多い業務、従業員の残業が常態化している業務など、社内の課題を徹底的に洗い出すことから始めましょう。その上で、各課題の解決策としてどのような技術が考えられるかを比較検討します。
コスト、導入のしやすさ、既存システムとの連携性、将来性など、複数の評価軸を持って冷静に判断することが自社にとって本当に価値のあるDX投資につながるでしょう。
本記事では、小売DXをリードする海外企業の成功事例から最新トレンド、そして国内で成功させるためのポイントまでを解説しました。
ウォルマートのOMO戦略やAmazon Goの無人決済など、海外の先進企業はデジタル技術を駆使して、これまでにない顧客体験を創造しビジネスを大きく成長させている様子がうかがえます。
これらの事例から学ぶべき最も重要なことは、単なる技術の模倣ではなく、その背景にある「顧客中心主義」や「データに基づいた意思決定」といった成功の本質を理解することです。そして、その本質を自社の文化や課題に合わせてどのように応用していくかを考えることが、DX成功の第一歩となります。
DXは一度システムを導入すれば終わりというプロジェクトではありません。市場や顧客の変化に対応し、継続的に改善を繰り返していく必要があります。この記事で紹介した事例やポイントをヒントに、まずは自社の課題を整理し、小さな一歩からでも自社ならではのDXを始めてみてはいかがでしょうか。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
