小売DXの第一歩はペーパーレス化!メリットや書類管理の課題を解説
小売

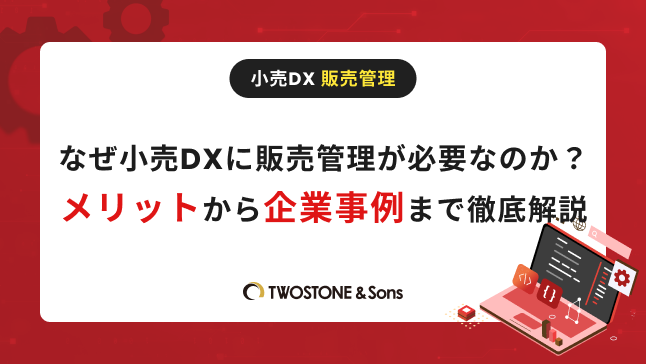
小売店のDX化を成功させる鍵は「販売管理」にあります。この記事では、販売管理システムを導入するメリットや、事業規模・業態に合った選び方のコツを詳しく解説します。おすすめのシステムも目的別に紹介しており、あなたの店舗が抱える課題の解決と成長をサポートできるでしょう。


・6万名以上のエンジニアネットワークを活用して課題を解決※
・貴社のDX戦略立案から実行・開発までワンストップで支援可能
※エンジニア数は2026年8月期 第1四半期決算説明資料に基づきます。
日々の売上管理や在庫確認に追われ、本来注力すべき戦略立案や顧客サービスに十分な時間を割けていないと感じることはないでしょうか。人手不足や競争の激化が進む現代の小売業界において、従来のやり方だけでは限界を感じる場面も少なくないでしょう。
この記事では、小売DXの第一歩として重要な「販売管理」に焦点を当て、その必要性からシステムの選び方、おすすめのサービスまでをわかりやすく解説します。自社の課題を解決し、成長を加速させるヒントを見つけていただければ幸いです。
多くの小売業が、変化の激しい市場環境の中で様々な課題に直面しています。経験や勘に頼る経営だけでは対応が難しくなっており、デジタル技術を活用した業務改革、すなわちDXの推進が求められています。
このセクションでは、なぜ販売管理のDXが重要視されているのか、その背景にある理由を解説します。
現在の小売業界は、少子高齢化などが背景にある慢性的な人手不足という大きな課題を抱えています。限られた人員で店舗を運営する中、手作業による売上集計や在庫管理は、入力ミスや確認漏れといったヒューマンエラーを引き起こす原因になり得ます。
また、特定の従業員しか業務内容を把握していない「業務の属人化」は、その担当者が不在の際に業務が滞るリスクをはらんでいます。これらの問題は見えないコストとして経営を圧迫し、顧客サービスの質の低下にもつながりかねません。販売管理をDX化することで、こうした定型業務の自動化が期待でき、スタッフは接客など付加価値の高い業務に集中できるようになるでしょう。
出典参照:2024年版 中小企業白書・小規模企業白書 概要|中小企業庁
スマートフォンの普及により、顧客は時間や場所を選ばずに商品を購入できるようになりました。その結果、実店舗に求められる役割も単に商品を販売する場所から、顧客一人ひとりに合った特別な購買体験を提供する場所へと変化しています。
ECサイトや大手チェーンとの競争が激しくなる中で、顧客の購買履歴や好みをデータとして把握し、パーソナライズされた提案を行うことが、他店との差別化につながります。顧客は単に商品を手に入れるだけでなく、自分に合った提案やスムーズな購買体験といった「価値」を求めています。アナログな管理手法では難しいデータ活用も、DXによって実現しやすくなるでしょう。
これまでの経営では、長年の経験や勘が重要な役割を果たしてきました。しかし、より精度の高い経営判断を行うためには、客観的なデータに基づいた分析が有効です。
販売管理システムを導入することで、どの商品がいつ売れたのか、どのような顧客がリピートしているのかといった販売データを正確に蓄積できます。データは、これまで気づかなかった顧客の隠れたニーズや、新たな商品の組み合わせといったビジネスチャンスを教えてくれることもあります。これらのデータを分析することで、売れ筋商品の発注を最適化して機会損失を防いだり、特定の顧客層に向けたキャンペーンを企画したりと、データに基づいた新たな売上機会の創出が期待できるのです。

小売DXを成功させる上で、その中心的な役割を担うのが「販売管理システム」です。これは商品の仕入れから在庫、販売、売上、顧客情報まで、事業運営に関わるデータを一元的に管理し、業務を効率化するためのITツールを指します。
これまでExcelや紙でバラバラに管理していた情報がシステム一つに集約されるため、情報の分断や入力ミスといったアナログ管理の課題解消につながります。
リアルタイムで正確な経営状況を可視化できる点が大きな特徴で、単に業務を楽にするだけでなく、蓄積されたデータを分析して次の戦略を立てるための「経営の羅針盤」とも言えるでしょう。近年では、専門知識がない方でも直感的に操作できるクラウド型のサービスが多く登場しています。
出典参照:デジタルガバナンス・コード|経済産業省
販売管理システムを導入すると、日々の業務が具体的にどのように変わるのでしょうか。多くのシステムに搭載されている主要な機能を知ることで、自社の課題解決のイメージがより明確になります。
このセクションでは、代表的な3つの機能について解説します。
販売管理システムの基本的な機能として、売上と顧客に関する情報をまとめて管理する機能が挙げられます。POSレジと連携させることで、商品が売れるたびに売上データが自動でシステムに登録され、いつでも最新の売上状況を正確に把握することが可能です。日々の締め作業で電卓を叩いて集計する必要がなくなり、作業負担と計算ミスを大幅に削減できます。
さらに会員カードやアプリと連携すれば、顧客の年齢層や性別、購買履歴といった貴重なデータも蓄積されます。これらのデータを分析することで、「どの年代の顧客が、どの曜日に、どのような商品を購入しているか」といった傾向を客観的に把握できます。この分析結果は、効果的な販売促進や品揃えの最適化につながり、顧客一人ひとりのニーズに合わせたサービス提供の土台となるでしょう。
多くの小売店にとって重要な在庫管理も、システム化によって大幅な効率化が期待できます。商品が売れると自動で在庫数がシステムに反映されるため、これまで時間と労力を要していた手作業での棚卸しの負担を軽減します。リアルタイムで正確な在庫数を把握できるため、顧客から在庫の問い合わせがあった際にも、バックヤードへ確認に行くことなく即座に回答でき、顧客満足度の向上にも貢献します。
また、販売実績データに基づいて、商品の売れ行きに応じた適切な発注点を設定することも可能です。在庫が一定数を下回った際に自動で発注アラートを出す機能もあり、発注漏れによる販売機会の損失や、過剰在庫を抱えるリスクを低減させる一助となるでしょう。正確な在庫数を維持することは、健全な店舗経営に不可欠です。
実店舗に加えてECサイトを運営している場合、在庫管理はさらに複雑化します。販売管理システムの中には、実店舗とECサイトの在庫情報を一元管理できるものがあります。どちらかのチャネルで商品が売れた際に、もう一方の在庫情報も自動で更新されるため、「ECサイトで注文が入ったのに実店舗で売れてしまっていて在庫がなかった」といった売り越しトラブルの防止に役立ちます。
この連携は在庫だけでなく、売上や顧客情報も同様です。店舗とECサイトのデータを統合して分析することで、例えば「ECサイトで商品を見た顧客が、後日実店舗で購入する」といったオンラインとオフラインを横断した購買行動を把握することも可能になります。これにより、効果的な販売戦略の立案が実現できるでしょう。
販売管理システムの導入は、業務効率化だけでなく店舗の収益性向上や持続的な成長にも貢献します。このセクションでは、システム導入によって期待できる代表的な4つのメリットについて、具体的に見ていきましょう。
販売管理システム導入の大きなメリットとして、バックオフィス業務の劇的な効率化が挙げられます。日々の売上集計や在庫確認や発注といった業務は、手作業では多くの時間と手間を要し、入力ミスなどのヒューマンエラーも発生しがちです。システムによってこれらの業務を自動化することで、作業時間を大幅に短縮し、業務の正確性を高めることが期待できます。
例えば、これまで営業終了後に数時間かかっていたレジ締めや売上報告書の作成が、ボタン一つで完了するようになります。これにより従業員の残業時間を削減し、人件費の抑制にもつながるでしょう。創出された時間を接客品質の向上や売場づくり、販売促進の企画といった、より創造的で店舗の売上に直結するコア業務に充てることが可能となり、店舗全体の生産性向上に貢献します。
正確な在庫管理は、店舗のキャッシュフローを健全に保つ上で非常に重要です。販売管理システムは、販売実績データに基づいて需要を予測し、適切な量を発注するためのサポートをします。これにより、人気商品の欠品による販売機会の損失(チャンスロス)を防ぎ、顧客の期待に応え続けることができます。
同時に、売れ行きの良くない商品の過剰在庫(デッドストック)を抱えるリスクも最小限に抑えることが可能です。過剰在庫は保管スペースを圧迫するだけでなく、仕入れにかかった資金を長期間寝かせてしまうことになり、キャッシュフローを悪化させる大きな要因です。無駄な在庫を減らすことは、資金繰りの改善に直結し、安定した経営基盤を築く上で有効な手段と言えるでしょう。
経営者の長年の経験や勘は、ビジネスにおいて非常に価値のあるものです。さらにそこに客観的なデータが加わることで、意思決定の精度とスピードは格段に向上します。販売管理システムを活用すれば、売上や在庫、顧客に関する最新のデータを、いつでもどこでもリアルタイムで確認できます。
これにより、「どの商品を重点的にプロモーションすべきか」「どの価格帯の商品が利益に貢献しているか」といった判断を、感覚に頼るだけでなく、具体的な数値という事実に基づいて迅速に行うことが可能になります。複数の店舗を運営している場合でも、全店舗の状況を横断的に分析し、店舗ごとの強みや課題を明確に把握できます。データという強力な羅針盤を得ることで、変化の激しい市場環境にも的確に対応していけるでしょう。
現代の小売業において、顧客との良好な関係を築くことは事業継続の鍵となります。販売管理システムで蓄積された顧客データを活用することで、一人ひとりに合わせた質の高いサービスを提供しやすくなります。例えば、顧客の過去の購買履歴から好みや購入サイクルを分析し、次回の来店時にパーソナライズされた商品を提案することが可能です。
また、購入金額に応じたポイントプログラムの管理や、誕生月に特別なクーポンを自動で配信するといった施策も容易に実行できます。こうした「自分のことを理解してくれている」という特別感は、顧客のロイヤリティを高め、単なる顧客から店舗のファンへと関係性を深めるきっかけとなります。結果として長期的なリピート購入につながり、安定した売上の基盤を築くことに貢献するでしょう。
多くのメリットが期待できる販売管理システムですが、導入を成功させるためには、事前に把握しておくべき注意点も存在します。メリットとデメリットの両方を理解し、自社の状況に合わせた計画を立てることが大切です。
販売管理システムの導入を検討する際、初期費用や月額利用料だけでなく、トータルコストで判断することが重要です。例えばシステムを利用するためのパソコンやタブレット、POSレジといった周辺機器の購入費用も考慮に入れる必要があります。既存の設備が使えない場合は、新たに見積もらなければなりません。
またクラウド型の多くは、利用機能や店舗数で料金プランが異なります。事業の成長に伴い上位プランへ変更すれば、月額費用が増加する可能性も視野に入れましょう。導入によって得られる業務効率化の効果と、これらの総費用を比較し、長期的な視点で費用対効果を慎重に見極めることが求められます。
新しいシステムを導入することは、これまでの業務フローが変わることを意味します。特に、長年アナログな方法に慣れてきた従業員にとっては、新しい操作を覚えることに抵抗を感じたり、業務に定着するまで時間を要することも考えられます。この移行期間を円滑に進めることが、導入成功の鍵となります。
そのためには、なぜシステムを導入するのかという目的やメリットを、経営層から従業員へ丁寧に説明し、理解と協力を得ることが不可欠です。導入ベンダーが提供する研修会を活用したり、社内で簡単なマニュアルを用意したりと、十分な教育期間を設けましょう。システムが現場に完全に定着し、効果を発揮するまでには、ある程度の時間とサポートが必要になることを理解しておくことが大切です。

数ある販売管理システムの中から、自社に最適な一つを選ぶためには、いくつかの重要なポイントがあります。このセクションでは、システム選びで後悔しないために押さえておきたい4つの視点を紹介します。
まず考慮すべきは、自社の事業規模や業種・業態にシステムが適合しているかという点です。例えば、個人経営の店舗と多店舗展開する企業では、求められる本部機能や管理の複雑さが異なります。自社の規模に対して機能が過剰すぎるとコストが無駄になりますし、逆に機能が不足していると、結局Excelなどを併用することになりDXの目的が達成できません。
また、業態に特化した機能の有無も重要な選定基準です。アパレルであれば色・サイズ別の在庫管理(SKU管理)、食品であれば賞味期限やロットの管理、雑貨店であればセット商品の管理など、自社のビジネスに不可欠な機能が標準で備わっているかを確認しましょう。将来的に店舗を増やす計画があるなら、多店舗管理に対応できるかも含めて、自社の現在と未来の姿にフィットするシステムを選ぶことが大切です。
多機能であることが、必ずしも良いとは限りません。使わない機能が多くても月額費用がかさむだけです。まずは自社が抱える課題を解決するために、「絶対に譲れない機能(Must)」と「あると嬉しい機能(Want)」をリストアップし、優先順位を明確にしましょう。この軸を持つことで、各システムを客観的に比較しやすくなります。
その上で、将来の事業展開を見据えた拡張性も確認しておくと安心です。例えば、将来的にECサイトを始める計画があるならEC連携機能、店舗数が増える可能性があるなら多店舗管理機能といった、将来のビジョンに対応できる柔軟性を持ったシステムを選ぶことが望ましいでしょう。最初はスモールスタートで始め、事業の成長に合わせて機能を追加できるようなシステムは、長期的なコストパフォーマンスにも優れています。
システムの導入と運用にかかるトータルコストが、自社の予算の範囲内であるかを確認することは不可欠です。初期費用だけでなく毎月発生する月額利用料や、オプション機能の追加料金、バージョンアップ費用、導入後のサポート費用なども含めて総額を把握しましょう。ハードウェアの購入や入れ替えが必要な場合は、その費用も忘れてはいけません。
料金プランが複数ある場合は、それぞれのプランで利用できる機能を詳細に比較し、自社にとってコストパフォーマンスが最も良い選択肢はどれか、慎重に検討することが求められます。安さだけで選んでしまうと、必要な機能が足りなかったりサポートが手薄だったりする可能性があります。価格と機能、サポート内容のバランスを総合的に見極めることが重要です。
システムは毎日使うものであるため、ITに不慣れな従業員でも直感的に操作できるわかりやすさが求められます。デザインが洗練されていても実際の業務フローに合わない、操作が複雑といったことでは現場に定着しません。多くのシステムでは無料のトライアル期間やデモンストレーションが用意されているため、契約前に実際に操作性を試してみることを強くお勧めします。
また、導入後に不明点やトラブルが発生した際に、気軽に相談できるサポート体制が整っているかも重要な確認項目です。電話やメール、チャットなど、どのようなサポートが受けられるのかを事前にチェックしておくと安心して運用を開始できるでしょう。手厚いサポートは、スムーズな導入と継続的な活用のための保険とも言えます。
このセクションでは、中小規模の小売店から支持されている代表的な販売管理システムを、目的別に4つ紹介します。
それぞれのシステムが持つ特徴を比較し、自社の課題解決に最も近いサービスを見つけるための参考にしてください。
スマレジは、iPadやiPhoneといった身近なデバイスで利用できるクラウド型のPOSレジサービスです。大きな特徴は、月額0円のスタンダードプランから始められる手軽さにあります。基本的なレジ機能はこの無料プランで利用でき、店舗の成長やニーズの変化に合わせて高度な在庫管理や顧客管理、売上分析といった機能を月額料金で追加していくことが可能です。
初期費用を抑えてスモールスタートしたい個人店や小規模な店舗にとって、非常に魅力的な選択肢と言えるでしょう。また、「スマレジ・アプリマーケット」というプラットフォームを通じて、会計ソフトや決済サービス、予約システムなど、様々な外部サービスと簡単に連携できる拡張性の高さも強みです。自社の業務に合わせて必要な機能を組み合わせ、オリジナルの販売管理環境を構築できます。
出典参照:スマレジ|株式会社スマレジ
STORES レジは、ネットショップ開設サービスで知られるSTORESが提供するPOSレジです。最大の強みは、同社のネットショップサービス「STORES」と完全に連携し、実店舗とオンラインストアの情報を一元管理できる点にあります。商品情報や在庫、顧客情報をまとめて管理できるため、オンラインとオフラインをまたいでビジネスを展開している店舗のバックオフィス業務を劇的に効率化します。
例えば実店舗で商品が売れると、ネットショップの在庫も自動で減少するため、売り越しによるトラブルを防ぐことができます。シンプルな操作画面も魅力で、IT機器の操作に不安がある方でも直感的に扱いやすいように設計されています。ネットショップと実店舗の連携をスムーズに行いたい事業者にとって、有力な候補となるでしょう。
ネクストエンジンは、複数のECサイトを運営している事業者向けの業務効率化に特化したシステムです。複数のECサイトなど、様々な販売チャネルの情報を一元管理することを得意としています。各モールからの受注情報を自動で取り込み、在庫数をリアルタイムで連携させ、発送完了メールの送信までを自動化する機能が充実しています。
複数のネットショップからの注文処理や問い合わせ対応、在庫調整といった煩雑な作業に追われている事業者のバックオフィス業務を大幅に削減します。これによりスタッフは商品企画やマーケティングといった、売上を伸ばすための創造的な業務により多くの時間を割くことが可能になります。EC事業の規模拡大を目指す事業者にとって、強力な業務基盤となるシステムです。
出典参照:ネクストエンジン|Hamee株式会社
アラジンオフィスは、中小企業向けの販売・在庫管理パッケージシステムです。幅広い業種に対応していますが、特にアパレル業界特有の色・サイズ別の在庫管理(SKU管理)や、食品業界で必須となるロット番号管理・賞味期限管理といった、専門的な管理機能が豊富に用意されている点が大きな強みです。これにより、業種特有の複雑な在庫管理を正確かつ効率的に行うことができます。
また、パッケージシステムでありながら、企業の独自の業務フローや商習慣に合わせて柔軟にカスタマイズできる点も特徴です。必要な機能を組み合わせて、自社に最適化されたシステムを構築することが可能です。販売管理だけでなく、生産管理や会計まで含めた基幹システムとして、企業全体の業務効率化を目指す場合に有力な選択肢となるでしょう。
出典参照:アラジンオフィス|株式会社アイル

自社に合いそうなシステムが見つかったら、計画的に導入を進めていきましょう。このセクションでは、導入を成功させるための基本的な4つのステップを紹介します。焦らず、一つひとつの段階を丁寧に進めることが大切です。
最初に行うべき最も重要なことは、「何のためにシステムを導入するのか」という目的をはっきりさせることです。「在庫管理の時間を半分にしたい」「データ分析で客単価を10%上げたい」など、現在自社が抱えている課題を具体的に書き出し、可能な限り数値目標を立ててみましょう。漠然と「効率化したい」と考えるよりも、具体的なゴールを設定することで、必要な機能が明確になります。
そしてこの目的を経営者だけでなく、現場で実際にシステムを使うことになる従業員とも共有することが不可欠です。全員が同じ方向を向いてプロジェクトをスタートさせることが、導入を成功に導くための第一歩となります。この目的が明確であればあるほど、後のシステム選定の軸がぶれません。
次に、ステップ1で定めた目的を達成できるシステムを探します。インターネット検索や業界専門誌、この記事で紹介した情報を参考に、自社の課題を解決できそうなシステムの候補をリストアップしましょう。この時、最初から1社に絞り込むのではなく、複数のシステムを比較検討することが重要です。
各システムの公式サイトで機能や料金プランを比較し、自社の要件に合いそうなシステムを2〜3社程度に絞り込みます。この段階で各社に資料請求を行い、より詳細な情報を入手しておくと、後の比較検討がしやすくなります。導入事例なども参考に、自社と似たような規模や業種の企業が、どのように活用して成果を上げているかを確認するのも良い方法です。
候補を絞り込んだら、実際に製品のデモンストレーションを体験して正式な見積もりを取り寄せましょう。デモでは日々の業務で頻繁に使うであろう機能を実際に操作させてもらい、画面の見やすさや操作のしやすさを確認します。特にレジ操作や在庫検索、日報の出力といった日常業務が、ストレスなく行えるかは重要なポイントです。
可能であれば現場の従業員の代表者にも同席してもらい、実務的な視点からの意見を聞くことが望ましいでしょう。見積もりを依頼する際は初期費用や月額料金だけでなく、オプション機能やサポートにかかる費用も含めたトータルコストを算出してもらい、各社を公平に比較検討します。不明な点は遠慮なく質問し、納得のいくまで説明を求めましょう。
導入するシステムが決定したら、契約と並行して社内での準備を計画的に進めます。いつまでに何を完了させるかという詳細な導入スケジュールを作成し、関係者全員で共有します。特に、既存の顧客情報や商品マスタなどを新しいシステムへ移行する作業は、データの形式を整えるなど手間がかかる場合があるため、余裕を持った計画が必要です。
また、従業員に対して導入の目的を改めて説明し、操作研修会などを実施します。一度の研修だけでなく、運用開始後もフォローアップの機会を設け、疑問点をすぐに解消できる体制を整えることが大切です。システムは導入して終わりではありません。定期的に活用状況を確認し、より効果的な使い方を模索していくという、継続的な改善の姿勢が成功の鍵となります。
小売業界では、販売管理システムの導入が業務効率化と経営判断の迅速化に直結します。しかし、システム選定や導入効果について具体的なイメージを持ちにくいという声も少なくありません。
実際に導入した企業の事例を見ることで、どのような課題が解決され、どんな変化が生まれたのかを具体的に理解できるでしょう。業種や規模が異なる企業でも、共通する導入のポイントや効果があります。
ここからは、販売管理システムを導入して成果を上げている3社の事例を紹介していきます。
全国に店舗を展開する島村楽器株式会社は、楽器販売と音楽教室を中心とした事業を運営しています。同社では、日立システムズのFutureStageという販売管理システムを導入し、店舗運営の効率化を実現しました。
導入前は店舗データをバッチ処理していたため、売上や在庫情報の把握に時間がかかっていました。顧客動向をリアルタイムで把握できない状況は、経営判断を行う上で大きな課題でした。また、1店舗あたり数千点に及ぶ商品を扱っており、在庫管理だけでもスタッフに負担がかかっていました。
システム導入後は、全店舗の在庫をリアルタイムで確認できるようになりました。例えば、顧客から在庫の問い合わせがあった際、以前なら他店に電話をかけて1つずつ確認していましたが、今では画面上ですぐにチェックできます。在庫が残り少なくなると発注勧告をしてくれる機能もあり、顧客を待たせることなく対応できるようになりました。
出典参照:島村楽器株式会社様:FutureStage 小売業向けシステム|株式会社日立システムズ
洗剤や日用品の製造販売を手がける株式会社UYEKIは、内田洋行のスーパーカクテルを導入しました。同社は全国に3拠点と2つの倉庫を持ち、複雑な在庫管理と業務プロセスに課題を抱えていました。
導入前は、販売管理システムの老朽化に加えて、取引増加に伴う購買業務の手作業が負担となっていました。手書き伝票を使用していたため、伝票発行の自動化や在庫管理の効率化が急務でした。また、製造を外部委託している同社では、資材を委託先に提供する際の管理が煩雑化していました。
システム導入により、販売・購買・売掛・買掛・在庫・統計業務がすべて自動化されました。特に効果が高かったのは同一資材が複数倉庫に分散して保管されている状況を一元管理できるようになった点です。どの倉庫に何があるかがパソコン1つで確認でき、倉庫別の在庫数量や在庫金額も素早く見える化できるようになりました。
出典参照:合成洗剤卸売業×販売管理パッケージシステム – 導入事例|株式会社内田洋行
京都を拠点にセレクトショップを展開する株式会社グジは、スマレジというクラウド型POSレジシステムを導入しました。同社は実店舗とECサイトを運営しており、効率的な在庫管理と顧客管理の必要性を感じていました。
導入前はエクセルで売上を管理するアナログな方法をとっており、どの顧客に商品を販売したかの記憶が曖昧になっていました。在庫管理や顧客管理は店舗運営の要となるため、数年でこの状況に限界を迎えていました。当時、従来型のPOSシステムは高額で、会社の規模では経費的に導入が難しい状況でした。
スマレジ導入の決め手となったのは、安価でありながら必要な機能が揃っていた点です。iPadやiPhoneでアプリをダウンロードすればすぐに運用を開始でき、新店舗のオープン時でも前日や当日の設定で対応できる手軽さがありました。また、同社の要望に合わせて機能をカスタマイズしてくれた点も高く評価しています。
出典参照:スマレジに決めた3つの理由「セレクトショップguji」|株式会社スマレジ
本記事では、小売DXの第一歩として販売管理システムの重要性や選び方、導入の進め方について解説しました。
人手不足や競争の激化といった課題に対応するためには、デジタル技術の活用が有効な手段の一つとなります。
販売管理システムは、日々の業務を効率化するだけでなく、データに基づいた経営判断を支援し、事業の成長を後押しする力強いパートナーとなり得ます。まずは気になるシステムの資料請求や無料トライアルから、自社の未来を変える一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
