小売DXの第一歩はペーパーレス化!メリットや書類管理の課題を解説
小売

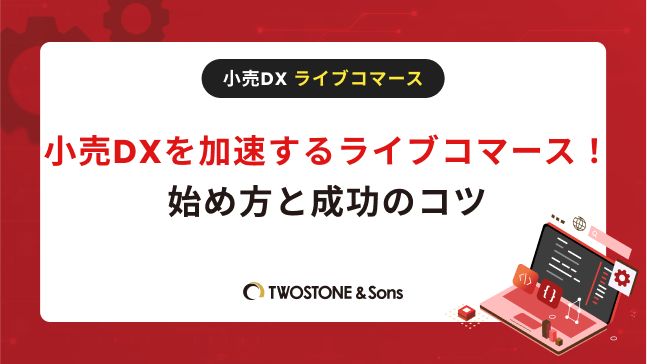
小売DXを加速するライブコマースの始め方を5ステップで解説します。プラットフォームの選び方から、アパレルや食品など相性の良い商材、失敗しないための注意点、成功のコツまで網羅。オンラインでの顧客体験を高めたい担当者は必見です。


・6万名以上のエンジニアネットワークを活用して課題を解決※
・貴社のDX戦略立案から実行・開発までワンストップで支援可能
※エンジニア数は2026年8月期 第1四半期決算説明資料に基づきます。
「オンラインでの接点は増えたけど、ECの売上が伸び悩んでいる」「リアル店舗のように、お客様との距離を縮めたい」
このようなお悩みを抱える小売企業の間で、近年注目が高まっているのが「ライブコマース」です。
リアルタイムで商品を紹介しながら視聴者と対話できるこの手法は、単なる販売チャネルではなく、顧客とのエンゲージメントを高め購買意欲を刺激する“体験型接客”ともいえます。写真や文章では伝わりにくい、商品の魅力や想いをライブ配信を通じてリアルに届けられる点が大きな特長です。
この記事ではライブコマースの基本から導入メリット、商材選び、成功のコツまで網羅的に解説します。導入の流れも5つのステップでわかりやすく紹介しているため、ぜひ参考にしてください。

ライブコマースとは、ライブ配信とEコマースを組み合わせた新しい販売手法です。
配信者がリアルタイムで視聴者とコミュニケーションを取りながら商品を紹介し、視聴者はその場で質問をしたり感想を共有したりしながら購入できます。
従来のECサイトが写真とテキストで商品を「静的」に伝えるのに対し、ライブコマースは動画と対話で「動的」に商品の魅力を伝えられるのが最大の特徴です。この双方向のコミュニケーションが、まるで実店舗で接客を受けているかのような臨場感と信頼感を生み出し、高い購買率に繋がります。
オンラインでの顧客接点が希薄になりがちな現代において、顧客とのエンゲージメントを高め、新たな購買体験を創出する手法として多くの小売企業から熱い視線が注がれています。
ライブコマースを導入することで、企業は多くのメリットを得られます。
まず、最大の利点は商品の魅力を最大限に伝えられることです。写真やテキストでは限界のあった商品の質感やサイズ感、使い方などを動画で立体的に見せることで、顧客は購入後のイメージを具体的に描け購買意欲が強く刺激されます。
また視聴者からの質問やコメントにその場で答える双方向のコミュニケーションは、顧客の疑問や不安を解消し、ブランドへの信頼と親近感を育みます。 このような対話を通じて顧客との繋がりが深まり、長期的なファン化を促進できるのです。
さらに配信で得られる反応はリアルタイムの貴重な顧客データとなり、その後の商品開発やマーケティング戦略に活かせます。
ライブコマースは様々な商材で活用できますが、特にその効果を発揮しやすいジャンルが存在します。商品の特性を理解し、ライブ配信のメリットを最大限に活かせる商材を選ぶことが成功の第一歩です。
このセクションでは、代表的な3つのジャンルについて、なぜライブコマースと相性が良いのかを具体的に解説します。
アパレルや化粧品は、ライブコマースと非常に相性が良い代表的な商材です。これらの商品は静的な写真やテキストだけでは伝わりにくい情報が多く、顧客が購入をためらう一因となっていました。
例えばアパレルであれば、モデルが実際に着用することで服のシルエットや動きのあるドレープ感、素材の質感をリアルに伝えられます。視聴者は身長の違うスタッフが着比べるところを見てサイズ感を確認したり、コーディネートの提案を受けたりできます。
化粧品も同様に肌に乗せたときの発色やテクスチャー、メイクアップのテクニックを実演することで、使用感を具体的にイメージさせることが可能です。
このようにオンラインでありながら実店舗に近い体験を提供できるため、顧客の不安を解消すだけでなく安心して購入してもらえるのです。
食品・グルメもまた、ライブコマースで大きな効果が期待できるジャンルです。
シズル感あふれる映像は視聴者の五感を刺激し、強い購買意欲を喚起します。例えば農家が自ら畑で採れたての野菜を紹介し、その場で調理して見せる配信は、商品の新鮮さや生産者のこだわりをストーリーとして伝え深い共感を呼びます。
またパティシエがケーキを作る工程をライブで見せたり、ソムリエがワインのテイスティングをしながらその魅力を語ったりすることも有効です。調理工程や生産背景を見せることで商品の付加価値が高まり、単なる「食べ物」ではなく「特別な体験」として顧客に届けることができます。
視聴者からの「この食材に合うレシピは?」といった質問に答えることで献立のヒントも提供でき、顧客満足度の向上にも繋がります。
雑貨・インテリアはライブコマースを通じて実際の使用シーンを見せることで、顧客の購買意欲を高めることができます。これらの商品は単体で見るよりも、生活空間に置かれたときの様子をイメージできた方が魅力が伝わりやすいためです。
例えば、デザイン性の高い食器を実際にテーブルセッティングして見せたり、アロマディフューザーの香りの特徴を言葉で表現しながら使い方を実演したりする配信が考えられます。また収納グッズであれば、散らかったスペースが綺麗に片付いていく様子を実演することで商品の魅力が直感的に伝わります。
顧客が自分の生活に商品を取り入れた際の具体的なイメージを喚起させることが重要です。複数の商品を組み合わせたコーディネート提案も、アップセルやクロスセルに繋がりやすい有効な手法と言えるでしょう。
多くのメリットがある一方で、ライブコマースを成功させるためには事前に理解しておくべき注意点も存在します。
まず、どれだけ魅力的な配信を企画しても見てもらえなければ意味がないため、集客のための事前告知が不可欠です。SNSやメールマガジンで配信日時や内容を繰り返し告知し、視聴者の期待感を高める必要があります。
次に、ライブ配信には機材トラブルや回線不良といったリスクがつきものです。予期せぬ事態に備え、十分なリハーサルとトラブル発生時の対応策を決めておくことが重要です。
さらに、リアルタイムでのやり取りは不適切な発言が炎上に繋がるリスクもはらんでいます。ブランドイメージに合った配信者を慎重に選び、配信のコンセプトを明確に共有しておくことでブランドイメージを損なう事態を防ぎましょう。

ライブコマースを始めるには、配信するためのプラットフォームが必要です。プラットフォームは大きく3つのタイプに分けられ、それぞれに特徴があります。
自社の目的や予算、ターゲット層などを総合的に考慮し、最適なプラットフォームを選ぶことが成功への鍵となります。このセクションでは、それぞれのタイプの特徴を詳しく見ていきましょう。
InstagramやYouTube、TikTokなどのSNSが提供するライブ配信機能を利用する方法です。
このタイプの最大のメリットは、普段から利用しているアカウントで手軽に始められる点にあります。特別なツール導入の必要がなくフォロワーに対して直接アプローチできるため、比較的集客しやすいのが特徴です。特に、すでに多くのフォロワーを抱えている企業にとっては、既存のファンとのエンゲージメントを深める絶好の機会となります。
一方で、多くのSNSではアプリ内で直接決済まで完結する機能がまだ限定的であり、購入のためにはプロフィール欄のリンクからECサイトへ遷移してもらう必要があります。この購入までの導線がやや煩雑になる点がデメリットと言えるでしょう。
まずはコストをかけずに試してみたい、という企業におすすめの方法です。
自社のECサイトにライブコマース機能を直接埋め込むことができる、専門のツール(SaaS)を利用する方法です。
このタイプの強みは、自社サイト内で配信から購入までをシームレスに完結させられる点にあります。視聴者は配信を見ながら、画面を離れることなくスムーズに商品をカートに入れて決済できるため、高い購入率が期待できます。
また、自社のブランドイメージに合わせたデザインで配信ページを構築できるため、世界観を統一しやすいのも魅力です。
顧客データも自社で管理・分析しやすく、マーケティング施策に活用しやすいでしょう。ただし、導入費用や月額利用料といったコストが発生する点がデメリットです。
本格的にライブコマースに取り組み、売上を最大化したいと考える企業に適した選択肢です。
大手ECモールが提供するライブコマース機能を利用する方法です。
このタイプの最大のメリットは、ECモール自体の高い集客力を活用できる点にあります。モールには常に多くの買い物客が訪れているため、まだ自社の認知度が低い企業でも新たな顧客層にアプローチできる可能性があります。
また大手モールが提供する機能であるため、視聴者も安心して利用できるという信頼性の高さも魅力です。
一方で、出店料や売上に応じた販売手数料が発生するため、コスト管理が重要になります。またモールの規定のフォーマットで配信する必要があるため、デザインや機能の自由度が低く独自性を出しにくい点がデメリットとして挙げられます。
ライブコマースを成功させるためには、行き当たりばったりではなく、計画的に準備を進めることが重要です。
このセクションでは、実際にライブコマースを始めるための基本的な流れを5つのステップで解説します。この手順に沿って進めることで、目的が明確で効果的な配信を実現できるでしょう。
まず最初に、「何のためにライブコマースを行うのか?」という目的を明確に設定することが最も重要です。
例えば「新商品の売上を10%向上させる」「新規顧客を50人獲得する」「ブランドの認知度を高める」など、できるだけ具体的な目的を立てましょう。目的が曖昧なままでは企画内容もぼやけてしまい、効果測定もできません。
そして、その目的が達成できたかを客観的に測るための指標であるKPI(重要業績評価指標)も同時に設定します。KPIには、売上目標であれば「購入率(CVR)」や「平均注文単価」、認知度向上であれば「ユニーク視聴者数」や「コメント数」、「SNSでのシェア数」などが考えられます。
この目的とKPIが、以降のすべてのステップの判断基準となります。
目的とKPIが定まったら、次に「誰に、何を、どのように伝えるか?」という配信の具体的な企画を立てます。
まずターゲットとなる顧客像を明確にし、その人たちが興味を持つであろう商品を選定します。配信者は、商品知識が豊富で視聴者と楽しくコミュニケーションが取れる人物が理想です。自社スタッフを起用するのか、インフルエンサーに依頼するのかを検討しましょう。
配信内容は単なる商品説明に終始するのではなく、視聴者が参加して楽しめる要素を取り入れることが成功の鍵です。例えば視聴者からの質問にリアルタイムで答えるQ&Aコーナーを設けたり、ライブ限定のクイズ企画を実施したりするなど、エンターテインメント性を意識した構成を考えましょう。
企画内容が固まったら、それを実現するための配信プラットフォームを選びます。
プラットフォームには手軽に始められる「SNS活用型」、自社ECサイトに機能を埋め込む「SaaS型」、モールの集客力を活かせる「モール出店型」など、様々な選択肢があります。どのプラットフォームが最適かは、ステップ1で設定した目的やターゲット層によって異なります。
例えば若年層の新規顧客獲得が目的ならばTikTokやInstagram、既存顧客との関係強化や売上最大化が目的ならばSaaS型が適しているかもしれません。各プラットフォームのメリット・デメリット、コストを比較検討して自社の戦略に最も合ったものを選びましょう。
初めてで不安な場合は、まずはコストのかからないSNS活用型から試してみるのも良い方法です。
配信の準備が整ったら、いよいよ集客と本番です。ライブ配信は、どれだけ多くの人に見てもらえるかが成功を大きく左右します。
少なくとも配信の1週間前からSNSやメールマガジン、ウェブサイトのバナーなどを活用し「いつ、どこで、どんな内容の配信をするのか」を繰り返し告知しましょう。配信テーマや登場する商品、限定特典などを少しずつ見せていくことで視聴者の期待感を高めます。
配信当日は事前に決めた企画や台本に沿って進行しつつも、ガチガチになりすぎないことが大切です。視聴者からのコメントや質問を積極的に拾い、対話を楽しみながら臨機応変に対応することでライブならではの臨場感と一体感が生まれます。
ライブ配信は、実施して終わりではありません。次回の成功に繋げるための効果測定と分析が不可欠です。
配信終了後、まずはステップ1で設定したKPIの数値を集計し目標を達成できたかを確認します。売上や視聴者数といった定量的なデータだけでなく「どのタイミングで視聴者が増減したか」「どんなコメントが多かったか」「どの商品への反応が良かったか」といった定性的な情報も重要です。
これらのデータを多角的に分析し「企画内容は適切だったか」「集客方法は効果的だったか」「配信時間に問題はなかったか」といった観点から、成功要因と改善点を洗い出します。
このPDCAサイクルを回し続けることが、ライブコマースの成果を継続的に高めていくための最も確実な方法です。

ライブコマースの基本的な始め方を理解した上で、さらにその効果を最大化するためにはいくつかの重要なコツがあります。
このセクションでは配信を成功に導き、視聴者を惹きつけて売上に繋げるための特に重要な3つのポイントを解説します。
ライブコマースの成否は、配信者の魅力に大きく左右されると言っても過言ではありません。
視聴者は商品だけでなく、「誰が」紹介しているのかも重視しています。商品知識が豊富なことはもちろんですが、それ以上に明るい人柄で視聴者とのコミュニケーションを楽しみ、その場の空気を盛り上げることができる人物が理想です。
必ずしも有名なインフルエンサーである必要はありません。商品への愛情や開発への熱い想いを持つ自社のスタッフが配信者を務めることで、その誠実さが視聴者に伝わり高い共感と信頼を得られるケースも多くあります。
ブランドの世界観や商品のターゲット層を考慮し、最もメッセージを届けられる人物を慎重に選定しましょう。
視聴者の「欲しい」という気持ちを「今すぐ買う」という行動に変えるためには、強力な後押しが必要です。そこで効果的なのが、ライブ配信中だけの特別な企画を用意することです。
例えば「配信終了後30分間だけ使える限定割引クーポン」や「ライブ中に購入した方だけの限定ノベルティプレゼント」、「通常はセット販売していない商品の特別セット」などが考えられます。
このような「今、ここでしか手に入らない」という限定性や希少性は、視聴者の購買意欲を強く刺激し「この機会を逃したくない」という気持ちにさせます。配信のクライマックスでこうした特典を発表することで、売上を最大化することが期待できるでしょう。
ライブコマースの成果は、配信中のパフォーマンスだけで決まるわけではありません。配信前から配信後までの一連の流れをデザインすることが重要です。
配信前の告知活動は、視聴者数を確保するための生命線です。SNSなどでカウントダウン投稿をしたり、配信内容を少しだけ見せたりして視聴者の期待感を醸成しましょう。
そして、見逃してはならないのが配信後のフォローです。ライブ配信の録画データ(アーカイブ)を必ず残し、いつでも見返せるようにしておくことでリアルタイムで視聴できなかった人にもアプローチできます。
アーカイブ映像を短く編集してSNSでシェアするなど、コンテンツを二次利用することで一度の配信効果を何倍にも高めることが可能です。
ライブコマースは、単に商品をオンラインで売るための新しい手法ではありません。リアルタイムで顧客の生の声を聞き、深い信頼関係を築くことでブランドの熱心なファンを育てていくための強力なコミュニケーションツールです。
写真やテキストだけでは伝えきれなかった商品の本当の魅力やブランドの想いを届け、顧客一人ひとりに寄り添った特別な購買体験を提供することは、まさに小売業界が目指すべきDXの理想的な姿と言えるでしょう。
この記事でご紹介したメリットや成功のポイントを参考に、まずは自社に合ったプラットフォームの検討から始めてみませんか。 ライブコマースという新しい武器を手に、お客様との関係を築きビジネスを次のステージへと前進させていきましょう。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
