小売DXの第一歩はペーパーレス化!メリットや書類管理の課題を解説
小売

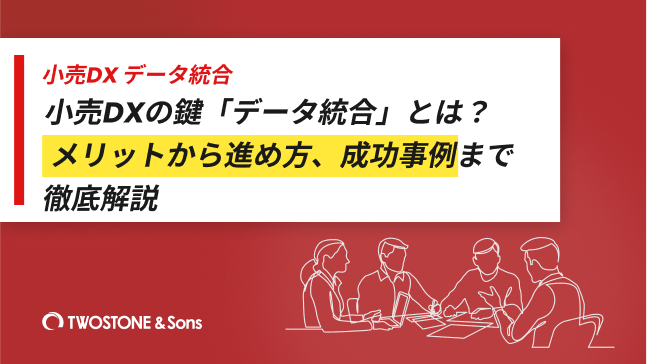
小売DXの鍵となるデータ統合。本記事では、その基本からメリット、具体的な進め方、IT基盤の選び方、失敗しないための対策、成功事例までを網羅的に解説します。データサイロ化に悩む担当者必見。顧客理解を深め、ビジネスを成長させるヒントがここにあります。


・6万名以上のエンジニアネットワークを活用して課題を解決※
・貴社のDX戦略立案から実行・開発までワンストップで支援可能
※エンジニア数は2026年8月期 第1四半期決算説明資料に基づきます。
店舗やECサイト、アプリなどで顧客との接点が増える中、「それぞれのデータがバラバラで、顧客の全体像が見えない」と感じていませんか。その課題を解決する鍵が「データ統合」です。
この記事では小売業のDXを推進する担当者の方へ、データ統合の基本からメリットや具体的な進め方、企業の成功事例までを分かりやすく解説します。データ活用の次の一歩を踏み出すためのヒントを見つけてください。
多くの小売企業で課題となっているのが、「データサイロ」と呼ばれる状態です。これは店舗のPOSシステムやECサイト、顧客管理システムなどがそれぞれ独立してデータを管理し、組織全体で情報をうまく活用できていない状況を指します。
データサイロに陥ると、例えば店舗の優良顧客がECサイトでは新規顧客として扱われるなど、顧客一人ひとりに対して一貫したサービスを提供することが難しくなります。
その結果、顧客満足度を下げてしまったり、貴重な販売機会を逃してしまったりと、経営に与える影響は少なくないでしょう。

小売DXで重要となる「データ統合」とは、単にデータを一箇所に集めることだけを意味するものではありません。店舗やECサイト、アプリなどのあらゆる場所から得られる顧客の情報を集約し、それらを一人ひとりの顧客に紐づけて整理することで、いつでも活用できる状態に整える一連のプロセスを指します。
大切なのは、集めたデータを「使える」形にすることです。例えば、店舗とECで別々に管理されている顧客IDを名寄せして同一人物として認識できるように処理します。このプロセスを経て初めて、データは分析や施策に活かせる企業の「資産」へと変わるのです。
現在、多くの小売企業がデータ統合に力を入れている背景には、顧客の購買行動の大きな変化があります。かつて顧客との接点は実店舗が中心でしたが、今ではSNSで商品を知り、ECサイトで情報を集め、実店舗で商品を確認してからアプリで購入するといったように、購買に至るまでの道のりが非常に複雑になっています。
このような状況の中で、顧客のニーズを的確に捉えて満足度の高いサービスを提供し続けるためには、オンラインとオフラインの垣根を越えて顧客の行動データを一元的に把握することが欠かせません。点在するデータを統合し、顧客一人ひとりの理解を深めることが、競争の激しい市場で選ばれ続けるための重要な鍵といえるでしょう。
データ統合は、企業経営に多くの利点をもたらします。このセクションでは、その中でも特に重要と考えられる4つのメリットについて、具体的に見ていきましょう。
データ統合がもたらす大きなメリットは、顧客一人ひとりの姿をより鮮明に捉えられるようになることです。店舗での購入履歴やECサイトでの閲覧商品、アプリの利用状況といったデータを組み合わせることで、「この顧客はAという商品を買った後、よくBという関連商品を見ている」といった具体的な行動パターンが明らかになります。
このような深い顧客理解に基づいて、それぞれの顧客に合わせたおすすめ商品の提案やクーポンの配信といった、きめ細やかなアプローチが可能になります。結果として顧客満足度が高まり、長期的なファンになってもらうことで、LTV(顧客生涯価値)の向上も期待できるでしょう。
データ統合は、これまで担当者の勘や経験に頼ることが多かった需要予測や在庫管理を、データに基づいた客観的なものへと進化させます。過去の購買データに天候やイベント、SNSのトレンドといった様々な情報を組み合わせて分析することで、より精度の高い需要予測が実現可能です。
これにより、「どの商品が、いつ、どの店舗で、どれくらい売れるのか」を高い確度で把握できるようになります。その結果、商品の欠品による販売機会の損失や、過剰な在庫を抱えることによるコストの増大といった、小売業特有の悩みを解決に導いてくれるでしょう。
データ統合基盤が整うと、組織全体で「同じデータ」を見ながら議論し、物事を判断する文化が育まれていきます。これまで部門ごとに見ていたデータが異なっていたために生じていた認識のズレがなくなり、全部門が客観的な事実に基づいて、迅速で合理的な意思決定を下せるようになります。
例えば、マーケティング部門が企画したキャンペーンの効果を、営業部門や商品開発部門も同じデータでリアルタイムに評価し、次の改善策を一緒に考えることができます。これにより、市場の変化や顧客ニーズの動きにも、より機敏に対応できるようになります。このようなデータドリブンな文化は、組織全体の力を高めることに繋がるでしょう。
データ統合は、日々の業務効率を大きく改善する点も見逃せません。これまで手作業で行っていた、レポート作成のためのデータ収集や集計といった作業の多くを自動化できるためです。また、手作業によるヒューマンエラーを減らし、データの正確性を高める効果も期待できます。
各システムから手動でデータを抜き出し、表計算ソフトで加工していたような時間が削減され、従業員はより付加価値の高い分析業務や新しい施策の企画といった、創造的な仕事に集中できるようになります。
これは単にコストを削減するだけでなく、従業員のモチベーションを高め、組織全体の生産性を向上させる効果も期待できます。
データ統合を進める上で、どのようなデータを集めるべきか見ていきましょう。このセクションでは、小売業において特に重要となる4つのデータ群を紹介します。
顧客データは、顧客を深く理解するための最も基本的な情報です。これには、氏名や年齢、性別、連絡先といった静的な「属性データ」と、会員ランクの変動やポイントの利用状況、ウェブサイトの閲覧履歴、メールマガジンの開封履歴といった動的な「行動データ」が含まれます。これらの多角的な情報を統合することで、単なる顧客リストではなく、一人ひとりの顔が見えるような立体的な顧客像を描き出すことが可能になります。
例えば、「最近サイト訪問が増えているが購入に至っていない顧客」や「優良顧客だが最終購入日から時間が経っている離反予備軍」といった具体的な顧客セグメントを作成し、それぞれに合わせたアプローチを検討できるようになります。顧客を正しく理解することは、効果的なコミュニケーションの第一歩といえるでしょう。
購買データは、「誰が、いつ、どこで、何を、いくつ、いくらで購入したか」を示す、ビジネスの成果そのものを表す根幹のデータです。実店舗のPOSシステムから得られるオフラインのデータや、ECサイトの注文履歴といったオンラインのデータがこれにあたります。この購買データを顧客データと紐づけることで、顧客ごとの購買頻度や平均購買単価、リピート率などを分析できます。
さらに、どのような商品が一緒に購入されやすいか(バスケット分析)を把握すれば、セット販売や関連商品のレコメンドといったクロスセル施策の精度を高められます。キャンペーンの効果測定や新商品の需要予測など、あらゆる分析の基礎となる非常に重要な情報源です。
在庫データは、どの商品が、どの店舗や倉庫に、どれくらいの量あるかを示す、キャッシュフローに直結する重要な情報です。このデータをリアルタイムで正確に把握し、購買データや顧客の行動データと連携させることで、精度の高い在庫管理が実現します。
例えば、ECサイトで在庫が切れている商品があった際に、近隣店舗の在庫状況を案内して購入を促したり、逆に店舗にない商品をECサイトから取り寄せて販売したりといった、販売機会の損失を防ぐための柔軟な対応が可能になります。また、需要予測に基づいて店舗間の在庫移動を最適化したり、発注プロセスを自動化したりすることで、過剰在庫のリスクを減らし、経営効率を高めることにも繋がります。
行動ログデータは、顧客がウェブサイトやアプリ上でどのように行動したかを示し、顧客の「今」の興味・関心をリアルタイムに捉えるための貴重な情報です。ECサイトでどのページをどれくらいの時間見たか、どの商品をカートに入れたか、どんなキーワードで検索したか、といった一連の行動履歴がこれにあたります。これらの情報を分析することで、顧客がどのようなプロセスを経て購買を検討しているのかを可視化できます。
例えば、カートに商品を入れたまま離脱してしまった顧客に対して、後日リマインドのメールを送ったり、特定のページをよく見ている顧客にだけ関連商品のクーポンをWeb接客ツールで表示したりと、顧客の状況に合わせたきめ細やかなアプローチが可能になり、購入の後押しができます。
データ統合を実現するためには、目的に合ったIT基盤を選ぶことが大切です。このセクションでは、代表的な4つのIT基盤とそれぞれの役割を解説します。
CDP(Customer Data Platform)は、店舗やECサイトなど、あらゆるチャネルから集めた顧客データを統合し、顧客一人ひとりを軸に管理するプラットフォームです。最大の強みは、統合したデータをMA(マーケティングオートメーション)ツールや広告配信プラットフォームといった外部の施策実行ツールと容易に連携できる点にあります。
例えば、「カート離脱した顧客」というセグメントを作り自動でリマインドメールを送るなど、一気通貫の施策展開が可能です。主にマーケターが活用することを想定しており、顧客理解を深めてパーソナライズされたマーケティングを実行したい場合に中心的な役割を果たします。
DWH(Data Warehouse)は、社内の様々なシステムから収集した大量のデータを、時系列に沿って整理・保管しておくための「データの倉庫」です。売上や在庫、財務データなど広範な業務データを対象とし、その目的は主に分析での利用です。長期間にわたる膨大なデータの保管と、高速なデータ集計を得意としています。
過去数年分の売上推移の分析や、商品カテゴリごとの収益性比較といった、経営判断に直結する高度な分析を行いたい場合に不可欠な基盤となります。データアナリストや経営企画部門などが活用し、企業の意思決定の根拠となるインサイトを導き出すために利用されます。
ETLやELTは、データ統合のプロセスにおいて、様々なシステムに点在するデータをDWHなどのデータ基盤へ運ぶ「パイプライン」の役割を担うツールです。ETLは、データを「抽出し(Extract)」「変換・加工し(Transform)」「書き出す(Load)」という処理を順番に行います。一方、ELTは先にデータを書き出してから変換・加工を行う点が異なります。
これらのツールは、エンジニアが手作業で連携プログラムを開発する手間とコストを削減します。データ統合プロジェクトにおいて、表舞台に出ることは少ないですが、正確で効率的なデータ連携を実現するための「縁の下の力持ち」として重要な役割を果たします。
BI(Business Intelligence)ツールは、DWHなどに蓄積された膨大なデータを、グラフやダッシュボードといった直感的に分かりやすい形に「可視化」するためのツールです。専門的なITスキルがなくても、簡単な操作でデータを様々な角度から分析し、レポートを作成できます。
例えば、全社の売上状況をダッシュボードでリアルタイムに共有し、気になる部分をクリックすれば詳細データを確認するといった、インタラクティブな分析が可能です。データの中に隠れた傾向や問題点を素早く発見して組織全体で情報を共有することで、データに基づいた迅速な意思決定をあらゆる階層でサポートしてくれるツールです。

多くのIT基盤の中から、自社に合ったものを選ぶにはどうすればよいのでしょうか。このセクションでは、選定の際に押さえておきたい2つのポイントを解説します。
ツール選びで最も大切なのは、「何のためにデータ統合を行うのか」という目的をはっきりさせることです。目的が曖昧なままでは、多機能なツールを導入しても十分に活用できない可能性があります。「ツール導入が目的化」してしまうのは、プロジェクトが失敗する典型的なパターンです。
「顧客一人ひとりに合わせたマーケティングを実現したい」のか、「全社の売上データを可視化して経営判断に役立てたい」のかで、選ぶべきツールは大きく異なります。前者の場合はCDP、後者の場合はDWHとBIツールが中心的な役割を担うでしょう。
まずは自社の課題を整理し、データ統合によって何を達成したいのかを具体的に定義することが、最適なツール選びの第一歩となります。
データ統合基盤は、それ単体で機能するわけではありません。現在社内で利用している店舗のPOSシステムやECサイトのシステム、基幹システムなどとスムーズに連携できなければ、そもそもデータを集められず、宝の持ち腐れになってしまいます。
導入を検討しているツールが、自社のシステムと連携するための機能を標準で備えているか(標準コネクタの有無)、API連携は容易か、追加の開発コストはどれくらいかなどを事前に確認することが求められます。
また、将来的に導入する可能性のあるシステムとの拡張性も考慮しておくとよいでしょう。連携の難しさは導入にかかる費用や時間に直接影響するため、慎重な検討が必要になるでしょう。
データ統合は、計画的に進めることが成功の鍵です。このセクションでは、プロジェクトを推進するための標準的な5つの手順を紹介します。
最初に行うべきは、データ統合によって何を達成したいのか、具体的な目的とゴールを設定することです。これはプロジェクト全体の羅針盤となる、最も重要な工程です。例えば、「2年後にECサイトからの売上を20%向上させる」「リピート購入率を15%改善する」といった、誰にでも分かりやすく測定可能な目標(KGI/KPI)を立てることが望ましいでしょう。
このゴールは特定の部署だけでなく、経営層から現場の担当者まで、プロジェクトに関わる全員で共有することが大切です。全員が同じ目標に向かって進むことで、部門間の協力も得やすくなり、プロジェクトの推進力が高まります。
次に、設定した目的を達成するために「どのシステムの、どのデータが必要か」を具体的に決めていきます。やみくもに全てのデータを集めるのではなく、ゴール達成に必要なデータを洗い出すことが重要です。同時に、データの品質にも目を向ける必要があります。「ゴミからはゴミしか生まれない」と言われるように、品質の低いデータを統合しても、価値のある分析結果は得られません。
例えば、顧客名の表記揺れ(「株式会社〇〇」と「(株)〇〇」など)を統一するルールや、欠損しているデータの扱いなどを事前に定義します。データの品質が、その後の分析の精度を大きく左右することを覚えておきましょう。
必要なデータが決まったら、それを実現できるIT基盤を選定します。複数のツールを機能やコスト、サポート体制、操作性などの観点から比較検討します。この際、本格的な導入の前にPoC(Proof of Concept:概念実証)を実施することをおすすめします。
これは、本格導入前の「お試し」として、一部のデータを使って小規模な環境で実際にツールを試し、目的が達成できるか、技術的な課題はないかを検証するプロセスです。PoCを行うことで、想定外のトラブルや導入後のミスマッチを防ぎ、リスクを最小限に抑えながら、自社に最適なツールを確信を持って選ぶことができます。
PoCで有効性が確認できたら、いよいよ本格的な導入に進みます。しかし、最初から全社規模で一気に導入するのはリスクが伴うため、特定の部門や商品、チャネルなどに限定して小さく始めるのが賢明なアプローチです。スモールスタートにより、リスクを抑えつつ早期に成功体験を得られます。
そして重要なのが、導入後も継続的に検証を行うことです。導入した施策の効果を定期的に検証し、得られた学びを次の改善に活かすPDCAサイクルを回していきます。小さな成功を積み重ね、その成果を社内で共有することで、プロジェクトへの理解と協力を広げていくことにも繋がります。
データ統合基盤は、導入して終わりではありません。継続的にデータを活用し、ビジネスの成果に繋げていくための運用体制を整えることが不可欠です。例えば、データを分析する担当者の配置や育成、定期的なレポーティングの仕組み作り、現場からの問い合わせに対応する窓口の設置などが挙げられます。
さらに、社内勉強会や成功事例の共有会などを開催し、データ活用のメリットを組織全体に広めていくことも重要です。単なる「仕組み」としてだけでなく、誰もがデータを当たり前に活用する「文化」として根付かせていくことが、プロジェクトの最終的な成功を決定づけます。
データ統合は大きな挑戦であり、残念ながら計画通りに進まないこともあります。このセクションではよくある失敗を乗り越え、プロジェクトを成功させるための3つの重要な対策を紹介します。
データ統合プロジェクトがうまくいかない最大の原因の一つに、「ツールを導入すること」自体が目的になってしまうことが挙げられます。これを防ぐためには、プロジェクトの初期段階で経営層を巻き込み、データ統合が経営課題の解決にどう貢献するのかを明確にすることが不可欠です。
そして、それを特定の部署の目標ではなく、全社共通のゴールとして合意形成を図ることが非常に重要になります。経営層の強力なコミットメントは、部門間の利害調整や予算確保を円滑にし、プロジェクトを推進する大きな力となるでしょう。トップが旗を振ることで、データ統合が単なるITプロジェクトではなく、重要な経営戦略であるという認識が社内に浸透します。
データ活用の成否は、データの品質に大きく依存します。不正確なデータに基づいた分析は、かえって誤った経営判断を招くリスクさえあります。プロジェクトを成功させるには、データガバナンス体制を構築することが求められます。これはデータの管理責任者を明確にし、データの入力ルールや品質チェックのプロセスを定め、組織として継続的にデータの品質を維持・向上させていくための仕組み作りです。
例えば、「顧客の電話番号はハイフンなしで統一する」「商品カテゴリのマスターデータを一元管理する」といった具体的なルールを設け、それを遵守する体制を整えます。地道な取り組みですが、信頼性の高いデータを維持することが、データ活用の成果を最大化する上で不可欠です。
データ統合は、マーケティング部や情報システム部、営業部など、複数の部門にまたがる全社的な取り組みです。各部門がそれぞれの立場から「自部門の業務が楽になるように」「既存のやり方を変えたくない」といった部分最適を主張し始めると、利害が対立してプロジェクトが停滞してしまうことも少なくありません。
これを避けるためには、各部門から代表者を集めた横断的なプロジェクトチームを作り、定期的に情報共有や意見交換の場を設けることが有効です。お互いの業務や課題を理解し、全社最適の視点から議論することで、建設的な解決策を見出すことができます。円滑なコミュニケーションが、部門間の壁を越えて協力体制を築くための鍵となります。

データ統合によって、企業はどのように変わるのでしょうか。
このセクションでは、実際にデータ統合を成功させ、成果を上げている小売企業の事例を2つ紹介します。
アパレル事業を展開する株式会社三陽商会は、2022年4月に公式オンラインストア「SANYO ONLINE STORE」と全国の店舗を連携させた新しい会員サービス「SANYO MEMBERSHIP」を開始しました。
この取り組みではCDP(顧客データ基盤)である「b→dash」を導入し、これまでブランドごとやオンライン・オフラインで分かれていた顧客情報を統合しています。
これにより、顧客はどの店舗やブランドを利用しても一貫したサービスを受けられるようになり、よりパーソナルな顧客体験の提供を目指しています。
出典参照:三陽商会・NRI デジタル・プレイドが共同で、OMO による顧客体験向上のためのトライアルを開始|株式会社三陽商会
家具・インテリア用品を扱う株式会社ニトリでは、公式アプリの便利な機能を通じて、顧客の買い物体験を向上させています。
特に「店内モード」は店舗で商品のバーコードをスキャンするだけで、商品の詳細情報やレビュー、他の顧客のコーディネート事例などをその場で確認できる機能です。アプリ上で在庫状況も分かるため、広い店内を探し回る手間が省けます。
このように、オンラインの豊富な情報と店舗でのリアルな体験をデータで繋ぐことで、スムーズで快適な買い物環境を実現しています。
出典参照:ニトリが「Repro App」を導入し、アプリ会員向けのオムニチャネル戦略をさらに強化|株式会社ニトリ
本記事では小売DXにおけるデータ統合の重要性から進め方、成功事例までを解説しました。
データ統合は単なるシステム導入ではなく、点在するデータを繋ぎ、顧客一人ひとりを深く理解するための経営戦略です。これにより顧客中心のビジネスモデルへと変革し、持続的な成長を目指せます。
まずは自社のデータ状況を把握することから、その第一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
