小売DXの第一歩はペーパーレス化!メリットや書類管理の課題を解説
小売

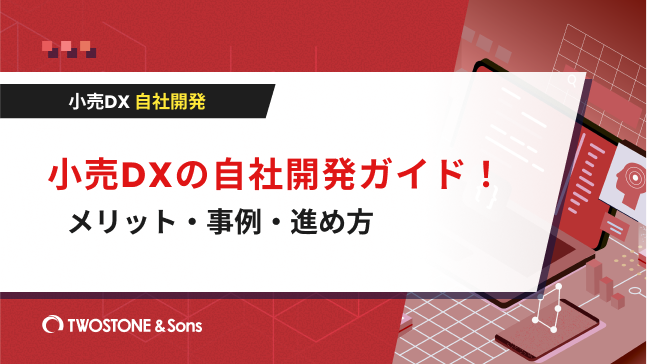
小売DXで自社開発を検討中の担当者様へ。パッケージシステムでは限界を感じていませんか?本記事では、自社開発のメリット・デメリットから、ニトリやカインズの成功事例、失敗しないための具体的な進め方までを網羅的に解説。意思決定に必要な情報がわかります。


・6万名以上のエンジニアネットワークを活用して課題を解決※
・貴社のDX戦略立案から実行・開発までワンストップで支援可能
※エンジニア数は2026年8月期 第1四半期決算説明資料に基づきます。
小売業界でDX推進が急がれる中、既存のパッケージシステムに限界を感じ、「自社開発」を検討する企業が増えています。独自の顧客体験を創出し、市場の変化に素早く対応できる魅力がある一方、コストや人材確保といった課題も存在します。
DX推進の責任者として自社開発が本当に最適な選択なのか、判断に迷うこともあるでしょう。この記事ではメリット・デメリットから成功事例、具体的な進め方まで、皆様の意思決定に役立つ情報を網羅的に解説します。
近年、多くの小売企業がパッケージシステムから一歩踏み出し、自社開発という道を選んでいます。その背景には単なる業務効率化を超えた、企業の競争力を根本から高めようとする強い意志があります。このセクションでは、自社開発が注目される3つの大きな理由について見ていきましょう。
現代の消費者は単に商品を購入するだけでなく、その過程全体での体験を重視する傾向にあります。しかし、多くの企業で使われているパッケージシステムは、汎用性を重視して作られているため提供できるサービスが画一的になりがちです。
自社開発であれば自社のブランドイメージや戦略に沿った、ユニークな顧客体験をシステムレベルから設計することが可能になります。例えば、店舗とECサイトの情報をシームレスに連携させるOMO戦略や、顧客一人ひとりの購買履歴に基づいたパーソナライズドな情報提供など、他社には真似のできないサービスを実現できるでしょう。
市場のトレンドや顧客の行動は、目まぐるしいスピードで変化しています。このような状況でビジネスチャンスを掴むためには、変化に素早く、そして柔軟に対応できるシステムが欠かせません。
パッケージシステムの場合、機能の追加や改修にはベンダーとの調整が必要となり、時間もコストもかかってしまうことがあります。一方自社開発であればシステムの主導権は自社にあるため、必要な機能を最適なタイミングで開発・実装することが可能です。このスピード感が、激しい市場競争を勝ち抜くための大きな力となるのです。
長年にわたって運用されてきた基幹システムが、時代の変化に対応できずに老朽化・複雑化してしまう「レガシーシステム」の問題も、多くの企業が抱える課題です。部分的な改修を繰り返した結果、システム全体がブラックボックスのようになり、新しい技術の導入やデータ活用を阻む足かせとなっているケースも少なくありません。
このような硬直化したシステムを刷新し、ビジネスの成長を加速させるための抜本的な解決策として、自社開発が有力な選択肢として浮上しているのです。データを自由に活用できる柔軟で拡張性の高いシステム基盤を再構築することは、未来への大きな投資と言えるでしょう。

自社開発に踏み切ることは、新しいシステムを手に入れる以上の価値を企業にもたらします。このセクションでは、自社開発ならではの3つの大きなメリットについて解説します。
自社開発が持つ最大の魅力は、自社の業務フローやビジネスモデルに完全に合致したシステムをゼロから構築できる点にあります。一般的なパッケージシステムでは対応が難しい、特殊な在庫管理や独自のポイント制度など、企業の強みとなる部分をシステムに反映させることが可能です。
この圧倒的なカスタマイズ性が他社との明確な差別化を生み出し、サービス全体の質を高めることに繋がります。まさに、企業の競争優位性の源泉をシステムという形で具現化できると言えるでしょう。顧客一人ひとりに寄り添ったサービスを提供することで、ブランドへのロイヤリティ向上も期待できます。
自社で開発したシステムからは、顧客の購買データやサイト上の行動データといった経営判断に不可欠な情報を直接収集し、自社の資産として管理できます。これらの貴重なデータを自由に分析・活用することで、データに基づいた客観的な意思決定や、より効果的なマーケティング施策の展開が期待できます。
また、開発プロセスを通じて、システム設計やプロジェクトマネジメントに関する技術的な知見が社内に蓄積されていきます。これは将来のDX推進を担う人材の育成という面でも、非常に大きな財産となるでしょう。蓄積されたノウハウは、次の新たなサービス開発を加速させる原動力にもなります。
パッケージシステムを利用していると、特定のベンダーが提供する技術やサービスに依存せざるを得ない「ベンダーロックイン」という状態に陥ることがあります。この状態では、ライセンス費用や保守費用がベンダーの意向で変動したり、自社が望むタイミングで改修ができなかったりするリスクが伴います。
自社開発であればシステムの主導権を自社で完全にコントロールできるため、特定のベンダーに縛られる心配がありません。長期的な視点で最適な技術を選んだり、コストを管理したりすることが可能になるのです。これにより自社の事業戦略に合わせた、柔軟で持続可能なIT投資計画を立てやすくなります。
多くの魅力がある自社開発ですが、成功に至るまでにはいくつかの課題が存在します。このセクションでは、代表的な3つの課題について説明します。
自社開発はオーダーメイドでシステムを構築するため、一般的にパッケージシステムの導入に比べて初期開発費用が高くなる傾向が見られます。エンジニアの人件費やインフラの構築費用、開発環境の整備など様々なコストが発生します。
また、システムが完成した後も、安定稼働を維持するための保守・運用コストが継続的に必要です。開発チームの人件費はもちろん、サーバーなどのインフラ費用、開発ツールやライセンス費用など考慮すべき項目は多岐にわたります。そのため、プロジェクト開始前に詳細な費用対効果を算出し、経営層の合意を得ておくことが不可欠です。
要件定義から設計や開発、テスト、そしてリリースに至るまで、自社開発のプロジェクトは数ヶ月から規模によっては数年単位の期間を要することもあります。特に、関係部署が多く要件が複雑な大規模システムの場合、開発期間が想定よりも長期化しやすいというリスクを考慮しておく必要があります。
プロジェクトが長引くとその間に市場の状況が変わり、完成したシステムが当初の目的とずれてしまう可能性も出てくるため、適切なプロジェクト管理が求められます。特に、関係部署が多く調整に時間がかかるプロジェクトほどその傾向は強まるため、計画段階で現実的なスケジュールを設定し、進捗を厳密に管理する体制が重要です。
自社開発を成功させるためには、プロジェクト全体を指揮するプロジェクトマネージャーや、実際にシステムを設計・開発するエンジニアなど、高度な専門スキルを持つIT人材の存在が不可欠です。
しかし現在、IT人材は多くの業界で需要が高まっており、優秀な人材を確保することは簡単ではありません。また、社内で人材を育成するにも相応の時間とコストがかかります。DX化の加速に伴い、優秀なIT人材は業界を問わず引く手あまたの状態です。そのため採用と育成の両面から、長期的な視点に立った人材戦略を立てることが重要になります。
実際に自社開発に取り組み、大きな成果を上げている企業は少なくありません。このセクションでは、小売業界をリードする2社の事例から、成功のヒントを探っていきましょう。
家具・インテリア小売大手のニトリホールディングスは、店舗とECの融合による顧客体験の向上を目指す「OMO戦略」を強力に推進しています。その中心的な役割を担っているのが、自社で開発・運用する公式アプリ「ニトリアプリ」です。
このアプリは2023年度には会員数が1,500万人を突破するなど、多くの顧客に利用されています。アプリを通じて店舗での商品検索や在庫確認、カメラで撮影した部屋に家具を試し置きできる機能などを提供し、顧客の購買体験を豊かにしています。システムを内製化することで、顧客データを一元的に管理・分析し、スピーディーなサービス改善に繋げている点が大きな特徴です。
出典参照:NITORI HOLDINGS 統合報告書 2024|株式会社ニトリホールディングス
ホームセンター大手のカインズは、データに基づいた意思決定を行う「データドリブン経営」への転換を積極的に進めています。その土台となっているのが、自社で構築したデータ分析基盤です。
カインズはデジタル戦略を推進する専門部署を設け、Google アナリティクスなどを活用して店舗とECのデータを統合・分析できる環境を整備しました。この取り組みには外部パートナーの支援も活用し、データ分析を担う組織づくりから着手したことが特徴です。これにより顧客の行動を深く理解し、品揃えの最適化や効果的なマーケティング施策の立案に繋げています。
出典参照:カインズの新たなデジタル拠点「CAINZ INNOVATION HUB」2020年1月 東京・表参道に開設|株式会社カインズ

自社開発は、計画性のないまま進めると失敗に終わる可能性が高まります。構想から運用、そして改善に至るまで、体系的なプロセスを踏むことが成功への鍵となります。このセクションでは、その具体的な5つのステップを紹介します。
プロジェクトの最初のステップは、「何のために、誰のためにシステムを開発するのか」という目的を徹底的に明確にすることです。解決したい経営課題や実現したい顧客体験は何か、具体的な目標(KPI)は何かを定義します。
この段階で経営層から現場のスタッフまで、関係者全員の認識を合わせてプロジェクトの方向性について合意を形成しておくことが、後の手戻りを防ぐ上で極めて重要です。例えば、「新システム導入により、顧客単価を5%向上させる」といった、具体的で測定可能な目標を設定することが望ましいでしょう。
次に、ステップ1で定めた目的を達成するために、システムにどのような機能が必要か(要求)を洗い出します。そしてその要求を、開発者が理解できる具体的なシステムの仕様(要件)に落とし込むのが「要件定義」です。この工程の質が、プロジェクト全体の成否を大きく左右すると言っても過言ではありません。
現場の業務フローを詳細にヒアリングし、ドキュメントとして可視化する地道な作業が求められます。要件が固まったら、それに基づいてシステムの全体像やデータベースの構造、使用する技術などを決定する「システム設計」のフェーズへと進みます。
設計が完了すれば、いよいよ開発のフェーズです。近年では、短い期間で「計画→設計→実装→テスト」というサイクルを何度も繰り返す「アジャイル開発」という手法が広く採用されています。アジャイル開発は、開発の途中で仕様の変更や追加の要望が出てきても柔軟に対応しやすいため、市場の変化が速い小売業のシステム開発に向いている手法と考えられます。
各機能の開発が終わるたびに厳密なテストを行い、品質を一つひとつ確認していくことが大切です。この反復的なアプローチにより、リスクを早期に発見し、軌道修正を図ることができます。
システムが完成し、テストをクリアしたら、いよいよ本番環境への導入(リリース)となります。しかし、システムは完成して終わりではありません。実際にシステムを使う現場の従業員がその価値を理解し、スムーズに使いこなせなければ、期待した効果は得られないでしょう。
操作マニュアルの作成や研修会の実施、問い合わせに対応するヘルプデスクの設置など、手厚いサポート体制を整えて新しいシステムが現場にしっかりと根付くまで支援を続けることが重要です。一部の部署で先行導入してフィードバックを得る「パイロット導入」も、本格展開前の課題発見に有効な手段です。
リリース後は、システムが日々安定して稼働し続けるための運用・保守活動が欠かせません。サーバーの監視や定期的なメンテナンス、セキュリティのアップデートなどを行います。同時に、プロジェクトの最初に設定したKPIを基に、システムの導入がどのような効果をもたらしたのかを定量的に測定します。
ユーザーからのフィードバックや実際の利用データを分析し、改善点を見つけ出して次の開発に繋げていくことで、システムの価値を継続的に高めていくことができるのです。まさに、システムは一度作ったら終わりではなく、ビジネスの成長と共に「育てていく」という視点が求められます。
自社開発プロジェクトには、残念ながら失敗のリスクも伴います。しかし多くの失敗には共通したパターンがあり、それを事前に知っておくことで、リスクを大きく減らすことが可能です。このセクションでは、代表的な3つの失敗パターンとその対策について解説します。
自社開発で最もよく聞かれる失敗の一つが、要件定義の曖昧さです。必要な機能が明確にならないまま開発を始めてしまうと、途中で大規模な手戻りが発生しプロジェクトが長期化したり、予算が膨らんだりする原因になります。
この対策として有効なのが「スモールスタート」という考え方です。最初から全ての機能を盛り込んだ完璧なシステムを目指すのではなく、最も重要で中核となる機能に絞って開発し、まずは小さくリリースします。実際に使ってもらいながらフィードバックを集め、段階的に機能を拡張していくことで、リスクを抑えながら着実にプロジェクトを進めることができます。
情報システム部門だけでプロジェクトを進めてしまい、現場の業務実態に合わないシステムを作ってしまうというのも、よくある失敗パターンです。このようなシステムは、現場の従業員から「使いにくい」「かえって手間が増えた」といった反発を招き、結局誰にも使われずに終わってしまう可能性があります。
これを防ぐためには、プロジェクトの企画段階から、実際にシステムを使う現場のキーパーソンをメンバーに加えることが不可欠です。現場の意見を丁寧にヒアリングし、開発のプロセスに参加してもらうことで当事者意識が芽生え、完成後のスムーズな導入と定着に繋がるでしょう。
自社開発は、短期的に見るとパッケージシステムの導入よりもコストが高くなることが多いため、経営層から「なぜパッケージではだめなのか?」と、プロジェクトの必要性を理解してもらえないことがあります。コスト面だけを説明しようとすると、承認を得るのは難しいかもしれません。
対策としては、単なる費用ではなく長期的な視点での「投資対効果(ROI)」を具体的に示すことが重要です。新しいシステムによってどれだけ業務が効率化され、コストが削減できるのか、あるいはデータ活用によってどれだけの売上向上が見込めるのかを定量的に説明し、未来への投資としての価値を説得することが求められます。
全てのシステムを一度に自社開発するのは現実的ではありません。まずは投資対効果が高く、自社の競争力を高めることに直接繋がる領域から着手するのが、成功への近道と言えるでしょう。このセクションでは、特に自社開発が有効と考えられる3つの領域を紹介します。
顧客との良好な関係を築き、管理する「CRM(顧客関係管理)」や、点在するあらゆる顧客データを統合・分析するための「CDP(顧客データ基盤)」は、企業の最も重要な資産である顧客情報を扱う領域です。
自社独自の基準で顧客を分類したり、一人ひとりの趣味嗜好に合わせたアプローチを行ったりするためには、パッケージシステムの機能だけでは限界があることも少なくありません。顧客を深く理解することこそが競争力の源泉と考えるのであれば、この領域は自社開発を検討する価値が高いと言えるでしょう。自社独自の分析軸で顧客を深く理解し、LTV(顧客生涯価値)を最大化する施策に繋げることができます。
オンライン(ECサイトやアプリ)とオフライン(実店舗)の垣根をなくし、顧客に一貫性のあるシームレスな購買体験を提供する「OMO」は、現代の小売業における重要な戦略の一つです。
店舗のPOSデータとECサイトの購買履歴、アプリ上での行動ログなどをリアルタイムで連携させるには、複雑なシステム連携が求められます。自社ならではの滑らかな顧客体験を設計して実現するためには、柔軟なカスタマイズが可能な自社開発が非常に有効な手段となります。例えばECサイトで見た商品を店舗で取り置きしたり、店舗での購買履歴を元にオンラインでクーポンを発行したりといった、双方向の連携がスムーズになります。
需要を予測して自動で発注を行ったり、複数の店舗や倉庫にある在庫を最適化したりするなど、商品の仕入れから顧客に届くまでの流れ全体を効率化する「SCM(サプライチェーン管理)」も自社開発のメリットが大きい領域です。
特に独自の物流網を持っていたり、生鮮食品のように特殊な管理が必要な商品を取り扱っていたりする場合、一般的なパッケージシステムの標準機能では対応しきれないケースが多く見られます。自社の業務プロセスに深く根差したシステムを構築することで、コスト削減や機会損失の低減に大きく貢献することが期待できます。精度の高い需要予測に基づいて発注を自動化し、欠品による販売機会の損失と過剰在庫による廃棄ロスの両方を削減できるでしょう。

全ての開発を社内のリソースだけで行うのが難しい場合、外部の開発パートナーとの連携がプロジェクト成功の鍵となります。しかしパートナー選びを誤ると、プロジェクトがうまく進まない原因にもなりかねません。信頼できるパートナーを見極めるための3つのポイントを紹介します。
パートナーを選ぶ上で大切なのは、単にプログラミングの技術力が高いということだけではありません。小売業界特有の商習慣や業務の流れ、そして業界が抱える課題について深い理解があるか、また関連するシステム開発の実績が豊富かを確認することが重要です。
業界知識が豊富なパートナーであれば、こちらの曖昧な要望を的確に汲み取り、より良い提案をしてくれる可能性が高まります。過去にどのようなプロジェクトを手がけてきたのか、具体的な事例を交えて説明してもらうと良いでしょう。特に自社と同じ業態(アパレル、食品スーパーなど)での実績があれば、より実践的な支援が期待できます。自社のビジネスモデルを深く理解し、戦略的な提案をしてくれるかどうかが重要な判断基準となります。
もちろん、プロジェクトを遂行するための確かな技術力は必須の条件です。モダンな開発手法や、クラウドサービスに関する知見を持っているかなどを確認しましょう。それと同時に自社の担当者とスムーズに意思疎通が図れるかという点も、見過ごせない重要なポイントです。
専門用語ばかりで話が通じなかったり、質問に対する返答が遅かったりするようなパートナーでは、プロジェクトを円滑に進めるのは難しいかもしれません。打ち合わせなどを通じて、対話しやすい相手かどうかを見極めることが大切です。技術的な議論とビジネス的な議論の両方を、同じ目線で話せる相手が理想的と言えるでしょう。日々のやり取りで使うツールや報告の頻度なども事前に確認しておくと、プロジェクト開始後のギャップを減らせます。
契約内容や見積もりが曖昧なままプロジェクトをスタートさせてしまうのは、後々のトラブルの原因となりかねません。開発のスコープ(範囲)やお互いの責任分担、そして最終的な成果物が契約書で明確に定義されているかを必ず確認してください。
また、提示された見積もりについても、項目ごとに詳細な内訳が示されており、その金額の根拠が合理的であるかをしっかりと精査しましょう。仕様の変更が発生した場合の追加費用に関するルールなども事前に双方で合意しておくことが、良好な関係を維持する上で重要です。契約前に疑問点を全て解消し、お互いが納得した上でプロジェクトを始めることが、信頼関係を築く第一歩です。
小売DXにおける自社開発は、単にシステムを新しくする選択肢の一つではありません。それは変化の激しい時代を勝ち抜き、持続的に成長していくための、企業の競争戦略そのものと言えるでしょう。
もちろんそこにはコストや期間、人材といった乗り越えるべき壁が存在します。しかし、パッケージシステムでは得られない圧倒的な柔軟性や、データやノウハウという貴重な資産を自社に蓄積できるメリットは、それらの課題に挑戦してでも手に入れる価値があると考えられます。
最も重要なのは、メリットとデメリットの両方を正しく理解し、自社の経営戦略と照らし合わせながら、どこから着手すべきかを見極めることです。この記事が、皆様にとって「自社開発」という重要な経営判断を下すための一助となれば幸いです。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
