小売DXの第一歩はペーパーレス化!メリットや書類管理の課題を解説
小売

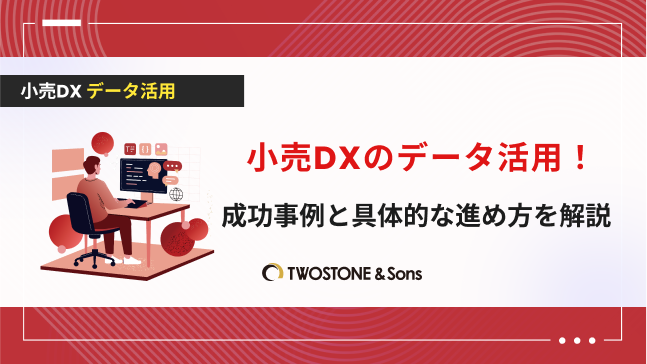
小売DXにおけるデータ活用の重要性が高まっています。この記事では、データ活用のメリットや分析手法、成功事例、実践的な進め方を5つのステップで解説します。自社に眠るデータの価値を最大限に引き出し、顧客満足度の向上と業務効率化を実現するためのヒントを提供します。


・6万名以上のエンジニアネットワークを活用して課題を解決※
・貴社のDX戦略立案から実行・開発までワンストップで支援可能
※エンジニア数は2026年8月期 第1四半期決算説明資料に基づきます。
消費者の購買行動が多様化し、小売業には従来以上に一人ひとりの顧客に合わせた対応が求められています。そのカギを握るのが、社内に蓄積された膨大な「顧客データ」の活用です。
しかし「データはあるが、どう活かせばいいか分からない」「分析が難しく施策につながらない」といった声は少なくありません。実際、多くの現場ではPOSや会員データ、ECサイトのログなどが部門ごとに分断され、全体像を把握できていないという課題が散見されます。
そこで今、小売DXの中核として注目されているのがCDP(カスタマーデータプラットフォーム)やBIツールを活用したデータ統合と分析です。この記事ではデータ活用の基本から、成功事例、導入手順、分析手法、そして現場で生かすためのKPI設定までを網羅的に解説します。
小売DXとはAIやIoT、ビッグデータなどのデジタル技術を活用し、従来のビジネスモデルや業務プロセス、そして顧客体験そのものを変革していく取り組みです。
単にデジタルツールを導入するだけでなく、データを活用して「顧客体験の向上」と「業務効率化」を両立させ、新たな価値を創造することが小売DXの本質といえるでしょう。
現代の小売業は、消費者の価値観の多様化、Eコマースの拡大、深刻な人手不足など多くの課題に直面しています。このような厳しい経営環境の中で経験や勘だけに頼るのではなく、データに基づいた客観的で的確な意思決定を行い、変化に迅速に対応していくことが求められます。
そのための有効な手段として、小売DXの重要性がますます高まっているのです。

小売DXを成功に導く上で、特に重要視されるのが顧客との関係性を管理するCRM(Customer Relationship Management)データの活用です。
なぜ今、CRMデータに注目が集まっているのでしょうか。その背景にある、現代の小売業が抱える課題を順に見ていきましょう。
かつての店舗運営は、長年の経験を持つベテランスタッフの勘や感覚に支えられてきた側面がありました。しかし顧客の購買行動が複雑化し、一人ひとりのニーズが細分化する現代において、個人の主観的な判断だけでは最適な対応が難しくなってきています。
例えばある商品の売れ行きが鈍った際、その原因が天候なのか、競合店のキャンペーンなのか、あるいは単なるトレンドの変化なのかを感覚だけで見極めるのは困難でしょう。客観的なデータに基づいて顧客を深く理解し、それぞれのニーズに合わせたアプローチを行うことが効果的な関係性を築く上で不可欠です。
データは顧客の声を代弁する貴重な情報源であり、経験や勘を裏付け、より精度の高い仮説検証と意思決定を可能にするための重要な鍵なのです。
多くの企業では、実店舗のPOSデータやECサイトの購買履歴、公式アプリの利用ログ、コールセンターへの問い合わせ履歴など、顧客に関する情報がそれぞれのシステムで個別に管理されています。このようにデータが分断された「サイロ化」の状態に陥っているケースは、決して少なくありません。
これでは、ある顧客が「店舗で下見をして、後日ECサイトで購入する」といった行動をとったとしても、その一連の流れを捉えることができません。一人の顧客が実店舗とオンラインでどのような行動をとっているのかを横断的に把握することが困難になり、顧客の全体像を正しく捉えられなくなります。
結果として店舗とECで矛盾したメッセージを送ってしまうなど、一貫性のないアプローチに繋がり、顧客体験を損なうリスクも考えられるでしょう。
スマートフォンやSNSの普及は、消費者が情報を得る手段や購買に至るプロセスを劇的に変化させました。誰もが手軽に情報を発信・受信できるようになったことで、トレンドの移り変わりは非常に速く、顧客が商品やサービスに求める価値も常に変化し続けています。
このような時代において過去の成功体験に固執していては、あっという間に市場から取り残されてしまう可能性があります。顧客データを分析し、ニーズの変化の兆候をいち早く察知することは、競争優位性を維持するために不可欠な要素です。
データ活用を通じて顧客が本当に求めているものは何か、次に何を求めているのかを深く洞察し、それに応える商品やサービスを迅速に提供し続けることが企業の持続的な成長に繋がるでしょう。
データ活用を推進することは、小売業にどのような恩恵をもたらすのでしょうか。このセクションでは、考えられる具体的なメリットについて、3つの側面から解説します。
顧客の属性データや購買履歴、Webサイトでの行動ログなどを詳細に分析することで、一人ひとりの興味関心や購買パターンを深く理解することが可能になります。
顧客理解をもとに個々に最適化された商品をおすすめしたり、誕生日など特別なタイミングでクーポンを提供したりすることで、画一的なサービスでは得られない満足度の向上が期待できます。満足度の高い購買体験は顧客のブランドに対する信頼や愛着(ロイヤリティ)を高め、再来店や継続的な購入を促します。
その結果、一人の顧客が取引期間全体を通じて企業にもたらす利益の総額、すなわち顧客生涯価値(LTV:Life Time Value)の最大化が見込めるのです。LTVの向上は、安定した収益基盤の構築に直結します。
データ分析は、需要予測の精度向上にも大きく貢献します。
過去の販売実績データに天候、曜日、地域のイベント情報、さらにはSNSでの言及数といった多様なデータを加味して分析することで、将来の売上をより高い精度で予測することが可能になります。精度の高い需要予測は、過剰な在庫による保管コストや廃棄ロス、あるいは販売機会の損失に繋がる欠品のリスクを大幅に低減させるでしょう。
これにより在庫管理や発注といったバックヤード業務が最適化・自動化され、従業員は接客や売り場づくりといった、より付加価値の高いクリエイティブな業務に集中できるようになります。結果として、店舗全体の生産性向上が期待できるのです。
従来の経験や勘に頼った経営判断から脱却し、リアルタイムで収集される販売データや顧客データをもとに、客観的かつ迅速な意思決定を行う。こうした「データドリブン経営」へのシフトが可能になります。
例えば、新たに開始したキャンペーンの効果を売上や来店客数といったKPIの変動からリアルタイムで把握し、効果が薄いと判断すれば即座に内容を修正・中止するといった俊敏な対応が取れるようになります。
市場の小さな変化や競合の動きにも素早く対応できるため、ビジネスチャンスを逃さず、リスクを最小限に抑えることが可能です。データという客観的な事実に基づいた意思決定は、組織全体の納得感を醸成し、強固で俊敏な経営基盤を築くことに繋がるでしょう。
実際にデータ活用によって大きな成果を上げている企業の事例は、自社の取り組みを考える上で大いに参考になります。このセクションでは、特に注目すべき2つの企業の事例を紹介します。
ディスカウントストア「トライアル」を展開する株式会社トライアルカンパニーは、「リテールAI」というコンセプトのもと、データ活用を積極的に進めています。
自社開発したAIカメラやスマートショッピングカートは、店内での顧客の属性や動線、棚前での行動を分析し、欠品検知や棚割り改善、発注業務の効率化に活用されています。AIカメラが捉える顧客の行動データと、スマートショッピングカートで得られる購買データを組み合わせることで、店頭での購買行動に基づいた販売戦略を強化しています。
一部店舗での実証を重ねながら、導入拡大が進められている状況です。
「GLOBAL WORK」や「niko and …」など多彩なブランドを展開する株式会社アダストリアは、自社ECサイト「.st(ドットエスティ)」を活用したデータ戦略に力を入れています。
会員施策や接客を起点としたOMO戦略を推進し、LTV向上に取り組んでいます。また、ECサイトではコーディネート提案やライブ配信といったコンテンツを拡充し、顧客との接点強化に注力しています。
リアル店舗とデジタルを連携させた取り組みにより、顧客体験価値の向上を図っています。
出典参照:統合報告書 2024(P.13,23)|株式会社アダストリア
小売DXを推進する上で活用できるデータは多岐にわたります。このセクションでは、その中でも特に重要となる代表的な3つのデータソースについて解説します。
POS(販売時点情報管理)データは「いつ、どの店舗で、誰が(会員情報と紐づく場合)、何を、いくつ、いくらで購入したか」といった、最も基本的かつ重要な購買情報です。
このデータを分析することで売れ筋商品や不振商品の特定はもちろん、時間帯や曜日ごとの売上傾向、顧客層別の購買パターン、さらには同時に購入されやすい商品の組み合わせ(併売分析)などを明らかにすることができます。
これらの情報は、品揃えの最適化、効果的な販促キャンペーンの企画、適切な人員配置の計画など、店舗運営のあらゆる意思決定の基礎となります。全てのデータ分析の出発点となる、非常に価値の高いデータソースといえるでしょう。まずはこのPOSデータを深く分析することから始めるのが定石です。
会員登録の際に収集される、顧客の年齢、性別、居住地、家族構成といったデモグラフィック(人口統計学的)情報がこれにあたります。これらの属性データを前述の購買履歴データと掛け合わせて分析することで、より詳細で立体的な顧客像を浮かび上がらせることが可能になります。
例えば「どのエリアに住む、どの年代の女性に、どの価格帯の、どのカテゴリーの商品が人気なのか」といった具体的な顧客セグメントごとのニーズを把握できます。
特定のセグメントに向けたダイレクトメールを送付したり、Web広告のターゲティング精度を高めたりと、よりパーソナルで効果的なマーケティング施策を展開するための重要なデータです。
自社で運営するECサイトや公式アプリ上での、顧客のあらゆる行動履歴がこのデータソースに含まれます。
具体的には、どのページをどのくらいの時間閲覧し、どの商品を検索・クリックし、どの商品をカートに入れたか、どの広告から流入してきたか、といった多岐にわたる情報が挙げられます。これらの行動ログデータを分析することで、顧客が購買に至るまでの思考プロセスや潜在的な興味・関心を深く理解することができます。
例えば「特定のページで離脱する顧客が多い」という事実が分かれば、そのページのUI/UXに問題があるのではないかという仮説を立て、改善に繋げることが可能です。顧客の「買いたい」という気持ちを後押しするための重要なヒントが詰まっています。

収集したデータを有効に活用するためには、目的に応じた適切な分析手法を用いることが重要です。このセクションでは、小売業の現場で広く使われている代表的な3つの分析手法を紹介します。
ABC分析は売上や利益といった指標に基づき、商品や顧客をA・B・Cの3ランクに分類する手法です。上位の売上を占める少数の商品や重要顧客に注力し、管理や施策の優先順位を明確化するのが狙いです。
例えば全体の売上に大きく貢献する商品群をAランクと位置づけ、在庫管理や発注業務で重点的に扱います。一方、売上貢献度が低いCランクの商品は、在庫縮小や取扱見直しの判断材料とされます。
顧客分析でも同様に、重点顧客の抽出やアプローチ戦略に活用される代表的な分析手法です。
RFM分析とは顧客を「Recency(最終購入日)」「Frequency(購入頻度)」「Monetary(累計購入金額)」という3つの指標で評価し、顧客を複数のグループに分類する分析手法です。この3つの指標を組み合わせることで顧客の状態を多角的に把握し、優良顧客や離反の可能性がある顧客などを可視化します。
例えば「R・F・M全てが高い顧客」は最も重要な優良顧客、「Rが低く(最終購入から時間が経っている)、F・Mが高い顧客」は離反の可能性がある顧客であると判断できます。
それぞれの顧客セグメントの特性に合わせて、優良顧客には特別なサービスを提供し、休眠顧客には再来店を促すクーポンを送付するなどきめ細やかなアプローチが可能になります。
アソシエーション分析は、購買データの中から「ある商品を購入した顧客が、他の特定の商品も一緒に購入する傾向」を見つけ出す手法です。店舗担当者の経験や直感だけでは気づきにくい商品の組み合わせを、客観的なデータに基づいて発見できるのが特長です。
関連性の高い商品を近くに陳列してクロスセルを促したり、ECサイトのレコメンド機能を改善したり、セット割引キャンペーンの設計に活用されたりしています。
購買行動の裏にあるニーズを探り、販促や売場づくりに活かせる実践的な分析手法といえるでしょう。
データ分析を効果的に進めるためには、目標達成の度合いを測るための重要業績評価指標(KPI)を事前に設定することが不可欠です。小売業において特に重視されるべき代表的なKPIを紹介します。
来店客数は店舗の集客力を示す最も基本的な指標であり、あらゆる売上の源泉となります。広告宣伝やイベント開催といった集客施策の効果を測る上で重要ですが、天候や曜日など外部要因にも影響されやすいため、多角的な視点での分析が求められます。
一方購買率は、来店した顧客のうち実際に商品を購入した顧客の割合を示し、「購買客数 ÷ 来店客数」で算出されます。この数値は店舗の品揃え、売り場の魅力、接客サービスの質などを総合的に評価する指標です。たとえ来店客数が多くても、購買率が低ければ売上には繋がりません。
両方のKPIをバランスよくモニタリングし、改善していくことが重要です。
客単価は、顧客一人あたりの平均購入金額を示し、「売上 ÷ 購買客数」で計算されます。
客単価を向上させるためには、より高価格帯の商品を推奨する「アップセル」や、関連商品を一緒に提案して購入点数を増やす「クロスセル」といった施策が有効と考えられます。
客単価を構成する重要な要素が買い上げ点数(一人あたりの平均購入商品数)です。まとめ買いキャンペーンの実施や、レジ横に関連商品を陳列するといった工夫が買い上げ点数の増加に寄与するでしょう。
これらのKPIを分析することで顧客の購買意欲や満足度を間接的に測り、収益性を高めるための具体的なアクションに繋げることができます。
リピート率は、新規に訪れた顧客がその後どのくらいの割合で再来店・再購入してくれたかを示す指標です。一般的に、新規顧客の獲得コストは既存顧客の維持コストより多くかかるといわれており、リピート率の向上は事業の収益性を安定させる上で極めて重要です。
そして、最終的に目指すべきKPIが顧客生涯価値(LTV)です。これは一人の顧客が取引を開始してから終了するまでの全期間にわたって、自社にもたらす利益の総額を示す指標です。LTVを最大化するには購入単価、購入頻度、継続期間といった要素を高める必要があります。
LTVを重視することで、短期的な売上にとらわれない、長期的な視点で顧客との関係構築が可能になります。
実際にデータ活用を始めるには、どのような手順で進めていけば良いのでしょうか。このセクションでは、体系的なアプローチとして5つのステップに分けて解説します。
まず最も重要なことは、「何のためにデータ活用を行うのか」という目的を明確に定義することです。目的が曖昧なままでは、どのようなデータを集め、どう分析すれば良いのかが定まらずプロジェクトが迷走してしまいます。
「優良顧客の離反率を前期比で3%改善する」「新商品のクロスセル率を15%に引き上げる」など、具体的で測定可能な目標を設定することが成功の鍵となります。
そして、その目標がどの程度達成されたかを客観的に評価するKPI(重要業績評価指標)、例えば離反率やクロスセル率などを具体的に定めます。この最初のステップが、以降の全ての活動の方向性を決定づけるのです。
設定した目的に基づき、分析に必要となるデータを特定し、収集するプロセスに入ります。店舗のPOSデータ、ECサイトの購買データ、顧客の会員情報など、社内の様々な部署やシステムに散在しているデータを一元的に集約することが求められます。
しかし多くの場合、データの形式や定義が異なっているため、そのままでは統合できません。そこで重要になるのが、データクレンジング(表記ゆれの修正や欠損値の補完)や名寄せ(異なるIDを持つ同一顧客の統合)といった地道な作業です。
このデータの「前処理」を丁寧に行うことが分析結果の信頼性を担保する上で不可欠であり、CDPなどのツールがこのプロセスを効率化する助けとなります。
収集・統合したクリーンなデータを、目的に合った分析手法を用いて分析します。
このフェーズではBIツールなどを活用して、分析結果をグラフやチャートで可視化します。そしてデータに隠されたパターン、傾向、相関関係などを読み解きます。重要なのは単なるデータの要約で終わるのではなく、その背景にある理由を掘り下げ、ビジネス上の意思決定に繋がる有益な知見(インサイト)を導き出すことです。
データという事実から、行動を促すプロセスといえるでしょう。
分析によって得られたインサイトをもとに、具体的なアクションプランを策定し、実行に移します。
例えば、「競合のB商品を購入した顧客に対し、A商品の優位性を訴求するクーポンを配信する」といった施策が考えられます。可能であれば、一部の顧客にのみ施策を実施する「A/Bテスト」などを行い、施策の純粋な効果を検証できるとより良いでしょう。
そして最も重要なのは、施策を実行して終わりにするのではなく、必ずその効果を測定することです。事前に設定したKPIが施策の前後でどのように変化したかを客観的に評価し、「やりっぱなし」を防ぎます。この検証結果が、次の改善への貴重な学びとなるのです。
データ活用は一度きりのプロジェクトではなく、継続的なプロセスとして組織に定着させることが不可欠です。ステップ1から4までの一連のサイクル(PDCA)を組織全体で繰り返し回し続ける文化を醸成することが求められます。
そのためにはデータ分析の結果を部署横断で共有し、次のアクションプランを議論する定例会議を設けたり、データに基づいた提案や挑戦を評価する制度を導入したりするなど、データ活用を全社的に推進するための仕組みづくりが重要です。
データ活用を特定の担当者だけのスキルにせず、組織全体の能力として昇華させることで持続的な競争優位性を築くことができるでしょう。

データ活用を効率的かつ効果的に進めるためには、目的に合ったツールを導入することが有効な選択肢となります。このセクションでは、小売DXを支える代表的な3種類のツールを紹介します。
CDP(Customer Data Platform)とは、あらゆる顧客データを一元管理するためのデータ基盤です。
実店舗の購買履歴やECサイトの行動ログ、アプリの利用状況、広告配信データなど、オンライン・オフラインを問わず社内に散在する情報を収集・統合し、実在する個人をキーにして管理します。
CRMが主に既存顧客との関係管理に焦点を当てるのに対し、CDPは匿名ユーザーを含むあらゆる顧客データを統合できる点が特徴です。
CDPを導入することで、これまで分断されていた顧客データをつなぎ合わせることができます。その結果、顧客一人ひとりの行動を時系列で追える「ジャーニー分析」などが可能になり、一貫性のある顧客体験(オムニチャネル)を実現するための中核的な役割を担うようになります。
BI(Business Intelligence)ツールは企業内に蓄積された膨大なデータを集計・分析し、その結果をグラフやダッシュボードといった、直感的で分かりやすい形式に可視化するためのツールです。
専門的なプログラミング知識がなくても、ドラッグ&ドロップなどの簡単な操作で様々な角度からデータを深掘り(ドリルダウン)したり、異なるデータを組み合わせて分析したりできます。
これによりデータ分析の専門家でなくても、現場のマネージャーや担当者が自らデータを分析し、日々の業務改善や意思決定に活かす「セルフサービスBI」が実現します。
データに基づいた会話が組織内で活発化し、データドリブンな文化を醸成する上で強力な武器となります。
MA(Marketing Automation)ツールは、その名の通りマーケティングに関する一連の施策を自動化・効率化するためのツールです。
例えば「資料をダウンロードした見込み客に対し、3日後にフォローアップメールを送り、さらに1週間後にセミナー案内を送る」といった一連のコミュニケーション(シナリオ)をあらかじめ設定し、自動で実行することができます。
また顧客の行動に応じてスコアを付け、購買意欲が高まったタイミングを検知する機能もあります。CDPで統合・分析した詳細な顧客データを活用することで、顧客一人ひとりの状況や興味に合わせたきめ細やかなコミュニケーションを効率的に展開することが可能になります。
多くの企業がデータ活用の重要性を認識しながらも、なかなか実践に移せない背景にはいくつかの共通した課題、いわゆる「壁」が存在します。
このセクションでは、主な3つの壁と解決策について解説します。
多くの企業では事業部や店舗、ECサイトといった単位でシステムが個別に導入されてきた歴史的経緯から、データがそれぞれのシステム内に孤立する「サイロ化」が起きています。
また手入力による表記の揺れや入力ミス、データの欠損など、データの品質が低いことも正確な分析を妨げる大きな要因です。
この壁を乗り越えるためには、まずCDPなどのツールを活用し、社内に散在するデータを一元的に管理する基盤を整備することが考えられます。同時に、データ入力時のルールを全社で標準化するデータガバナンス体制を構築し、定期的にデータをクレンジングするプロセスを確立することが重要になるでしょう。
データを分析しビジネスに有益な知見を導き出すためには、統計学や事業ドメインに関する知識、ITスキルを併せ持つ専門人材(データアナリストやデータサイエンティスト)の存在が望ましいとされています。
しかしこうした高度なスキルを持つ人材は社会全体で不足しており、採用競争は激化しています。また、社内で育成するにも時間がかかります。
解決策の一つとして、全ての分析業務を自社で完結させようとせず、外部の専門家やコンサルティングサービスを積極的に活用するという選択肢が考えられます。また近年では、現場の担当者でも高度な分析が可能なBIツールも普及しており、こうしたツールを導入して社内のデータリテラシーを底上げしていくアプローチも有効です。
データ活用を事業成長に繋げるためには、特定の部署だけに任せるのではなく、開発・営業・カスタマーサービスを含めた全社的な協力体制が不可欠です。
経済産業省の「デジタルガバナンス・コード3.0」でも、経営層がデジタル活用を「企業価値向上の手段」と位置づけ、明確な方針を示した上で自ら積極的に関与することが重要だとされています。
また現場任せにせず、経営層が率先してステークホルダーとの対話や部門間の連携促進を図ることで、社内文化や組織風土の変革が進みます。これによりデータ活用の成果が単なる一部の施策にとどまらず、持続的な成長を支える基盤となるのです。
小売DXにおけるデータ活用は、もはや避けては通れない重要な経営テーマとなっています。
その第一歩として推奨されるのが、どのようなデータがどこに、どのような形式で存在しているのかを把握する「データの棚卸し」です。
POSシステムの販売データ、会員システムの顧客情報、ECサイトのアクセスログ、さらには日々の業務報告書に至るまで、まずは身近なところから見直してみてはいかがでしょうか。
厳しい市場環境を勝ち抜くためには自社に眠る情報を最大限活用し、一歩進んだサービスを提供するためのヒントを見つけ出すことです。この記事が、皆様のデータ活用の旅の始まりの一助となれば幸いです。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
