小売DXの第一歩はペーパーレス化!メリットや書類管理の課題を解説
小売

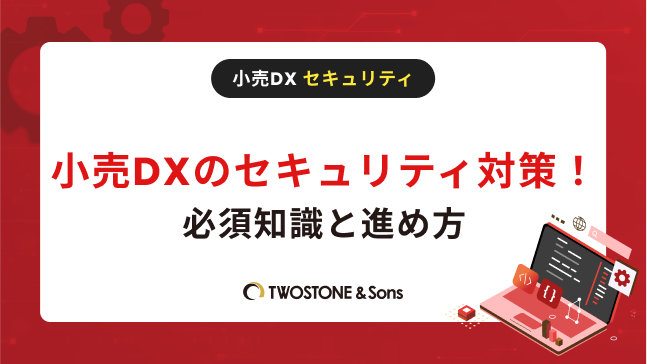
小売業のDX推進に伴い、サイバー攻撃のリスクは多様化・巧妙化しています。本記事では、POSシステムの脆弱性やランサムウェア、サプライチェーン攻撃など小売業特有のリスクを網羅的に解説。対策の進め方やコストを抑える方法まで、安全なDX実現に必要な知識を提供します。


・6万名以上のエンジニアネットワークを活用して課題を解決※
・貴社のDX戦略立案から実行・開発までワンストップで支援可能
※エンジニア数は2026年8月期 第1四半期決算説明資料に基づきます。
顧客体験の向上や業務効率化を目的に、デジタルトランスフォーメーション(DX)を進める小売業が増えています。POSやECサイト、キャッシュレス決済などのデジタル化は多くのメリットをもたらす一方で、サイバー攻撃や情報漏洩といった新たなリスクも浮上しています。
特に小売業は顧客情報やクレジットカード情報、販売・在庫データといった「狙われやすい情報資産」を多く保有しており、サイバー犯罪者にとって格好の標的です。業務停止や信用失墜など、被害が直接的に事業へ影響するケースも少なくありません。
こうした背景から、DXの推進とセキュリティ対策は切り離せない課題となっています。この記事では、小売DXに潜むセキュリティリスクについて解説します。守るべき情報資産の整理、多層防御や教育を含む対策の進め方、コストを抑える工夫まで解説しているため、安全なDXを実現するヒントにしてください。

小売業のDX化は利便性を高める一方で、新たな攻撃の標的を生み出しています。攻撃者は、デジタル化によって生じたシステムの脆弱性を狙って侵入を試みます。
このセクションでは小売業が特に注意すべき7つのセキュリティリスクを挙げ、その具体的な脅威について解説します。これらのリスクを理解することは、効果的な対策を講じるための第一歩となります。
店舗運営の中核であるPOSシステムは、サイバー攻撃の主要な標的です。
古いOSや未適用のセキュリティパッチといった脆弱性を放置すると、マルウェア感染のリスクが高まります。攻撃者はPOSシステムに侵入し、クレジットカード情報を窃取する「POSマルウェア」に感染させたり、システムを停止させて業務を妨害したりします。
これにより、顧客情報の漏洩や売上機会の損失といった深刻な被害に直結する可能性があります。
オンライン販売の拠点であるECサイトも、常に攻撃の脅威にさらされています。
Webアプリケーションの脆弱性を悪用するSQLインジェクションや、決済ページでカード情報を窃取するフォームジャッキングといった攻撃により、顧客の個人情報やカード情報が漏洩する被害が発生しています。
一度情報漏洩が起きると金銭的な被害に加え、企業のブランドイメージと顧客からの信頼を著しく損なう結果を招きます。
ランサムウェアは企業のデータを暗号化して利用不能にし、復旧と引き換えに身代金を要求するマルウェアです。
小売業が感染した場合にはPOSや在庫管理といった基幹システムが停止し、店舗運営そのものが不可能になるなど、事業継続に深刻な影響を及ぼす可能性があります。
近年ではデータを暗号化するだけでなく、窃取した情報を公開すると脅す「二重脅迫」の手口も増えており、極めて悪質な脅威となっています。
小売業が保有する大量の顧客情報は、攻撃者にとって価値の高い資産です。
外部からの不正アクセスだけでなく、従業員の操作ミスや内部不正が原因で情報が流出するケースも少なくありません。漏洩した個人情報はダークウェブなどで違法に売買され、なりすましや詐欺行為などに二次利用される危険性があります。
顧客に直接的な被害が及ぶため、企業は法的な責任や社会的な信用の失墜という厳しい事態に直面します。
キャッシュレス決済の普及は利便性を高める一方、新たなセキュリティリスクをもたらします。
決済端末やシステムの脆弱性を突かれてカード情報が盗まれたり、フィッシング詐欺で得たアカウント情報で不正利用されたりする可能性があるのです。
特に複数の決済サービスを併用している店舗では、それぞれの仕様や管理体制の違いがセキュリティ上の盲点となることがあります。
安全な決済インフラの提供は、顧客の信頼を維持するための基本的な責務であり、小売業者には決済環境の安全性を確保する責任があります。
自社のセキュリティが堅牢でも、取引先や業務委託先など関連組織の脆弱性を踏み台として攻撃されるのがサプライチェーン攻撃です。
例えばシステム開発会社や物流パートナーが攻撃を受け、そこを経由して自社のネットワークに侵入されるケースが想定されます。自社に直接的な原因が見当たらないため、発見が遅れやすく被害が拡大しやすいのが特徴です。サプライチェーン全体での対策が求められます。
顧客向けに提供する無料Wi-Fiや業務用のWi-Fiも、設定に不備があると情報漏洩の入口となりえます。
特に来店客が多い店舗では、不特定多数がアクセスする環境そのものがリスク要因となり、攻撃者にとって格好の侵入口となるのです。
通信が暗号化されていない場合、通信内容を傍受されIDやパスワードを盗取されるリスクがあります。また業務用ネットワークとの分離が不十分だと、Wi-Fi経由でPOSなどの重要システムへ侵入される危険性もあり、適切な設定と管理が不可欠です。
サイバー攻撃者が小売業を標的とする際、その目的は金銭に直結する、あるいは換金性の高い「情報資産」を盗取することにあります。
まず、自社がどのような価値ある情報を保有しているのかを把握することが重要です。それらの情報がどのようなリスクにさらされているかを理解することで、効果的なセキュリティ対策を立てやすくなります。
氏名や住所などの個人情報に加え、誰がいつ何を購入したかという購買履歴が結びついたデータは、攻撃者にとって非常に価値の高い情報です。
この情報を悪用し、個人の趣味嗜好に合わせた巧妙なフィッシングメールを送るなど、次の標的型攻撃の精度を高めるために利用されます。特に会員制サービスやポイントカードを導入している企業では、詳細な購買履歴が蓄積されやすく、情報の漏洩時に被害が広範囲に及ぶおそれがあります。
クレジットカード情報は攻撃者にとって最も直接的に金銭的利益につながるため、常に攻撃のターゲットとなっています。
ECサイトやPOSシステムから窃取されたカード情報は、ダークウェブで違法に取引され不正利用されます。一度流出した情報は回収が困難で、複数の不正利用に転用されるケースも少なくありません。
カード情報の漏洩は顧客の金銭被害に加え、企業側も賠償金の支払いや信用の失墜という計り知れないダメージを受けることになります。
売上実績や在庫状況といった販売データは、企業の経営戦略に関わる重要な機密情報です。例えば販売の傾向や在庫回転率といった指標は、仕入れや販促施策の判断材料となるため、第三者にわたると経営判断の優位性を失いかねません。
これらの情報が競合他社に漏洩すれば、市場での競争において著しく不利になります。またランサムウェア攻撃によってこれらのデータが暗号化されると、発注や在庫管理といった基本的な業務が行えなくなり、事業継続が極めて困難な状況に陥ります。
顧客情報だけでなく従業員の氏名、住所、給与情報といった個人情報も攻撃の標的です。これらの情報が漏洩すれば、従業員個人が詐欺被害に遭うリスクや、人事部を装った標的型攻撃に悪用される危険性があります。
また従業員の会社に対する不信感にもつながり、健全な組織運営を維持するためにも従業員の個人情報保護は重要です。
小売業では店舗ごとに従業員の入れ替わりも多く、情報管理が煩雑になりやすい点にも注意が必要です。

巧妙化するサイバー攻撃に対して、もはや単一の対策だけで防ぐことはできません。現代のセキュリティ対策では、複数の防御策を層のように重ねる「多層防御」が基本とされています。
さらに、対策は技術面だけにとどまりません。「組織体制」「技術的防御」「インシデント対応」の三位一体で推進していくことが不可欠です。この3つの観点から、具体的に講じるべき対策を見ていきましょう。
セキュリティ対策の基盤は「人」と「ルール」です。経営層がリーダーシップを発揮し、全社的な情報セキュリティポリシーを策定・周知することが重要です。
経済産業省の「デジタルガバナンス・コード」でも、経営層がサイバーセキュリティリスクを経営リスクのひとつとして認識し、組織体制を整備するよう記載されています。
経営者を筆頭に、従業員一人ひとりの意識も組織全体の防御力を左右します。フィッシングメールの見分け方など、具体的な脅威と対策について定期的に教育や訓練を実施する必要があります。こうした取り組みを通し、組織全体のセキュリティレベルを底上げすることが大切です。
出典参照:デジタルガバナンス・コード3.0(P.13-14)|経済産業省
技術的な対策ではネットワークの入口から個々の端末まで、複数の防御壁を設けることが重要です。小売業ではECサイト、POSシステム、決済端末など守るべき対象が多岐にわたるため、こうした多層的なアプローチが特に有効です。
外部からの攻撃を防ぐ「UTM」、Webサイトを守る「WAF」、そしてPCやサーバーへの侵入を検知・対応する「EDR」など、役割の異なるセキュリティ製品を組み合わせます。
これにより一つの防御層が突破されても次の層で脅威を食い止める、穴のない防御体制を構築します。
「攻撃はいつか発生するもの」という前提に立ち、万が一インシデントが発生した場合に被害を最小限に抑え、迅速に事業を復旧させるための事前の計画が不可欠です。
特に小売業では店舗運営の中断が売上や顧客対応に直結するため、迅速な初動対応が求められます。
インシデント発見時の報告フロー、指揮命令系統、外部専門家への連絡手順などを具体的に定めた「インシデント対応計画」を策定し、定期的な訓練を通じて実効性を高めていくことが重要です。
セキュリティ対策において、「何から手をつければ良いのか分からない」という担当者も少なくありません。場当たり的な対策は効果が薄く、無駄なコストにつながる可能性があります。
このセクションでは、セキュリティ対策を体系的かつ効果的に進めるための実践的な4つのステップを紹介します。
対策の第一歩は、自社がどのようなセキュリティ上の弱点(脆弱性)を抱えているのかを客観的に把握することです。
そのための有効な手段が、専門家による「脆弱性診断」の実施です。脆弱性診断は、Webサイトやネットワークに潜むセキュリティホールを特定し、レポートとして報告してくれます。
これによりリスクが具体的に「可視化」され、対策を検討するための客観的な根拠を得ることができます。
洗い出されたすべてのリスクに一度に対応することは、現実的ではありません。そこで「攻撃された場合の影響の大きさ」と「攻撃される可能性の高さ」の2軸でリスクを評価し、対策の優先順位を決定します。
小売業ではECサイトやPOS、決済端末など複数のリスク源が存在するため、対象ごとの緊急度と重要度を丁寧に見極める必要があります。例えば「カード情報漏洩」のように影響が甚大なリスクは最優先で対処するなど、限られた予算とリソースを最も効果的な対策に集中させることが投資対効果を高める上で重要です。
対策すべきリスクの優先順位が定まったら、それを低減するための具体的なセキュリティ製品やサービス(ソリューション)を選定します。自社の事業規模やシステム環境、予算に応じて、必要な機能や価格、サポート体制などを総合的に比較・検討することが大切です。
特に小売業では本部システムと店舗システムが分かれていることも多く、導入時の適合性や運用負荷も考慮する必要があります。複数のベンダーから提案を受け、自社にとって最適なパートナーを選び出すことが対策の成否を分ける鍵となります。
セキュリティ対策は、ソリューションを導入して終わりではありません。サイバー攻撃の手法は日々進化するため、導入後も継続的に対策を改善していく「運用」のプロセスが不可欠です。
特に店舗運営では現場任せになりやすいため、導入した対策が継続的に機能しているかどうかを本部が主体的に確認・支援する姿勢も欠かせません。
セキュリティ機器のログ監視やソフトウェアの更新を怠らず、定期的に自社の体制全体を見直しましょう。必要に応じて改善を重ねていくことで、現場で機能するセキュリティ体制を支えます。
セキュリティ対策を検討する上で、費用は重要な要素です。かかるコストは企業の規模や求めるセキュリティレベルによって、大きく変動します。
このセクションでは、代表的なセキュリティ対策にかかる費用の目安や価格体系について解説します。
脆弱性診断の費用は、診断方法と対象範囲によって異なります。ツールで自動検査する「ツール診断」は数万円から数十万円程度が相場です。
一方専門家が手動で詳細に分析する「手動診断」は、より高精度ですが費用も高く、数十万円から数百万円に及ぶこともあります。重要なシステムには手動診断、その他には定期的なツール診断といった使い分けが考えられます。
ECサイトやPOSなど顧客情報を扱うシステムは攻撃リスクが高いため、可能であれば手動診断の対象として検討すべきです。
UTMやEDRといったセキュリティ製品の価格は、主に保護対象の端末数(ライセンス数)に応じた課金体系が一般的です。例えば小規模オフィス向けのUTMは、機器代と月額の保守費用がかかります。
EDRは1ライセンスあたり月額数百円からが相場です。初期費用を抑えたい企業では、月額課金制のクラウド型製品を選ぶケースも増えています。
機能やサポート内容によって価格は大きく異なるため、複数の製品を比較検討することが重要です。
社内に専門家がいない場合、外部のコンサルティングやセキュリティ運用代行(MDR)の利用が有効です。コンサルティングはプロジェクトの内容により数十万円から、MDRなどの運用代行は監視対象に応じた月額課金制で数十万円からが目安となります。
特に多店舗展開している小売業では、全拠点の状況を一元的に監視・対応する仕組みとしても有効です。自社で24時間体制を構築するよりも、結果的にコストを抑えつつ質の高い運用を実現できる可能性があります。

セキュリティ対策の重要性を認識しつつも、中小企業にとってはコストが大きな負担となる場合があります。しかし、対策を先延ばしにすることは、将来的にそれ以上の損害を生むリスクを抱え込むことになります。
このセクションでは対策コストを抑えながら、効果的にセキュリティレベルを向上させるための方法を紹介します。
国の中小企業支援策である「IT導入補助金」には、セキュリティ対策推進枠が設けられています。これは、IPAが認定する「サイバーセキュリティお助け隊サービス」の導入にかかる費用の一部を補助する制度です。補助対象のサービスは、事前に登録されたIT導入支援事業者から選ぶ必要があります。
UTMやEDRといったツールの導入・運用費用などが対象となり、コスト負担を大幅に軽減しながら専門家が推奨するレベルの対策を導入できる可能性があります。
出典参照:IT導入補助金2025|サービス等生産性向上IT導入支援事業事務局
セキュリティ対策は一度にすべてを実施しようとせず、優先度の高いリスクから段階的に着手する「スモールスタート」が効果的です。リスク評価の結果をもとに、特に効果が見込める対策に絞って予算を集中させましょう。
例えば、まずは全従業員へのセキュリティ教育から始めるなど、段階的に対策範囲を広げていく方法がおすすめです。少しずつ範囲を広げていくことで、無理なく着実にセキュリティレベルを高めることができます。
小売業のDXは業務効率や顧客体験を向上させる大きなチャンスである一方、サイバー攻撃のリスクと常に背中合わせです。特にPOS・EC・決済・顧客情報といった重要な資産が狙われやすく、攻撃が事業そのものに直結することもあります。
本記事では、代表的な7つのリスクと小売業が抱える情報資産、技術・組織・プロセス面のセキュリティ対策を紹介してきました。また、リスクを可視化し優先順位を立てて着実に進めるためのステップや、IT導入補助金を活用してコストを抑える方法にも触れています。
重要なのは「守り」を固めながら、DXを進めていくことです。自社の状況を正しくつかみ、無理なく続けられる対策を整えていきましょう。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
