小売DXの第一歩はペーパーレス化!メリットや書類管理の課題を解説
小売

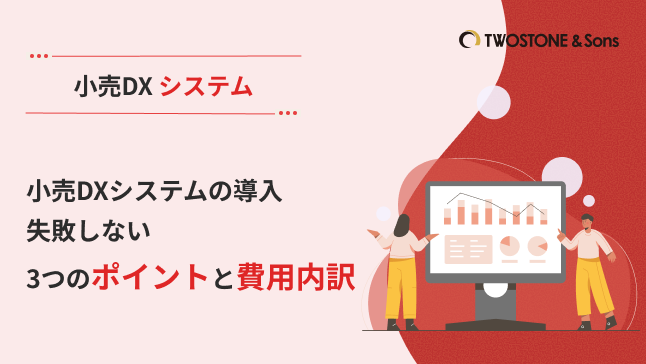
小売業の人手不足や在庫管理にお悩みですか?小売DXシステムの導入が解決の鍵です。この記事では、小売DXシステムの基礎知識から、目的別の選び方、おすすめシステムの比較、費用相場までを網羅的に解説。失敗しないポイントを押さえ、自社に最適なシステムを見つけましょう。


・6万名以上のエンジニアネットワークを活用して課題を解決※
・貴社のDX戦略立案から実行・開発までワンストップで支援可能
※エンジニア数は2026年8月期 第1四半期決算説明資料に基づきます。
店舗運営において、「人手が足りない」「在庫管理がうまくいかない」といった課題はありませんか。業界全体でデジタル化が進む中、これまでのやり方に限界を感じている担当者様も多いかもしれません。
その解決策として注目されるのが「小売DXシステム」です。しかし、種類が多くて自社に何が合うのか分かりにくいという声も聞かれます。この記事では小売DXの基本からシステムの選び方、おすすめのツールまで、分かりやすく解説していきます。

小売業が抱える課題は、DX、すなわちデジタルトランスフォーメーションによって解決へと導かれることがあります。まずは多くの企業が直面している代表的な4つの課題を見ていき、自社の状況と照らし合わせてみましょう。
小売業界では採用難や少子高齢化を背景に、人手不足がますます深刻な問題となっています。その結果、現場で働くスタッフ一人ひとりへの業務負担が増大し、日々のレジ業務や品出しや発注作業といったルーティンワークに追われてしまう状況が生まれがちです。
本来であれば、お客様への丁寧な接客やより魅力的な売り場づくりといった、売上に直結するコア業務に時間を割きたいところですが、なかなか手が回らないという声も少なくありません。
小売DXシステムを導入することで、会計や発注などの定型業務を自動化・効率化し、スタッフの負担を軽減することが期待できます。創出された時間を活用して顧客満足度を高めるための活動に注力できるようになれば、従業員のモチベーション向上や離職率の低下にもつながっていくでしょう。
「在庫管理は店長の経験と勘が頼り」という状況は多くの店舗で見られますが、これには大きなリスクが伴います。個人の感覚に頼った発注は需要予測が外れた場合に、人気商品の欠品による販売機会の損失や、逆に売れ残りによる過剰在庫を招く原因となりかねません。
過剰在庫は保管スペースを圧迫するだけでなく、キャッシュフローの悪化や商品の価値低下にも直結する深刻な問題です。特に実店舗とECサイトで在庫情報が分断されていると、顧客が求める場所に商品がないという事態も頻発します。
在庫管理システムを導入すれば、販売データを基にした客観的な需要予測や、店舗とECサイトの在庫情報をリアルタイムで一元管理することが可能になります。これによりデータに基づいた最適な在庫コントロールが実現し、経営の安定化に貢献します。
現代の消費者は実店舗だけでなく、ECサイトやSNSなど様々なチャネルを通じて情報を収集し、商品を購入します。このような購買行動の多様化に対応し、顧客一人ひとりに合ったサービスを提供することが、売上を伸ばす上で非常に重要です。
しかし、多くの企業ではPOSデータや会員情報を持ってはいるものの、それらを十分に活用しきれていないのが実情です。特に店舗とECで顧客データがバラバラに管理されていると、一人の顧客の全体像を捉えられません。
顧客管理システム(CRM)を活用すれば、これらの分散したデータを統合して顧客の購買履歴や行動を深く分析できます。その分析結果に基づいて個々の顧客に最適な情報やクーポンを届けることで、顧客満足度とロイヤルティを高めていくことが可能です。
日々の売上報告やスタッフの勤怠管理、経費の精算、発注書の作成といったバックオフィス業務には、いまだに紙やExcelを使った手作業が多く残っているケースが見られます。
これらの業務は一つひとつの作業時間は短くても、積み重なると膨大な時間と労力を消費し、本来のコア業務を圧迫する原因となります。また、手作業によるデータ入力は、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生しやすいというリスクも伴います。
各種DXシステムを導入してこれらのバックオフィス業務を自動化・ペーパーレス化することで、業務全体の生産性が向上します。これにより、迅速かつ正確な経営判断をサポートする体制を整えることができます。
小売業が抱える課題を解決するため、様々な種類のDXシステムがあります。このセクションでは、代表的な4つのシステムがどのような役割を担うのかを説明します。自社の課題解決のヒントを探してみてください。
POSシステムとは「販売時点情報管理」システムのことで、単に会計処理を行うだけでなく、商品が売れた瞬間の情報をデータとして収集・分析する役割を担います。「いつ、どの商品が、いくらで、どのような顧客に売れたか」といった貴重な販売データをリアルタイムで蓄積できるのが大きな特徴です。
収集したデータは、売れ筋商品や不振商品を分析する「ABC分析」や、時間帯別の売上傾向の把握に活用でき、効果的な販売戦略や人員配置の最適化に役立ちます。
近年主流のクラウド型POSシステムは導入コストを抑えやすく、インターネット環境があればどこからでも売上状況を確認できる利便性も備えています。在庫管理や顧客管理システムと連携させることで、店舗運営全体の司令塔として機能し、より高度なデータ活用を実現する基盤となります。
在庫管理システムは、店舗や倉庫にある商品の在庫数を正確に把握し、入出庫から棚卸しまでの一連の業務を効率化するツールです。キャッシュフローにも影響する「適正在庫」の維持に役立ちます。
手作業で起こりがちな入力ミスなどを防いで在庫データの精度を高めることで、欠品による機会損失や、過剰在庫が引き起こすコスト増大のリスクを減らすことにつながります。
特に実店舗とECサイトを運営する場合、双方の在庫情報をリアルタイムで一元管理する機能が重要です。どちらかで商品が売れた際にもう一方の在庫も自動で更新されるため、売り越しを防げます。データに基づいた需要予測機能は、属人化しがちな発注業務の標準化もサポートします。
顧客管理システム(CRM)は、顧客との良好で長期的な関係を築くことを目的としたシステムです。顧客の氏名や連絡先といった基本情報に加え、購入履歴や問い合わせ履歴など、顧客に関するあらゆる情報を一元的に管理します。
これらのデータを活用することで、顧客を「最近購入した優良顧客」「しばらく購入のない休眠顧客」といったグループに分け、それぞれのセグメントに合わせたきめ細やかなアプローチが可能になります。
例えば、特定のブランドをよく購入する顧客に新商品の先行案内を送るなど、一人ひとりに寄り添ったコミュニケーションは、顧客満足度を高めてリピート購入を促進することにつながるでしょう。
複数のECモールや自社のECサイトを運営している場合、その管理業務は非常に煩雑になりがちです。ECサイト一元管理システムは、これらの複数チャネルの運営を一つの画面でまとめて効率化するためのシステムです。
主な機能として、各サイトから入る注文情報を自動で取り込む「受注管理」、全サイトの在庫数をリアルタイムで同期させる「在庫連携」、そして一つの商品情報を各サイトの仕様に合わせて一括で登録・更新する「商品登録」があります。
このシステムを導入することで、各サイトの管理画面を個別に行き来する必要がなくなり、受注処理や在庫更新にかかる時間と手間を大幅に削減できます。また、手作業による在庫更新のタイムラグが原因で起こる「売り越し」といったミスを防ぎ、販売機会の最大化をサポートします。
このセクションでは、多くの企業で導入されている代表的な小売DXシステムを、目的別に紹介します。それぞれのシステムが持つ特徴を理解し、自社の目指す姿と照らし合わせてみてください。
「スマレジ」はiPadなどのタブレットで利用できるクラウドPOSレジです。基本的なレジ機能は無料で利用開始でき、事業の成長に合わせて必要な機能をプランアップで追加できます。
このシステムの大きな特徴は、豊富な拡張機能と外部サービスとの連携力にあります。在庫管理や顧客管理や会計ソフトなど、様々なツールと連携させることで、自社の業務フローに合わせた柔軟なシステム構築が可能です。操作画面も分かりやすく、小規模な店舗から多店舗展開する企業まで、幅広いニーズに対応できるサービスといえるでしょう。
出典参照:スマレジ|株式会社スマレジ
「ネクストエンジン」は複数のECサイトと実店舗の在庫や受注情報を一元管理できるシステムです。特にネットショップ運営の効率化に強みがあり、多くのEC事業者に利用されています。
このシステムを導入することで、EC運営に関わる多くの手作業を自動化できる可能性があります。例えば各ECモールからの注文を自動で取り込み、在庫数をリアルタイムで更新し、お客様への発送完了メールを自動で送信するといった流れを構築できます。EC事業の規模拡大を目指す企業にとって、業務負担の軽減とミスの削減に貢献するでしょう。
出典参照:ネクストエンジン|Hamee株式会社
「Salesforce」は世界的に広く利用されている顧客管理(CRM)プラットフォームです。その中でも「Salesforce Service Cloud」は、小売業における顧客との関係づくりを強力にサポートします。
顧客の購買データや行動履歴を詳細に分析し、一人ひとりに合わせたコミュニケーションを実現するための機能が豊富に揃っています。AI(人工知能)を活用した需要予測や商品推薦なども可能で、データに基づいた戦略的なマーケティング活動を展開したい企業に適しています。多機能であるため、その能力を最大限に引き出すには計画的な導入と活用が求められます。
出典参照:Salesforce|株式会社セールスフォース・ジャパン
「TEMPOSTAR」は、複数のECサイトと実店舗の情報をまとめて管理できる一元管理システムです。特に、企業の独自の運用フローに合わせたカスタマイズ性の高さに定評があります。
在庫や受注、商品情報の一元管理といった基本機能に加え、特定の条件に合う注文だけを処理から分けたり独自の帳票を作成したりと、細かい設定が可能です。すでに複数のECサイトを運営しており、既存の業務フローを大きく変えずに効率化を図りたい、といった複雑なニーズにも対応しやすいサービスです。
出典参照:TEMPOSTAR|NHN SAVAWAY株式会社

自社に合ったシステムを導入するためには、機能や価格だけでなくいくつかの視点から慎重に検討することが大切です。このセクションでは、システム選びで後悔しないために事前に確認しておきたい3つのポイントを解説します。
システムを選定する際、まず考慮すべきは自社の事業規模や業態に合っているかという点です。例えば、個人経営の店舗であればシンプルで直感的に使えるシステムが適している一方、多店舗展開する企業では、複数店舗のデータを一元管理できる高度な機能が求められます。
将来的な事業拡大の計画があるなら、その拡張性(スケーラビリティ)も重要な判断基準です。「今は3店舗だが、数年後には10店舗を目指す」といったビジョンがある場合、店舗数が増えてもスムーズに対応できるシステムを選ぶ必要があります。
また、アパレル業界であれば色・サイズ別の在庫管理、食品スーパーであれば賞味期限やロット管理といったように、業態特有の業務プロセスが存在します。自社の商材や業務フローに特化した機能を備えているかを確認することで、導入後のミスマッチを防げるでしょう。
多くの企業では会計ソフトや勤怠管理システム、ECカートなど、すでに何らかのITツールを運用しているはずです。新しく導入する小売DXシステムが、これらの既存システムとスムーズに連携できるかは、業務効率を左右する非常に重要なポイントです。
もしシステム間の連携ができない場合、データを手作業で二重に入力する手間が発生したり、各システムの情報にズレが生じたりする可能性があります。これではかえって業務が非効率になり、DXの目的を達成できません。
特に、会社の根幹となる会計システムや基幹システム(ERP)との連携は必須要件として考えるべきでしょう。システム選定時には、どのような方法(API連携、CSV連携など)で連携できるのか、また自社で利用中のツールとの連携実績があるかをベンダーに具体的に確認することが不可欠です。
どんなに高機能なシステムでも、現場スタッフが使いこなせなければ意味がありません。ITツールに不慣れな方でも直感的に操作できるか、日々の業務でストレスなく使えるかは、導入後の定着を左右する重要なポイントです。
多くのサービスが提供する無料トライアルを活用し、経営層だけでなく現場スタッフも一緒に、自社の業務フローに合うか操作性をしっかり確認しましょう。
また、導入後のサポート体制も重要です。操作で困った時やトラブル発生時に電話やメールで迅速に対応してもらえるか、分かりやすいマニュアルが用意されているかなど、安心して運用できるサポートがあるかを確認しておくことが不可欠です。
小売DXシステムの導入は、ツールを導入して終わりではありません。計画的に進め、導入後も改善を続けることが成功への道筋です。このセクションでは、導入を成功させるための3つのステップを紹介します。
システム導入を成功させる最初のステップは、「何のために導入するのか」という目的を明確にすることです。「在庫管理の作業時間を削減する」「ECサイトの売上を向上させる」など、具体的で測定可能な目標を設定します。
目的が曖昧なままでは必要な機能が分からず、導入後にミスマッチが起こる可能性があります。目的を定めたら、予算や導入時期、社内の推進体制などを盛り込んだ具体的な導入計画を策定します。
この段階で経営層から現場スタッフまで関係者全員で目的意識を共有しておくことが、プロジェクトを円滑に進める上で非常に重要です。
導入計画が固まったら、次はその計画に合うシステムを探します。IT製品の比較サイトなどを活用し、自社の課題を解決できそうなシステムを複数リストアップしましょう。
候補がいくつか挙がったら、資料請求やオンライン説明会で詳細な情報を収集します。自社と同じ業種・規模の企業での導入実績も、有力な判断材料になります。
最終的に2〜3社に候補を絞り、デモンストレーションを依頼して実際の操作感を確認します。無料トライアルを活用し、現場担当者にも試してもらうのが理想的です。機能、費用、サポート体制などを総合的に比較し、最適なシステムを決定します。
システムの導入が完了しても、それで終わりではありません。導入効果を最大化するためには、導入後の効果測定と継続的な改善活動が不可欠です。
まずは、ステップ1で設定した目標が達成できているかを定期的にデータで確認します。作業時間の削減が目標であれば、導入前後でどれだけ時間が短縮されたかを測定します。
もし期待した効果が出ていない場合は、その原因を分析して対策を講じる必要があります。システムの使い方が浸透していないなら社内研修を実施するなど、PDCAサイクル(計画→実行→評価→改善)を回し続けることで、システムは真に自社の力となります。
システムの導入にあたり、費用は重要な検討項目です。一般的に、導入時にかかる「初期費用」と継続的に発生する「月額費用」の2種類があります。費用はシステムの機能や規模によって大きく変動します。
初期費用は、システムを導入する際に一度だけ発生するコストです。近年主流のクラウド型システムでは初期費用が無料のサービスも増えていますが、数万円から数十万円程度かかる場合もあります。
主な内訳は、アカウント発行や基本設定などの「導入支援費用」です。その他にPOSレジ用のタブレットやバーコードリーダーといったハードウェアの購入費用や、既存システムからのデータ移行、個別のカスタマイズを行う場合には、追加で費用が発生することがあります。導入前に複数のベンダーから見積もりを取り、どこまでが標準サービスで何がオプション費用になるのかを正確に把握しておくことが重要です。
月額費用は、システムを利用し続けるために毎月支払うライセンス料です。クラウド型システムの場合、この月額費用が主なコストとなり、料金は数千円から数十万円以上と幅広いです。
料金体系は、利用する店舗数やユーザー数に応じて変動するプランが一般的です。また、必要な機能を追加するオプション形式や、ECサイトの売上に応じて変動する従量課金制を採用しているサービスもあります。自社の事業規模や必要な機能を見極め、過不足のないプランを選ぶことがコスト最適化の鍵です。将来的な事業拡大も視野に入れ、プランのアップグレードが柔軟に行えるかどうかも確認しておくと良いでしょう。
システム導入の費用対効果を高めるには、まず国や自治体の補助金活用を検討しましょう。「IT導入補助金」のような制度を利用できれば、コストを大幅に抑えることが可能です。補助金は公募期間や対象となる要件が毎年変わるため、公式サイトなどで常に最新の情報を確認することが大切です。
また、いきなり全店舗に導入するのではなく、特定の店舗だけで試験的に始める「スモールスタート」も有効な手段です。小さな範囲で操作性や効果を検証し、成功モデルを確立してから全社に展開することで、導入失敗のリスクを最小限に抑え、着実にDXを進めることができます。
出典参照:IT導入補助金2025|サービス等生産性向上IT導入支援事業事務局

ここまで、小売DXシステムに関する様々な情報をお伝えしてきました。多くの選択肢がある中で、自社に最適なシステムを選ぶためには、まず自社の現状を正しく理解することが何よりも大切です。
システム導入は、あくまで課題解決のための手段です。大切なのはツールを導入することそのものではなく、それを使って何を成し遂げたいのかを明確にすることにあります。
ぜひこの機会に、あなたの会社が抱える課題を改めて整理し、どの課題から優先的に取り組むべきかを考えてみてください。解決したい目的がはっきりすれば、選ぶべきシステムの姿もおのずと見えてくるはずです。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
