小売DXの第一歩はペーパーレス化!メリットや書類管理の課題を解説
小売

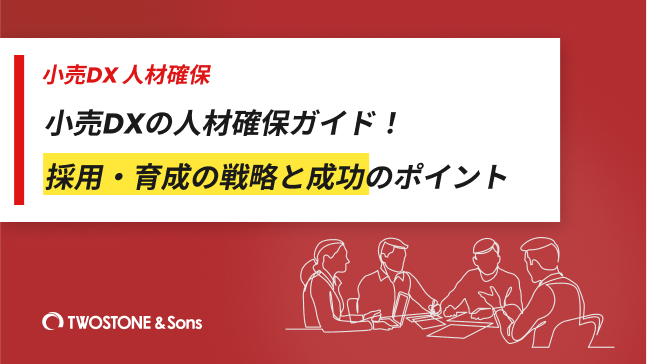
小売業界でDX推進が急務となる中、人材確保は多くの企業が直面する課題です。本記事では、DXに必要な人材像やスキルセットを具体的に解説します。さらに、採用・育成・外部連携といった人材確保の具体的なアプローチや、他社の成功事例も紹介し、貴社の人材戦略を成功に導くためのヒントを提供します。


・6万名以上のエンジニアネットワークを活用して課題を解決※
・貴社のDX戦略立案から実行・開発までワンストップで支援可能
※エンジニア数は2026年8月期 第1四半期決算説明資料に基づきます。
小売業界において、デジタルトランスフォーメーション(DX)の推進は、企業の競争力を維持・向上させる上で重要な経営課題となっています。顧客ニーズの多様化や人手不足といった課題に対応するため、多くの企業がDXに着手していますが、その成否を分ける大きな要因が「人材の確保」です。
しかし、DX推進の担当者の方々からは、「そもそもどのような人材が必要なのかわからない」「採用市場での競争が激しく、優秀な人材を確保できるか不安だ」といった声も聞かれます。
本記事では、小売DXにおける人材確保という課題に対し、必要な知識から実践的なノウハウまでを体系的に解説します。 この記事を通じて、自社がとるべき人材戦略の方向性を明確にするための一助となれば幸いです。
現代の小売業界は大きな変革期にあり、従来のビジネスモデルのままでは立ち行かなくなる可能性が指摘されています。
このような状況下で企業が持続的に成長するためには、デジタル技術を活用できる人材の確保が急務です。このセクションでは、その背景にある3つの主要な要因について解説します。
日本の生産年齢人口の減少は、小売業界に深刻な人手不足という構造的課題をもたらしています。店舗での接客やレジ、在庫管理といった労働集約型の業務が多く、人材確保は年々困難になっています。
この課題に対し、DXは有効な解決策となり得ます。AIによる需要予測や発注業務の自動化、セルフレジの導入による省人化などがその一例です。
しかし、これらのデジタル技術は、導入するだけで効果が最大化されるわけではありません。自社の業務に合わせて最適化し、日々運用しながら改善していくことが不可欠です。そのためには、技術の仕組みを理解し、ビジネス課題と結びつけて活用を推進できる人材の存在が求められます。
スマートフォンの普及は消費者の購買行動を大きく変えました。人々は店舗へ行く前にオンラインで情報を集め、購入後にはSNSで体験を共有します。実店舗とECサイトを使い分けることも一般化しています。
また、単に商品を手に入れる「モノ消費」から、商品を通じて得られる体験価値を重視する「コト消費」へとニーズはシフトしています。価格や機能だけでなく、ブランドへの共感も購買の重要な動機です。
このような複雑で多様化した顧客ニーズに応えるためには、データに基づいた顧客理解が欠かせません。顧客の属性や購買履歴、行動履歴などを分析し、一人ひとりに最適化された情報やサービスを提供できるDX人材が、企業の競争力を左右する重要な役割を担います。
これからの小売業において、成長の鍵を握るのはデータ活用による顧客体験(CX)の向上です。勘や経験だけに頼った店舗運営では、変化の速い市場や多様な顧客ニーズに対応しきれなくなっています。
優れた顧客体験は、顧客満足度を高めてリピート購入を促し、長期的な関係性を築くことでLTV(顧客生涯価値)の最大化に繋がります。これを実現するためには、あらゆる顧客接点で生まれるデータを収集・分析し、具体的な施策に落とし込むことが求められます。
例えば、Webサイトの行動履歴を分析してUI/UXを改善したり、店舗内の動線を分析して売り場レイアウトを最適化したりすることが考えられます。こうしたデータドリブンなアプローチを実践するためには、専門的なスキルを持つ人材が不可欠となります。

小売DXを推進するためには、多様な専門分野の人材がそれぞれの役割を担い、連携していくことが不可欠です。
経済産業省が策定した「デジタルスキル標準」などを参考に、このセクションでは特に重要とされる5つの職種と、それぞれに求められるスキルについて解説します。
出典参照:デジタルスキル標準|経済産業省
DXプロデューサーは、経営戦略とデジタル技術の両方を深く理解し、DXプロジェクト全体の方向性を定めて推進するリーダーの役割を担います。ビジネス課題を的確に捉え、それを解決するためのDX戦略やロードマップを策定し、経営層と現場をつなぐ橋渡し役となります。
具体的な業務としては、プロジェクトのKGI/KPI設定、予算管理や進捗管理、そして社内外のステークホルダーとの調整などが挙げられます。そのため、小売業界のビジネスモデルに関する深い知見に加え、プロジェクトマネジメント能力や論理的思考力、そして関係者を巻き込みながら物事を前に進めるリーダーシップが不可欠です。DXの「何を」「なぜやるのか」を定義し、プロジェクトを成功に導く羅針盤のような存在と言えるでしょう。
データサイエンティストは事業活動を通じて蓄積される膨大なデータを分析し、ビジネスに有益な知見を抽出する専門家です。POSデータや顧客IDに紐づく購買履歴、Webサイトのアクセスログ、さらには商圏データといった多種多様なデータを扱います。
統計学や機械学習などの専門知識を駆使し、需要予測モデルの構築や顧客のセグメンテーション、価格最適化、レコメンデーションエンジンの開発などを行います。そのために、PythonやRといったプログラミング言語、SQLによるデータベース操作のスキルが求められます。また、複雑な分析結果をビジネスサイドの担当者にわかりやすく伝え、具体的なアクションに繋げる「翻訳者」としてのコミュニケーション能力も非常に重要です。
デジタルマーケターはWebサイトやSNS、アプリ、メールマガジンといったデジタルチャネルを通じて、顧客とのあらゆる接点を最適化し、良好な関係を築く役割を担います。その業務はSEO(検索エンジン最適化)による集客、Web広告の運用やSNSキャンペーンの企画・実行、MA(マーケティングオートメーション)ツールを活用した顧客育成など多岐にわたります。
デジタルマーケターにはGoogle Analyticsなどの分析ツールを用いて効果測定と改善を繰り返すPDCAサイクルを回す能力が不可欠です。また、オンラインとオフラインの顧客データを統合し、一貫した顧客体験を提供するOMO(Online Merges with Offline)の視点も求められます。顧客の購買行動がデジタルへとシフトする中で、企業の売上に直結する重要な職務です。
DXエンジニアは、DX戦略を具現化するためのシステムやアプリケーションを設計・開発・運用する技術職です。ECプラットフォームの構築や改修、顧客管理システム(CRM)や在庫管理システム(WMS)の導入・連携、店舗で利用するモバイルアプリの開発などが主な業務となります。
Java、PHP、Pythonといったプログラミング言語のスキルはもちろん、AWS(Amazon Web Services)やMicrosoft Azureなどのクラウドプラットフォームに関する深い知識が求められます。また、ビジネスサイドの要求を正確に理解し、それを技術的な仕様に落とし込む能力も重要です。変化に迅速に対応するため、アジャイル開発などのモダンな開発手法に精通していることも強みとなるでしょう。
UI/UXデザイナーは顧客が利用するWebサイトやアプリケーションについて、快適で満足度の高い利用体験を設計する専門職です。UI(ユーザーインターフェース)は画面のデザインや操作性など、ユーザーが直接触れる部分を指します。一方、UX(ユーザーエクスペリエンス)は、そのサービスを通じてユーザーが得られる満足感や感動といった体験全体を指します。
具体的な業務にはペルソナやカスタマージャーニーマップの作成、ワイヤーフレームやプロトタイプを用いた設計、ユーザビリティテストを通じた課題発見と改善などが含まれます。単に見た目を美しくするだけでなく、人間中心設計の考え方に基づいてユーザーの課題を解決し、ビジネス目標の達成に貢献することが求められる職務です。

即戦力となるDX人材を確保するために、外部からの採用は有効な手段の一つです。
しかし、DX人材の需要は高く、採用競争は激化しています。このセクションでは、採用を成功に導くための具体的な4つのステップを解説します。
採用活動を始める前に、まず自社のDX戦略に基づいた採用計画を策定することが重要です。場当たり的な採用は、ミスマッチや早期離職のリスクを高める可能性があります。
「どのようなビジネス課題を解決したいのか」「そのために、どのようなスキルや経験を持つ人材が、いつまでに、何名必要なのか」を明確にします。この人材要件定義が、その後の採用活動全体の軸となります。
経営層や現場の責任者と十分に議論し、職務内容、必須スキルと歓迎スキル、求める人物像などを具体化した「人材要件定義書」を作成することが求められます。この最初のステップを丁寧に行うことが、採用の成否を大きく左右します。
採用したい人物像が明確になったら、その人材に出会うための最適なチャネルを選定します。DX人材は売り手市場であり、従来の求人広告を出すだけの「待ち」の姿勢では、優秀な人材と出会うことは難しいです。
企業側から候補者に直接アプローチする「ダイレクトリクルーティング」や、IT・DX領域に特化した人材紹介サービスの活用が有効です。また、社員の紹介を通じて採用するリファラル採用は、企業文化への適合度が高い人材を確保しやすいという利点があります。
さらに、SNSなどを活用して自社の技術的な取り組みや企業文化を発信し、候補者との接点を作るソーシャルリクルーティングも重要性を増しています。これらのチャネルを組み合わせ、多角的にアプローチすることが成功の鍵です。
選考過程では候補者が持つ専門的なスキルと、自社の企業文化に合うか(カルチャーフィット)の両面を慎重に見極める必要があります。
スキル面では、職務経歴書に加えて過去の実績がわかるポートフォリオの提出を求めたり、技術面接やケーススタディに取り組んでもらったりする方法が有効です。これにより、候補者の実践的な課題解決能力を評価できます。
カルチャーフィットの面では、面接を通じて候補者の価値観や仕事への姿勢、チームでの協調性などを確認します。一方的に評価するだけでなく、候補者からの質問にも丁寧に答え、相互理解を深める場とすることが重要です。現場のチームメンバーとの面談を設定することも、入社後のミスマッチを防ぐ上で効果的です。
優秀なDX人材は、複数の企業から内定を得ているケースが少なくありません。そのため、内定を通知してから入社承諾を得るまでの「クロージング」のプロセスが極めて重要になります。
内定者に対して行うオファー面談では、給与や福利厚生といった条件面だけでなく、入社後に期待する役割や具体的な業務内容、キャリアパスなどを魅力的に伝えることが大切です。候補者が抱える懸念や疑問点を丁寧にヒアリングし、解消に努める姿勢が求められます。
内定後も定期的にコミュニケーションをとり、現場のキーパーソンとのカジュアルな面談を設定するなど、入社への動機付けを継続的に行います。丁寧で誠実な対応を通じて、候補者に「この会社で働きたい」と思ってもらうことが最終的なゴールです。
外部からの採用と並行して、自社の事業や文化を深く理解している既存社員を育成する「リスキリング」も、DX推進における重要な人材戦略です。
このセクションでは、社内育成を成功させるためのポイントを解説します。
効果的な人材育成のためには、場当たり的な研修ではなく、戦略に基づいた計画的なアプローチが不可欠です。まず会社のDX戦略と連動させ、「将来的にどのようなスキルを持つ人材が、どの部署にどれくらい必要になるか」という育成ゴールを明確に設定します。
次に、アセスメントツールなどを活用して、現状の社員のスキルレベルを客観的に把握します。これにより育成ゴールと現状とのギャップが明らかになります。
このギャップを埋めるために、どのような育成プログラム(研修、OJT、自己啓発支援など)を、どの対象者にどのような順序で提供していくかを具体的に計画します。個々の社員のキャリアプランや意向もヒアリングしながら、一人ひとりに合った育成計画を策定することが、モチベーション維持の観点からも望ましいでしょう。
DX人材を育成するための研修には、オンラインで学べるe-ラーニングや集合研修、外部セミナーへの参加など、多様な選択肢が存在します。プログラムを選定する際は、いくつかの基準を設けて総合的に判断することが重要です。
まず、自社のDX戦略や解決したい課題に直結した、実践的なカリキュラムであるかを確認します。次に、受講者の現在のスキルレベルや職務内容に適した難易度・内容であるかも重要なポイントです。
単に知識をインプットするだけでなく、演習やグループワークなどを通じて、学んだことをアウトプットする機会が豊富に用意されているプログラムが望ましいでしょう。受講後のフォローアップ体制や、学習の進捗を可視化できる仕組みの有無も選定基準となります。
研修で得た知識を定着させ、実践的なスキルへと昇華させるためには、OJT(On-the-Job Training)が非常に有効です。実際の業務の中でDX関連の課題に取り組む機会を意図的に創出することが、人材の成長を大きく促進します。
例えば、小規模なDXプロジェクトを立ち上げ、育成対象者を主要メンバーとしてアサインする方法があります。この際、経験豊富なメンターを配置し、適宜サポートやフィードバックを行う体制を整えることが成功の鍵です。
また、データ分析の専門家と現場の担当者がペアを組み、一緒に課題解決に取り組むといった方法も考えられます。重要なのは、失敗を恐れずに挑戦できる心理的安全性を確保することです。挑戦したプロセスを評価する文化が、社員の積極的なスキル習得を後押しします。
DXに関連する資格の取得を支援する制度も、社員の学習意欲を高める上で効果的な施策の一つです。資格取得という明確な目標があることで、社員は体系的に知識を学ぶモチベーションを維持しやすくなります。
対象となる資格は、ITの基礎知識を問う「ITパスポート試験」や、より専門的な「基本情報技術者試験」、データ分析スキルを証明する「統計検定」、特定のクラウドサービスに関する認定資格など、職種やレベルに応じて様々です。
具体的な支援策としては、受験料の補助や学習教材の購入費用補助、合格した際の報奨金(インセンティブ)支給などが考えられます。こうした制度は、社員の自己啓発を後押しすると同時に、会社としてDXを重視しているという明確なメッセージにもなります。
出典参照:ITパスポート試験|独立行政法人情報処理推進機構、基本情報技術者試験|独立行政法人情報処理推進機構、統計検定|一般財団法人統計質保証推進協会
育成施策を成功させる上で、最も本質的な要素は、社員一人ひとりが自律的に学び、挑戦することを奨励する組織文化を育むことです。特定の研修プログラムを提供するだけでは、持続的な人材育成は実現しません。
経営層がDXの重要性やビジョンを繰り返し発信し、DXによる成功事例を社内で積極的に共有することが、社員の意識改革に繋がります。また、部署の垣根を越えて知識やノウハウを交換できる社内勉強会やコミュニティ活動を支援することも有効です。
さらに、新しいスキルを習得した社員やDX推進に貢献した社員を適切に評価し、処遇に反映させる人事制度の見直しも重要です。組織全体で学習と挑戦を奨励する風土を醸成することが、変化に強い企業体質を作り上げます。
自社内での採用や育成には、ある程度の時間とコストがかかります。
DX推進のスピードを加速させるためには、専門的な知見や技術力を持つ外部のパートナー企業と連携することも、非常に有効な戦略です。
外部パートナーの活用形態には、コンサルティングや業務委託(アウトソーシング)、SES(システムエンジニアリングサービス)などがあります。それぞれの特徴を理解し、自社の目的や状況に応じて最適な形態を選択することが重要です。
コンサルティングは、DX戦略の策定やプロジェクトの方向性について、専門家から客観的な助言を受けたい場合に適しています。業務委託はWebサイトの運用やデータ分析など、特定の専門業務を外部のプロフェッショナルに任せたい場合に有効です。
SESは、特定の期間に特定の業務のためにエンジニアなどの技術力を確保したい場合に活用されます。自社のリソースで不足している部分を補う形で、柔軟に専門人材を活用できる点がメリットです。
パートナー企業の選定は、DXプロジェクトの成否に大きな影響を与えます。選定にあたっては、複数の観点から慎重に評価することが求められます。
まず、企業のウェブサイトなどで公開されている導入事例を確認し、自社と同じ小売業界での支援実績が豊富かどうかを確かめることが一つの判断基準となります。業界特有の課題や商習慣への理解があるパートナーは、より的確な提案が期待できます。
また、自社が抱える課題領域(例:データ分析、ECサイト構築、基幹システム刷新など)における専門性の高さも重要です。さらに、単なる作業代行に留まらず、自社のメンバーと一体となってプロジェクトを進め、ノウハウを社内に残してくれるような伴走力のある企業かどうかも見極めるべきポイントです。
外部パートナーとの協業を成功させるためには、パートナーに業務を「丸投げ」するのではなく、自社が主体性を持ってプロジェクトを推進する体制を築くことが不可欠です。
まず、自社内にプロジェクトの責任者(窓口)を明確に設置することが重要です。この責任者がパートナー企業との定例会議などを通じて密にコミュニケーションをとり、進捗を管理し、社内関係部署との調整役を担います。
また、プロジェクト開始前に、達成すべきゴールや成果物の定義や双方の役割分担、スケジュールなどを明確にした契約を締結することが、後の認識の齟齬やトラブルを防ぐ上で極めて重要です。パートナーを「業者」としてではなく、共にゴールを目指す「チーム」として尊重する姿勢が、良好な関係構築に繋がります。

このセクションでは、実際に小売業界でDX人材の確保や育成に成果を上げている企業の取り組みを紹介します。
自社の人材戦略を検討する上での参考にしてください。
株式会社トライアルホールディングスは、「リテールAI」を駆使した次世代の店舗運営の実現を目指しています。同社は、自社開発のAIカメラやスマートショッピングカートから得られる膨大なデータを分析・活用できる人材を「競争優位の源泉」と位置づけ、その採用と育成に注力しています。
具体的な取り組みとして、ITエンジニアやデータサイエンティストといった専門人材を積極的に中途採用する一方、社内でもデータ活用を推進する人材の育成に力を入れています。テクノロジーを軸に流通業界の変革をリードするため、多様な人材がそれぞれの専門性を発揮し、活躍できる環境整備を経営戦略上の重要課題として推進している点が特徴です。
出典参照:対処すべき課題|株式会社トライアルホールディングス
株式会社ベイシアは、全従業員を対象とした大規模なデジタル人材育成プログラム「Beisia Digital Academy」を導入し、組織全体のDXリテラシー向上に取り組んでいます。このプログラムは、役員から店舗のパート社員まで、全ての従業員がデジタルツールを使いこなし、データを活用して業務改善や新たな価値創造ができるようになることを目指しています。
外部からの専門人材採用だけに頼るのではなく、自社の事業を熟知した従業員を育成することで、現場の実情に即したDXを推進する狙いがあります。全社一丸となってDXに取り組むことで、現場主導のイノベーションが生まれやすい土壌を育んでいる好事例と言えるでしょう。
出典参照:デジタルリテラシー向上のための研修制度体制|株式会社ベイシア
株式会社ユナイテッドアローズは、顧客との重要な接点である販売員のデジタルスキル向上に力を入れています。販売員が自らライブコマースで商品を解説したり、個人のSNSアカウントでスタイリングを発信したりすることを支援し、オンラインとオフラインを融合させた新しい顧客体験の創出を目指しています。
これは、販売員一人ひとりがメディアとなって顧客と繋がり、ファンを育成していくという考え方に基づいています。また、社内公募制度「束矢(たばや)グランプリ」などを通じて現場の知見を持つ人材をDX推進部門へ登用するなど、DXの内製化を積極的に進めている点も特徴です。現場の声を活かしながら、顧客視点のDXを実現している事例です。
出典参照:人材育成クラウド型動画研修サービス「shouin」をユナイテッドアローズが全社向けオンライン研修に採用|株式会社ユナイテッドアローズ
本記事では、小売DXにおける人材確保の重要性から具体的なアプローチ、企業の成功事例までを解説しました。
DXの推進は、単に新しいツールやシステムを導入することではありません。それらを活用し、ビジネスの成長や新たな価値創造に繋げることができる「人材」の存在が、その成否を大きく左右します。
まずは自社の現状課題とDXによって目指す姿を明確にし、それに基づいて採用・育成・連携を組み合わせた最適な人材戦略を立案・実行することが、小売DX成功への第一歩となるでしょう。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
