小売DXの第一歩はペーパーレス化!メリットや書類管理の課題を解説
小売

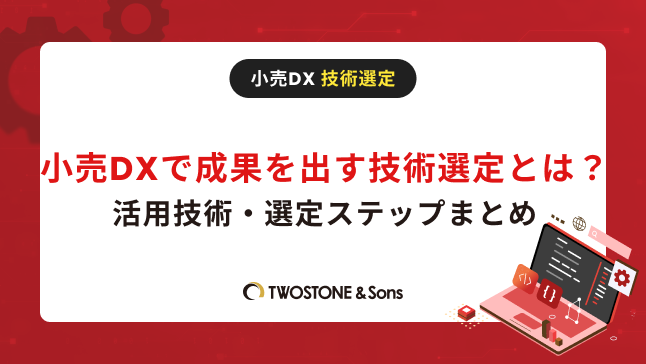
この記事では、DXで活用される技術の全体像から、失敗しない選定の重要ポイント、具体的な6つのステップまでを網羅的に解説します。店舗運営の効率化やデータ活用など、自社の課題解決に最適な一手を見つけるためのヒントが満載です。


・6万名以上のエンジニアネットワークを活用して課題を解決※
・貴社のDX戦略立案から実行・開発までワンストップで支援可能
※エンジニア数は2026年8月期 第1四半期決算説明資料に基づきます。
「競合のデジタル化が進み、売上が伸び悩んでいる」「人手不足が深刻で、現場の負担が大きい」そんな課題を抱える小売企業にとって、今やDX(デジタルトランスフォーメーション)は避けて通れないテーマです。
しかし、やみくもに新しいツールを導入しても現場に定着せず、費用ばかりがかさんでしまうといった失敗も少なくありません。
そこで鍵を握るのが「自社にとって本当に必要な技術」を見極め、的確に選び取ることです。課題を明確にし現場と連携しながら、目的に合ったツールを選定・活用することが成果を出すための第一歩です。
この記事では小売業界でのDXを成功に導くための技術選定について、重要性の整理から具体的な技術例、失敗を防ぐ選定ステップまでを網羅的に解説します。自社のDXに何から着手すべきか悩んでいる方、ツール選定でつまずきたくない方は、ぜひ最後までご覧ください。
デジタルトランスフォーメーション(DX)とは、単なるIT導入ではありません。デジタル技術やデータを活用してビジネスモデルや業務そのものを変革し、新たな価値を生み出し競争力を高めることを指します。
小売業界でも消費者ニーズの多様化や人手不足、ECとの競争激化といった課題が深刻化しており、DXによる変革の必要性が高まっています。
IPA(情報処理推進機構)の「DX実践手引書」では、DXは顧客視点の価値創出とビジネス変革に挑む取り組みだと示されています。
その意味でも、DX推進の第一歩となる技術選定は重要です。目的に合わない技術を選べば、コストや労力をかけても効果が出ず、現場で活用されない事態にもなりかねません。課題に合った技術選びこそが、小売DX成功のカギを握っています。
出典参照:DX実践手引書(P.7)|独立行政法人情報処理推進機構(IPA)

小売DXを実現するためには、様々な技術が活用されています。このセクションでは、代表的な技術を領域別に解説します。
顧客体験の向上において中心的な役割を担うのが、OMO(Online Merges with Offline)です。これはオンラインであるECサイトやアプリとオフラインである実店舗の垣根をなくし、顧客に一貫した購買体験を提供するマーケティング手法を指します。
例えば店舗とECの顧客データや購買履歴を一元管理することで、個々の顧客に最適化されたレコメンドやサービスを提供できます。またチャットやビデオ通話ツールを活用したオンライン接客は、顧客が場所に縛られず、専門的なアドバイスを受けながら商品を選べる新しい体験を創出します。
店舗運営における長年の課題である「レジ待ち」や「レジ締め業務」の解決策として、セルフレジやキャッシュレス決済の導入が加速しています。顧客自身が会計を行うセルフレジやレジを通さずに決済が完了する無人レジは、レジ待ち時間を大幅に短縮し、顧客満足度を向上させます。
これによりスタッフはレジ業務から解放され、接客や品出しといった付加価値の高い業務に集中できるという大きなメリットが生まれます。また多様なキャッシュレス決済に対応することは、顧客の利便性を高めるとともに、現金の取り扱いコストや管理リスクを削減する効果も期待できます。
欠品による機会損失や過剰在庫によるコスト増は、小売業の利益を圧迫する大きな要因です。この課題を解決する技術として、RFID(Radio Frequency IDentifier)が注目されています。これはICタグを使って複数の商品を一括で読み取る技術で、棚卸しや検品作業を劇的に効率化し、リアルタイムでの正確な在庫把握を可能にします。
さらに過去の販売実績や天候、イベント情報などのデータをAIが分析し、精度の高い需要予測を行うAI需要予測も重要です。これにより発注業務を自動化し、欠品や過剰在庫を未然に防ぐことで在庫の最適化を実現します。
発注、経理、勤怠管理といったバックオフィス業務は、定型的でありながら多くの時間を要します。こうした業務の効率化には、RPA(Robotic Process Automation)が有効です。
これまで手作業で行っていたPC上の定型業務をソフトウェアロボットが代行する技術で、データ入力や帳票作成などを自動化し、業務効率を大幅に向上させます。
また販売、在庫、会計、人事といった企業の基幹業務を統合的に管理するクラウドERP(Enterprise Resource Planning)もDXのカギとなります。クラウド型であれば場所を選ばずに情報共有が可能となり、経営状況をリアルタイムで可視化できるため、迅速な意思決定につながります。
経験や勘に頼る経営から脱却しデータに基づいた意思決定を行う「データドリブン経営」の実現には、専門的なツールが不可欠です。
その中核となるのがCDP(Customer Data Platform)で、店舗、ECサイト、アプリなど、あらゆるチャネルから収集した顧客データを統合・分析するための基盤です。
CDPによって顧客一人ひとりを深く理解し、パーソナライズされた施策を実行できます。そして企業が持つ様々なデータを集約・分析し、グラフやレポートとして可視化するBI(Business Intelligence)ツールを活用することで、売上動向や在庫状況などを直感的に把握し迅速な意思決定を支援します。

導入したシステムが、実は使えない「負の遺産」になってしまう。そんな失敗を避けるために、技術選定で必ず押さえるべき3つの重要なチェックポイントを解説します。
「なぜDXを行うのか?」「導入によって何を達成したいのか?」という目的とゴールが曖昧なままでは、最適な技術は選べません。「業務を効率化したい」といった漠然としたものではなく、例えば「AI需要予測を導入して、食品廃棄ロスを30%削減する」「CRMを刷新し、リピート購入率を15%向上させる」のように具体的な数値目標を設定することが重要です。
目的が明確であれば、評価すべき機能や費用対効果の判断基準も自ずと定まります。この最初のボタンをかけ違えるとプロジェクト全体が迷走してしまうため、最も時間をかけて議論すべきポイントです。
DXの成否は現場にかかっています。どんなに優れた技術やツールを導入しても、実際にそれを使う現場のスタッフが「使いにくい」「業務の実態に合わない」と感じてしまえば、定着することはありません。トップダウンで導入を進めた結果、現場の抵抗にあい、結局使われなくなってしまったという失敗例は後を絶ちません。
技術選定の初期段階から店長や店舗スタッフなど、現場の担当者を必ず巻き込みましょう。現状の業務フローにおける課題や新しいシステムへの要望をヒアリングすることで、本当に現場で役立つ、実用的なツールを選ぶことができます。現場の協力なくしてDXの成功はないということを忘れないようにしましょう。
多くの企業では、すでにPOSシステムや会計ソフト、基幹システムなどを導入しているはずです。新しく導入する技術やツールがこれらの既存システムとスムーズに連携できるかは、必ず確認しなければならない最重要項目の一つです。特にデータの連携はDXの根幹をなす部分であり、ここの確認を怠ると致命的な問題に発展しかねません。
もし連携ができなければデータの二重入力が発生して逆に手間が増えたり、システム間でデータが分断されてしまい、DXの目的であるデータの一元管理が実現できなかったりする可能性があります。API連携の可否や、連携実績などを事前にベンダーにしっかりと確認しましょう。
このセクションでは小売業が抱える代表的な課題と、その解決に有効な技術・ツールの組み合わせを提案します。自社の課題と照らし合わせ、解決策のヒントを見つけてください。
深刻な人手不足と現場の業務負荷を軽減するためには、業務の自動化・省力化がカギとなります。例えばレジ業務を自動化するセルフレジやキャッシュレス決済は、スタッフを単純作業から解放します。
さらに受発注や日報作成といったPCでの定型業務は、RPA(業務自動化ツール)に任せることができます。また複雑なシフト作成業務をAIで自動化するシフト管理システムを導入すれば、店長の負担を大幅に削減し、より付加価値の高い業務に集中できる環境を整えることが可能です。
店舗とECサイトのデータが分断されている状態では、顧客に最適な体験を提供できません。この課題を解決するのが、OMOプラットフォームです。店舗とECの顧客情報、ポイント、購買履歴、在庫情報を一元管理し、シームレスな顧客体験を実現します。
また実店舗のEC連携POSレジを導入すればECサイトの在庫情報とリアルタイムで連携させ、売り越しや販売機会の損失を防ぎます。これらのデータをCDP(顧客データ基盤)に統合することで、オンラインとオフラインを横断した、よりパーソナライズされたアプローチが可能になります。
顧客との関係性を強化しリピーターを育成するためには、データに基づいたコミュニケーションが不可欠です。CRM(顧客関係管理)やMA(マーケティングオートメーション)ツールを活用すれば、顧客情報や購買履歴に基づき、一人ひとりに合ったクーポンや情報を最適なタイミングで配信できます。
これにより顧客とのエンゲージメントを高め、LTV(顧客生涯価値)の向上を目指します。また公式アプリによるプッシュ通知や会員限定特典、あるいはオンライン接客ツールによる質の高い接客も顧客満足度を高め、再来店を促すための有効な手段です。
経験や勘に頼った経営から脱却しデータに基づいた迅速な意思決定を行うためには、社内のデータを可視化・分析する仕組みが必要です。
BI(ビジネスインテリジェンス)ツールは売上データ、顧客データ、在庫データなどをダッシュボードで可視化し、経営状況を直感的に把握できるようにします。
また社内に散在するデータを一箇所に集約・整理するデータ分析基盤を構築することは、データドリブン経営の土台となります。さらにAI需要予測システムを活用すれば、客観的なデータに基づいた仕入れや人員配置の最適化が可能となり、経営の精度を大きく向上させることができます。

小売業で使われるDXツールには、様々な種類があります。このセクションでは、各領域で代表的なDXツールをいくつかご紹介します。
店舗運営の現場では、利便性と多機能性を備えたクラウド型POSレジが広く普及しています。直感的な操作性に加えて在庫管理や売上分析、顧客管理機能を持つものも多く、業務効率化やサービス向上に役立っています。特に小規模店舗や個人事業主向けに、手軽に導入できるスマートフォンやタブレットで使えるPOSレジアプリが人気です。
またキャッシュレス決済の普及により、決済サービスと連携可能なPOSレジも定番化しています。一つの端末でクレジットカードや電子マネー、QRコード決済に対応できるシステムも登場しており、顧客満足度向上や会計業務のスピードアップに貢献しています。
さらに店舗とネットショップの在庫・売上を一元管理できるツールも増え、リアル店舗とECを連携させたOMO施策の第一歩として活用される例も増えています。
在庫管理業務の効率化には、スマートフォンで簡単に入出庫の管理ができるツールが役立っています。バーコードやQRコードを使ったアプリ型のシステムもあり、専用端末が不要なことからコストを抑えた導入が可能です。特に中小規模の店舗やEC事業者では、こうした手軽な在庫管理ツールが支持を集めています。
また需要予測や自動発注にAIを活用したシステムも登場し、食品スーパーやアパレル業界などでは、欠品防止や在庫ロス削減に効果を発揮しています。販売実績や天候、イベント情報などをもとにした需要予測は、属人的な経験則に頼る従来の発注管理に比べてより的確な在庫コントロールが可能です。
さらに、ECと実店舗の在庫を統合的に管理し最適化を図るツールも登場しており、全体最適化による利益向上を目指す動きが広がっています。
顧客情報の一元管理や営業活動、マーケティング施策を効率化するためのCRM(顧客管理)やMA(マーケティングオートメーション)ツールは、企業の規模を問わず重要性が増しています。顧客との接点が多様化する中、オンライン・オフラインを問わず一貫した顧客対応を実現するには、こうしたツールの活用が欠かせません。
特に商談や案件管理、メール配信、顧客ごとの購買データ分析などをまとめて管理できるプラットフォームは、営業・マーケティング部門の効率化に貢献しています。無料プランから始められるサービスも多く、導入しやすい点も魅力です。
さらにWebサイトやアプリの行動データをリアルタイムで分析し、顧客ごとに最適なコミュニケーションを図るための顧客体験(CX)向上ツールも注目を集めています。顧客理解を深めることで、ロイヤル顧客の育成やLTV(顧客生涯価値)の向上につながります。
ビジネスインテリジェンス(BI)ツールは企業内に蓄積されたデータを分析・可視化し、経営判断や業務改善に活かすためのツールです。データをグラフやチャートで直感的に表示できることから、専門的な知識がなくても扱いやすい点が評価されています。
特にExcelや業務システムと連携しやすいツールは、日常業務の延長で活用できるため、多くの企業で導入が進んでいます。Webデータの分析に強みを持つツールもあり、検索エンジンや広告管理ツールと連携しやすい無料の分析ツールなど、用途に応じた選択肢が豊富です。
DX推進の一環としてBIツールとデータ分析基盤の整備は重要視されており、販売実績や顧客データ、在庫情報など多様なデータを一元管理し、業務改善や戦略立案に役立てる企業が増えています。データに基づく意思決定(データドリブン経営)を目指す企業にとって、不可欠な基盤と言えるでしょう。
思いつきでツールを導入するのは失敗のもとです。体系的なプロセスに沿って技術選定を進めることで、成功の確率を格段に高めることができます。
このセクションでは、技術選定を成功させる6つのステップを順に見ていきましょう。
まずは現状把握から始めます。経営層、情報システム部、店舗、バックオフィスなど、様々な部門の担当者からヒアリングを行い、「人手不足で残業が多い」「在庫が合わない」「顧客データが活用できていない」といった課題を具体的に洗い出します。
そして、それらの課題を解決した先のゴール(KGI/KPI)を明確に設定することが重要です。この最初のステップを丁寧に行うことで、後のプロセスがぶれることなく進められます。
ステップ1で明確になった課題と目標を基に、それを解決できる可能性のある技術やツールについて幅広く情報収集を行います。本記事のような解説記事はもちろん、IT製品の比較サイト、業界専門の展示会、各ベンダーが主催するウェビナーなどを積極的に活用し、どのような選択肢があるのか、市場の動向を把握しましょう。
この段階では特定のツールや流行りの技術に安易に飛びつくのではなく、自社の課題解決に本当に貢献するかという視点で、様々な可能性をフラットに検討することが大切です。複数の選択肢をリストアップし、それぞれの技術やツールが持つ大まかな特徴やメリット・デメリットを整理しておくと次のステップがスムーズに進みます。
調査したツールの中から候補を絞り込み、自社に必要な要件を具体的にまとめた「要件定義書」を作成します。要件にはシステムが備えるべき機能を定義する「機能要件」と、性能やセキュリティ、運用性などを定義する「非機能要件」があります。この要件定義が、後のベンダー選定における客観的な評価基準となります。
さらに、ベンダー(開発会社)に提案を依頼するためのRFP(提案依頼書)を作成しましょう。RFPには自社の概要、プロジェクトの背景と目的、解決したい課題、具体的な要件、期待する提案内容、選定プロセスとスケジュールなどを記載します。質の高いRFPを作成することで各社から精度の高い提案を引き出し、公平に比較しやすくなります。
作成したRFPを複数のベンダーに提示し、提出された提案内容と見積もりを比較検討します。この時価格だけでなく、機能の充足度、導入実績、サポート体制、拡張性、そして担当者の対応などを総合的に評価することが重要です。評価項目を一覧にした「評価シート」を作成し点数付けを行うと、客観的で公平な比較がしやすくなります。
各社のプレゼンテーションや質疑応答の場では、提案内容の実現可能性や自社の業務への理解度を深く確認しましょう。このプロセスを通じて各社の強みや弱みを見極め、自社のパートナーとして最もふさわしいと考えられる企業を2〜3社に候補として絞り込みます。
選定候補のツールについてデモンストレーションを依頼したり、可能であればトライアルを導入したりして、実際の操作性や効果を検証します。
実際にツールを使用する現場の担当者に使ってもらい、そのフィードバックをアンケートやヒアリング会を通じて収集することが極めて重要です。「操作が直感的か」「既存の業務フローにスムーズに組み込めるか」といった、現場目線の評価が導入後の定着を左右します。
この段階で導入にかかる初期費用や月額費用といったTCO(総所有コスト)と、それによって得られる効果を具体的に試算し、投資対効果を冷静に判断します。
トライアルの結果と費用対効果の検証に基づき、全ての関係者が納得した上で最終的に導入するツールを1社に決定します。その後、決定したベンダーと協力し、詳細な導入計画を策定します。この計画には具体的なマスタースケジュール、タスクリスト、導入体制図、データ移行の段取り、社内研修計画、そしてリスク管理計画などを盛り込みます。
またベンダーとの契約時には、システムの稼働率や障害発生時の対応時間などを定めたSLA(サービス品質保証)の内容をしっかりと確認することも忘れてはなりません。この詳細な計画が、スムーズな導入と社内への定着を実現するためのロードマップとなります。
ツールそのものの性能はもちろんですが、「誰と(どの会社と)一緒にDXを進めるか」というパートナー選びも同様に重要です。このセクションでは、信頼できるパートナーを見極めるための3つのポイントを解説します。
自社と同じ業種・業態の企業への導入実績が豊富かを必ず確認しましょう。小売業界特有の商習慣や業務フローを深く理解しているベンダーであれば、的確な提案やスムーズな導入が期待できます。業界知識が乏しいベンダーだと要件の理解に時間がかかったり、的外れな提案が出てきたりする可能性があります。
公式サイトの導入事例をチェックする際は、単に企業名を見るだけでなく「どんな課題を」「どのように解決し」「どのような定量的・定性的な成果が出たか」までを詳しく読み込みましょう。可能であれば、そのベンダーが導入した企業に直接話を聞く「リファレンスチェック」を行うこともミスマッチを防ぐ上で非常に有効な手段です。
ツールの導入はゴールではなく、スタートです。導入後に不明点やトラブルが発生した際のサポート体制は、事業継続性の観点からも極めて重要です。サポートの連絡手段、対応時間、返答速度のSLA(サービス品質保証)などを具体的に確認しましょう。
さらに単なるツール提供に留まらず、DX推進のパートナーとして活用方法の提案や定期的な効果測定、業界の最新動向の共有など、導入後も継続的に支援してくれる「伴走力」のあるベンダーを選ぶことが成功のカギとなります。
契約前に定例会の有無やコンサルティングの範囲など、どのようなサポートが受けられるのかを具体的に確認してください。
必ず複数のベンダーから見積もりと提案を取り、その内容をじっくり比較検討しましょう。価格の安さだけで判断するのは危険です。初期費用が安くても、後から高額なカスタマイズ費用やサポート費用が発生するケースもあります。見積もりの内訳(初期費用、月額費用、ライセンス体系、カスタマイズ費用など)を詳細に確認し、総所有コスト(TCO)で比較することが重要です。
提案内容を精査する際は、「自社の課題を正しく理解しているか」「提案が具体的で実現可能か」「自社の成長に合わせて拡張できるか」といった視点で評価します。担当者の説明が丁寧で、こちらの疑問に真摯に答えてくれるか、その熱意や人柄も長期的なパートナーシップを築く上で大切な判断材料となります。
小売業がDXで成果を出すには、「目的に合った技術を選び、使いこなすこと」が欠かせません。重要なのは課題を明確にし、現場の声を反映しながら適切なプロセスで選定・導入することです。導入して終わりではなく、顧客体験の向上や業務改善につなげてこそ、DXは価値を発揮します。
本記事でご紹介した、活用領域ごとの技術例や失敗しない選定ステップ、信頼できるベンダーの見極め方を参考に、まずは自社の課題を洗い出し、最適なパートナーとともにDXを進めてみてください。
小さな一歩の積み重ねが、未来の大きな変化につながります。まずは、自社の現状を整理することから始めてみましょう。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
