証券DXとデジタル通貨の融合による変革とは?効果的な施策を解説
証券

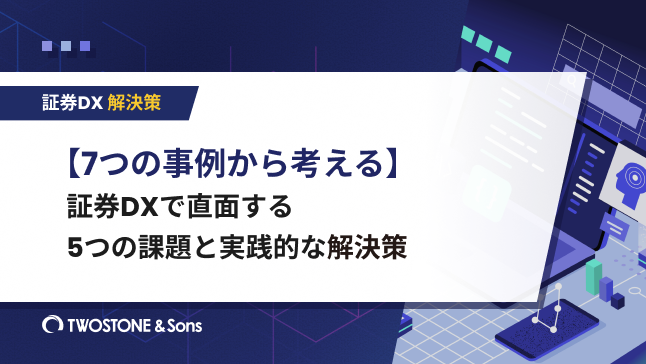
証券業界はデジタル技術の進展により変革期を迎えています。本記事では、DX推進の重要性と「2025年の崖」リスクを踏まえ、代表的な課題とその解決策、具体的な企業事例を詳しく解説します。
今、証券業界は転換点に立たされています。投資家の価値観や行動様式が変化し、デジタル技術の進展がビジネスモデル全体に影響を及ぼす中、従来の業務フローや顧客対応だけでは限界を感じている方も多いのではないでしょうか。特に、将来の成長や競争力を維持するためにはDX(デジタル・トランスフォーメーション)の推進が不可欠です。
本記事では証券DXの現状を整理するとともに、業界が直面している「2025年の崖」というリスクにも焦点を当てます。その上で、証券業界でよく見られる5つの課題とそれに対する実践的な解決策を、7つの具体的な事例を通してご紹介します。読み進めていただくことで、今後の証券ビジネスにおけるDX戦略の方向性をつかみ、次の一手に自信を持って取り組めるようになるでしょう。

証券業界では近年、業務効率化と顧客接点の強化を目的としたDX推進が活発化しています。その背景には、既存の仕組みだけでは顧客ニーズに応えきれなくなっている現状があります。多様化する投資スタイルやオンライン取引への移行スピードに柔軟に対応するために、業務全体の見直しが求められているのです。
まず、顧客の投資行動が変化している点が挙げられます。現代では従来の対面中心の取引から、スマートフォンを活用したオンラインでの情報収集や取引が主流となりつつあります。特に若年層や中堅世代の投資家はスピードと利便性を重視しており、店舗に足を運ぶ機会は減少しているのです。
加えて、競合との差別化も課題となっています。新興フィンテック企業は、シンプルで直感的な操作性を提供するアプリやAIを活用した資産管理ツールを武器に、急速に市場を拡大しています。従来型の証券会社がそのままの体制で対抗するには限界があり、顧客体験の高度化が急務です。
このような変化の中では、DXは単なるデジタル化ではなくビジネスモデルそのものの変革を意味します。営業体制や商品提供のあり方を抜本的に見直し、デジタル技術を活用した新たな価値創出が期待されています。
DXの必要性が高まる背景には、いわゆる「2025年の崖」問題も無視できません。これは、老朽化した基幹システムの維持コストや保守体制が限界を迎え、企業の競争力を著しく損なうリスクが指摘されている状況を指します。
証券業界においても多くの企業が数十年前に構築された基幹システムを継続利用しており、現代のニーズに合った柔軟な開発やサービス拡張が難しくなっています。例えば新しい投資商品をスピーディーに提供したくても、システム対応に時間がかかるために機会を逸してしまうことがあるでしょう。
さらに、旧来のシステムを熟知しているエンジニアの高齢化や退職が進み、保守・運用の体制が不安定になるケースも増加しています。こうした背景から、DXの実行が遅れれば遅れるほど技術的にも人的にも深刻な問題を抱えるリスクが高まります。
一方でDXの取り組みには多大なリソースと戦略的視点が求められるため、どこから手をつけるべきか判断に迷う企業も多いのが実情です。そのため、段階的な移行計画を立てて確実に成果を出せるアプローチが重要になります。
証券業界におけるDXの必要性は日増しに高まっていますが、実際の現場では多くの障壁が存在します。単に新しいシステムやツールを導入するだけでは、持続的な成果にはつながりません。
ここでは証券DXの推進において多くの企業が直面している5つの課題を取り上げ、それぞれの背景や具体例、そして対応策を詳しく見ていきます。
証券業界では、長年にわたって独自に構築・運用されてきた基幹システムが存在します。これらのレガシーシステムは安定稼働している反面、外部の最新ツールやクラウドサービスと連携しにくく、DX推進の妨げとなるケースが多いです。
例えば顧客管理や取引記録が複数のサーバーに分散されている場合、デジタルチャネルでの一貫したユーザー体験を提供しづらくなります。その結果顧客対応の効率が落ち、営業活動の精度にも影響が出てきます。
解決策としては、段階的なモダナイゼーションが有効です。すべてを一度に刷新するのではなく必要な機能からAPI連携を取り入れることで、既存システムの価値を活かしながら柔軟なデジタル化を実現できます。特定の業務プロセスに限定したクラウド移行やマイクロサービス化も選択肢となるでしょう。
DXは単なるIT導入ではなく、データを基軸とした業務変革です。しかし、社内に蓄積されたデータを活用しきれていない企業も少なくありません。活用不足の要因として、部門間でのデータのサイロ化や分析スキルの不足が挙げられます。
例えば営業部門とマーケティング部門が顧客情報を個別に管理している場合、的確なニーズ分析やタイミングの良いアプローチが難しくなるでしょう。また、データが蓄積されていてもそれを意思決定に活かせる体制が整っていない場合、導入されたツールが宝の持ち腐れになってしまう危険性があります。
この課題に対処するためには、まず社内で共通のデータプラットフォームを整備することが第一歩です。その上でBIツールやダッシュボードを活用し、リアルタイムでのデータ可視化を進めていく必要があります。また、各部門にデータ活用の意識を浸透させる教育も並行して行うと効果的です。
高度な技術が求められるDXにおいて、IT人材の不足は深刻な課題です。特に、証券業界では伝統的なビジネスモデルに精通した人材が多く、クラウド技術やデータエンジニアリングに精通した人材は限られています。
例えばデータ基盤の刷新やAIツールの導入プロジェクトを進めようとしても、社内で実行できるエンジニアがいなければ外部依存が強くなり、ノウハウの蓄積が進みません。結果として内製化ができず、コスト増にもつながります。
このような状況では、社内育成と外部連携を並行して進めるのが現実的です。社内向けのリスキリング研修や部門横断での勉強会を実施すると、業務理解を持ったIT人材を育てることが可能になります。また、外部の専門パートナーと連携しながらプロジェクトを推進すると、知見を取り込みつつ社内定着を図ることもできるでしょう。
DX推進によって顧客データや取引情報の取り扱いが増えることで、セキュリティ対策や個人情報保護の重要性が一層高まっています。特に証券業界はサイバー攻撃や情報漏えいリスクの標的になりやすく、技術的にも法的にも高い水準での管理が求められます。
例えば、新たに導入したクラウドサービスにおいてアクセス権限の設定が不十分だった場合、内部不正や外部からの侵入リスクが発生しかねません。また、GDPRや国内の個人情報保護法に適合しない運用を行っていると、法的な制裁や信頼低下に直結するでしょう。
このようなリスクを回避するには、まずゼロトラストセキュリティの考え方を取り入れることが重要です。社内外問わずすべての通信やユーザーを検証しながらシステムを運用することで、安全性を確保できます。さらにデータの暗号化やアクセスログの常時監視など、多層的な対策を組み合わせることで堅牢なセキュリティ体制を構築できます。
最後に見逃せないのが、DXの目的が明確でないまま施策を進めてしまい期待した効果が出ないという問題です。導入するテクノロジーに注目するあまり、本来解決すべき業務課題や顧客価値の視点が抜け落ちるケースが散見されます。
例えば、AIチャットボットを導入したものの顧客のニーズに応じた対応ができず、かえって不満が増えてしまったという事例がその一例です。これは、施策の目的が「対応コストの削減」だけに偏り、「顧客満足の向上」という視点が欠けていたことが原因といえます。
この課題を回避するためには、DXの目的を経営層から現場まで共有することが不可欠です。顧客中心の視点に立ち、どのような価値を提供したいのかを明確にし、その実現に必要な施策を段階的に実行する必要があります。また、施策の評価基準やKPIを事前に設定し、PDCAサイクルの徹底が着実な成果につながります。
技術や戦略を取り入れる際には、自社の経営方針や現場の業務フローとの整合性が不可欠です。
ここでは代表的な6つの解決策を取り上げ、実行可能な手段とポイントを具体的にご紹介します。
老朽化したシステムと現代的なツールの間に溝がある場合、まず求められるのが柔軟なIT基盤の再構築です。クラウドサービスの導入とAPIによる連携は、異なるシステム同士をスムーズにつなげる上で効果的です。
例えば取引情報を管理する基幹システムとCRMツールが分断されている場合、API連携によってリアルタイムの情報更新が可能になるでしょう。これにより顧客対応のスピードや質が向上し、社内の業務効率も改善されます。
導入にあたっては、段階的な移行計画を立てることが成功のカギとなります。すべてを一度に移すのではなく、リスクの少ない領域からクラウド化を進めることで業務への影響を最小限に抑えられるのです。加えて、社内の運用ルールやガバナンスの整備も並行して行う必要もあります。
煩雑な定型業務にリソースを割いていては、戦略的な活動に時間を使う余裕が生まれません。そうした課題に対し、AIやRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)を用いた業務自動化が注目されています。
例えば口座開設に必要な本人確認プロセスでは、画像認識AIによって書類の内容を自動チェックし、RPAでシステムへの登録までを一貫して処理できます。これにより1件あたりの処理時間を短縮し、人為的ミスも抑制可能になるのです。
成功のポイントは、自動化の対象を絞り込むことです。全社的に一斉導入するのではなく、まずは手作業が多く、標準化しやすい業務から着手するのが効果的です。加えて、社内の業務設計そのものを見直す機会として活用することでより根本的な業務改善にもつながります。
非対面取引が主流となる中、顧客との接点をいかに多様化・深化させるかは企業の競争力に直結します。そこでデジタルチャネルを強化すると、個別ニーズに応じたサービス提供が可能となり、顧客ロイヤルティの向上にもつながるでしょう。
実際に、モバイルアプリ上での資産運用シミュレーションやチャットでの金融相談窓口などは、若年層を中心に高い評価を得ています。こうしたチャネルの整備により、来店不要での取引や相談が日常的に行えるようになるのです。
これらのシステムの導入にあたっては、チャネルごとに顧客体験の一貫性を保つ工夫が求められます。UI/UX設計においても、直感的な操作性を追求することが不可欠です。導線の最適化やパーソナライズ機能の導入により、利便性と満足度の両立を図れるのです。
顧客の行動や市場の変化を迅速に捉え柔軟に対応するためには、データに基づく意思決定が不可欠です。これを実現するには、営業やリスク管理においてもデータドリブンなアプローチを積極的に取り入れる必要があります。
例えば過去の取引履歴や問い合わせ傾向を分析すると、顧客ごとに最適なタイミングで適切な提案を行えるようになるでしょう。また信用リスクに関しても、リアルタイムのデータ分析によって早期警告が可能となり、損失の回避につながります。
この環境を整えるためには、データの収集・統合から分析・活用に至るまでのプロセス全体を見直す必要があります。社内外のデータを統一的に管理するための基盤整備と分析ツールの導入に加えて、分析結果を営業現場やリスク管理部門で活用できる体制づくりが求められるのです。
若年層にとって証券サービスへの接点は、スマートフォンやSNSなどのデジタルツールを通じたものであることが一般的です。従来型の店頭サービスだけでなく、複数のチャネルを戦略的に活用することで新たな層を取り込む可能性が広がります。
例えば、Instagramを通じた資産運用コンテンツの発信やYouTube上での証券教育動画などは、情報提供とブランディングの両立に役立つでしょう。こうしたアプローチは証券に対する心理的ハードルを下げ、エンゲージメント向上に直結します。
ポイントは、単なる複数チャネルを用意するだけでなく、それぞれの特性を踏まえたコンテンツ設計と運用を行うことです。チャネル間での連携を強化し、どのタッチポイントでも一貫したブランド体験を提供できる体制を整えましょう。
自社単独でDXを進めようとすると、技術面・人材面での限界がすぐに訪れます。そこで注目されるのが、外部パートナーとの協業による加速です。専門知識や技術力を持つ企業との連携により、自社に不足している機能を短期間で補完できるようになるでしょう。
例えば、データ分析に長けたスタートアップ企業と共同でリスクモデルを構築したり、UI/UX設計に強みを持つ外部デザイン会社とアプリ開発を進めたりといった取り組みが挙げられます。このような協業は、スピード感を持って成果を出したい場面で特に有効です。
ただしパートナー選定においては、単なる外注ではなく「共創」の意識が重要です。目的やビジョンを共有し長期的な視点で関係性を築くことで、より高い効果が期待できます。また、社内に対しても外部との協働を前提としたプロジェクトマネジメント能力が求められます。

デジタル変革を成功させるには、個別の技術導入だけでなく全体戦略とその実行プロセスが一貫して設計されている必要があります。
ここでは証券業界がDXを円滑に推進するためのステップを段階的に整理し、各段階で何を重視すべきかを具体的に解説します。
まず必要なのは、自社の現状の正確な理解です。業務フローのボトルネックや顧客接点での摩擦、システムの老朽化による影響など、問題点を客観的に洗い出します。
例えば手作業による口座開設プロセスが遅延の原因になっている場合、どの段階で滞りが発生しているかを明確にすると改善の方向性が見えてきます。このように、現場レベルのヒアリングやKPIデータの分析を通じて具体的な障害を特定することが、DX戦略の起点になるのです。
可視化された課題は、今後の投資判断や優先順位の決定に直結します。曖昧なままでは的外れな施策に終始し、リソースが無駄になりかねません。だからこそ、現状分析は丁寧かつ多角的に進めるべきなのです。
続いて、なぜDXに取り組むのか、その目的を組織全体で共有する必要があります。単なる業務効率化ではなく、顧客満足度の向上や収益モデルの再構築など戦略的意義を明示することが重要です。
例えば、「リテール営業の効率を高め、顧客一人当たりのLTV(顧客生涯価値)を最大化する」など具体的な目標を設定すると、部門ごとの役割も明確になります。目的が曖昧なままでは現場の理解が得られず、部分最適に陥るリスクが高まってしまうのです。
明確なゴールが定まると、技術導入の妥当性やROIの算出も可能になります。関係者間でビジョンを共有すると、社内の協力体制も築きやすくなります。
DXが機能するためには、現在の業務プロセスと既存システムとの間にある非効率や齟齬を見極める必要があります。特にレガシーシステムが残っている場合、その制約をどう乗り越えるかが課題です。
例えば顧客情報の管理が複数のシステムに分散されていると、情報連携に支障を来し、営業活動のパフォーマンスが低下します。このような構造的な問題を明確にすれば、次にどのシステムを統合すべきかが判断しやすくなるでしょう。
現場主導で行われてきた業務には属人化が進んでいることも多く、デジタル対応の前に業務の標準化が求められるケースもあります。これらの課題を棚卸しして、理想とのギャップを埋める構想を描くのがこの段階です。
ギャップが特定されたら、それに対応する最適な技術や方法を選びます。ここでは流行のテクノロジーを無計画に取り入れるのではなく、解決したい課題との整合性を重視すべきです。
例えば顧客対応のスピード向上を狙うなら、AIチャットボットやFAQ自動化ツールの導入が有効です。一方で取引リスクの即時検出には、リアルタイムのアナリティクス基盤が不可欠です。
さらに、ツールだけでなく導入のプロセスや運用体制もあわせて検討する必要があります。自社にとって扱いやすく拡張性のある構成を選ぶことで、後の展開もスムーズになります。
すべてを一度に刷新しようとするとリスクが高く、現場の混乱を招く可能性があります。そのため、小さく始めて成果を確認しながら段階的に拡張していくアプローチが有効です。
まずは一部の支店でペーパーレス化を試験的に導入し、業務効率の変化や顧客満足度への影響を観察しましょう。そこで得られた知見を基に、他部門への展開を検討するのが現実的です。
初期段階で成果を見せることができれば社内の抵抗感も軽減され、全社的な取り組みへとスムーズに移行できます。段階的に進めることで、柔軟に軌道修正もしやすくなるのです。
デジタル化が進むほど、情報漏えいや法令違反といったリスクも高まります。したがって、あらかじめガバナンス体制やセキュリティポリシーを固めることが不可欠です。
例えば、顧客データを取り扱うシステムにはアクセス制限や暗号化の仕組みを徹底し、運用上のルールも明文化する必要があります。特に証券業は、金融商品取引法やFISCガイドラインといった規制を厳格に守らなければなりません。
加えて、外部ベンダーと連携する場合も委託管理基準や監査体制を明確にしておくことが求められます。ルールと責任範囲を明確にすることで、トラブルの未然防止につながるのです。
施策を実施した後も、終わりではありません。推進の効果を継続的に検証し、新たに浮上してくる課題に対応していくことが重要です。これによりDXの取り組みが一過性で終わらず、持続可能な改善活動になります。
例えば、営業支援システムを導入したものの実際の現場では入力負荷が高く使いにくいという声が上がることもあります。こうしたフィードバックを収集し、UI/UXの改善や研修の見直しにつなげることが成果の維持に直結するのです。
PDCAを繰り返す仕組みを構築することで業務改善の精度が上がり、DXが組織文化として根づいていきます。柔軟に対応しながらも、ぶれない軸を持つことがカギになります。
近年証券業界でもデジタル変革が急速に進み、多くの企業が独自のアプローチでDXを推進しています。単なる業務効率化にとどまらず、組織文化や顧客体験の質の向上を目的とした取り組みが増加しているのです。
ここでは課題解決に向けた証券会社の実践事例を取り上げ、それぞれの取り組みの背景や成果について詳しく紹介します。
みずほフィナンシャルグループでは全社的なDX戦略の一環として、社員同士の知見や発想を可視化し共有する「Wiz Chat」を導入しています。この取り組みは社内に眠る暗黙知を顕在化し、課題解決のヒントを導き出すことを目的としたものです。
例えば新しいサービスを検討する際、過去に失敗したプロジェクトや顧客からの声をWiz Chatに集約することで企画の立案段階から多角的な視点を取り入れられるようになりました。これにより属人化していた情報やノウハウの共有が進み、イノベーションの創出が加速しています。
この事例が示すように、社内コミュニケーションをテクノロジーで再設計することはデジタル戦略における基盤の強化にもつながります。
野村證券では顧客向けの情報提供プロセスを見直し、スマートフォン向けアプリを軸とした情報配信の自動化を進めました。これにより、顧客ごとのニーズや投資履歴に応じたレコメンド機能の提供が可能となっています。
背景には、営業担当者のリソース不足やタイムリーな情報提供の難しさといった課題がありました。アプリによる自動配信を取り入れることで、顧客対応の精度を高めると同時に担当者の負担軽減も実現しました。
このように顧客接点の再構築は、単なる利便性の向上だけでなく人的資源の最適化にも寄与します。
参考:野村證券株式会社
SBIネオファイナンシャルサービシーズは地域社会に根差したDXを推進するため、証券データベースを構築しました。このプラットフォームは、地域の中小企業や個人投資家に対して適切な証券サービスを提供する基盤となっています。地域特性に合わせた情報を一元管理し、地域経済活性化に貢献しています。
この取り組みの特徴は、データを活用して地域のニーズを的確に把握しサービス開発に反映させていることです。実際に地域産業の成長性や資金需要を分析し、それに適した融資や投資の提案を行っています。こうしたDX戦略によって地域密着型証券の新たなモデルが構築され、地元企業との連携強化が進んでいるのです。
岡三証券グループは業務の全領域にわたりデジタル化を推進した結果、国のDX認定制度を取得しました。この認定は、企業のDX取り組みが国の基準を満たし、かつ持続可能な改革を達成している証明です。岡三証券は内部プロセスの効率化と顧客体験の向上を同時に進めています。
この事例の肝は、全社横断的なDX戦略の策定にあります。例えば、取引システムの刷新やペーパーレス化、さらには顧客向けオンラインサービスの強化に注力しました。結果的に従来の人手に依存した業務が減少し、より戦略的な業務にリソースを集中させる体制が整いました。こうした包括的な取り組みが認定取得の背景となっています。
参考:株式会社岡三証券グループ
大和証券グループは人材育成に力を入れ、社員のデジタルスキル向上を目的とした「デジタルITマスター認定制度」を導入しました。専門知識や技術の習得を体系化し、DX推進のための人材基盤を強化しています。この制度は社員のモチベーションアップにもつながっています。
制度の導入で、社員一人ひとりが最新のデジタル技術やトレンドを理解し、自ら業務改善に取り組む姿勢が醸成されました。実際に、AIやRPAの活用方法を学ぶことで日常業務の自動化提案が増加し、結果として業務効率が向上しました。人材育成を通じてDXを組織文化に根付かせる効果が顕著に表れているのです。
参考:株式会社大和証券グループ
マネックス証券は、従来の証券取引中心のビジネスモデルから資産運用モデル(アセットマネジメントモデル)へと転換しました。これにより顧客ニーズに即したパーソナライズドなサービス提供が可能となり、DXの本質的な実現を果たしています。
この転換は単なるシステム導入にとどまらず、サービス設計や顧客対応方法の根本的な見直しを伴っています。実際にビッグデータ解析を活用して顧客の投資傾向を分析し、最適な商品提案の自動化を実現しました。その結果顧客満足度が向上し、企業競争力も高まったのです。
参考:マネックス証券株式会社
東海東京証券は多様なFinTech技術を融合させた統合プラットフォームを構築し、統括的なDXを実現しました。これにより、取引・分析・顧客管理を一元化し、迅速かつ効率的な業務運営が可能となっています。さらに、新しい証券サービスの開発基盤にもなっています。
このアプローチの利点は、分散していた業務システムやデータを統合してシームレスな情報連携を実現できる点です。実際に、AIによる市場予測やリスク管理機能と連動した顧客向けサービスを提供することで、より高度な証券ソリューションを展開しています。結果として、業務の質とスピードの両立が達成されました。
参考:東海東京証券株式会社

証券業界におけるDX推進は、多様な課題を的確に捉えて解決策を練り上げることが何より重要です。これまでの事例からも、単に最新技術を導入するだけでは不十分であり、自社の課題に寄り添った戦略を立てることが成功のカギとなっていることがわかります。
まずは、自社が直面している課題を具体的に洗い出し、優先順位をつけて一つずつ解決に取り組む姿勢が求められます。その過程では、専門的な知識や実務経験に基づいた判断が必要となる場面も多く、外部の専門家と連携することも有効な選択肢のひとつでしょう。
自社の強みを正しく把握し、それに基づいてDXをどのように展開していくかが解決のポイントです。まずは本記事の内容を参考にしながら、自社に合ったアプローチを検討してみてはいかがでしょうか。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
